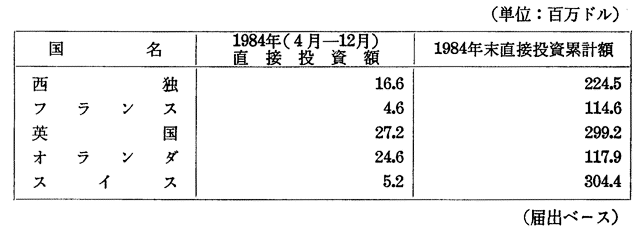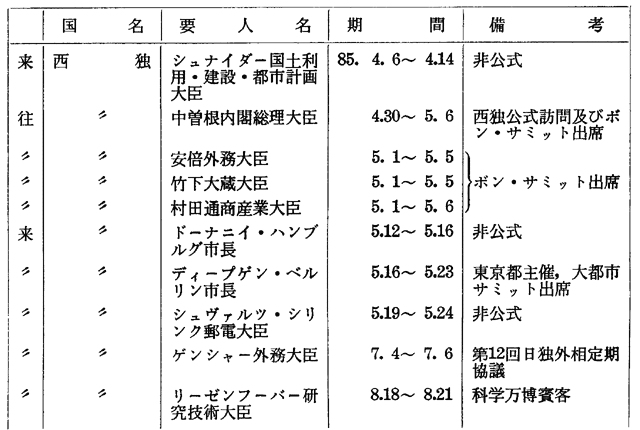
2.我が国と西欧諸国との関係
(1)日・西欧関係全般
我が国と西欧諸国とは,文化的,歴史的に密接な関係にあり,また,自由と民主主義及び市場経済といった基本的価値観・制度を共有している。東西関係を中心とした現下の厳しい国際情勢の下,我が国が世界の平和と繁栄の維持・発展のため,国際社会において果たすべき役割に対する西欧諸国の期待は高まっており,かかる背景の下,日欧協力関係,特に,日欧政治関係は近年緊密化しつつある。
このような緊密な日欧関係を反映して,85年にはルッベルス=オランダ首相が訪日したほか,86年には,ドロールEC委員長,クラクシ=イタリア首相等西欧諸国首脳が訪日し,また,中曽根内閣総理大臣は,85年7月,フランス,イタリア,ヴァチカン,ベルギー及びEC委員会を歴訪し,各国首脳及び政府要人と幅広い意見交換を行った。
他方,安倍外務大臣は85年,ボン・サミットの前後に米国,ノールウェー及びオーストリアを訪問し,さらに6月にはスウェーデン(ポーランド,東独),デンマークを訪問した。また,7月には,東京において日独定期外相協議が,86年1月には安倍外務大臣が訪欧して,日英及び日独定期外相協議が開催された。さらに,83年に我が国とEC諸国との間で開始された日・EC議長国外相協議は,85年4月及び9月にそれぞれ第5回及び第6回会合が開催された。
(2)日・西欧経済関係
(イ)他方,85年の日欧経済関係は再び厳しい雰囲気の中で推移した。例えば5年4月11日のOECD閣僚理事会におけるドクレルクEC委員の演説,6月19日のEC外相理事会の対日関係宣言,6月29日のミラノ欧州理事会結論文書等ではいずれも世界経済の中で日本がその地位にふさわしい責任を果たしていない,日本の貿易黒字は自由貿易体制を危うくしているなどの厳しい対日姿勢が打ち出されてきた。この背景には,我が国の累次の市場開放措置の実施にもかかわらず,我が国の100億ドル前後の黒字が続く日・EC貿易の趨勢に一向に改善が見られないことへのEC側の強い不満や,日本の黒字が米国の保護主義を強めることになるのではないかとの懸念等があると見られる。
中曽根内閣総理大臣の欧州諸国訪問や,市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの発表(7月30日)は,かかる状況の中で行われた。
アクション・プログラムは,4月に発表された対外経済対策を踏まえ,我が国の関税,基準・認証制度,政府調達,金融資本市場等の広汎な分野において,5月末に開かれた第2回日・EC貿易拡大委員会(TEC)や,6月初めの日・ECハイレベル協議の場等を通じて表明された欧州諸国の要求や関心にも十分配慮しつつ,思いきった改善・改革措置を講じることとしたものである。
すなわち,関税引下げ(ECよりの関税引下げ要請128品日中インスタント・コーヒー,ワイン,ウイスキ、スキー等71品目をカバー),基準・認証制度(化粧品の包括許可制の導入,電気用品に係る自己認証品目の拡大,IEC規格との整合化等),政府調達(随意契約の縮減,資格審査手続の改善等EC側の要求にはほとんど応えている),サービス(外国弁護士,不正商品等)等の分野で,国内的困難にもかかわらず,EC側の要請に応える措置が多く盛り込まれた。
我が国はアクション・プログラムの内容を説明するための政府ミッションを8月初めにEC諸国に派遣した。EC側産業界には,アクション・プログラムによって開かれる市場参入機会を積極的に利用しようとの気運も見られたが,EC委員会は10月に対日関係報告を公表し,アクション・プログラムの効果について否定的な評価を与えるとともに,同プログラムを補完するために,我が国が製品,農産加工品の輸入を実質的に増大するためのタイム・テーブル付数量目標を設定するようになどの厳しい要求を提示してきた。
EC委報告は,10月のEC外相理事会で承認をうけ,11月に東京で行われた第2回日・EC委閣僚会議においても,EC委側はこの輸入数量目標の設定要求に日本側が応じるよう迫った。これに対して,日本側は,市場経済体制をとっており,かかる要求には応じられないとして拒否し,議論は平行線をたどった。
(ロ)86年1月に,ドロールEC委員長が公賓として来日した。同委員長は,世界経済の安定と発展のためには,日・欧・米三極の協力強化,特に,三極の中で弱い日・欧関係の強化が重要であるとして,日本市場の一層の開放に期待を表明する一方で,EC諸国の一層の対日進出努力の必要性についても強調した。
3月に行われたEC外相理事会は,ドロール訪日を踏まえて,今後の対日関係について検討した結論文書を採択した。その内容は,10月の対日関係報告に比べれば,EC側の対日進出努力の必要性に言及するなどよりバランスのとれたものとなっているが,基本的には,EC内で対日強硬姿勢をとる幾つかのメンバー国の意向が色濃く反映された厳しいトーンに貫かれており,今後の日・欧経済関係の動向は楽観を許されない状況にある。
<要人往来>
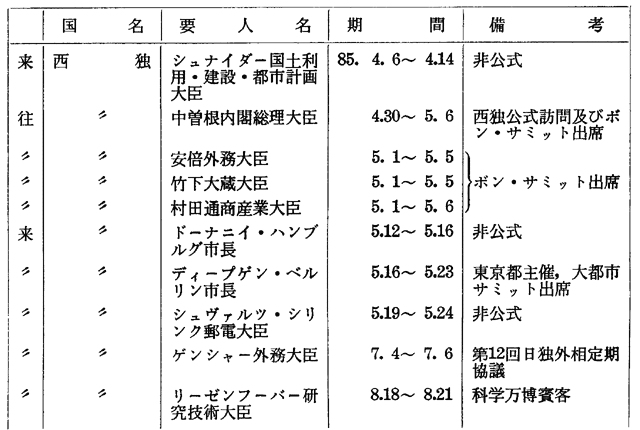
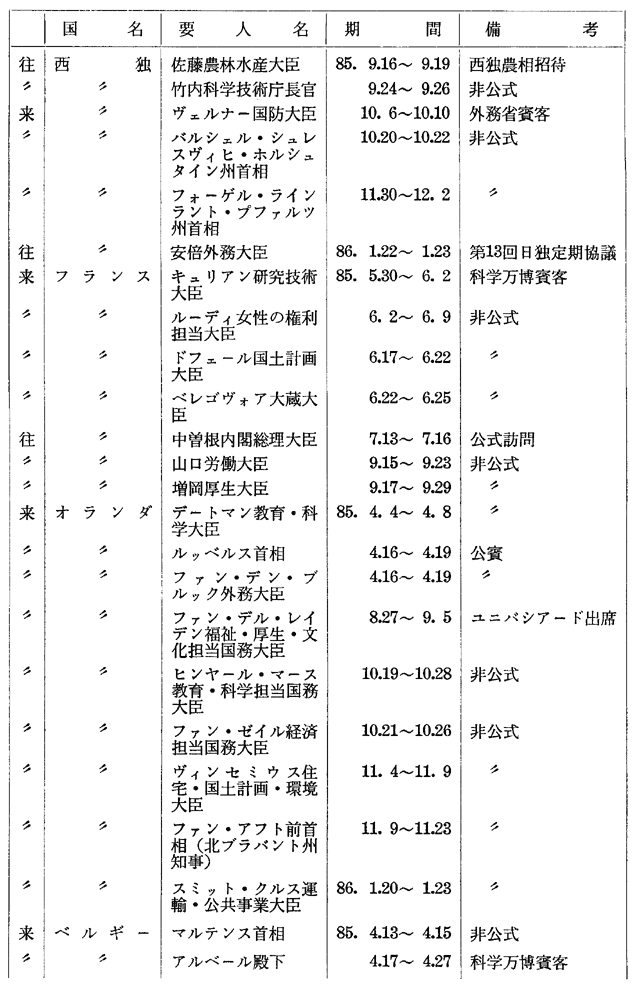

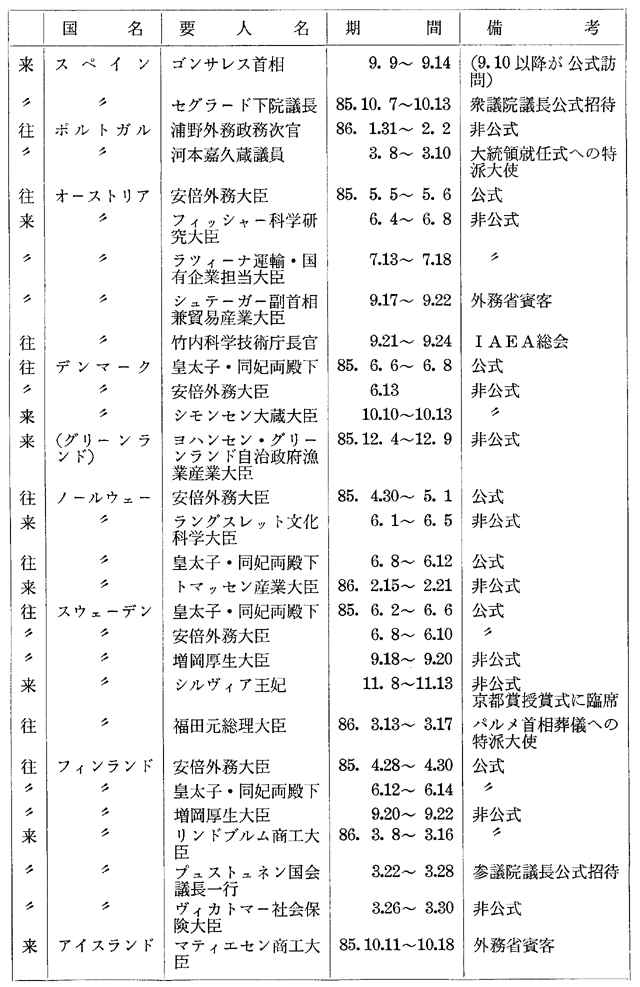
<貿易関係>
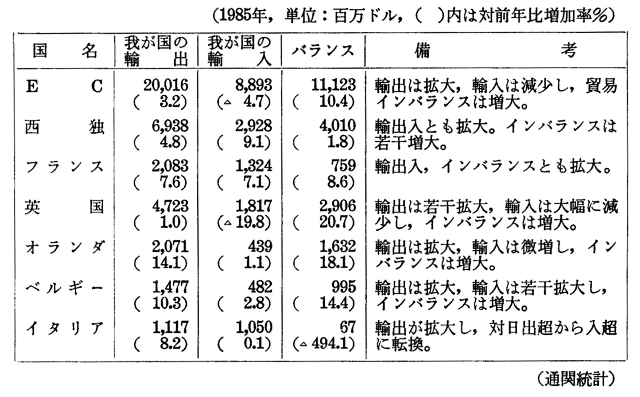
<民間投資>
(あ)我が国の対西欧直接投資
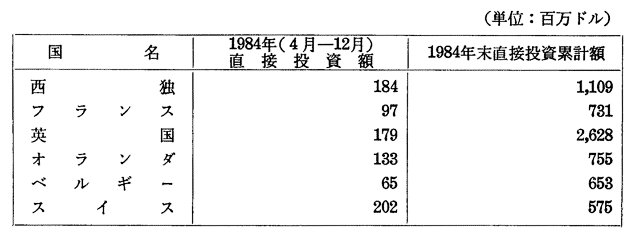
(い)西欧諸国の我が国に対する直接投資