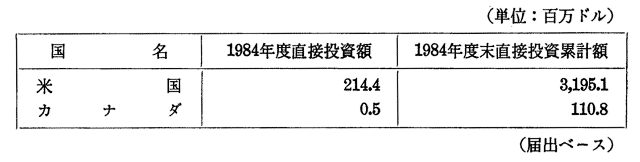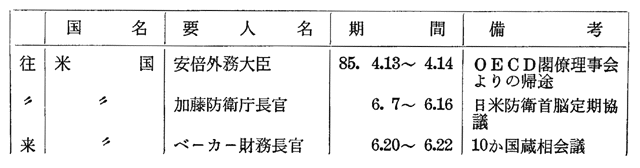
2.我が国と北米地域との関係
(1)米国
(イ)日米関係全般
(a)日米両国は,自由と民主主義という政治・経済上の価値観を共有し,日米安全保障条約に基づく安全保障面での協力関係,往復で950億ドルに上る貿易量に象徴される緊密な経済関係,さらには科学技術面での共同研究,文化交流等といった広範な分野にわたり,友好的な協力関係を築き上げてきた。
我が国は,このような米国との安定した友好協力関係を強化,発展させることが,日米両国民に多大の利益をもたらすとともに,世界の平和と繁栄にとっても肝要であるとの認識の下に,日米関係の強化,発展を我が国外交の基軸としてきている。
(b)82年末に底をついた米国経済は,83年から84年にかけて上向きに推移,成長率は鈍化したものの85年も引き続き堅調を維持し,失業率の低下,物価の安定と言った明るい材料に支えられ,また,我が国の市場開放の努力,円高是正の傾向もあり,米国議会を中心に大きな高まりを見せていた市場開放の対日要求も,若干沈静化に向かった。しかし,増加を続ける米国の対日貿易赤字額は,85年には500億ドル近くとなり,再び議会で対日要求が強まっている。
防衛の分野では日米間の協力関係は良好に維持してきている。
(c)日米両国間に横たわる幾多の問題はあるものの,日米関係の固い絆は近年更に強くなりつつある。
83年の日米両国首脳の相互訪問(1月の中曽根内閣総理大臣訪米,11月のレーガン大統領訪日)により築かれた個人的信頼関係は,85年1月の総理訪米によりさらに確固たるものとなり,86年4月には両国首脳間の不動の友情と相互信頼関係の深さを象徴するものとしてキャンプ・デービッドのレーガン大統領山荘において日米首脳会談が行われた。
日米両国は,今や世界のGNP全体の30%以上を占め,世界の貿易量の20%以上を占めており,その動向は,アジア・太平洋地域,ひいては世界に対し多大の影響を与えるとともに,今後ともグローバルな意義をさらに強めていくものと思われる。
(ロ)日米経済関係
(a)議会などにおける米国内の我が国に対する批判や保護主義圧力は,拡大を続ける大幅な対日貿易赤字(85年は497億ドル:米商務省統計)を背景として,85年から86年にかけても衰えることなく,我が国が対米黒字を目に見える形で減らすことを求める声も聞かれる。
(b)このような状況の下,レーガン大統領は85年8月末に履物に対する輸入救済策を拒否し,12月は繊維法案に拒否権を行使するなど,保護主義的措置に強く反対する姿勢を一貫して堅持する一方,諸外国に対しては公正な貿易を厳しく求めていくことを明らかにする新貿易政策を85年9月に発表した。
(c)日米間では,85年1月に開始された電気通信など4分野における協議(モス協議)が多大の成果を挙げ一応決着し,安倍外務大臣とシュルツ国務長官の共同報告書として発表された。モス協議は今後も継続することが合意されている。また,皮革や弁護士問題も解決をみた。
(d)我が国は,こうした日米間の交渉や協議と並行して,調和ある対外経済関係を目指して,独自にアクション・プログラムを発表し,関税,基準・認証などの分野で大幅な市場アクセス改善措置を講じ,内需拡大策も発表した。さらには,86年4月の「国際協調のための経済構造調整研究会の報告書」を受けて,政府としての経済構造調整の推進体制も決定された。これとは別に,日米間において,日米それぞれの構造問題と対外インバランスとの関係につき対話を行うことが86年4月合意された。
こうした政策展開も米行政府の一定の評価を得ている。
(e)以上の動きに加え,85年9月の5か国蔵相会議後のドル高・円安大幅是正などもあり,米議会を中心とする対日批判そのものは若干沈静化したものの,86年秋の中間選挙をも念頭におきつつ,保護主義的内容をもつ包括的な貿易法案が議会で審議されるなど,保護主義の底流は依然として根強い。
(ハ)日米安保関係
(a)緊密な協議・協力
今日の国際社会においては,我が国が単独で国の安全を確保することは困難である。そのため我が国は必要最小限の自衛力を整備するとともに米国との安全保障体制によって安全を確保することとしている。
現行の日米安保条約は85年で発効から25年を迎えたが,同条約は我が国のみならず,極東の平和と安全の維持に大きく寄与してきている。
近年両国間の防衛面での協力関係は極めて良好であり,日米関係が全般として良好に推移していることの大きな要素となっている。85年においても,同条約の一層円滑かつ効果的な運用を期するため,日米両国間で緊密な協議及び協力が行われた。
(i) 85年においては4月に安倍外務大臣のブッシュ副大統領表敬,シュルツ国務長官との会談(ワシントン),5月の日米首脳会談(ボン),6月の加藤防衛庁長官のワインバーガー国防長官との会談(ワシントン),9月の安倍外務大臣とシュルツ国務長官との会談(ニューヨーク),10月の日米首脳会談(ニューヨーク),さらに86年1月の安倍外務大臣のレーガン大統領,ブッシュ副大統領,シュルツ国務長官及びワインバーガー国防長官等との会談を通じ日米間の良好な防衛関係が確認された。以上の一連の会談では,我が国としては我が国の防衛努力(中期防衛力整備計画,防衛予算)を説明し,米側から高い評価を得るとともに,対米武器技術供与,空母艦載機夜間着艦訓練問題,池子米軍家族住宅問題等日米安保体制の運用にかかわる問題について意見交換を行った。
(ii) 同じく86年1月には,ハワイで第16回日米安保事務レベル協議が開かれ,国際情勢,中期防衛力整備計画を含む我が国の防衛努力,シーレーン防衛共同研究,OTHレーダー,空母艦載機夜間着艦訓練問題,在日米軍駐留支援経費等について意見交換が行われた。
(b)日米安保体制の円滑な運用
(i) 政府は,日米安保条約・地位協定に基づき,我が国の安全並びに極東における国際の平和及び安全のため米軍の我が国駐留を認めており,その駐留を円滑かつ実効あるものにするために各種の措置を講じてきている。85年においても施設区域の整備や在日米軍の日本人労働者の労務費負担を行った。また,米軍施設・区域の円滑な機能を確保しつつも周辺地域の経済的,社会的発展との調和を図るため,施設・区域の整理・統合等の措置もとられた。
(ii) 85年においても日米安保体制の信頼性及び抑止力の向上のための努力が引き続き行われ,F-16の三沢配備が開始されたほか,陸海空それぞれにおいて各種の日米共同訓練が実施された。
(c)戦略防衛構想(SDI)
85年3月に,ワインバーガー米国防長官から安倍外務大臣宛に米国の戦略防衛構想(SDI)研究への参加招請がなされて以来,政府は,研究参加につき慎重に検討を行ってきている。その間,85年4月に米国からSDIに関するブリーフィング・チームが来日したほか,同年9月及び86年1月には政府調査団が訪米し,また86年3月には,官民合同調査団が訪米した。
なお,85年5月,ボン・サミットの際の日米首脳会議において,中曽根内閣総理大臣はレーガン大統領との間でSDIに関し,次の5つの原則的事項につき確認した。
(1)ソ連に対する一方的優位を追及するものではない。
(2)西側全体の抑止力の一部としてその維持・強化に資する。
(3)攻撃核兵器の大幅削減を目指す。
(4)ABM条約に違反しない。
(5)開発・配備については,同盟国との協議,ソ連との交渉が先行すべきである。
(ニ)日米航空関係
(a)85年4月,米国のユナイテッド航空及びパンアメリカン航空は,ユナイテッド航空がパンアメリカン航空の太平洋路線を買収することにつき合意したことを発表し,米国運輸長官の認可を申請した。運輸長官は,同年10月,これを認可することを決定し,大統領は,11月,運輸長官の決定を承認した。
(b)同年12月,米国政府は,日本政府に対し,日米間の太平洋路線において,パンアメリカン航空に代えてユナイテッド航空を指定することを通告し,ユナイテッド航空は,我が国運輸大臣の許可を申請した。
(c)これを受けて,日米両国政府は,日米航空協定上のパンアメリカン航空の地位の承継の問題について協議を行い,86年1月合意をみ,ユナイテッド航空は,同年2月からパンアメリカン航空の輸送力をほぼそのまま引き継ぐ形で運航を開始した。
(d)上記のユナイテッド航空問題等により85年夏以来中断していた包括的協定改訂協議については,これを86年末までに終結させるべく同年3月から再開された。この協議においては,まず,早急に解決を要する問題として,日本側より,日本貨物航空(NCA)の増便問題,米側より,フレート・フォワーダー(貨物取扱い業者)によるチャーター便の運航,営業環境の整備(通関手続の簡素化,空港使用条件の緩和等)等の問題が提起され,現在協議が継続中である。
(ホ)日米医学・科学協力
(a)日米医学協力委員会(65年1月設立)第21回会合は,85年7月15日~19日までワシントンで開催され,8部会の活動報告を中心に意見交換が行われたほか,サウスカロライナ州の国立環境健康科学研究所の視察が行われた。
(b)科学協力に関する日米委員会(61年設立)の第10回共同議長会合は,85年5月15日東京において開催された。また,筑波で開催された科学技術博覧会及び筑波学園都市の視察が行われた。
(ヘ)日米エネルギー関係
(a)政府レベルでエネルギー関係を協議する日米エネルギー作業部会は85年9月ワシントン(第6回),86年3月東京(第7回)で開催された。
(b)石油については,85年10月,米国政府はアラスカ・タックインレット原油の輸出解禁を発表し,内部的手続を進めた。一方我が国においては,85年12月に「特定石油製品輸入暫定措置法」が成立し,86年1月から実際の輸入が開始されたが,米側は,この動きを高く評価した。
(c)石炭については,85年4月に日米民間代表により,技術的問題を協議するための,第2回常設作業部会(STC)が米国で開催された。
民間サイドでは,ペルが炭のプレF/S(商業採算性調査)が継続された。
(d)天然ガスについては85年5月に,アラスカ・ノーススロープ・プロジェクトのプレF/S実施が,日米双方のコンタクト・ポイントの間で合意され,話合いが続けられた。
(2)カナダ
(イ)日加関係全般
(a)日加関係は,マルルーニー政権の対日関係重視の姿勢,中曽根内閣総理大臣の訪加(86年1月)等もあり,順調に発展している。総理訪加の際には,日加間で両国が国際社会において有する共通の立場を再確認し,将来に向けて日加協力の基本テーマを設定した。その後,この基本テーマに沿って,平和と軍縮の追求,保護主義との戦い,日加経済関係の拡大等の分野における日加間の協力関係が着実に進展している。
(b)また,カナダよりは,クラーク外相をほじめ大蔵,通産大臣等の主要閣僚が訪日するなど,各界要人との交流,意見交換も活発に行われた。
また,東京サミット後に,マルルーニー首相の公式訪問が予定されている。サミットをはさんでの日加間の首脳相互訪問を通じて,現在の日加協力関係の一層の発展が期待される。
(ロ)日加経済関係
日加貿易は我が国からの製品輸出,カナダからの原材料輸入という相互補完的なパターンで推移してきている。85年の往復貿易額は92億9,000万ドルと前年とほぼ横ばいであった。我が国はカナダにとって輸出入とも米国に次ぎ第2位の貿易相手国となっている。二国間収支は我が国統計では一貫して我が国の入超となっているが,近年その幅は縮小傾向にあり,従来出超であった加側統計においても対日入超となったことは注目される。
対加自動車輸出問題では従来の「天気予報」方式による輸出見通しの通報を廃止し,日加双方で輸出入をモニターすることとした。
石炭の輸入は1,780万トン(うち原料炭1,700万トン)と全石炭輸入の19.4%を占め,84年に続き,豪州に次いで第2位となった。
長年にわたり民間で話合われていたLNG輸入問題は,価格等を巡り難航していたが,原油価格急落等の影響もあり,結局双方合意の上で白紙還元された。
漁業関係では85年4月,日加漁業協議が開かれ,対日漁獲割当等を中心に討議が行われたが,85年の割当はほぼ前年並みの3万8,000トンに決定された。
投資面では,自動車関連の対加直接投資の動きが目立った。
日加間のフォーラムとしては第6回日加経済協力合同委員会(5月)等が開かれたほか,新たに日加電気通信定期協議(5月),日加産業協力協議(9月)が開かれた。民間でも,第8回日加経済人会議がカルガリーで開かれ,カナダ側からはマルルーニー首相も参加し,スピーチを行うなどカナダ側の強い関心が示された。
<要人往来>
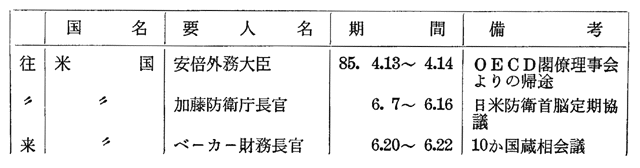
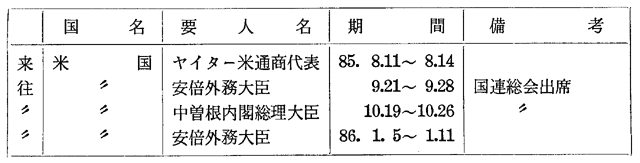
<要人往来>
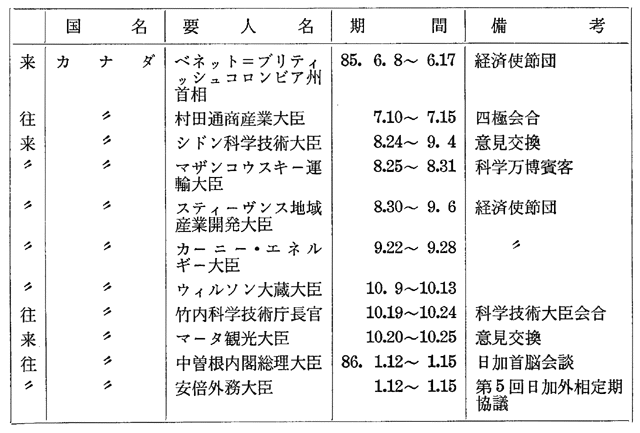
<貿易関係>
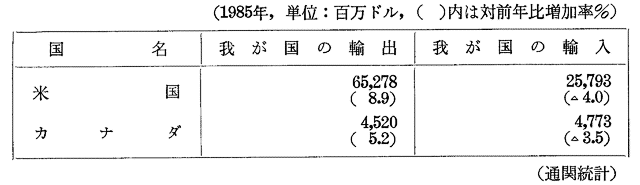
<民間投資>
(あ)我が国の対北米直接投資
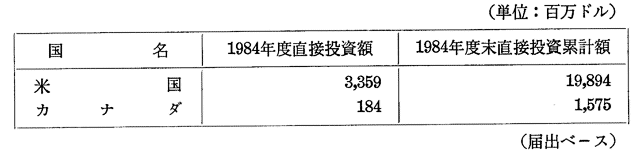
(い)北米の我が国に対する直接投資