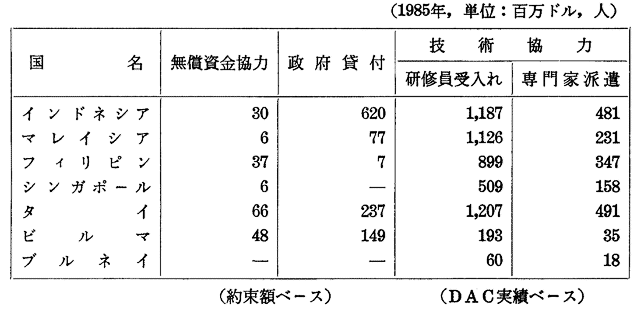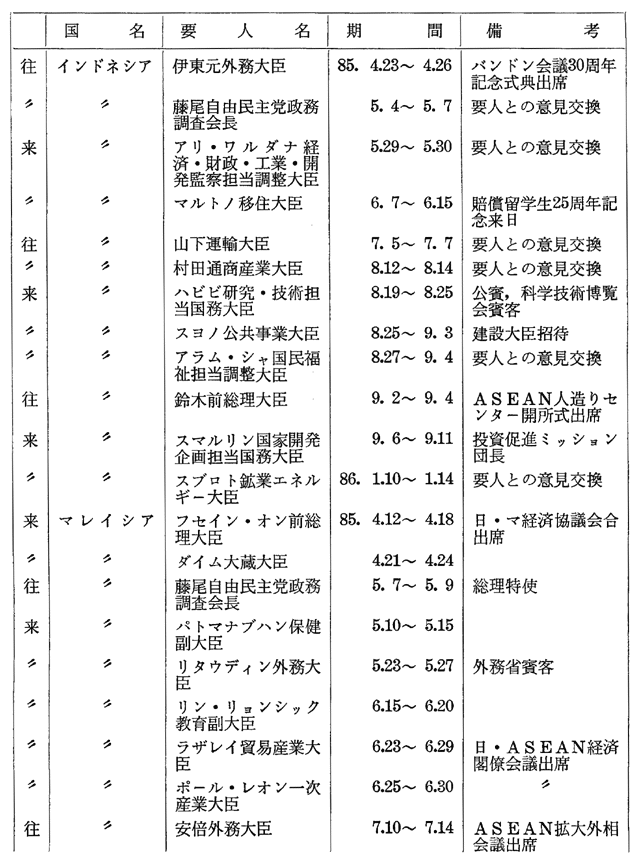
3.東南アジア諸国連合(ASEAN)6か国及びビルマ
(1)ASEAN6か国及びビルマの内外情勢
(イ)インドネシア
(a)内政
スハルト政権は,85年においても前年に引き続き次期総選挙(87年)及び次期大統領選出(88年)に向けての体制固めに努め,国軍の再編を進めるとともに,パンチャシラ(国是五原則)を唯一の原則として確立させるため政党法改正法及び社会団体法を成立させた。この過程においてパンチャシラの徹底化政策に一部のイスラムグループや反体制グループが反発し,84年9月以降ジャカルタを中心に暴動,爆破等の事件が発生したのに引き続き,85年に入っても中部ジャワのボロプドール遺跡爆破事件(1月),東部ジャワのバス爆破事件(3月)が発生した。しかし,その後以上の事件の関係者が相次いで逮捕されたこともあり,事態は鎮静化した。政府は事件関係者に対しては,国家転覆罪を適用することとし,85年1月以降タンジョンプリオク事件及び銀行爆破事件の裁判を開始した。この結果事件関係者には,10年から20年の懲役刑判決が下された(ダルソノASEAN元事務局長は上告した)。
かくてスハルト政権は,一部のグループからの反発を受けながらも,いわゆる政治5法案を成立させ,すべての社会団体にパンチャシラを唯一の原則として認めさせることに成功しつつあり,体制固めを一層前進させた。
しかし内外の経済環境はかなり厳しいものがあり,国内経済不況,失業者の増大,貧富の格差の問題等が指摘されていることから今後の同国の政治的・社会的安定の維持は,経済の停滞をいかに克服し,国民の期待に添い得るかにかかっていると見られる。
(b)外交
インドネシアは,ASEANとの連帯及び非同盟積極自主外交を標ぼうするとともに,米国,日本及びEC等西側諸国との協調を通じて開発を進め,もって国家強靱性の強化を図るとの基本路線をとっているが,85年においてもこの路線が踏襲された。
85年の主な動きとしては,第1回アジア・アフリカ諸国会議30周年記念式典の開催(4月),67年以来外交関係が凍結されている中国との間での直接貿易の再開(7月),スハルト大統領の東欧諸国訪問(9月)に見られる対東側外交を含む幅広い外交の展開,カンボディア問題解決に向けてのモフタル外相のイニシアティブ等が挙げられる。
中国との直接貿易再開は,中国市場へのアクセス拡大を図るため,「イ」商工会議所(KADIN)が中国国際貿易推進委員会との間で交渉を進め,7月に両者の問に了解覚書が調印され,18年振りに直接貿易が再開された。ただし「イ」政府は中国との国交正常化に対しては依然慎重な態度を維持している。スハルト大統領の東欧諸国訪問に加えて,ソ連,チェッコスロヴァキア,北朝鮮等の共産圏諸国との要人の往来が相次いだところ,かかる動きは非同盟外交政策の確認と経済貿易拡大努力の現われと見られる。
(c)経済
84年の国内総生産は,前年比5.8%増と予想外の好成績であったが,85年については3%前後となる見通しである。分野別では,米の生産は2,630万トンと見込まれ,引き続き好調であるが,鉱業生産が大幅に下落したと見られている。貿易面では,非石油・ガス産品の輸出が国際価格の低落等から振るわなかったこともあり,輸出は総じて不調であった。かかる状況下で,「イ」政府は,85年4月,非石油・ガス産品の輸出促進策の一環として一連の物流円滑化の諸措置を決定した。また,石油・ガス輸出は石油需給の緩和から両者合わせてほぼ横這いとなった。
投資面では,85年の国内投資は,実績ベースでは回復が見られず,外国からの投資も対前年比大幅減となった。
このように,「イ」政府は,経済の過度の石油依存構造を改め,また経済の効率化を促進することにより不況からの脱出に努めているが,世界経済の停滞に加え,昨今の石油価格の急落により楽観し得ない状況にある。
(ロ)マレイシア
(a)内政
85年はマレイシアの内政上,見逃し得ない事件が続発した年であった。
(サバ州政情)4月のサバ州選挙において長年の州政権党であるサバ人民統一党(ブルジャヤ党。マレイ系主体)が連邦与党たる国民戦線の強い肩入れにもかかわらず,結党間もないサバ統一党(PBS)に惨敗した。その後PBSは,国民戦線への加盟を申請したが,選挙時のしこりもあってか受入れられず,さらに州野党がPBS政権の合法性を巡り訴訟を引き起こすなど,サバ州政情は波乱含みとなっている。
(マレイシア華人協会内紛)国民戦線内の第二党たるマレイシア華人協会(MCA)では,2年余にわたり指導権争いが続いてきたが,11月の党大会において反主流派のタン・クン・スワンが圧倒的多数で総裁に選出され,一応の結着がつけられたかに見えた。しかるに,その後同人の支配する大手企業パン・エレクトリック社が倒産し,そのあおりでシンガポール証券取引所が12月初旬閉鎖され,86年1月タン新総裁がシンガポール当局に会社法違反等の容疑で起訴される事態になった。
(バリン事件)半島北部諸州においては,従来よりイスラム過激派グループによる小規模な活動が行われていたが,11月19日,マハディール首相の地元であるケダ州のバリン郡で,イスラム過激派に指導された村民と連邦警備隊が武力衝突し,死者18名を出した。このことは,国民特にマレイ人社会に大きな衝撃を与えた。
(その他)
このほか83年に発覚した25億リンギに上るブミプトラ・マレイシア・ファイナンス社(BMF。マレイシア最大のブミプトラ銀行の香港子会社)の不正融資事件の取扱い,官公労の賃上げ争議,麻薬犯罪の増加に示される治安の悪化等,マハディール政権として対処を要する問題が少なくない。
(b)外交
85年のマレイシア外交は,従来よりの外交路線を継続したといえるが,特にマハディール首相の精力的な外交姿勢が目立った。まず,マハディール首相就任以来円滑さを欠いていた「マ」英関係は,4月のサッチャー首相の訪「マ」及びマハディール首相の初めての英連邦首脳会議出席に見られるとおり,一応の修復がなされた。マハディール首相は,11月下旬中国を公式訪問し,李先念主席,趙紫陽総理,トウ小平中央顧問委主任と会談した。
同訪中には,百名以上のマレイシア経済関係者が同行し,マハディール首相は,懸案である中国のマラヤ共産党に対する精神的支援の問題を棚上げにし,経済関係強化を打ち出すなど,実務的態度に終始したことが注目された。
マハディール首相の3回のインドネシア訪問を始め,要人のASEAN諸国との間の往来は,引き続き活発になされ,7月にはクアラ・ルンプールにおいてASEAN外相会議が開催された。またカンボディア問題解決に向け間接対話提案を打ち出した。
その他の要人往来も盛んで,ブランツ=ユーゴー首相(3月),ロンギ=ニュー・ジーランド首相(3月),ダスカレスク=ルーマニア首相(5月),ガユーム=モルディブ大統領(9月),リャボフ=ソ連副首相(11月),エルシャド=バングラデシュ大統領(11月),金永南北朝鮮副総理兼外交部長(12月)等がマレイシアを訪問した。また,マハディール首相はスウェーデン,フィンランド,ノルウェー,デンマーク,オーストリア(4月),タイ(5月),サウディ・アラビア(9月)を訪問した。このほかマハディール首相は2回にわたり日本を非公式に訪問した(7月及び12月)。
なお,南極問題,麻薬問題でマレイシアは,積極的なイニシアティブをとった。
(c)経済情勢
原油,天然ゴム等一次産品輸出に大きく依存しているマレイシア経済は,85年には先進諸国の景気停滞による対外需要不振及び価格の落ち込みの影響を大きく受け,加えて緊縮財政による国内建設不況等により,経済成長率が,84年の7.6%成長(GDPベース)から2.8%へ落ち込んだ(中央銀行統計)。特に輸出は,天然ゴム及びパーム油等農産品の国際市況悪化による輸出所得の減少が大きく響き,84年より1.4%後退した。
このような景気後退状況下にあって85年の消費者物価は0.3%の上昇と極めて安定していたが,一方失業率は84年6.3%から85年7.0%へ悪化した。
(ハ)フィリピン
(a)内政
85年のフィリピン内政は,8月に,マルコス大統領等の対外資産問題が契機となって野党がマルコス大統領の弾劾を求める(国民議会で否決)など,波乱含みで推移したところ,11月に至り,マルコス大統領が87年に予定されていた次期大統領選挙の繰り上げ実施を示唆して以来事態が急速に展開した。
こうした中で12月2日には,アキノ暗殺事件に関し,公務員弾劾裁判所で無罪判決が言い渡された。
大統領選挙は,与党側では,マルコス大統領及びトレンティーノ元外相が,また,野党側では,アキノ夫人,ラウレルUNIDO総裁が,それぞれ正副大統領候補となって争われた。86年2月7日に投票が行われたが,選挙管理委員会と「自由選挙のための全国市民運動」(NAMFREL)との間で,開票速報の結果が相違したものとなったが,同月15日,国民議会は,マルコス,トレンティーノ両候補を正副大統領選挙の当選者として宣言した。
この後も混迷した情況が続いていたが2月22日にはエンリレ国防大臣,ラモス参謀総長代行らが国防省に立てこもり,マルコス大統領の退陣を要求し,アキノ夫人を始めとする野党と多数の市民の支持の下に勢力を拡大した。2月25日にはアキノ夫人,マルコス大統領の双方が大統領就任式を行うとの事態となったが,同日午後にはフィリピン国軍の大部分がアキノ側支持にまわったこともあり,同日夜マルコス氏はマラカニアン宮殿を離れ,26日フィリピンを出国した。アキノ大統領は,同日新閣僚名簿を発表するなど新政府の体制造りに入った。
アキノ大統領は3月25日には,暫定憲法を発表するとともに,今後の政治日程(新憲法起草委員会の設立及びその活動予定,並びに新議会の開設等)を公表した。
(b)外交
85年についても,フィリピン政府は,内政上の対応に迫られ,外交面においては,経済再建のための国際機関及び我が国,米国等主要援助供与国との交渉に重点が置かれた。
対米関係については,米国より,多くの要人が訪比し,マルコス大統領等比国要人に対し,政治・経済・軍事等の面での諸改革を求めた。
ソ連との関係では,イメルダ大統領夫人が3月(チェルネンコ書記長の葬儀参列及びゴルバチョフ書記長との会談)及び10月に訪ソし,ソ連側から,ソロヴィヨフ外務省第2極東部長が訪比した。
中国との関係では,4月,呉学謙外交部長が訪比し,6月には比中両国の国交樹立10周年が祝われた。
なお,86年2月のアキノ新政権発足後,ラウレル副大統領が,新外相に任命された。
(c)経済
85年のフィリピン経済は,84年に引き続き,経済困難克服のため,一連の金融引締,緊縮財政政策がとられたことなどから,全般に低調に推移した。具体的には,物価は年間平均23.1%の上昇となったが,経済成長率はマイナス4%となった。また国際収支状況を見ると,貿易収支は,4億8,000万ドル,経常収支は,8,000万ドルの赤字となった。
また,フィリピンは,IMFからスタンドバイクレジットによる支援を受ける一方,民間銀行団から,新規融資,短期貿易信用等の金融支援措置を得て,対外債務問題への対処に努めた。
(ニ)シンガポール
(a)内政
85年は,リー首相より次世代への権力の完全な移譲へ向けての模索が引き続き行われた年であった。
上半期を過ぎ,経済不況が国内の最大課題となる中で,同首相は不況克服が首相後継者にとっての試金石であることを示唆した。この面で85年を通じ最も活躍が注目されたのは,ゴー・チョク・トン第1副首相及びリー・シェン・ロン国務相であった。特にリー国務相は,政界入り1年目であるにもかかわらず,商工兼国防担当国務相のポストに加えて,4月経済委員会委員長に任命され,経済政策全般にわたる発言権を与えられた。他方,トニー・タン商工相は,従来タブー視されていた中央厚生基金(CPF)の利率引下げを大胆にも提言したところ,同商工相の存在も引き続き注目に価する。
なお,3月にデヴァン・ナイア大統領が病気を理由に辞任し,その後8月にウィー・キム・ウィー=シンガポール国営放送会長(前駐日大使)が第4代大統領に選出された。
(b)外交
85年のシンガポール外交は,従来に比し,一層活発に展開された。
リー首相は,4月にインドネシア,6月にタイを訪問するなど,近隣諸国との関係強化を図った。また,9月に中国,続いて10月に米国へ(その後バハマでの英連邦首脳会議に出席)と首脳外交を精力的に行った。
上記訪中の際には,両国の経済・貿易関係の拡大につき合意を見た。米国訪問では,リー首相が自由貿易体制維持の必要を強調した。
なお,訪「シ」した主な諸外国要人としては,1月ヴィラタ首相(フィリピン),呉外交部長(中国),3月ロンギ首相(ニュー・ジーランド),ヘイドン外相(豪州),4月サッチャー首相(英国),7月李外相(韓国),9月シティ外相(タイ)等が挙げられる。
(c)経済
84年以降下降局面にあったシンガポール経済は,85年に入りその下げ足を早め,第2四半期に至って対前年同期(以下同)でマイナス1.2%と過去20年来初のマイナス成長を記録した。その後,第3・第4四半期は,更に落ち込みを見せ,年全体でマイナス1.7%の成長となった。
これは,米国向けを中心とする輸出の低迷(対外輸出-1.5先(1~10月期))に加え,造船,海運,不動産,建設等構造不況業種の存在,新規投資の減少(海外からの製造業新規投資約9億ドル(84年の約7割弱))等の要因によるものである。
このような経済の低迷は,雇用面の悪化をもたらし,約9万人の雇用が失われた。このうち,約6万人は外国人労働者と見られるものの,失業率は,年央の調査で4.1%となり,84年まで2~3%とほぼ完全雇用を達成してきたシンガポール経済も雇用の確保が深刻な問題となるに至った。
また,このような景気の停滞を反映し,経済界では倒産が相次ぎ,特に11月のパン・エレクトリック社の経営危機は,証券ブローカーの経営危機を引き起こし,証券市場の3日間閉鎖という事態を招来するに至った。
(ホ)タイ
(a)内政
85年9月9日,軍の一部によりクーデターが試みられたが,プレム首相は,王室及び軍の大勢の支持を得て同日中にこれを鎮圧し,同事件に関与したとされるクリアンサック前首相を含む関係者40名が起訴された。
プレム首相は,また,今次事件解決に功労のあったチャワリット陸軍大将を10月の軍定期異動で陸軍参謀長に昇格させるとともに,内政上の懸案となっていたアーティット国軍最高司令官兼陸軍司令官の定年再延長要求についてはこれを却下(86年3月)し,軍部のプレム支持体制固めを図った。
他方,政党との関係では,クリアンサック党首率いる国家民主党に代わって進歩党が連立内閣に参加したほかは,4政党連立体制に基本的変化はなかったが,一連の補欠選挙で与党民主党が伸張を見せたのに対し,与党第1党の社会行動党の凋落傾向が目立った。特に,12月のバンコック補選敗北を機にククリット社会行動党党首が辞任,右を機に党内の不満が噴出し,同党所属閣僚の交代(86年1月)につながった。
(b)外交
85年のタイ外交は84年同様,(i)同国の安全保障に直接かかわるカンボディア問題への対応,(ii)日・米等西側諸国との関係強化,(iii)中国との良好な関係の維持の3点を中心に展開された。
カンボディア問題では,84-85年乾期の軍事的成果を背景にしたヴィエトナムの外交攻勢を前に,ASEANの結束の維持を図るとともに,民主カンボディア連合政府に対する支援を継続し,7月には,他のASEAN諸国とともに,民主カンボディアとヴィエトナムとの間接対話を提案した(ASEAN外相会議共同声明)。
我が国を含む西側諸国との関係では,貿易分野において摩擦が生じることもあったが,各国との友好関係を維持・強化し,防衛(米国との関係),経済協力,難民対策の面で一層の援助及び協力を期待するとの基本姿勢に変りはなかった。
中国とは,外交関係樹立10周年を迎え,李先念主席がタイ・中外交関係樹立以来中国の国家元首として初めて訪タイする(3月)など緊密な関係を維持した。
ソ連とは,タイ・米経済関係に波風が立つ中でソ連よりタイに対し貿易拡大を示唆するなど関係改善へのアプローチが見られ,サリモフ=ソ連最高会議幹部会副議長の訪タイ(10月),タイ・ソ友好協会の設立の動きなどが注目されたが,タイ政府は基本的に対ソ関係改善には警戒的で,慎重な姿勢を堅持した。
84年発生した国境紛争(三村問題)以来冷却化しているタイ・ラオス関係は,ニット外相特使のラオス訪問(7月),一部戦略物資の対ラオス禁輸解除(11月)等若干「雪どけ」の兆しは見られたものの大きな進展はなかった。
(c)経済
85年のタイ経済は,厳しい国際環境の下,特に一次産品価格低迷による輸出所得の伸び悩み(特に米,砂糖)に直面し,民間消費は概して停滞,民間投資も下降を続け,実質経済成長率は84年の6.2%から4.0%に下落した。
貿易収支及び経常収支は,工業製品輸出の好調,石油輸入の落ち着き,観光収入の堅調もあって,改善が見られたが,依然として大幅な赤字(それぞれ22億5,000万ドル,14億8,000万ドル)を続けている。また,70年代後半以降対外債務返済額が急増しているにもかかわらず輸出が伸び悩み,デット・サービス・レシオが上昇している(80年14.8%→85年21.5%,ただし公的債務及び民間債務の両者を含む)。
タイ政府は83年末以来引き締め基調の経済政策を継続しており,財政支出抑制と対外債務管理強化の観点から大規模プロジェクトの見直しなどが行われたが,依然として,12億8,000万ドルの大幅な財政赤字が存在する。
(ヘ)ブルネイ
(a)内政
ブルネイは,84年1月1日に英国から完全独立を果たし,以来,新生独立国家としての体制造りを推進している。国政は,世襲制の国王を元首とする立憲君主制を基本政体としており,現国王の第29代国王ハサナル・ボルキアが総理大臣・大蔵大臣・内務大臣を兼任している。立法議会は84年2月に解散されたままとなっているが,高い所得水準を背景に内政は安定している。85年5月,独立以来初の政党であるブルネイ国家民主党が結成され,その動向が注目されている。
(b)外交
独立した84年には,国際機関加盟,外交関係の開設等活発な動きがあったが,85年は,比較的地道に諸外国との関係緊密化を図ったと言えよう。
ブルネイの対外政策の基本は,ASEANを中心に域内の安定に努めるとともに,国防については英国との防衛取極を中心に近隣の英連邦諸国との緊密な協力を図っていくというものである。国王は,10月英連邦首脳会議(バハマ)に出席したほか,11月オマーン国祭日記念式典に出席した。
(c)経済
経済活動の中心は,石油及び天然ガスであり(84年国内総生産の74%,総輸出額の99%を石油・天然ガスで占めている),同資源により,高い所得水準(84年1人当たりGDPは1万7,824ドル)を維持している。石油の生産,販売は,ブルネイ・シェル石油会社が,天然ガスの生産は,ブルネイLNG会社がこれにあたっており,LNGは長期契約に基づきその全量(年約500万トン)を我が国へ輸出している。
一方,石油資源は21世紀初めには枯渇するとの見方もあることから,過度の石油資源依存からの脱却を目指し,経済の多角化・人材開発を促進すべく,86年より第5次開発5か年計画が開始された。
(ト)ビルマ
(a)内政
85年は,4年に一度の党大会及び総選挙が実施されるなど政治面では比較的動きの多い年であったが,結果的には,ネ・ウィン=ビルマ社会主義計画党総裁の監督の下でサン・ユ大統領を中心とした現体制が一段
と強化された。国内治安面では,ビルマ共産党及びカチン,カレン等の少数民族反乱軍の掃討,鎮定努力が続けられたが,依然としてこれら反乱軍は,主に国境地区を根拠として活動を続けている。
(b)外交
外交面では,85年においても,従来の基本路線である非同盟中立政策を軸とした活発な動きが見られた。特に,対中国関係は前年に引き続き極めて活発に展開され,李先念主席(3月)のビルマ訪問(以下「訪緬」)に続き,ネ・ウィン党総裁の訪中(5月)が実現する等各方面の交流が目立った。
また,近隣諸国,特にASEAN及び南西アジア諸国からは,ジァウル・ハク=パキスタン大統領(5月),シリントーン=タイ王女(86年3月)等の要人の訪緬が相次いだほか,ダスカレスク=ルーマニア首相(5月)等東欧諸国からの要人の訪緬があった。
これに対しビルマからは健康診断及び治療のため,ネ・ウィン党総裁が西独(6月),サン・ユ大統領が米英両国(11月~86年1月)を訪問したほかは,国内政治日程上の制約もあってか,政府首脳部による注目すべき訪問外交は特に見られなかった。
(c)経済
85年は,ビルマ経済にとり全般的に84年に引き続き困難な年であった。政府は,経済情勢の悪化に対し,街頭小売商人の追放,外国製薬会社のビルマ人代理人の活動規制,米や石油の闇取引きの規制等の動きに
見られるように・差し当たり統制強化により対処した。その中でも特筆すべき事件は,資本家の手元にある闇資金を暴くためにとられた「100チャット」紙幣等の高額紙幣の流通停止措置(11月)であり,この措置により一般大衆も少なからぬ打撃を被る結果となった。
貿易面では,主要輸出産品である米が需要の伸び悩みと価格低迷により,また,同じくチーク材が資源の制約と関連インフラの不備により,ともにこれ以上の輸出拡大が困難な事情にあることに加え,代替輸出産品の開発の遅れなどから,輸出は前年同様に不振を極め,政府は輸入節減策を強いられた。
(イ)インドネシア
インドネシアは我が国にとって第2の投資対象国であるとともに貿易面で第3の相手国であり,他方インドネシアにとって我が国は,投資,貿易とも最大の相手国となっている。かかる相互補完関係を背景に我が国とインドネシアとの関係は,近年ますます緊密化している。85年においても双方の要人の往来が頻繁に行われ,藤尾自由民主党政務調査会長一行,村田通商産業大臣並びに鈴木前総理のインドネシア訪問,インドネシアより元賠償留学生一行及び投資促進ミッションの来日,日「イ」エネルギー合同委員会の東京開催等を通じて両国間の相互理解の一層の増進が図られた。
(ロ)マレイシア
安倍外務大臣のASEAN拡大外相会議出席のためのマレイシア訪問(7月),マハディール首相の2回(7月及び12月)にわたる訪日,藤尾自由民主党政務調査会長一行の訪「マ」(5月)及び経団連ミッションの訪「マ」(1月)等日「マ」要人の交流が活発に行われ,また,筑波科学技術博覧会開催期間中は,「マ」側王族を始め多数の「マ」側要人が訪日した。
82年より開始された「東方政策」に基づくマレイシアからの留学生及び産業技術研修生の派遣計画は,85年においても,日「マ」双方の側において順調に実施された。
日「マ」間の懸案であった航空問題もマレイシア航空の単独運航による東京経由米国西海岸乗り入れが実現する形で解決され,8月クアラ・ルンプールにおいて日「マ」航空協定付表改訂のための交換公文が署名された。
(ハ)フィリピン
85年の日比関係は,前年に引き続き経済及び経済協力問題を中心に展開した。特に我が国からは,2月の稲山(経団連会長)ミッション,5月の藤尾(自由民主党政務調査会長)ミッション等,政財界代表による使節団が訪比し,両国間の貿易,投資,経済協力等に関し幅広い意見交換がなされた。
また11月には,イメルダ大統領夫人が非公式に訪日した。
85年の両国の貿易は対日輸出12億4,300万ドル,対日輸入9億3,700万ドルとフィリピン側の輸入需要低下と日本側の輸出保険が制限的なことから比側の出超となった。
また,我が国は,85年6月,アクション・プログラムの一環として,フィリピンの関心の深いバナナ関税を10~3月期35%,4~9月期17.5%からそれぞれ25%,12.5%に引き下げる方針を示した。
(ニ)シンガポール
日本とシンガポールの間では,単に経済分野だけではなく,社会及び文化等広範な分野で緊密な関係が発展してきている。我が国は,シンガポールの期待にこたえるべく,日「シ」技術学院,日「シ」ソフトウェア技術研修センター,シンガポール生産性向上プロジェクト等への協力を進めている。
他方,貿易の分野では,我が国は,シンガポールにとり重要な貿易パートナーであり,輸出入総額で85年では米国,マレイシアに次ぐ第3位となっている。シンガポールの日本への輸出は,15億9,000万米ドルと対前年比10.7%減,他方,同国の日本からの輸入も38億6,000万米ドルと前年比16.3%減となった。
(ホ)タイ
日・タイ関係は全体として極めて良好で,広範な分野で緊密な関係が維持された。
その中で,最大の懸案となっている貿易不均衡問題を巡っては,我が国は6月にタイ側関心品目の骨なし鶏肉等について関税引下げを決定するとともに,12月にはピチャイ副首相の下でタイ側が作成した「タイ・日経済関係構造調整白書」に基づき両国の経済関係の現状と今後の協力関係のあり方について意見交換を行い,相互理解の増進が図られた。
(ヘ)ブルネイ
我が国は,ブルネイの最大の貿易相手国(84年のブルネイの全輸出入量に占める対日輸出・対日輸入の割合いは,それぞれ68%及び20%)であり,ブルネイ産原油の約5割,LNGの全量が我が国へ輸出されている。
ブルネイの国造りに対して,我が国は技術協力,教員派遣等を通じ,積極的な協力を行っている。
また,ブルネイは,85年の筑波科学万博に出展し,7月にラーマン開発大臣が科学万博賓客として来日した。
86年3月には,在本邦ブルネイ大使館が開館の運びとなり,今後一層の両国間の交流活発化が期待されている。
(ト)ビルマ
85年の両国関係は,トゥン・ティン副首相等の閣僚の訪日及び藤尾自由民主党政務調査会長の中曽根内閣総理大臣特使としてのビルマ訪問等要人の相互訪問が活発に行われたのを始め,経済協力を中心としたあらゆる分野において,前年に引き続き着実な進展を見せた。
86年1月には,ビルマ側の要請に応じ我が国よりビルマ輸出産品調査ミッションが派遣された。
<要人往来>
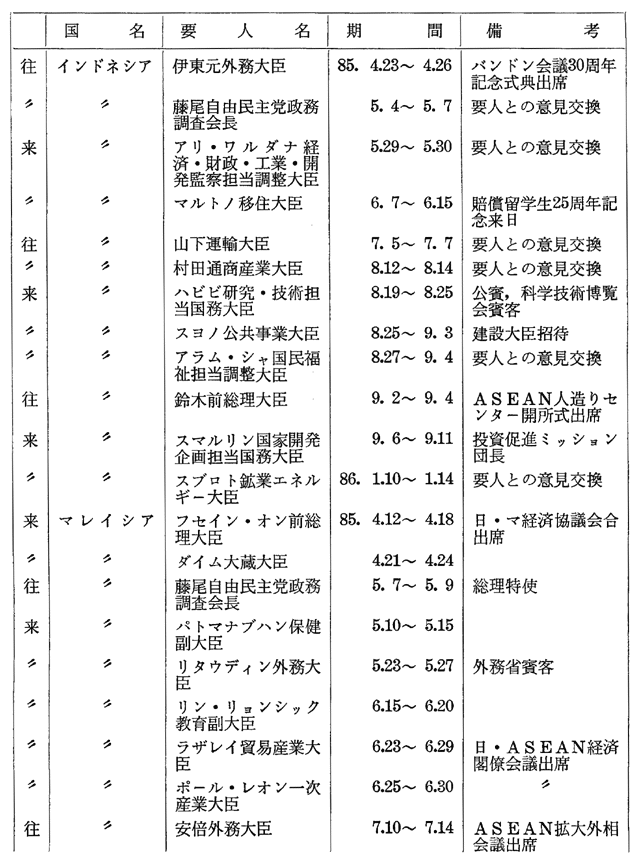
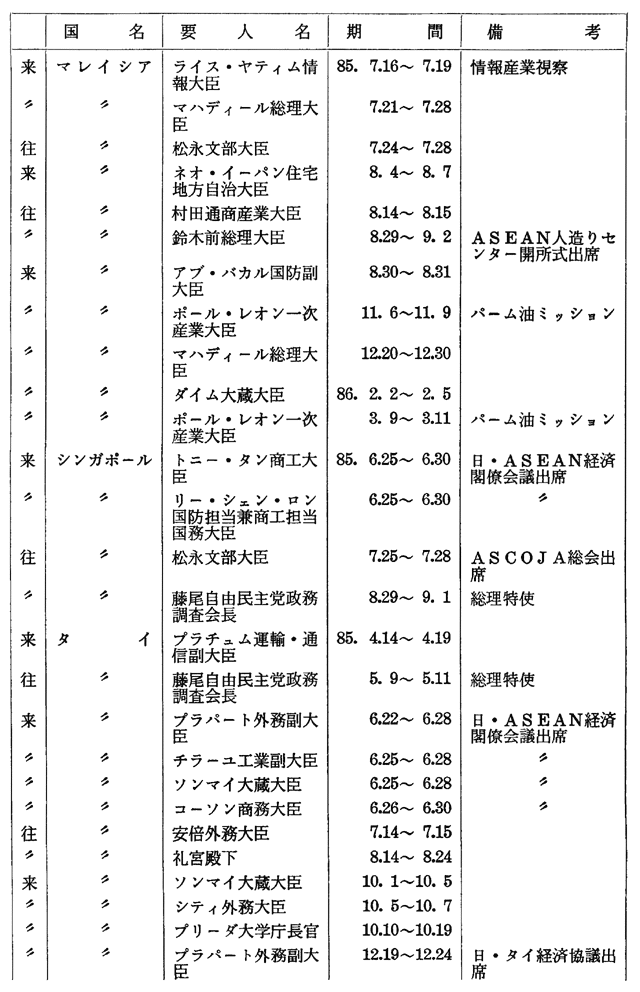
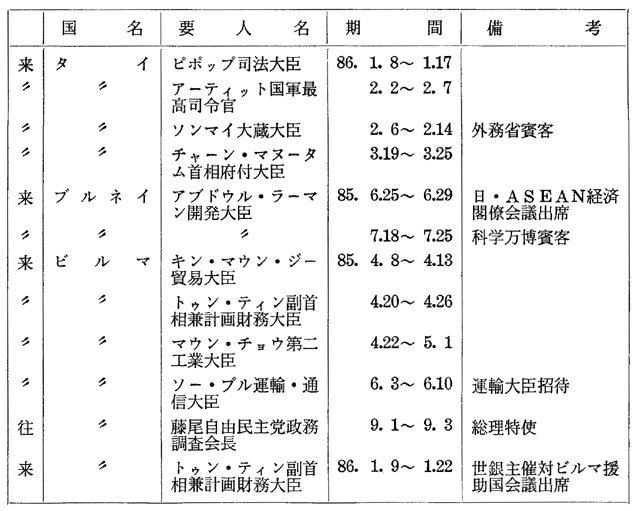
(<要人往来>フィリピンの項は234頁参照)
<貿易関係>
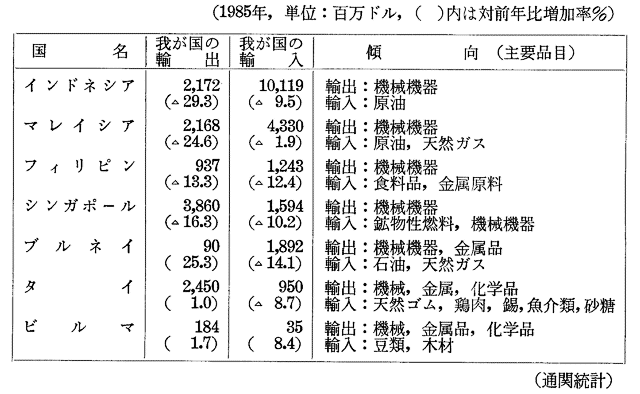
<民間投資>
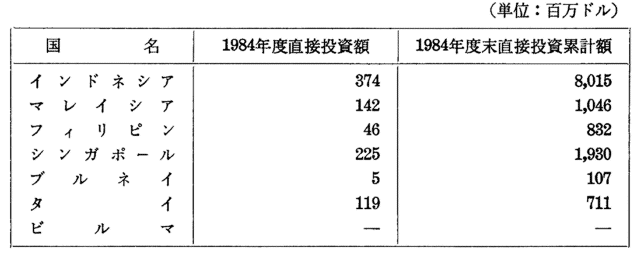
<経済協力(政府開発援助)>