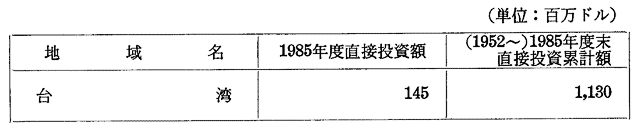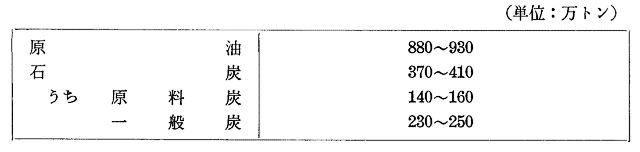
2.中国
(1)中国の内外情勢
(イ)内政
(a)全般
85年には中央・地方の党・政・軍幹部の大幅な若返りが実施され,100万人の兵員削減や大軍区再編成等軍近代化への動きも見られた。85年は第6次5か年計画の最終年,経済体制の全面的改革の初年度に当たり,また86年より実施される第7次5か年計画策定のための準備が行われた。
(b)党全国代表会議と若返り
9月の党全国代表会議とその前後の党第12期4中全会,5中全会で党中央の若返りが図られた。政治局では葉剣英政治局常務委員ら10名が辞任,胡啓立ら6名が就任したほか,書記処,中央委員会等でもメンバーの新旧交替が行われた。
国務院では,85年だけで,45閣僚のうち半数近くが交替し,地方でも29省・市・自治区の党委書記15名,省長12名が交替するなど,若返りと教育程度重視による人事異動が行われた。
(c)整党と不正の取締り
第2期整党は,84年12月より地区・県レベルで行われ,85年冬から87年春にかけて全国農村で行われている。これと併行して85年秋頃より思想教育強化,党風是正とともに再び「不正の風」是正の強調と厳しい処罰が行われた。
(d)軍の改革
84年の兵役法改正に続き,85年6月,軍の少数精鋭化のため2年間に兵員100万人を削減することが正式に決定された。また,大軍区の統合,指導部組織の簡素化と若返り,集団軍への改編等,軍の改革が行われた。86年1月に設置された国防大学は9月開校の予定である。
(e)全国人民代表大会
第6期全人代第4回会議は86年3月から4月にかけて開催され,趙紫陽総理が第7次5か年計画に関する報告を行い,同計画及び民法通則,義務教育法,外資企業法が採択された。
(ロ)外交
(a)全般
中国は85年も積極的な外交活動を展開した。トウ小平主任は3月「現在世界の戦略問題は平和と経済発展である」旨発言し,10月の国連創設40周年記念会期における趙紫陽総理の演説もこれを基調として行われた。超総理は86年3月の全国人民代表大会において従来の外交諸政策をまとめた「外交10原則」を発表した。なお,ボリビア(7月),グレナダ(10月),ニカラグァ(12月)との外交関係樹立により,中国は133か国と外交関係を持つことになった。
(b)対米関係
7月の李先念国家主席の訪米,10月のブッシュ副大統領の訪中により高いレベルの対話が継続され,貿易額も増大するなど全般的に順調に進展した。
李主席訪米時に米中原子力協定が調印され,年末これにレーガン大統領が署名した。また中国は対米繊維製品輸入規制を目的とするジェンキンズ法案に反発し,年末レーガン大統領の拒否権により同法案が廃案となったことを歓迎した。軍事関係では,春に予定されていた米艦の中国寄港は見送られたものの,10月ガブリエル空軍参謀総長が訪中,11月徐信副総参謀長が訪米し,86年1月米中両国海軍艦艇が洋上で初めて挨拶を交換するなどの交流が見られた。
(c)対ソ関係
ゴルバチョフ書記長登場以来の1年間に,中ソ間の経済,貿易,技術協力・文化等実務面での進展は見られたが,中国側の提起している「三つの障害」除去について進展は見られなかった模様である。
7月姚依林副総理が訪ソし長期貿易協定,経済技術協力協定に署名し,9月国連総会に出席した中ソ外相の会談において両国外相の相互訪問が原則的に合意された。また,12月モスクワに立寄った李鵬副総理はゴルバチョフ書記長と会談した。86年に入ってからも3月アルヒポフ第1副首相が訪中するなど往来は続いている。
(d)対アジア関係
(i) 北朝鮮との関係では,5月胡ヨウ邦総書記が非公式に,10月李鵬副総理が各々訪朝した。また,11月金永南外相訪中の際,領事条約が調印された。
韓国との関係では8月及び86年2月中国空軍機が韓国に入域するという事件が発生したが,中国と韓国との間の直接交渉を通じて冷静に処理された。
(ii) 東南アジア諸国との関係では,4月バンドン会議30周年記念式典出席のためインドネシアを訪問した呉学謙外交部長がモフタル外相と会談し,7月には,両国間直接貿易再開に関する覚書が調印された。
9月には,リー・クアン・ユー=シンガポール首相が,また11月にはマハディール=マレイシア首相が相次いで訪中するなど,中国とASEAN諸国との関係強化が図られた。86年3月フィリピンのアキノ新政権成立に際しては祝電を発出した。このほか,85年3月李先念主席がビルマ,タイを訪問した。
(iii) 南西アジア関係では,10月国連総会出席の中印両国首相が会談したのを始めとして,11月第6回中印交渉がニュー・デリーで開かれた。その他パキスタン,バングラデシュ等との間においても要人の往来が見られた。また,12月の南アジア7か国首脳会議開催に当たり祝電を発出した。
(iv) インドシナ関係では,胡ヨウ邦総書記が年末年始に西沙群島を訪問し軍民を激励したのに対し,ヴィエトナム側は反発を示した。他方,86年3月民主カンボディア政府が北京で8項目の新提案を発表し,中国は直ちに支持を表明した。
(e)対西欧・大洋州関係
6月趙紫陽総理は英国,西独,オランダを訪問した。5月エアネス=ポルトガル大統領が訪中し,86年よりマカオ問題の交渉開始に合意した。
4月胡ヨウ邦総書記は豪州,ニュー・ジーランド等大洋州5か国を歴訪し,他方5月フィジー首相,6月キリバス大統領,86年3月ロンギ=ニュー・ジーランド首相が訪中した。
(f)対東欧・モンゴル関係
李鵬副総理は5月と12月に東欧5か国を訪問し,また3月オポドフスキー=ポーランド副首相,10月クライバー東独副首相,12月オブジナ=チェッコスロヴァキア副首相が訪中,この間中国はアルバニアを含む東欧諸国と長期貿易協定を締結した。
12月中国・モンゴル間で,86年よりモンゴル側が定期航空便を復活することに合意した。
(g)対南米関係
10月趙紫陽総理は中国総理として初めて南米4か国を歴訪した。中国がこの1年間に外交関係を樹立した3国がすべて中南米地域である点も注目される。
(ハ)経済情勢
(a)農村における経済体制改革では,85年前半までに全国5万6千余の人民公社を改組し,9万2千余の郷鎮政府を設立させた。また,生産請負責任制発展の過程で専業農家を発展させているほか,農産物の商品化が進められている。
85年には30余年来続けられてきた農業・副業生産物の統一買上・販売制度を契約買付制に改め,統一買上・販売を実施していた39品目については一部を除き統制を撤廃,価格も自由化が図られた。
都市の改革については,企業の自主権拡大を中心として進められた。
また,従来よりの企業縦割体制に対し,横断的な連携も強化され,85年全国で結ばれた経済技術協力取決めは3万5,000件余に上った。
さらに対外開放について,85年3月には,長江三角州など3デルタ地帯の「沿海経済開放区」指定が行われるなど,開放地域は次第に拡大されてきた。しかし,これら開放区に期待された輸出型で先進的な工業体系の形成という当初の目的は未達成であり,86年初めの全国経済特区工作会議では,外向型経済確立の目標が打ち出されている。
(b)85年の経済実績は,国内総生産額で7,780億元(2,649億ドル)と前年比12.5%増,国民所得では6,765億元(2,304億ドル)と同じく12.3%増,また,工農業総生産額では1兆3,269億元,16.4%増となった。以上,生産は大幅に伸長したが,固定資産への過剰投資,消費基金の過度の伸び,需給インバランス,通貨増発等による物価上昇(前年に比し8.8%上昇),社会成員間の所得格差拡大などの問題が指摘されている。
(c)85年の農業総生産額は4,510億元と前年比13%増(ただし,村営工業分を除くと3,575億元と3%増)となったが,穀物生産高は自然災害,作付調整等により3億7,898万トンにとどまり,前年比7%減となった。
(b)85年の工業総生産額は8,759億元と前年比18%増。うち,軽工業総生産は4,089億元,同じく18.1%増,重工業総生産は4,670億元,同17.9%増とほぼ均衡して発展。大衆の生活水準向上による需要増大を反映して,耐久消費財の伸長(テレビ62%増,家庭用洗濯機53%増)は顕著であったが,他方,エネルギー生産,鉄鋼等素材生産は比較的低い成長に推移した(一次エネルギー生産高7.8%増,粗鋼7.3%増)。
(e)85年の全人民所有制単位の固定資産投資は1,652億元,うち,基本建設投資は1,061億元と前年比42.8%増と急増したが,エネルギー・交通への投資は相対的に鈍化,これらの基本建設投資総額に占めるウエイトは84年の37%から85年には36%弱へと低下している。
(f)85年の社会商品小売額は4,305億元と前年比27.5%増で,特に扇風機100%増,家庭用洗濯機70%増など家電製品の伸びが顕著であった。
(g)85年の貿易総額は通関統計によると696億2,000万ドルと前年比30%増。うち中国の輸出は,273億6,000万ドル,同一%増,輸入422億6,000万ドル,同54.2%増となった。輸出入バランスは149億ドルの入超となったが,他方,貿易外収支は35億ドル弱の黒字(移転収支も含むと考えられる)となった。
外資利用は85年には使用実績で43億ドル,前年比59%増となった。
(h)85年の農民1人当たりの純収入は397元,前年比実質8.4%の伸びとなった。大都市住民1人当たりの収入は752元で実質10.6%の伸びとなった。また,全国勤労者の平均賃金は1,142元,実質4.7%の上昇となった。
(i)85年末の人口は10億4,639万人,自然増加率は11.23%となった。
(イ)全般
85年に入ってからも,日中間には,彭真全国人民代表大会常務委員長の訪日(4月),第4回日中閣僚会議の開催(7月,東京)安倍外務大臣の訪中による日中外相協議の開催(10月)等に見られるように,要人の活発な往来が行われた。このほか,日本側からは,木部建設大臣(7月),木村参議院議長(7月),山口労働大臣(8月),竹内科学技術庁長官(9月),山下運輸大臣(9月),金子経済企画庁長官(9月),村田通商産業大臣(9月),河本国土庁長官(9~10月)等が訪中し,中国側からも,銭正英水利電力部長(4月),何康農牧漁業部長(4月),宋平国家計画委員会主任(4月),宋健国家科技委員会主任(5月),呂東国家経済委員会主任(5月),方毅国務委員(5月)等の来日が実現するなど,両国閣僚の往来を始めとする,政財界要人の活発な交流が引き続き行われた。このように頻繁な人的往来は,日中関係が深さと広がりを増してきていることを具体的に物語るものである。
特に,7月末に東京で開催された第4回日中閣僚会議へは,中国側より,谷牧国務委員,呉学謙国務委員兼外交部長を始め6閣僚と2次官が参加,日本側からも6閣僚が出席し,両国間の経済交流等につき,活発な意見交換を行うとともに,原子力協定の署名を行った。
10月,北京における日中外相協議の開催は,このように良好な日中関係を背景として,両国の外交担当大臣同士が率直な意見交換を通じ,相互理解と相互信頼を一層増進させることを目的としたものであった。安倍外務大臣は,訪中期間中,呉学謙部長との協議を始めとして,トウ小平主任,趙紫陽総理,李鵬副総理,谷牧国務委員等と会見し,日中両国が今後とも日中共同声明,日中平和友好条約,「平和友好,平等互恵,相互信頼,長期安定」という日中関係四原則を踏まえ,友好協力関係を更に発展させていくことを確認した。
また,日中関係を21世紀へ向けて安定的に発展させていくための方途を探ることを目的として発足した日中友好21世紀委員会は,10月に北京及び大連において第2回会合を開催した。この会合後,日本側委員と会見した胡ヨウ邦中国共産党総書記は,「中日友好関係発展についての4つの意見」を表明,その後,中曽根内閣総理大臣も同意見を支持することを表明した。
このように,日中関係は85年に入ってからも安定的な発展の途をたどったが,他方,両国間の貿易インバランスが年間約60億ドルに達したほか,8月15日に中曽根内閣総理大臣を始めとする閣僚が靖国神社公式参拝を行ったことに対し,中国側から中国人民の感情を傷つけるものとの批判が寄せられるなどの問題も生じている。これらの問題については,外相協議等の場を通じ意見交換が行われており,特に靖国問題については,我が方より公式参拝の趣旨,目的等につき説明を行ってきている。
(ロ)日中経済関係
(a)85年の日中貿易は,往復約189億ドル(対前年比43.9%増)と過去最高を記録し,貿易収支は引き続き我が国の出超(約60億ドル)となった。これは我が国の対中輸出が電気・機械機器を中心に伸長したためである。
(b)政府ベースの資金協力としては,84年度からの新規円借款について,84年3月の中曽根内閣総理大臣訪中の際に,我が国から鉄道,港湾,通信,水力発電の7プロジェクトに対し,我が国の財政事情等を勘案の上できる限り協力する旨表明し,84年10月に84年度分として715億円,85年7月に85年度分として751億円を供与する内容の交換公文が締結された。
無償資金協力について,85年度の無償資金協力としては,「肢体障害者リハビリテーション研究センター整備計画」,「日中青年交流センター建設計画(詳細設計)」,食糧増産援助など中国の経済発展に寄与するプロジェクトに対し,合計約58億円を限度とする額の供与に関する交換公文が締結された。
(c)国際協力事業団(JICA)を実施機関とする政府ベースの技術協力としては,運輸交通,経営管理,農林業,保健医療を始めとする広範囲の分野で研修員の受入れ,専門家の派遣,機材供与などを実施したほか,「中日友好病院」や「企業管理研修センター」などを始めとして8件のプロジェクト方式技術協力を行った。また,青年海外協力隊を中国に派遣するための取極が,85年10月に署名された。そのほか,運輸交通,地域開発,エネルギー,鉱物資源,大気汚染や工場近代化など幅広い分野を対象とする各種の開発調査協力が行われている。
(d)日本輸出入銀行の石油・石炭開発金融(総計4,200億円)については,これまでに3,154億円の融資契約が調印されている。84年12月には新規融資として,石炭2プロジェクト,石油4プロジェクトに対し,5,800億円を限度として供与する内容の覚書が調印され,これまでに656億円の融資契約が調印されている。
(e)日中長期貿易取決め(民間)は,86年1月に86年から90年までの5年間の対日原油・石炭供給量を次のとおりとすることで合意した。
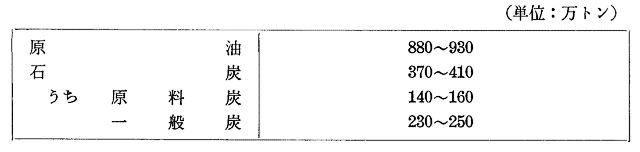
(ハ)人的往来と文化交流
日中間の人的往来は,72年(日中国交正常化当時)約9,000名であったが,85年には38万8,518名となった。この間両国閣僚レベルの往来も頻繁となり,85年度の要人の往来は下表のとおりである。
両国間の文化交流は,民間及び地方自治体ベースで盛んに行われているが,両国政府間でも79年12月に締結された文化交流協定等に基づき順調に発展している。具体的には,我が国政府は青少年交流,中国人留学生の受入れ,中国の日本語教育に対する援助及び文化無償資金供与(10件,累計4億7,050万円)等の分野で協力している。
(ニ)日中友好会館の建設
日中国交正常化10周年の記念事業として,我が国の政・財界及び関係団体を中心に,中国からの留学生・研修生等のための宿舎及び日中文化交流のための各種施設から成る「日中友好会館」を東京に建設する計画が策定された。この計画は,82年9月に政府首脳レベルで両国政府の建設支援が合意され,我が国政府は,既に83年度6,975万円,84年度6億9,750万円の建設関係費を補助済みで,85年度においても7億5,000万円の補助を行っている。現在既に会館のA棟(学生寮及び語学学校)が完成済み(85年3月)であり,残るB棟(各種文化交流施設ほか)については88年3月に完工予定である。
(ホ)中国残留日本人孤児問題
(a)83年1月に行われた孤児問題に関する日中間の協議の結論を確認する口上書が,84年3月17日,北京で交換された。これにより中国政府は,孤児の訪日親族捜し等に対し引き続き協力すること,日本政府は孤児の日本への永住により生ずる家庭問題を責任をもって適切に解決することなどが確認され,これに基づき,日本政府は85年度より身元未判明孤児の永住帰国受入れを開始した。
(b)85年9月,11月から12月の間並びに86年2月から3月の間の3回にわたり計400名の孤児が来日,肉親捜しが実施され,103名の身元が判明した。
<要人往来>
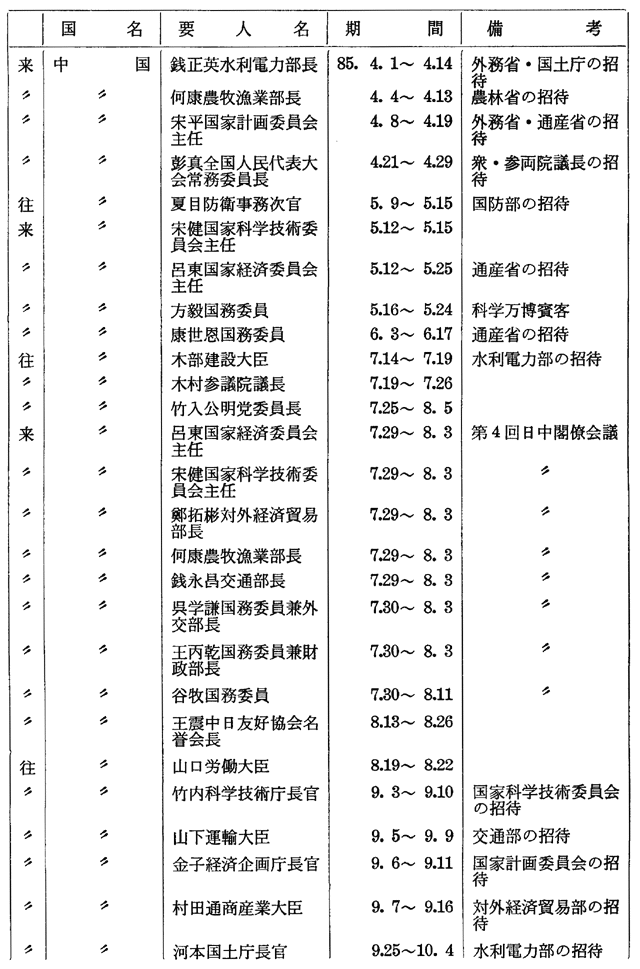
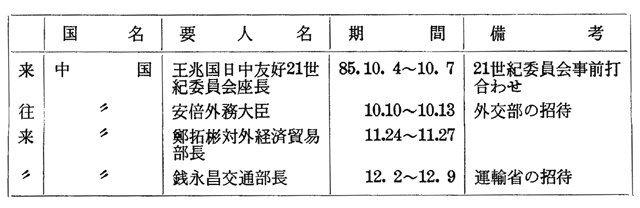
<貿易関係>
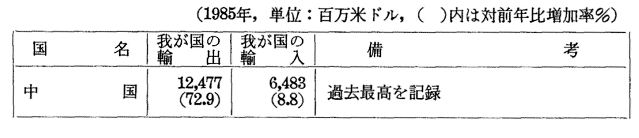
<民間投資>
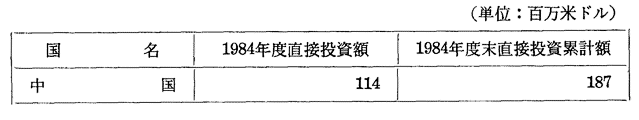
<経済協力(政府開発援助)>
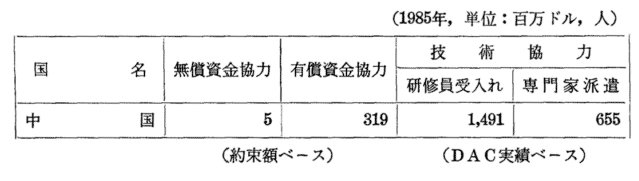
我が国と台湾との実務関係
(イ)来日台湾人数は年々増加の傾向をたどり,85年には84年より若干増加して約35万7,000人に達したが,同年の訪台日本人峯はやや減少して約61万6,000人となった。
(ロ)85年における日台間輸出入額は前年比85%減の84億1,100万ドルとなり,日本側の出超額は16億4,000万ドル(前年比41.1%減,日本側統計)と大幅に減少した。
<貿易関係>
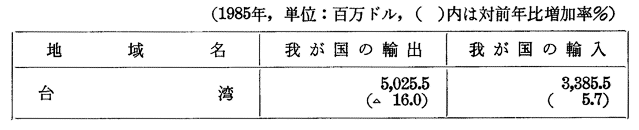
<民間投資>