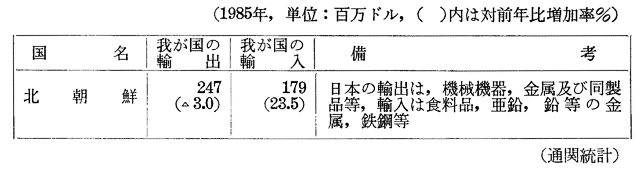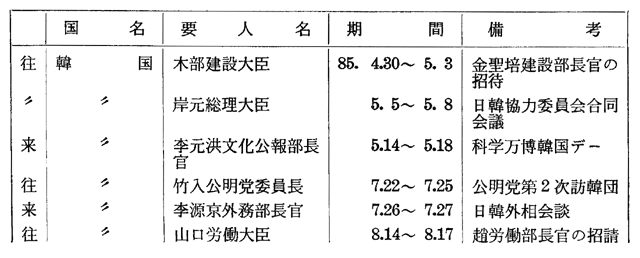
第1章 各国の情勢及び我が国とこれら諸国との関係
第1節 アジア地域
1.朝鮮半島
(1)朝鮮半島の情勢
(イ)韓国の政情
(a)内政
85年2月に実施された総選挙で,与党民正党は安定多数を確保したが,旧野党政治家が中心となって結成された新民党が第一野党に進出した。
新民党は88年の政権交替(全斗煥大統領の任期は88年2月まで)を控え,大統領直接選挙制への憲法改正を強く要求し,現行の大統領間接選挙制による平和的政権交替を目指す民正党と厳しく対立した。
また,現体制に不満を抱く一部学生の示威行為は85年中も断続的に繰り返され,学生による米文化院や政府・与党の建物占拠事件が発生した。
(i) 改憲問題
新民党は85年8月1日の臨時全党大会において李敏雨総裁を再選して党体制を固め,改憲を主張し,9月20日に開会された定期国会において,「改憲特別委員会」の設置を要求するなど,これを拒否する政府・与党との対決姿勢を強めた。さらに,86年に入り,2月同党は改憲に対する国民の真意を問うとして民主化推進協議会(金泳三,金大中両氏が共同議長)と協力して1千万人署名運動を開始した。
これに対し,政府当局は,改憲要求の署名運動は認めないとの方針に基づき,取締りに乗り出し,一時緊張した局面を迎えた。このような状況の中で2月24日,全大統領が与野党代表会談を開き,改憲案については89年に国民の意思を問うなどの考え方を示した。他方,新民党は3月7日,86年秋までに憲法を改正し,87年秋までに新憲法により大統領選挙を行うことを提案し,これが受入れられない限り署名運動は続けるとの立場を表明するなど与野党の対立の状況が続いた。
(ii) 学園問題
84年の韓国政府の「学園自律化」方針実施以来,各大学における学生の動きが活発化し,85年も春頃より各大学で学生デモが相次いだ。
5月に入り,光州事件5周年にちなんで大規模な反政府デモが展開され,5月末には在ソウル米文化院占拠事件が発生した。
7月下旬より政府内部で学園対策として,学生デモを厳しく規制するための「学園安定法」制定の動きが見られたが,野党及び反政府勢力の反対が激しく,与野党党首会談の結果,全大統領は8月17日,同法案の国会提出延期を発表した。
11月には学生による建物占拠事件が相次ぎ,在韓米商工会議所,セマウル運動中央本部,民正党中央政治研修院等が一時占拠された。
86年に入ってからも学生の校内デモは散発的に行われていたが,3月の新学期開始とともに学生の動きが活発化する兆しも見られる。
(b)外交
(i) 首脳外交等
85年には全斗煥大統領の2度目の訪米(4月)が行われ,世銀・IMFソウル総会(10月)を成功裡に終えた。
また,国連40周年記念総会に盧信永国務総理が出席し(10月),日米中ソ4大国による南北クロス承認及び南北の国連加盟を訴えた。
招待外交も活発に行われ,フランス,オランダ,パキスタン,コスタ・リカ,バングラデシュの首脳が訪韓した。
86年に入り,盧国務総理のインド,豪州,ニュー・ジーランド訪問(3月)が行われ,全大統領の英国,西独,フランス,ベルギー訪問(5月),サッチャー英国首相及びマルルーニー=カナダ首相の訪韓(いずれも5月)が行われた。
(ii) 対米関係
85年4月の全大統領訪米の際,米側より韓国防衛に関する確固たるコミットメントの再確認が行われたこともあり,基本的には順調に推移したが,85年後半より経済貿易問題がクローズアップされた。
(iii) 社会主義諸国との関係
中国との関係では,85年にも国際競技の枠内ではあるが,各種スポーツ競技への参加や韓国経済界幹部の訪中等が行われ,人事交流は若干の拡がりを見せた。
また,中国魚雷艇事件(3月),中国軍用機不時着事件(8月)が発生し,両国当局者の直接交渉により処理された。また,86年2月にも中国軍用機による亡命事件があった。
ソ連との関係では,国際スケート連盟主催のエキジビション(3月・ソウル,大邸),世界柔道選手権大会(9月,ソウル),第5回世界ジュニア・ハンドボール大会(10月,ソウル),第4回ワールドカップ・アマチュア・ボクシング大会(11月,ソウル)にソ連の選手団が参加した。
(c)韓国の経済
85年の韓国経済は,米国等先進国の景気停滞や保護主義の高まり,及び,軽工業部門におけるほかの開発途上国の追い上げなどの影響により,輸出が伸び悩み,また,国内的にも消費・投資が冷え込むなど景気が停滞し,経済成長率は5.1%にとどまった。
輸出は下半期に入り増加に転じたものの,前年比3.5%増の303億ドルにとどまった。他方,輸入は前年比1.6%増の311億ドルであったため,経常収支は前年より約5億ドル改善し,8億8,000万ドルの赤字となった。対外債務は,前年より36億ドル増加し467億ドルとなった。
物価は引き続き安定しているが,失業率は4.0%と増加し,雇用状況は悪化した。
(ロ)北朝鮮の情勢
(a)内政
金日成主席を中心とする指導体制が堅持される一方,子息金正日労働党政治局常務委員,秘書が金日成に次ぐ者として党・行政等の各分野での指導を拡大し,金正日後継体制造りが一層本格化したものと見られる。
85年は「祖国解放40周年と朝鮮労働党創立40周年を迎える意義深い年」とされ,主体思想を基本指針として社会主義制度の強化を図る三大革命(思想,技術,文化)路線が引き続き展開された。
権力構造には特別な動向は見られなかったが,経済部署の機構改編と人事異動が行われた。
(b)外交
北朝鮮は非同盟諸国外交及び対中・ソ外交に積極的である。
85年も朴成哲副主席,李鐘玉副主席,金永南副総理・外交部長ら政府・党の要人が非同盟諸国,東欧等を訪問したほか,特にアフリカ諸国からの要人招待を活発に展開した。
中国及びソ連との関係では,ソ連との関係強化の動向が見られたが,北朝鮮は基本的には中ソ両国との間でバランスを維持しつつ,両国との関係緊密化に努めた。ソ連とは85年4月に金永南外交部長の訪ソ,8月にアリエフ第1副首相の訪朝,12月に姜成山総理の訪ソ,86年1月にシェヴァルナッゼ外相の訪朝等各種レベルの人的往来が行われたほか,経済・技術協力協定等の各種取極が結ばれた。中国との間でも85年5月に胡ヨウ邦総書記が,10月に李鵬副総理が各々訪朝し,北朝鮮からも各種代表団が訪中した。
(c)経済情勢
86年の金日成主席の「新年の辞」では,85年同様,経済問題に関する言及が少なく,かつ,経済実績についての具体的数字は一切発表されなかった。第2次7か年計画は84年に終了したが,85年は87年から開始される第3次7か年計画に向けての「調整の年」として位置づけられ,科学技術の革新,企業の独立採算制への移行,人民生活の向上,「機械子生み運動」の展開等の施策のほか,経済部署の機構改編経済閣僚の刷新等の面で意欲的な取り組みが行われた。
(ハ)南北関係
(a)南北対話
チームスピリット期間中中断されていた南北間の対話は,85年5月再開された。経済会談は,5月,6月,9月,11月の4回板門店で行われ,経済協力共同委員会の設置につき原則的に合意されたが,その名称及び運用等を巡り双方の意見が対立した。
赤十字の分野では,第8回本会談が5月(ソウル),第9回が8月(平壌),第10回が12月(ソウル)開催され,9月には,分断後初めて離散家族及び芸術団の相互訪問が実現したが,本会談は離散家族探しの方法を巡り膠着の様相を示すようになった。北朝鮮側の提案で始まった国会会談予備接触(7月及び9月,板門店)では,本会談の議題を巡り双方の主張が対立している。
88年オリンピックの開催を巡るスポーツ会談もI0Cの仲介の下に10月及び86年1月にローザンヌで開催されたが,共同開催と統一チーム結成問題について双方の主張は対立した。なお,86年に入り各種分野における対話はチームスピリット86を理由とする北朝鮮側の中断通告により,1月末より一時中断の状況となった。
(b)軍事情勢
大規模な軍事力が対侍している朝鮮半島では引き続き緊張状態が継続しているが,85年は84年に比し,概して平穏であった。
この間,北朝鮮は,装備の近代化等により軍事力を強化するなどの動きを示し,特に,ソ連との軍事的接近の兆候が注目された。
これに対し,米韓両国は,韓国の第2次戦力増強5か年計画(82~86年)及び米国の対韓軍事援助の継続等により,韓国防衛のための全体的継戦能力を強化した。
一方,信頼醸成のため,米韓両国は,チームスピリット86に際し,例年と同様北朝鮮側に演習の事前通報及び参観招請を行った。また,板門店の軍事休戦委員会では,北朝鮮側が,非武装地帯の緊張緩和に関する初めての提案(7月)を行い,今後の双方の対応が注目されている。
(イ)概観
65年の国交正常化以来20年間日韓関係は着実な発展をみせ,ますます良好かつ密接なものとなっており,両国間で広範な分野にわたって交流と協力が行われている。
84年の全大統領の歴史的訪日の成果の延長上に,累次にわたる外相会談及び85年8月の閣僚会議が行われ,高いレベルでの間断なき対話が維持されたほか,各種の政府間実務者協議を通じて,在日韓国人待遇問題,貿易問題,漁業問題等両国間の諸問題につき突込んだ意見交換が行われた。
(ロ)日韓定期閣僚会議
第13回日韓定期閣僚会議が85年8月29~30日,2年振りにソウルで開催された。
この会議を通じ,日韓双方で二国間関係のみならず,新ラウンド等国際面での協力の推進につき意見が一致したほか,21世紀に向けた相互理解増進と信頼関係構築のため両国民間の幅広い交流拡大の必要性につき改めて認識の一致を見た。さらに,外相会談の定期化につき合意したことは,両国間の意思疎通を今後一層密にするという観点からも極めて重要な成果であった。
(ハ)在日韓国人の待遇問題
在日韓国人の待遇問題については,85年5月に東京において事務レベルの非公式意見交換が,8月にソウルにおいて「在日韓国人の待遇に関する実務者協議」が行われた。また,12月には東京において「在日韓国人子孫の日本での居住に関する日韓会議」が開催され,いわゆる三世以下の在日韓国人子孫の問題につき事務レベルでの意見交換が行われた。
(ニ)貿易
85年の日韓貿易は,日本の輸出が約71億ドル,輸入が約41億ドルで総額では前年に引き続き100億ドルを突破した。65年の日韓国交正常化以来,日韓貿易は急速に拡大してきているが,その間,一貫して日本側の出超となっているため,韓国側は対日貿易不均衡問題としてこれを重視している。我が国は,85年7月のアクション・プログラム策定に際し,韓国側の要望に十分な配慮を払ったほか,12月の第18回日韓貿易会議等の場において政府間協議を行っている。
(ホ)産業技術協力
日韓両国間では,民間企業間の技術提携・直接投資を通じ,技術移転が行われているが,政府レベルにおいても,我が国の経済協力の枠組の中で韓国に対する技術協力が推進されている。85年度の「韓国技術者研修計画」では,計116名の研修生を受け入れ,両国関係者の高い評価を得ている。また,直接投資が産業技術の移転に有効であるとの観点より,韓国の投資環境についても意見交換が行われている。
(ヘ)日韓科学技術協力協定
84年9月全斗煥大統領が我が国を訪問した際,中曽根内閣総理大臣との間で本協定の締結交渉の早期開始に合意したことを受け,両国政府間で交渉を行った結果,85年12月20日ソウルで署名,発効に至った。
(ト)日韓大陸棚共同開発
大陸棚共同開発区域では,物理探査の結果を踏まえ,これまで6か所で試掘が実施されたが,いずれも商業化可能量の石油・天然ガスを発見するに至っていない。
(チ)漁業問題
西日本及び山陰沖水域における韓国漁船の操業問題に関し,我が国は,機会あるごとに,韓国漁船による領海・漁業専管水域「侵犯操業」の根絶と日韓漁業協定合意議事録の尊重等を韓国側に対し強く働きかけてきている。韓国政府もほぼ常時問題水域に漁業指導船を派遣する等対策を講じているが,韓国漁船による違反操業の根絶には至っていない。86年2月には第20回日韓漁業共同委員会が開催され,これらの問題についても話合いが行われた。
北海道周辺水域の韓国漁船操業問題については,80年11月から83年10月までの自主規制措置に続き,83年11月から86年10月までの自主規制措置が実施されている。また,我が国は,韓国側の要請に応じ,韓国済州島沖南西水域での底引網漁業につき自主規制措置を同様の期間実施している。
(リ)竹島問題
我が国は,韓国による竹島の不法占拠に対し,従来から繰り返し抗議しており,85年10月の海上保安庁巡視船の調査結果に基づき抗議を行ったほか,各種会議の機会にも,この問題を積極的に韓国側に提起している。
<要人往来>
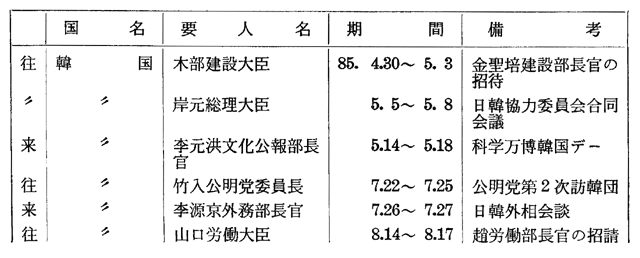
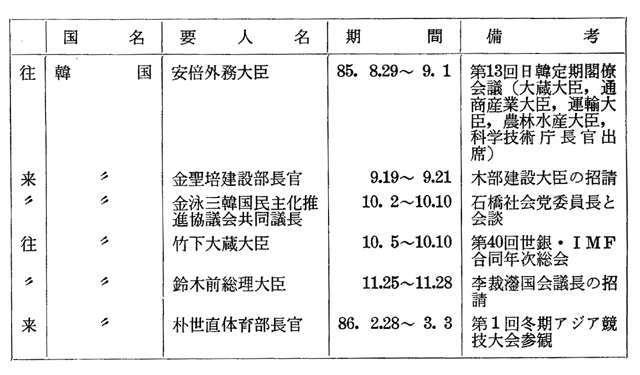
<貿易関係>
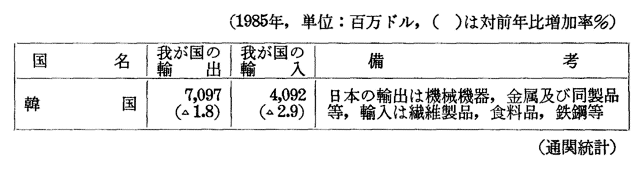
<民間投資>
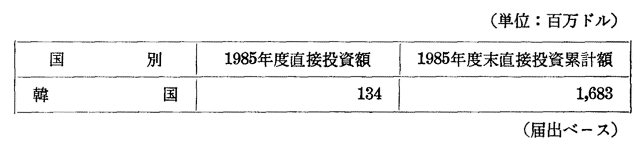
<経済協力(政府開発援助)>
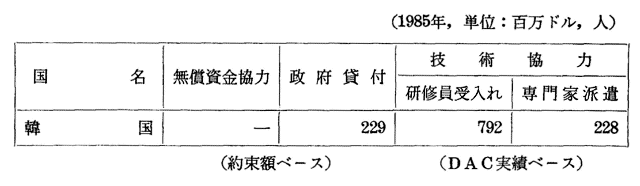
我が国と北朝鮮との間には外交関係はないが,貿易,経済,文化などの分野では民間交流が行われている。85年における主な動きは次のとおり。
(イ)漁業関係
北朝鮮周辺水域における我が国漁船の漁業活動については,日朝民間関係者間の民間漁業暫定合意が82年6月30日に失効して以来操業は中断されていたが,両国民間関係者の努力により,84年10月15日,86年12月31日までを有効期間とする従来とほぼ同様の合意が成立し,操業が再開されている。他方,85年10月に我が国漁船と北朝鮮艦艇が衝突し,我が国漁船が沈没する事件が発生したが,乗組員は全員無事救助され,その後帰日した。また,86年1月には我が国漁船計2隻が北朝鮮に拿捕され,うち1隻は釈放・送還された。
(ロ)人的交流
(a)85年中の邦人の北朝鮮への渡航者数は,1,291名である。渡航目的のうち最も多いのは商用であり,このほか親善交流等があった。
(b)一方,同期間中の北朝鮮からの入国者数は403名であり,入国目的はスポーツ,商用等であった。
(c)なお,同期間中の在日朝鮮人に対する北朝鮮向け再入国許可数は4,423件であり,親族訪問,学術・文化・スポーツ,商用等であった。
(ハ)貿易
85年の日朝貿易は,輸入が前年比23.5%の増加を示したのに対し,輸出が3.0%減少し,総額では,前年比6.6%増の4億2,600万ドルとなった。
<要人往来>
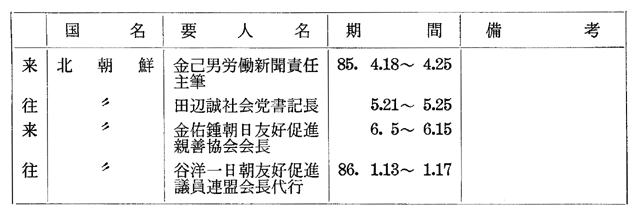
<貿易関係>