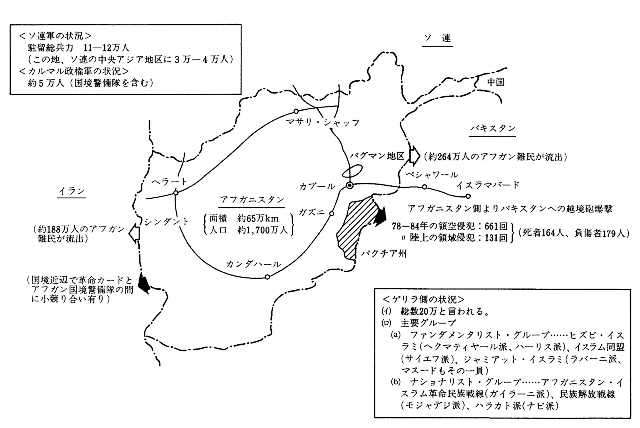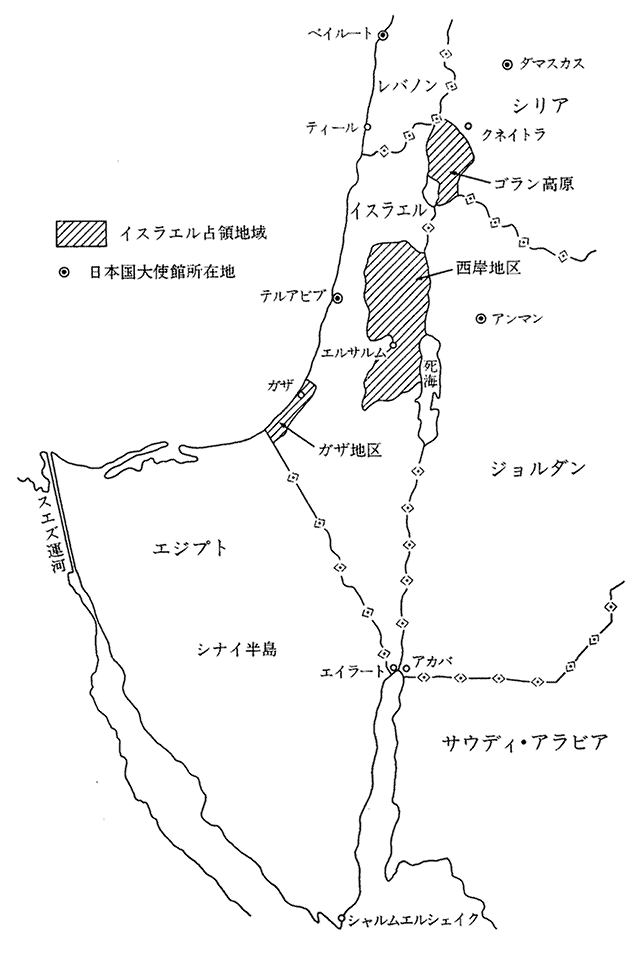
7.中近東地域
(1)中近東地域は,世界の主要な原油供給源として戦略的重要性を有している。特に我が国は,原油必要量の約7割を依存しているのみならず,貿易及び投資先としても中近東諸国と極めて密接なかかわりを持っている。しかし,この地域はイラン・イラク紛争,中東和平問題,レバノン紛争,各種テロ問題等の政治問題のほか,急激な経済発展により生じた経済・社会問題,最近の石油価格の低下に伴う財政収入の減少等種々の問題を抱えている。こうした諸問題が域内の不安定要因となり,ひいては,国際社会全体に大きな影響を及ぼす可能性もあるので,その動向には不断の注意を要する。
このような状況のなかで,我が国は,経済・技術協力を通じ中近東諸国の国造り,人造りに積極的に協力するとともに人的交流,文化交流の強化を通じ相互理解の増進にも努めている。
(2)我が国の国際的地位の高まりとともに,近年,中近東諸国から我が国に対し単に経済分野だけでなく政治面でも積極的な役割を果たすことを要望する声が強まっている。このような期待に応えるべく,我が国は,85年においても,中東和平問題及びイラン・イラク紛争の早期平和解決に向けての環境造りのため,当事者に対し働きかけを行うなど,機会あるごとに関係者との協議を重ねた。
(3)85年は,2月のフセイン・アラファト合意成立以来中東和平への動きが活発化し,ジョルダン・パレスチナ合同代表団と米国との話合いの実現が期待されたが,関係当事者間の意見の相違はまだ大きく,結局右話合いは実現されず,また,ジョルダンとアラファトPLO議長との話合いも決裂し,86年2月以降中東和平の動きは停滞を余儀なくされている。
またレバノン情勢も85年6月イスラエル軍がほぼ撤退を完了し,その後シリアを中心に国民和解への努力が行われたが実現するには至っていない。こうした状況下・我が国は7月の外務大臣による中近東諸国訪問や国連等の場を通じて関係当事者との政治対話を進め,各当事者が柔軟かつ現実的な対応を行うよう働きかけた。
(4)イラン・イラク紛争については,依然として解決の目途はたたず,85年3月,5月,6月の相互都市攻撃の激化,8月中旬より始まったイラクのカーグ島攻撃,86年2月初めよりのイラン軍の攻勢等の動きがあり,情勢は緊張含みで推移した。このような状況の中で,我が国は,ハイレベルでの両国との対話を継続しつつ引き続き同紛争の早期平和的解決のための環境造りの方途を探る努力をした。
85年3月末より4月初めにかけて,アジーズ=イラク外相の訪日を,また,7月初めには,イランよりラフサンジャニ・イスラム議会議長の訪日を実現し,それぞれ二国間関係,イ・イ紛争を含む国際情勢につき率直な対話を行ったほか,安倍外務大臣は国連総会等の機会をとらえてイラン,イラク両国の外相と会談した。また,安倍外務大臣は,9月の国連総会演説において,両当事国の安保理出席,あるいは国連事務総長を介しての当事者間の何らかの対話の実現への希望を表明するとともに,我が国としても志を同じくする国々と緊密に協議していく旨明らかにした。
(5)アフガニスタンについては,依然として11~12万のソ連軍が駐留し,ソ連・アフガン現政権と反政府ゲリラとの戦闘が各地で続いており,問題解決の目途はたっていない。
我が国は,国際場裡において,機会あるごとに累次の国連決議に言うソ連軍の全面撤退等の4条件を満たす解決の必要性を訴えてきている。
中東和平問題
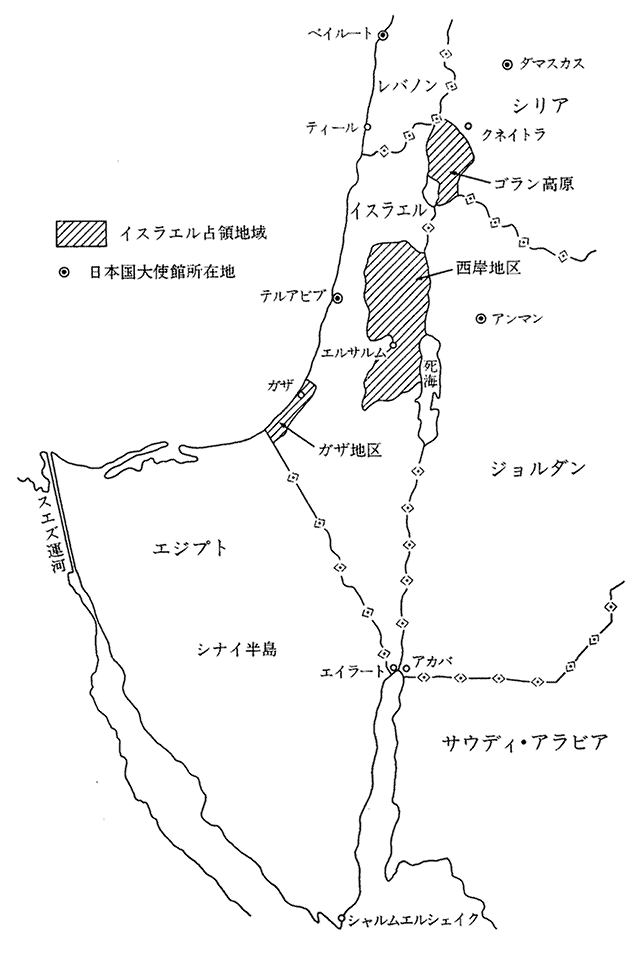
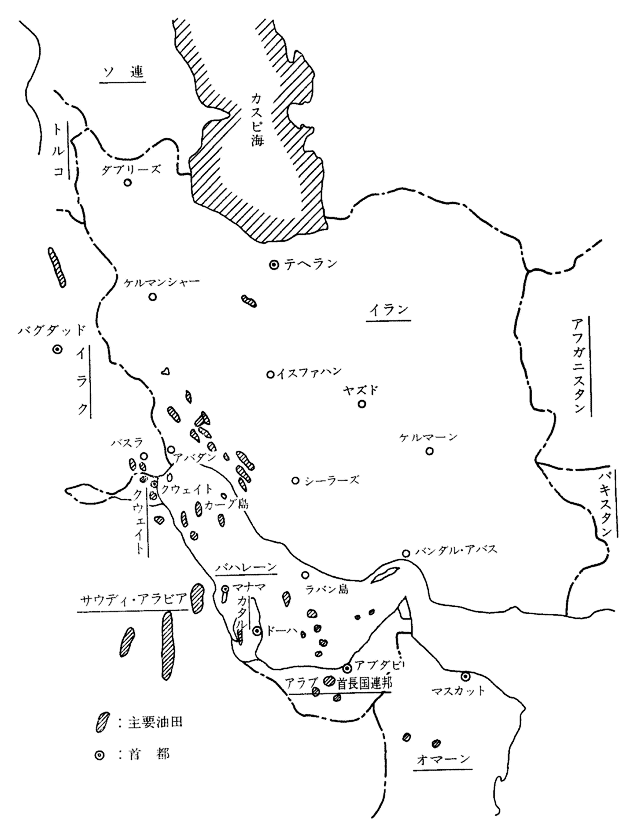
イラン・イラク紛争
イラン・イラク両国の主張・立場の相違
<紛争開始の経緯>に関するイランの主張
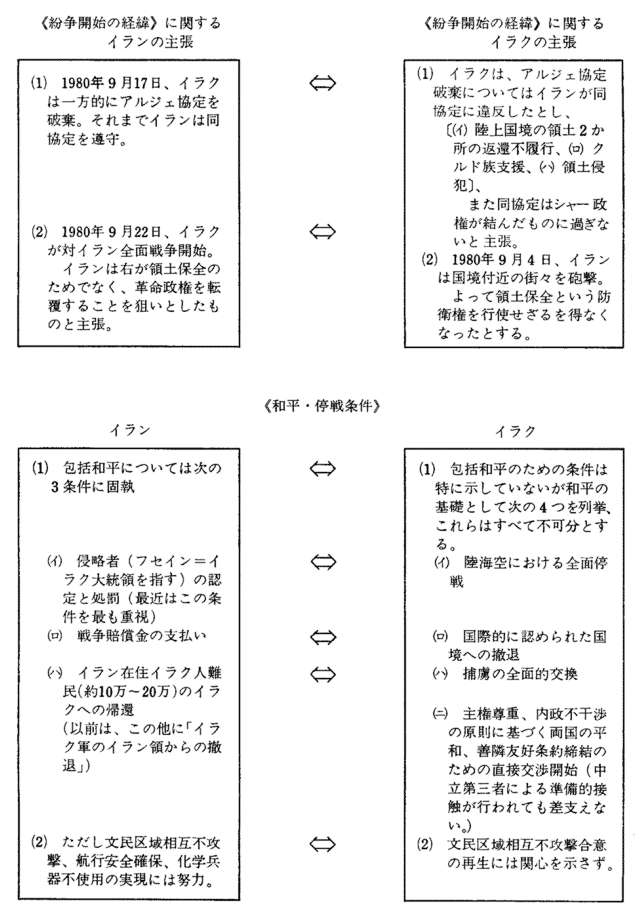
アフガニスタン情勢