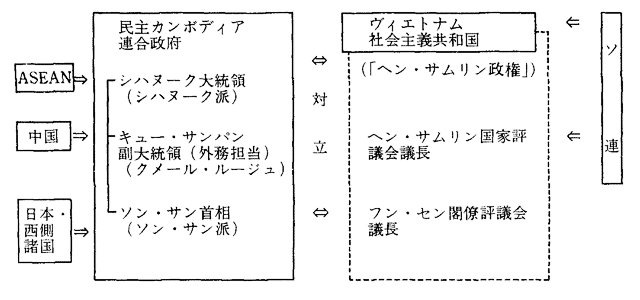
第3章 1985年の我が国の主要な外交活動
第1節 各国との関係の増進
1.アジア地域
(1)概要
(イ)多様な政治的,経済的,文化的背景を持つアジア地域の平和と安定の維持は,ひとえに我が国のみならず世界の平和と安定の維持に不可欠である。
85年のアジア地域では,カンボディアでのヴィエトナム軍による大規模な乾期攻勢,パキスタンヘのアフガン難民の流入継続等直接・間接にソ連の介入が深く関係する緊張状態が引き続き看取された。しかしその一方で朝鮮半島で南北間の対話の趨勢が維持されたほか,南アジア地域協力連合(SAARC)が結成され,域内協力拡大のための枠組が設けられるなど,域内緊張緩和への動きも見られた。また86年2月フィリピンでは広範な民衆の支持を受けた新政権が誕生し,新たな発展の契機となることが期待される。
経済面では,大半のアジア諸国は世界経済の低迷,一次産品の価格下落等により,経済成長率の下降傾向を余儀なくされた。貿易,投資,技術移転の促進と経済協力の拡充を求める声はアジアの多数の諸国が異口同音に要望するところとなっている。
(ロ)かかる状況下,我が国は,アジア諸国の一員として,アジア地域各国との友好関係の増進と,域内開発途上国の発展への協力という積極的なアジア外交を引き続き展開した。日中関係では日中外相協議の発足を始め政財界要人の積極的な交流等を通じ,良好かつ安定的な友好協力関係の一層の発展に努めた。日韓関係も,85年には国交正常化20周年を迎え,一層成熟した関係となっている。ASEAN諸国との関係において,我が国はカンボディア問題についてのASEANの立場を引き続き支持し,フィリピン新政権への支持の態度を示す積極的な取組みを行ったほか,第2回日本・ASEAN経済閣僚会議を開催(東京)し,今後の一層緊密な経済交流の樹立へ向けて忌憚ない意見交換を行った。他方,85年8月15日の靖国神社の公式参拝を巡りアジア諸国からは様々な反応が寄せられたが,我が国としては,公式参拝の目的が戦没者の追悼を行い,併せて我が国と世界の平和への決意を新たにすることにあること,また,我が国が過去においてアジアの国を中心とする多数の人々に多大の苦痛と損害を与えたことを深く自覚し,このようなことを2度と繰り返してはならないとの反省と決意の上に立ち,平和国家としての道を歩んできており,このような反省と決意にはいささかの変化もない点を説明し,内外の理解を得られるよう努めてきている。
(2)朝鮮半島
(イ)朝鮮半島の平和と安定は,我が国の安全と東アジアの安定にとって重要である。我が国としては,朝鮮半島の緊張緩和及び永続的平和の実現を強く希望しており,中国,米国,ソ連等朝鮮半島に大きな関心を有している諸国との意思疎通を深め,南北対話促進のための環境造りに貢献すべく努力した。
85年から86年初めにかけて行われた中曽根内閣総理大臣によるレーガン米国大統領,盧信永韓国国務総理,趙紫陽中国総理との会談,及び安倍外務大臣による米国,中国・韓国,ソ連との外相会談等においては朝鮮半島問題についても重要な議題の一つとして意見交換が行われた。
(ロ)南北対話については,経済,赤十字,国会会談予備接触,スポーツの各分野で対話が進展してきた。我が国は,朝鮮問題は第一義的には南北両当事者間の直接対話を通じて解決されるべきであるとの基本的立場から,従来より韓国の対話努力を支持しており,今後とも関係国と緊密に協力しつつ,対話促進のための環境造りの面を中心に出来ることがあれば貢献していく考えである。
(ハ)我が国は,韓国との友好協力関係を引き続き重視している。
両国首脳の相互訪問の実現によって日韓関係には新たな章が開かれたが,その後も累次の外相会談,閣僚会議,各種実務者協議を通じ,あらゆるレベルにおける両国間の間断なき対話を維持しつつ,その成果を更に発展させていくべく努めてきた。
今後とも,両国の各界各層の幅広い交流を一層促進し,個別の問題によって友好協力関係の基本が揺らぐことのない成熟したパートナーの関係に発展させていく考えである。
(ニ)北朝鮮との間には外交関係はないが,今後とも経済・文化等の分野における民間レベルの交流を積み重ねていく方針である。
(3)中国
隣国中国との間に良好で安定した関係を維持発展させることは,我が国外交の重要な柱の一つであり,日中両国の友好協力関係の発展は,両国にとって重要であるばかりでなく,アジアひいては世界の平和と安定にとっても大きな意味を有する。我が国はこのような観点から,85年も積極的な対中国外交を展開した。
具体的には,7月末第4回日中閣僚会議を成功裡に開催したほか,10月安倍外務大臣が訪中して行われた日中外相協議に見られるような両国間の対話の拡充,強化を図ったことである。特に,10月の日中外相協議では,今後とも日中関係を日中共同声明,日中平和友好条約,日中関係四原則を踏まえて発展させていくことを,中国側との間で改めて確認するなどの成果を収めた。
他方,8月には,靖国神社公式参拝を巡り問題が生じたが,我が国は外相協議等の場を通じて,公式参拝の趣旨,目的等を説明してきている。
(4)東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国及びビルマ
(イ)ASEAN諸国は,政治,経済,文化等の分野で共通の目標に向けて連携,結束を強化し,東南アジアにおける安定勢力としてこの地域の平和と発展に大きく貢献してきている。我が国は,歴史的,地理的にも密接な関係を有するASEAN諸国との友好協力関係の増進を最も重要な外交課題の一つとしてきており,これら諸国の経済・社会開発のための自主努力に対してもできる限り支援してきている。
(ロ)他方85年のASEAN諸国は,先進国経済の低迷,(軟調な一次産品市場,一次産品価格の低迷)輸出所得減少等を反映し,経済成長の低下,対外不均衡の拡大等の問題に直面しており,折りから米議会での繊維関連法案審議等に見られる保護主義的動きへの懸念の高まりと相まって先進諸国側の市場開放,対外(対開発途上地域)投資・技術移転促進等への要請を強めた。
かかる状況を踏まえ我が国としては自由貿易維持・強化との基本的立場に立ち,累次の対外経済対策に加えアクション・プログラム等の一層の市場アクセス改善措置を講じるところとなったが,右とあい前後してASEAN諸国等に各々経団連ミッション(1月21~31日,2月11~16日),藤尾ミッション(自由民主党政務調査会長)(5月4~14日,8月29日~9月4日)を派遣し,ASEAN諸国等と広く経済問題全般にわたり意見交換を行うとともに,我が国として可能なものに協力を約し,また市場アクセス改善に一層の努力を行う旨説明した。さらに,79年以来6年振りに日・ASEAN経済閣僚会議を開催(6月27~28日,東京)し,貿易・投資・技術移転等につき意見交換を行うとともに,6月25日に決定された関税に関するアクション・プログラムにつき我が国としてASEAN関心品目にも最大限の配慮を行ったなど詳細に説明し,続く7月にはASEAN拡大外相会議(7月11~13日,クアラ・ルンプール)に安倍外務大臣が出席し,政治問題を中心に討議が行われたが,我が国からはカンボディア問題に関する4原則,人造り協力プロジェクトヘの参加等を表明し,アジア,なかんずくASEANの平和と繁栄は世界の平和と繁栄にとり不可欠との認識の下に積極的姿勢を示した。
(ハ)フィリピン情勢は,85年も動揺を続けたが,86年2月の大統領選挙後の政変によりアキノ新政権が誕生した。我が国は,同国の安定化は,東南アジアを始めとするアジアの平和と繁栄に重要な意義を有することにも鑑み,同政権に対する確固たる支持の姿勢を示している。
(ニ)また,我が国は,東南アジアと南西アジアの境に位置し,独自の経済・外交政策を展開するビルマとの間でも友好協力関係の増進を図った。
(5)インドシナ地域
インドシナにおいては,依然,ヴィエトナムのカンボディアヘの武力介入が継続し,これに反対する民主カンボディア連合政府との間で戦闘状態が続いた。
我が国は,インドシナ,ひいては東南アジア全域の平和と安定のためには,カンボディア問題が1日も早く解決し,ASEAN諸国とインドシナ諸国との間に平和共存関係が樹立されることが望ましいとの基本的立場から,カンボディアからのすべての外国軍隊の撤退とカンボディア人の民族自決の実現を柱とする包括的政治解決を求める方針を堅持し,立場を同じくするASEAN諸国の外交努力を支援するとともに,ヴィエトナムとの対話も継続した。
我が国はかかる外交努力の一環として,7月のASEAN拡大外相会議に
図1
カンボディア問題
(1)全体の構図
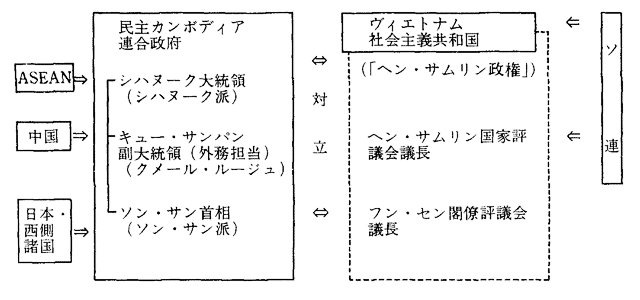
(2)主要な対立点
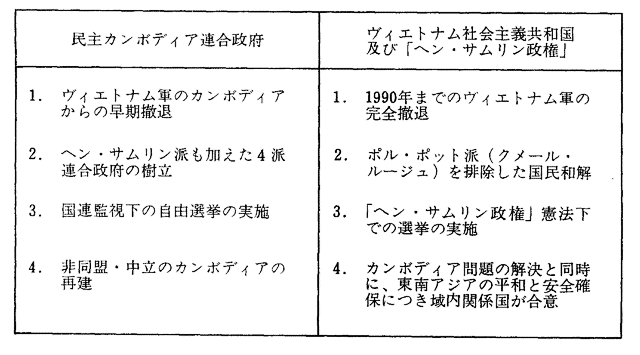
おいて,安倍外務大臣より今後の対応を考えるにあたり踏まえるべき4原則((あ)ヴィエトナム軍撤退及び民族自決,(い)対話の促進,(う)民主カンボディア支持,(え)カンボディア人の人造り)を示し,また,秋の国連総会においては,ASEAN諸国等とともに,包括的政治解決を求めるカンボディア情勢に関する決議案の共同提案国となり,同決議案は,84年を上回る圧倒的多数を得て採決された。
図2
(3)軍事情勢図
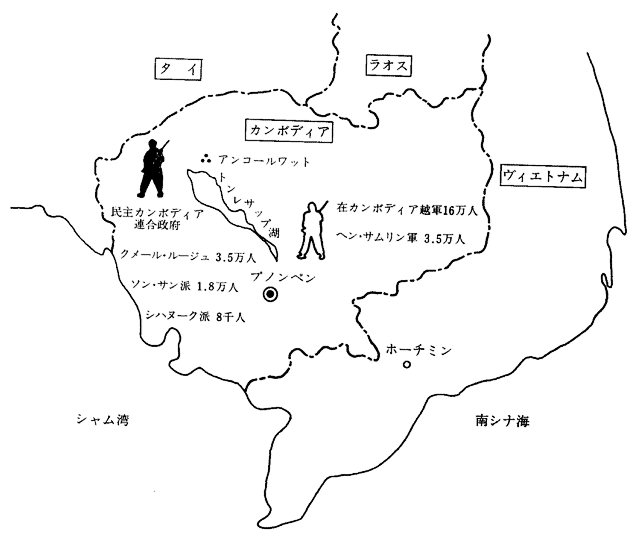
(4)主要事項年表
年月日
主要事項
1953年11月
1960年6月
1970年3月
5月
1975年4月
1976年1月
4月
1977年6月~12月
1978年12月
〃
1979年1月
〃
2月
10月
11月
1981年3月
7月
1982年8月
1983年9月
1984年7月
11月~1985年3月
1985年7月
〃
8月
1986年3月
カンボディア王国フランスからの完全独立達成
シハヌーク殿下国家元首に就任
クーデター発生,ロン・ノル政権成立
シハヌーク殿下北京において「カンボディア王国民族連合政府」(GRUNX)を樹立
プノンペン陥落,プノンペンにおいてカンボディア王国民族連合政府成立
民主カンボディア(DK)に国名変更
シハヌーク殿下国家元首辞任・クメール・ルージュを中心とする新体制発足
ヴィエトナム・カンボディア国境紛争激化
民主カンボディア,ヴィエトナムとの国交断絶
カンボディア救国民族統一戦線(「ヘン・サムリン政権」の母体)結成
ヴィエトナム軍のカンボディア侵攻
ヴィエトナム軍のプノンペン占領(「ヘン・サムリン政権」成立)民主カンボディア政権(DK)・タイ・カンボディア国境地域へ退避,抗ヴィエトナム(「抗越」と略す)ゲリラ戦を展開
中・越紛争発生(~3月)
ソン・サン元首相,クメール人民民族解放戦線(KPNLF)を結成,抗越ゲリラ戦を展開
第34回国連総会においてカンボディア情勢決議(在カンボディア外国軍隊の撤兵等を求めるもの)を採択(以下毎年同趣旨の決議採択)
シハヌーク殿下,独立・中立・平和・協調のためのカンボディア民族統一戦線(FUNCINPEC)を結成,抗越ゲリラ戦を展開
国連主催のカンボディア国際会議(ICK)開催,ICK宣言(紛争の包括的政治解決を求めるもの)を採択
抗越三派による民主カンボディア連合政府(CGDK)成立
ASEAN・カンボディア問題に関する共同アピール(ヴィェトナム軍の部分撤退と撤退地域における安全地域の設置等を求めるもの)を発表
安倍外相,ASEAN拡大外相会議においてカンボディア問題に関する「3項目提案」(上記共同アピール実現に必要な資金協力等を提案したもの)を発表
ヴィエトナム軍,大規模攻勢により抗越三派の主要拠点を制圧,抗越三派はゲリラ戦を継続
ASEAN,民主カンボディア連合政府とヴィエトナムとの「間接対話」を提案
安倍外相,ASEAN拡大外相会議においてカンボディア問題に関する「4原則」を発表
ヴィエトナム,在カンボディア・ヴィエトナム軍の1990年までの完全撤退を発表
民主カンボディア連合政府,カンボディア問題に関する「8項目提案」を発表
(6)南西アジア
南西アジア地域は,9億にも及ぶ人口を擁し,中束と東アジアを結び,インド洋を抱える極めて重要な地域である。
我が国は,この地域の動向がアジア全域ひいては世界の平和と安定に結び付いているとの見地から,同地域諸国に対し,積極的に経済・技術協力を行い,友好協力関係の増進に努め,同地域の安定強化に寄与してきた。とりわけ,ソ連のアフガニスタン軍事介入以降,南西アジア諸国との政治対話の活性化に努めてきたが,85年6月には,バングラデシュのエルシャド大統領が国賓として,また同年11月から12月にかけてインドのガンジー首相が公賓として,それぞれ我が国を公式訪問した。さらに,プレマダーサ=スリ・ランカ首相(4月)及びビレンドラ=ネパール国王(9月)が,ともに科学万博賓客として訪日した。
また,86年3月には,ツェリン=ブータン外相が同国の外相として初めて我が国を公式訪問し,その際,我が国とブータンとの外交関係が設定された。
これらの首脳レベルでの対話を通じて,南西アジア諸国との友好協力関係を更に深め,我が国がアジアの平和と繁栄に貢献していく基盤が強化された。