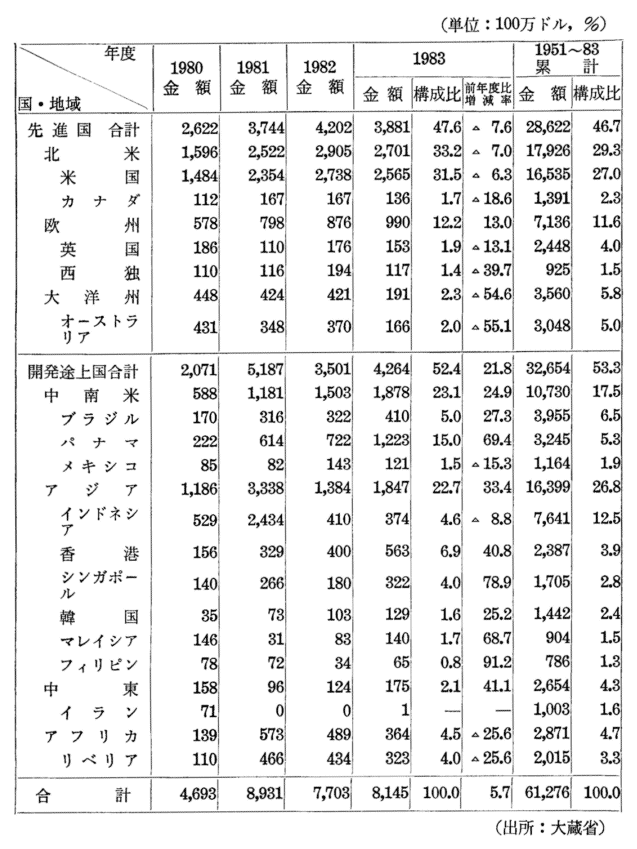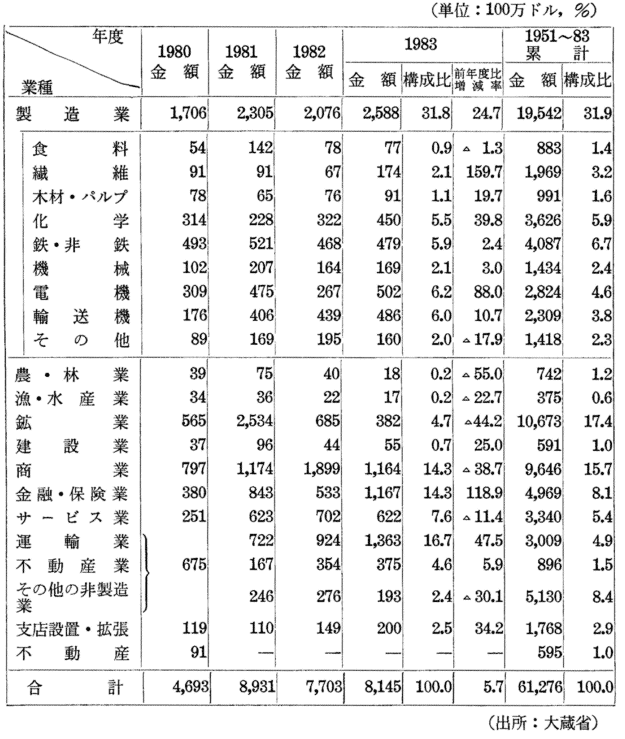第3節 国際投資問題
1.我が国の投資概要
83年度の我が国の対外直接投資(届出ベース)は,81億4,500万ドルと前
年度(77億300万ドル)比5.7%の増加となった。
(1) まず,地域別にみると(表1),先進国向投資は前年度比7.6%減の38億8,100万ドルと落ち込んだものの,構成比は47.6%と引き続き高水準を維持している。他方,途上国向投資は同21・8%増の42億6,400万ドルと堅調な推移を示した。最大の構成比を占める北米向投資は前年度比7.0%減の27億100万ドルとなったが,欧州向は同13.0%増の9億9,000万ドルと活発な投資が続いている。また,アジア向は同33.4%増の18億4,700万ドル,中南米向は同24.9%増の18億7,800万ドルとなった。
(2) 次に業種別にみると(表2),製造業(特に繊維及び電機),金融・保険業,運輸業,建設業等において前年度比増加がみられた。
(3) この結果,83年度末現在の対外直接投資(届出累計額)は612億7,600万ドルとなった。地域別及び業種別の各々の累計額は,表1,表2のとおりであり,我が国の主要投資先国を累計額でみると,米国,インドネシア,ブラジルの順に多く,この3か国で全体の46.0%を占めている。
(4) 最近の我が国の対外直接投資の特徴をみると,米国・欧州等の先進国向 投資が増加傾向にあり,その構成比は70年代が約4割であったのに対し 80年代は5割前後の水準を占めている。また,これまでの先進国向投資は商業・サービス業・金融業が中心であったのに対し,最近では製造業への投資が目立っている。これは欧米諸国との貿易摩擦が深刻化し,輸出に代わって海外で生産する気運が高まっているためと考えられる。
他方,アジア,中南米向投資も総じて引き続き堅調である。しかし,最近は製造業への投資のウェイトが低下したのに対し,商業・サービス業等への投資が急増している。
このように,我が国の対外直接投資は従来の低賃金追求型中心の投資から貿易摩擦回避型の投資に変わりつつあるといえよう。また,対外直接投資は海外での生産を通じて輸出を抑え,その結果,貿易収支の黒字幅を縮小させる方向に働くとともに,途上国に対しては産業協力として役立つものと考えられ,直接投資は,我が国がより充実した資本輸出国になるための主要な要素になると思われる。
表1我が国の主要国・地域別海外直接投資<届出ベース>
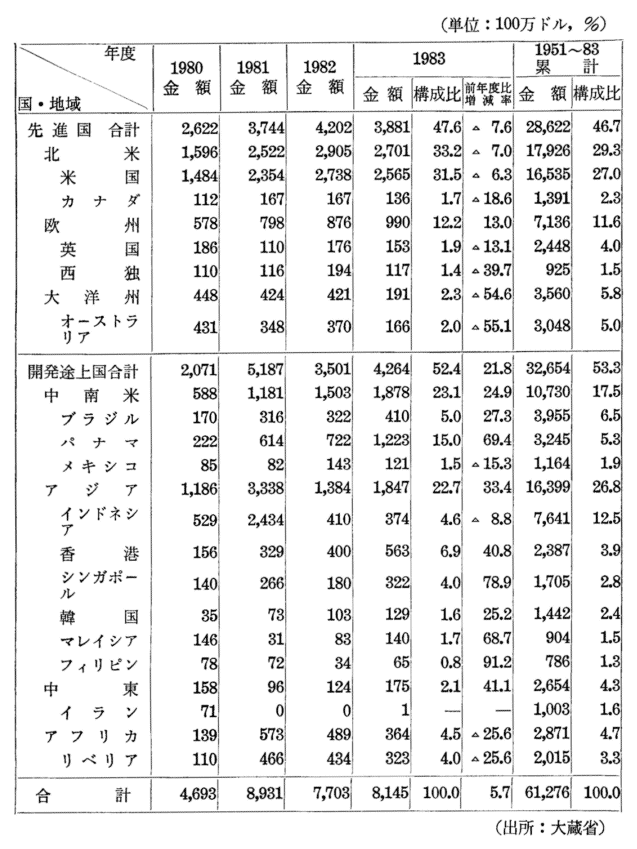
表2我が国の業種別海外直接投資<届出ベース>
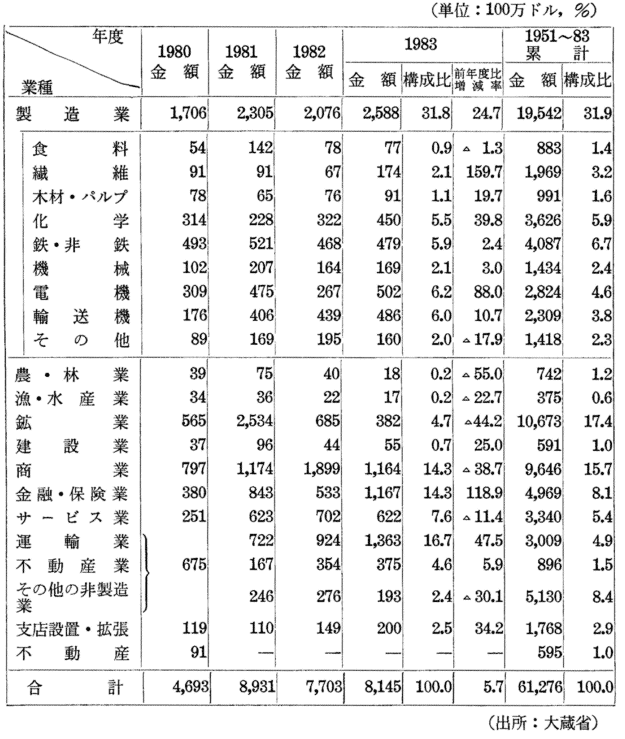
2.投資保護協定の締結の促進
(1)我が国の対外直接投資は,今後とも一層活発に行われることが予想される。こうした背景もあって,近時いわゆるカントリー・リスク問題についての認識が深まっている。
海外投資は,投資母国の経済に貢献するのみならず,資本・技術経営手法の移転,雇用創出効果等により投資受入国の経済発展にも資するものであり,また,経済的・人的交流を通じて両国関係を緊密化する。こうした効果を有する海外投資を今後とも更に促進していくことが望ましいが,海外投資に関しては,投資家にとって予見可能性及び法的安定性が限られる可能性があり,この意味で投資環境は国内投資の場合と異なると言えよう。
(2)こうした投資環境への対応は,一義的には海外投資を行う民間の責任と判断に委ねられているものであるが,投資母国及び投資受入国の役割は,この投資環境をできる限り良好なものに整備することであろう。
投資保護協定は,投資保険,税制等の施策と並んで,こうした投資環境の整備のための諸施策の一環として重要である。我が国は,かつては海外投資が必ずしも活発でなかったこともあり,海外投資については通商航海条約中の投資関連規定で対応するとの考え方をとっていたが,海外投資が近年急増している状況の中で,投資のみを対象として実体的及び手続的規定を共に詳細に定める投資保護協定の必要性が認識されるに至っている。
(3)我が国は,すでにエジプト及びスリ・ランカとの間に投資保護協定を有しているが,上述の認識の下に,80年12月の日中閣僚会議及び81年1月の鈴木総理大臣のASEAN諸国訪問の際,中国及びASEAN諸国とも,それぞれ投資保護協定の締結交渉に入ることにつき合意に達し,現在,鋭意交渉を行っているところである。
目次へ