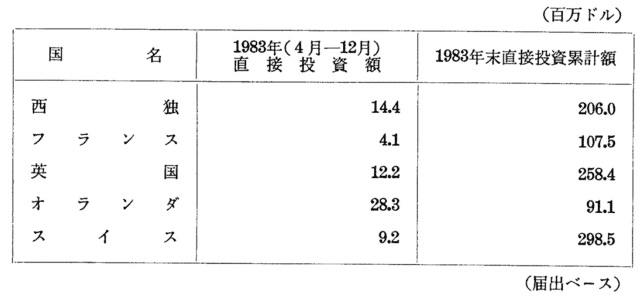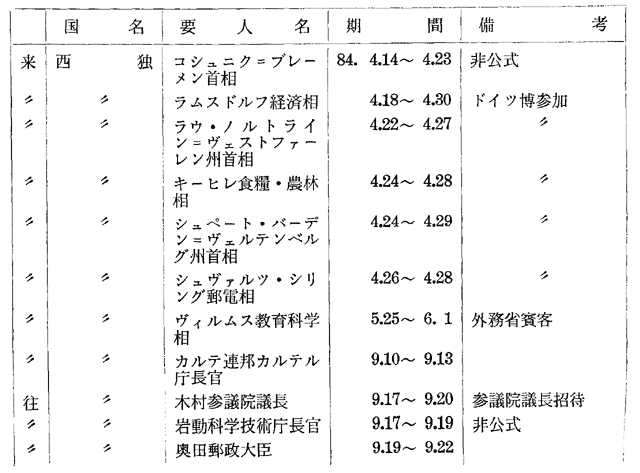
2.我が国と西欧諸国との関係
(1)日・西欧関係全般
我が国と西欧諸国は,文化的,歴史的に密接な関係にあり,また,自由と民主主義及び市場経済といった共通の基本的価値観によって固く結ばれている。現在の厳しい国際情勢の下,我が国が世界の平和と繁栄の維持・発展のため,国際社会において果たすべき役割に対する西欧諸国の期待は高まっており,このような背景の下,日欧間の協力関係は政治,経済のみならず,文化,科学技術等幅広い分野において著しく緊密化している。
83年に西欧諸国要人の訪日が相次いだのに続いて,84年においても,マルテンス=ベルギー首相,トルソEC委委員長,ソアレス=ポルトガル首相の訪日が実現し,また,ロンドン・サミットに出席した機会に中曽根総理大臣が訪英する等首脳レベルにおける日欧間の対話は更に活発化した。
また,首脳レベルの交流に加え,外務大臣をはじめとした閣僚レベルの協議も活発であり,9月の第4回目・EC議長団協議の際に安倍外務大臣によって提唱された日・EC政務局長会議の第1回会合が85年3月に開催されるに至ったことに見られるごとく,高級事務レベルにおいても緊密な協議が行われた。
(2)日・西欧経済関係
(イ)84年に入り日欧経済関係を取り巻く雰囲気は改善した。82年,83年はフランスのVTRの通関をポワチエに限る措置やECの対日ガット23条協議の提起に見られるように,両者の関係は緊迫化したが,西欧諸国における景気回復や我が国が講じた種々の市場開放措置や輸出自粛の実施に対する西欧側の評価を反映し,西欧諸国の対日姿勢は若干好転した。なかんずく,84年5月のトルソEC委委員長(公賓)の訪日,日・EC委閣僚会議の開催により,日・ECの双方において,対話と協力の必要性が確認された。
また,日欧貿易インバランスの改善のためには,西欧諸国の側においても対日輸出努力が必要であることについて,我が国は機会あるごとに西欧側に指摘してきたところであるが,84年4月のドイツ博,10月のフランス物産展等に見られるように,西欧側の対日輸出努力の強化が注目された。
さらに,84年秋には,西欧諸国のいくつかの国(イタリア,ベネルクス諸国,アイルランド,ノールウエー)はこれまで有していた対日差別的数量制限を部分的にせよ撤廃または緩和することを表明した。
12月には,85年についての日・EC間の輸出自粛に関する協議の結果,自粛の対象品目を過去2年の10品目(注)から8品目にすることが合意された。
産業協力分野においても,西欧側の日本企業誘致は積極化した。なかんずく,フランスの対日姿勢の変化は著しく,外務省賓客として訪日したファビウス工業研究大臣(現首相),クレッソン産業再編・貿易大臣のいずれも,日本の対仏産業協力案件が増加したことを強調し,今後も協力を強化していきたいとの意向を表明した。
(注)VTR,カラーTVブラウン管,カラーTVセット,NC旋盤・マシニングセンター,乗用車,軽商業車,クォーツ時計,フォークリフト・トラック,自動二輪車*,ハイファイ機器*
*85年には対象品目から除外
(ロ)しかしながら,日欧間には基本的に大きな貿易インバランスが解消されておらず,西欧諸国はこれに対し根強い不満を有していることから,日欧間は,雰囲気の改善にかかわらず依然として困難な問題を抱えている。すなわち,84年の日・EC間のインバランスは101億ドルと,過去最高を記録した前年(104億ドル)に比し,わずかながら減少したとはいえ,依然として構造的なEC側の赤字であり,EFTA諸国ほかを含めた日欧間のインバランスの幅は106億ドルとなっている。また,西欧諸国は我が国の種々の対外経済対策は対米偏重であるとの不満も有している。
こうした中で,ECは84年4月,製品輸入比率の引き上げを政策目標として採用すること,関税・内国税の引き下げ,数量枠の軽減ないし廃止,基準・認可手続等の改善,金融資本市場の一層の自由化,輸出自粛要請等を内容とする新たな対日要求リストを提出した。
我が国は,84年5月の日・EC委閣僚会議の際,日・EC貿易関係をより幅広く均衡のとれた基盤の上に構築するために,問題を個別,具体的に検討する場として,日・EC貿易拡大委員会を設置することにつきEC側と合意した。85年2月末から3月初めにかけて開催された第1回会合において,上記のEC側の対日要求事項のうち,大学病院等の政府調達,医薬品等の基準・認証制度を含むいくつかについて具体的に掘り下げた検討が行われた。
<要人往来>
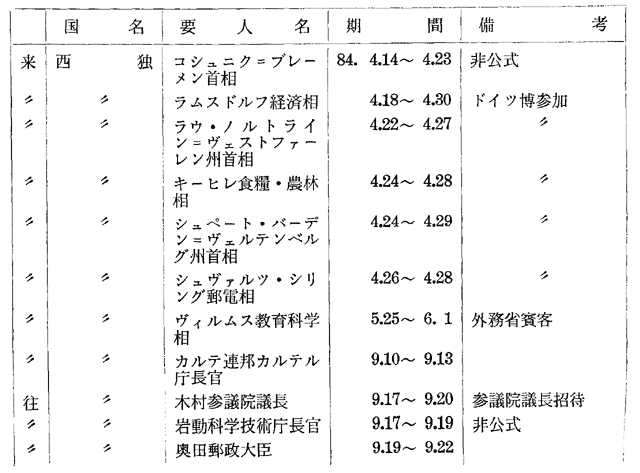
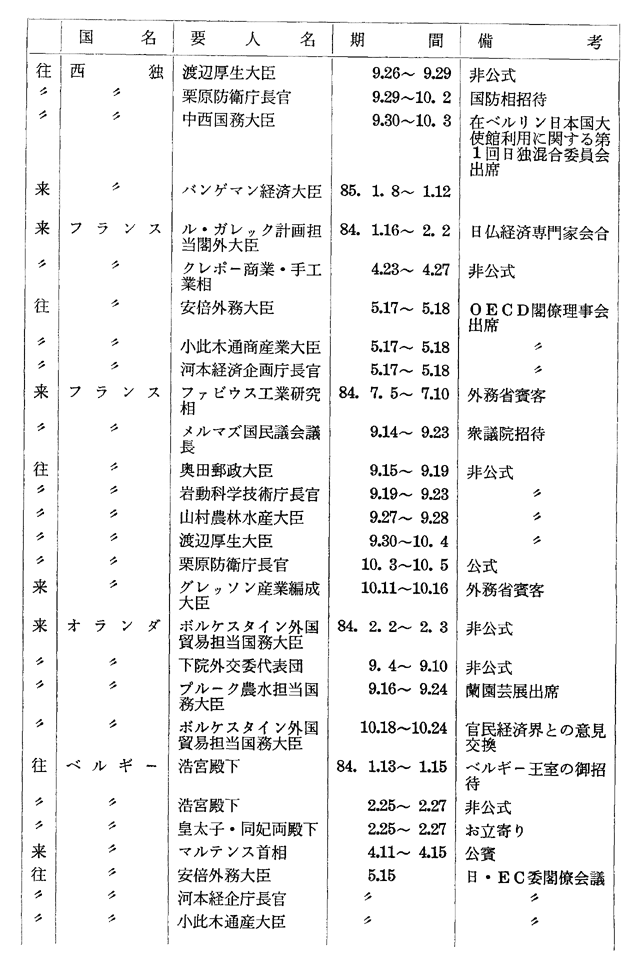
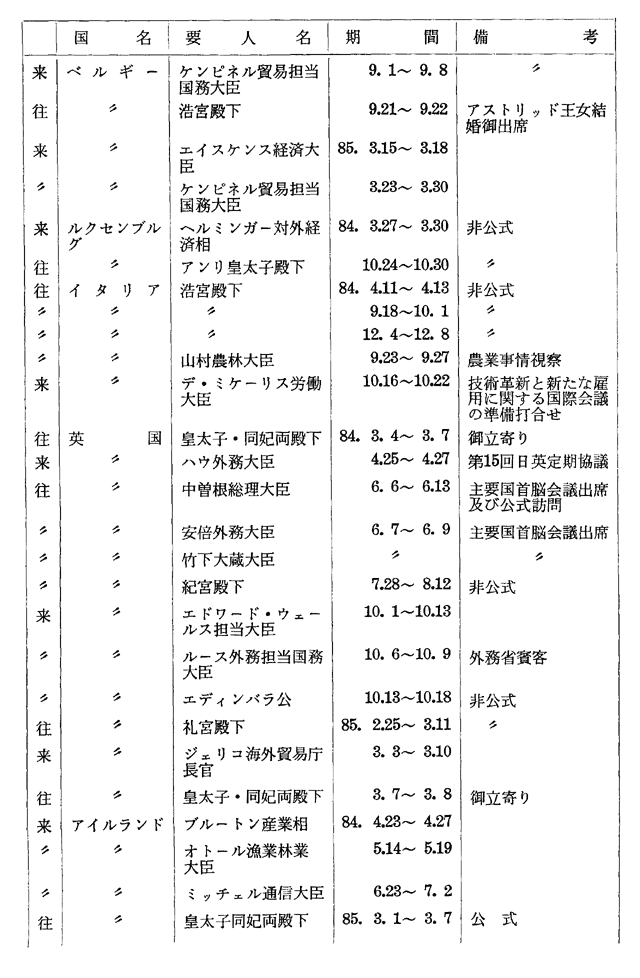
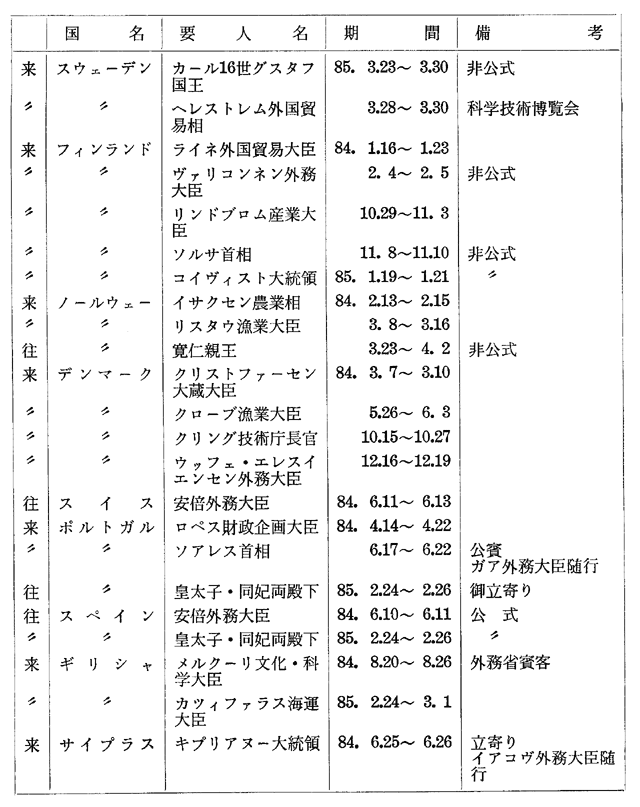
<貿易関係>
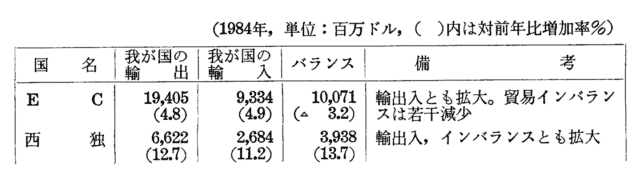
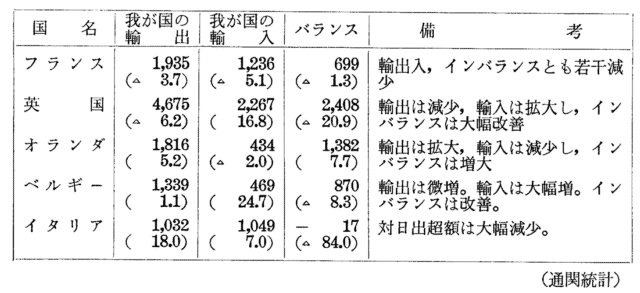
<民間投資>
(あ)我が国の対西欧直接投資
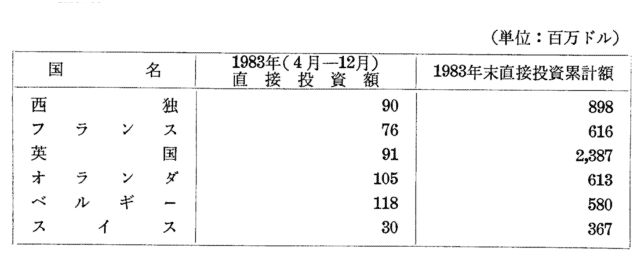
(い)西欧諸国の我が国に対する直接投資