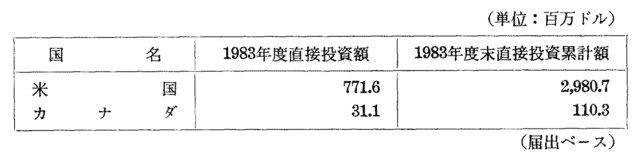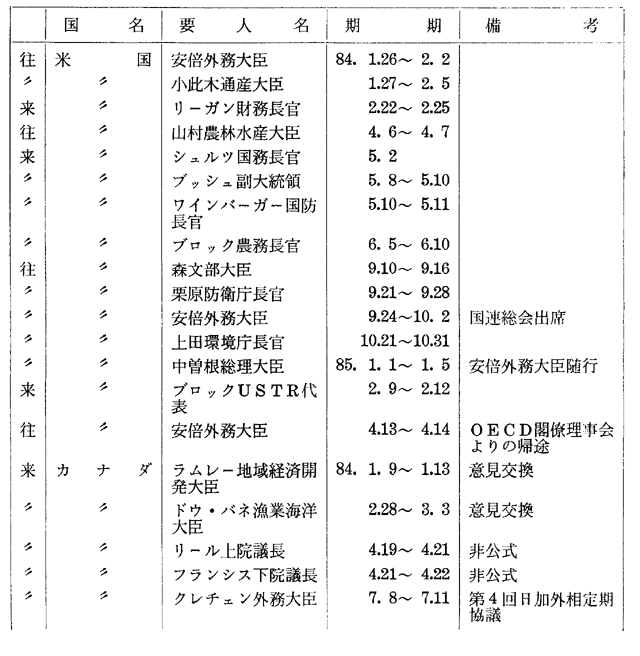
2.我が国と北米地域との関係
(1)米国
(イ)日米関係全般
(a)日米両国は,自由と民主主義という政治・経済上の価値観を共有し,日米安全保障条約に基づく安全保障面での協力関係,往復で800億ドルを超える貿易量に象徴される緊密な経済関係,さらには科学技術面での共同研究,文化交流等といった広範な分野にわたり,友好的な協力関係を築き上げてきた。
我が国は,このような米国との安定した友好協力関係を強化,発展させることが,日米両国民に多大の利益をもたらすとともに,世界の平和と繁栄にとっても肝要であるとの認識の下に,日米関係の強化,発展を我が国外交の基軸としてきている。
(b)82年末に底をついた米国経済は,83年から84年にかけて上向きに推移し,失業率の低下,物価の安定と言った明るい材料に支えられ,また,我が国の市場開放の努力もあり,米国議会を中心に大きな高まりを見せていた市場開放の対日要求も,一時沈静化に向かった。しかし,増加を続ける米国の対日貿易赤字額は,84年には300億ドルを超え,大統領選挙終了を契機に,再び議会や労働組合の中で対日要求が強まり始めている。
防衛の分野では日米間の協力関係は良好に維持されてきている。
(c)日米両国間に横たわる幾多の問題はあるものの,日米関係の固い絆は近年さらに強くなりつつある。
83年の日米両国首脳の相互訪問(1月の中曽根総理大臣,11月のレーガン大統領)により築かれた個人的信頼関係は,85年1月の総理訪米によりさらに確固たるものとなった。
日米両国で世界のGNP全体の30%以上を占め,世界の貿易量の20%以上を占める両国の動向は,アジア・太平洋地域,ひいては世界に対し多大の影響を与えるものであり,今やグローバルな意義をさらに強めていくものと思われる。
(ロ)日米経済関係
(a)84年前半の日米経済関係は,83年11月のレーガン大統領訪日のフォローアップを中心に種々の動きがあった。まず1月に電々調達取極の3年延長が合意され,4月には,VAN問題に関して,特別第二種電気通信事業の完全内外無差別の競争原理の導入を可能とする電気通信事業法案,外国製タバコについては,専売公社改革の一環として輸入自由化,流通改善を実現させる関連法案の国会提出が行われた。
さらに4月には長年の懸案だった牛肉,かんきつ問題が決着し,オレンジ,オレンジジュースの輸入割当の増加,高級牛肉の輸入拡大等の措置等がとられることとなった。
(b)以上のような進展をも受け,政府は4月27日,関税引下げ,衛星に関する政策声明,投資促進等米国の関心事項を含む対外経済対策を発表した。これらの措置は5月のブッシュ副大統領訪日の際米側より高く評価され,レーガン大統領訪日のフォローアップに一区切りがっくこととなった。これに加え5月下旬には日米円ドル委員会の報告書が出され,円の国際化・金融の自由化に向けて,具体的なスケジュールが示されるに至った。
(c)84年後半は,11月に大統領選挙が行われたこともあり米国において日米経済関係が大きくクローズアップされることはなかったが,9月にレーガン大統領が鉄鋼救済措置を公表し,我が国もこの措置に基づき10月より米側との交渉を開始した。また10月下旬には,運用いかんによっては保護主義的色彩を持ち得ることが懸念された84年米国貿易関税法が成立した。
(d)84年の末に至り,記録的な対日貿易赤字(米側統計で84年は368億ドル)を背景としつつ,我が国に対する批判は高まった。
(e)85年1月の総理訪米時には,今後の日米経済関係に関する協力過程を安倍外務大臣とシュルツ国務長官が総攬することとなり,1月下旬には,この首脳会談に基づき次官レベルでの協議が行われ,電気通信,エレクトロニクス,林産物,医薬品・医療機器の4分野で日本市場の開放につき話合いを行うこととなった。
(f)この間米議会では,ダンフォース上院議員の対日決議案が3月28日92対0で上院本会議を通過するなど日本に対する批判が一時急速に高まったが,4月9日の対外経済対策の発表やその後の四分野協議の進捗振りは,5月のボンサミットの際の日米外相会談,日米首脳会談で米側より評価されるに至った。
(g)なお,81年4月から4年間にわたって行われた対米乗用車輸出については,85年の1年間我が国独自の判断に基づき対米乗用車輸出を自主規制することを決定した。
(ハ)日米安全保障条約
(a)緊密な協議・協力
日米安全保障条約は,我が国のみならず,極東の平和と安全の維持に大きく寄与してきている。84年も,同条約の円滑かつ効果的な運用を期するため,日米両国間で緊密な協議及び協力が行われた。
(i) 84年5月8日から同11日にかけて,ブッシュ副大統領,シュルツ国務長官及びワインバーガー国防長官が相次いで来日し,中曽根総理大臣,安倍外務大臣,栗原防衛庁長官等と会談し,日米安保体制の維持・強化の重要性を再確認した。ワインバーガー国防長官は,第6回米韓安保協議の帰途来日したものであり,総理大臣,外務大臣及び防衛庁長官との会談で,日本の防衛努力,シーレーン防衛,艦載機夜間着艦訓練問題等について話し合うとともに,日米両国間の相互理解・協力関係の確認と,その強化に対する期待を表明した。
(ii) 84年6月下旬には,ハワイで第15回日米安保事務レベル協議が開かれ,我が国の防衛政策,59中業を含む防衛努力,シーレーン防衛共同研究,共同訓練,装備技術協力,駐留支援その他日米間の適切な役割分担,継戦能力,インターオペラビリティ(相互運用性)等の問題について意見交換が行われた。
(iii) 84年9月には,ワインバーガー国防長官の招待に応じて栗原防衛庁長官が訪米し,前記の諸問題等について話合いを行った。日本側より,レーガン大統領の対ソ対話の呼び掛けを評価するとともに,平和と軍縮への期待が表明されたほか,59中業の長官指示を含む我が国の防衛努力,継戦能力,インターオペラビリティ,艦載機夜間着艦訓練問題等が話題となった。
(iv) 85年1月には,中曽根総理大臣が訪米し,ロスアンジェルス郊外においてレーガン大統領と,総理就任来5度目の会談を行った。同首脳会談で,中曽根総理大臣は,ジュネーヴにおける軍縮交渉を中心とするソ連との間の交渉再開に向けてのレーガン政権の努力を評価するとともに,我が国の防衛努力について説明した。また,艦載機夜間着艦訓練問題もとりあげられた。更に,戦略防衛構想(SDI),東西関係のほか,朝鮮半島情勢等についても意見交換が行われた。中曽根総理大臣及び首脳会談に出席した安倍外務大臣は,帰途ハワイに立寄り,クラウ米太平洋軍総司令官と懇談した。
(b)日米安保体制の円滑な運用
(i) 政府は,日米安保条約の目的達成のため米軍の我が国駐留を認めており,その駐留を円滑かつ実効あるものにするために各種の措置を講じてきているが,84年においても施設区域の整備や在日米軍の日本人労働者の労務費負担を行った。特に84年には,85年から三沢に配備が開始されるF-16の受入れのための経費も予算に計上された。また,米軍施設・区域の存在と周辺地域の経済的,社会的発展との調和を図るため,施設・区域の整理・統合等の措置もとられた。
(ii) 日米安保体制の信頼性及び抑止力の向上に資するとの観点から,84年においては,米陸軍特殊部隊の沖縄配備や,原子力空母を含む各種米艦艇の本邦寄港も行われた。また,陸海空それぞれにおいて各種の日米共同訓練が実施され,84年5月には海上自衛隊がリムパック演習に参加した。
(ニ)日米漁業関係
(a)84年においては,当初割当(1月)の486,000トンに続き,4月に223,000トンが割当てられた。また,7月割当の際には,対外国割当留保分が上積みされた結果,385,000トンが割当てられた。
(b)前記4月割当の数量は当初予定されていた数量より2万トン少ないが,これは,我が国漁船による米水域内の操業違反が頻発したため,満足な解決策が得られるまで留保するとの措置がとられた結果である。
なお,操業違反問題については,両国政府間で解決を図っていくこととしている。
(c)85年当初割当は,最初167,000トンであったが,すけとうだらの洋上買付,米水産加工品の買付等我が国の積極的な対米漁業協力の姿勢が評価され,新たに164,000トンが追加され,合計331,000トンとなった。
(ホ)日米航空関係
(a)83年12月のホノルルでの協議における合意に基づき,日米航空関係の全般的見直しのための協議は,84年3月の東京における第1回協議(84年版参照)に引き続き,84年9月にサンディエゴで開かれ,日米航空関係の現状と今後のあり方に関する米側の考え方を中心に意見が交換された。
(b)さらに,日本貨物航空(NCA)の米国乗り入れ問題を含む当面の諸問題を解決するための協議が84年12月(ワシントン),85年2月(東京),3月(ワシントンで2回)及び4月(東京)と5回にわたって開催され,以下を骨子とする合意がまとめられた。
(i) 85年5月1日より,日本貨物航空の米国乗り入れを認める。
(ii) 85年5月1日より,東京,大阪からグアム/サイパンの2路線に日米双方2社ずつ,福岡,名古屋,那覇からグアム/サイパンの3路線に双方1社ずつの乗り入れを認めることとする。
(iii) 86年4月1日より,東京―ホノルル,名古屋―ホノルル,東京―米国内の新規地点等の路線から双方が一定の条件下で各々選択した3つの路線への乗り入れを認める。双方は,この3路線のひとつに小口貨物航空企業を乗り入れさせることができる。
(c)上記の合意は,5月1日のボンにおける外相会談において最終的に確認され,外交上の公文が交換された。その際シュルツ国務長官より,日米関係が困難な時期にこのように懸案が解決されたことは有意義であり,また,この合意は日米双方にとって利益となる旨述べ,安倍外務大臣より,同長官の尽力を多とする旨述べた。
(ヘ)日米医学・科学協力
(a)日米医学協力委員会(65年1月設立)第20回会合は,84年7月16日~20日まで東京で開催され,8部会の活動報告を中心に意見交換がなされたほか,筑波研究学園都市の視察が行われた。
(b)科学協力に関する日米委員会(61年設立)の第10回共同議長会合は,東京で開催されるが,筑波で開催される科学技術博覧会視察を兼ねて,85年5月に行われることとなった。
(2)カナダ
(イ)日加関係全般
カナダ国内における政権交替が続いた中にあって,クレチェン自由党外相,及びクラーク進歩保守党外相がそれぞれ7月,12月に訪日し,我が方首脳と緊密な対話を行い,関係の維持・発展がなされたほか,各界要人の交流も活発に行われた。
(ロ)日加経済関係
(a)日加貿易は我が国からの製品輸出,カナダからの原材料輸入というパターンで推移している。84年の往復貿易額は前年比15%近くの伸びを示し,初めて90億ドルを超え,92億4,000万ドルとなった。日加往復貿易額は83年に初めてカナダとEC(英国を除く)間の貿易額を上回ったが,これは84年においてもやや上回った。
我が国はカナダにとって輸出入とも米国に次ぎ第2位の貿易相手国である。2国間収支は一貫して日本側の入超となっているが,近年その幅は縮小しており,84年には6億5,000万ドルの赤字であった。
個別分野を見てみると,対加自動車輸出問題では,84年度の輸出台数につき16万6,000台(カナダの市場動向によっては17万台)となろうとの見通しを84年6月カナダ側に伝えた。
漁業関係では84年2月,日加漁業協議がオタワで開かれ,その結果84年の対日漁獲割当34,100トン(その後4,000トン追加)が決定された。
エネルギー分野では,石炭に関し,カナダの新規炭鉱からの出炭が開始されたこともあり,84年の我が国の石炭輸入は約1,600万トン(主として原料炭)と前年より約50%増となった。これは我が国の全石炭輸入量の約18%に当たる。
LNG輸入問題については,日加事業当事者間で話合いが進められてきたが,カナダの連邦政府及び州政府の輸出許可は下りたものの,商業ベースにのせるために大詰めの交渉が引き続き継続された。
民間の交流は活発に行われており,例えば日加経済人会議第7回会合が84年5月神戸で開かれ,両国から合計約450名近くの参加者により活発な議論が行われた。
<要人往来>
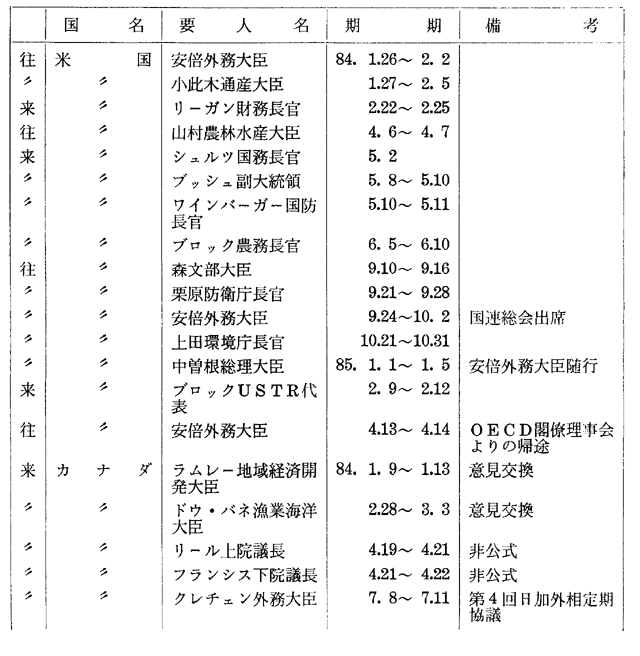

<貿易関係>
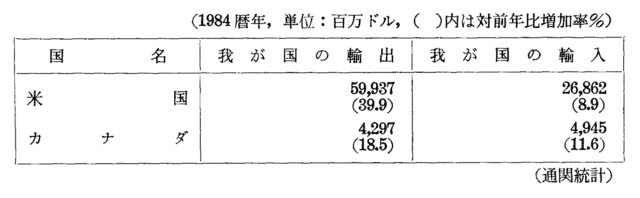
<民間投資>
(あ)我が国の対北米直接投資
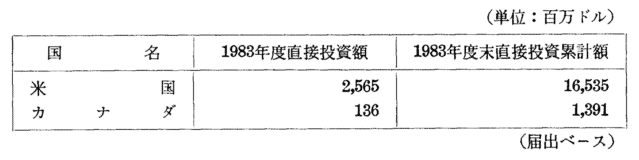
(い)北米の我が国に対する直接投資