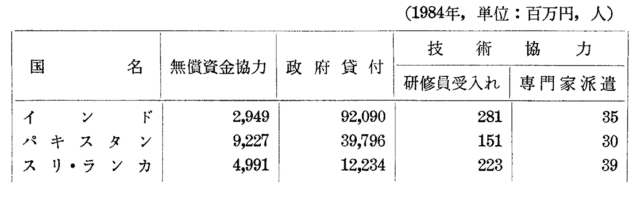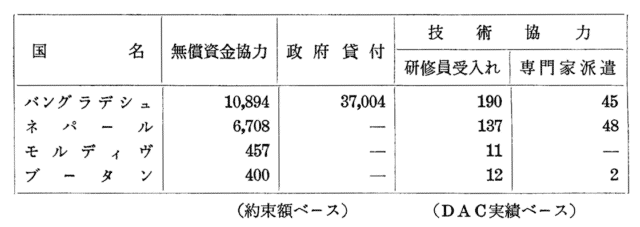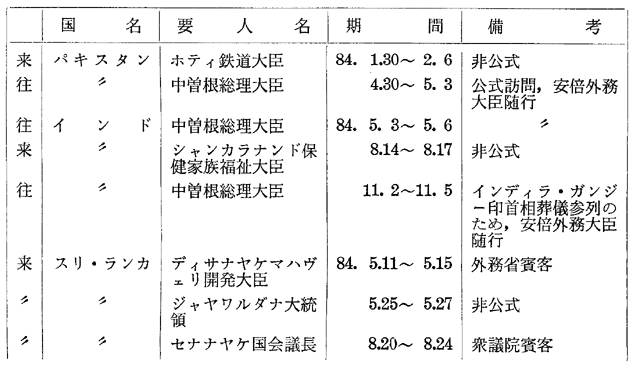
7.南西アジア地域
(1)南西アジア地域の内外情勢
(イ)概要
84年前半には印パ関係改善への動き,南アジア地域協力(SARC)第2回外相会議の開催(7月)等南西アジア地域全体の安定にとり好ましい動きが見られたものの,後半にはインドとパキスタンをはじめとする近隣諸国との関係が冷却化し,インディラ・ガンジー印首相暗殺(10月)もあって,南西アジア地域の不安定化が懸念された。しかし,12月ラジーブ・ガンジー印新首相が総選挙で圧勝したことにより,インド亜大陸の不安定化は避けられ,それに伴いその他の国では内政固めの動きが見られた。
(ロ)インド
(a)内政
84年においてもテロ活動を続行するシク教徒過激派に対し,印政府は,6月にパンジャブ州全土に軍隊を導入してその掃討に乗り出した。シク教総本山の黄金寺院においては,聖域として立てこもる過激派と軍隊との間で激しい戦闘が行われ,死者500名以上を出して同寺院は制圧された。
黄金寺院の武力制圧は,シク教徒一般の宗教感情を著しく傷つけ,シク教徒兵士の反乱,ハイジャック事件等を起こした。
10月31日,インディラ・ガンジー首相はシク教徒警護官により暗殺されたが,同事件は黄金寺院事件に対するシク教徒過激派の報復と言われ,激昂したヒンドウ教徒による反シク暴動が各地で発生した。
同暗殺事件は国民に大きな衝撃と危機感を与えたが,首相の長男ラジーブ・ガンジー氏が大きな混乱もなく後継首相に選ばれ,同年末行われた総選挙においては,同首相率いる与党ガンジー派コングレス党が地滑べり的勝利を得た。
ガンジー新政権は引き続き85年3月に行われた地方議会選挙においても,大部分の州において順当に勝利を収め,政権の基礎を固めた。
(b)外交
84年は総選挙を控え内政に対する考慮に重点が置かれたこともあり,総じて周辺諸国との間に不協和音が目立った。
パキスタンとは,84年前半においては要人の往来が続き,関係改善の動きが軌道に乗るかに見えたが,後半に至り第2回印パ合同委員会の突然の開催延期等その動きは後退した。
スリ・ランカとは,同国の民族対立を巡って,相互に漁船,哨戒艇の拿捕事件等が相次ぎ非難の応酬があった。
バングラデシュとは,デリー・ダッカ間直行航空便運航の原則的合意等前向きの動きも見られたが,4月にインド側がバングラデシュ人の流入を防ぐ目的で国境沿いにフェンスの構築を始めたため,これに反対するバングラデシュとの間で発砲事件が発生した。
(c)経済
84年度の農業生産は,未曽有の穀物生産を記録した前年度の後をうけて1%増にとどまるものと見られているが,2年続きの豊作による工業製品の需要増大により工業生産は7%増,経済成長率は4%増と予想されている。物価も,85年2月現在,卸売物価の上昇率は前年同期の年率10.8%に比し4.6%と低下した。
国際収支も安定的に推移しており,外貨準備高(金,SDRを除く)は84年9月現在前年同期の48億2,000万ドルに比し,52億8,000万ドルと若干増加した。
(ハ)パキスタン
(a)内政
ハック大統領は,83年8月,85年3月までに総選挙を実施し,民政移管を行う旨発表したが,84年はこの実現のための動きが活発化した。政権側は反政府野党連合「民主主義回復運動」所属諸政党との妥協を見い出すことはできなかったが,野党側も党勢を欠き,83年に見られたような反政府運動の高まりは見られず,終始政権側の主導で事態が推移した。
12月には突如現政権のイスラム化政策に対する賛否を問い,賛成多数の場合には今後5年間大統領として留任するとの国民投票を実施し,この結果国民の信任を得ることに成功した。ハック大統領は85年3月には大統領権限を強化するための73年憲法改正を実施した。
85年2月には予定通り非政党ベースでの国民議会及び州議会選挙が,また3月には連邦上院議会選挙が実施され,初議会が招集された。この場でハック大統領は国民議会のジュネジョ議員を首相に指名,同首相は国民議会議員の信任を得た。
(b)外交
84年前半,特に3月から5月にかけて活発な招待外交を展開した。この間に中国国家主席,マレイシア首相,カタル首長,サウディ・アラビア副首相,中曽根総理大臣,トルコ首相,米副大統領が相次いで訪パした。
「パ」にとっての大きな外交懸案であるアフガン問題については何らの進展も見られなかった。ソ連は7月に予定されていた「パ」外務次官の訪ソを直前になって中止したが,これとともにアフガニスタンよりの領空侵犯及び越境砲爆撃が激増した。また,同時期に予定されていたインドとの印パ関係改善のための二国間協議も延期され,10月にはインドの対パ核施設攻撃の可能性が報じられる程となった。このように対ソ,対印関係には緊張する場面が見られたが,ハック大統領は対印平和攻勢に徹するとの姿勢を貫き,11月初めの故ガンジー首相葬儀にはハック大統領自らが参列し印新首相と会談した。
「パ」は回教諸国との連帯を外交の柱としているが,84年を通じイラン・イラク紛争仲介の外交努力が行われ,パキスタン・イラン・トルコ3国間の協力機構(ECO)再発足の動きも見られた。
(c)経済
83年7月より84年6月までの年度においては天候不順による綿花の不作(対前年比38.4%減)により農業部門全体で4.6%のマイナス成長となった。工業部門についても綿紡績工業に悪影響が波及し,GDP成長率の伸びは4.5%にとどまった。
貿易面では,綿製品の輸出が激減したのに加え,伝統的な輸出産品であった綿花を輸入することになり,また輸入品の国際価格の上昇等から貿易収支は33億ドルの赤字に拡大した。
さらに出稼ぎ労働者等よりの送金も減少し経常収支の赤字が拡大し,基礎収支も黒字から赤字へ転落した。外貨準備も対前年比1割減の25億ドルにとどまった。消費者物価も前年度の4.5%から8.4%に増大し,総じて83/84年度の「パ」経済は77年以来最も厳しいものとなった。
84/85年度の綿花及び米の収穫は同国史上最大の豊作と見られている。
(ニ)バングラデシュ
(a)内政
82年3月政権成立以来,エルシャド大統領が民政移管の一環としてその実施を図ってきた国会総選挙は,戒厳令の即時撤廃,中立政権下における自由かつ公正な総選挙の実施等を要求する主要野党との意見調整がつかないまま,これまで3度にわたり延期を余儀なくされてきた。しかし,85年3月突如,同大統領のこれまでの政策等に対する信任を問う国民投票が実施され,その結果同大統領は投票総数(投票率72%)の94%以上を得る圧倒的な支持を獲得した。
(b)外交
英国,カナダ,タイ,マレイシア等の各国首脳のバングラデシュ訪問及びエルシャド大統領による米国等の諸外国への訪問が行なわれた83年に比較して,84年は,民政移管に係わる内政指向が強かったこともあり7月のジェッダにおけるOIC平和委員会(首脳レベル)出席,9月のイラク訪問,11月の故インディラ・ガンジー=インド首相の国葬参列等がエルシャド大統領の主要な外交活動であった。
(c)経済
83/84年度のGDP成長率は4.5%(工業5.7%,農業4%),食糧穀物生産は前年度比36万トン増の1,546万トンと当国経済は比較的順調に推移した。
83/84年度の輸出は対前年度比21%増の8億2,500万ドルを記録し,この輸出の増大に対し輸入が24億6,700万ドル(前年度23億ドル)にとどまったこと,又出稼ぎ労働者からの送金が5億9,500万ドルに達したこともあり,84年6月における外貨準備高は史上最高の5億ドルを記録した。しかしながら,84年5月から9月にかけ豪雨による大洪水に襲われ,食糧穀物,ジュート生産等農業分野に多大な被害をもたらしたため,84/85年度当初において経済全体に深刻な影響を及ぼした。
(ホ)スリ・ランカ
(a)内政
84年における内政は1年を通じシンハラ・タミル民族問題への対応を巡り推移した。ジャヤワルダナ大統領は,本問題の根本的解決を図るべく,1月よりすべての政党,宗教,人種などの代表よりなる全政党会議を断続的に開催した。同大統領は,12月14日開催された全政党会議に対し,それまでの討議結果をもとに,地方自治の拡大及び第二院の設置を骨子とする提案を行ったが,タミル側の受入れるところとならず,かつ,シンハラ側にも仏教団体を中心に反対が多く,結局本件提案は撤回され,全政党会議も解散した。他方,政府は,北部及び東部において分離独立を要求しテロ活動を続けているタミル人過激派の動きに対する取締りを強化した。しかしながら,テロ活動は徐々にエスカレートし,その攻撃対象は軍・警察から無辜の市民へも及んだ。
(b)外交
従来よりの非同盟路線を堅持し,世界各国との関係はおおむね良好に推移している。ただ隣国インドとの関係は,北部及び東部の分離独立を要求するタミル人過激派のテロ活動を中心とする民族問題を巡り冷却化している。スリ・ランカ側がインド政府は同国南部にタミル人過激派の訓練キャンプの存在を許容しているとして,インド政府を非難する一方,インド側は,訓練キャンプの存在を否定するとともにスリ・ランカ政府軍は無法な行為を行っていると非難するなど両国間に非難の応酬が行われた。
(c)経済
83年末よりの紅茶の国際価格の高騰により,紅茶の輸出額が著増したこと,ゴム,織物,衣料品などの輸出も伸びたことにより,国際収支,特に総合収支は黒字に転じ,外貨準備高は5か月分の輸入をまかなえる6億ドル以上となった。また,財政収支は,紅茶による収入増などもあり,その赤字幅は,9.8%(83年13.8%)にまで減少した。
(ヘ)ネパール
(a)内政
83年7月汚職,経済政策の失敗等により瓦解したタパ内閣の後をうけて成立したチャンド政権は,不信任動議提出の動きなど困難な事態に直面したものの,王宮の支持と経済情勢の好転を背景にこれを乗切った。また,懸案の内閣改造を行うとともに,国会内の自らの支持基盤の強化に努めた。他方,政党政治復活を要求する反体制勢力の目立った動きもほとんどなく,国王親政体制はチャンド政権のもとで比較的安定した時期を迎えつつある。
(b)外交
非同盟中立,善隣友好,国連中心を外交の基軸としており,84年においても南アジア地域協力(SARC)の推進とともに,「ネパール平和地帯」提案に対する支持獲得に努力し,支持国数も60か国(85年3月末現在)に達した。
(c)経済
ネパール経済は順調なモンスーンに恵まれ,農業生産も対前年度比18.4%増となり,政府の推計によるとGDPも7.4%と著増した。84/85年度においても引き続き穀物生産は好調であり,政府は従来禁止していた米の輸出を再び許可する旨発表した。
(ト)モルディヴ
任期2期目のガユーム大統領は,内政面では,社会経済開発政策を従来どおり積極的に推進すると同時に民主主義の原則にのっとったイスラム色を徐々に強めるという基本政策をとっており,その地位は安定している。
経済面においては,主力産業たる漁業,海運,観光が前年に引き続き低迷を続け,財政とりわけ国際収支は大幅な赤字を記録した。
対外面においては,従来の非同盟政策を引き続き堅持するとともに,ガユーム大統領が,モロッコ,パキスタン,スリ・ランカ,中国,韓国の各国を公式訪問したほか,アラファトPLO議長,マハティール=マレイシア首相がモルディヴを公式訪問した。また,7月には,南アジア地域協力(SARC)第2回外相会議がモルディヴにおいて開催された。
(チ)ブータン
国内政情は国王親政体制の下に安定が維持されており,84年には政府の政策決定に重要な役割を果たす国王諮問評議会議員(任期5年)や高等裁判所陪審員の選挙が平穏に行われ,国王の指導体制は一層強化されつつある。対外面においては新たにモルディヴと外交関係を樹立したほか,クウェートに領事館を開設,国王はインド,バングラデシュを公式訪問,ツェリン外相もスウェーデン等北欧4か国を歴訪,外交の多角化とともに経済開発の資金調達に努力している。
(2)我が国と南西アジア諸国との関係
我が国と南西アジア諸国は,伝統的に友好関係を維持してきているが,この1年もこの良好な関係を緊密化する動きが見られた。
特に,インドとパキスタンについては,4~5月に中曽根総理大臣が我が国総理として23年振りに両国を訪問し,首脳レベルでの対話を深めたほか,11~12月にかけて我が国のハイ・レベルの経済人から成る政府派遣経済使節団が,両国を訪問し,両国の官民の有力者と貿易,投資上の問題につき有益な意見交換を行う等関係の緊密化が進んだ。
このほか,インドとの関係では,中曽根総理大臣が11月の故ガンジー首相の葬儀の際及び85年3月の故チェルネンコ書記長の葬儀の際の2回にわたり,ラジーブ・ガンジー首相と会談し,首脳レベルでの緊密な接触を維持した。
また,パキスタンとの関係では,84年4月の中曽根総理大臣の訪パ時に,第1回日・パ合同委員会が,日・パ両国の外務大臣出席の下に開催されたのに引き続き,第2回会合が85年3月開催される等間断なき対話が保たれた。また,ガンジー首相の国葬参列の際には中曽根総理大臣とエルシャド大統領との会談が行われ,日・バングラデシュ両国友好関係の増進を図る上で有意義であった。
他の南西アジア諸国との間でも,スリ・ランカとの間で航空協定が締結された(2月)ほか,85年3月には秩父宮妃殿下がネパールを公式訪問する等関係増進が図られた。
<要人往来>
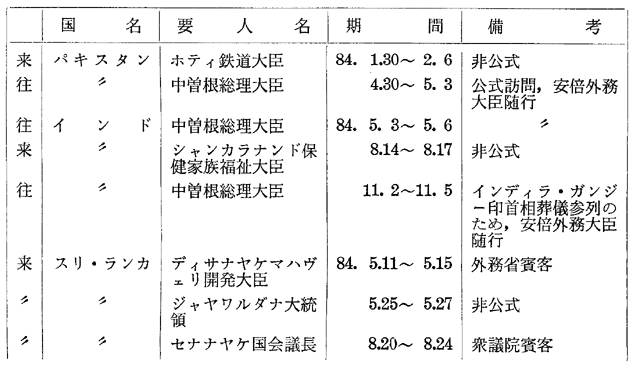

<貿易関係>
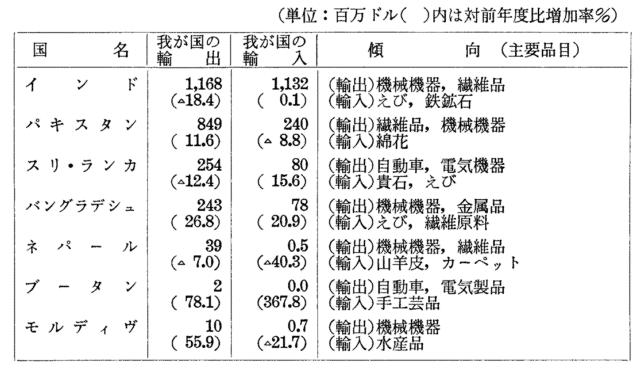
<民間投資>
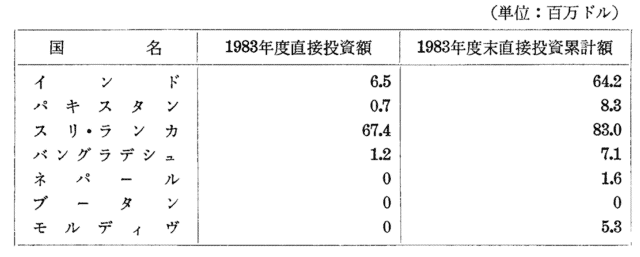
<経済協力(政府開発援助)>