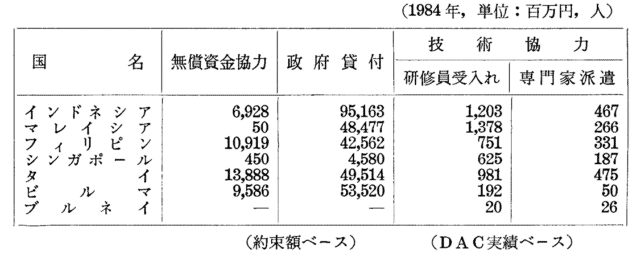3.東南アジア諸国連合(ASEAN)6か国及びビルマ
(1)ASEAN6か国及びビルマの内外情勢
(イ)インドネシア
(a)内政
スハルト政権は,84年4月より第4次開発5か年計画に着手した。84年は内政面では,次期総選挙(87年)に向けて国軍の再編与党ゴルカルの強化,総選挙関連法の整備等の体制固めが行われたほか,パンチャシラ(国是五原則)を国家の唯一のイデオロギーとして確立するための諸施策がとられた。
かかるスハルト政権の支持基盤拡充策,なかんずく,政党及び社会団体に対するパンチャシラの徹底策を背景として,9月,ジャカルタの近郊で,イスラム・グループと治安当局の対立から,暴動事件が発生し,同事件を契機に,ジャカルタを中心に爆破事件,火災事件が頻発した。同時に,有識者,退役軍人等を中心とする反体制グループの活動が表面化した。爆破事件等は,84年末以降も,地方都市にて散発的に発生している。
今後の同国の政治的・社会的安定性の維持は,85年に予定される社会団体法案の審議の動向及び,国内経済の停滞をいかに克服しうるかにかかっていると思われる。
(b)外交
インドネシアは,従来より,ASEANとの連帯及び非同盟積極自主外交を標榜するとともに,米国,日本及びEC等西側諸国との協調を図りつつ,東側諸国との関係をも維持する対外関係の多角化を目指しているところ,84年においても,基本的には,この路線を踏襲した。
対米関係では,米国からダム国務副長官(2月),ブッシュ副大統領(5月)が訪「イ」したのに対し,モフタル外相が訪米(5月)し,ハイレベルの対話が行われた。
東側諸国との関係においては,モフタル外相がインドネシア外相としては10年振りに訪ソした(4月)ほか,経済・財政・工業担当調整相がソ連,ハンガリー,チェッコスロヴァキア及び東独を歴訪した(10月)。
カンボディア問題について,インドネシアは,国軍総司令官の訪越(2月),ヴィエトナム外相の訪「イ」(3月)及び第1回「イ」・越セミナーの開催等を通じ,同問題の早期解決のための外交的イニシアティブをとってきた。さらに,85年に入ってから,2月に第2回「イ」・越セミナーが開催され,3月には,モフタル外相が訪越した。
中国との関係について,インドネシアは国交正常化には,依然として慎重な態度を維持しているが,経済関係の促進には積極的であり,84年10月,モフタル外相は中国市場へのアクセスを図るために,将来対中直接貿易を再開する旨発言した。その後,再開に向けて検討が進められている模様である。
パプア・ニューギニア(PNG)との関係では,両国の国境地帯で,84年2月頃より発生したイリアン・ジャヤ州からPNGへの不法越境を契機に,両国関係が悪化したが,両国外相の相互訪問(4月及び10月)等,問題解決の努力が行われた結果,両国関係は修復された。
(c)経済情勢
84年の経済は,前年にとられた財政再建措置の効果が定着しつつあり,対外的には石油・ガス産品輸出の伸び,及び非石油・ガス産品のうちアルミ,セメント等の輸出の大幅増により,貿易収支は23億ドルの黒字,外貨準備は約100億ドルに回復した。ただし,国内的には緊縮財政などの結果,内外よりの投資が大幅に落ち込み,経済成長率は4.3%と第4次開発5か年計画の目標値(5%)には至らなかった。「イ」政府としてはさらに製品輸出の拡大,新規投資の導入に力を入れ,雇用増進を図ってゆくものと見られる。
(ロ)マレイシア
(a)内政
84年の内政は,年間を通じて重要問題が続発したが,それぞれに一応の解決が図られた結果,引き続き安定が維持された。5月の与党第一党UMNO(統一マレー国民組織)党大会での党役員選挙と7月の内閣改造で,87年までのマハディール首相の地位が確保された。またイスラム過激派対策として,北部4州における政治集会禁止措置(8月)及び同過激派の活動に関する白書の公表(11月)等が行われた。なお,連合与党・国民戦線の有力メンバーであるMCA(マレイシア中国人協会)の指導部の主導権争いを巡る3月以来の内紛は,約1年振りに解決された。
(b)外交
84年において,同国は,従来よりの外交政策の基本路線,すなわち,ASEAN諸国との協力強化,イスラム諸国との協力推進,非同盟中立,自由主義諸国との協力を踏襲しつつも,7月より就任したASEAN常任委員会議長国の立場からのASEAN外交推進,国内外のイスラム運動の高まりを反映してのイスラム諸国との連携強化及び自由主義諸国との交流の面で動きの目立った年であった。
マハディール首相は,1月の米国,カナダ,フランス,スイス訪問を皮切りに,ブルネイ(2月),パキスタン(3月),PNG・豪州・ニュー・ジーランド(8月),イタリア・国連・日本(9~10月),モルディヴ(11月),リビア・エジプト・マリ(12月)を訪問したほか,85年には,インドネシア(3月)を訪れた。
諸外国より同国を訪問した要人も多く,主なものだけでも,プレム=タイ首相,呉中国外相(2月),ハサナル・ボルキア=ブルネイ国王(3月),ヴェラヤティ=イラン外相(4月),シュルツ米国務長官,アラファトPLO議長(7月),ヤマニ=サウディ・アラビア石油相(8月)のほか,85年についても,ロンギ=ニュー・ジーランド首相,プラニンツ=ユーゴ首相(3月)等が来訪している。
イスラム諸国との協力については,エジプトのイスラム諸国会議への復帰に積極的な役割を果たした。また,7月にはアラファトPLO議長の訪「マ」を受け入れる等イスラム穏健勢力としての活躍が目立った。アフガニスタン問題では,ムジャヒディン支持の立場から在クアラ・ルンプール代表事務所の設置に承認を与えた(3月)。イランとの間では外相の相互訪問が行われた。
ソ連との間では,貿易収支改善の一環として,ソ連よりの軍用ヘリコプター購入が検討され,また中国との間では,外相の相互訪問が実現し,85年中のマハディール首相の訪中が検討されている等の動きはあるも,中・ソ両国との関係は,基本的には引き続き経済関係を中心とする実務的なものとなっている。
(c)経済
先進国の景気回復により海外よりの需要が拡大し,輸出価格が上昇したこともあって,84年の同国経済は,総じて好調に推移し,実質GDP成長率は6.9%(前年5.9%)と見込まれる。貿易収支の黒字幅は,前年の6億ドルから20億2,000万ドルへ大幅な拡大を示したが,貿易外収支の恒常的赤字の傾向に変化なく,42億5,000万ドル(前年36億3,000万ドル)の赤字を記録した。
なお,最近2年間の緊縮予算の結果,84年の連邦政府の財政ポジションは改善され,経常予算収支は1億9,300万ドルの黒字(前年1億ドル),総合予算収支は36億2,500万ドルの赤字(前年39億2,400万ドル)となった。
85年は,第4次開発計画の最終年に当り,また新経済政策期間(1971~90年)の最後の5年間のための第5次開発計画策定が行われることとなり,同国経済の今後を占う意味で重要な年となろう。
(ハ)フィリピン
(a)内政
5月14日の国民議会議員選挙の結果,野党が183名の地域代表議員中,無所属を含めると69議席を獲得した結果,新議会における野党の政府批判活動が活発化した。しかし,与党KBL(新社会運動)が,依然として議席の過半数を保持していることから,議会の立法による実質的な政治的変革は見られなかった。
他方,アキノ元上院議員暗殺事件調査委員会は,10月にアグラヴァ委員長の報告書と他の4人の委員の報告書の2本立てで調査結果を発表した。両報告書とも,(イ)アキノを暗殺したのは,アキノを護衛した兵士の1人であり,(ロ)同暗殺は軍関係者の共同謀議によるものであるとした。両報告書はマルコス大統領により,公務員関係の検察機関たる行政監察府に送付され,行政監察府は,85年1月,調査委員会の4人の委員報告書で起訴すべしとされた26名全員を起訴した。
また,84年11月にマルコス大統領が健康悪化のため約2週間公けの場より姿を消したことから,同大統領の健康に関し,種々の観測が行われた。なお,84年には,フィリピン共産党及び新人民軍が,農村地域を中心に活動を活発化するに至ったと見られる。
(b)外交
84年において,フィリピン政府は,内政上の対応に迫られ,また,経済再建のための国際機関及び米国,我が国等主要援助供与国との交渉に重点を置いた。
フィリピンの対外関係の基軸である対米関係については,米国がフィリピンに対し,その経済危機対処のための各種の援助を実施するとともに,両国間でフィリピンの民主的制度の拡充について各種の意志疎通が行われた。
ソ連との関係では,イメルダ大統領夫人等を中心とする比・ソ友好協会による文化・スポーツ交流が盛んに行われた。
1月に過去17年間外務大臣の職にあったロムロ外相が辞任し,6月にトレンティーノ新外相が任命されたが,85年3月解任された。
(c)経済
84年のフィリピン経済は,経済危機克服のため,一連の金融引締,緊縮財政,為替調整政策等が取られたことなどから,低調に推移した。具体的には,経済成長率はマイナス5.5%,物価は年間平均50.3%の上昇となった。また国際収支状況をみると,貿易収支は6億8,000万ドル,経常収支は約11億ドルの赤字であったが,総合収支は2億9,000万ドルの黒字になった。
かかる状況下で,フィリピン政府は12月,総額6億1,500万SDRのスタンドバイクレジット供与に関するIMF理事会の正式承認を得た。また,年末に開催されたパリクラブ会合では中長期公的債務等の債務救済措置の大綱につき関係国の間で申し合わせがなされ,国際的な金融支援態勢の枠組みが一応整った。
(ニ)シンガポール
(a)内政
84年は,年末の総選挙に伴い政治指導者の世代交替が進展し,リー首相後継者問題に一応の方向付けがなされた年といえよう。
12月に行われた総選挙において,68年の第1回選挙以来続いた人民行動党(PAP)の総選挙での全議席独占が破られ,79議席中2議席を野党に譲った上,与党の得票率も前回総選挙(80年)の75.5%から62.9%に下落した。
総選挙後の内閣改造においては,若手指導者が多く主要閣僚に就任する等,世代交替が一層進展した。また,同内閣改造において,リー首相に次ぐ地位たる第1副首相にゴー・チョク・トンが,第2副首相にオン・テン・チョンが,大蔵大臣にトニー・タンがそれぞれ任命された。これら3名は,これまでリー首相後継者として有力視され,ポストの面でも均衡が保たれていたところ,今般この3人に序列が付けられたことが注目される。
(b)外交
シンガポールは,国際情勢全般についてはソ連の勢力拡張を主因とする東西間の緊張が存し,アジアでは米ソ両大国に中国を加えた三極による勢力争いが展開されているとの厳しい現実認識に立脚して外交を展開している。
84年のシンガポール外交は,同年が建国25周年に当たり,国を挙げて内政面への充実に目が向けられたこともあってか,全般に控え目なものとなった。
具体的には,リー首相のブルネイ独立記念式典出席(2月),ダナバラン外相のバハレーン・オマーン訪問(11月),ラジャラトナム副首相のマレイシア訪問(11月)があったほか,外国からの要人来訪については,ホーク豪首相(2月),民主カンボディアのシハヌーク大統領(2月),ソン・サン首相(3月)の来訪が目立った動きであった。
(c)経済
83年第3四半期以降,急速な回復を見せたシンガポール経済は,84年に入って米国景気の回復鈍化を背景に,第1四半期10.1%から第2四半期9.2%,第3四半期8%,第4四半期7%(各年率換算)と次第にその伸び率を低下させながらも,製造業,建設業,金融ビジネスサービス部門の成長により,84年全体の実資成長率は8.2%となり,前年の7.9%を上回った。なお,労働生産性上昇率は,83年の5.2%を上回る6.6%となったほか,物価は原油価格と一次産品価格の低迷を反映し,安定傾向を維持している。
(ホ)タイ
(a)内政
84年の内政は,年初から年央にかけて,政権復帰を狙う野党タイ国民党による内閣不信任案動議の提出等政府批判の動きが散発的に見られたが,大勢に影響を与えるものではなく,政情は比較的平穏裡に推移した。しかし,同年後半に至り,プレム首相の健康問題(8月)と,それに伴う首相後継者問題に絡む憲法改正論議の復活,バーツ切下げ(11月)を巡る政府と軍の対立等,一時政局は緊迫したが,王室,与党及び一般国民の支持を背景にプレム首相は難局を乗り切り,その指導力を高めた。一方,プレム首相の後継者問題に絡み,85年に定年を迎えるアーティット最高司令官兼陸軍司令官の動きが注目されたが,プレム首相は軍の意向等を考慮し,85年4月,定年の1年延長を決定した。
なお,勢力を退潮させているタイ共産党は,党幹部を含む主要関係者の逮捕により一層の打撃を受けた。
(b)外交
84年のタイ外交は,前年同様(i)カンボディア問題を中心とするASEANの結束の強化,(ii)・米等西側諸国との関係強化,(iii)中国との良好な関係の維持の3点を中心に展開された。また,タイは,国連加盟以来初めて安保理選挙に立候補し,当選を果たして大いに国威を高めた。最大の外交懸案であるカンボディア問題については,84年中にASEAN側とインドシナ側との間で接触が続けられたが,タイはヴィエトナム軍の撤退等を求める包括的政治解決を一貫して主張,従来の基本姿勢を維持した。
84年11月より,ヴィエトナム軍がタイ,カンボディア国境地帯の民主カンボディア連合政府を構成する三派の軍に対し大規模な乾期攻勢を開始し85年3月までに民主カンボディア側の主要拠点を軒並み制圧するとともに,タイ領侵犯を繰り返したため,タイは右を撃退するとともに国連等を通じ厳重抗議を行った。
中国とは,呉外交部長訪タイ(2月),シティ外相訪中(7月)及び季国家主席による初の中国元首訪タイ(85年3月)が実現するなど,引き続き良好な関係が維持された。
ソ連とは,アーサ外務次官の訪ソ(10月),カーピッツァ外務次官の訪タイ(85年3月)等があったが,両国関係に大きな変化は見られなかった。
他方,ラオスとの関係では,4月国境地域の三村の帰属を巡って紛争が発生,2度にわたる交渉でも妥結に至らず両国間の大きな懸案となった。
(c)経済情勢
84年のタイ経済は,民間投資を中心とした内需の低迷に直面した反面,米国を中心とした世界経済の好転,農業部門における生産増に支えられた輸出の伸びにより,実質経済成長率は6.0%を記録した。
タイ政府は83年に大幅に拡大した貿易赤字等に対処するため,一連の金融引締め基調の政策をとるとともに,11月17.4%に及ぶバーツ価切り下げを実施した。これら諸政策の効果もあり,84年の対外収支は改善され,貿易赤字幅は83年の38億8,000万ドルから29億7,000万ドルに縮小し,総合収支は83年の7億9,000万ドルの赤字から4億5,000万ドルの黒字に転じた。
他方,財政面では84年度でも13億9,000万ドルの財政赤字を抱え,公的対外債務残高は75億ドルに上った。
(ヘ)ブルネイ
(a)内政
ブルネイは,84年1月1日に英国から完全独立を果たした。以来,新生独立国家としての体制作りを推進している。
ブルネイの国政は,総理大臣・大蔵大臣・内務大臣を兼ねる世襲制の国王(サルタン)を中心として運営されており,立憲君主制を基本政体とした保守政治が行われている。立法議会は84年2月に解散されたままとなっているが,高い経済水準を背景に内政は安定している。
(b)外交
ブルネイは,完全独立後直ちに英連邦(84年1月1日),ASEAN(1月7日),イスラム会議機構(1月14日)に加盟し,これら関係諸国並びに我が国及び米国等と緊密な関係にある。また,9月21日には国連への加盟が認められた。
旧宗主国である英国との関係においては,一部に英国離れの動きも見られるが,対外・国防政策面では依然として英国と協力関係にあり,両国間の防衛取極に基づき,英国軍(グルカ兵1個大隊約950人)がブルネイに駐留している。
ブルネイは,ASEAN諸国との関係を特に重要視している。2月23日の独立記念式典にはASEAN5か国首脳が出席した。独立後,ブルネイは,ASEAN近隣諸国,我が国および韓国(4月),ニュー・ヨークの国連本部(9月)を訪問するなど積極的な首脳外交を展開している。
(c)経済
生産の中心は石油および天然ガスであり,石油の84年の1日当り生産量は15万9,000バーレル,天然ガスの年間生産量は525万トンに達している。これらの採掘利権による納付金が巨額にのぼり,高い経済水準を維持している(83年1人当り国民所得は21,140ドル)。これら納付金から得られるブルネイの外貨準備は84年末には約150億ドルに達したものと見られている。
他方,石油・天然ガス以外には,特に見るべき産業はない。石油減産等から80年を境に貿易収支の黒字幅が減少傾向にあること(もっとも83年の黒字幅は,依然として24億6,000万ドルの高水準にある),及び21世紀初めには石油資源が枯渇するのではないかとの見方もあることから,石油・天然ガス依存から脱却すべく,各種産業の育成をはじめとする国造りの施策が検討されている。
(ト)ビルマ
(a)内政
84年は,内政面で特に目立った動きもなく,比較的平穏裡に推移した。国内治安面では,1月に政府軍が大規模なカレン族反乱軍掃討作戦を行い,その後も同反乱軍の拠点を包囲しているため,密貿易を資金源とするカレン族反乱軍は財政的に窮地に追い込まれている。
(b)外交
外交面では,従来の基本路線である非同盟中立政策を軸とした活発な動きがみられた。特に中国との間では,サン・ユ大統領(10~11月)と李先念主席(85年3月)の相互訪問が実現する等頻繁な交流が目立った。また,ネ・ウィン党総裁のインド訪問(11月),サン・ユ大統領の我が国訪問(7月),マウン・マウン・カ首相の大洋州訪問(4月),チッ・フライン外相のネパール,インド,バングラデシュ訪問(5月)等の活発な訪問外交が展開され,善隣友好関係の促進が図られた。
(c)経済
84年は,ビルマ経済にとり全般的に前年に引き続き困難な年であった。特に,米の国内供給不足から,イラワジ・デルタを中心に精米所や米貯蔵倉庫に対する米の略奪事件が発生し,そのため,一時,ラングーン等の闇市場の米価が急騰したが,政府の米配給量の増加等の緊急措置により事態は沈静化した。
また,輸出は,米を中心とする一次産品国際価格の低迷に加え,11月のタイの通貨切り下げの影響も受け不振を窮めており,政府は輸入節減策を強いられている。このため,輸入原材料に依存する国営工場は操業率低下を余儀なくされている。かかる状況下で,ビルマ政府が,10月,西独の機械製造企業に対し,外国企業としては初めて,ビルマでの合弁会社設立を認可したことは注目される。
(2)我が国とASEAN6か国及びビルマとの関係
(イ)インドネシア
84年は両国閣僚(安倍外務大臣,坂本労働大臣,モフタル外相,ハビビ研究技術相,スブロト鉱業・エネルギー相ほか)の往来に加え,日・「イ」国会議員連盟渡辺会長の訪「イ」により,国会議員レベルの交流に新たなページが開かれるなど両国関係は一層緊密化した。
貿易面では,84年も貿易収支は「イ」側の黒字(「イ」の対日輸出112億ドル,輸入31億ドル)であるが,「イ」は非石油・ガス産品の輸出振興のため,我が国の貿易拡大措置を求めている。投資面では,84年には我が国を含め諸外国からの対「イ」投資が減少したため,「イ」側より投資の拡大について,我が国の協力を求めてきている。また,84年度中に,「イ」側イニシアティブによる科学技術分野の「イ」政府派遣留学生の日本受け入れについて,両政府間で話合いがまとまり,85年度より実施に移される予定である。
(ロ)マレイシア
82年より開始された東方政策を軸に全般的に両国関係の緊密化が促進された。84年8月開催された第1回日・「マ」コロキアム開会式でのマハディール首相の日本批判演説を契機として,両国関係に若干円滑さを欠く側面が見られたものの,両国首脳会談(10月)を通じ,懸案となっていた航空問題につき解決の努力が払われたこともあり,年末にかけて関係は再び正常化された。
貿易関係では,我が国は同国にとって第1の貿易相手国であり,LNGの対日輸出本格化もあり,84年の貿易収支は我が方通関統計上同国の15億ドルの大幅黒字が記録された。
同国の東方政策に基づく産業技術研修生は82年以来84年まで4陣にわたり,総計801名を受入れている。
(ハ)フィリピン
84年の日比関係は,フィリピンの経済困難もあり,経済協力問題を中心に展開した。我が国はフィリピンに対し,第12次円借款(425億円)の供与のコミットを行ったほか,日本銀行が米国及び韓国と協調して,つなぎ融資を供与した。
他方,日比貿易については,対日輸出が日本の景気回復等の結果増加する一方で,対日輸入は,フィリピンの輸入抑制政策と国内需要の低下などにより,大幅に減少したため,貿易収支は4年ぶりに比側の黒字となった。
(ニ)シンガポール
日・「シ」関係は,単に経済分野だけでなく,社会及び文化等極めて広範な分野で緊密な関係が発展している。我が国としては,シンガポールからの期待に応えるべく,日シ技術学院,シンガポール生産性向上プロジェクト,日シ・ソフトウエア技術研修センターへの協力など積極的な協力を進めている。
貿易分野では,我が国は,シンガポールにとって米国,マレイシアに次ぐ貿易相手国となっている。84年の貿易収支はほぼ前年と同様,我が国の28億ドルの出超となっている。
(ホ)タイ
84年はシティ外相(10月),ピチャイ副首相(12月)等の訪日,安倍外務大臣(7月)等の訪タイが実現したほか,5年振りに第11回日タイ貿易合同委員会がバンコックで開催された。
両国間の懸案である日タイ貿易不均衡問題は,83年に引続き84年もタイ側の大幅な赤字(14億ドル)を記録し,同問題解決を求める声が学生の日本商品不買運動等に発展したほか,貿易面のみならず,投資,経済協力も含め日タイ経済関係全般の在り方を見直すためにタイ政府部内に7月日タイ経済構造調整小委員会が設置された。
(ヘ)ブルネイ
我が国はブルネイの最大の貿易相手国(83年のブルネイの全輸出入量に占める対日輸出・対日輸入の割合いは,それぞれ68%及び19%)であり,ブルネイ産原油の約5割,天然ガスのほぼ全量が我が国へ輸出されている。
また,ブルネイの国造りに対し,我が国は,研修員の受け入れ及び専門家の派遣等により積極的に協力している。
要人の交流の面では我が国から江崎特派大使がブルネイ独立記念式典に出席し(2月),ブルネイからはハサナル・ボルキア国王が国賓として我が国を訪れた(4月)のをはじめ,多数の要人が訪日した。
(ト)ビルマ
84年の両国関係は,7月にサン・ユ大統領が国賓として初めて訪日したのをはじめ,経済協力を中心としたあらゆる分野において,前年に引き続き着実な進展を見せた。また,85年3月には,森山外務政務次官がビルマを訪問した。
<要人往来>

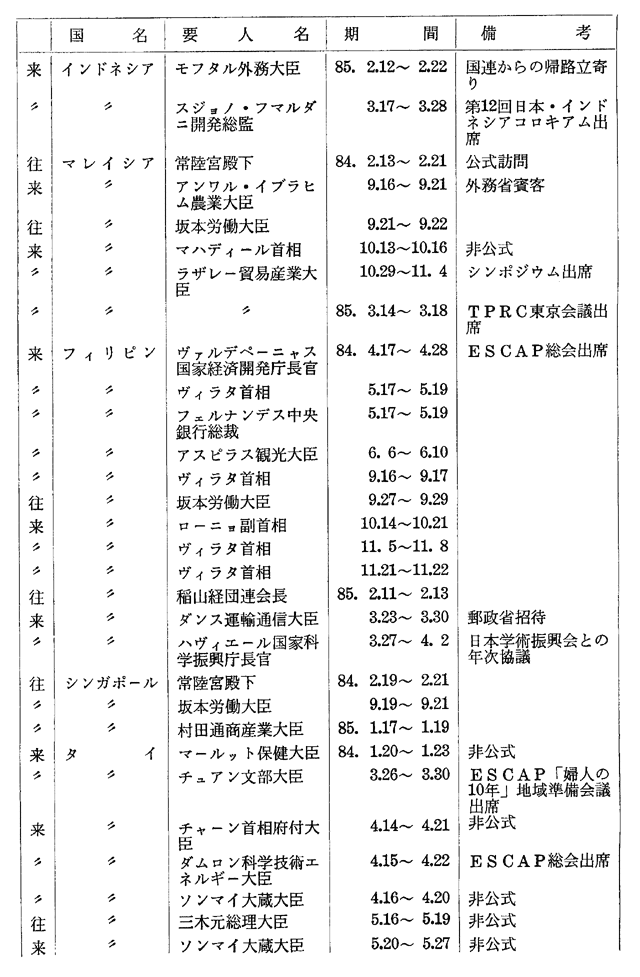
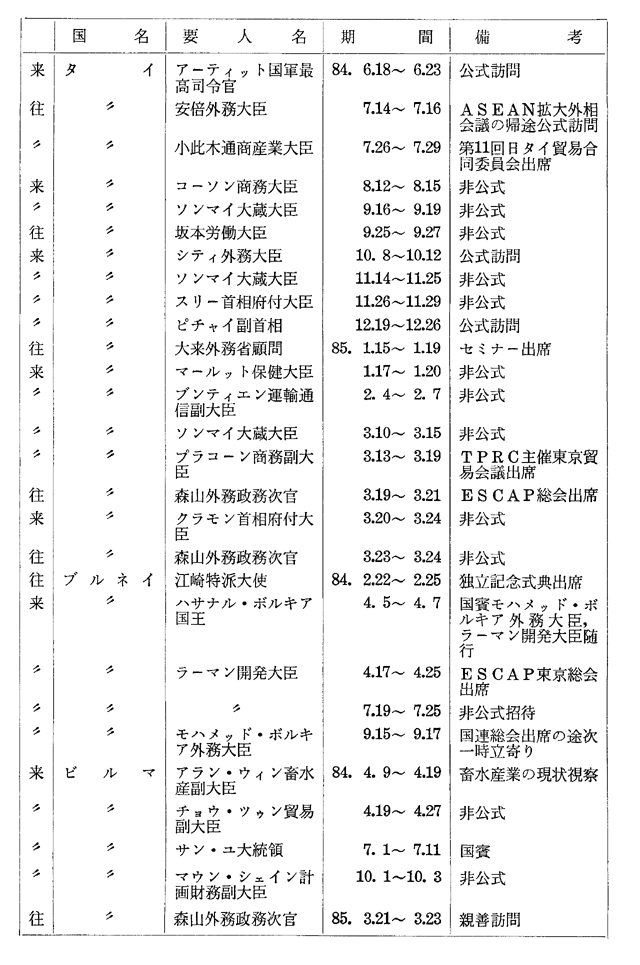
<貿易関係>
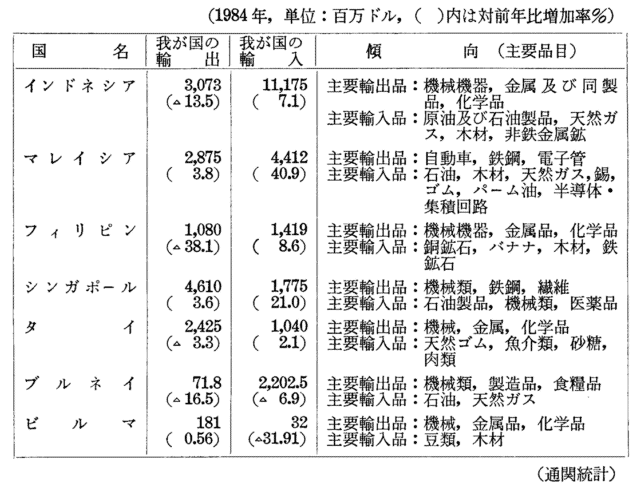
<民間投資>
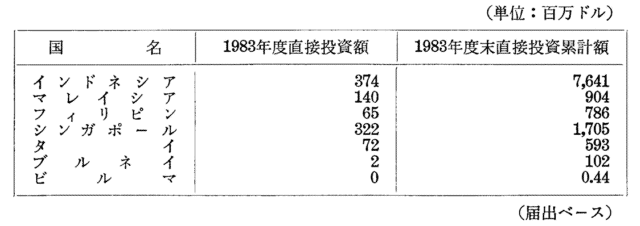
<経済協力(政府開発援助)>