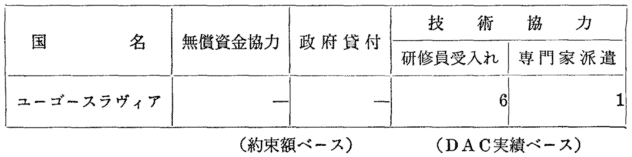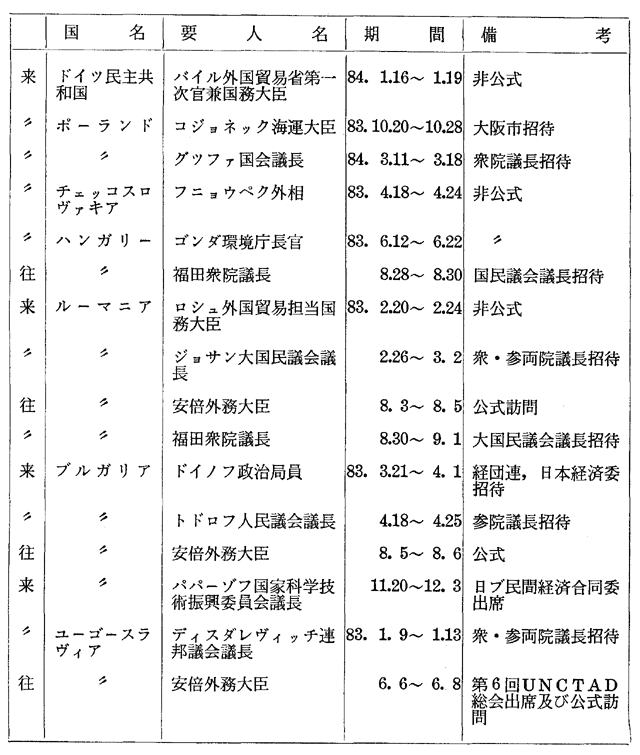
2. 我が国とソ連・東欧諸国との関係
(1) ソ連
(イ) 北方領土問題
(a) 4月5日,高島大使はチーホノフ首相を表敬訪問し,日本人がソ連に対し抱いている不信感の最大の原因が領土問題にあり,その解決のためには時間が掛かろうが,少なくともソ連がその存在を認めることが重要である,それがなされれば日本人の対ソ不信感除去の第一歩が踏み出される旨述べた。これに対しチーホノフ首相は,領土問題は存在しないというのがソ連の立場であり,日本人の対ソ不信感なるものは存在しないなど述べ,領土問題についての従来のソ連側の立場を繰り返した。
(b) 4月12,13の両日,東京で第3回目ソ事務レベル協議が行われた。日本側から北方領土問題について,第1に田中・ブレジネフ共同声明のラインに戻ること(そもそも戦後未解決の問題には4島が入ることは確認されている),第2に北方領土のソ連軍を撤退させること,第3に平和条約締結交渉を再開すること,そのためにグロムイコ外相が訪日すべきことをソ連側に伝えたのに対し,ソ連側は,領土問題についてのソ連側の立場は一度ならず述べられているので追加して述べることはしない,田中・ブレジネフ共同声明には日本側が述べていることは書かれていないとし,従来と同様頑なな態度に終始した。
(c) 4月29日,天皇誕生日に際し,高島大使はソ連の報道番組“ヴレーミヤ”において国祭日記念スピーチを行い,その中で領土問題につき「両国が1956年の日ソ共同宣言の根本精神にのっとり,日ソ国交正常化に際して外交関係回復後の継続交渉に委ねられることになった問題を解決」することを訴えた。
(d) 他方,国内的には北方領土返還の声は引き続き大きくなりつつあり,8月20日から22日まで安倍外務大臣は現職の外務大臣として5回目の北方領土の現地視察を行い,この問題解決に対する政府の不動の姿勢と不退転の決意を改めて内外に表明した。
(e) 9月29日,安倍大臣は,第38回国連総会一般討論演説で,北方領土問題に対する我が国の基本的立場を国際世論に訴えた。
(f) 84年2月15日,アンドロポフ前書記長の葬儀に出席した安倍大臣はグロムイコ外相と会談,領土問題について日本側の基本的立場を述べたが,グロムイコ外相は領土問題に対するソ連側の立場は日本側承知のとおりであり,その立場を繰り返さない旨述べるにとどまった。
(g) 84年3月12,13の両日,モスクワで第4回目ソ事務レベル協議が行われた。ここでも日本側は,日ソ関係が厳しい状況にある最大の原因は日ソ間に未解決の領土問題が存在し,そのため平和条約が未締結であることであるとして本問題の早期解決を訴えたが,ソ連側は,北方領土はソ連領であるとの従来の立場を繰り返すにとどまった。
(ロ) 在日ソ連大使館員の国外退去
(a) 5月末,外務省は在日ソ連大使館ヴィノグラードフ一等書記官が高度技術の入手に関し,外交官として好ましからざる行為を行ったとの通報を警察庁より受領した。
(b) 外務省は,警察庁とも緊密に連絡をとり検討した結果,6月17日,ソ連側に対し関係ソ連外交官の退去を求め,その結果,同19日,ヴィノグラードフ書記官は出国した。
(ハ) 大韓航空機撃墜事件
(a) 9月1日未明,アンカレッジからソウルに向けて飛行していた大韓航空007便がソ連軍用機のミサイルにより撃墜され,邦人28名を含む269名の乗客乗員の犠牲者を出した。政府は,いかなる理由があるにせよ非武装かつ無抵抗の民間航空機を撃墜することは人道にもとり,国際法に反するのみならず,国際民間航空の安全確保という点からも許されず,強く非難されるべきであるとの立場から,関係諸国との連絡,協力体制を強め,事件の一層の究明,機体及び乗客の捜索に全力を挙げた。
(b) 政府はソ連側に対し,事件発生以来真相の究明と事件に対する誠意ある対応を求めて種々のレベルで鋭意折衝を行ったが,ソ連側は満足な回答を行わず,6日,国連安保理事会で日米共同のソ連機パイロットの交信記録が公表されるに及んで,ようやく9日撃墜の事実を認めるに至った。しかしソ連はこの大韓機による領空侵犯は,米国の計画による挑発行為と決めつけ,すべての責任は米国にあるとして自己の責任を認めようとせず,今日に至るまで誠意ある対応を示していない。
(c) これに対し,政府は,ソ連に対して我が国の抗議の姿勢を明確に示すため,9月15日から28日まで日ソ間の両国航空機の運航を停止するとともにその他の航空関係の対ソ措置を9月15日から11月15日まで実施した。また,政府は,9月14日,ソ連に対し文書をもって損害賠償請求を行ったが,ソ連は,右請求は米国に向けられるべきであるとして右文書の受理を拒否した。
(d) 他方,9月26日及び12月20日の両日,樺太ネベリスクでソ連側から,日米代表団に対し撃墜された大韓航空機関連物件の引き渡しが行われたが,遺体,その他の墜落状況に直接関係する物件は含まれていなかった。
(e) なお,安倍外務大臣は,9月28日,国連総会で本件に関しソ連を非難し,ソ連側の誠意ある対応を求める演説を行い,我が国の立場を広く国際世論に訴えた。
(ニ) 東西経済関係
82年10月から11月にかけて,米国の提唱により,サミット参加国(及びEC)大使会議がワシントンで開催され,西側主要国内で,対ソ・東欧経済関係に関し,戦略物資,高度技術,信用供与政策,エネルギー等の分野で分析研究を行っていくことが合意された。
このような合意を踏まえ,そのフォローアップとして,83年初めから具体的分析・研究が,ココム(戦略物資,高度技術),OECD(信用供与,エネルギー)等のフォーラムで進められた。その結果,5月のOECD閣僚理事会,さらには6月のウィリアムズバーグ・サミットまでに一定の成果が得られ,82年に見られたような東西経済関係を巡る西側内部の対立は事実上収拾された。
その後の各分野における作業は,ココム,OECD等の従来のフォーラムに吸収される形で順調に行われている。
(ホ) 日ソ経済関係
(a) 日ソ貿易
82年まで日ソ貿易は,順調に増加を続けてきたが,83年になって不調に転じ,輸出は28億2,100万ドルで対前年比27.6%滅,輸入も14億5,600万ドルで対前年比13.4%減と,共に減少した。この結果,貿易総額は42億7,700万ドルで対前年比23.4%減とこれまでで最高の落ち込みを示した。輸出の減少は,主要輸出品目たる鉄鍋と機械機器の輸出が,大幅に減少したためで,特に油井用のシームレスパイプの減少は著しく,前年の約5億ドルから83年はわずか8,600万ドルと4億ドル以上も落ち込み,これだけで全減少額の約1/3に当たる。他方,輸入の減少は金の輸入が83年にも前年に引き続き大幅に減少したためで,従来の主要品目である木材,非鉄金属,鉱物性燃料等はほぼ前年と同水準にあり,金を除けば対ソ輸入は下げ止まりの傾向にある。
(b) シベリア開発協力
(i) 日ソ間でこれまでに具体化したシベリア・極東地域の資源開発を中心とする協力プロジェクトは8件あるが,このうち現在実施中のものは,南ヤクート原料炭開発,サハリン島陸棚石油・ガス探鉱開発及び第3次極東森林資源開発の3件がある。
(ii) 南ヤクート炭開発プロジェクトについては,83年末までにバンクローンが予定どおりほぼ全額消化され,85年からは開発された南ヤクート炭の日本への出荷が開始される予定である。
サハリン・プロジェクトについては,83年9月末に探鉱作業が最終的に終了し,現在は開発段階に移行するための様々な準備作業が行われている。
第3次極東森林資源開発プロジェクトも順調に実施されている。
(c) 日ソ政府間貿易経済協議の開催
83年10月13,14の両日,モスクワで日ソ両政府間の貿易経済協議が開催され,日本側から外務・通産・大蔵・農水の各省からなる代表団が訪ソした。協議では最近の日ソ貿易実績レヴュー,日ソ貿易経済関係にかかわるその他の諸問題を議題として活発な意見交換が行われた。
(へ) 漁業関係
(a) カーメンツェフ=ソ連漁業大臣の訪日
83年2月16日から22日まで,カーメンツェフ=ソ連漁業大臣が訪日し,金子農林水産大臣との間で日ソ漁業関係の諸問題に関し意見交換が行われた。
(b) 日ソさけ・ます交渉
日ソ漁業協力協定に基づき83年の日本によるさけ・ます操業に関する日ソ政府間交渉が,4月11日から21日までモスクワで行われた。この結果,ソ連200海里外の北西太平洋における日本のさけ・ます漁獲割当量を42,500トンとするなどの内容の議定書が締結され,また,日本側がソ連に対する漁業協力費42億5,000万円を負担することとなった。
(c) 「日ソ」及び「ソ日」漁業暫定協定延長交渉
日ソ両国のそれぞれ相手国200海里水域内における漁業に関する「日ソ」及び「ソ日」漁業暫定協定が83年末に失効するため,両協定の有効期間を延長し,84年の双方の漁獲割当量等を定めるための交渉が11月21日から12月23日までモスクワで行われた。この結果,両協定の有効期間を84年末まで1年間延長する議定書が締結され,また,相手国200海里内での漁獲割当量を日本側70万トン,ソ連側64万トンとすることなどが定められた。
(ト) 墓参
6月,政府は,83年の北方4島,ソ連本土及び樺太への政府ベースの墓参実施をソ連政府に対し申し入れた。これに対し,ソ連側は,8月,樺太(豊原,真岡,本斗・内幌)及び北方4島への墓参を通常のソ連入国手続をとることを条件として認めるが,その他の諸地域への墓参については同意できない旨回答した。政府は,その他の申入れ地域への墓参につきソ連側の再考を要請し,また北方4島への墓参については,64年から75年まで行われてきた身分証明書による渡航という方法に従い本件墓参が実施できるようソ側の再考を求めたが,ソ側は上記の回答が最後の回答であるとして我が方の要請に応じなかった。この結果,9月13日から樺太墓参を実施予定であったが,大韓航空機事件発生に伴う対ソ航空措置との関係で交通手段が確保できず,結局唯一実現可能であった樺太墓参も中止となった。
(チ) 未帰還邦人
政府は,ソ連に居住している未帰還邦人で帰国ないし一時帰国希望を表明している者への帰国指導を行うとともに,ソ連側がこれら未帰還邦人に対し遅滞なく日本への帰国ないし一時帰国を許可するよう機会あるごとに要請した。83年には,2名が一時帰国した。
(2) 東欧諸国
(イ) 我が国と東欧諸国との関係
83年は要人往来が盛んな年であった。8月には安倍外務大臣が我が国の外相として初めて,ルーマニア,ブルガリアを訪問し,主としてINF問題等の国際問題につき率直な意見交換を行った。安倍大臣の両国訪問は相互理解を増進し,両国とのパイプを太くすることに大きく寄与した。その他,外相レベルでは4月にはチェッコスロヴァキアのフニョウペク外相が我が国を非公式に訪問した。
また,議員交流も盛んで,我が国からは8月に福田衆議院議長がルーマニアを訪問し,2月にはルーマニアのジョサン大国民議会議長,4月にはブルガリアのトドロフ人民議会議長が来日している。また,84年3月にはグッファ=ポーランド国会議長が来日した。
経済面では東欧諸国の経済不振等により80年から82年まで3年連続して貿易高は減少したが,83年には10億3,000万ドルと対前年比34%の大幅な伸びを示した。
(ロ)ポーランド問題への対処ぶり
ポーランド問題については7月22日に戒厳令が解除されるなど不充分ながらも一定の改善が見られたことから,我が国は西側諸国との協調の下で,11月対ポーランド債務繰延交渉の再開に応じた。
(ハ)ユーゴースラヴィアとの関係
安倍外務大臣は6月のUNCTADVI出席の際に,ユーゴースラヴィアを公式に訪問し,同国の指導者と有益な意見交換を行った。
我が国は83年1月,対外債務問題,インフレ高進等の困難な経済状況に直面していたユーゴースラヴィアに対し,6,000万ドル(西側全体で13億6,000方ドル)の輸出信用供与を行った。その後もユーゴースラヴィアの経済の安定を図るとの観点から84年3月には我が国は他の西側諸国と共に対ユ債務繰延要請に応じた。
<要人往来>
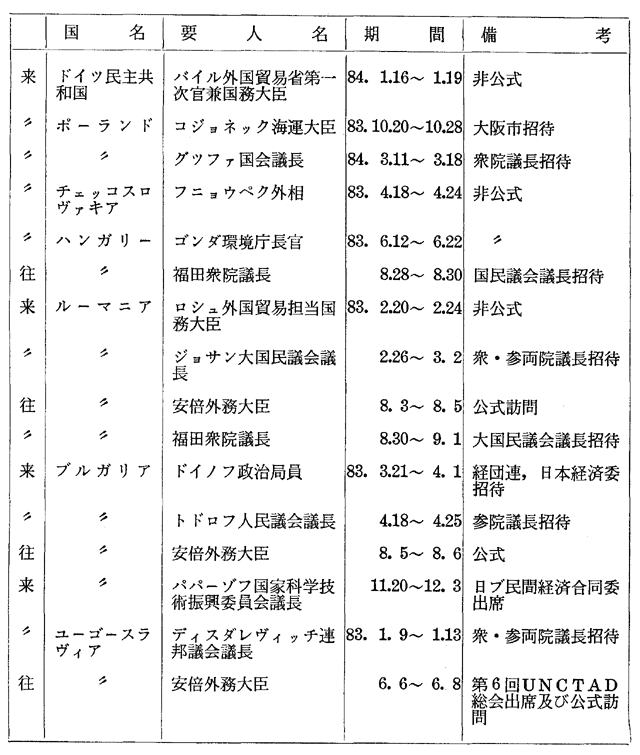
<貿易関係> (1983年,単位:百万ドル,()内は対前年比増加率%)
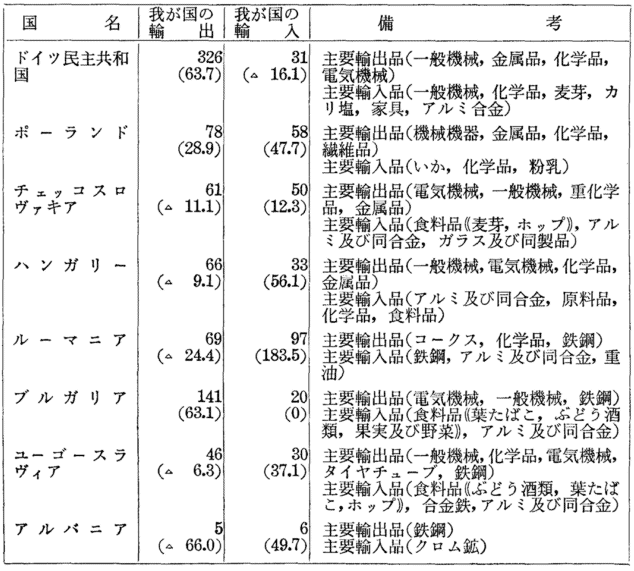
<民間投資> (単位:百万ドル)
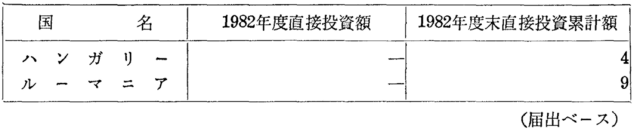
<経済協力(政府開発援助)> (1983年,単位:百万円,人)