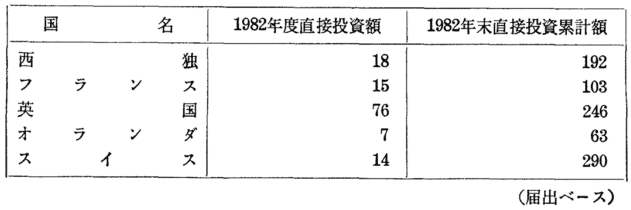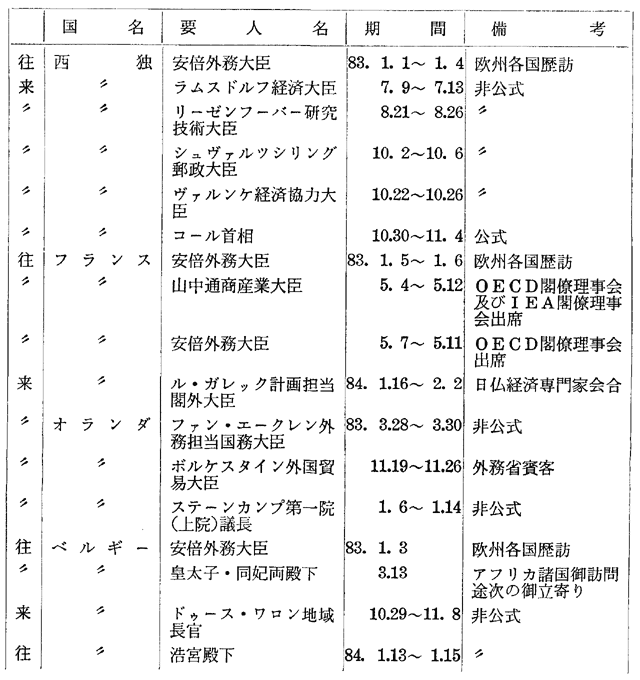
2. 我が国と西欧諸国との関係
(1) 日・西欧関係全般
日欧関係が政治,経済をはじめ各般にわたり緊密化するにつれ,日欧間の交流も増大してきている。特に,我が国が国際社会において果たすべき役割について欧州諸国において認識が深まるにつれて,日欧間の協力,とりわけ政治分野における協議は着実に増大している。
82年にペルティーニ=イタリア大統領,ミッテラン=フランス大統領,サッチャー英国首相をはじめとする西欧諸国からの要人が来日したのに続
いて,83年にはシュルター=デンマーク首相(7月),ヒラリー=アイルランド大統領(9月),コール西独首相(10月)の訪日が実現し,日欧政治対話は更に大きく進展した。
首脳間の交流に加え,外務大臣をはじめとして種々のレベルで協議が行われているほか,国連,OECD等の機会をとらえ更に緊密かつ頻繁に意見交換が行われている。特に,英国,フランス,西独との間では,現下の国際情勢,二国間関係等を巡り・事務次官協議等の高級事務レベルにおいて緊密な協議が行われた。
(2) 日・西欧経済関係
(イ) 83年の我が国の対EC貿易額は輸出入とも増加を示した(輸出は185億2,300万ドル・前年比8.5%増・輸入は81億2,000万ドル,前年比7.4%増)。この結果73年以降81年まで拡大の一途をたどり,82年に初めて縮小を見た我が国の対EC貿易黒字は再び増加し,104億ドルと過去最大となった。
(ロ) 世界経済が回復に向かう中にあって,EC加盟国間の景気回復には跛行性(英,西独の着実な回復,仏等の停滞)が見られ,また,雇用情勢も依然として低迷を続けた。こうした第二次石油ショック以来の経済的困難を背景にEC側は対日貿易不均衡を問題とし,我が国に対し一層の市場開放要求を行うとともにVTR,乗用車等のセンシティブ品目の輸出自粛を継続するよう要求した。
(i) EC側は,我が国特有の経済社会制度がECの対日輸出を阻害しているとして,ガット23条1項協議を申し入れ3回にわたる協議を行ったが,82年12月の外相理事会の決定に基づき,83年4月,ガット理事会に対し,対日貿易不均衡問題に関する日本との協議のガット23条2項協議への移行を求める動きを示した。EC側はその理由として,これがガットの信頼強化に資するものである旨の説明を行った。
これに対し,我が国は,日本としてもガット体制の強化のため一連の市場開放努力をを払ってきており,今後ともECとの対話を継続する用意があるとしつつ,23条2項協議移行については立場を留保する旨を明らかにした。結局,ガット理事会議長は本件については将来の理事会会合で取上げる旨述べ,本件は実質討議が行われないまま「棚上げ」されることとなった。
(ii) 9月,いわゆるエアバス問題により,我が国と仏,西独との間にはぎくしゃくが生じ,また,EC側は,10月のEC外相理事会で,対日関係をレビューした際,日・EC関係が「引き続き不満足かつ不穏な状態」にあるとして重大な懸念を表明した。しかし,EC側は,10月21日に我が国がとった総合経済対策を評価し,これにより,日・EC関係は,一応の小康状態を保ちつつ推移した。
他方,EC側は対日市場開放要求の中で,単にEC産品・製品の輸出拡大を通じて貿易インバランスの縮小を求めるにとどまらず,さらに,金融資本市場の自由化等の分野まで範囲を拡大してきている。
(iii) センシティブ品目の対EC輸出については,EC側は82年に我が国のとった輸出自粛措置をおおむね評価しつつも,乗用車,軽商業車,クォーツ時計,フォークリフト・トラック等の輸出が83年においても前年に比べ大幅に伸びていることを指摘し,84年についても83年と同様の輸出自粛を行うよう要求した。83年11月に訪日したダヴィニヨンEC委副委員長と我が国関係者の協議の結果,VTR等EC側関心10品目につき83年同様,84年分についても日本側が輸出自粛することが合意された。
(ハ) 以上のとおり,日・EC経済関係は,緊張要因をはらみつつ推移したが,他方,日・EC関係をより幅広く緊密なものにすべく,産業協力をはじめとして科学技術,開発援助等の分野での協力の推進が確認された。また,11月ダヴィニヨン副委員長訪日の際,閣僚レベルの交流を深めるため日・EC委閣僚会議の設置につき原則的な合意が見られた。
<要人往来>
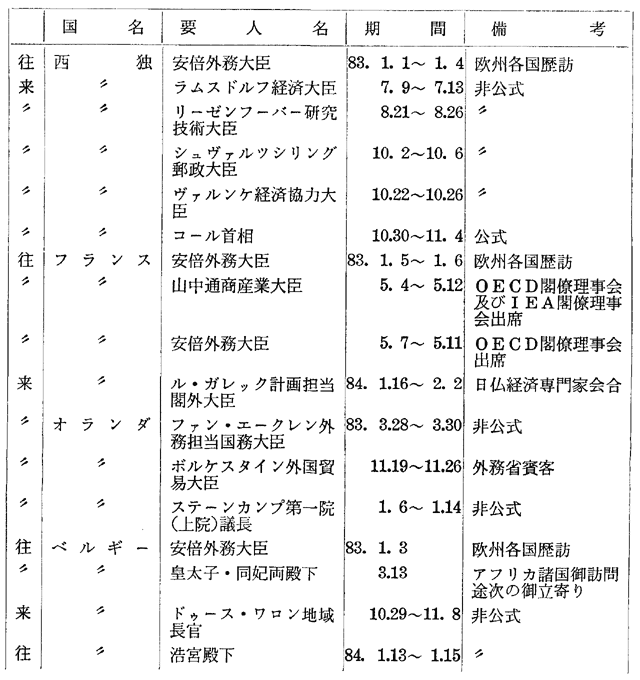
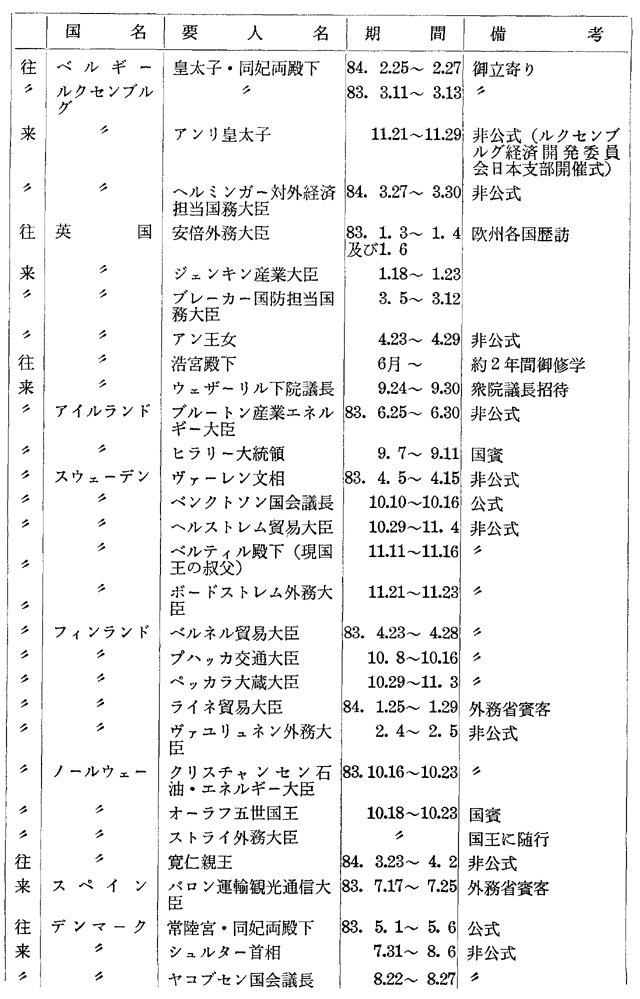

<貿易関係> (1983年,単位:百万ドル,()内は対前年比増加率%)
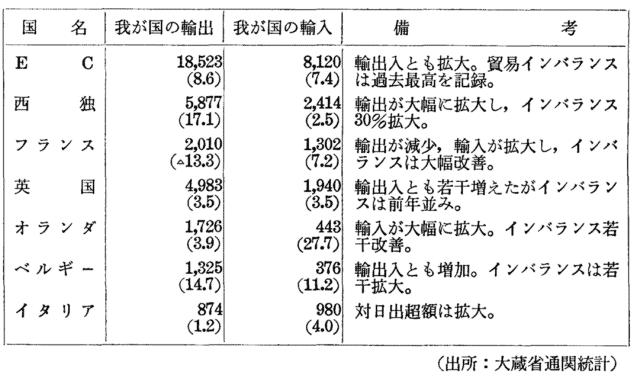
<民間投資>
(あ)我が国の対西欧直接投資(単位:百万ドル)
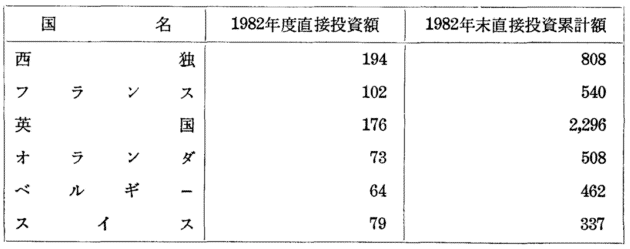
(い)西欧諸国の我が国に対する直接投資(単位:百万ドル)