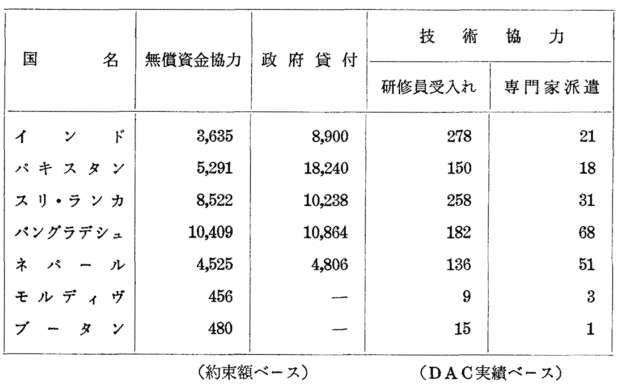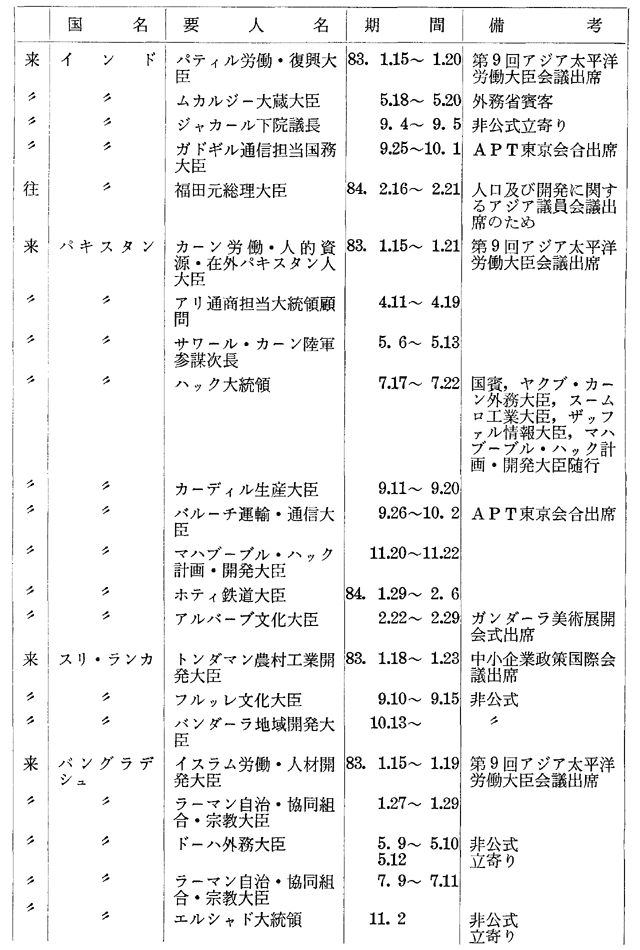
7. 南西アジア地域
(1) 南西アジア地域の内外情勢
(イ) 概要
83年前半,インドとパキスタンとの関係改善の動きが,第1回の印パ合同委員会の開催(6月)となって結実したこと,「南アジア地域協力(SARC)」が初の7か国外相会議によって正式に発足(8月)したこと等同地域の安定に資する動きが見られたが,後半には,スリ・ランカの国内民族対立に起因する騒擾事件の発生・パキスタンのシンド州を中心とする反政府運動,インド・パンジャブ州におけるシーク教徒の自治権拡大運動の先鋭化,バングラデシュの反政府政党の動き等各国とも内政上の困難に直面するようになり,かつ,これらの騒擾に絡んでインドと近隣諸国との間で不協和音が顕在化しているが,いずれも大局的には,それぞれの国の現政権自体を揺るがすほどのものとはなっておらず,全体的には南西アジア地域の安定に重大な影響を及ぼすには至っていない。
(ロ) インド
(a) 内政
83年は,1月に与党コングレス(I)党の伝統的地盤の一つであった南部アンドラ・ブラデシュ及びカルナタカ両州の州議会選挙でコングレス(I)党が敗北したことから,ガンジー首相にとり波乱の幕開けとなったが,2月のデリー特別区の選挙では圧勝して威信を回復した。
3年来続いているアッサム州の「外国人」追放運動は,2月の州議会選挙を契機に多数の死者を出す騒擾事件に発展した。その後小康を保っているものの,依然問題解決の兆しは見えていない。
シーク教徒の自治権拡大運動で揺れるパンジャブ州は,過激派によるテロ活動の続発により,10月には大統領直轄下に置かれ,騒擾地域に指定された。しかしテロ活動は依然あとを断たず,同州の治安状況は目立った回復を示すには至っていない。
(b) 外交
3月,インドは第7回非同盟首脳会議を主催して非同盟運動におけるリーダーとしての地位を固め,また11月には英連邦首脳会議を主催した。
国内に多数のタミル人を抱えるインドは,7月にスリ・ランカで発生したシンハラ,タミル人間の人種暴動に対し,仲介を申し出るなど大きな関心を示した。
ソ連とは,6月にヴェンカタラーマン国防相が訪ソし,また84年3月ウスチノフ国防相が訪印して対印武器供与につき話合われた。特にウスチノフ訪印はチェルネンコ政権成立後いち早く行われたため注目された。
印米間の長年の懸案であったタラプール原子力発電所に対する部品供給問題は,6月のシュルツ国務長官訪印の際原則的に第三国が供給肩代わりすることで,一応の解決を見た。
(c) 経済
83年度の穀物生産は,天候に恵まれたため史上最高の1億4,200万トンが見込まれており,農業生産は9%増,工業生産4.2%増,経済成長率6~7%増と予想されている。しかし物価は再び上昇傾向にあり,84年1月現在の卸売物価上昇率は年率9.7%を記録した。
国際収支は,国内石油の増産,在外インド人によるインド銀行預入れ増等により若干改善を示し,IMFからの借入れを予定していた計50億SDR(81年から3年間)中11億SDRの引出しを取り止めた。12月現在の外貨準備高(金,SDRを除く)は前年の35億ドルに対し43億ドルであった。
(ハ) パキスタン
(a) 内政
ハック政権下の同国内政は安定の度合いを強めつつ83年央まで平穏に推移した。政権担当以来満6年を過ぎた同大統領は,8月に,85年3月までに総選挙を実施し,この結果に基づき民政に移管する旨発表したが,同時に選挙の方法,憲法及び将来の政体につき制限を加えるものであったことから,政党側は即時,無条件の民政移行を要求して全国各地で一斉に反政府運動を展開した。野党連合「民主主義回復運動」の反政府運動自体は平和的手段による不服従運動であり,現政権の基盤に大きな影響を与えるものではなかったが,ブットー前首相の出身州であるシンド州においては,反パンジャブ州感情に基づいた過激な動きが続き,ハック政権にとって大きな試練となった。
このシンド州の騒擾も11月までには完全に鎮静化したが,パ内政の多難な一面を露呈するものであったと言えよう。
(b) 外交
82年にはハック大統領自身,米・中・ソ・印を含む延べ23か国を訪問し,活発な外交活動を展開したが,その後も3月インドにおける非同盟会議に出席,5月ネパール,7月日本,8月トルコ,9月サウディ・アラビア等を訪問し精力的な外交を展開した。
またイラン・イラク紛争,アフガニスタン問題解決のため中東,欧州諸国,米・ソ両国等を精力的に訪問したヤクブ・カーン外相の活躍が目立った。
インドとは,6月に第1回印パ合同委員会が開催され,関係改善の緒についたが,8月以降のシンド州騒擾に言及するガンジー首相はじめインド政府,与党要人の発言が相次ぎ,これを巡り両国間で非難の応酬があり,関係改善の動きは一時中断した。
(c) 経済
82/83年は,農業生産が4.8%増で前年を大きく上回り,小麦の収穫量は1,230万トン(前年の10.6%増),米337万トン(2.7%減),綿花480万ベール(9.8%増)となり,工業は,前年の成長率(11.9%増)を下回ったものの鉄鋼,肥料,セメント,綿糸,精糖等の伸びが大きく8.3%増となり,GNP成長率は6.5%の目標を達成した。
貿易面では,輸出が9.4%増の26億ドルを記録し,輸入が1%減の57億ドルとなったため赤字幅は29億ドル(8%減)となり若干改善された。海外パキスタン人からの本国送金が29億ドルに増えたため総合収支は大きく好転した。
物価上昇率は5%増と前年の12%を大きく下回った。
パキスタンは7月から総額4,980億ルピーで農業,エネルギー,社会インフラ開発を重視する第6次5か年計画に着手した。
他方83年の夏場の雨と,その後の病虫害の影響で綿花は大幅な減産となり,経済全体に影響を与えることが懸念されている。
(ニ) バングラデシュ
(a) 内政
82年3月の軍部によるクーデター以後,主要野党勢力は,次第に民政移管の方法・時期を巡り政府と対決姿勢を強めるとともに,あくまで国会議員選挙を郡議会議長選挙に先立ち実施すべしと主張していたところ,83年11月,反政府座り込みデモを実施しデモ隊と警官隊が衝突,多数の死傷者を出すに至った。この騒擾事件から2週間後の12月11日,突如エルシャド戒厳令司令官は,国政への責任及び民主主義移行のためとして自ら大統領に就任した。
同大統領は上記騒擾事件にもかかわらず,あくまで郡議会議長選挙の先行実施の方針を貫くかに見えたが,84年3月,同郡議会議長選挙を5月27日に予定されている大統領選挙,国会議員選挙が実施されるまで延期する旨を発表した。
(b) 外交
エルシャド大統領は,米国公式訪問をはじめ第6回国連貿易開発会議(UNCTAD)総会,非同盟首脳会議,英連邦首脳会議出席等活発な首脳外交を展開し,またエリザベス英女王やカナダ,タイ,マレイシアの各首相ら要人の訪問が相次いだ。他方対印関係は,国境フェンス問題,ファラッカ問題等を巡り複雑化しており,また,ソ連との関係は,年末のソ連外交官退去処分に伴い低調である。
(c) 経済
82/83年度のGDP成長率は3.8%,食糧穀物生産は史上最高の1,510万トン,外国投資も独立後最大の10億6,000万タカを記録するなど当国経済は比較的好調に推移した。
82/83年度の輸出は,6億8,700万ドルであったが,輸入が23億ドル(前年度25億ドル)にとどまったこと,また,出稼ぎ労働者による海外送金が6億ドル(前年度4億ドル)に増大したこと等のため外貨準備高が6月には3億ドルを記録した。
なお上述のとおり食糧生産そのものは好調であったが,人口増加等のため依然として食糧不足は解消されず,外国から184万トン(82年6月~83年7月)の輸入を余儀なくされた(我が国は83年度KR食糧援助約4万トン,米の延払い45,000トンを供与した)。
(ホ) スリ・ランカ
(a) 内政
ジャヤワルダナ大統領は,82年10月の再選,同年12月の各党の国会議席数を凍結したまま任期を6年間延長するための国民投票での勝利に続き,83年5月の国会議員の補欠選挙と地方都市選挙でも勝利を収め,長期安定政権の基礎を固めた。
他方,北部・東部を根拠地とする少数民族タミル人は,従来同地域の分離独立を主張し,一部過激派は,武力による分離独立を主張しテロ活動を続けてきたが,7月23日,タミル人過激派によるシンハラ人将兵13名殺害を発火点に首都コロンボで,多数民族シンハラ人による報復的なタミル人殺害と,その店舗・住宅・工場等の焼打ち略奪事件が発生し,これが瞬く間に全国に波及し,多数の死者を出す一大民族騒擾事件に発展した。この騒擾事件は一応鎮静化したが,ジャヤワルダナ大統領は,同国の民族問題の根本的解決を図るべく,84年1月から全政党会議を開催した。
(b) 外交
引き続き非同盟路線を堅持している。7月騒擾以前の年前半は・ジャヤワルダナ大統領がインド,イタリア,エジプトを訪問し,マハディール=マレイシア首相,エルシャド=バングラデシュ戒厳令司令官のスリ・ランカ訪問など招待・訪問外交が目立ったが,後半は,7月騒擾事件に関連して,インド及びスリ・ランカの特使の往来,また,ジャヤワルダナ大統領の実弟が大統領特使として,韓国,日本,インドネシア,マレイシア,フィリピン,中国,タイ,シンガポールを訪問し,7月の騒擾事件につき説明するなど,本騒擾事件の後始末に関連する外交が目立った。
(c) 経済
7月の騒擾のため多くの被災民を生み出し,経済活動が一時停滞し,観光業も大きな影響を受けた一方,異常気象による農業不振の結果,実質国内総生産の成長率は,82年の5.1%を下回る4.9%にとどまったものと見られる。物価は,石油価格の値上げ等により,消費者物価指数で18%程度上昇したものと見られる。また,貿易収支の赤字は,工業製品輸出の不調に加え,茶,ゴム,ココナッツの伝統的一次産品の生産量減少により,82年度(9億8,400万ドル)より更に拡大したものと見られる。
(卜) ネパール
(a) 内政
79年以降4年有余続いたタパ内閣は,前年の凶作による食糧危機,汚職問題等の責任をとる形で,7月国会における不信任動議の可決により崩壊,「清潔にして能率的な政府」を看板とするチャンド内閣が成立した。政党なきパンチャーヤット制度下においても政権交替が民主的手続により行われたことは,国王が目指す民主化が一層推進されたものとも考えられ,王制の安定維持に資するものとも言えよう。
(b) 外交
ネパールは非同盟中立,善隣友好外交を標擁している。国王はスペイン,米国を公式訪問,またフランス,パキスタン大統領,タイ首相等が訪問し,活発な首脳外交が展開され,ネパール平和地帯提案に対する支持国も38か国に達した。
(c) 経済
天候に恵まれ農業生産が持ち直し,経済成長にも多少の明るさが見られたが,食糧需要の増加と前年の貿易収支悪化の影響により深刻な外貨不足を招いた。
(ト) モルディヴ
11月に5年の任期満了を迎えるガューム大統領は,8月国民議会から大統領候補の指名を受け,9月30日実施された国民投票で95.6%の圧倒的支持を得て再選された。経済面では,漁業は,国際魚価の低迷もあって伸び悩んだが,観光業の成長と公共投資の増大に支えられ,国内総生産は,対前年比10%増となったと推定される。
対外面では,ガューム大統領の北朝鮮公式訪問(8月),エルシャド=バングラデシュ戒厳令司令官のモルディヴ公式訪問のほか,ソ連(2月)及びシンガポールとの航空協定署名が目立っているが,基本的には,従来の非同盟政策を堅持した。
(チ) ブータン
国内政情は国王と王族を中心とした強力な指導体制下に安定を維持しており,外交面では従来のインド,バングラデシュに加え,新たにネパールと外交関係を樹立し,また世銀,アジア開銀等に加盟,経済開発のための資金調達に努力している。
(2) 我が国と南西アジア諸国との関係
我が国と南西アジア諸国は,伝統的に友好関係を維持してきているが,この1年も,この良好な関係を一層緊密化する動きが見られた。
インドとの間では,5月のムカルジー蔵相の来日,12月の目印貿易協議及び84年3月の目印文化混合委員会を通じて政治・経済・文化面での政府間の対話を深めた。経済関係も順調に推移し,特に鈴木自動車とマルチ社の合弁事業の生産開始に代表されるように自動車部門における両国企業間の提携が進んだ。
パキスタンとの間では,7月にハック大統領が我が国を公式訪問し,両国間の政治対話を深めた。この際,我が国は約300億円の対パキスタン円借款供与を意図表明した。さらに,両国間の協力関係を一層推進するため日本・パキスタン合同委員会を設置することが合意され,同委員会の準備会合が12月にイスラマバードで開催された。8月には我が国国会議員団が,パキスタンを訪問した。
バングラデシュ,ネパール,スリ・ランカなど他の南西アジア諸国との関係も政府,民間の双方で活発な動きが見られた。バングラデシュヘは,11月に秋田衆議院議員が特派大使として訪問し,12月には日・バ商業・経済協力合同委員会が開かれた。ネパールからは,12月にビレンドラ国王が,カトリ外相らと共に米国公式訪問の帰途,我が国に立ち寄り,二国間の友好関係が確認された。スリ・ランカとの間でも,日・ス航空協定交渉ほか経済協力・人物交流等で二国間関係の増進が図られた。
このほか11月には,我が国から投資環境調査団がインド,パキスタン,スリ・ランカの3国を訪れ,今後の我が国投資の可能性を調査した。
<要人往来>
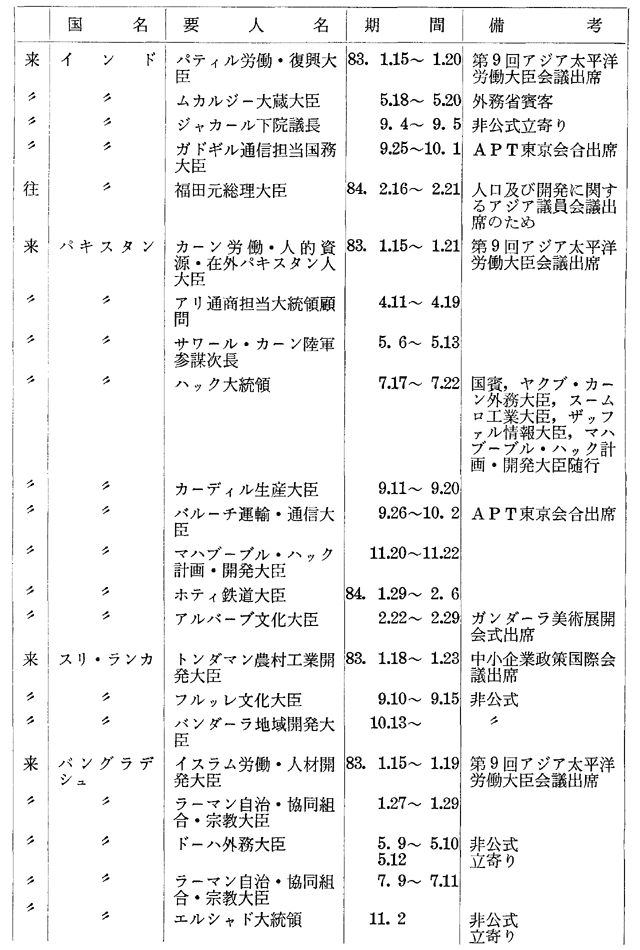
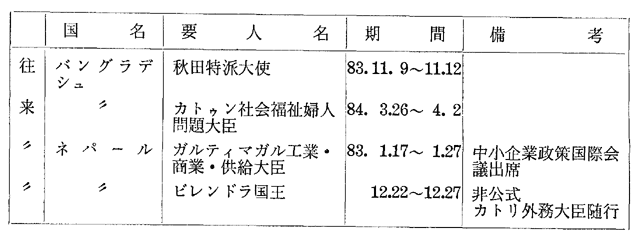
<貿易関係> (1983年,単位:百万ドル,()内対前年比増加率%)
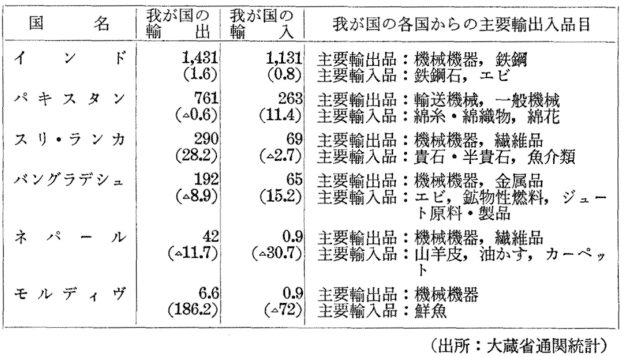
<民間投資> (単位:百万ドル)
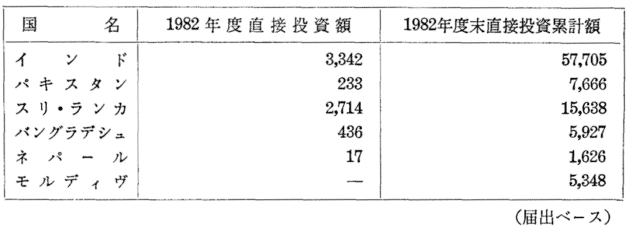
<経済協力(政府開発援助)> (1983年,単位:百万円,人)