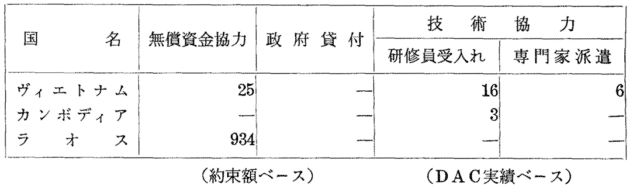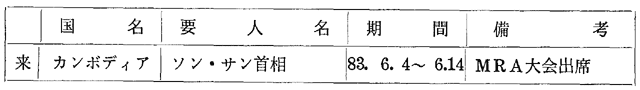
5. インドシナ地域
(1) インドシナ3国の内外情勢
(イ) ヴィエトナム
(a) 内政
(i) 82年3月の第5回党大会以後は党・政府内で主要な人事異動はなく,83年も引き続きレ・ズアン党書記長を頂点とし,これにチュオン・チン国家評議会議長及びファム・ヴァン・ドン首相を加えた三者による集団指導体制が維持された。
(ii) 内政の最大の課題は経済困難の克服と南部の社会主義改造であるが,ヴィエトナムを巡る国際環境が依然厳しい中で,新経済政策の継続,新農業税法の施行及び商工業税法の一部改正(いずれも3月),国債の発行(11月)など経済立て直しのための努力がなされたが,食糧生産を除いては必ずしも計画どおりには進捗しなかった。
(b) 外交
(i) ラオス及びカンボディア(「ヘン・サムリン政権」との特別な関係)とともに,ソ連との協力関係の強化を最重視する外交基本姿勢に変化はなく,レ・ズアン党書記長がソ連邦60周年記念式典への出席(82年12月末~83年1月)及び休養(7~8月)のため同国を訪問し,いずれの訪問でもアンドロポフ書記長と会談した。他方,ソ連からは,ソ越友好協力条約5周年に当たり,10月末にアリエフ党政治局員兼第一副首相を団長とするソ連党・政府代表団が訪越するなど,ハイレベルでの交流が見られた。
(ii) 膠着状況にあるカンボディア問題については,83年もASEAN及び西側諸国に対する対話の働きかけの姿勢が見られた。2月には,初めてのインドシナ3国首脳会議が開かれ,3国間の団結と協力を図るとともに,ASEAN諸国に対し東南アジア地域の平和と安定を呼びかけ,また,米・中国との関係正常化の希望を表明した。4月のインドシナ3国臨時外相会議,7月及び84年1月の第7・8回インドシナ外相会議でもASEAN諸国に対する対話促進の呼びかけが行われたが,カンボディア問題についてのヴィエトナムの基本姿勢に変化は見られず,問題解決の見通しは依然立っていない。また,グエン・コー・タック外相は,6月にフィリピン,タイを訪問したのをはじめ,10月には国連総会出席の帰途,英国,フランス及びマレイシアを,84年3月にはインドネシア,豪州を訪問し,他方,フランス(3月)及び豪州(6月)の各外相がそれぞれヴィエトナムを訪問した。
(iii) 対立関係が続いている中国との関係では,83年にもヴィエトナム側から旧正月及び両国の国慶節に際する国境での敵対行為の停止,中越会談の再会を提案したが,これらは実現せず捕虜・抑留者の交換にとどまった。
(iv) 82年10月,米国との間でヴィエトナム戦争中の行方不明米兵問題につき専門家会合を年4回開催することが合意された後,83年6月の会合を最後に同会合は中断されていたが,84年1月の第8回インドシナ外相会議のコミュニケで,本件につき米側と協力する用意があると発表されたのを受けて,2月,アーミテージ米国防次官補がヴィエトナムを訪問し,専門家会合を再開することが合意された。
(c) 経済情勢
(i) 最重要政策目標である食糧生産は83年,1,695万トン(籾換算)と,同年の計画目標の1,700万トン(同上)のレベルをほぼ達成した。これにより必要最少限ながら食糧自給が可能となった。
工業生産では,小・手工業部門は好調であったが,電力,石炭,セメント等の基幹部門の生産は,82年に比し増加はしたものの,83年計画目標は達成できなかった。
また,輸出は,82年比51%増を目標としていたが,実績は,同17%増にとどまった。
(ii) 政策面では,農業における生産請負制,工業における出来高払い制,各生産単位・地方に対する自主権拡大等の新経済政策は,83年も引き続き一定の成果を挙げたと見られている。
他方,経済管理・運営面では,依然多くの問題点が改善されず,また,各部門の生産性・品質管理の低下,分配・流通分野の混乱,投機行為による自由市場の物価急騰といった諸問題が見られた。
(iii) 南部農業の社会主義改造は,順調に進められているとされているが,集団化率等の数値は発表されていない。
(iv) 12月に開催された国会でヴォー・ヴァン・キエット副首相兼国家計画委員会委員長(党政治局員)は,84年の計画目標を発表した。それによると食糧生産を1,800万トン(籾換算)に増加するとともに,人口増加率を83年の2.4%から84年は1.9~2.0%に引き下げ,引き続き食糧自給の確保を目指し,また,工業総生産を83年比9.5%増とする等の目標が挙げられている。特に,電力48億3,000万kwh(83年比12%増),セメント160万トン(同83%増),繊維3億2,000万m(同23%増),製紙67,000トン(同26%増),肥料40万トン(同67%増)等意欲的な目標となっている。さらに,対外経済関係では,社会主義諸国のみならず,西側諸国及び国際機関との関係を増進し,必要物資の輸入を図ることが必要であり,このため輸出の増進(83年比22%増),運輸・サービス等による外貨獲得に努めることとされている。
(ロ) カンボディア
(a) 内政
82年7月の民主カンボディア連合政府(シハヌーク大統領,キュー・サンパン外務担当副大統領及びソン・サン首相)の樹立に際して,三派間の関係から連合の行末を危倶する向きも多く・現に三派間の不協和音も一時伝えられた。しかしながら,連合政府樹立後1年を経過し,三派間では結束及び協力の強化が図られた。
他方,「ヘン・サムリン政権」は,引き続きヴィエトナムの軍事的支援とソ連,ヴィエトナム,東欧諸国からの経済支援の下に,カンボディアの現状の既成事実化を図ってきている。
なお,民主カンボディア側の軍事活動は,徐々に地域的な広がりを見せてきているものの,ヴィエトナム軍の優勢を揺るがすには至っていない。また,83~84年の乾期にヴィエトナム軍が前年同様民主カンボディア諸勢力に対し攻勢をかけたため,タイ,カンボディア国境地帯の多数のカンボディア難民が再びタイ領に流入した。
(b) 外交
ASEAN諸国は,ヴィエトナムの武力介入を容認せずとの立場からヴィエトナム軍の撤退とカンボディアの民族自決を柱とする「包括的政治解決」を追求し,このASEAN諸国の立場は国際社会の大方の支持を得てきた。82年民主カンボディア連合政府が成立して以来,同政府はASEAN諸国と協力し,シハヌーク大統領を中心に問題の「包括的政治解決」に対する各国の支持獲得のための活発な外交活動を展開し,83年の国連総会でも「包括的政治解決」を求めるカンボディア情勢決議が,前年と同様圧倒的多数で採択された。
他方,ヴィエトナムをはじめとするインドシナ側は,2月のインドシナ首脳会議,4月の臨時外相会議及び7月の外相会議を通し,ヴィエトナム軍の条件付部分撤退,ASEANに対する対話呼びかけ等の提案を繰り返したが,「ヘン・サムリン政権」の存続を前提とする基本姿勢に変化はなかった。これに対しASEAN諸国は,インドシナ側の提案には新味がないとし,6月のASEAN拡大外相会議,9月のASEAN外相共同アピールにより,カンボディア問題の包括的政治解決に関する国連諸決議及び81年7月の「カンボディア国際会議」宣言を基礎としたカンボディア問題の政治解決実現の探求を再確認した。
また,カンボディア問題の背景にある中・越関係については,中国側がヴィエトナムのカンボディアからの撤退を関係正常化の前提としていることもあり,両国間の対話は再開されていない。
(c) 経済
タイ・カンボディア国境に滞留している20~30万人のカンボディア人に対し,引き続き人道的援助が必要とされており,また,「ヘン・サムリン政権」下の地域における経済も,ある程度復興が進んでいるものの,依然食糧自給を達成するには至っておらず,国際機関からの援助に依存している状況にある。
(ハ) ラオス
(a) 内政
83年を通じ大きな動きは見られず,基本的には安定的に推移した。
党及び行政面では,82年に開かれた第3回ラオス人民革命党大会決議を受けて,党基盤の整備・強化策の一環として4月に第1回人民革命青年全国大会が,また,12月に第1回全国労働組合大会が開かれた。行政機構改編も82年に引き続き推進され,地方レベルにまで及んだ。
国防・治安面では,メコン河でタイ側との銃撃事件が発生し(1月及び5月)一時両国間の緊張が懸念されたが無事収拾され,全体としては特段の問題はなかった。他方,農業生産,特に米の生産は天候不順のため減収となり,関係各国,国際機関等に対し食糧援助要請を行った。
(b) 外交
ラオスは従来,外交基本政策としてヴィエトナム,カンボディア(「ヘン・サムリン政権」)との「特別の関係」の強化とソ連をはじめとする社会主義諸国との協力関係の強化を明確にしている。第1回インドシナ3国首脳会議がヴィエンチャンで開催され(2月),3国間の連帯関係の一層の強化が表明され,ヴィエトナム,カンボディア(「ヘン・サムリン政権」)との間で各分野,各レベルにおける代表団の往来等が活発に行われた。
ラオスは,ソ連との全面的協力関係を重視しており,カイソーン党書記長兼首相は,5月及び9月に訪ソした。また,ソ連はラオスに対する最大の経済協力供与国となっており,経済協力関連の代表団の往来も頻繁に行われた。
東欧諸国との間でも,ポーランド外相のラオス訪問(11月),ラオス人民軍代表団の東独訪問(6月)等,順調な関係が続いた。
しかし,中国とは依然として冷たい関係にあり,ラオスは,中国を「米帝国主義と結託した中国拡張主義」として非難し続けた。
隣国タイとの関係は,メコン河での銃撃事件の発生があったものの,双方の努力で収拾され,その後クリアンサック=タイ下院外交委員長のラオス訪問(8月),シーサワット内相のタイ訪問(84年1月)等により貿易を含む両国関係の改善へ向けての努力がなされた。
西側諸国との関係については,米国に対しては,米帝国主義非難の基本姿勢は崩していないが,米国からの行方不明米兵捜索センター(JCRC)代表団の受入れ(2月及び12月)等82年に続き行方不明米兵捜索問題に柔軟な姿勢を示した。
また,7月にヘイドン豪外相のラオス訪問があり,豪・ラオス経済協力関係の継続が確認された。
(c) 経済情勢
第3回党大会で採択された社会・経済開発5か年計画は,3年目に入ったが,最重点目標たる農業生産の向上は天候不順により目標達成に至らず,籾米生産は82年比16%減の約100万トンとなった。
工業生産は対GNP比10%以下と低調であるが,原材料の輸入が順調となり,82年の低落から脱し,回復に向かったものと見られている。
財政は恒常的に大幅赤字となっており,また,国際収支は,貿易収支の改善にもかかわらず,外国援助が減少したため悪化した。
このような経済情勢下,外国援助がラオス経済発展のための大きな鍵であると見られている。
(2) 我が国とインドシナ3国との関係
ヴィエトナムとの間では,依然未解決のカンボディア問題が関係発展の阻害要因となっており,関係は停滞したまま推移しているが,我が国は人道的見地から,12月に台風緊急援助として10万ドルを供与し,また,84年1月,文化面での協力として日本語学習用機材を供与した。同国との貿易については,過去数年にわたり減少していた輸出入ともに83年は回復を示した。
ラオスとの間では,82年のカンパーイ外相臨時代理の訪日を契機に一層の発展を見た友好関係が引き続き維持強化され,我が国の経済協力は着実に増加し,またラオスからの中堅指導者層の訪日があった。
カンボディアとの間では,我が国は引き続き,民主カンボディア連合政府を支持するとともに,国際機関を通じる人道援助を継続した。
また,6月に,我が国で開催されたMRA大会出席のため訪日したソン・サン首相と安倍外務大臣が会談した。
<要人往来>
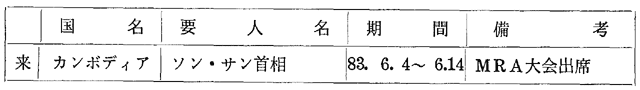
<貿易関係> (1983年,単位:千ドル,()内は対前年比増加率%)
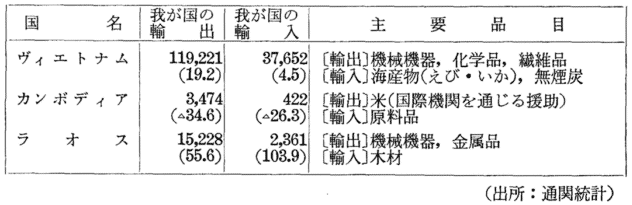
<経済協力(政府開発援助)> (1983年,単位:百万円,人)