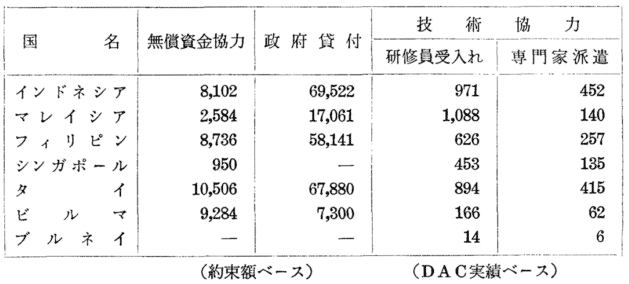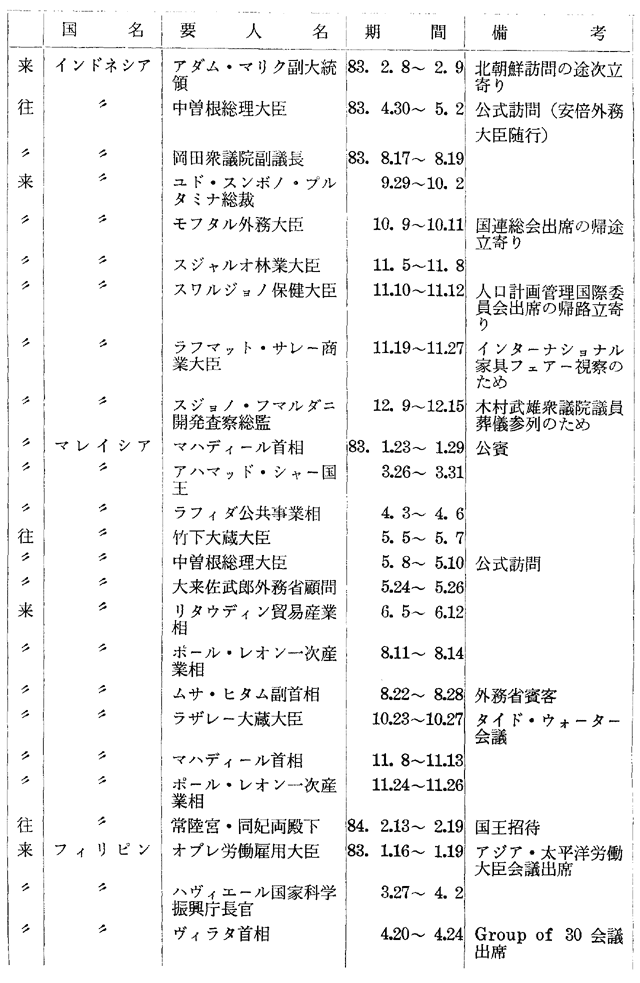
3. 東南アジア諸国連合(ASEAN)6か国及びビルマ
(1) ASEAN6か国及びビルマの内外情勢
(イ) インドネシア
(a) 内政
83年のインドネシア内政は,前年に実施された総選挙の結果を踏まえ,3月上旬の国民協議会総会におけるスハルト大統領及びウマル副大統領の選出,これに引き続く第4次スハルト内閣の組閣,各省庁幹部の大幅な人事異動,8月の国軍の改編と軍首脳部の刷新,10月のゴルカル全国大会の開催等に見られるように,スハルト現政権が今後更に5年間施政を行っていく上での体制固めが行われた点に特色がある。
これら一連のスハルト政権の体制固めの中で,中期的な内政安定の観点から,若手の登用等の世代の交代への準備を進める一方,イデオロギー面での国民意識の統一,クリーンな政府の構築等に意欲的に取り組んでいる。他方,反政府・政府批判分子の動きはほぼ完全に封じられており,また,治安情勢も表面上比較的平穏であって,全体として見れば,インドネシアの内政は今のところ極めて安定していると言える。
4月1日から第4次5か年計画がスタートしたが,同国を取り巻く内外の経済環境は厳しく,経済的不況が長期化すれば社会不安や治安の悪化を招く可能性もある。したがって,現下の経済的困難をいかに克服するかが,政治的社会的安定を維持する上で大きな課題となろう。
(b) 外交
83年は,ASEANとの連帯,西側諸国との協調,非同盟・自主・積極外交といった従来の基本路線を踏襲しつつ,対外関係の多角化が図られた。カナダ外相(1月),西独大統領(3月),西サモア首相(11月),デンマーク外相(84年1月)ら要人のほか,東側諸国からも,ユーゴースラヴィア連邦幹部会議長(2月),ポーランド外相(11月)らの訪問が相次いだ。また,非同盟諸国との関係では,第1回非同盟諸国情報大臣会議がジャカルタで開催された。
対米関係では,11月に予定されていたレーガン米大統領の訪問が延期になったものの,両国の友好関係に変化は認められなかった。他方,ソ連とは,外務次官の訪イ(2月)にもかかわらず依然冷却した状態が続いた。なお,中国との国交正常化には,依然として慎重な態度が維持されている。
83年には,豪州,PNGなど近隣国との関係では一時緊張が高まった。豪労働党政権誕生(3月)に伴い,同政権の外交姿勢との関連で意見の齟齬が見られたが,豪外相(4月及び11月),豪首相(6月)の訪問により調整された。対PNG関係では,首相の訪イ(12月)などを通じ緊密な関係構築に向かっていたが,両国国境付近での反乱分子等の活動もあり一時緊迫した。
注目される動きとして,インドネシアはASEAN常任委員会議長国としての立場から,84年初頭,東南アジア地域の平和と安定に積極的な外交活動を展開し,国軍総司令官の訪越(1月),第1回イ越セミナーの開催(2月),カンボディア連合政府大統領の訪イ招待(3月),民主カンボディア政府首相の訪イ(3月),越外相の訪イ招待(3月)などが実施された。
(c) 経済情勢
(i) 83年当初は,前年の石油減産に引き続く石油価格の下落,輸出の低迷,天候不順による農業生産の不振等により,経済の前途はかなり暗いものがあったが,インドネシア政府は,緊縮予算の策定,ルピアの大幅切下げ,主要プロジェクトの繰延べ,金融統制の緩和,税制の整備等の一連の経済建直しを図ったこともあり,83年半ばから経済は徐々に上向きに転ずる兆候が見られた。
(ii) しかし,83年の経済全般の実績は依然低調であり,経済成長率も前年の4.2%程度にとどまったものと見られる。物価上昇率は,ルピアの切下げや3年連続の国内石油製品価格の値上げにもかかわらず,11.5%にとどまった。
(iii) 83年の石油生産は,前年の日産133万7,000バーレルから140万バーレルを超える水準にまで増加したが,価格がバーレル当たり5ドル引き下げられたため,石油輸出額も対前年比12.5%の減少となった。
(iv) 83年の総輸出額は前年比5.3%減となったが,非石油・ガス産品は同27.4%の増加を示した。貿易収支は48億ドルの黒字となった。また,83年度の経常収支赤字は47億ドルにまで縮小し,総合収支も21億ドルの黒字となる見込みである。なお,公的外貨準備高は一時30億ドル台まで減少したものの83年度末で48億ドルにまで回復したと見られる。
(ロ) マレイシア
(a) 内政
83年は,マハディール首相が81年の政権担当以来初めて試練に直面した年であった。年前半は一部閣僚の辞職等に伴う小規模な内閣改造(6月)を除き特筆すべき動きはなく比較的平穏に推移したが,8月以来約6か月にわたって国王の権限に関する憲法改正問題が内政上最大の争点となった。内閣改造では,運輸大臣にチョン・ホン・ニャン,文化・青年・スポーツ大臣にアンワル・イブヒム,保健大臣にチン・ホン・ニャン,連邦区大臣にアブドル・サマッド,総理府大臣にオンキリが横滑り又は昇格して起用された。
非常事態を発布する権限及び法律の裁可権についての国王の権限を縮小する憲法改正案が8月国会を通過したが,右改正について国王及びサルタン側の同意が得られず,政府側との間で長い間論争が行われた。84年1月双方の間でようやく妥協が成立し,前者については,従来どおり国王に権限を残し,後者の法律裁可権については,国王の権限を一部制限する形で解決が図られた。
なお,現在の第7代国王は84年4月に5年間の任期が終了するが,84年2月サルタン会議でジョホール州サルタンが第8代国王に選出された。
(b) 外交
83年も,従来の外交政策の基本路線であるASEAN諸国との協力強化,イスラム諸国との協力,非同盟中立,自由主義諸国との協力を踏襲しつつ積極的に展開された。
ASEAN協力では,引き続きカンボディア問題に対して主要な関心が払われた。特にタイ,シンガポール外相の訪マ(2月),ニューデリーにおけるガザリ外相・コータック=ヴィエトナム外相会談,ソンサン=カンボディア連合政府首相(3月),シティ=タイ外相(6月),スハルト=インドネシア大統領(12月),プレム=タイ首相,シハヌーク=カンボディア連合政府大統領(84年2月)がそれぞれマレイシア訪問,ブルネイ独立式典(84年3月)等の機会を利用して関係国首脳の間でカンボディア問題解決に向けて意見を交換した。
イスラム諸国との間では,5月のアジア太平洋地域パレスチナ問題国際会議でホスト国としてクアラ・ルンプール宣言採択のため主導的役割を果たし,8月ジュネーヴで開かれた国際会議にはガザリ外相を派遣するなどパレスチナ問題に対して積極的な関心を示した。また,フセイン・ジョルダン国王が9月訪問したほか,中東和平に関連し種々のイスラエル非難声明が発出された。
対米関係では,従来両国関係をギクシャクさせる要因となっていた米国のスズ放出問題が解決するなど,関係改善の兆しが見られ,84年1月にはマハディール首相の初めての訪米が実現した。ソ連,中国との関係は現状維持で特に目立った動きは見られなかった。
英国との関係は,「東方政策」の裏返しとして冷却していたが,3月のマハディール首相訪英,在英マレイシア人留学生問題の解決,英国産品に対する差別的取扱いの停止等により改善されつつある。
なお,マハディール首相はこのほか日本(1月),バングラデシュ,モルディヴ(4月),ユーゴースラヴィア,トルコ,ルーマニア(5月),韓国(8月),カナダ,フランス,スイス(84年1月),パキスタン(3月)の各国を訪問した。
(c) 経済情勢
83年のマレイシア経済は,実質GNP成長3.2%と近年にない低成長に終わった(76~80年平均8.4%)。低水準の輸出と公共支出の削減が主な成長率低下の要因となった。対外貿易に大幅に依存する同国経済にとって輸出不振の影響は大きいが,81,82年と続いた貿易赤字は83年に黒字に転化する等若干の回復を示した。81年から開始された第4次5か年計画は,83年以来中間見直しが行われていたが,84年3月,政府支出削減の必要性,民間部門の役割の拡大等を内容とする中間報告書が発表された。
(ハ) フィリピン
(a) 内政
8月21日のアキノ元上院議員の暗殺事件は,それまで比較的平穏な展開を示していたフィリピンの政治情勢を大きく変え,マルコス政権は,18年目にして最大の試練を迎えた。
アキノ暗殺事件以後野党,財界人などからマルコス大統領退陣及び各種民主化措置を求める声が高まり,一時期はメトロ・マニラを中心に反政府デモが頻発した。しかし,マルコス大統領が健康を回復していくとともにアキノ事件調査委員会の中立化,選挙法の改正,副大統領制導入のための憲法改正を通じて譲歩の姿勢を示したこと等により,84年に入り,政情は小康状態となった。
一方,アグラヴァ元控訴裁判所判事の率いるアキノ暗殺事件調査委員会では,連日のごとく公聴会を開き,精力的に調査活動を行ってきている。
(b) 外交
83年前半は,要人の訪問が盛んで,トルドー=カナダ首相(1月),ヘイドン豪外相(4月),中曽根総理大臣(5月),シティ=タイ外相(5月),ラマダーン=イラク第一副首相(5月),コー・タック=ヴィエトナム外相(6月),チッ・フライン=ビルマ外相(8月)がフィリピンを訪問したが,アキノ暗殺事件以後は外国要人の訪問はほとんど途絶えた。
83年後半,フィリピン政府は政治・経済の安定化のために忙殺され積極的な外交を展開し得なかったが,83年全体としては,対米友好協力,ASEANとの連帯,西側先進国・中東諸国との貿易経済関係緊密化,東側諸国・第三世界との関係促進という外交の基調は維持された。
フィリピンの対外関係の基軸である対米関係については,6月に,比米基地協定の改訂により,84~89年の5年間に米国が9億ドルの経済・軍事援助を行うことが合意された。11月に予定されていたレーガン米大統領の訪比が延期されたが,比米関係の基調には悪影響は生じなかった。
ソ連との関係では,4月にソ連外務次官が訪比した際,文化協定に基づく83,84年の文化交流実施計画が合意された。その後間もなくソ連最高会議代表が訪比するとともに11月には,スポーツ交流に関する取決めがソ連閣僚会議体操スポーツ委員会とフィリピン・オリンピック委員会との間で締結された。
中国とは,84年1月のイメルダ夫人の訪中の際に,中国側からフィリピンヘの信用供与の意図表明がなされ,また貿易に関する了解覚書を締結するなどの動きが見られた。
また,17年にわたり外相としてフィリピン外交の中心的役割を果たし,国連でも創設当時からの貢献者として多大な尊敬を集めてきたロムロ外相が高齢と健康を理由に84年1月14日の同人の85歳の誕生日をもって,外相職を去った。
(c) 経済情勢
83年のフィリピン経済は世界経済回復の兆し,一次産品価格上昇の気配,原油価格の低落等から,貿易収支を中心に好転が期待されたが,83年前半顕著な改善は見られなかった。このため政府は6月にペソの切下げ(7.2%)を実施したほか,一連の輸入制限措置を講じるなど一層の努力を払ったが,8月以降の大統領の病気悪化説とアキノ事件を契機とする政情の動揺から一挙に経済危機,とりわけ資本逃避等による金融危機へと発展することとなった。
この結果,外貨準備が激減し,10月以降は,ペソの再切下げ(21.4%)を実施したのに続き,パリ・クラブの開催要請及び主要債権銀行に対する債務返済凍結要請を余儀なくされた。一方,IMFに対しては,6億1,500万SDRに上るスタンド・バイ・クレディットの供与を要請したが,右合意は84年に持ち越された。
このほか政府は,懸命の自助努力を行い,金融の引締め,財政緊縮に努めるとともに徹底的な輸入抑制を図るためL/C開設を中銀自ら規制し,食糧,肥料,石油等必要物資以外の輸入には外貨割当てを一時的に停止するなどの措置をとった。しかし,これらの結果,国民生活を圧迫しインフレ上昇,企業,工場の操業短縮・閉鎖及びその結果としての一時的解雇,失業等の事態が発生している。
(ニ) シンガポール
(a) 内政
83年もリー首相の率いる人民行動党(PAP)による事実上の一党支配(野党議員は1名のみ)という枠組みに全く揺らぎは見られなかった。しかし,10月のホン蔵相の急逝に伴い,リー首相をはじめ政府要人は折に触れ総選挙が近くなることがあり得る旨を示唆しているが,過去の例から言っても,国会議員の5年の任期を約1年残した時点で国会が解散されていることから,84年のうちに総選挙が行われる可能性は高いと見られている。
ここ数年来,シンガポール内政の重要課題の一つとなっている次代指導者の育成に関しては,後継候補者グループの一員であったリム・チー・オン無任所相が4月に突如失脚し,これによりトニー・タン商工相兼蔵相,ゴー・チョク・トン国防相,オン・テン・チョン無任所相の3名が,リー首相後継者として有力となったと言われている。他方,9月にはヨー・ニン・ホン(国防担当)国務相及びジャヤクマール(内務法務担当)国務相が,代行という名目であっても,それぞれ閣内相に抜てきされるなど,いわゆる第三世代の台頭も急速に進んでいる。
なお,唯一の野党議員としてジャヤラトナム書記長を国会に出している労働者党(WP)は,党経理に関し不正を働いたとのかどで同書記長及び同党議長が起訴されるなど(84年1月地裁で一部有罪判決),多難な道を歩んでいるほか,その他の野党は依然として弱体であるとされている。
(b) 外交
シンガポールは,国際情勢全般についてはソ連の勢力拡張を主因とする東西間の緊張が存し,アジアでは米ソ両大国に中国を加えた三極による勢力争いが展開されているとの厳しい現実認識に立脚して外交を展開している。
83年のシンガポール外交は,ASEAN協調を最優先とするなどの従来の方針を堅持しながらも,82年に見られた活発な外交的展開(ASEAN議長国としての活動及びリー首相の諸外国訪問)に比して若干控え目なものとなった。
具体的には,ラジャラトナム副首相とダナバラン外相の非同盟首脳会議(3月)や国連総会(9月)出席,リー首相の英連邦首脳会議(11月)出席等,定例的な場での活動ははあったものの,これらを除けば中曽根総理大臣(5月)をはじめとする諸外国要人の訪問受入れに終始した。
この背景としては,他のASEAN諸国がそれぞれ内政問題を抱えている状況にあって事態を静観せざるを得なかったこと,従来シンガポール外交に大きな発言力を持っていたラジャラトナム副首相が10月以降病床にあったことのほか,経済面との関連で,83年は内外の諸情勢の帰趨をよく見極める必要があったばかりか,国内における諸般の環境作りに多忙であった等の事情によるものと考えられる。
(c) 経済情勢
83年のシンガポール経済は,第1四半期において,世界経済の低迷下で輸出不振からくる製造業の落ち込み等により,5.5%という最近にない低い成長率を記録した。このため政府は,住宅建設を中心とする建設工事の大幅な増資等,内需を中心とする景気の維持に努め,そのかいもあって,第2四半期に7.2%の成長率にまで持ち直した。第3四半期に入り,米国の景気回復後,先進諸国経済に回復の兆しが見え始めるとともに,輸出が順調な回復を見せたほか,市場環境の好転に伴って電気機器,エレクトロニクス,石油関連等を中心に製造業も立ち直りを見せ,成長率7.9%の水準にまで高まった。さらに第4四半期も伸張を続け,シンガポール経済の83年全体の実質成長率は7.9%に達し,前年の6.3%を大きく上回った。
80年代に向けての産業構造高度化政策の指標としてシンガポール政府が着目している労働生産性上昇率は,82年の1.2%を大幅に上回って,83年には生6%以上となる見込みである。なお物価は,原油価格の値下がりと一次産品価格の低迷等を主因として,卸売物価,消費者物価ともに極めて安定している。また,雇用は,外国人労働者の締出し政策や生産活動の活発化等が原因となって逼迫気味に推移してきており,ほぼ完全雇用が達成されている。
(ホ) タイ
(a) 内政
83年前半アーティット陸軍司令官が改憲を審議するため国会開会を支持するとの発言を行ったことを契機に,国会開会後,3月の憲法改正案(上院の権限維持及び公務員の閣僚兼任等を規定)の否決,その直後の下院解散,4月の総選挙実施と政局は大きく揺れ動いた。総選挙では,軍の支持を受けていたサイアム民主党など少数政党が伸び悩み,改憲に反対した社会行動党,タイ国民党及び民主党の主要政党に議席が集中する結果となった。
また,選挙後,一部少数政党を合併吸収して第1党となったタイ国民党が政権担当に意欲を示したが,軍・王室の支持を得られず,選挙には不出馬のプレム首相が結局再任され,5月7日,社会行動党,民主党,タイ人民党及び国家民主党の4党連立による第4次プレム内閣が成立した。
その後の政局は,年初来の一連の動きで改憲に失敗した軍部がその後,直接的な政治介入に慎重な態度をとり,また,下院における与党勢力が234議席中208議席の絶対多数を占めたこともあって,一部与党の内部対立や下野したタイ国民党による種々の政府批判の動きはあったものの,安定的に推移した。
また,10月軍の定期異動でアーティット陸軍司令官が国軍最高司令官をも兼任することとなり,同司令官は,名実共に軍の第一人者の地位を固めた。
その他の動きとしては,前年大幅な退潮を余儀なくされたタイ共産党は,83年も引き続き大量の投降が続き,その勢力は更に縮小した。
(b) 外交
83年の最重点課題は,引き続きカンボディア問題であった。
タイは,前年に成立した民主カンボディア連合政府に対し側面的支援を与える一方,ヴィエトナムに対しては,在カンボディア・ヴィエトナム軍がタイ・カンボディア国境地帯から30km撤退すればシティ=タイ外相がヴィエトナムを訪問する用意があるとのいわゆる「シティ提案」を行って問題解決の糸口を探る姿勢を示したが,同提案はヴィエトナムの受け入れるところとはならなかった。
タイは,また,日米をはじめとする西欧諸国との関係強化を引き続き重点政策とし,トルドー=カナダ首相及びティンデマンス=ベルギー外相(1月),ヘイドン豪外相(4月),ホーク豪首相(11月)がタイを訪問し,タイからはシティ外相がベルギー(7月),米国(12月)を訪問するなど要人の往来が活発に行われた。
近年良好な関係が維持されてきている中国との間では,楊得志総参謀長(1月),呉学謙外相(7月)等の訪タイ等があり,それらの機会を通じ中国の対タイ支援が改めて明らかにされた。
隣国ラオスとの間では,5月,メコン河での銃撃事件が発生したが,事態は拡大することなく収拾され,クリアンサック前首相一行の訪問(8月)などを通じその後関係改善のための努力がなされた。
ソ連との間では,スパイ容疑によるソ連外交官の国外追放事件(5月),タイ人旅客も犠牲となった大韓航空機事件(9月)があったものの,ソ連に対する非難は控え目なものにおさえられた。
なお,8月,プレム首相は,タイ首相として初めて南西アジア諸国を訪問した。
(c) 経済情勢
83年のタイ経済は,農業部門における年全体を通じての生産増(前年比2.6%増),農産物価格の上昇に伴う農家世帯の所得・購買力の増加と民間投資の増加(対前年比20%増)を主因とする景気回復により,82年の4.1%を大きく上回る6.0%の実質成長率を記録した。しかし,このような内需中心の景気回復を反映して原料・半製品,資本財,輸送機械の輸入が増加し,輸入総額は前年比21.6%増となった。他方,年前半の農業生産の不振を反映して農産物の輸出余力が減少したのをはじめ,工業製品の輸出も減少し,輸出総額は前年比7.1%の落込みとなり,この結果,貿易赤字幅は,82年の15.7億ドルから38.7億ドルに大幅拡大した。また,資本収支も,年央以降資本流入に鈍化が見られ,総合収支は82年の1.4億ドルの黒字から7.9億ドルの赤字に転じた。
さらに財政面では83年度12億4,000万ドルの財政赤字を抱え,11月末一連の税制改正を行う一方,84年度歳出規模を前年度比8.5%増に抑制した。
エネルギー面では,82年央以降供給不足問題が生じていたシャム湾北側のエラワン鉱区の天然ガス埋蔵量につき8月当初推定の4割程度の数字が公表された。
(ヘ) ブルネイ
(a) 内政
ブルネイ(正式国名「ブルネイ・ダルサラーム国」)は84年1月1日に英国から完全独立し,2月23日,独立記念式典が挙行された。同国政府は内政面で新生独立国家としての体制作りを推進している。
ブルネイの国政は,世襲制のサルタンが,憲法に定められた5種類の会議体,すなわち,宗教会議,枢密院,政府閣僚会議(内閣に相当),立法議会(国会に相当)及び王位継承会議からの補佐若しくは助言を得て運営されており,立憲君主制をその基本政体としている。なお立法会議のメンバーには,かつて公選議員も参加していたが,70年4月に選挙が取りやめられて以来現在に至っており,ブルネイにおける今後の議会民主化等の動きが注目される。
ブルネイの内政は,豊富な石油と天然ガスの生産による高い経済水準を背景に安定しているが,石油資源が21世紀初めには枯渇するのではないかとの見方もあり,石油資源依存一本への危険性から脱却すべく,各種産業の育成をはじめとする国造りの施策が検討されている。
(b) 外交
83年末まで英国が外交について責任を持っていたこともあり,政府外交機関の整備,外交官養成等体制作りが現在焦眉の急となっている。ブルネイは84年1月1日の完全独立後直ちに英連邦(1月1日),ASEAN(1月7日),イスラム会議機構(1月14日)に加盟し,これら諸国,米国及び我が国との関係緊密化を図っている。
ブルネイには,英国との防衛取極に基づき英国軍(グルカ兵1個大隊約950人)が駐留しており,また,石油・天然ガス生産はシェルとの合弁事業により,行っている。ブルネイの海外資産運用につき英国クラウン・エージェントの撤退(8月)等ブルネイの英国離れの動きもあるが,ブルネイは完全独立と同時に第49番目の英連邦加盟国となり,84年2月23日の独立記念式典には英国からチャールズ皇太子が出席,英国とは引き続き緊密な関係を維持している。
ブルネイは完全独立後ASEANの第6番目の加盟国となった。ブルネイはASEAN加盟を既定路線として81年から毎年ASEAN外相会議にモハメッド現外相(国王の弟)がオブザーバーとして参加してきた。ASEAN加盟各国との関係についても,英連邦国であるマレイシアとシンガポールには以前から弁務官事務所を設置していたが,83年後半からはインドネシア,タイ,フィリピンにも政府事務所を開設し,関係緊密化に努めている。独立記念式典にはASEAN5か国首脳(スハルト=インドネシア大統領,マルコス=フィリピン大統領,リー・クアン・ユーコシンガポール首相,マハディール=マレイシア首相,プレム=タイ首相)がそろって出席した。
84年1月,ハサナル・ボルキア国王はイスラム首脳会議に出席のためモロッコを訪問したほか,3月にはマレイシア,4月には我が国を訪問し,引き続き韓国を訪問するなど積極的に首脳外交を展開している。
84年2月24日国連安保理は,ブルネイの国連加盟承認を総会に勧告する決議案を全会一致で採択した(秋の国連総会において国連加盟が実現する見込み)。
(c) 経済情勢
経済活動の中心は石油及び天然ガスであり,これらからの収入により高い所得(81年一人当たり国民所得はアジア第1位で17,380ドル)を維持している。石油の生産,販売には,ブルネイ・シェル石油会社が当たっている。石油需給緩和の影響で,3月原油価格を5ドル/B値下げ(84年4月現在30.1ドル/B)し,生産量も80年以降減少している(83年の生産量155,000B/D)。天然ガスは南西アンパ油田から長期契約に基づきブルネイLNG会社により年約500万トン生産され,全量我が国へ輸出される。外貨準備は,その増勢が鈍化しているものの,83年末には約120億ドルに達したと見られる。その資産運用には,8月にブルネイ投資庁を設立,従来の英系金融機関に加え,日,米の金融機関にも委託するなど運用先の多様化を図っている。
(ト) ビルマ
(a) 内政
5月,国家評議会委員,ビルマ社会主義計画党副総書記の要職にあったティン・ウー准将が,ボ・ニー内務宗務大臣と共に解任された。同准将は,ネ・ウィン党総裁の大統領辞任後のサン・ユ大統領を中心とする集団指導体制の一翼を担う実力者であったが,11月,公金流用等の罪で終身刑の判決を受け,その政治生命は完全に断たれた。
10月,ラングーン市内殉難者廟で訪問中の全斗煥韓国大統領一行のうち閣僚4名を含む多数が死亡する爆弾テロ事件が発生し,ビルマ国内に強い衝撃を与えたものの,現政権の安定に影響を与えることとはならなかった。また,同月,カレン州パアン市において,KNU(カレン国民同盟)反乱軍がフランス人技術者夫妻を誘拐する事件が発生した。夫妻は,11月釈放されたが,ビルマ政府軍は,84年1月からKNU反乱軍の大規模な掃討作戦を実施し,反乱軍の重要拠点2か所を占領したと報じられている。
(b) 外交
83年は,年初来,ユーゴースラヴィアのスタンボリッチ幹部会議長(2月),安倍外務大臣(3月),バングラデシュのエルシャド戒厳令司令官(5月)の来訪があり,また,ビルマ側からは,チッ・フライン外相のマレイシア,フィリピン訪問(8月),サン・ユ大統領のハンガリー訪問(9月)等が行われ,ビルマの対外関係は,平穏裏に推移しつつあった。
10月に発生した韓国大統領一行に対するテロ事件は,ビルマ外交に大きな試練を与えたが,ビルマ政府は,11月,綿密な調査の結果,同事件を北朝鮮政府の指示に基づく犯行と断定し,北朝鮮との外交関係断絶という厳しい措置をとることにより難局を切り抜けた。
年後半も,チッ・フライン外相の英国訪問(11月),また,ヘイドン豪外相(11月),呉学謙中国外交部長及びシュトロウガル=チェッコスロヴァキア首相(84年2月)等がビルマを訪問しており,ビルマの厳正非同盟中立路線に変化の動きは見られなかった。
(c) 経済情勢
83年度の実質経済成長率は,5.6%(暫定値)に達し,当初目標(5.0%)を上回った。しかし,主要輸出品である米・木材を中心とする一次産品の国際価格が前年度に引き続き低迷したほか,原油生産量の停滞も続き,外貨準備高が大幅に減少した。こうした事態に対処するため,ビルマ政府は,8月,IMFから2,915万SDRの輸出所得変動補償融資を受け入れたほか,消費物資の輸入引締めを実施している。
(2) 我が国とASEAN6か国及びビルマとの関係
(イ) インドネシア
我が国との関係は,貿易,投資,経済協力及び文化交流の増進,要人の往来の活発化を通じ緊密の度を加えている。4月から5月にかけて,中曽根総理大臣がASEAN諸国歴訪の第一歩としてインドネシアを訪問し,両国首脳間の個人的友情関係の構築と両国間の友好・協力関係の一層の強化が図られた。また,この機会に,改めて我が国の防衛政策につき説明が行われ,スハルト大統領はこれに理解を示した。
また,我が国はインドネシアにとり,引き続き貿易,投資の面で最大の相手国であり,経済協力の分野でも最大の援助国となっている。
(ロ) マレイシア
5月の中曽根総理大臣の訪問,マハディール首相の2回(1月及び11月)にわたる訪日,アハマド・シャー国王(3月),ムサ・ヒタム副首相(8月)等の相互訪問を通じ「東方政策」を軸に緊密化している両国関係には,一層の進展が見られた。「東方政策」に基づくマレイシアからの産業技術研修生第2陣226名(4月),第3陣192名(10月)の受入れが順調に行われ,留学生第1陣の約40名は2年間の予備教育を終えて84年4月来日が予定されている。
経済協力では,1月マハディール首相訪日時に約束された210億円の円借款と500億円の直接借款の供与について実施上の手続がとられた。貿易関係は,我が国はマレイシアにとって引き続き第1の貿易相手国であり,貿易収支はマレイシアにとって若干(3億6,000万ドル)の黒字を維持しており,83年から開始されたLNGの対日輸出により更に改善されることが期待される。
民間レベルの経済交流に関連して,11月マレイシアに日本人商工会議所が設立され,84年3月第7回目・マ経済協議会合同会議がクアラ・ルンプールで開催された。
(ハ) フィリピン
ASEANの中で我が国の最も近くに位置するフィリピンとの関係は,広範な分野で年々緊密化の度合いを深めている。5月の中曽根総理大臣の訪問は,両国首脳の信頼関係を一層高めた。
しかし,フィリピンは,8月のアキノ暗殺事件後の政情不安から,金融,経済危機に直面し,徹底的な輸入抑制を図ったため,日系企業をはじめとする現地企業の中には部品,原材料等を輸入できず,操業停止や操業短縮に追い込まれた企業も出た。
我が国は,フィリピンにとり,米国と1,2位を争う最大の貿易相手国であるが,83年貿易収支は我が国の4億4,000万ドルの出超となり,出超幅は82年より拡大している。
(ニ) シンガポール
シンガポールと我が国との関係は,シンガポールが広い分野で我が国の経験から学びとろうとする姿勢を示していることもあり,単に貿易や投資等の経済分野だけでなく,社会及び文化等極めて広範な分野で緊密な協力関係が発展してきている。我が国として,このシンガポールの期待にこたえるべく,日シ技術学院の設立,日シ・ソフトウェア技術研修センター及びシンガポール生産性向上プロジェクトの継続,並びにシンガポール大学への電子顕微鏡供与及びシンガポール科学博物館への展示機材供与など積極的な協力を進めている。
我が国は,同国にとってマレイシアに次ぐ貿易相手国となっているが,我が国の対シ輸入が前年に比べかなり減少したため,我が国の83年度出超幅は拡大した。
(ホ) タイ
83年は,皇太子・同妃両殿下(3月),中曽根総理大臣(5月)及び安倍外務大臣(6月)等の訪タイが実現する一方,タイからはシリントーン王女(10月)が初めて訪日して両国の相互理解増進に大きく貢献した。また,我が国の経済協力も引き続き積極的に行われた。
両国間の懸案である貿易不均衡については,タイの景気回復を反映して対日輸入が増加した反面,年前半における農業生産の不振により対日輸出が減少したことにより,赤字幅が大幅に拡大した。
(へ) ブルネイ
我が国は,ブルネイが我が国にとって重要な資源(石油及び天然ガス)供給国であり,地理的にも東南アジアで枢要な位置にある国であることから,その完全独立前から,政府レベルでの友好協力関係増進を図ってきた。
3月に外務省から技術協力総合ミッションが派遣されたのをはじめ,5月には中曽根総理大臣がブルネイを訪問してサルタンとの間で会談を行い,我が国の協力姿勢が宣明された。これを受けて,我が国は研修員の受入れ及び専門家の派遣等によりブルネイの国造りのための協力を積極的に行うとともに,文化・スポーツ面の人的交流も推進している。84年4月にはハサナル・ボルキア国王の国賓訪日も実現した。
我が国はブルネイの最大の貿易相手国(輸出入ともに第1位)となっており,ブルネイ産原油の約5割,液化天然ガス(LNG)のほぼ全量が我が国へ輸出されており,貿易収支は我が国の大幅入超となっている。
(ト) ビルマ
83年,ビルマからトゥン・ティン副首相兼計画財務相(5月),キン・マウン・ジィ貿易相(6~7月)及び人民議会代表団(7月)が訪日し,我が国からは,安倍外務大臣(3月)及び鈴木前総理大臣(7月)が訪問するなど,両国関係は,引き続き着実に進展した。我が国は,83年も,引き続きビルマにとり最大の貿易相手国で,かつ,最大の援助供与国であった。
<要人往来>
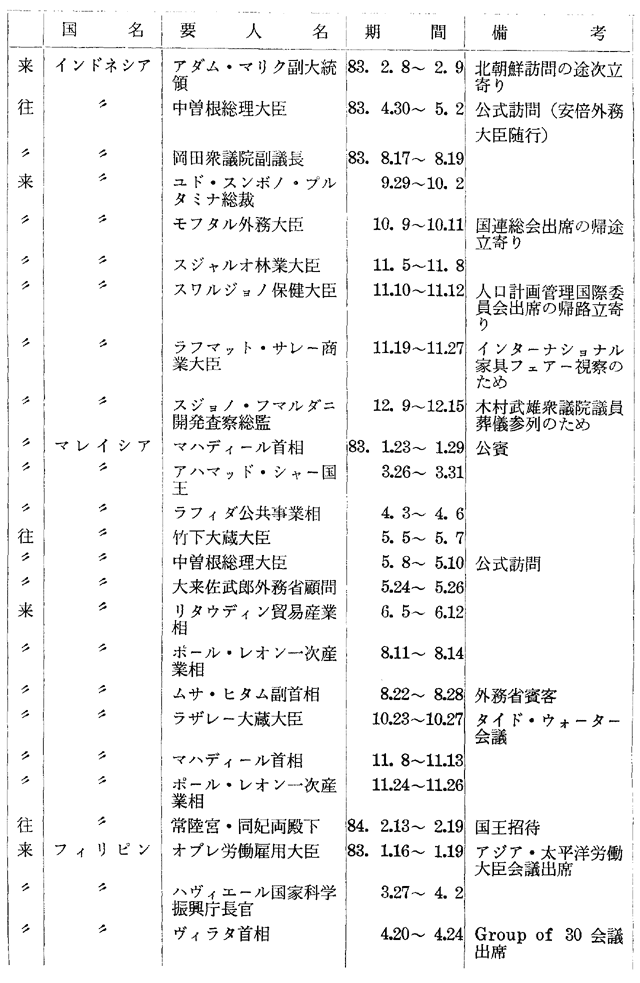
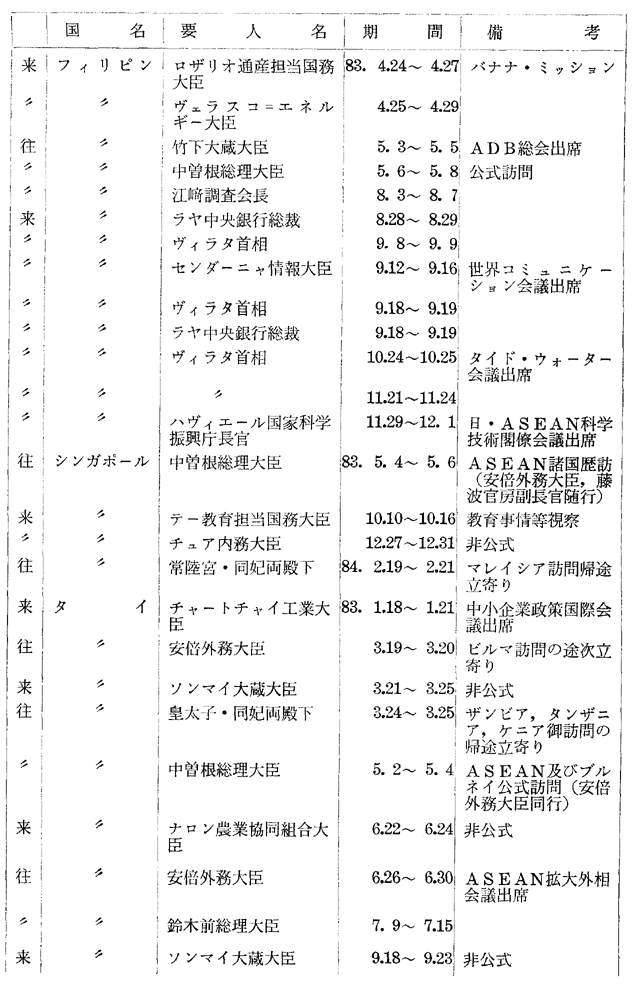
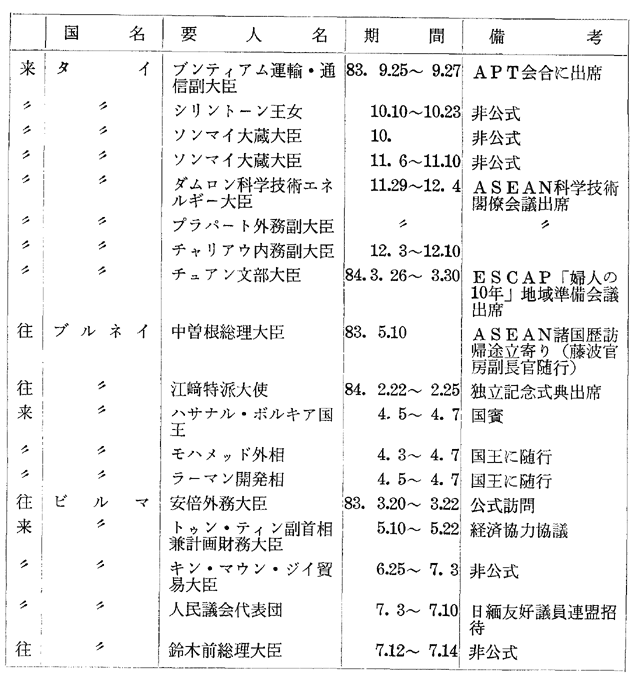
<貿易関係> (1983年,単位:百万ドル,()内は対前年比増加率%)
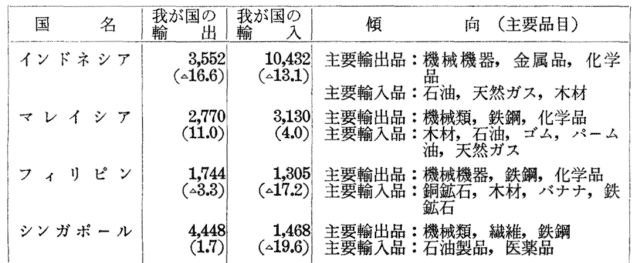
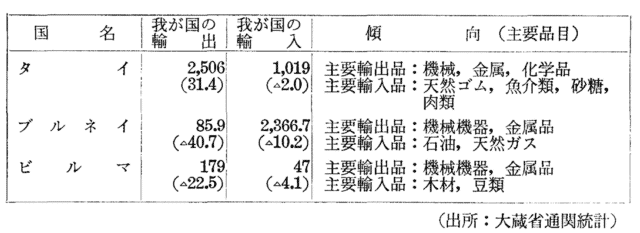
<民間投資> (単位:百万ドル)
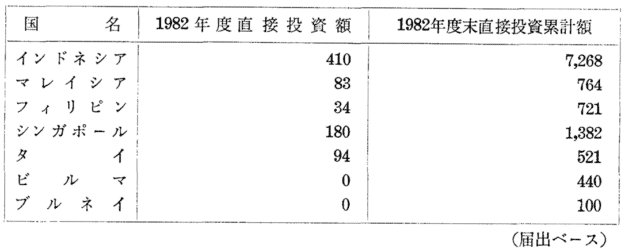
<経済協力(政府開発援助)> (1983年,単位:百万円,人)