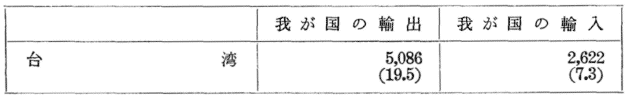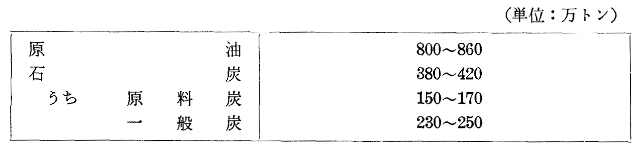
2. 中国
(1) 中国の内外情勢
(イ) 内政
(a) 全般
83年は,82年秋の第12回党大会で提起された内外政策を実施に移し始めた第1年目であり,6月の第6期全国人民代表大会(全人代)第1回会議開催,7月の「トウ小平文選」発刊,10月の党第12期二中全会の開催と整党の開始,年末に毛沢東生誕90周年記念行事などの動きが見られた。また犯罪者取締りが積極的に進められた。
(b) 第6期全人代第1回会議
人事では,再設された国家主席(国家元首)に李先念,全人代常務委員会委員長に彭真,新設の国家中央軍事委員会主席にトウ小平(党中央軍事委員会主席及び党中央顧問委員会主任兼任)が各々就任し,国務院総理には趙紫陽が留任した。この結果,現指導部は党(胡ヨウ邦総書記),政(趙紫陽総理),軍(トウ小平中央軍事委員会主席)にわたる重要ポストをすべて掌握し,その指導力はより強化された。
政策について,趙紫陽総理は政府活動報告の中で,今後5年間の任務として農業・軽工業・重工業のバランスのとれた発展,経済効率の向上,ボトル・ネックとなっているエネルギー,交通等の分野の強化,人民の生活改善,人口抑制等を挙げるとともに,経済体制改革と機構改革の推進・教育・科学技術の振興,知識分子の優遇・治安強化及び国防近代化等を掲げた。
(c) 整党
整党は,「文革」によって弛緩した党の再建を図り,党を近代化建設事業の中核とすることを目的として思想,規律,組織面から党を整頓することである。具体的にはいわゆる「三中全会」路線に反対する者や権力に安住したり権力を乱用したりする者等を党から排除して現行路線を一層強力に推進する上での足腰を強化することを目指していると見られている。
整党を指導する機関として胡ヨウ総書記を主任とする中央整党工作指導委員会が設置された。83年末から86年末までの3年間を2期に分け,段階的に整党が行われる予定である。
(ロ) 外交
(a) 全般
中国は,第12回党大会で打ち出した独立自主の外交方針にのっとって従来より一層幅広く活発なかつきめの細かい外交活動を展開した。この間ソ連・東欧諸国との関係改善へ向けての動き,第三世界との関係強化への努力も注目されたが,胡ヨウ邦総書記の訪日及び中曽根総理大臣の訪中に象徴される日中関係の一層の進展,米中首脳の相互訪問等に示された中国の西側先進国との関係強化への努力が特に顕著であった。
(b) 対米関係
2月のシュルツ国務長官訪中後も米中間の不協和音は続いたが,5月米国が輸出管理法上,中国を非共産圏諸国と同じグループに含める旨決定し,9月ワインバーガー国防長官訪中の際,米国は対中高度技術移転規制緩和のための新ガイドラインを中国側に伝え,中国側がこれを積極的措置として評価したことを契機として米中関係改善の機運が高まった。米中関係において台湾問題が最大の問題である状況には何ら変わりはないことを十分に踏まえる必要はあるが,米中双方が両国関係の重要性を認識していることも事実であり,10月の呉学謙外交部長の訪米,84年1月の趙紫陽総理訪米,4月のレーガン大統領訪中等を通じ,両国関係は着実な発展を遂げつつあると言えよう。
(c) 対ソ関係
中ソ関係改善については,84年3月までに4回の外務次官級協議が開かれ,またアンドロポフ書記長葬儀の際に訪ソした万里副総理とアリエフ第一副首相との会談等の動きもあったが,中国側の提起している「三つの障害」については,実質的進展は見られなかった模様である。ただし,貿易額の増大,交換留学生増員,スポーツ交流,友好団体相互訪問に見られる人的交流の拡大など経済・文化面等の実務関係は徐々に進展しつつある。
(d) 対アジア関係
(i) 中国は3月に,カンボディア問題に関する5項目の提案を行い,4~5月には中越国境における越の武力挑発を非難し越軍に攻撃を加えた。また12月には民主カンボディア連合政府の三派首脳を同時に北京に招待し,連合政府支持の方針を改めて示した。
(ii) 北朝鮮との関係では,呉学謙外交部長(5月),彭真全人代常務委員長(9月)の訪朝,金正日書記の訪中(6月)等双方の指導者間で密接な接触が行われたが,ラングーン事件について中国は,慎重な態度をとった。韓国との関係では中国民航ハイジャック事件解決のための民航局長の訪韓,国連関係会議出席のための韓国人の訪中許可,国際試合でのスポーツ選手団相互訪問等の動きが見られた。
(iii) 李先念国家主席は84年3月,パキスタン,ネパール,トルコ,ジョルダンを公式訪問し,中印国境交渉(第4回,10月),中国・ブータン国境交渉(第1回,84年4月)も開かれた。
(e) 対ヨーロッパ関係
(i) 胡ヨウ邦総書記は5月,ルーマニア,ユーゴースラヴィア両国を訪問し,その後中国外務次官及び担当局長が東欧諸国を歴訪した。アルバニアとの貿易も5年ぶりに再開された。
(ii) 西欧関係では,ミッテラン仏大統領訪中(5月),ECとの定期政治協議合意(6月),オランダとの大使級外交関係再開(84年2月)等の動きが見られた。
(ハ) 経済情勢
(a) 83年は第6次5か年計画(81~85年)の第3年目に当たり,経済調整の進展に努力が払われた。工業,農業生産の伸長が著しく,総生産額の対前年伸長率は10.2%で,81~83年の3年間の年平均伸長率も7.8%となり,計画目標4~5%を大幅に上回っている。財政収支均衡,物価安定,外貨収支バランス等の目標もほぼ計画どおり達成されているが,経済効率の向上,エネルギー・交通等ネック部門の改善は依然として余り大きな進展は見られず,今後の課題となっている。
(b) 農業生産は生産責任制がほぼ完全に普及し,生産意欲が向上していることなどにより全般的に好調に推移し,総生産額は前年に比べ9.5%増となった。特に穀物は3億8,728万トン(同9.2%増)と大幅増産となっている。
(c) 83年の工業総生産額は6,088億元(対前年比10.5%増),うち重工業生産額3,134億元(同12.4%増),軽工業生産額2,954億元(同8.7%増)で,引き続き重工業の伸長が著しい。一次エネルギー生産量は前年に比べ6.7%増と回復したものの,工業生産の高い伸びにはなお追い付いていない。主要産品の生産量は粗鋼4,002万トン(同7.7%増),セメント1億825万トン(同13.7%増),自動車240,000台(同22.4%増),綿布148億8,000万m(同3.1%減),砂糖377万トン(同11.5%増)等となっている。
(d) 財政収支は計画を13億4,600万元上回る43億4,600万元の赤字となったため,歳入増加に重点を置き,税収の確保,企業収益の向上等のための各種措置がとられている。他方83年にはエネルギー・交通関係の投資が活発に行われ,基本建設投資総額に占めるシェアは34.4%に達している。
(e) 労働雇用の面では,個人経営の一層の拡大に伴い就業機会が増加し,83年末の都市未就業率は82年末の2.6%から2%に低下した。都市労働者の一人当たり年平均所得は前年に比べ3.5%増加,農民一人当たり平均年収も14.7%以上増加した。83年末の個人貯蓄残高は892億5,000万元で82年末に比べ217億1,000万元増加(32.1%増),人口一人当たり約87元となった。
(f) 対外貿易は国内投資の活発化を反映し,鋼材等の輸入が増加したため総額で423億8,160万ドル(対前年比5.6%増)と若干増加した。貿易収支は82年に引き続き55億8,420万ドルの黒字となった。中国は対外開放政策堅持との方針の下に,引き続き外国からの資金,技術の導入に積極的に取り組んだところ,83年の外資利用状況は,政府借款及び国際金融機関からの借款が13億3,000万ドル,新規合弁企業105件(外資分2億ドル)などとなっている。83年末の外貨準備高は143億4,200万ドル(対82年末比28.9%増)である。
(2) 我が国と中国との関係
(イ) 全般
83年には,二階堂総理特使(2月),桜内前外務大臣(4月)が訪中,陳慕華対外経済貿易部長(2~3月),姚依林副総理(4月)及び胡ヨウ邦総書記(11月)が来日したほか,第3回日中閣僚会議が開催(9月,北京)され,また84年3月には中曽根総理大臣が訪中した。
11月に来日した胡ヨウ邦総書記は,中曽根総理大臣と会談したほか,国会における演説,青年の集いにおける日本青年との対話,経済団体との懇談等を行い,さらに札幌,大阪,京都,神戸,長崎と広く足を伸ばし,各地方の状況を熱心に見学した。中曽根総理大臣との会談では,両首脳は,両国が21世紀に向かって平和的,友好的に付き合っていくことを確認し,今後,「平和友好,平等互恵,相互信頼,長期安定」の四つの原則に基づき,各方面の交流,協力関係を拡大,強化することにつき合意した。
84年3月に訪中した中曽根総理大臣は,訪問地の北京,武漢で中国人民の盛大な歓迎を受けた。中曽根総理大臣は,趙紫陽総理をはじめ,胡ヨウ邦総書記,トウ小平党中央顧問委員会主任,彭真全人代常務委員長,トウ穎超全国政治協商会議主席等の中国指導者と会談し,打ち解けた雰囲気の中で率直な意見交換を行った。日中双方の首脳は,現在の良好で緊密な日中関係を21世紀に向かって長期にわたり安定的に発展させていくとの決意を確認し,さらに,これをいかなる施策により具体化していくかについて話し合った。また,日中関係を21世紀に向かって確固たるものにするための方策につき研究・検討し,その成果・結論を踏まえ両国政府に提言を行うための「日中友好二十一世紀委員会」の発足につき合意するとともに,我が国は中国の近代化の努力に対し引き続きできるだけ協力することを確認した。
(ロ) 日中経済関係
(a) 83年の日中貿易は,往復約100億ドル(対前年比12.8%増)と2年ぶりに100億ドル近くに達した。これは我が国の対中輸入が原油価格の下落の影響等により前年を下回ったにもかかわらず,鉄鋼を中心に輸出が伸長したためである。
(b) 日中両国政府は,両国間経済・文化交流の一層の円滑化を図るために81年1月以来租税協定締結に向けて折衝を重ね,83年9月署名に至った。この協定は中国にとって外国と結ぶ初めての租税協定(条約)となる。
(c) 政府ベースの資金協力としては,7月に,83年度分円借款の供与限度額を690億円とするとの内容の交換公文が締結され,また同月には「中日友好病院」建設計画に対する無償資金協力の83年度分72億円の供与に関する交換公文が締結された。
なお,84年度からの新規円借款については,84年3月の中曽根総理大臣訪中の際に,我が方から運輸,通信,エネルギーの分野の重点7プロジェクトに対し,我が国の財政事情等を勘案の上できる限り協力する旨を表明した。
(d) 政府ベースの技術協力としては,交通運輸,経営管理,保健医療など広範な分野での研修員の受入れ,専門家を派遣したほか,中日友好病院,企業管理センターに対するプロジェクト方式による技術協力や,黒龍江省三江平原における農業開発など農業,エネルギー,鉱物資源開発や工場近代化等を対象とする各種の開発調査協力事業が行われた。
(e) 輸出入銀行の石油・石炭開発金融(4,200億円)については,これまでに3,150億円の融資契約が調印されている。
(f) 日中長期貿易取決め(民間)は,11月に84年の対日石炭供給量を下方修正することで合意され,84年の対日石油・石炭供給量は次のとおりとなった。
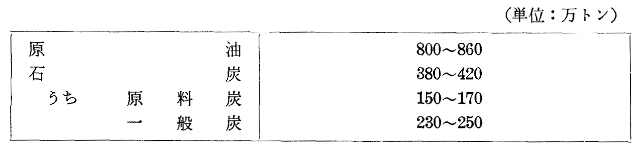
<貿易関係> (1983年,単位:百万ドル,()内は前年比増減率%)
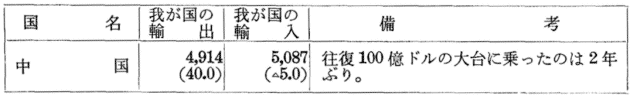
<民間投資> (単位:百万ドル)

<経済協力(政府開発援助)> (1983年度,単位:百万円)
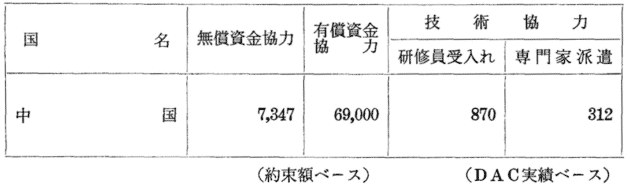
(ハ) 人的往来と文化交流
日中間の人的往来は,72年(日中国交正常化当時)約9,000名であったが,83年には188,000名を超えた。この間両国閣僚レベルの往来も頻繁となり,83年度の要人の往来は次表のとおりである。
<要人往来>
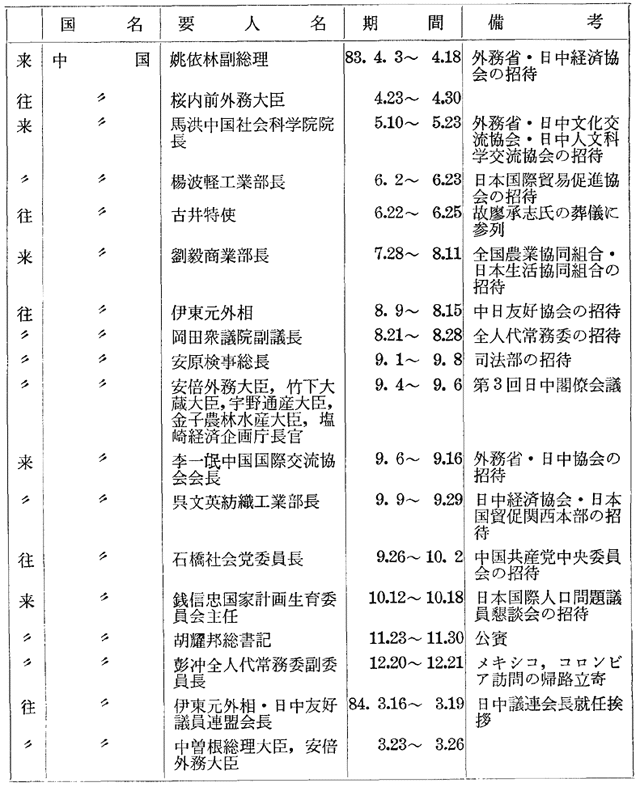
両国間の文化交流は,民間及び地方自治体ペースで盛んに行われているが,両国政府間でも79年12月に締結された文化交流協定等に基づき順調に発展しており,我が国政府は青少年交流,中国人留学生の受入れ,中国の日本語教育に対する援助及び文化無償資金供与(7件,計3億3,050万円)等の分野で協力している。
(ニ) 日中友好会館の建設
日中国交正常化10周年の記念事業として我が国の政界,財界及び関係団体を中心に,東京に中国からの留学生・研修生等のための宿舎及び日中文化交流のためのセンター等の総合施設「日中友好会館」を建設する計画が推進されている。この計画は,82年9月に政府首脳レベルで両国政府の建設支援が合意され,我が国政府は,既に83年度7,500万円,84年度7億5,000万円の建設費を補助済みで,84年5月から会館の一部のA棟の建設が開始されている。
(ホ) 中国残留日本人孤児問題
83年12月に60人,84年2月から3月にかけて50人の孤児が来日,肉親捜しが実施され,66人の身元が判明した。83年1月に行われた孤児問題に関する日中間の協議の結論を確認する口上書が,84年3月17日,北京で交換された。これにより中国政府は,孤児の訪日親族捜し等に対し引き続き協力すること,日本政府は孤児の日本への永住により生ずる家庭問題を責任をもって適切に解決すること等が確認された。
(3) 台湾
我が国と台湾との実務関係
(イ) 来日台湾人数は年々増加の傾向をたどり,83年には前年より若干増加して約33万人に達し,また,同年の訪台日本人数も前年より増加して約60万人となった。
(ロ) 83年における日台間輸出入額は前年比15.1%増の77億ドルとなり,日本側の出超額は24億6,000万ドル(前年比36.0%増,日本側統計)に増大した。この日台間の貿易インバランス問題解消措置の一環として,9月に民間経済界の「輸入等促進ミッション」が訪台し,11億3,000万ドルの買付けを行った。
<貿易関係>
(1983年,単位:百万ドル,()内は対前年比増加率%)(大蔵省通関統計)