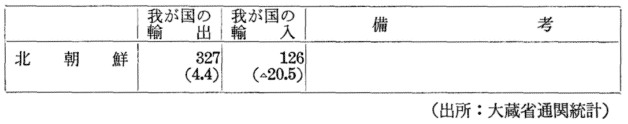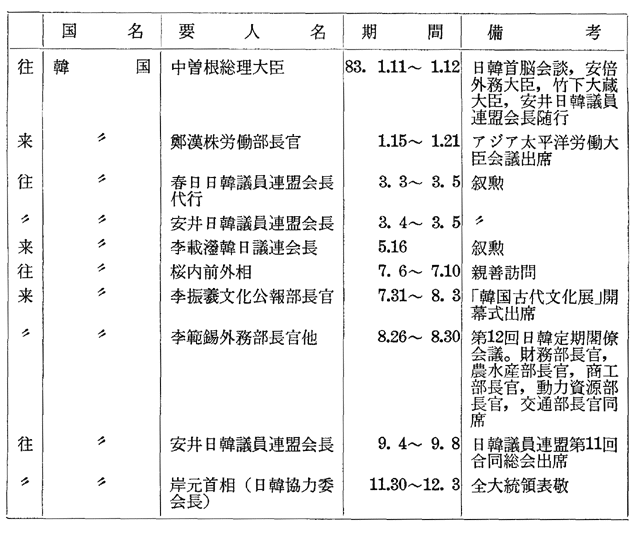
第1章 各国の情勢及び我が国とこれら諸国との関係
第1節 アジア地域
1. 朝鮮半島
(1) 朝鮮半島の情勢
(イ) 韓国の政情
(a) 内政
83年は,大韓航空機事件やビルマにおける爆弾テロ事件等韓国の政局を揺るがす大きな事件が相次いだが,全斗煥政権はこれら事件に冷静に対処し,内閣改造を断行し,動揺した民心を収拾した。さらに,内政・外交・経済各方面での政策の継続を明らかにして困難を克服,内外から評価を得るとともに国政運営の安定度を高めた。
83年初頭から84年3月までの主な内政動向は次のとおり。
(i) 政治活動被規制者の解除
韓国政府は2月25日,朴政権下の政治家等で80年11月以来政治活動を規制されていた者(82年末現在555名)のうち250名の規制を解除した。
(ii) 金泳三氏の断食闘争
政治活動規制を受けている大物政治家金泳三元新民党総裁が,5月に反政府声明「国民に送るメッセージ」を発表した後,22日間の断食闘争を行った(5~6月)。
(iii) 金融不正事件
新興財閥「明星グループ」による私債不正調達及び脱税事件(8月)並びに市中銀行による手形不正支払保証事件(9月)が相次いで摘発され,その被害額は邦貨に換算すると数百億円に及んだ。
(iv) 大韓航空機撃墜事件
9月1日,サハリン沖で,ソ連機による大韓航空機撃墜事件が起こり,乗客乗員計269名全員が死亡した。韓国と国交のないソ連によるこの人道にもとり,国際法に反する行為は、韓国国民に強い衝撃と怒りを与えた。
(v) ビルマ爆弾テロ事件
10月9日,ビルマを公式訪問中の全斗煥大統領一行に対する爆弾テロが発生,同大統領は無事であったものの,随行の4閣僚を含む17名が死亡,12名が負傷するという未曾有の大惨事が発生した。
(vi) 内閣改造
全斗煥大統領は、ビルマ事件犠牲者の合同国民葬(10月13日)の翌日,多数の欠員の生じた内閣の改造(15日付)を発表し,いち早くビルマ事件後の国内体制を整えた。
(vii) 除籍学生の復学措置等
韓国政府は、ビルマ事件後も引き続き「国民和合」及び「政局安定」の雰囲気作りに努めた。12月には,80年の戒厳令施行当時,政治的理由で追放された大学教授(86名)の復職及び80年以降学生デモ等により除籍された大学生(1,363名)の復学を84年度新学期(3月)から認めるとの方針を明らかにした。また,年末特赦を実施し,314名の「政治犯」(うち131名は学生)を含む1,765名を赦免した。さらに,84年2月25日,政治活動被規制者301名のうち202名について規制を解除した。
(b) 外交
(i) 基本方針
全斗煥大統領は,83年1月18日の国政演説で,次の外交基本方針を明らかにした。
(あ) 友邦諸国との協力体制の多角化
(い) 韓米関係の各分野での協力の拡大
(う) 歴史上初の日韓両国首脳会談を契機に真正な善隣友好の新時代を構築
(え) 太平洋首脳会談開催のため外交的努力を傾注
(お) 開発途上国との南南協力政策の推進
(か) 未修交国との人的交流の促進
(ii) 対米関係
韓国にとって安定した米韓関係が,とりわけ重要である。2月のシュルツ国務長官の訪韓,4月の李範錫外務部長官の訪米,11月末の李源京外務部長官の訪米等によって,米国との強固な関係が再確認された。特にレーガン大統領の訪韓(11月12~14日)は,米国の韓国に対する政治的,外交的支援を再確認し,相次ぐ大事件に見舞われた韓国国民への大きな励ましとなった。
(iii) 欧州等先進国との関係
韓国は対外関係多角化の見地から欧州等先進国との関係強化に力を入れ,ベルギー,豪州,伊の各外相,84年2月のホーク豪州首相の訪韓及び成東春大統領秘書室長の訪豪(83年5月)等の首脳,閣僚レベルの交流が行われた。
(iv) 非同盟諸国との関係
韓国は,アジア,アフリカ等の諸国との関係を北朝鮮との外交競争の場ととらえ,また86年のアジア競技大会,88年のオリンピックのソウル開催の成功に向けて,これらの国々に対し活発な外交活動を展開した。しかし,全斗煥大統領は,10月8日ビルマ,インド,スリランカ,豪州,ニュー・ジーランド,ブルネイ歴訪の途についたが,最初の訪問国ビルマで爆弾テロ事件が発生し,歴訪は中止のやむなきに至った。この事件により韓国の対非同盟外交活動は,一時的に水をさされることとなったが,全斗煥大統領は事件後の国会での施政方針演説で,「今後とも第三世界との交流拡大及び未修交国との国交樹立に努力する」旨強調し,外交方針の継続を確認した。
(v) 社会主義諸国との関係
韓国政府は,5月に発生した中国民航機のハイジャック事件を円満に処理し,また,その際,韓中両国当局者間の直接接触が初めて実現した。また,10月のソウルでの列国議会同盟(IPU)総会開催は,ソ連による大韓航空機撃墜事件で韓ソ関係が急激に悪化したことにより,9月末,ソ連をはじめとする共産圏,社会主義諸国が同総会への参加を取りやめ,韓国政府としては,IPU誘致の所期の狙いは達せられなかったが,総会自体は成功裏に終了し,韓国の国際的地位の向上を反映するものとして注目された。
(vi) 環太平洋諸国首脳会談構想
82年7月31日の鎮海での記者会見で全斗煥大統領から発表された,環太平洋諸国の首脳が共通の関心事と協力方法について協議するため定期的に会談を開くという太平洋首脳会談構想は,韓国の国会に対する2月4日の外務部業務報告においても確認された。
(c) 韓国の経済
60年代から70年代にかけて高度成長を続けた韓国経済は,79年の第2次オイル・ショック以降停滞し,80年には実質成長率が-5.2%を記録するなど厳しい経済調整の局面を迎えたが,83年に入りようやく米国を中心とする先進諸国に景気回復の兆しが見られ,これに伴って経済活動に活気が戻った。すなわち韓国経済の原動力とも言うべき輸出は83年年央から増大し,これに伴い実質成長率も5年ぶりに9.3%の高水準に達した。
また,輸出が対前年比11.9%増の244億ドルと伸びたのに対し,輸入は原油価格の値下がり等により同8.0%増の262億ドルにとどまったため,貿易収支の赤字幅も前年の26億ドルから17億ドルへ改善し,また,経常収支もドル金利の低落等により赤字幅が前年の27億ドルから16億ドルに改善した。さらに物価上昇率も,卸売物価が0.2%消費者物価が3.4%にとどまり引き続き安定を示した。
こうした中で,韓国政府は,12月に第5次経済社会発展5か年計画(82~86年)の修正計画を発表した。この修正計画では,従来に引き続き物価の安定と国際収支の改善を図りながら近年累増し,83年末に401億ドルに達した対外債務を縮小することに重点を置いている。
(ロ) 北朝鮮の情勢
(a) 内政
金日成主席を中心とする指導体制が堅持されており,83年も主体思想を基本方針とし,社会主義制度の強化を図る三大革命(思想,技術,文化)路線を推進する動きが引き続き展開された。
政権内部の主要人事としては,ビルマ事件後の83年12月末に外交部長が交替し,金永南労働党国際事業部長が新外交部長に任命(12月)されたほか,84年1月の最高人民会議第7期第3回会議で李鐘玉総理が国家副主席に,姜成山第一副総理が総理に選出された。
また,金日成主席の子息金正日労働党秘書は,各種行事に金日成主席に次ぐ序列で出席したほか,労働新聞,平壌放送等が同人の著作,活動ぶりを報じるとともに,同人が金日成主席の後継者たる資質を兼ね備えた指導者であるとのキャンペーンを引き続き展開した。また,6月の金正日訪中によって後継者としての金正日の地位を国際的に印象付けるなど金正日後継体制作りが本格化していると見られる。
(b) 外交
(i) 北朝鮮は,77年以来非同盟諸国との要人の往来に積極的に取り組んできた。83年にも,朴成哲副主席,李鐘玉総理,金永南党政治局員,許ダム外交部長兼副総理など政府及び党の要人がアフリカ,東南アジア諸国などを訪問したほか,アジア,アフリカなどから要人が北朝鮮を訪問した。
(ii) しかし,北朝鮮は,10月9日ラングーンで発生した爆弾テロ事件は北朝鮮工作員による犯行であるとビルマ政府によって断定され,ビルマ政府により外交関係断絶・政府承認取消しという措置を受けた(11月4日)ほか,諸外国から外交関係断絶などの措置を受けた。この結果,83年末現在で北朝鮮と外交関係を持つ国は,82年末の106か国から102か国に減少した(このうち韓国とも外交関係を持つ国は67か国)。
(iii) この事件後,北朝鮮は,外交部長の交代をはじめとする外交陣容の改編を行ったほか,米韓両国との三者会談を提案(84年1月)するとともに,最高人民会議第7期第3回会議で,開発途上国及び資本主義諸国との経済交流を通じた対外関係の改善を打ち出すなど,その失墜した対外関係の修復に努めている。
(iv) 中国及びソ連との関係で,北朝鮮はバランスの保持に留意する態度を維持している。中国とは,6月に金正日秘書,84年2月に金永南外交部長が各々訪中し,中国側からは,5月に呉学謙外交部長,9月に彭真全人代常務委員長が北朝鮮を訪問した。他方,ソ連とは,84年2月アンドロポフ書記長の葬儀に朴成哲副主席を団長とする朝鮮労働党・国家代表団が訪ソしたほか,5月タルイジン副首相が訪朝したのをはじめ各種レベルの人的往来が行われた。
(c) 経済情勢
(i) 84年の金日成の「新年の辞」では,演説の半分以上が経済問題に費されながら,何ら具体的な生産実績についての言及がなかったことから,北朝鮮の経済は,不振であった前年よりも更に一層困難な状況になりつつあるのではないかと見られている。
(ii) 北朝鮮は現在西側諸国を含む諸外国に対し,多額の未払債務を抱え,返済も滞りがちであると言われている。対日債務についても,83年4月に支払繰延べが行われていることから,北朝鮮の外貨事情は更に悪化しているものと見られている。
(ハ) 南北関係
(a) 南北対話
北朝鮮は,84年1月に米韓両国との間で朝鮮半島の問題につき話し合うといういわゆる「三者会談」を提案した。この提案は,韓国の参加に言及しつつも話合いの手順として,先ず在韓米軍の撤退問題及び休戦協定を平和協定に代える問題につき米国と話し合うことが先決であるとしていることなど,おおむね従来の北朝鮮の考え方を述べたものであると見られる。
これに対し,韓国は,平和統一実現のためには責任ある南北当局間で対話を持ち,信頼回復のために努力する必要があると指摘しつつ,民族和合の基盤を固めるためには,北朝鮮がビルマ事件につき謝罪するなど納得する措置をとることが必要であるとの立場を表明した。
また,米国は韓国の立場を支持しており,いずれにせよ,韓国,米国及び我が国は,南北両当事者の直接対話が何よりも重要であるとの認識で一致している。これに対し,中国及びソ連は,北朝鮮の三者会談提案を支持するとの立場を明らかにしている。
このように朝鮮半島を巡る話合いが進展するか否かについて見通しが立て難い状況の中で,84年3月末,北朝鮮側から,オリンピック等のスポーツ大会への南北単一チームによる参加問題についての話合いが提案されたところ,今後の動きが注目される。
(b) 軍事情勢
83年の朝鮮半島情勢は,武装スパイの侵入事件(4件),大韓航空機撃墜事件,ビルマ爆弾テロ事件等の発生により前年以上に厳しいものがあった。特にビルマ事件直後は,韓国軍・在韓米軍・北朝鮮軍とも警戒態勢を強化し,緊張が高まった。
北朝鮮は,装備の近代化,国産化を進めつつ軍事力の増強に努めた。これに対応して,韓国も第2次戦力増強計画(82~86年)に基づき新規に戦車を取得するなど軍事力の向上を図った。また,米国は,レーガン大統領の訪韓により対韓防衛公約を確認するとともに,韓国軍近代化のために対韓軍事援助を継続して行ったほか,在韓米軍の質的向上を図り,朝鮮半島の軍事バランスの維持に努めた。
他方,これら軍事バランス維持のための施策と並行して緊張緩和と信頼醸成のため・米韓連合司令部は,82年同様米韓合同演習「チームスピリット84」に際して事前通告するとともに演習参観招待を行った。しかし,北朝鮮は,この招待に応ぜず,これに呼応して戦闘動員態勢を強化した(注,前年は準戦時態勢をとった)。
また,8月には中国空軍機(ミグ21)が韓国に着陸し,その後,中国パイロットは,台湾へ亡命するという事件が発生した。
(2) 我が国と韓国との関係
(イ) 概観
65年の日韓国交正常化以来,日韓関係は,着実な発展を見てきており,両国間で広範な分野にわたって交流と協力が行われている。
83年は,1月の中曽根総理大臣の訪韓を契機として盛り上がった両国間の国民的基盤に基づく交流を背景に,8月末に日韓定期閣僚会議と日韓外相会談が開催されたほか,数次にわたる政府レベルの協議を通じ,日韓間の産業技術協力問題や漁業問題等について進展が見られた。また,9月,10月と相次いで発生した大韓航空機撃墜事件,ビルマでの爆弾テロ事件により困難な立場に置かれた韓国に対し,我が国は外交的,政治的に可能な限りの支援,協力を行った。特にビルマ事件が北朝鮮の工作員による犯行である旨ビルマ政府により公式に発表された後,我が国は官房長官談話を発表し(11月7日,資料編参照),北朝鮮に対する措置を明らかにした。
(ロ) 日韓定期閣僚会議
8月末に開催された日韓定期閣僚会議と外相会談では,産業技術協力への前向きな対応,文化交流の促進,85年の日韓国交正常化20周年記念行事の検討等につき両国の意見が一致した。また,日韓高級事務レベル協議やアフリカ協議の開催についても合意した。このように日韓関係を国民的基盤に立脚させるとともに,多元的なものにするため両国が努力するとの認識で一致した(共同新聞発表,資料編参照)。
(ハ) 日韓高級事務レベル協議
84年3月,ソウルで日韓高級事務レベル協議が開催された(日本側は中島外務審議官,韓国側は李相玉外務第一次官補がそれぞれ代表)。この協議は,前年の日韓外相会談で広く諸々の国際情勢につき意見交換を行うとの趣旨で開催が決まったものであり,朝鮮半島情勢のほか,米ソ,日ソ,中ソ,日米,中東情勢等につき幅広い意見交換が行われた。
(ニ) 産業技術協力問題
韓国は83年1月の首脳会談以来,我が国に対し産業技術移転の促進,中小企業技術者の日本での研修等の産業技術協力を要請している。我が国としては,産業技術協力は基本的には民間の自主的判断により行われるべきであるとの立場であるが,研修生の受入れ等政府として可能な分野については協力を進めていくこととしている。
具体的には,83年夏に開催された第12回日韓定期閣僚会議で,(a)産業技術協力に影響をもたらす政策のレヴュー等につき話し合うため日韓貿易会議の下に実務者会議を設けること,(b)韓国の技術者の日本における研修計画を推進することに合意し,これを受け12月及び84年2月に実務者会議が開催され当面の案件である技術者研修計画を中心に協議が行われた。
また,閣僚会議では,民間の直接投資が技術移転に大きな役割を果たしているとの観点から,投資環境の問題についても話し合うことで一致した。これを受け,10月ソウルで日韓間の実務者会議が開催され,対韓投資を阻んでいると考えられる諸問題につき意見が交わされた。
(ホ) 通商関係
日韓貿易は79年の総額96億ドルをピークにその後停滞していたが,83年には,韓国の景気回復を背景に輸出入とも増大し,日本の韓国への輸出は60億ドル,韓国からの輸入は34億ドルとなった。
なお,国交正常化以来,日本側の出超が続いており,近年出超幅は縮小傾向にあったが,83年は韓国の景気回復に伴い,日本からの機械類の輸入が伸びたため日本側の出超幅は拡大した。
<要人往来>
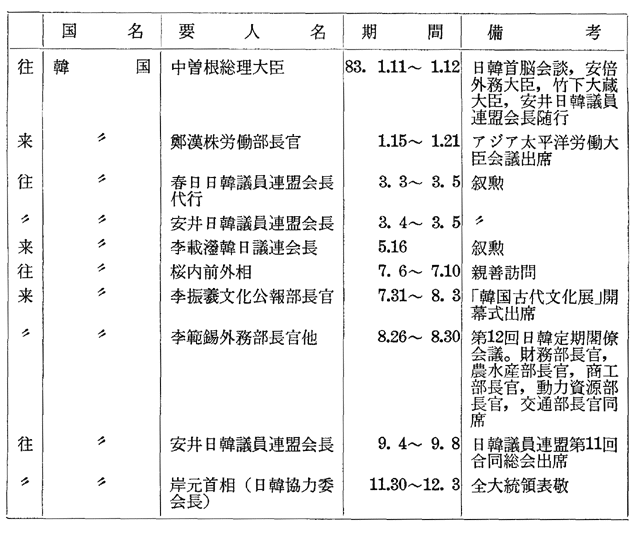
<貿易関係> (1983年,単位:百万ドル,()内は対前年比増加率%)

<民間投資> (単位:百万ドル)
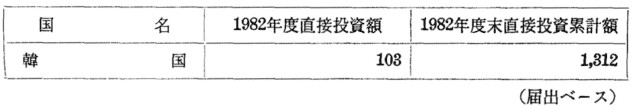
<経済協力(政府開発援助)> (1983年,単位:百万円,人)

(へ) 日韓大陸棚共同開発
大陸棚共同開発区域では,79年以降毎年物理探査が実施されている。また,試掘も3か所で実施されたが,いずれも微量の油・ガスの兆候はあったものの商業的発見には至らなかった。
(ト) 漁業問題
西日本水域における韓国漁船の操業問題について,政府は,機会あるごとに韓国漁船による領海・漁業専管水域侵犯操業の根絶と日韓漁業協定合意議事録の尊重を強く働きかけてきている。韓国政府としてもほぼ常時問題水域に漁業指導船を派遣するなど対策を講じているが,韓国漁船による違反操業の根絶には至っていない。
北海道周辺水域の韓国漁船操業問題については,80年11月から実施されてきた自主規制措置が83年10月で期限切れとなるため,それ以降の措置につき両国政府当局間で鋭意話合いを行った結果,漁業資源保護の強化等を内容とする新たな自主規制措置が11月1日から3年間実施されることとなった。また,我が国は,韓国側の要請にこたえ韓国済州島周辺水域での底引網漁業につき新たな自主規制措置を同様の期間実施することとなった。
竹島周辺水域の安全操業を確保する問題については,政府は引き続き努力を払っている。
(チ)竹島問題
我が国は,韓国による竹島不法占拠に対し,従来繰返し抗議しており,11月の海上保安庁巡視船の調査結果に基づき抗議を行ったほか,各種会議の機会にも,この問題を韓国側に提起している。
(3) 我が国と北朝鮮との関係
我が国と北朝鮮との間には外交関係はないが,貿易,経済,文化などの分野では民間交流が行われている。83年における主な動きは次のとおり。
(イ) 漁業関係
北朝鮮周辺水域における我が国漁船の漁業活動については,日朝民間関係者間の民間漁業暫定合意が82年6月30日をもって失効したため,それ以降操業中断のやむなきに至っている。その後,北朝鮮の関係団体は,我が国がビルマ事件に関連してとった措置に対し,11月声明を発出し,本件暫定合意延期のための協議を現時点では行わないとの態度を表明した。他方,8月と12月に我が国漁船計3隻が北朝鮮に拿捕・連行される事件が発生したが,いずれもその後の民間関係者の努力により解決した。
(ロ) 人的交流
(a) 83年中の邦人の北朝鮮への渡航者数は,876名である。渡航目的のうち最も多いのは商用であり,このほか親善交流等があった。
(b) 一方,同期間中の北朝鮮からの入国者数は434名であり,入国目的の大部分は商用であった。
(c) さらに同期間中の在日朝鮮人に対する北朝鮮向け再入国許可数は4,133件であり,渡航用務の主なものは,親族訪問,学術・文化・スポーツ,観光,商用であった。
(ハ) 日朝貿易
83年は,82年よりも若干金額が下回った(前年比2.6%減の4億5,300万ドル)。
輸出は機械類,同輸入は魚介類等の食料品,鉱産物製品が中心である。
<貿易関係> (1983年,単位:百万ドル,()内は対前年比増加率%)