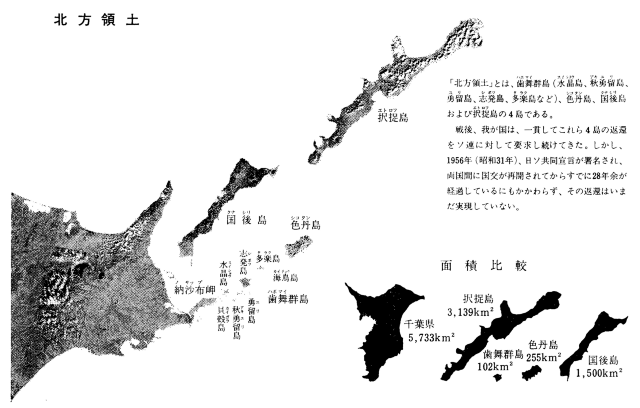
回国連総会一般討論演説(資料編参照)において,80年の伊東,81年の園田,82年の櫻内の各外務大臣の演説に引き続きこの問題についての我が国の基本的立場を広く国際世論に訴えた。
(ヘ) 我が国は9月の大韓航空機撃墜事件に関連して一連の航空の分野における対ソ措置を実施した。
(ト) なお,経済面では,2月に大型の民間貿易経済ミッション(通称永野ミッション)が訪ソしたほか,政府間でも10月モスクワで貿易経済協議が行われた。
(チ) 対ソ外交は,我が国の対外関係の中でも最も重要なものの一つであり,真の相互理解に基づく安定的な日ソ関係の確立はアジア,ひいては世界の平和と安定にとっても重要である。しかしながら,このような関係の確立のためには,北方領土問題の解決は避けて通れない問題であり,国民の総意を背景に,この問題を解決して平和条約を早期に締結するよう,今後とも粘り強くソ連側に呼び掛けていく考えである。
(2) 東欧地域
(イ) 我が国と東欧諸国の関係は,着実な進展を見ており,相互の関心は,一層高まりつつある。我が国は,各国の国情及び政策に留意しつつ要人往来,経済・文化面での協力等を通じ友好関係の促進に努めている。
(ロ) 83年8月,安倍外務大臣が我が国の外相として初めてルーマニア,ブルガリアの両国を訪問し,主としてINF問題等の国際問題につき両国の指導者と率直な意見交換を行った。これは両国との相互理解を増進し,東欧とのパイプを太くするとの意味において極めて有益であった。
(ハ) ポーランド問題については西側諸国との協調と結束を基本として対処し,11月には,債務繰延交渉の再開に応じた。
(ニ) 我が国は,独立・非同盟路線を堅持しているユーゴースラヴィアの外交姿勢を高く評価している。かかる観点から,6月,安倍外務大臣がベオグラードで開催されたUNCTADVIへの出席と併せ,同国を公式に訪問した。また,他の西側諸国と共にユーゴースラヴィア経済の安定と発展のため,輸出信用供与等の支援を行った。