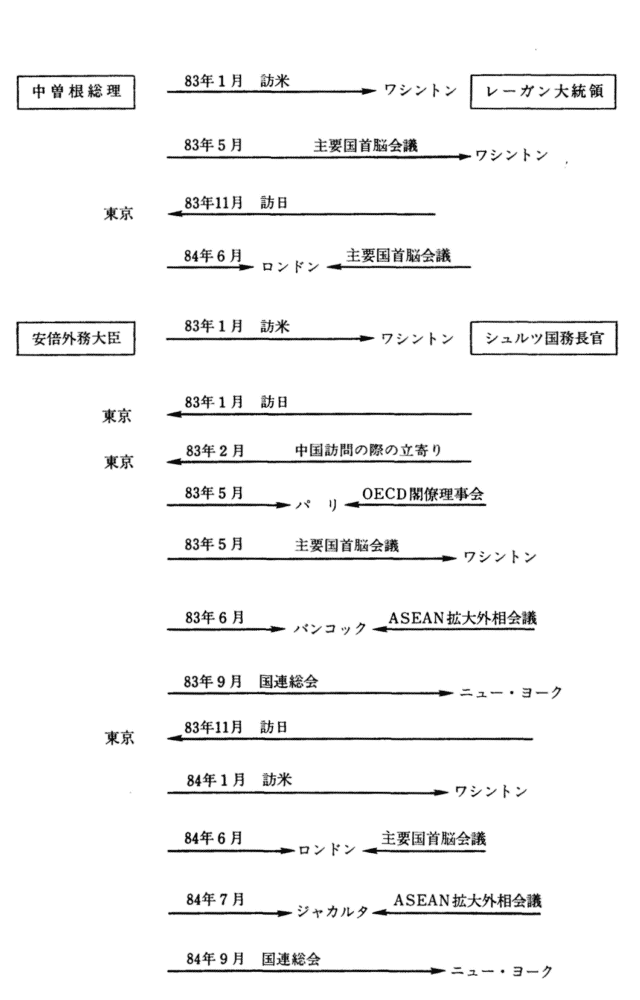
1. 対日信頼度
質問「日本を米国の信頼できる友邦と見なすか。」

2. アジアにおける米国のパートナー
質問「アジアの安定と平和が米国の関心事であるとの見地から、米国にとりより大切なパートナーは日本、中国、ソ連、それ以外の国のいずれであるか。」
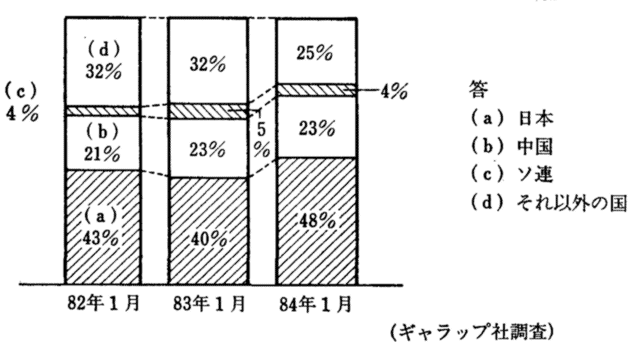
のほか,5月のウィリアムズバーグ・サミットの前日にもワシントンで会談が行われた。これらを通じて明確化されたテーマは「世界の平和と繁栄のための日米協力」である。安倍外務大臣とシュルツ国務長官との間では,1月訪米の際,年に少なくとも4回は会合する旨の合意が見られたが,結果的には9回の会合をワシントン,東京,パリ,バンコック,ニュー・ヨークで行った。これらの高いレヴェルにおける個人的関係の緊密化は,両国間の個別の摩擦案件が政治問題化することなく回避できたことの大きな要因である。なお,「日米諮問委員会」は,大統領訪日や外務大臣訪米といった両国関係の節目に当たり,有効かつ適切な勧告を行った。
(2) カナダ
(イ) 我が国とカナダは,共に他の先進民主主義諸国と政治・経済理念を共有する自由主義諸国の一員であり,国際社会における共通の理念と目標を追求する上での重要なパートナーである。日加両国関係は,経済貿易面を中心に近年ますます緊密化の度合いを増しているが,こうした側面のみならず安定し成熟した関係を築いていく上で重要な政治,経済協力,文化,科学,技術等の各分野でもその関係強化が図られている。
(ロ) 83年においても日加間において要人の往来や各種協議が盛んに行われた。トルドー首相は,1月にASEAN歴訪後訪日したのに続き,11月にも自らの「平和イニシアティブ」推進のために再び訪日し,中曽根総理大臣に自らの核軍縮提案を説明した。また,両国外相は,6月バンコックで開催されたASEAN拡大外相会議の機会に協議を行った。事務レベルでも経済協力に関する定期協議が初めて開催されたほか,各種協議(経済,国連,文化等)が行われた。さらに,ローヒード=アルバータ州首相が外務省賓客として8月に来日したほか,議員交流の分野でもペロー上院議員一行が参議院議長の招待により訪日した。