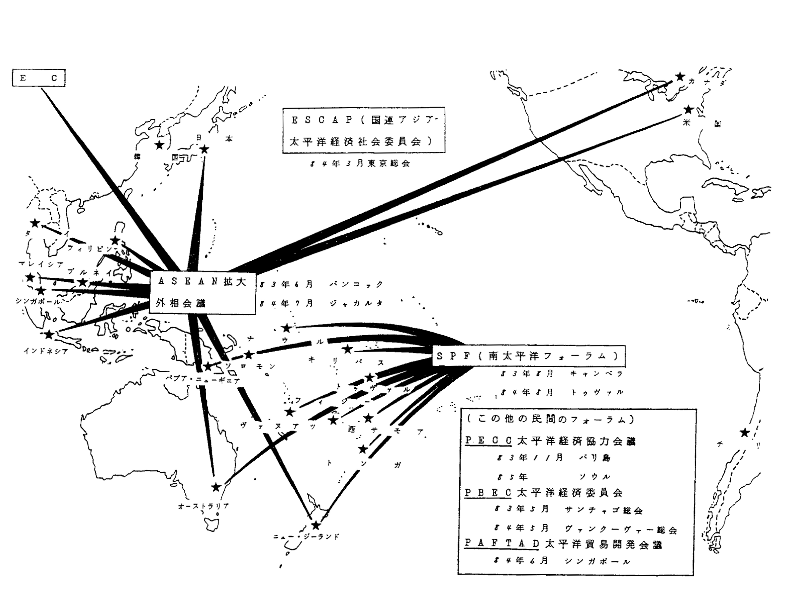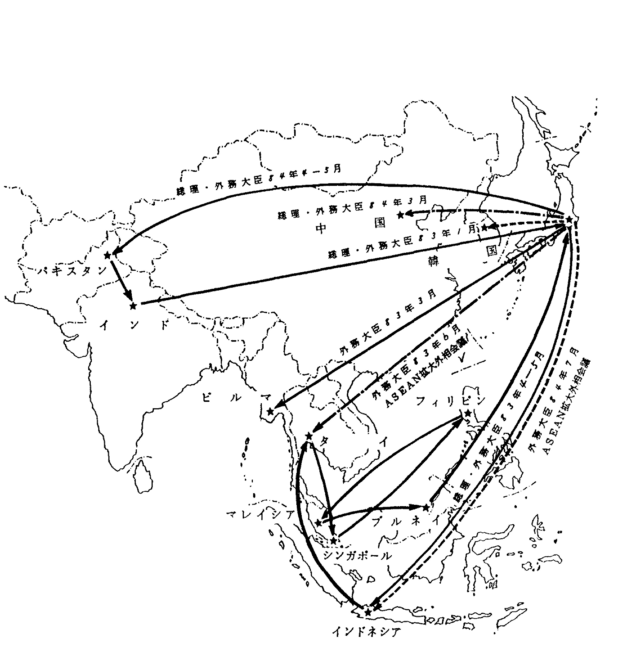
倍外務大臣による韓国,米国,中国との外相会談等である。
南北対話については,北朝鮮が84年1月にいわゆる三者会談(南北朝鮮及び米国)を提案したが,当事者間の立場の差は依然として大きい。我が国は,朝鮮半島問題は,第一義的には南北両当事者間の直接対話を通じて解決されるべきであるとの基本的立場から,従来韓国の対話努力を支持しており,南北対話の実質的な再開を期待しつつ,今後の推移を注視し,かつ,我が国としてできることがあれば協力していく考えである。
(ロ) 我が国は,韓国との友好協力関係を引き続き重視しており,両国間の多元的な分野での交流と協力の強化を図るとともに,広く両国国民の相互理解と信頼関係に裏打ちされた揺るぎなき日韓関係を構築するよう努力している。8月の日韓定期閣僚会議では,1月の首脳会談が両国の友好協力関係の新たな発展のための重要な契機となったことにつき意見の一致を見,85年が日韓国交正常化20周年に当たることを記念して両国の相互理解及び相互交流を促進するための行事を実施すべく,日韓両国間で検討していくことに合意した。
(ハ) なお,ビルマにおける爆弾テロ事件に関し,我が国は,テロ行為が国際的に許されるべきでないとの立場から,北朝鮮との関係について厳しい態度で臨むこととしたが,従来の経済,文化等の分野における交流の基本的枠組みは,これを維持する考えであり,同時に北朝鮮が朝鮮半島の緊張緩和に向けて真摯な努力を傾けることを期待している。
(3) 中国
(イ) 我が国は,72年の国交正常化以来,中国との間に良好にして安定した関係を維持,発展させていくことを外交の主要な柱の一つとし,両国関係の発展を図ってきた。良好で安定した日中関係は,日中両国にとってのみならず,アジアと世界の平和と安定に寄与するものであるとの認識に立って,我が国は,経済建設を進める中国に対し今後とも引き続き積極的に協力していくこととしている。
(ロ) 11月の胡ヨウ邦共産党総書記の訪日,84年3月の中曽根総理大臣の訪中は,両国関係を今後更に長期にわたり安定的に発展させるための基礎を堅固にする上で大きな意味を有するものであった。これらの訪問を通じ,両国首脳は,両国が体制の違いを乗り越え,21世紀に向かって平和的,友好的に付き合っていくことを再確認するとともに,今後,「平和友好,平等互恵,相互信頼,長期安定」の四つの原則に基づき,各方面の交流,協力関係を拡大,強化していくことにつき意見の一致を見た。
(ハ) 83年の日中間の貿易額は100億ドルの大台を回復した。対中経済協力は,円借款,無償資金協力,技術協力等様々な分野で順調に行われている。中曽根総理大臣の訪中の際には,84年度以降の新規円借款につき運輸,通信,エネルギーの分野の重点プロジェクトに対しできるだけの協力を行う考えを表明した。
(4) 東南アジア諸国連合(ASEAN)諸国及びビルマ
(イ) インドネシア,マレイシア,フィリピン,シンガポール,タイの5か国は,ASEANという地域協力機構を通じて,政治,経済,文化等の分野で共通の目標に向けて連携,結束を強化し,東南アジアにおける安定勢力としてこの地域の平和と発展に大きく貢献してきている。84年1月には,ブルネイが新たな加盟国として加わり,地域協力の基盤は拡大された。我が国は,政治,経済のみならず歴史的,地理的にも密接な関係を有するASEAN諸国との友好協力関係の増進を最も重要な外交政策の一つとしており,これら諸国の経済・社会開発のための自主努力に対してもできる限り支援してきている。
83年は中曽根総理大臣がASEAN5か国及びブルネイを訪問,ともすれば経済面に片寄りがちであった日・ASEAN関係をより幅広いものとすべく,科学技術協力,青年交流の拡大等を提唱し,長期的に安定した日・ASEAN関係の構築に大きく貢献した。
ASEAN諸国にとって最大の政治・外交問題は,膠着状態にあるカンボディア問題であるが,安倍外務大臣は,83年6月のASEAN拡大外相会議や同年秋の国連総会の場などにおいて,包括的政治解決を求めるASEAN諸国の努力をこれまでのとおり支持する旨表明した。
経済・技術協力の分野でも,我が国とASEAN諸国との協力関係は着実に発展を遂げた。すなわち,中曽根総理大臣のASEAN諸国訪問時の約束のフォローアップとして,プラント・リノベーション協力(老朽化したプラントの再活性化)を推進し,また,12月には東京において科学技術関係閣僚会議を開催,日・ASEAN間の科学技術協力の枠組みを作った。また我が国の資金協力の下,ASEAN工業プロジェクトの第1号として着工したインドネシアの肥料工場が84年1月に完成を見たことは,我が国の対ASEAN協力における象徴的出来事として特筆される。
(ロ) また我が国は東南アジアと南西アジアの境に位置する親日国ビルマとの友好協力関係の増進を重視している。この関連で3月には,安倍外務大臣がビルマを訪問し,サン・ユ大統領以下政府要人との間で有益な意見交換を行った。
(5) インドシナ地域(カンボディア問題)
インドシナにおいては,依然,ヴィエトナムのカンボディアヘの武力介入が継続し,これに反対する民主カンボディア連合政府(シハヌーク大統領,キュー・サンパン副大統領,ソン・サン首相)との間で戦闘状態が続いた。
我が国は,インドシナ,ひいては東南アジア全域の平和と安定のためには,カンボディア問題が一日も早く解決し,ASEAN諸国とインドシナ諸国との間に平和共存関係が樹立されることが望ましいとの基本的立場から,国連総会の累次関連決議及びカンボディア国際会議宣言にのっとったカンボディア問題の包括的政治解決を求める方針を堅持し,立場を同じくするASEAN諸国の外交努力を支援した。
我が国は,かかる外交努力の一環として,中曽根総理大臣のASEAN諸国歴訪の際,総理より各国首脳に対し,また,日・ASEAN外相会議では安倍大臣より,包括的政治解決に向けてのASEAN諸国の努力を支持するとの基本姿勢を再確認するとともに,カンボディア難民に対する継続的支援を表明した。
また,秋の国連総会では,従来に引き続き,カンボディア情勢に関するASEAN決議案の共同提案国となった。同決議案は,前年と同様,圧倒的多数を得て採択された。
(6) インドシナ難民問題
インドシナ難民の発生後9年を経た今も,東南アジア地域には約16万人(84年3月末現在)の難民が滞留しており,東南アジア諸国をはじめ関係各国は長期化した本問題への対応に苦慮している。
我が国は,本問題が依然として人道上及び東南アジア地域の平和と安定にかかわる深刻な問題となっているとの認識から,83年度も国連難民高等弁務官(UNHCR)等を通じ総額約6,000万ドルに上る大口の資金援助を行ったほか,定住及び一時受入れ(84年3月末現在の受入れ累積総数約1万人)の面でも引き続き積極的に協力した。
なお,83年4月「国際救援センター」(収容規模720名)が新設され,本邦一時滞在ボート・ピープルの処遇が改善された。
(7) 南西アジア
南西アジア地域は,9億にも及ぶ人口を擁し,中東と東アジアを結び,インド洋を抱える極めて重要な地域である。
我が国は,この地域の動向がアジア全域及び世界の平和と安定に直接結び付いているとの見地から,従来,同地域諸国との間で経済技術協力を中心に友好協力関係の増進に努め,同地域の安定強化に寄与してきた。とりわけ,ソ連のアフガニスタン軍事介入以降,同地域の重要性が一段と増したことにかんがみ,政治的対話の活発化に努め,例えば7月にはパキスタンのハック大統領が,同国の大統領としては23年ぶりに我が国を公式訪問した機会に,中曽根総理大臣との間で国際情勢を中心に2回にわたり会談を行った。また84年4月末から5月初めにかけては,中曽根総理大臣が,インド,パキスタン両国を,我が国の総理としては23年ぶりに公式訪問し,ガンジー首相,ハック大統領と国際政治・経済の諸問題につき有益な意見交換を行った。
これらの首脳レベルでの対話を通じて,インド,パキスタンをはじめとする南西アジア諸国との友好協力関係を更に深め,我が国がアジアの平和と繁栄に貢献していく基盤が強化されたと言えよう。