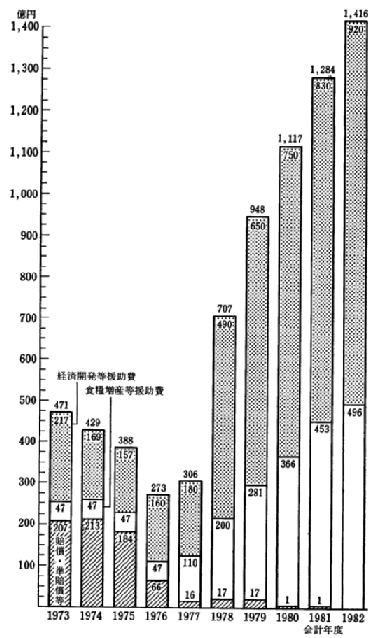
第3節 無償資金協力
1.概況
無償資金協力とは,開発途上国がその経済・社会の発展のための計画を実施する上で必要な施設・資機材及び役務を調達するために必要とする資金を返済義務を課さないで供与する形態の援助であり,政府開発援助のうち技術協力とともに二国間贈与を構成するものである。
我が国の無償資金協力は68年度に開始され,今日に至るまでその資金量は年々大幅に増大しており,現在では我が国のODAの推進,とりわけその質を向上させる重要な柱となっている。また,無償資金協力は,開発途上国の経済・社会開発,民生の安定及び住民の福祉の向上に寄与することを目的として行われているが,同時に我が国と当該開発途上国との友好・協力関係の増進に多大の貢献を行っている。
我が国無償資金協力は,経済開発等援助費による(イ)一般無償援助,(ロ)水産関係援助,(ハ)災害関係援助及び(ニ)文化関係援助並びに食糧増産等援助費による(イ)食糧援助及び(ロ)食糧増産援助から成っている。82年度予算における経済開発等援助費は920億円で,対前年度比約10.8%の増加,また,食糧増産等援助費は496億3,700万円で,対前年度比約9.6%の増加であった。
なお,我が国が55年から実施してきた賠償・準賠償は,76年をもって終了している。
2.経済開発等援助費による無償資金協力
(1)一般無償援助
一般無償援助は,経済開発等援助費の主要な部分を構成しており,82年における交換公文締結ベースの一般無償援助実績は,供与国42か国,供与総額約816億円に達している。
一般無償援助は,開発途上国がその経済・社会開発,民生の安定,福祉の向上を推進する上で基礎となる計画を実施するために必要な資金を供与するものであり,基礎生活分野での援助及び人造り援助に重点を置いている。具体的には,教育,医療・保健,農業,民生・環境改善,通信,運輸などの分野で,経済的収益性が低く,開発途上国が自己資金あるいは借入資金により実施することが比較的困難な案件を対象としている。
82年における交換公文締結ベースの一般無償援助実績を分野別に見ると次のとおりである。
無償資金協力予算の推移
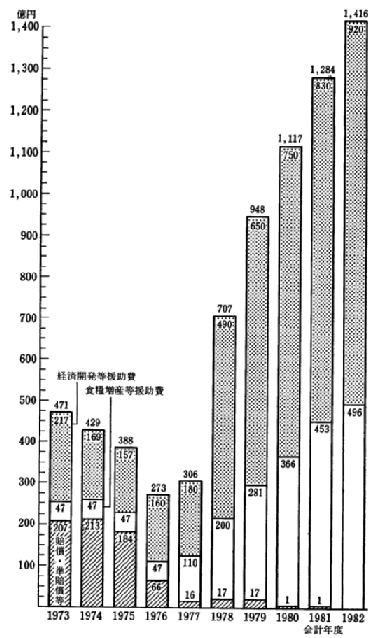
(注)1977年度以降の賠償・準賠償等は対モンゴル経済協力(特殊対外債務等処理費)。
1977年度以降の食糧援助等は食糧援助及び食糧増産援助。
(イ)教育・研究分野
マレイシアの職業訓練指導員上級技能訓練センター,タイの職業訓練開発センター,インドネシアの地質研究所及びフィリピンの高等化学研究所建設計画等職業訓練センターや研究所の建設計画を中心に総計9件のプロジェクトに対し92億5,000万円の供与となっている。
(ロ)医療・保健分野
81年度から援助を開始したスリ・ランカのスリジャヤワルダナプラ総合病院及び中国の中日友好病院に対する援助の継続に加え,ネパールのトリブバン大学教育病院,パキスタンのイスラマバード小児病院,スーダンのカルトゥーム訓練病院等7件の病院建設計画のほか,タイのプライマリヘルスケア訓練センター,ケニアの中央医療研究所設立計画等総計26件のプロジェクトに対し289億3,000万円の供与となっている。
(ハ)農業分野
タイの中央造林研究訓練センター及びビルマの中央農業開発訓練センター建設計画エジプトの米作機械化計画等総計10件のプロジェクトに対し105億5,400万円の供与となっている。
(ニ)民生・環境改善分野
ケニアの地下水開発計画,コモロの飲料水供給計画,ビルマの消防装備強化計画等総計27件,145億6,000万円の供与となっている。
(ホ)運輸分野
パキスタンのダリア・カーン~デラ・イスマイル・カーン橋梁建設計画,ブルンディ,ルワンダの公共輸送力増強計画等総計13件のプロジェクトに対し94億3,000万円の供与となっている。
(ヘ)通信分野
タイのスコタイ・タマチラート放送大学建設計画,ビルマのテレビ放送施設拡充計画等総計3件のプロジェクトに対し57億3,500万円の供与となっている。
また,我が国は,78年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)貿易開発理事会(TDB)閣僚会議の決議に基づき,我が国に対して公的債務を有している貧困開発途上国(18か国)を対象に,債務救済のための無償援助を78年度から実施しており,82年には13か国に対し,約31億4,400万円を供与した。
一般無償援助地域・分野別実績(注)(単位:億円,%)
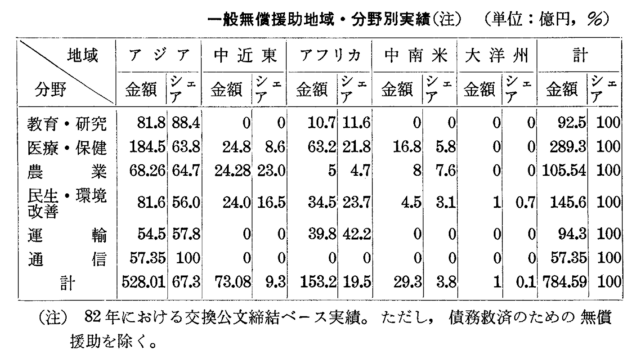
(2)その他
(イ)水産関係援助
水産関係援助は,開発途上国の水産振興に寄与するために,漁業訓練施設,訓練船,水産研究施設建設関係プロジェクトなどに協力するものである。82年においては,ペルーの水産物利用開発計画タイの内水面漁業センター建設計画ソロモンの漁村開発計画等総計16件のプロジェクトに対し94億8,500万円の供与となっている。
(ロ)災害関係援助
災害関係援助は,風水害,地震,干魃などの自然被害を被った国に対し緊急に実施される援助及び紛争等により発生した難民・被災民に対し人道上の観点から行われる援助からなる。82年においては,トンガのサイクロン被害,ニカラグァ,ホンデュラス等の洪水被害及びカンボディア難民・アフガン難民・アフリカ難民等に対し総計11件,18億2395万円の援助を実施した。
(ハ)文化関係援助
文化関係援助は,開発途上国における教育及び研究の振興,文化財及び文化遺跡の保存利用,文化関係の公演及び展示などの開催のために使用する資機材の購入に必要な資金を供与するものであり,75年度から文化交流に関する国際協力の一環として実施されている。82年においては,総計23件,9億600万円の援助を実施した。
3.食糧援助
我が国の食糧援助は,GATTのケネディ・ラウンド(KR:Kennedy Round)関税一括引下げ交渉の一環として成立した「1967年の国際穀物協定」,及び右協定を引き継いだ「1971年の国際小麦協定」を構成する「1980年の食糧援助規約」に基づいて実施されている。
この食糧援助規約は,74年の世界食糧会議において採択された開発途上国に対する年間1,000万トン以上の穀物の援助目標を国際社会の共同の努力により達成することをその目的としており,我が国をはじめ米国,EC諸国,カナダ,オーストラリア等を加盟国として加盟各国の穀物による年間最低拠出量を具体的に規定している。
我が国は同規約に基づき,毎年小麦換算で30万トンの最低拠出義務を負っており,開発途上国が我が国産米,第三国産穀物を購入するために必要とする資金を無償で供与している。82年における交換公文締結ベースの食糧援助実績は,23か国,2国際機関に対し総額219億2,400万円であった。
国際機関に対するものは世界食糧計画(WFP)を通ずる対カンボディア難民・タイ被災民援助及び対アフガン難民援助,国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通ずる対パレスチナ難民援助に向けられた。国際機関に対する援助を除く食糧援助供与先を地域別に見ると,アジア地域44.2%,アフリカ地域42.0%,中近東地域13.8%となっており,このうちLLDCが約45%を占めている。
4.食糧増産援助
我が国は,開発途上国の自助努力による食糧生産の増大を支援するため,77年度から「食糧増産援助」として新たに予算措置を講じ,開発途上国が食糧増産プロジェクトを遂行する上で必要とする肥料,農薬,農機具等の農業物資の購入のために必要な資金を無償供与している。この援助は,別途一般無償援助で実施されている各種農業プロジェクト援助と共に,開発途上国の農業開発に大きく貢献している。
82年における交換公文締結ベースの食糧増産援助実績は,26か国に対し,総額309億円であった。その地域別内訳は,アジア74.8%,アフリカ11.3%,中近東7.4%,中南米5.8%,大洋州0.7%となっており,このうちLLDCが28.8%を占めている。
5.無償資金協力の効果的実施
前述のように,我が国の無償資金協力の規模は年々拡大の一途をたどっているが,それゆえに従来にも増して効果的かつ適正な援助を実施する必要性が高まっている。
このため,78年度から「技術協力と密接に関連する無償資金協力」の実施促進に係る業務(契約の締結に関する調査,斡旋,連絡,その他必要な業務及びこれら契約の実施状況に関する必要な調査)については,JICAが外務省と密接な連絡をとりつつ行うこととなっており,交換公文締結後の諸手続の迅速化に努めている。
また,77年度から各界の有識者から成る無償援助審査諮問委員会を経済協力局長の諮問機関として設置し,専門的な見地からの意見・助言を求めることにより,我が国の無償援助政策の企画・立案及び実施に反映させてきている。さらに既に援助を完了した案件については,在外公館自ら又は調査団の派遣等を通じ評価調査を実施している。