
2. 我が国と中近東地域との関係(中東情勢と我が国の対応)
(1)レバノン情勢
我が国は,6月に始まったイスラエル軍のレバノン侵攻は,レバノンの領土主権を侵害し当該地域の安定を脅かすのみならず中東和平問題の解決を一層複雑にするとの観点から,侵攻開始直後,いち早く国連安全保障理事会に単独で停戦案を提案するとともに宮澤外務大臣臨時代理談話(資料編参照)を発表し,即時停戦を呼び掛け,かつ,イスラエルの行為を非難した。また関係当事者と緊密な連絡を保ちつつ,これら当事者に対し紛争拡大を防止すべく働き掛けた。さらに,我が国は6月及び11月の2回にわたり,パレスチナ人を含むレバノン被災民に対し合計200万ドルの緊急援助を行った。
(2)中東和平問題
我が国は関係当事者に対し,あらゆる機会をとらえ現実的な立場から和平実現を図るよう説得を続けている。かかる観点から,我が国は,9月にレーガン米国大統領の発表した中東和平新提案(資料編参照)について,中東の包括的和平に至る積極的な要素を含んでいるとしてこれを高く評価する旨の宮澤外務大臣臨時代理談話(資料編参照)を発表した。また,12月にはフェズ提案に基づくアラブ側の立場を説明するために来日したフセイン=ジョルダン国王に対しても,中曽根総理大臣から和平への現実的対応を申し入れた。
我が国は,PLOは和平問題の重要な関係当事者であるとの観点からPLOと積極的な対話を行うよう努めている。かかる政策の一環として,5月し,にはファフーム=パレスチナ民族評議会(PNC)議長が来日した。また,83年3月には西岸パレスチナ人の有力者であるミルヘム元ハルフル市長が来日した。
(3)イラン・イラク紛争
イラン・イラク紛争は依然として,解決の兆しを示していないが,我が国はイラン,イラク両国と友好関係にあり,同紛争の継続は我が国とこれら両国との関係発展の大きな障害となっている。我が国は,80年9月紛争拡大以来一貫して早期終結を呼び掛けてきたが,5月戦闘が激化するに及び,櫻内外務大臣の談話(資料編参照)という形で,両国に対し,一日も早く戦闘を停止し,本紛争解決のための話合いに入るよう改めて要請した。また10月末,鳩山特使がイラクを,松永外務審議官がイランを各々訪問した際にも,重ねて紛争解決を勧めた。さらに83年に入ってからは,イラン原油流出事故との関連で,ノールーズ油田の位置する海域での戦闘を停止し,原油流出源封鎖作業に協力するよう現地駐在大使を通じ両国に対し申し入れた。
(4)アフガニスタン問題
ソ連によるアフガニスタンヘの軍事介入が依然として続く中で,我が国は,3月の「アフガニスタンの日」(欧州議会が制定)に際し外務大臣談話を発表した。これは,ソ連の軍事介入は国際法及び国際正義に反するものであり,直ちにソ連軍の全面撤退が行われ,アフガン国民が内政不干渉,自決権尊重の原則に基づき自らの手で国内問題の解決を図り得るようにすべきであるとの従来の我が国の立場を改めて表明したものである。また11月の国連総会においても,我が国は,ソ連軍の全面撤退等を骨子とする総会決議を強く支持した。
なお,パキスタンへ流入するアフガン難民は300万人近くにも達すると言われているが,我が国は,かかる難民に対し,国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)及び世界食糧計画(WFP)を通じて82年度に約1,500万ドルの援助を行った。
<要人往来>

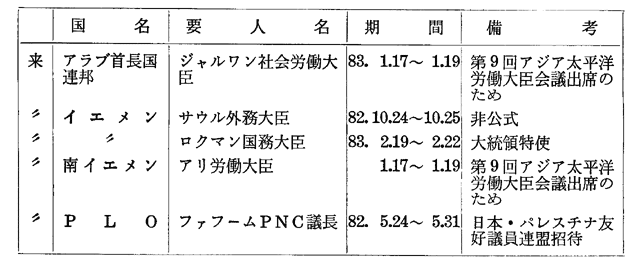
<貿易関係>(1982年,単位:百万ドル,( )内は対前年比増減率%)
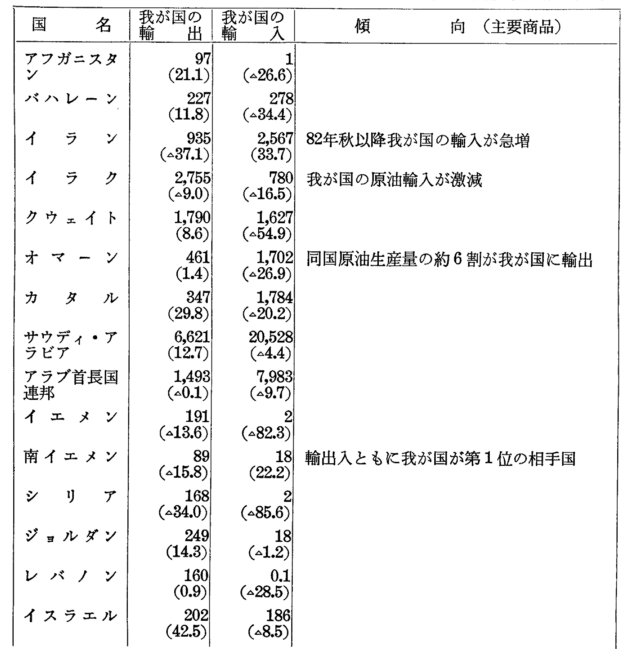
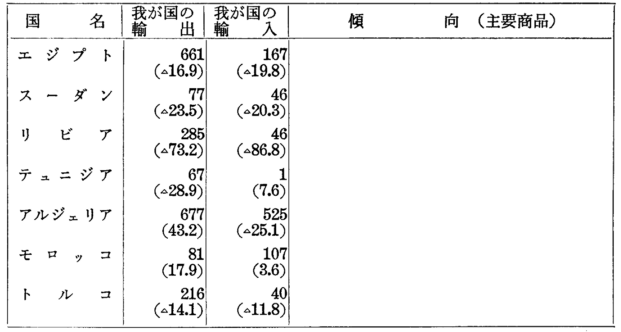
(出所:大蔵省通関統計)
<民間投資>(単位:百万ドル)
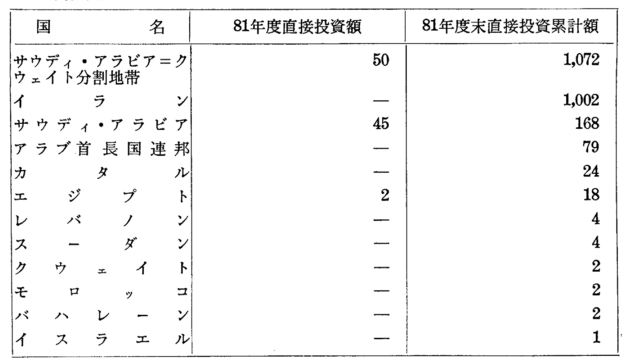
(届出ベース)
(注)サウディ・アラビア=クウェイト分割地帯とは,1970年5月に分割された旧中立地帯を指す。
<経済協力(政府開発援助)>(1982年,単位:百万円,人)
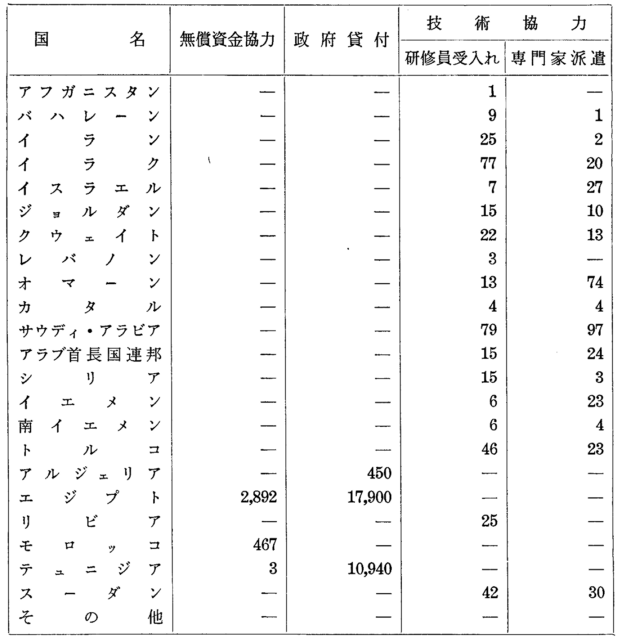
(約束額ベース)(DAC実績ベース)