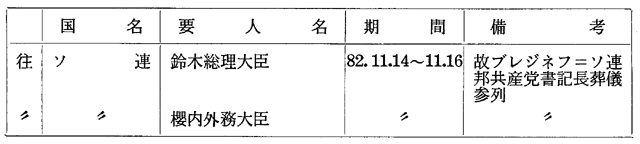
2.我が国とソ連・東欧諸国との関係
(1)ソ連
(イ)北方領土問題
(a)1月20日から22日までモスクワにおいて第2回目ソ事務レベル協議が行われた。日本側から北方領土問題に関連し,73年10月の日ソ共同声明のラインにソ連側が戻ること,北方領土のソ連軍の速やかな撤退,平和条約締結交渉を早期に行うべきことをソ連側に伝えたのに対し,ソ連側からは,「北方領土問題は存在せず」との従来の姿勢と異なる対応は見られなかった。
(b)6月1日,グロムイコ外務大臣を表敬訪問した高島駐ソ大使は,日ソ間に現存する不信感を除くためには,ソ連側が少なくとも領土問題の存在を認めることが必要としたのに対し,グロムイコ外務大臣は不信感の存在は認めたが,ソ連側に責任はないとし,領土問題は存在しないとの従来の立場を繰り返した。
(c)6月9日,第2回軍縮特別総会に際しニューヨークで日ソ外相会談が行われた。櫻内外務大臣から,日ソ国交回復後,平和条約締結交渉が途切れているのは残念である。1956年の日ソ共同宣言,73年の日ソ共同声明からも明らかなとおり,未解決の懸案たる領土問題を話し合うことが日ソ関係の発展のためにまず重要である旨述べたのに対し,グロムイコ外務大臣は,73年の日ソ共同声明には領土という字句はない,平和条約の締結には賛成であるが,日ソ間に共通の言葉が見つかっていない,領土問題についてはソ連は全く違った立場を取っており,既にブレジネフ書記長等が種々の機会に言っているので改めて言う必要はない旨述べた。
(d)他方・国内的には北方領土返還の声は引き続き大きくなりつつあり,8月20日には北方領土問題等解決促進特別措置法が国会で可決され,返還運動のための国内基盤の整備が一段と図られることとなった。また,8月21日から23日まで櫻内外務大臣は現職の外務大臣として4回目の北方領土の現地視察を行い,本問題解決に対する政府の不動の姿勢と不退転の決意を改めて内外に表明した。
(e)10月1日,櫻内外務大臣は,第37回国連総会一般討論演説において,北方領土問題に対する我が国の基本的立場を国際世論に訴えた。
10月4日,櫻内外務大臣はグロムイコ外務大臣と会談し,6月の会談に引き続き北方領土問題を解決して平和条約を締結する必要を述べるとともに,外相レベルにおける交渉を継続するためグロムイコ外務大臣の訪日を要請した。これに対し同大臣は日本側が領土問題を持ち出すことが日ソ関係の発展を妨げているとし,領土問題に対するソ連の見解は既に何度も表明されている。自分の領土は自分の領土である旨述べるとともに,グロムイコ外務大臣自らの訪日問題に対しては,時期と雰囲気が問題であるとして消極的姿勢を示すにとどまった。
(f)12月6日に安倍外務大臣が,同9日に中曽根総理大臣がそれぞれパヴロフ駐日ソ連大使と会見し,領土問題に対する我が国の基本的立場を改めて同大使に伝達し,本問題の解決が日ソ関係を進めていく上での基本的条件であることをソ連側に明らかにした。
(ロ)ポーランド問題関連対ソ措置
2月23日,政府はポーランド情勢との関連で,ソ連の自制を求め,将来の介入を抑止するため一定の具体的措置をとることとして,その内容を宮澤官房長官談話(資料編参照)により発表した。
その後,ポーランド情勢には基本的改善は見られず,政府は1年余にわたって,この措置を維持してきている。
(ハ)東西経済関係
81年12月末,米国はポーランドの戒厳令施行はソ連に責任があるとして,7項目の対ソ措置を発表した。その中には,米国製の石油,ガス関連機器の対ソ輸出停止措置が含まれていた。
6月,ヴェルサイユ・サミットの後,米国はポーランド情勢に基本的改善が見られないとして,この石油・ガス関連対ソ措置を強化し,ライセンス生産等により米国の技術が含まれた石油・ガス関連機器が第三国からソ連に輸出されることを禁止した。これに対し,ヤンブルグ・ガス・パイプライン・プロジェクトヘの機材をソ連に提供している欧州諸国は,このような米国の対ソ措置強化は米国内法の域外適用であり,国際法違反であるとして強く反発し,米欧対立が高まることとなった。
我が国としても,ヴェルサイユ・サミット等で合意された東西経済関係は,西側の政治,安全保障上の目的と合致する形で取り進めるべきであるとの考え方は理解できるとしつつも,このような米国の措置は,我が国が75年以来,ソ連との間で進めてきているサハリン・プロジェクトの実施に大きな影響を与えるのみならず,国際法上も正当化し得ない旨米側に申し入れ,その撤廃を求めた。
このような情勢を背景として,10月から11月にかけて,米国の提唱により,サミット参加国(及びEC)大使会議がワシントンで開催され,西側内部の意見の相違を調整し,同時に東西経済関係をどのように取り進めるかについての認識を一致させるための努力が払われた。その結果,西側主要国内で,対ソ・東欧経済関係に関し,戦略物資,高度技術,信用供与政策,エネルギー等の分野において分析研究を行っていくことが合意された(ただし,フランスはこの合意には不参加を表明した)。
このような合意をも踏まえ,米国は11月13日,大統領演説の形で石油・ガス関連機器に関する制裁措置を解除することを発表した。この決定により,我が国のサハリン・プロジェクトの実施上被っていた諸困難は取り除かれ,また,ヤンブルグ・プロジェクトを巡る米欧間の対立も一応解消に向かうこととなった。
(ニ)シベリア開発協力
(a)日ソ間でこれまでに具体化したシベリア・極東地域の資源開発を中心とする経済協力案件として現在実施中のものは,南ヤクート原料炭開発,サハリン島大陸棚石油探鉱,ヤクート天然ガス探鉱及び第3次極東森林資源開発の4件がある。
(b)現在実施中のプロジェクトのうち,サハリン島大陸棚石油探鉱プロジェクトについては,米国の石油・ガス関連機材の対ソ輸出に関する措置により,82年度の探鉱作業は影響を受け83年度にずれ込むことになった。
南ヤクート及び第3次極東森林資源開発の二つのプロジェクトは順調に実施されている。
(ホ)日ソ貿易
(a)82年の日ソ貿易のうち輸出は38億9,900万ドルで対前年比19.6%増と好調な伸びを示したが,輸入は16億8,200万ドルで対前年比16.8%減と落ち込んだ。この結果,貿易総額は55億8,100万ドルで過去最大となったが,対前年比は5.6%増にとどまった。輸出の伸びは,主として従来の中心品目たる鉄鋼,機械機器の増加によるものであり,他方,輸入の減少は,81年に著増した金の輸入が減少したことに加え,従来の主要品目である木材,非鉄金属等の不振によるものである。
なお,82年の日ソ貿易が我が国対外貿易総額に占める比率は2.06%である。
(b)永野ミッションの訪ソ
83年2月22日から26日まで,永野重雄日本商工会議所会頭を団長とする貿易経済代表団(総勢約250名)が訪ソし,日ソ問の貿易・経済関係につきソ連側関係者との間で協議を行った。
また,永野会頭は,訪ソ中チーホノフ首相,アルヒーポフ第一副首相,バトリチェフ外国貿易相等と会談した。
(ヘ)日ソ漁業関係
(a)日ソさけ・ます交渉
日ソ漁業協力協定に基づき,82年における日本によるさけ・ます操業に関する日ソ政府間交渉が,4月13日から4月23日までモスクワで行われた。この結果,ソ連200海里外の北西太平洋における日本のさけ・ます漁獲量を42,500トンとする等の内容の議定書が締結され,また,ソ連に対する漁業協力費として,日本側が40億円を負担することとなった。
(b)「日ソ」及び「ソ日」漁業暫定協定延長交渉
日ソ両国のそれぞれ相手国200海里水域内における漁業に関する「日ソ」及び「ソ日」漁業暫定協定が82年末に失効するため,両協定の有効期間を延長し,83年の双方の漁獲量等を定めるための交渉が11月24日から12月6日まで東京で行われた。この結果,両協定の有効期間を83年末まで1年間延長する議定書が締結され,日ソ双方の相手国200海里内での漁獲量を日本側75万トン,ソ連側65万トンとすることなどが定められた。
(c)83年2月にカーメンツェフ=ソ連漁業大臣が訪日し,金子農林水産大臣との間で日ソ間の漁業関係につき広範な意見交換が行われたことは今後の日ソ漁業関係にとり有意義なことであった。
(ト)墓参
6月,政府は,82年の北方4島,ソ連本土及び樺太への政府ベースの墓参実施をソ連政府に対し申し入れた。これに対し,ソ連側は,8月,樺太(豊原,真岡,本斗)への墓参を認めるが,その他の諸地域への墓参については同意できない旨回答した。政府は,その他の申入れ地域についても人道的見地から墓参ができるようソ連側の再考を求めたが,ソ連側は上記の回答が最終的回答であるとして我が方の要請に応じなかった。以上の結果,82年においては,9月16日から9月23日まで樺太墓参のみが実施された。
(チ)未帰還邦人
政府は,日本への帰国指導を行うとともに,ソ連側がこれら未帰還邦人に対し遅滞なく日本への帰国ないし一時帰国を許可するよう機会あるごとに要請した。82年においては,4名が一時帰国を行った。
<要人往来>
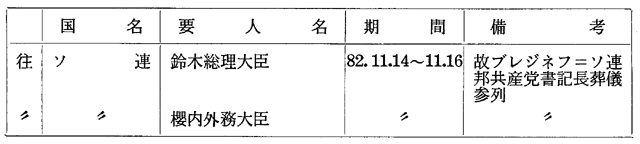
<日ソ貿易>(1982年,単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率%)
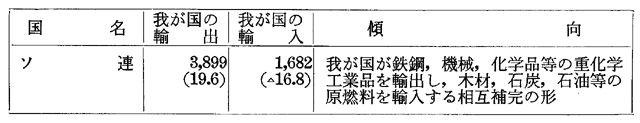
(出所:大蔵省通関統計)
(2)東欧諸国
(イ)ポーランド情勢に対する我が国の立場81年12月13日ポーランドにおいて戒厳令が布告されたことに対し,政府はかかる事態に深い憂慮の念を表明する外務大臣談話(12月25日)を発表した。しかし,その後事態の改善は見られず,また,右事態はソ連の圧力の下に生じたものと判断されたので,政府は,ポーランド当局に対し異常な事態を早急に終了させるよう,またソ連に対しては自制するよう求めた外務大臣談話(資料編参照)を1月14日に発表した。我が国のかかる立場については,政府は1月6日にソ連側に対し,また1月7日にポーランド側に対しそれぞれ申し入れた。
さらに,ポーランドを巡る事態に基本的改善が見られないことから2月23日,政府としては,西側諸国の結束を維持し,西側諸国と協調していくことが重要であるとの認識の下に,対ソ連措置とともに対ポーランド措置について宮澤官房長官談話(資料編参照)を発表した。
かかる我が国のポーランド情勢に対する基本的考え方は,10月,国連総会の際に行われた櫻内外務大臣とオルショフスキ=ポーランド外務大臣との会談等を通じ,ポーランド側に引き続き表明してきている。
(ロ)その他東欧諸国との関係
我が国の東欧諸国との通商関係は,12月に債務繰延協定が締結されたルーマニアとの貿易額が前年比で半減したのをはじめ,東欧諸国の対外ポジションの悪化の影響を受け,東独を除き前年比減を記録した。
(ハ)ユーゴースラヴィア
ユーゴースラヴィアは対外収支バランス,インフレ高進など困難な状況にあり,同国政府としても経済安定化のための諸措置をとりつつあるが,83年には対外債務支払いにも支障を生ずる恐れがあったため,82年末,西側諸国は対ユ経済支援のための会合をパリにて開催し,その後スイスのベルンに場所を移して1月下旬総額約13億6,000万ドルの経済支援を決定した。我が国としてもユーゴースラヴィアの東西関係における重要性にもかんがみ,他の西側諸国と共に対ユ経済支援に参加し,総額6,000万ドルの輸出信用供与を決定した。
<要人往来>
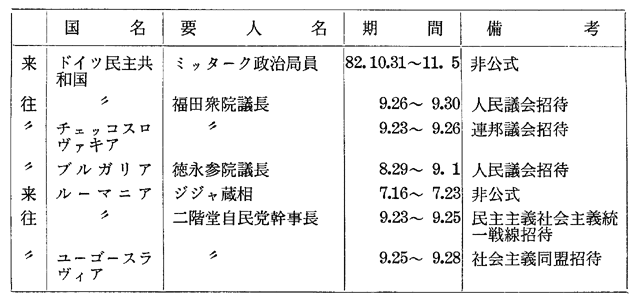
<貿易関係>(1982年,単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率先)
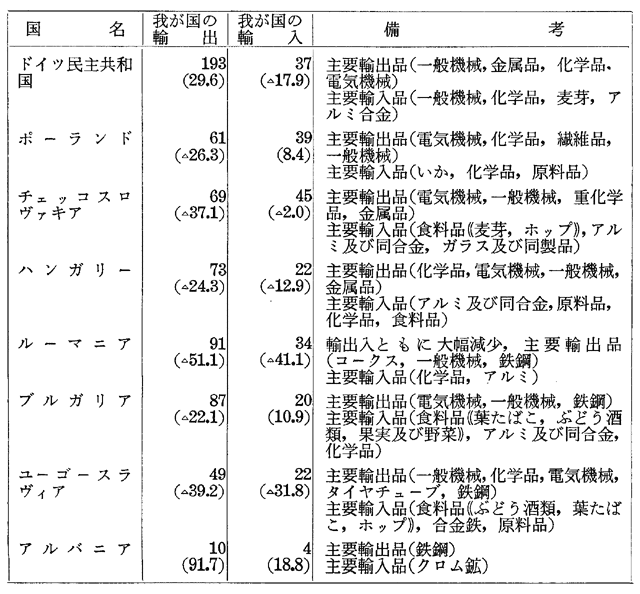
<民間投資>(単位:百万ドル)
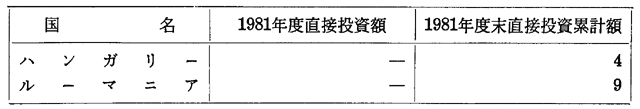
(届出ベース)
<経済協力(政府開発援助)>(1982年,単位:百万円,人)
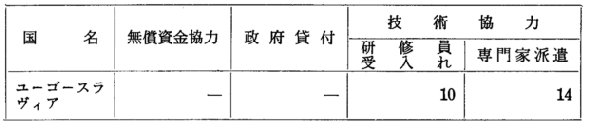
(約束額ベース)(DAC実績ベース)