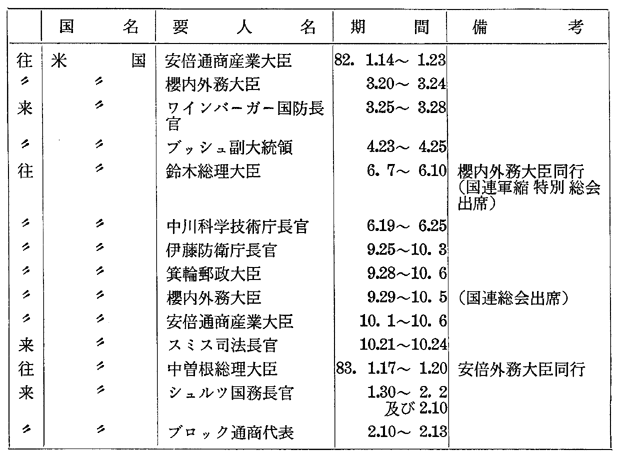
2.我が国と北米地域との関係
(1)米国
(イ)日米関係全般
(a)日米両国は,自由と民主主義という基本的価値を共有するとともに,日米安全保障条約に基づく安全保障面での協力関係,往復で年間600億ドル近い貿易に代表される密接な経済関係,科学技術,文化等広範な分野での緊密な友好協力関係を築き上げてきた。我が国は,かかる米国との安定した友好協力関係を強化,発展させることが,日米両国民に多大の利益をもたらすとともに,世界の平和と繁栄にとって欠くべからざるものであるとの認識の下に,日米関係の強化,発展を我が国外交の基軸としてきた。
(b)他方,米国経済が依然として不況下にあり我が国の対米貿易収支が大幅な黒字を記録(82年度122億ドル)していることを背景に,我が国の市場開放を求める米国の要求は高まりを見せ,また,議会を中心として,米国内では保護主義的動きが見られるようになってきた。さらに,東西関係,中東,インドシナをはじめとする国際情勢が依然厳しい状況の下で米国は自らの国防力の強化に努める一方で,日米安保条約の円滑かつ効果的な運用を図ることや,我が国が一層の防衛努力を行うよう期待を高めている。
(c)このように日米関係の現状には相当厳しいものがあるとの認識の下に,中曽根総理大臣は83年1月に訪米し,レーガン大統領をはじめとする米国指導者と会談し,大統領との間に個人的信頼関係を確立するとともに,日米同盟関係を再確認した。
(ロ)日米経済関係
(a)82年には日本の市場開放が年初から大きな問題であった。1月の安倍通商産業大臣訪米,2月の江崎自民党国際経済対策特別調査会長ほかの訪米,3月の第3回日米貿易小委員会の開催と櫻内外務大臣訪米等の機会をとらえて米側は残存輸入制限,たばこ,基準認証手続等につき繰り返し市場開放を要請した。また1月半ばには米議会に相手国の貿易障壁を米国と同程度に撤廃させようとする「相互主義法案」が提出されるなど情勢は厳しさを増した。これに対し日本側は1月30日の経済対策閣僚会議において67項目に及ぶ輸入検査手続等の改善などを決定したほか,5月28日にはヴェルサイユ・サミットを念頭において市場開放措置「第2弾」を決定,200項目以上にわたる関税の撤廃・引下げ,輸入制限の緩和,たばこの輸入拡大等を図った結果,夏に向かって日米経済関係は小康を得た。
(b)しかし秋に入り米側の市場開放要求は厳しさを加え,特に10月ハワイで開催された牛肉・かんきつ等農産物輸入を巡る日米協議において米側は牛肉・かんきつの輸入制限を現行日米合意の期限である84年4月以降完全に撤廃せよという極めて厳しい要求を示した。また長引く米国経済の不況を背景とする保護主義圧力は一層強まり,自動車部品の一定割合を米国内で生産することを義務付ける「ローカル・コンテント」法案が中間選挙に臨んで支持者を増加させ,12月には遂に下院を通過するに至った。
(c)このような状況で開催された12月の第4回日米貿易小委員会において,米側は国内の保護主義圧力を抑えるため,輸入検査手続等の改善,たばこ,チョコレート等米側関心品目の関税の一層の引下げ,農産物の輸入拡大等,一層の市場開放努力を要請し,早急な対応を求めた。これに対し日本側は,12月にたばこ,チョコレートについての思い切った関税引下げを含め「第2弾」と合わせ計323品目について関税撤廃・引下げを決定し,さらに83年1月には経済対策閣僚会議において官房長官の下で基準・認証制度について法改正を含め全面的な再検討を行うこと,通商オンブズマン制度について諮問会議開催等機能強化を図ること等を決定した。こういつた迅速な対応を可能とした中曽根総理大臣の指導力は米側に好感をもって迎えられ,83年1月の総理大臣訪米に際してはレーガン大統領自ら市場開放努力を評価する旨述べた。また懸案の牛肉・かんきつ問題については中曽根総理大臣から,双方が冷静となって専門家会合に委ねるべきであるとの考えが示され,解決への方向が明らかとなった。
(d)その後,「ローカル・コンテント」法案との関係が注目された対米自動車輸出自主規制は,83年2月のブロック通商代表訪日の際,現行どおり168万台で3年目も延長されることとなった。3月には基準・認証制度の全面的見直しが完了し,内外無差別の原則を法制度的に確保するため17の法律を改正すること,基準・規格制定過程の透明性の確保,外国試験データの受入れ,手続の簡素化・迅速化等を図ることが決定され大きな進展を見た。
(e)82年にはまた先端技術が日米間で注目を浴びた。安倍通商産業大臣訪米の際に合意された日米先端技術産業作業部会は3回の会合の後に,貿易・投資に係る開放性の確保,内国民待遇の徹底,技術協力等を骨子とする提言を取りまとめ,83年2月のブロック代表訪日時に安倍外務大臣との間で正式に右提言実施の意思を確認した。他方米工作機械メーカーの提訴に端を発する日本の産業政策批判は特に先端技術産業の分野での施策(「ターゲティング」)が不公正であるとの非難となっており,米議会を中心にその動向が今後注目される。
(ハ)日米漁業関係
(a)我が国は,米国の漁業水域における漁獲活動を規定した日米漁業協定が12月31日に満了することとなっていたため,2月以来新たな漁業協定を締結すべく米側と交渉を行ってきた。米側は近年の自国水産業振興政策を背景に厳しい態度で交渉に臨んできたが,我が方から,これまでの対米漁業協力及び漁獲実績などを挙げて米国との特殊かつ伝統的な漁業関係を強調した結果,協定案文につき最終的合意を見,9月10日,ワシントンにおいて日本側大河原駐米大使と米国側クロンミラー大使との間で署名され,日米漁業新協定は83年1月1日発効した。
(b)新協定は,旧協定に比し,米国内法との関係から米国の水産業の発展のための協力に関する条項が新たに設けられているなど若干の相違はあるが,基本的には旧協定を踏襲しており,新協定と共に合意された合意議事録では,他の入漁国には見られない特殊かつ伝統的な漁業関係が反映されたものとなっている。
(c)一方,米国は自国水産業振興のため外国漁業に対する規制を強めてくる傾向にある。例えば,80年に漁業保存管理法が大幅に改正されたのは,その目的が米国水産業の発展,外国漁業の段階的削減にあるとされており,また,83年3月,スチーブンス議員が排他的経済水域設定に関する大統領宣言実施のため上程した法案には,原則として88年以降外国への漁獲割当をゼロとする条項が含まれている。
(ニ)日米安全保障条約
(a)緊密な協議・協力
日米安保条約は,我が国のみならず,極東の平和と安全の維持に大きく寄与してきている。82,83年においても,日米安保条約の円滑かつ効果的な運用を図るため,日米間において引き続き緊密な協議及び協力が行われた。
(i) 3月には,櫻内外務大臣が訪米し,レーガン大統領,ヘイグ国務長官などと現下の国際情勢及び二国間問題につき意見交換を行ったが,その際,米側は,我が国の継続的な防衛力整備についての期待を表明したのに対して我が国は,防衛計画の大綱に従って着実に防衛力を整備していくとの基本的な考え方を説明した。
また,3月ワインバーガー国防長官が来日し,国際軍事情勢,安全保障問題などについて鈴木総理大臣,櫻内外務大臣及び伊藤防衛庁長官と意見交換を行い,我が方は,改めて日本が行っている防衛努力について説明した。
(ii) 9月には,伊藤防衛庁長官が訪米し,ワインバーガー国防長官らと会談した。日本側が厳しい財政状況下で防衛力整備に努力していることを説明したのに対し,米側からは,我が国がなお一層防衛努力を行うことを期待する旨の発言があった。なお,この会談の際米国のF-16戦闘機の三沢配備計画に対し,日本政府としては基本的に協力する旨の意向を伊藤長官から表明した。
(iii) また,櫻内外務大臣は,10月,第37回国連総会出席の機会に,シュルツ国務長官と会談し,現下の国際情勢及び防衛問題を含む日米関係などについて意見交換を行った。
(iv) 83年1月には,中曽根総理大臣が訪米し,レーガン大統領,シュルツ国務長官及びワインバーガー国防長官などと会談した。日米首脳会談で,中曽根総理大臣は,我が国の基本的な防衛政策について説明するとともに,今後とも引き続き防衛力整備に努めていく旨述べた。
(v) 追って同月下旬には,シュルツ国務長官が来日し中曽根総理大臣を表敬するとともに安倍外務大臣と会談した。この会談では世界平和維持の問題,とりわけINF交渉などについての意見交換が行われた。
なお,対米武器技術供与の問題については,一昨年米国政府から日米間の防衛分野における技術の相互交流の要請があり,以来政府部内で慎重に検討を続けた結果,83年1月,米国の要請に応じ,相互交流の一環として米国に武器技術を供与する道を開くこととし,その供与に当たっては武器輸出三原則によらないこととするとの政府の決定が行われた(資料編参照)。
また,83年3月には第14回日米安保事務レベル協議における了解に基づき,日米防衛協力小委員会が開催され,いわゆるシーレーン防衛についての研究が日米間で開始されることとなった。
(b)日米安保体制の円滑な運用
政府は,日米安保条約・地位協定の目的達成と,施設・区域周辺地域の経済的,社会的発展との調和を図るため,在日米軍施設・区域の整理統合を推進してきたが,82年においても施設・区域の全面返還・一部返還が相当数実現した。
また,83年度の在日米軍関連予算は,そのより円滑な駐留に資するよう前年度に引き続き増額された。
(ホ)日米原子力問題
81年10月の新しい日米共同声明・共同決定に基づき,両国政府は,84年末までに,日米原子力協定上の諸規定が,「予見可能で,かつ,信頼性のある態様」で実施され得るような「長期的取決め」を作成することとなっていたところ,6月,米の新対外原子力政策(日本及び欧州原子力共同体(ユーラトム)諸国を対象として,原子力協定上米国が有する事前同意権を包括的に行使するとの内容)が決定された。これを受けて,8月以来協議が行われている。
(ヘ)6日米航空交渉
(a)3月のサンフランシスコにおける日米航空協定改定交渉は,すべての懸案を解決するための最終会合とするとの日米双方の合意に基づき開催されたが,右交渉の大詰めに至り,一括解決の見通しが立たなくなったため,一括解決案の主要項目であった輸送力調整方式,運賃問題等を棚上げし,日米両国間で当面処理を要すべき争点の絞られた関心問題のみの妥結を図るとの部分合意案が日米双方から提案されたが,最終的妥結に至らず,交渉は不調に終わった。
(b)しかし,当面の問題解決のための暫定取決め成立へ向けての努力が4月以来日米双方間で引き続き行われた結果,ヴェルサイユ・サミットの際の日米首脳会談を控え,双方で暫定取決めにつき原則的に了解する運びとなり,右首脳会談における合意を受けて,6月4日ワシントンにおいて両国代表者間で協議記録に署名した。
(c)右協議記録のうち,日米航空協定に関連する部分を日米両国の合意(暫定取決め)とすることが9月3日の閣議において決定され,9月7日ワシントンにおいて大河原駐米大使とトレント運輸副長官との間で書簡を交換し,右暫定取決めは同日発効した。この暫定取決めに署名の日から3年間又は83年末までに再開される日米航空関係の全般的見直しのための交渉の終了までのいずれか遅い時まで有効であり要点は次のとおりである。
(1)米側に対し
(イ)コンチネンタル/ミクロネシア航空
サイパン・名古屋間(週7便,83年4月から)
(ロ)ユナイテッド航空
シアトル/ポートランド・東京間(週7便,83年4月から)
(2)日本側に対し
(イ)貨物便東京・シカゴ間(週2便,双方合意の時点から)
(ロ)貨客便東京・シアトル/シカゴ間(週5便,83年4月から) (ハ)ロス・アンジェルス以遠サンパウロ/リォ・デジャネイロヘ(週2便,84年4月から)
(3)チャーター便年間300便
(片道ベース・発地国主義)を双方で認める(暫定取決め署名時から)。
<要人往来>
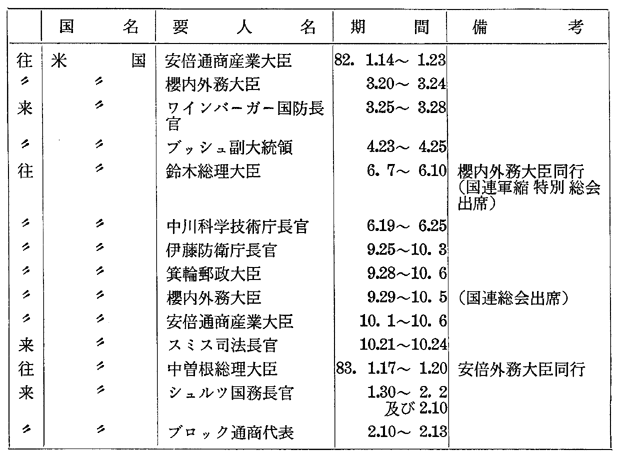
(2)カナダ
(イ)日加経済関係
両国間の貿易動向は,引き続き我が国の工業製品の輸出,カナダの一次産品輸出という相互補完関係により,過去5年間の往復貿易額は年率17%の増加を示している。二国間貿易収支は,一貫して日本側の入超(82年15億8,000万ドル)で推移している。
2月に第4回日加経済協力合同委員会が開催され,両国経済関係の一層の緊密化のため,種々の具体的な進展を得るべく意見交換が行われた。
農林業分野においては,我が国の対カナダ依存度が高い菜種について,11月に日加菜種会議が開かれた。
漁業関係では,5月に日加漁業協議が開かれ,対日漁獲割当及び我が国によるカナダ水産物の買付促進について討議され,その結果,82年の対日割当25,100トンが決定された。
エネルギー関係では,日本は82年も約1,000万トンの主として原料炭をカナダから輸入した。これは日本の全原料炭輸入の約15%に当たる。
また天然ガス(LNG)についても,82年末,カナダ国家エネルギー庁(NEB)における対日輸出プロジェクトに関する審査が大詰めを迎えた(その後83年1月,NEBは対日LNG輸出を許可,カナダ政府もこれを承認した。今後プロジェクトが順調に進めば,86年から対日輸出が始まる。
カナダの対日LNG輸出は,カナダにとって米国以外の国への初のLNG輸出となる)。
投資関係では,3月に対加投資調査団が派遣され,また,80年末に発効した新銀行法によりカナダにおいて外国銀行の設立が可能となったが,83年までに日加双方各7行の銀行が進出し得ることが合意された。
82年においても,対加輸出のうち自動車が問題とされたが,8月に,4月から12月までの対加自動車輸出は約12万台となろうとの見通しを発表することにより,一応の決着を見た。
民間レベルにおいても,5月,札幌において第5回日加経済人会議が開催される等の交流が見られた。
(ロ)日加原子力問題
日加原子力協定改正議定書は,80年9月発効したが,81年2月の第1回日加合同作業委員会の際,カナダ産核物質に係る再処理等についてのカナダ政府の事前同意を包括的なものとするための協議を開始したい旨先方から提案があり,1月の第2回合同作業委員会以来,協議が行われてきたところ,このための交換公文が83年4月14日オタワにおいて署名・交換された。
これにより今後は,従来のようにカナダ産核物質の再処理や,英国及びフランスヘの再処理のための管轄外移転について,カナダ政府の事前同意を個別のケースごとに得る必要がなくなったため,日加原子力関係の一層の進展と共に,我が国の原子力平和利用の安定的な運営・発展に資することとなった。
<要人往来>
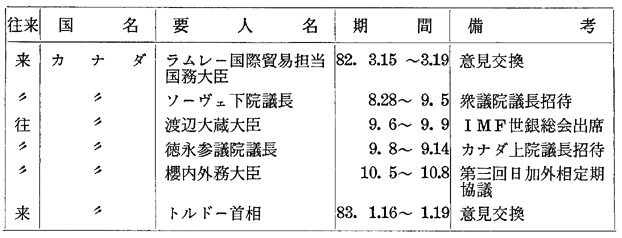
<貿易関係>(1982年,単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率%)
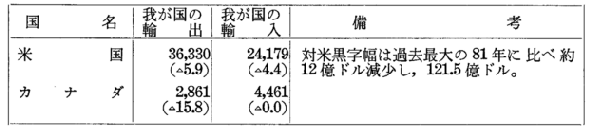
(出所:大蔵省通関統計)
<民間投資>
(あ)我が国の対北米直接投資(単位:百万ドル)

(届出ベース)
(い)北米の我が国に対する直接投資(単位:百万ドル)
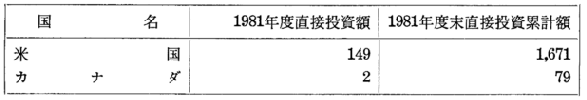
(届出ベース)