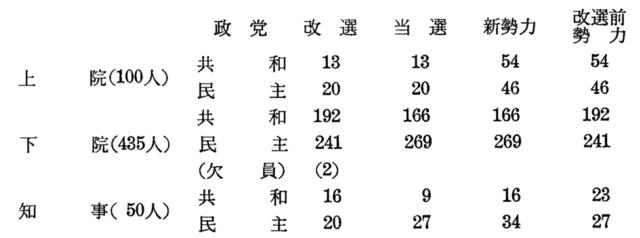
第3節 北米地域
1.北米地域の内外情勢
(1)米国
(イ)内政
(a)中間選挙
82年は米国経済の再建,国防力の強化等を目指すレーガン政権が,その施政前半の評価を問われる中間選挙を迎えた年であった。長引く経済不況,高失業率といった状況下で11月に行われた同選挙は,当然のことながら経済問題が全国的に最も大きな争点となった。レーガン大統領は,現在の経済困難は前の民主党政権がもたらしたものであり,今や経済は改善に向かっていると説き,「現状路線を」(Stay the Course)とのキャッチ・フレーズを掲げた。他方民主党は,レーガン経済政策の失敗を主張し,レーガン政権は歳出削減のため社会福祉費の抑制等弱者への配慮に欠けた不公正な政治を行っていると非難し,「路線変更を」(Change the Course)と訴えた。
選挙の結果は次表のとおりとなり,下院で28議席増,知事選で7州増と民主党が勢力を伸ばした。
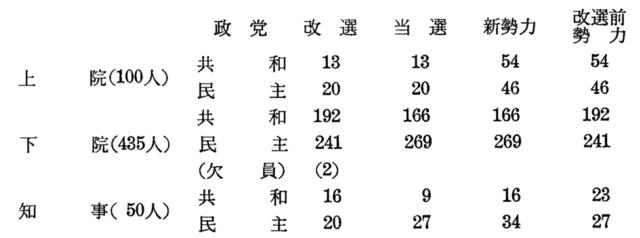
この結果の評価については,共和党が上院で現状維持を果たしたこと,中間選挙では伝統的に政権党が議席を減らす傾向があること(下院における戦後平均議席減31,今回の共和党下院議席減26)等を考え併せれば,共和党の善戦も指摘できる。したがって,今回の選挙結果から,米国民は,共和党現政権の政策に必ずしも満足していないものの,民主党の主張に呼応したものでもなかったことがうかがわれる。
82年には,米国内においても反核運動が盛り上がりを見せ,中間選挙でカリフォルニア,マサチューセッツ州等8州において核凍結を求める決議案が住民投票で可決され,今回の選挙の一つの特色となった。
(b)レーガン政権と議会との関係
82年はレーガン経済政策に対する疑問が深まり,特に財政赤字増大への危機感,中間選挙の思惑等を背景として,レーガン政権の議会運営は厳しさを増し,議会特に民主党の抵抗が強まり,政府の妥協的姿勢も見られた年であった。例えば83年度予算案に関しては,社会福祉関係費抑制反対のほか,特に国防費増大に対する反発が強まり,結果的には政府要求額より約180億ドル削減の総額2,316億ドルの国防予算(予算権限額)が成立したが,主要兵器システムのうち,MXミサイル及びパーシングIIミサイルの調達経費が削除された。また,政府は総額983億ドルに上る増税法案(8月成立),交通網整備公共事業財源のためのガソリン税引上げ法案(12月成立)の立法化を図る等財政赤字問題,失業対策に現実的・妥協的対応を見せ始め注目された。しかし,レーガン大統領は,83年1月の年頭一般教書演説(資料編参照)においても減税計画の推進,歳出削減,国防力強化等基本的政策の継続を明らかにしている。中間選挙による下院民主党議席伸長の結果,従来レーガン政権の法案成立を助けてきた下院保守連合(共和党及び南部保守派議員)の形成が難しくなっているだけに,レーガン大統領は,問題の解決に超党派的努力をもって取り組んでいく必要があることを特に強調している(同演説)。
(c)レーガン政権内の動静
82年から83年初めにかけて,レーガン政権内でかなりの更迭が行われた。閣僚では,6月にヘイグ国務長官の辞任が発表され,後任にシュルツ元財務長官が任命されたのを皮切りに,83年3月現在までのところ,ワイデンボーム経済諮問委員会委員長,エドワーズ・エネルギー庁長官,ルイス運輸長官,シュワイカー保健・社会福祉長官がそれぞれ辞任しているほか,ロストウ軍備管理軍縮局長,バーフォード環境保護庁長官等高官の更迭があった。この中で特に注目されたのは,ヘイグ長官及びロストウ長官(辞任発表83年1月)の更迭で,その背景には,外交及び軍縮問題を巡る政権内での対立があったとの見方も行われた。また,バーフォード長官(同3月)の更迭は,議会が廃棄物処理問題を巡り,環境保護庁と企業との間に癒着関係があったのではないかとの疑惑を追求する中で行われ,レーガン政権が抱えたスキャンダルとして報道等で大きく取り上げられた。なお,ホワイト・ハウス内主要ポストでは,1月アレン大統領補佐官(国家安全保障問題担当)の辞任(後任はクラーク国務副長官)等があった。
(d)84年大統領選挙への動き
84年11月に行われる大統領選挙を目指した動きは,特に民主党側において早くから見られ,83年4月までにクランストン上院議員,ハート上院議員,モンデール前副大統領,アスキュー前フロリダ州知事,ホリングス上院議員,グレン上院議員の6名が大統領候補として正式に出馬声明を行っている。他方,共和党側では,レーガン大統領が,再出馬するか否かについての動向が注目されている。
(ロ)外交
(a)政権発足以来,「力による平和」の確立を標榜してきたレーガン大統領は,82年初めの年頭一般教書においても,「米国の外交政策は力と公正と均衡の政策である」と述べて,こうした姿勢を堅持していく決意を再確認した。
そして政権2年目の82年においては,財政赤字の中での国防費の大幅増や,抑制と相互主義に基づく対ソ政策の展開(ポーランド関連の対ソ措置に踏み切る一方で,軍備管理交渉を推進)等,所期の目標の具体化に努めた。
その間,1月にはアレン大統領補佐官(国家安全保障担当)が辞任して,後任にクラーク国務副長官が就任し,更に6月には,ヘイグ国務長官が辞任して,後任にシュルツ元財務長官が任命されるという事態もあったが,外交の基本姿勢には変化は見られなかった。
(b)対ソ関係では,前年同様,抑制と相互主義に基づく関係確立に努め,11月のソ連指導部の交代にかかわりなく,ソ連側に対し,言葉ではなく行動で抑制を求めるとの姿勢を維持した。その間外相聞及び軍備管理の分野等で対話は継続されたが,注目すべき進展はなかった。また,6月にはポーランド情勢に改善が見られないことを理由に,石油・ガス関連材料の対ソ輸出制限を強化し,同措置解除(11月)後も,対ソ信用供与,対ソ・エネルギー依存,対ソ高度技術移転の規制等で西側の協調を図るなど,ソ連・東欧圏との貿易・経済関係については,政治,安全保障上の考慮を払うとの基本姿勢を明確に維持している。
軍備管理交渉では,81年11月以来の中距離核戦力(INF)交渉に続いて,6月には,戦略兵器の分野でもレーガン大統領の交渉開始提案(5月ユーレカ大学において)(資料編参照)を受けて,戦略兵器削減交渉(START)が開始された。ただし両交渉とも双方の立場には大きな隔たりがあり,見るべき進展はなかった。
以上のように,82年においても,米ソ関係は,低迷したまま推移した。他方,建設的な対話には応じるというのが米国の基本的な立場であり,かかる観点から,上記軍備管理交渉のほか,1月のヘイグ・グロムイコ会談(ジュネーヴ)に続いて,6月,9月,10月に,国連総会の機会をとらえて外相会談が行われた。更に11月のブレジネフ書記長の葬儀の際には,ブッシュ副大統領とシュルツ国務長官によるアンドロポフ新書記長との会談が行われた。
なお,米ソ首脳会談については,83年1月にブッシュ副大統領が,西ベルリンで,欧州国民に対するレーガン大統領の公開状を公表し,アンドロポフ書記長に対し,INF条約署名のために会見することを提案するとの大統領の意向を明らかにしたものの,それ以上の進展は見られなかった。
(c)同盟国との関係では,レーガン大統領の訪欧(6月)等を通じて,西側の協調,結束に努めた。他方,6月のヴェルサイユ・サミット直後にとられた対ソ経済措置強化を巡っては,米欧間に摩擦が見られたが,上述のとおり,11月には,包括的な対ソ経済政策につき協調していくとの期待の下に同措置は解除された。
米欧間の当面最大の懸案であるINF問題についても,ブッシュ副大統領の訪欧(83年1月~2月)等を通じて意見調整に努めている。
(d)アジアについては,日本との協力関係のより一層の推進を図るとともに,中国,韓国,ASEANとの関係強化に努めた。
米中関係については,81年末以来,対台湾武器供与問題を巡る摩擦が表面化したが,ブッシュ副大統領の訪中等による折衝の結果,8月には共同コミュニケ(資料編参照)の発表を見るに至り,一応事態は収拾された。しかし,米中間には,台湾問題のほかにも,技術移転や繊維等の二国間問題が残されており,その後もシュルツ国務長官の訪中(83年2月)等を通じ,意見調整が図られている。
(e)中東については,4月に予定どおり,シナイ半島の返還を実現させた。また,イスラエルによるレバノン侵攻に際しては,ハビブ特使の調停工作を通じて停戦及びベイルートからのPLO撤退を実現させ,その後も,レバノンからの全外国軍隊の撤退に取り組んでいる。こうして,中東和平問題とレバノン情勢が複雑に絡み合う中で,レーガン大統領は,包括的な和平に向けての新提案を発表し(9月),パレスチナ問題についての米国自身の見解を明らかにして広範な支持を得た。
しかし,その後は,レバノンからの全外国軍隊の撤退問題の難航と併せ,フセイン=ジョルダン国王による和平交渉参加も実現しておらず,事態は米国の所期の目標どおりには推移していない。
(f)中南米は,ソ連やキューバの浸透を阻止するとの観点から,レーガン政権が,政権発足以来最も重視してきた地域であり,82年においても,経済,安全保障の両面から積極的に対応する姿勢を維持した。
2月にレーガン大統領が具体的措置を明らかにした中米・カリブ開発構想や,同大統領のジャマイカ,バルバドス訪問(4月)及びブラジル,コロンビア,コスタ・リカ,ホンデュラス訪問(11月~12月)は,こうした姿勢の現れと受けとめられている。なお,この中南米歴訪については,これら地域の安定に不可欠な民主主義の一層の定着を鼓舞することをねらったものと見られている。
(g)その他,アフリカについては,コンタクト・グループを通じ,南部アフリカ問題の解決に努めた。
(ハ)経済情勢
82年の米国経済は年初における大方の予想に反して,結局景気回復軌道に乗ることができなかったが,年末に至って乗用車販売・住宅着工等の指標に景気回復への兆しが現れ,実際12月に景気が底入れした後83年に入って景気回復過程に転じた。82年を通じての主要な経済動向は次のとおり。
まず第1に,実質GNPは-1.7%と戦後最大のマイナス成長となった(1954,75年は-1.2%)。需要の内訳を見ると,年全体では,個人消費,政府支出がわずかながら増加(1%台)を示した反面,住宅投資(10.4%減),輸出(7.1%減),設備投資(3.8%減)はかなり大幅な減少となった。年間の推移を見ると,個人消費は一貫して着実な増加を示し,政府支出は年後半に穀物買入れの増加から急増した。設備投資は年間を通じて減少を続けたが,住宅投資は前年の大幅減少後の低迷から82年後半には回復に向かった。輸出は,世界不況とドル高の影響から特に年後半,大きく減少した。
第2に需要の停滞から生産は減少を続け,失業率が戦後最悪の二桁台を示すなど,雇用情勢は悪化した。鉱工業生産は,81年夏から82年11月まで,2か月を除いて14か月間減少を続け(81年7月のピークからは12.4%の減少),82年平均は8.2%の減少となったが,とりわけ耐久財生産の減少が大きかった。その過程で稼働率は7割を切り,11月には67.4%と1948年の統計開始以来の最低を記録した。製造業の在庫率(在庫/売上比率)は,年初の1.81か月から一時低下したものの,10月には1.78か月と再上昇した。雇用情勢を見ると,失業率は年初の8.6%から上昇を続け9月以降,戦後最悪の二桁台となり,12月には10.8%(軍人を含むでは10.7%)まで上昇した。失業者数は年間に250万人増加し,12月には1,200万人を超えた。
他方,第3に物価安定は予想以上に進展し,12月の前年同月比は,卸売物価で3.5%上昇,消費者物価で3.9%上昇と,年間としては過去10年間で最低の上昇率となった。なお,国内外の景気後退とドル高の影響から国際収支は悪化した。すなわち,輸出(9.2%減),輸入(6.5%減)とも減少し,貿易収支は427億ドルの赤字(FAS-CIFベース81年397億ドルの赤字)となり,経常収支でも第3四半期から赤字に転じた。
これらの動きをまとめると,82年の経済動向には,81年からの高金利の影響が大きく,年央までの住宅建設,乗用車販売の低迷,全般的なドル高と波及効果としての輸出減退はその一例である。しかし,インフレ収束に伴い,市場金利は徐々に低下し,金融当局の姿勢も夏以降,次第にインフレ再燃を警戒しつつも,景気も無視し得ないとの態度に転換した。すなわち,公定歩合は7月以降12月まで,計7回の引下げで12%から8.5%とされ,プライムレートは11%まで引き下げられた。この間制度変更もあって,通貨量(M1)はターゲット(2.5~5.5%)を大幅に上回る年率12%の増加(7~12月)を示した。
金利低下を受けて,まず住宅関係が回復に転じ,さらに,乗用車販売にも回復の兆しが見られた。すなわち,住宅着工は年前半の年率94万戸水準から,年後半には119万戸水準に回復し,乗用車販売もローン金利の引下げ等から82年モデルの在庫が一掃され,11月年率940万台,12月,1月870万台と水準を高めた。これら個人消費や住宅に加え,政府支出の増加があったため,10~12月の最終需要は4.1%増(国内最終需要は53%増)となり,この間,大幅な在庫減らし(年率187億ドル)が行われた。
第4四半期におけるこのような在庫整理によって景気回復への基礎ができた。事実,82年末から,83年初にかけては明るい動きを示す幾つかの指標が表れた。例えば,(あ)鉱工業生産が12月0.1%増に続き,1月0.9%の大幅増となり,(い)耐久財受注が12月に急増し,住宅着工は1月170万戸水準を超え,(う)失業率の大幅低下(1月は10.2%)など雇用情勢に改善の動きが見られた。このように米国経済は82年12月を底として,景気回復過程に入り83年初以降景気は着実に回復に向かっている。
(2)カナダ
(イ)内政
82年にはカナダの永年の政治的課題であった「憲法のカナダ化」が達成された。改憲案は連邦政府とケベック州を除く9州政府との合意の後,英加両国議会の承認を経て,4月オタワでエリザベス女王臨席の下,「1982年憲法」として公布されるに至り,カナダは名実ともに主権国家となった。
他方,改憲交渉の過程で独り改憲案に反対し続けたケべック州は孤立し,連邦政府との対立は新憲法のケベック州への適用拒否権の確認を求める裁判等の形で尾を引いたが,ケベック州の分離独立の動きが大きく再燃するには至らなかった。
他方,カナダ経済は戦後最大の難局(高インフレ率と失業率)に直面した。連邦政府は国内の経済開発,国際競争力の強化を目的とした政府機構の改革(1月),連邦公務員賃金の抑制策(6月),雇用創出計画(10月)を打ち出したが,大幅な改善は見られず,膠着状態が続いた。かかる国内経済の不振のため,憲法改正という歴史的課題の解決にもかかわらず,与党自由党に対する支持率は大幅に低下し,野党進歩保守党への支持率をも下回った。
(ロ)外交
(a)カナダは82年においても活発な外交活動を展開した。カナダは同年のNATO理事会の議長国としてNATO外相非公式会議のイニシアティブを取り,米欧間の意見調整に積極的役割を果たすとともに,ガット(GATT)閣僚会議の議長国としても会議の成功に努め,また国連海洋法会議でも積極的な姿勢を示した。
(b)対米関係は,82年前半経済分野で種々の摩擦はあったが,10月のシュルツ長官の訪加を契機に個別問題で具体的な進展があり,好転した。カナダはまた,NATOへの協力の観点から83年2月,カナダにおける米防衛システムの実験評価に関する米加取極に署名した。
(c)さらに,カナダは太平洋国家としての立場から,アジア・太平洋諸国との関係を重視し,これら諸国との関係を積極的に促進させており,83年1月にトルドー首相がASEAN諸国と日本を訪問した。
(d)また,カナダは貿易政策を効果的に遂行するため,1月に国際貿易関係業務の外務省への移管・統合をはじめとする連邦政府の機構改革を行った。
(ハ)経済情勢
81年後半から悪化し始めたカナダ経済は,82年に入って更に低迷を深め,82年第4四半期連続対前期比GNPマイナス成長を記録,結局年間実質GNP成長率は-4.8%であった(その後の経済見通しによれば,このカナダの深刻な不況も,82年第4四半期で底を打ったと見られている)。
消費者物価は82年に入り徐々に低下し,12月には9.3%まで低下した。年間では10.8%の上昇率であった。物価は83年に入り更に低下を続けると予測されている。
失業率は前年後半に記録した戦後最高の8%を突破して更に上昇を続け,12月には12.8%を記録した。12.8%の水準は大恐慌以来の高率である。82年の年間失業率は11.0%であったが,83年以降も二桁の高率で推移するものと見込まれている。
カナダ経済の極度の不振に伴い,税収が81年11月の82年度財政演説における歳入見通しを大幅に下回り,当初財政赤字見通しは105億加ドルであったが,6月のミニ財政演説では195億加ドルに増大,さらに,10月のラロンド新大蔵大臣による経済財政演説では235億加ドルと見込まれ,結局82年度は最終的には253億加ドルと当初見通しの約2.5倍の財政赤字を記録した。この赤字額は歳出額の約30%に達するものであり,カナダ経済の運営を困難なものとしている。財政赤字は83年には更に拡大する見通しとなっている。
国際収支については,82年は,カナダ経済の不振を反映して輸入が大幅な減少(81年769億加ドル82年667億加ドル)を示し,対前年比横這いであった輸出(82年845億加ドル)と相まって,貿易収支は大幅な黒字(178億加ドル)を記録,従来赤字を続けてきた経常収支も小幅ながら黒字(27億加ドル)に転じた。