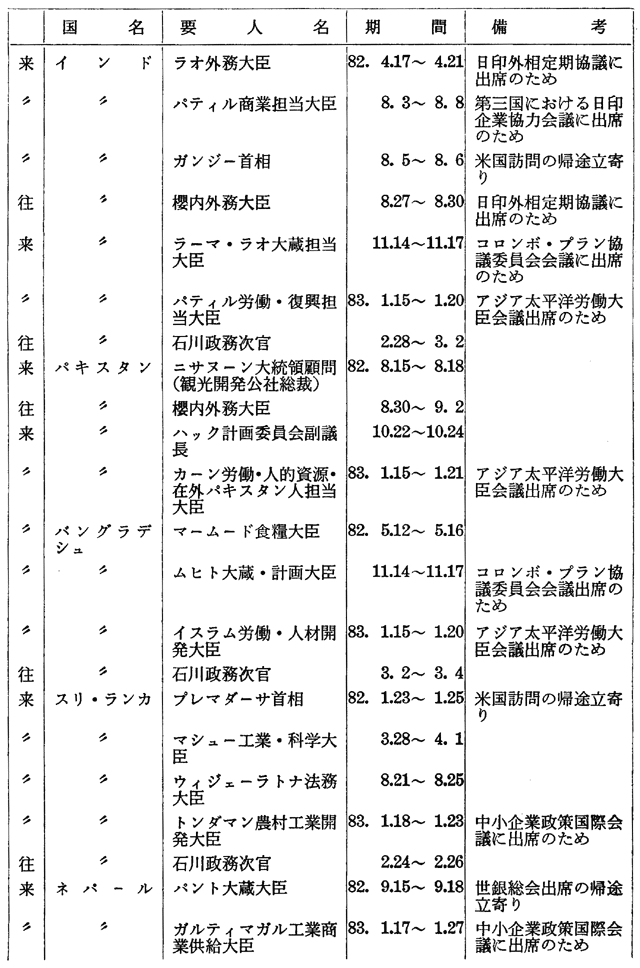
7.南西アジア地域
(1)南西アジア諸国の内外情勢
(イ)概要
82年における南西アジア地域情勢は,3月のバングラデシュの政変以降もインド,パキスタン,スリ・ランカ等の政権が安定していることを反映して比較的平静に推移した。
83年に入ってからは,インド南部2州の州議会選挙におけるコングレス(I)党の敗北,アッサム州選挙を巡る騒擾,パキスタンのカラチにおけるスンニ派とシーア派の回教徒両派の衝突,バングラデシュにおける学生の騒擾等の波乱はあったものの,これらはいずれも大局的にはそれぞれの国の現政権自体を揺るがすほどのものとはなっておらず,全体的には南西アジア地域の安定は維持されている。
他方,82年の域内各国の経済は,パキスタン,スリ・ランカでは比較的良好であったが,インド,バングラデシュ等では農業生産が不振であり,また各国とも厳しい国際収支の悪化に直面し,外国からの援助を強く要請している。
同地域諸国の外交面では,(i)インドとパキスタンの関係改善のための対話の促進,(ii)インドと米国を含む西側諸国との関係強化,(iii)印・中国境問題をも含めた両国間対話の再開,さらには,(iv)南アジア地域協力に関する域内国間の話合いの進展等,南西アジア地域の安定強化に向けての努力は着実に進められている。特にインドは,2月の南南会議や83年3月の非同盟首脳会議の開催国として重要な役割を演じ,他方ハック=パキスタン大統領は米国,ソ連,中国,ASEAN諸国など23か国に及ぶ積極的な訪問外交を展開した。
(ロ)インド
(a)内政
82年の内政では,上院議員改選,地方選挙,大統領選挙(与党候補のザイル・シン前内相が当選)等の重要選挙が行われ,与党コングレス(I)党はおおむね依然第1党としての強さを示したが,一部の地方選では伸び悩みが見られた。83年に入ってから実施された地方選挙で,与党は従来同党の牙城とされてきたアンドラ・プラデシュ及びカルナタカの南部2州において敗北を喫した。このことは,それに続くデリー特別区での与党の勝利にもかかわらず,ガンジー政権の将来にとって様々な問題点を提起するものであった。
パンジャーブ州のシク教徒の自治権拡大運動は2度にわたってハイジャック事件を起こす等,次第に先鋭化の方向をたどった。また3年来続いているアッサム州の「外国人」追放運動は,83年2月に行われた同州議会選挙に際して,外からの移住者とアッサム人の衝突に発展し,多数の死傷者を出した。
(b)外交
永い間の懸案であったガンジー首相の訪米(7月),訪ソ(9月)を実現し,印米関係改善を軌道に乗せるとともに,印ソ友好関係の再確認を行って,ガンジー政権の標傍する非同盟外交の枠組みを一応完成させた。また印米間の永年の懸案であったタラプール原子力発電所核燃料供給問題も,ガンジー首相訪米の際,燃料供給をフランスが米国に代わって行うことに原則的合意が得られて解決した。
パキスタンとの関係では,11月にハック=パキスタン大統領がデリーに立ち寄り,印パ首脳会談が行われ,印パ合同委員会設立につき合意した(83年3月設置協定調印)。
延期されていた事務レベル協議は8月及び12月行われたが・不戦条約及び平和友好協力条約についての交渉は進展しなかった。
対中国関係では81年に引き続き第2回(5月),第3回(83年1月)の事務レベル協議が行われた。国境問題について新しい進展はなかったが,対話の継続という基本方針では双方の意見が一致している。
インドは2月に南南会議を,83年3月には非同盟首脳会議を主催して,第三世界における指導国として威信を高めた。
(c)経済
農業生産は干ばつ及び一部洪水のため落ち込み,鉱工業生産も世界不況及び1年にわたるボンベイ繊維工場のスト等により伸び悩み,82年の経済成長率は2%にとどまるものと見られている。インフレも,卸売物価で見る限り沈静化したが,消費者物価は8%台でいまだ高水準にある。石油価格上昇による国際収支の悪化からは依然脱却できずにおり,外貨準備高(金,SDRを除く)は30億ドル台にとどまっている。
(ハ)パキスタン
(a)内政
81年には連邦評議会の設立をはじめとする各種の措置が講じられ,政権の基盤が大きく強化されたが,82年も国内情勢は安定的に推移した。連邦評議会メンバーのボパリの暗殺や弁護士スト等も発生したが,他の反政府運動に結び付くまでには至らなかった。10月には紆余曲折の末,現政権も故ブットー首相夫人の海外治療を許可している。総じて野党の活動が低調であったため不定期ながらも連邦評議会も4回開催され安定した国政運営が行われた。
また,アフガン難民はその後も流入が続き82年末で約290万人に達している。
(b)外交
かかる内政の安定を背景に,ハック大統領は席の温まる間もないほどの積極的な訪問外交を展開し,訪問した国は1年間に23か国に上った。
特に11月には突如訪印が実現し,印パ両国関係のみならず,南西アジア域内情勢の安定化に大きく寄与することとなった。また,故ブレジネフ書記長の葬儀参列の際アンドロポフ新書記長との会談が実現し,アフガン問題発生以来の冷え切った両国関係が多少改善された。これらの外交的成果を携え12月に訪米し,対パ米世論の改善に実を挙げた。
(c)経済
経済面では,初期の天候不順のため小麦生産が低調で,このため農業部門(成長率3%)の伸びを鈍化させることとなったが,工業生産(12%)の好調に支えられ,GDP成長率は63%を達成し,また物価上昇は10%内に収まっている。主力輸出品(綿花及び米)の価格下落により輸出が17.2%減となり,海外在住者送金も頭打ちとなったため経常収支赤字が16億ドルとなったが,IMFの拡大信用供与措置等により管理し得る状態にある。
(ニ)バングラデシュ
(a)内政
3月,無血クーデターにより政権を掌握したエルシャド戒厳令司令官は,その後16名の閣僚を順次任命し体制を整え,前政権の閣僚・経済人等を汚職容疑で逮捕,軍事法廷で審理を開始するとともに,政治活動を禁止し,2年後の民政移管を約した。他方,地方行政改革をはじめ司法・土地・教育等の各分野の改革措置に着手した。
しかしながら,小学校1年からのアラビア語の必修を主な内容とする
「新教育政策」は学生,政党関係者の強い反発を呼び起こし,2月,反政府暴動にまで発展するに至った。
一方,目下戒厳令下,その活動が禁止されている(屋内政治活動は83年4月から認められている)諸政党は,軍政権に対し早期総選挙の実施を強く要求している。
(b)外交
エルシャド政権成立後も外交の基本政策に変更はなく,イスラム連帯の推進と積極的訪問・招待外交及び首脳外交を展開した。10月,エルシャド・ガンジー会談が開かれガンジス川水利問題等が討議された。
(c)経済
82年度は,生ジュート・ジュート製品等の輸出価格が大幅に低下した結果,交易条件が前年度に引き続き悪化し,貿易赤字の増大を招いたほか,外国援助も質量ともに停滞した。また干ばつによる食糧生産の不振は産業各分野の活動停滞等深刻な状況をもたらし,GDP成長率は前年度5.9%を大きく下回る1.1%と見込まれる。
(ホ)スリ・ランカ
(a)内政
10月,大統領選挙が行われ,現職のジャヤワルダナ大統領が再選され(83年2月就任),また,12月に行われた現国会議員の任期を6年間延長するための国民投票において政府与党は勝利を収め,長期安定政権の基礎を固めた。他方,野党,特に過去に現政府与党の統一国民党と交互に政権を担当してきた自由党は,党内の不統一もあり,大統領選挙,国民投票共に奮わなかった。
(b)外交
スリ・ランカは,非同盟路線を堅持しており,83年3月,非同盟首脳会議にはジャヤワルダナ大統領自らが出席した。82年は大統領選挙,国民投票と内政問題が中心となり,外交的には大きな動きはなかった。
(c)経済
82年の経済は,実質国内総生産成長率が,81年の5.8%を下回る5.0%程度と見込まれるものの,物価は,11%程度と小康気味に推移し,また,貿易収支の赤字もほぼ81年(8億1,100万ドル)と同程度になると見込まれる。
(へ)ネパール
(a)内政
81年の改訂憲法下での直接選挙制による国会議員選挙に引き続き,82年は郡・町村議会等地方議会選挙が実施され,一層の民主化が推進されたことにより王制の安定強化に役立った。また,反体制派の領袖B.P.コイララやK.I.シン元首相等が死去し,反体制運動は弱体化しつつある。
(b)外交
非同盟中立外交を標榜し,81年に引き続きネパール平和地帯提案の支持獲得に努力し,原則的支持を含め30か国からの支持を取り付けた。
(c)経済
異常天候による干ばつのため農業生産が落ち込み,深刻な食糧不足が生じ政府は友邦国,国際機関に緊急食糧援助を要請した。
(ト)モルディヴ
ガユーム大統領,閣僚は地方アトールを巡回し,地方の開発の促進に努め,政情は安定した。経済的には,主要産業たる漁業,観光業,海運業とも世界的な不況の影響を受け不振であった。
対外的には,7月に英連邦に加盟したが,非同盟政策を堅持し,83年3月の非同盟首脳会議にガユーム大統領が出席した。
(チ)ブータン
国内政情は国王の親政体制の下で一応安定しており,外交面では国連を中心に各種フォーラムにおいて後発開発途上国(LLDC)内陸国としての経済的困難を訴え,開発への協力を求めた。
(2)我が国と南西アジア諸国との関係
我が国と南西アジア諸国との関係は伝統的な友好関係に基づいているが,この1年間はこのような緊密な関係に更に弾みが付いた年と見ることができる。
第1に,インドとの間では2月に目印外交協議,4月にラオ外相を迎えての外相定期協議と,政府間の政治・外交面での対話を深めるとともに,6月のパリでの援助国会議で330億円に上る対インド円借款供与の意図表明を行った。さらに,8月初めにはガンジー首相が米国公式訪問の帰途,我が国に立ち寄り,鈴木総理大臣と意見交換を行った。次いで同月末には櫻内外務大臣がインド(及びパキスタン)を公式訪問し,ガンジー首相はじめインド政府要人と幅広く意見交換を行った。インドとの経済関係は順調に推移し,特に自動車関連の合弁事業等が活発な動きを示した。他方,我が国からの貿易出超の定着傾向が見られた。
第2に,パキスタンとの間では2月の日パ事務レベル定期協議9月初めの櫻内外務大臣のパキスタン訪問を通じ二国間の政治対話が行われた。櫻内外務大臣はハック大統領をはじめとするパキスタン政府要人との会談を精力的に行うとともに,アフガン難民キャンプを視察した。パキスタンに対する経済活動・経済協力も活発に行われ,82年度の対パキスタン円借款の意図表明額は280億円に達した。
なお櫻内外務大臣は上記インド,パキスタン訪問の際,ニュー・デリーで演説し,今後の我が国の対南西アジア外交積極化の意向を明らかにし,これは好感を持って迎えられた。
バングラデシュ,スリ・ランカ,ネパール等の他の南西アジア諸国との関係も政府,民間の双方で活発な動きが見られた。バングラデシュからは3月のクーデター後,5月にマームード食糧大臣が我が国を訪れた。スリ・ランカとの間では4月の日ス経済合同委員会開催の後も,二国間関係は活発に推移した。ネパールとの間でも,経済協力,人物交流等で,二国間関係の増進が図られた。83年2月には石川外務政務次官が先方政府の招待により,これら3国を訪問し,スリ・ランカではジャヤワルダナ大統領,ネパールではビレンドラ国王,そしてバングラデシュではエルシャド戒厳令司令官等との会見を行うなど,二国間関係の増進に努めた。モルディヴとの間でも,11月にジャミール外務大臣が我が国を訪問するなど友好関係が高められた。
このほか,議員交流では,8月に日本で日本・パキスタン友好議員連盟が発足したほか,スリ・ランカにおいて日本との友好議員連盟が発足するに至った。
(3)アフガン難民問題
79年末のソ連のアフガニスタン軍事介入後,急速にパキスタンへ流入し始めたアフガン難民は,83年3月現在290万人近くに達し,パキスタン政府にますます深刻な負担を強いている。
また,アフガン難民はインドシナ難民の場合とは異なり,第三国定住による解決方法もなく,今後,アフガン問題の政治的解決が達成され,難民の本国帰還が可能となるまで,パキスタン領内に滞留し続けるものと考えられる。
我が国は79年来,本難民の救済援助を積極的に進めてきているが,82年度はUNHCR(国連難民高等弁務官)及びWFP(世界食糧計画)を通じ約1,730万ドルの協力を行った。
<要人往来>
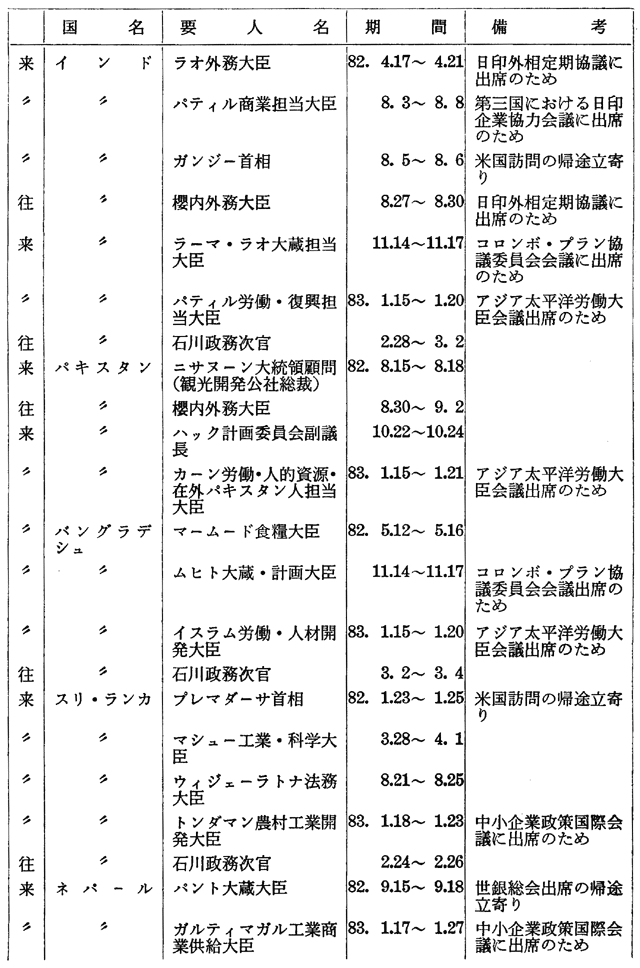
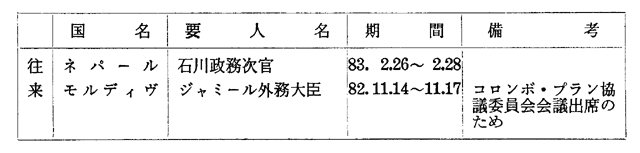
<貿易関係>
(1982年,単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率%)
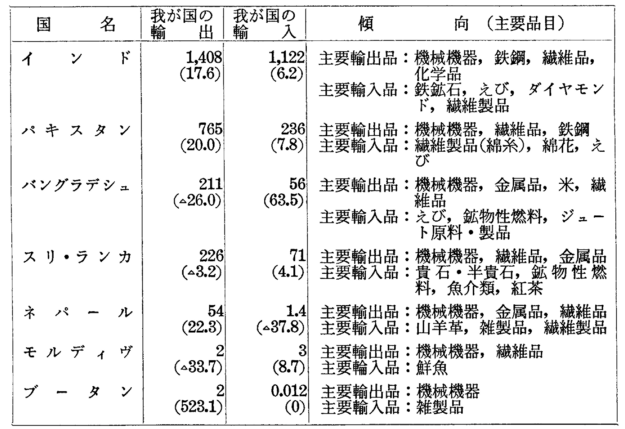
(出所:大蔵省通関統計)
<投資関係>(単位:百万ドル)
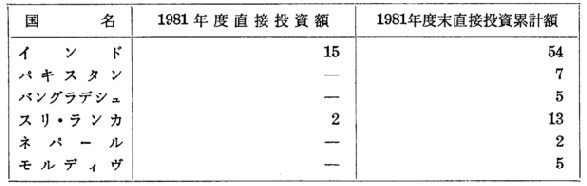
(届出ベース)
<経済協力(政府開発援助)>(1982年,単位:百万円,人)
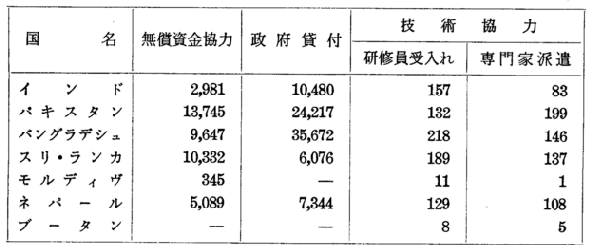
(約束額べース)(DAC実績べース)