
5.インドシナ地域
(1)インドシナ諸国の内外情勢
(イ)ヴィエトナム
(a)内政
(i) 82年の内政における最大の出来事は,3月,ハノイにおいて開催された第5回共産党大会であった。同党大会は,カンボディアヘの武力介入及び中国との対立の継続,経済困難が深刻化して第2次経済5か年計画が失敗に帰したという厳しい内外情勢の下で開催されたものであった。
(ii) 同党大会は当初予定の81年末開催から3か月延期された経緯もあり,一部においてはヴィエトナム指導部内に今後の路線(対中・ソ関係,カンボディア等についての外交政策,又は経済政策)ないしは党人事を巡り,対立が生じているとの推測も行われた。しかしながら,レ・ズアン党書記長が「政治報告」の中で,「ソ連との団結及び全面的協力は党と国家の外交政策の礎石である」と強調し,ソ連との関係を一層強化することを鮮明にする一方,中国を「直接かつ危険な敵」とし,78年以来の反中親ソ路線に変更が見られなかった。
また,同「報告」において,ラオス・カンボディア(「ヘン・サムリン政権」)との間での「特別な関係」を再確認していることはカンボディア問題の既成事実化を追求せんとする姿勢を表明したものと見られる。
(iii) 党人事の改選については,政治局員6名,書記局書記6名,中央委員36名の解任という大幅な異動が見られた。
しかし,レ・ズアン書記長,チュオン・チン政治局員,ファム・ヴァン・ドン政治局員の序列には変化がなく,レ・ズアン書記長をトップとする指導体制は維持された。
他方,政治局ではヴォー・グエン・ザップ(73歳),グエン・ズイ・チン(73歳)等の高齢者が引退し,ヴォー・ヴァン・キエット(61歳),レ・ドゥック・アイン(63歳),グエン・ドゥック・タム(63歳)等が政治局入りしたことは,同第5回党大会において将来の党指導体制を考慮した世代の交代が行われたものと見られる。
(b)外交
(i) 党大会においてソ連との関係を一層強化することを鮮明にする一方,西側諸国との意見交換のため,グエン・コー・タック外相は4月初めからフランス,スウェーデン,ベルギー,西独等を訪問したほか,7月及び10月,ASEAN諸国(シンガポール,マレイシア,タイ,インドネシア)を訪問した。
(ii) 中国との間では,依然として対立が継続したが,一方,旧正月及び両国の国慶節に際しては国境での敵対行為の停止,次官級会談の再開等を中国に提案した。しかし,実現したのは従来どおり双方の抑留者の交換のみであった。
(iii) 10月及び83年3月に行われた中ソ外務次官レベル会談においてカンボディア問題が取り上げられ,10月にはチュオン・チン国家評議会議長の訪ソが行われ,ヴィエトナムの対応ぶりが注目されたが,中ソ会談が目立った進展を示さなかったこともあり,ヴィエトナムのカンボディアに対する基本姿勢に変化は見られなかった。
(c)経済情勢
(i) 79年,80年と連続して下降した国内生産の活性化を図るため,81年1月から国営企業における「出来高払制度」,農業部門においては「生産請負制度」を導入し,労働意欲を高めるいわゆる「新経済政策」を実施して以来,それぞれの分野で生産の増加が見られ82年においても一応の成果があったと見られる。
また,3月の第5回党大会における経済報告で,南部経済の取扱いについて発表し,第2次経済5か年計画(76年~80年)における急速な社会主義化政策の失敗を反省,当面緩やかな社会主義化を進める方針を打ち出した。すなわち,南部農業の集団化を合作社の前段階である「生産集団」レベルにとどめるとともに,工業生産,貿易についても地方において自主権を認め,南部経済の潜在的活力を利用する現実的な方策を取ることとした。
しかしながら,膠着状態となっているカンボディア問題を抱え,出兵に要する人的・財政的負担,西側諸国や国際機関からの援助の先細りと相まって極端な外貨不足,社会資本の老朽化,エネルギー・原材料・部品の不足等の状況は依然続いており,経済管理・運営面での欠陥もほとんど改善されていないため,経済活動は全般的には低調に推移している。
(ii) 12月,ヴォー・ヴァン・キエット副首相兼国家計画委員会委員長は国会において,82年の経済情勢について報告を行い,その中で,食糧生産は計画を超過達成(籾換算で1,626万トン)したほか,電力,石炭,セメント,生地等の工業生産においても計画を達成し,特に小・手工業分野における消費財の生産活動が活発化したが,他方,エネルギー・原材料・部品の極度の不足,生産・建設・運輸における非能率,製品管理における浪費と汚職,南部社会主義改造の遅滞等の困難に直面している旨指摘している。
(ロ)カンボディア
(a)内政
民主カンボディアは,祖国をヴィエトナムの支配から解放し,独立,中立,非同盟のカンボディア国家を実現することを目指して,幅広い反ヴィエトナム民族統一戦線の結成を呼び掛けていた。このため,反ヴィエトナム三派の代表であるシハヌーク殿下(独立・中立・平和・協力のためのカンボディア民族統一戦線議長),ソン・サン議長(クメール人民民族解放戦線)及びキュー・サンパン民主カンボディア首相は,81年のシンガポールでの三派首脳会談を経て,6月,クアラ・ランプールにおいて民主カンボディア連合政府結成の宣言(資料編参照)に署名し,次いで7月,カンボディア領内において正式に民主カンボディア連合政府を樹立した(シハヌーク大統領,キュー・サンパン外務担当副大統領,ソン・サン首相)。
他方,「ヘン・サムリン政権」は引き続きヴィエトナムの強い軍事的・経済的支援の下にあったが,2月,第1期国会第2会期において,チャン・シ閣僚評議会議長,プー・トン同副議長兼国防相を選出した。
なお,在カンボディア・ヴィエトナム軍は,82~83年の乾期において,タイ・カンボディア国境のカンボディア人難民集結地を攻撃したため,多数の難民が,再びタイ領内に流入した。
(b)外交
ASEAN諸国の強い期待と支援の下に,シハヌーク大統領に率いられた民主カンボディア連合政府が樹立されたこともあり,82年の国連総会においては,全外国軍隊のカンボディアからの撤退とカンボディア人の民族自決権を柱とするカンボディア問題の包括的政治解決を求めたASEAN,我が国等の共同決議案「カンボディア情勢」は,81年を上回る圧倒的多数で採択された(賛成105,反対23,棄権20)。また,民主カンボディアの国連での代表権も同様に,81年をはるかに上回る大幅な支持を得て(支持90,反対29,棄権26)引き続き維持された。
ただし,83年3月ニューデリーで開催された非同盟首脳会議における民主カンボディアの議席は,ASEANの外交努力にもかかわらず,引き続き空席のままとされた。
他方,ヴィエトナムをはじめとするインドシナ側は,2月(ヴィエンチャン)及び7月(ホーチミン市)に外相会議を,また,83年2月にインドシナ首脳会議(ヴィエンチャン)を開催し,東南アジア全般の問題についてASEAN側と話し合う用意があるとして,両ブロック間の地域会議ないしこれに類似した会議の開催,ヴィエトナム軍の条件付部分撤退等を含む提案を繰り返したが,「ヘン・サムリン政権」の既成事実化を前提とする基本的姿勢に変化はなかった。
ASEANとインドシナ間の対話について,ASEAN5か国外相は,83年3月,共同声明を発出して,「カンボディア国際会議」にヴィエトナムを導くためにASEANとヴィエトナムとの話合いの考えを留意するとともに,同会議の枠内及び国連決議を基礎にした包括的政治解決実現の探求を再確認した。
また,10月から中・ソ外務次官レベル会談が始まったが,これに関連して,83年3月,中国外交部は,ヴィエトナム軍の無条件全面撤退の宣言,ソ連の対越支援の停止等を含む5項目声明を発表した。
(c)経済
国内の農業生産の向上及び国際機関を通ずる人道的援助の成果もあり,食糧事情は大幅に改善された。しかし,タイ・カンボディア国境に依然滞留している20~30万人のカンボディア人に対しては,引き続き人道的観点からの援助が必要とされている。
(ハ)ラオス
(a)内政
82年の主要な動きとしては,4月にラオス人民革命党第3回大会が10年ぶりに開催され,カイソーン党書記長兼閣僚評議会議長を中心とする指導体制が,一段と強化されたことである。
同大会では,国防強化と経済建設を基礎とする社会主義建設路線が採択された。特に,経済建設の必要性が強調され,81年から実施中の第一次社会・経済5か年計画に関する報告が承認された。
また,国防・治安については,カイソーン党書記長兼閣僚評議会議長の「政治報告」の中で最重要事項として扱われているが,82年においても,地方での反政府活動に関する報道も伝えられた。
なお,党大会においては,党の主要人事には異動はなく,8月に党大会の決議に基づき効率的経済建設を目的とする行政機構の再編が行われ,経済関係省庁の副大臣には多くのテクノクラートが登用された。
(b)外交
82年のラオス外交の基調は引き続きヴィエトナム及びカンボディア(「ヘン・サムリン政権」)との特別な関係の強化,ソ連をはじめとする社会主義諸国との全分野における協力関係の強化にあった。
ヴィエトナムとの関係では,2月のインドシナ外相会議の際にグエン・コー・タック外相,4月のラオス党大会の際にはチュオン・チン=ヴィエトナム党政治局員等がラオスを訪問し,ラオス側からは,3月のヴィエトナム党大会の際にカイソーン党書記長兼閣僚評議会議長,7月のインドシナ外相会議の際にプーン外相,8月にはプーミ閣僚評議会副議長がそれぞれヴィエトナムを訪問するなど各方面での協力関係の強化が図られた。また,カンボディアとも2月にフンセン外相,4月にヘン・サムリン書記長等がラオスを訪問し,「ヘン・サムリン政権」との連帯関係の強化が推進された。
社会主義共同体の一員としてラオスは,ソ連との関係を極めて重要視している。ヴィエトナムとの「特別関係」に対し,ソ連とは「全分野における協力関係」に位置付け,カイソーン党書記長自身が,3月,9月及び12月の3度ソ連を訪問し,ソ連首脳と会談した。ソ連側もロマノフ政治局員等がラオスを訪問し,協力関係の緊密化が図られた。また,ドイツ民主共和国とは9月に友好協力条約を締結した。
中国とは中越紛争以来,依然として冷たい関係にある。
他方,ASEAN,特にタイとの関係については「善隣友好関係の維持発展」を強調し,タイからは3月にシティ内相,8月にプンミー商相がラオスを訪問した。
米国に対しては米帝国主義者との非難を繰り返しつつも,9月に行方不明米兵士(MIA)捜索調査団の受入れを認める等対米外交姿勢にある程度の柔軟性を示した。
(c)経済情勢
第3回党大会では社会主義経済建設を基本としつつも,ラオス経済の現状に即した現実的方針が打ち出された。2年目に入った社会・経済開発5か年計画では引き続き農業生産及び輸送力の向上に主力が注がれ,特に米の生産は81年同様に100万トン台を記録し,おおむね自給を達成したと見られる。
ラオス経済の発展は全般としては,遅々としているものの政変に伴う混乱期を脱し着実性を増している模様である。しかし,依然として外貨,技術不足等発展のため解決すべき問題が残されている。
(2)我が国とインドシナ諸国との関係
10月には,我が国と伝統的に友好関係にあるラオスからカンパーイ外相臨時代理が,我が国を公式訪問したが,これは新体制移行後,同国からの初めての要人訪日であり,最近の両国間の関係の発展を示すものであった。他方,ヴィエトナムからは,83年3月にラウ外務次官が訪日し,同国との間の対話を維持する努力が行われたが,カンボディア問題を巡り同国との関係は依然停滞したまま推移している。
カンボディアについては,我が国は,民主カンボディア連合政府を支持し,秋の第37回国連総会の機会に,櫻内外務大臣がシハヌーク大統領と会談した。
<要人往来>

<貿易関係>(1982年,単位:千ドル,( )内は対前年比増加率%)
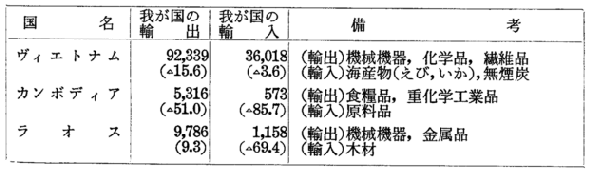
(出所:大蔵省通関統計)
<経済協力(政府開発援助)>(1982年,単位:百万円,人)
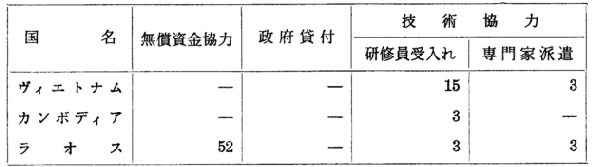
(約束額ベース)(DAC実績ベース)