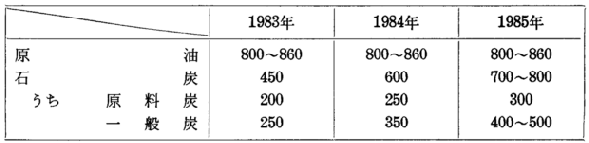
2.中国
(1)中国の内外情勢
(イ)内政
(a)国務院等の機構改革
3月に,(i)82年内に国務院各部・委員会等の機関数及び職員をそれぞれ約3分の1ずつ削減する,(ii)83年1月から各省・市・自治区レベルの党・政府の機構改革を行うとの構想が打ち出され,8月までに(イ)副総理を13名から2名に削減するとともに国務委員(副総理とほぼ同格)を新設,(ロ)部・委員会等の数を52から43に削減,(ハ)右に伴う閣僚・次官の大幅な削減更迭等が行われた。
(b)中国共産党第12回全国代表大会(十二全大会)
9月十二全大会が開催され,中央委員会の政治報告,新しい党規約等を審議,採択し,中央委員,顧問委員等の選出を行った。同大会終了後,引き続き改選された中央委員による第12期中央委員会第1回全体会議(一中全会)が開催され,党の最高指導者である総書記(党主席・副主席は廃止し総書記制に移行)以下の党指導部人事を決定した。
(i) 人事
中央政治局常務委員(6名)については,胡ヨウ邦,葉剣英,トウ小平,趙紫陽,李先念,陳雲が留任したが,華国鋒は平の中央委員に降格された。新設の党中央顧問委員会にはトウ小平,許世友,耿ヒョウ,姫鵬飛等の党・軍の元老クラスが収まり,トウ小平がその長(主任)に就任した。
(ii) トウ小平の開会演説及び胡ヨウ邦による政治報告(資料編参照)は,同大会について,建国への基本方針を策定した「七全大会(1945年)以来の最も重要な大会」であるとの意義付けを行い,今後の党・国家の任務として近代化建設,台湾を含む祖国統一,覇権主義反対の三大任務を掲げ,その核心である近代化建設を促進するための今世紀末までの長期目標として,(あ)機構及び経済体制の改革,(い)社会主義精神文明の建設,(う)経済及びその他領域における犯罪活動の取締り,(え)党の作風と組織の整頓の4点を挙げている。
(iii) 党規約
新しい党規約の特色としては,イデオロギー色が後退(毛沢東個人への礼讃,継続革命等の表現なし),社会主義社会の優越性を強調している点等が挙げられる。
(c)第5期全国人民代表大会第5回会議(全人代第5回会議)
82年末に開催された同会議においては,毛沢東による「継続革命論」等文革的色彩が強かった前憲法が廃され,80年秋の全人代以来草案作りが進められてきていた新憲法が採択された。新憲法は54年憲法(1954年制定)を基礎として作成され,内容的には現指導部が近年実施してきた近代化路線を盛り込んだ実務的色彩の濃いものとなっている。また,国政・国家機構等の面において法治主義を強く貫いており(党による憲法の遵守規定,立法機関としての全人代の権限強化,党の軍隊から国家の軍隊への移行を規定した国家中央軍事委員会の設置等),更には文革時期の反省に立ち,限定的ながら国民の基本的権利に対し配慮したものとなっている。
(ロ)外交
(a)全般
第12回党大会での胡ヨウ邦報告(資料編参照)は,独立自主外交路線及び対外開放政策の堅持を強調するとともに,世界平和の擁護,覇権主義反対,平和共存五原則に基づく各国との関係発展,第三世界との団結強化の基本政策を明らかにした。
中国は我が国を含む西側主要国と協力関係を発展させるとの方針を堅持し,他方,ソ連との間で外務次官レベルの対話を再開する等対ソ関係の改善に積極的姿勢を示すとともに,第三世界諸国との関係強化に努めた。
(b)対米関係
米中間の最大の問題となっていた米国の台湾に対する武器供与問題は,ブッシュ米副大統領の訪中(5月)等を通じ米中間で協議を重ねた結果,8月,武器供与は量的にも質的にも国交正常化以後数年間の水準を超えず,漸減していくことを主内容とする共同コミュニケが発表され(資料編参照),一応の合意を見た。
83年2月,シュルツ米国務長官は中国を訪問し,米中双方が対話を続け信頼関係を築いていくための良好な雰囲気が醸成されたが,その後も中国テニス選手の亡命事件,中国のアジア開発銀行参加問題,湖広鉄道債券問題等を巡り米中間の不協和音が続いている。
(c)対欧関係
中国は,西欧諸国との友好協力関係の発展を図っており,ルクセンブルグ首相(4月),英国首相(9月)等西欧諸国首脳に対する招待外交を活発に展開してきている。ただし,オランダとの関係は,オランダの対台湾潜水艦売却問題以来,代理大使レベルの関係となった。
(d)対ソ関係
中国は,中ソ関係の改善を呼び掛けたブレジネフ演説(3月)等に対し慎重な対応を見せていたが,その後,胡ヨウ邦総書記が第12回党大会において条件付きながら対ソ関係正常化の可能性に言及する等,積極的な対ソ姿勢を打ち出した。
その後,中ソ外務次官レベル会談が,北京(10月),モスクワ(83年3月)において開催されたが,中国側は,ソ連に対し中ソ関係正常化のための3条件(中ソ国境及びモンゴルからのソ連軍の削減・撤退,ヴィエトナムのカンボディア侵略に対する支援の停止,アフガニスタンからのソ連軍の撤退)を提示しており,これまでのところ,関係正常化に向けての実質的な進展は見られない。
ただし,貿易額の増大,留学生を含む人的交流の拡大,国境貿易再開等が合意されており,経済・文化等の分野における関係の進展が見られる。
(e)対アジア・大洋州関係
(i) 中国はヴィエトナム軍のカンボディアからの完全撤退を強く求め,盛んな外交活動を進めている。中越国境では83年3月から両軍の小競り合いが続き,中国は4月中旬から「武力挑発に対する反撃」を開始した。
(ii) 中国は東南アジア諸国との関係強化に力を入れており,82年にはビルマ外相(7月),タイ首相(11月),マレイシア外相(11月)等が訪中した。
(iii) 南西アジアについては,同地域に対するソ連の浸透を阻止するとの立場から,引き続き同地域各国との関係強化に努めており,ネパール国王(7月),パキスタン大統領(10月)が訪中し,また国境問題等の話合いのための中印次官級会談も引き続き開催された。
(iv) 北朝鮮との間には最も友好的な党及び国家関係を維持しており,胡ヨウ邦主席及びトウ小平副主席の訪朝(4月),金日成主席(9月)の訪中が行われた。
(v) 大洋州との関係では,フレーザー豪首相が訪中(8月)したのを受けて,趙紫陽首相がニュー・ジーランド及び豪州を訪問(83年4月)し,経済協力関係の強化等につき話合いを行った。
(f)中近東・アフリカ関係
中国は,「独立自主」外交の下に第三世界諸国との団結・協力の強化に積極的な姿勢を示しており,趙紫陽首相が12月から約1か月間アフリカ11か国を歴訪したほか,リビアのカダフィ大佐(10月),ジョルダン国王(12月)が訪中した。
(ハ)経済情勢
(a)82年には81年に引き続き財政収支の均衡及び物価の安定に努めた。82年の財政赤字は29億元(80年128億元,81年27億元)と81年に引き続き小幅にとどまり,小売物価上昇率も1.9%とほぼ安定した。12月に開催された第5期全人代第5回会議で「第6次5か年計画」(81年~85年)が採択されたが,右期間中には経済成長率は若干低目に抑え(年率4%~5%),経済効率の向上,エネルギー・交通等経済のネック部門の改善に重点を置くこととしている。
(b)82年の農業生産は総額2,629億元(対前年比11.0%増)と前年に比べ大幅に伸長した。82年の農業生産は穀物3億5,343万トン(同8.7%増)をはじめ全般的に良好で,一部地域における自然災害の影響は余り大きくなかった。生産責任制の普及,多角経営,自留地栽培等緩和政策の推進を反映し,綿花,採油用種子等経済作物も前年に続き増産となった。
(c)82年の工業生産総額は5,577億元(対前年比7.7%増),うち重工業総生産額2,762億元(同9.8%増),軽工業総生産額2,815億元(同5.7%増)で81年に落ち込んだ重工業生産の回復が著しい。82年の産業別生産状況を見ると,エネルギーでは石炭6億6,600万トン(同7.1%増),電力3,277億kwh(同5.9%増)は順調だが,原油1億212万トン(同0.9%増)と横ばい,天然ガスは109億3,000万m3(同6.4%減)と減少している。国内在庫調整の進展を反映し粗鋼は3,716万トン(同4.4%増)と急速に回復し,セメントも9,520万トン(同14.8%増)と大幅に増産した。軽工業製品も増産を続けており砂糖338万トン(同6.6%増),綿布153億5,000万m(同7.6%増)はじめ,自転車2,420万台(同38.0%増)など耐久消費財も伸長している。
(d)82年には引き続き個人経営を含む労働雇用政策の改善が進められた結果,都市部の失業率は2%に低下した。大衆の生活水準は賃上げ,ボーナス支給などにより前年に引き続き上昇しており,82年都市家庭一人当たり年収は約500元(約65,000円,対前年比7・8%増),農民一人当たり年収も平均270元(対前年比20.9%増)で,300元を超すものが全体の22.6%を占めるに至っている。82年末の都市・農村の貯蓄残高は675億3,800万元で81年末に比べ約52億元増加した(同29%増)。82年末の一人当たり貯蓄残高は67元であった。
(e)対外貿易は国内経済調整の影響で82年には往復389億ドル(対前年比3.5%減)と減少した。これは主として機械設備等を中心に輸入抑制策が強化されたためで輸入総額は171億ドル(同12.1%減)にとどまり,貿易収支は47億ドルの黒字を記録した。82年の外資導入額は16億4,000万ドル,うち7億ドルは政府間借款及び直接投資である。82年末の外貨準備高は111億2,500万ドル(対81年末比2.3倍)となっている。
(2)我が国と中国との関係
(イ)趙紫陽総理の来日
趙紫陽総理が5月31日から6月5日まで来日したが,同総理は鈴木総理大臣と会談したほか,記念講演において「平和友好,平等互恵,長期安定」の三原則に従って両国関係を進めていくことを提唱した。
(ロ)教科書問題
7月,中国政府から,我が国の歴史教科書の日中関係に関する記述につき史実が改竄されているとして,誤りを正すよう申入れが行われた。我が国は,8月官房長官談話(資料編参照)により政府の基本認識及び是正のための措置を明らかにし,更に談話に盛られた措置の具体的説明を行った結果,中国側は,今後執られる行動を見守るとしつつ,日本側の説明を評価するとの立場を明らかにし本問題は外交上一応の決着を見た。
(ハ)鈴木総理大臣の訪中
鈴木総理大臣は9月26日から10月1日まで訪中し,趙紫陽総理,トウ小平党中央顧問委員会主任及び胡ヨウ邦総書記と会談したほか,国交正常化十周年の記念日にあたる9月29日,「豊かな交流と揺るぎない友好」と題する記念講演を行った(資料編参照)。
(ニ)日中経済関係
(a)82年の日中貿易は,往復88億6,324万ドル(対前年比14.7%減)と大幅に減少した。日中貿易が前年実績を下回ったのは,76年以来6年ぶりである。これは中国の対日輸入が機械設備を中心に大きく減退したためである。
(b)政府ベースの資金協力は,9月に,82年度分円借款の供与限度額を650億円とするとの内容の交換公文が締結された。また6月には「中日友好病院」建設計画に対する無償資金協力の第2年度分64億8,000万円の供与に関する交換公文が締結された。
(c)政府ベースの技術協力は引き続き交通運輸,企業管理,保健医療,農業,資源開発等の広範な分野で,研修員受入れ,専門家派遣,開発調査等の協力が積極的に行われている。
(d)輸銀の石油・石炭開発金融(4,200億円)については,これまでに2,856億円の融資契約が調印されている。
(e)日中長期貿易取決め(民間)は,9月に対日石油・石炭供給量を次のとおりとすることで合意された。
(単位:万トン)
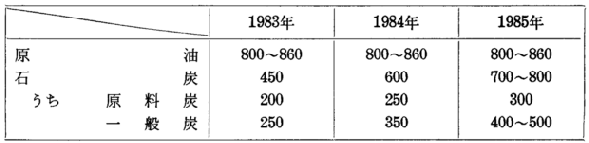
<貿易関係>(1982年,単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率%)
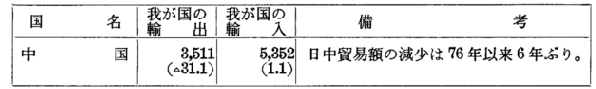
(出所:大蔵省通関統計)
<民間投資>(単位:百万ドル)
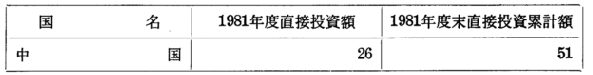
(届出ベース)
<経済協力(政府開発援助)>(1982年,単位:百万円,人)
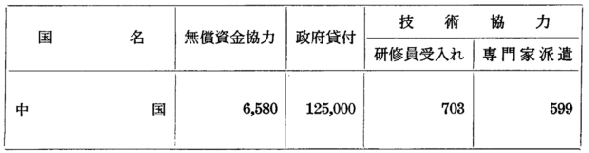
(約束額ベース)(DAC実績べース)
(ホ)人的往来と文化交流
日中間の人的往来は,72年(日中国交正常化当時)約9,000名であったのが,82年には15万名を超えたほか,両国閣僚レベルの往来も次表のとおり極めて活発になっている。
<要人往来>
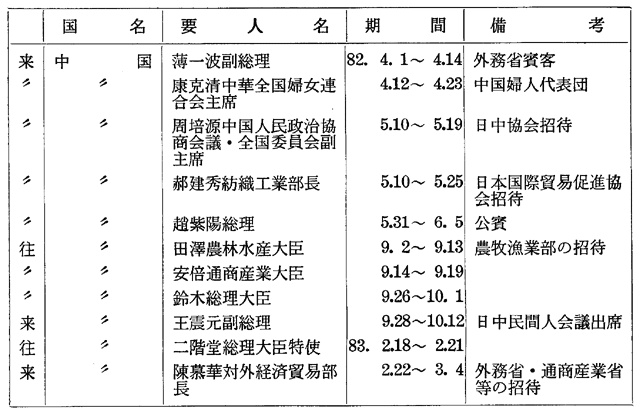
両国間の文化交流は,79年12月に両政府間で締結された文化交流協定等に基づき順調な進展を見せている。特に82年は日中国交正常化十周年にあたり,これを記念して政府をはじめ,友好都市及び各民間団体により各種文化行事が行われた。また,83年3月には,文化交流に関する第2回政府間協議が東京で開催され両国間の文化交流を一層発展させるべく意見交換を行った。
両国間では学者,留学生,青少年,芸術家,スポーツ選手等の交流,学術研究・調査の実施,各種公演,展示,講演会,映画会等が実施されており,交流の規模は着実に拡大している。
(へ)日中友好会館の建設
我が国の政界・財界及び関係団体を中心に日中国交正常化十周年の記念事業として,約100億円の建設費で東京に中国からの留学生・研修生等のための宿舎及び日中文化交流のためのセンター等を有する総合施設として日中友好会館を建設する計画が推進されてきているところ,9月鈴木総理大臣訪中の際,趙紫陽総理との間に,両国政府もこの計画を歓迎し積極的にこれを支援することが合意された。
(ト)中国残留日本人孤児問題
日中両国政府は,82年春以降,中国残留日本人孤児の養父母等に対する扶養費の支払いの問題等について協議を行ってきたが,83年1月両国政府は右問題の解決につき基本的合意に達した。その結果,83年2月から3月にかけて,45名の孤児について訪日肉親捜しが実施され,22名の身元が判明した。
(3)台湾
(1)内政
台湾においては1月に郷・鎮の県轄市長・県市議員選挙が行われ,81年11月の県市長,台湾省議員等の選挙以来の一連の地方選挙が一段落した。
その後,台湾の政情には大きな変化もなく平穏に推移したと見られる。
(2)外交
(イ)台湾は,82年においても引き続き外交関係を有する諸国に対しては既存の関係を維持する努力を続け(83年3月末23か国と国交,前年同期と増減なし。ただし,83年3月に象牙海岸との国交中止,ソロモンとの国交樹立があった),また,外交関係のない国に対しては実務関係を強化する努力を行った。その具体的現れとしては,4月にルクセンブルグと航空貨物路線を開設したこと,11月に台湾側の在米機関である北米事務協調委員会のボストン事務所が開設されたこと等が注目された。
(ロ)82年の中台関係においては,前年の葉剣英中国全人代常務委員長の9項目提案のごとき大きな動きはなかったが,中国側からは引き続き様々な「統一」を念頭においた働きかけがなされた。これに対し台湾側は,このような中国の統一の呼びかけを拒否ないし無視するとの立場を変えておらず,逆に「三民主義による中国統一」を主張している。第三国においては,学術面及びスポーツ面において若干の中台接触事例が見られた。香港を中継する中台間の間接貿易は中国側の消費財輸入抑制の影響を受けて82年には前年に比べ約30%減少した。
(3)経済
82年の台湾経済は引き続き景気不振の様相を深めていたところ,工業生産指数は81年に比べて0.8%の減少,実質経済成長率は81年より更に低い3.8%の伸びとなった。82年の台湾の対外貿易は前年比約6%減の約411億ドルとなったが,輸出が前年比約2%減に対し輸入が同約11%減であったため貿易収支の黒字は33億ドルに増加した。82年中の海外からの総投資額(承認額)は約3億8,000万ドルとほぼ81年並みの水準を維持した。
(4)我が国との関係
(イ)来日台湾人数は年々増加して,82年には前年より若干増加して約31万名に達し,また同年の訪台日本人数は前年より若干減少して約56万名であった。
(ロ)日台貿易は台湾側の大幅入超が続いているが,82年においては日台間輸出入額の約15%減という状況の下で台湾側の入超額は18億1,000万ドル(前年比約37%減,日本側通関統計)に減少した。2月13日以降台湾側は対日貿易赤字を改善し,必需品以外の消費品の輸入を削減するためとして,消費品1,500余品目の日本からの輸入禁止措置を実施した。7月に自民党国際経済対策特別調査会江崎会長一行が訪台した後,台湾側は8月,11月の2回に分けてVTR等数品目を除き右対日輸入禁止措置を撤廃した。また83年1月には台湾から日本市場調査団が来日した。
<貿易関係>(1982年,単位:百万ドル,( )内は対前年比増加率%)
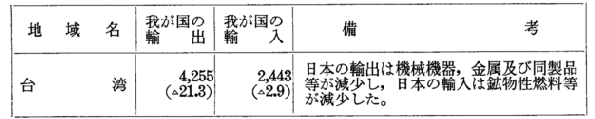
(出所:大蔵省通関統計)