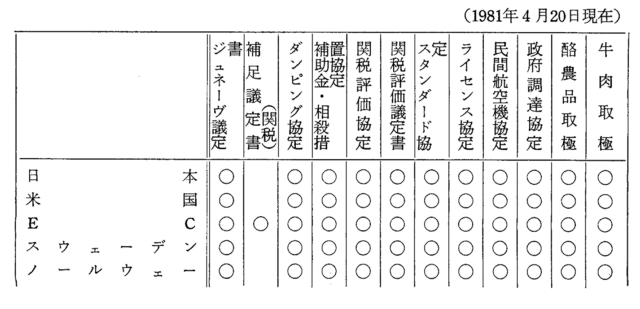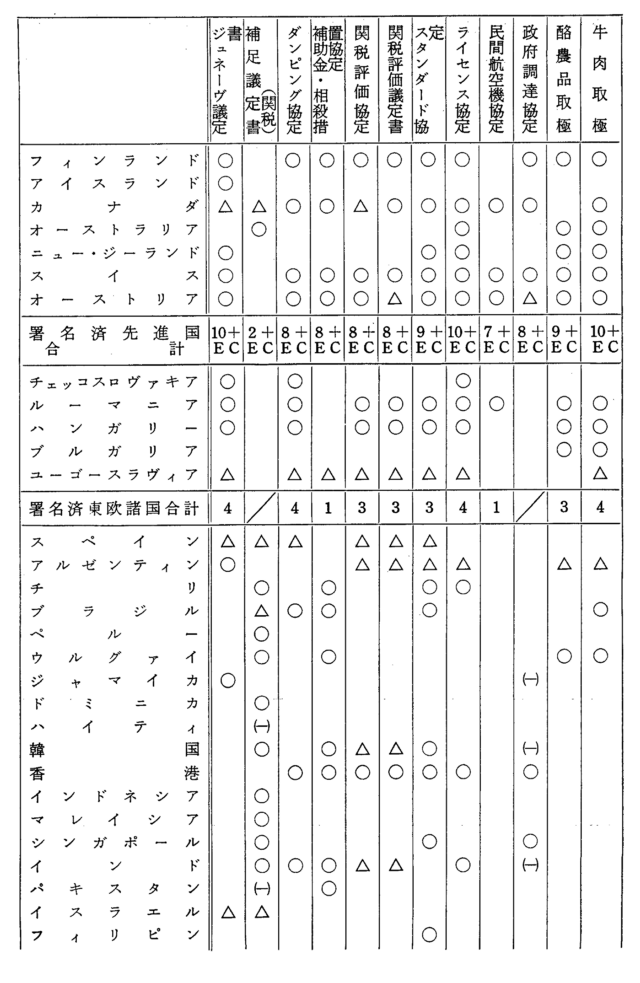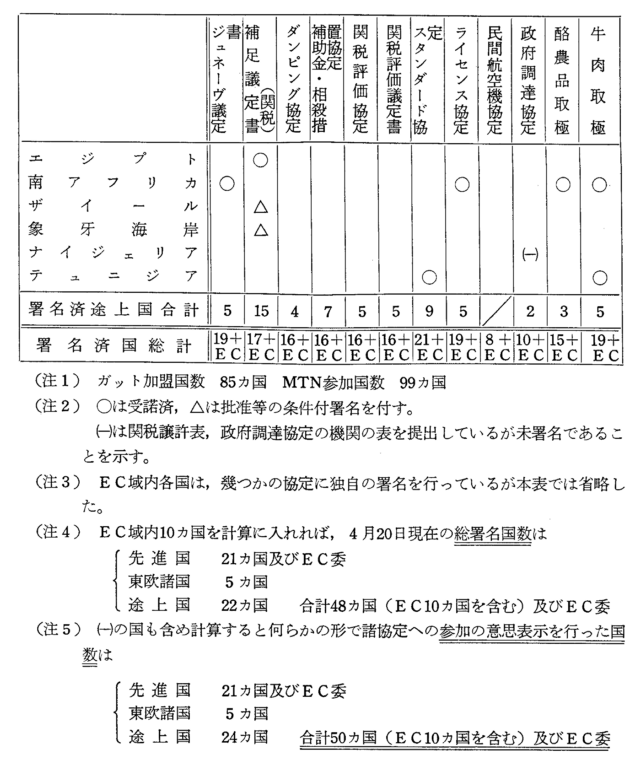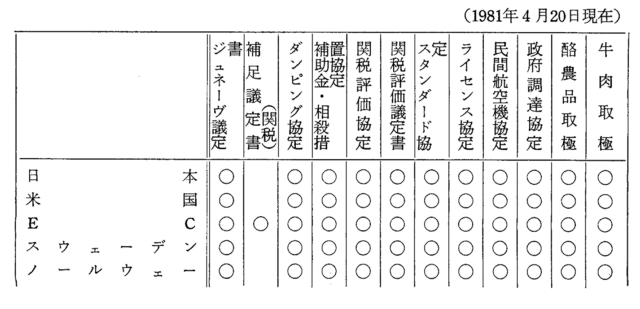
第2節 通商問題
(1) 80年の世界貿易はドル・ベースでは対前年比20%の伸び(79年25%増)を示したものの,数量ベースにおいては前年の6%増に比し1%増を記録したに過ぎず低水準となった。この伸び率の低下は,原油及び石油製品貿易量が10%近く減少したことを主に反映したものであるが,同時に,工業製品も79年の5.5%から3%まで伸び率を下げており,また工業国の輸入量は2%減(79年8%増),輸出量は3%増(同6.5%増)といずれも前年伸び率をかなり下回っている。石油を除く世界貿易量は4%上昇している。(統計はいずれもGATT資料による。)
(2) 石油価格の上昇などを背景に世界経済が停滞する中で,保護主義の高まりが危惧されたが,引続き開放貿易体制の維持・強化を図る努力が続けられた。6月にはその一環としてOECD貿易宣言が採択されており,更に同月開催のヴェニス・サミットの宣言においても,開放的な世界貿易体制を強化し保護主義的行動を求める圧力に立ち向かう決意が表明されるとともに,東京ラウンド諸協定の実施をコミットし,ガット体制の強化のためにできるだけ多くの国がこれら協定に参加することが求められた。
2. ガット及びOECD
(1) ガット
(イ) 81年1月1日には東京ラウンド諸協定のうち,政府調達に関する協定及び関税評価に関する協定が発効し,既に80年中に発効している他の7協定,2取極と併せすべての協定,取極が発効するに至った。わが国は他国に先がけて,これらすべての諸協定,取極を受諾している。各協定別の参加国リストは別表(215ページ)のとおりであるが,いずれか一つの協定又は取極にでも署名している国は,先進国が21カ国及びEC委(EC域内10カ国を含む),東欧諸国は5カ国であり,開発途上国は22カ国となっている(81年4月20日現在)。
(ロ) 東京ラウンド後のガットの第1の活動は,諸協定の下に各々設置された委員会の活動を通じて,これら協定の規定と精神が誠実に履行されることを確保していくことである。更に東京ラウンド交渉において解決の得られなかったセーフガードを始めとする問題についても引続き検討がなされており,ガットの作業の重要な課題の一つとなっている。
(a) セーフガード
セーフガードに関する交渉は東京ラウンドの最重要課題の一つとして進められたが,各国の意見の一致が見い出せぬまま作業はいったん中断され,79年末にはガット総会において新たな委員会が設置され作業を継続することが決定された。その後各国間で調整が行われているが交渉の妥結の目途は立っていない。
(b) 貿易開発委員会
(i) 東京ラウンド終了後のガッドの優先課題の一つとして南北問題が取り上げられ,79年11月の第35回総会においては,従来ガット第IV部(一般協定の途上国条項)実施のレビューを行っていた貿易開発委員会(CTD)の機能を強化すべく,次の5項目を同委員会の活動内容として決定した。(あ)貿易自由化計画(熱帯産品問題,関税前倒し問題,タリフ・エスカレーション,非関税措置(NTM)問題),(い)構造調整問題,(う)フレームワーク「授権条項」,ガット第IV部実施状況レビュー,(え)先進国がとる保護措置の検討,(お)LLDC問題の検討。
(ii) 以上を受けCTDは作業計画の具体化に着手し保護措置小委員会及びLLDC小委員会を設置し,また,貿易自由化計画については資料の収集・作成に努め,これら資料を中心に検討を行ってきている。途上国は熱帯産品につき早期に交渉を開始することを求めている。構造調整問題についてはガット全体の作業として検討が進められており,CTDはこの検討結果を踏まえて作業に着手する予定である。
(c) 18カ国協議グループ(CG18)
CG18は各国の貿易政策を中心にハイレベルでの自由率直な意見交換を行う場として,1975年に設置されたものであり,80年には3回にわたり会合がもたれた。議題としては,(あ)現下の経済情勢と貿易政策,(い)構造調整と貿易政策,(う)南北対話と貿易政策,(え)CG18の将来の作業が取り上げられた。このうち構造調整問題については,同分野でガットが果たし得べき役割について検討するため作業部会を設置することを理事会に助言し,右部会設置が11月に決定された。また,CG18の将来の作業として,(あ)サービス部門の貿易,(い)輸出制限及び輸出課徴金,(う)制限的商慣行,(え)MTNの実施,(お)紛争処理などを取り上げていくことが提案されている。
(2) OECD
(イ) 新たな保護貿易措置を導入しないとの「OECD貿易プレッジ」は,74年に採択されて以降毎年更新されてきていたが,80年6月の閣僚理事会では,多角的かつ開放的な貿易体制を維持・強化するとのOECD加盟諸国の決意をうたった新たな「貿易宣言」が採択された。同宣言には,具体的には特に多角的貿易交渉(MTN)の確実な実施,開発途上国との貿易関係の強化,貿易及び他の経常取引における制限的措置の回避,輸出競争を歪める措置の回避,積極的調整政策の推進による保護主義的効果を有する国内措置の回避が盛り込まれている。また今回の貿易宣言の大きな特徴は,有効期間を特に定めなかった代わりに,定期的に貿易政策及び貿易動向のレビューを行うことが明示されていることにあり,第1回目のレビューは81年前半に行うこととなっている。
(ロ) サービス分野の貿易(trade in services)について,OECD貿易委員会は79年から検討を始めていたが,80年中に幾つかのパイロット・スタディの対象分野(建設・エンジニアリングなど)について,何が貿易阻害要因になっているかを識別する作業が行われてきた。サービス分野は,今後OECDにおける貿易分野の重要な作業となろう。
(ハ) 南北貿易については,南北関係全般のコンテクストの中で,南北経済問題グループなどの場でも貿易関係の議論が行われ,他方貿易委員会では,一般特恵制度の改定問題,GN(国連包括交渉),UNCTAD貿易開発理事会の準備などが行われたが,特に目立った進展はなかった。
(ニ) 80年は西側先進国間の輸出信用アレンジメントの金利改定が国際貿易問題の焦点の一つとなった。多くの国における市場金利上昇に伴い,アレンジメントの最低金利が市場金利と大幅に乖離してきたため,是正策が必要であるとの声が米国その他より起こっていたが,80年2月には,アレンジメント会合ワレン議長の手になる金利スタディ・レポートが提出された。同レポートは是正策として,金利について通貨別にマトリックスを作り,定期的に金利水準を調整する通貨別変動金利体系(differ-entiated rate system;DRS),及び通貨別とせずに一律の金利を設定し,定期的に金利水準を調整する統一変動金利体系(uniform moving matrix;UMM)を提示していた。これを踏まえ,2月及び5月のアレンジメント会合で討議が行われたが,DRSを支持する国,UMMを支持する国,現状維持を望む国に分かれ,合意ができなかったため,12月1日までに新体系を造るべく交渉することとなり,とりあえず7月1日より高所得国及び中間所得国向けの最低金利については0.75%,低所得国向けについては0.25%それぞれ引き上げることが合意され,実施された。この12月1日までに合意という目標は,その後6月のOECD閣僚理事会及びヴェニス・サミットでも確認された。その後夏から秋にかけて数回にわたり交渉が続けられたが,ECが11月までマンデートを得られなかったため交渉が進展せず,時計をとめて12月にも交渉を続けたが,結局合意が得られず,その後も交渉が続けられている。
(1) 欧米先進工業国においては,インフレ下で経済成長が停滞し失業が増大している状況を背景として,保護主義的な風潮が強まりつつあったが,わが国としては,自由かつ開放的な貿易体制を維持・強化することが世界全体の貿易の健全な姿を維持し,世界経済の順調な発展を保つ上で不可欠であるとの考えから,自由貿易体制の維持・強化のための努力を行った。また,わが国は,市場の一層の開放に努めてきた。
(2) 米国との間においては自動車部品・タバコの関税引下げなど及び日本電信電話公社(以下電々公社)の調達の開放について話合いが鋭意行われたが,この結果電々公社調達問題については,12月19日交渉が妥結し,電々公社はその調達について内外企業を差別しない競争的な手続を採用することを決定した。また,自動車部品関税が撤廃され,タバコの関税引下げが行われる(それぞれ81年4月実施)など,両国間の着実な話合いの努力により問題の円満な解決が図られてきている。
(3) ECとの間においてはEC側は,対日貿易不均衡の増大に加え日本の輸出が特定のセンシティヴなセクターに集中していることに懸念を表明し,日本側の輸出抑制を求めた。これについては,大来政府代表のEC訪問(80年10月),日・ECハイレベル協議(81年1月)に加え,伊東外務大臣のEC訪問(80年12月)を通じ双方の立場についての理解を深めるとともに,日・EC通商経済関係の円滑な発展を図るための努力が行われた。
また,この過程において,わが国は,80年11月,ECとの経済関係に関する伊東外務大臣談話を発表し,わが国の基本的立場を明らかにするとともに,特定品目の集中豪雨的輸出が行われることがないよう勧奨していく所存である旨明らかにしている。
(4) わが国の80年の貿易額は輸出29兆3,825億円(対前年比30.4%増),輸入31兆9,953億円(対前年比32.0%増)といずれも高い伸びを示して過去最高となった。他方,これを数量ベースで見ると,輸出は第1四半期16.2%増(対前年同期比)となり,以後2ケタ台と好調を持続し,年間では対前年比16.7%増となって,マイナスに転じた前年(1.0%減)とは対照的な大幅増加となった。一方,輸入については,第1四半期に5.7%減とマイナスに転じた後落込みが続き,年間では対前年比5.9%減と前年(10.8%増)とは様変わりとなった。
(別表)