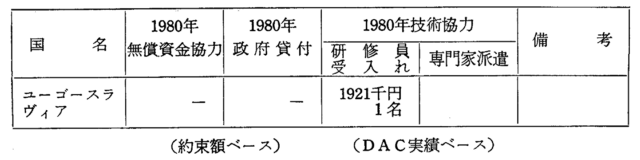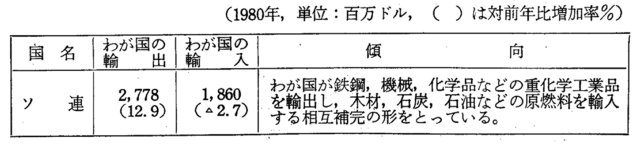
2. わが国とソ連・東欧諸国との関係
(1) ソ連
(イ) 北方領土問題
(a) 北方領土におけるソ連の軍備強化措置に関連し,80年2月8日,政府は,79年の2度にわたる日本政府の声明を再確認して,軍備強化の措置を速やかに撤回するようソ連政府に改めて強く申し入れた。
また,国会においても,3月13日衆議院,同月19日参議院のそれぞれ本会議で,「北方領土問題の解決促進に関する決議」が採択され,この決議は,4月11日に駐ソ魚本大使からフィリュービン外務次官を通じソ連政府に伝達された。
(b) 9月23日,伊東外務大臣は,第35回国連総会一般討論演説において,北方領土におけるソ連の軍備強化措置にも言及しつつ,外務大臣としては初めて北方領土問題を直接取り上げ,この問題に対するわが国の基本的立場を広く国際世論に訴えた。この翌24日,伊東外務大臣は,グロムイコ外相との会談において,北方領土返還要求は日本国民の総意であり,早急に領土問題を解決して平和条約を締結すべき旨,また,北方領土におけるソ連の軍備強化は日ソ友好に逆行するものである旨強調したが,ソ連側は従来からの頑固な態度を崩さなかった。
(c) 80年10月25日,26日の両日,伊東外務大臣は,北海道の現地関係者その他の強い要望にこたえ,現職の外務大臣として3回目の北方領土の現地視察(根室訪問)を行い,北方領土問題解決に対する政府の不動の姿勢と不退転の決意を改めて内外に表明した。
(d) 81年1月6日,1855年の日露通好条約の調印日にちなんで,「2月7日」を「北方領土の日」と設定することにつき閣議了解が行われた。この「北方領土の日」設定は,真の相互理解に基づく日ソ友好善隣関係の発展のためには,北方領土問題の解決が不可欠であるとの認識に基づき,この設定を強く求める国民の声及びこれを背景として,80年11月28日に国会の衆・参両院のそれぞれ本会議において全会一致で採択された決議の趣旨を踏まえて行われたものである。
1月20日,ソ連側は,「北方領土の日」設定などに関連して,わが国の北方領土返還要求運動を「ソ連に対する非友好的キャンペーンである。」として非難する口頭声明を行った。これに対し,同月28日,政府は,未解決の領土問題を解決して平和条約を締結することが,日ソ両国にとっての最も基本的な課題である旨を強調し,北方領土返還要求は,北方領土問題を解決し真の日ソ友好善隣関係を確立せんとする日本国民の総意であり,ソ連政府がこのような日本国民の真意を正しく理解し,真の友好善隣関係の発展にふさわしい態度を示すことを強く求める申入れを行った。更に,2月16日,ソ連側は,上記とほぼ同様の口頭声明を行った。
(e) 81年3月15日,伊東外務大臣は,ポリャンスキー在京ソ連大使と会談して日ソ関係の諸問題及び国際問題につき話し合い,日ソ間に真の信頼関係を築くためには,何よりも領土問題の解決が不可欠である旨を強調し,「日ソ関係において,領土問題は避けて通れない問題である。」と述べた。
(ロ) シベリア開発協力
日ソ間でこれまでに具体化したシベリアの資源開発を中心とする経済協力案件としては,既に終了したものとして,第1次及び第2次極東森林資源開発とボストーチヌイ港建設の3件があり,現在実施中のものとして,パルプ・チップ開発,南ヤクート原料炭開発,サハリン島大陸棚石油探鉱及びヤクート天然ガス探鉱の4件がある。また第2次極東森林資源開発を継続する新規プロジェクトとして,日ソ当事者間で交渉が行われていた第3次極東森林資源開発案件がまとまり,81年3月双方当事者間で基本契約が締結された。
実施中の各プロジェクトに関しては次の動きがあった。
(a) 南ヤクート原料炭開発
本プロジェクトに対する追加融資に伴う基本契約のアデンダムが81年2月日ソ当事者間で調印された。
(b) サハリン島大陸棚石油探鉱
80年にも79年に引続き天然ガス・油層の試掘に成功したほか,日ソ当事者間において開発に関する技術問題について話し合った。
(ハ) 日ソ貿易
(a) 80年の日ソ貿易は,輸入は前年水準をやや下回った反面,輸出が若干伸びたため,貿易規模は日ソ貿易始まって以来の最高額,46億3,800万ドル(対前年比6.1%増)を記録した。輸出の伸びは,主として従来からの中心品目たる機械・設備,化学品,繊維品の増加により,また輸入の減退は,主として中心品目たる木材,繊維原料などの不振による。
なお,日ソ貿易がわが国対外貿易総額に占める比率は1.7%を示した。
<日ソ貿易>
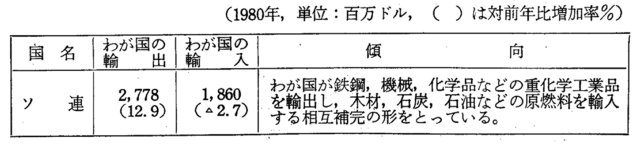
(b) 1976~80年日ソ貿易支払協定に基づき,81年1月東京において貿易年次協議(通算23回目)が開催され,5年間にわたる両国間の貿易の実績検討,貿易に関する諸問題について意見交換が行われた。
(ニ) 日ソ漁業交渉
(a) 「日ソ」及び「ソ日」両漁業暫定協定延長交渉
日ソ両国のそれぞれ相手国200海里水域内における漁業につき定めた「日ソ」及び「ソ日」漁業暫定協定が,80年末で失効するに伴い,両暫定協定を更に延長し,81年の日ソ双方の漁獲量を定めるための交渉が11月25日から12月6日まで東京で行われた。その結果,両暫定協定の有効期間を81年末まで1年間延長する議定書が締結されるとともに,日ソ双方の相手国200海里での漁獲量につき,日本側は75万トン,ソ連側は65万トンとすることなどが定められた。
(b) 日ソ漁業委員会定例会議
「日ソ漁業協力協定」に基づく日ソ漁業委員会の第3回定例会議が11月17日から22日まで東京で開催され,北西太平洋の漁業資源の検討並びに当該漁業資源の保存及びその合理的利用について協議し,81年度の両国間の漁業協力計画につき検討を行った。
(c) 日ソさけ・ます政府間協議
「日ソ漁業協力協定」に基づき,日本による80年度の海上におけるさけ・ます操業に関する日ソ政府間協議が4月2日から15日までモスクワで行われた。その結果議定書が締結され,ソ連邦200海里外の北西太平洋における日本の漁獲量を42,500トンとし,ソ連に対する漁業協力費として,日本側は37億5,000万円を負担する旨の合意がなされた。
(ホ) 墓参
6月,政府は80年の北方4島,ソ連本土及び樺太への政府ベースの墓参実施につき,ソ連政府に対し申入れを行った。これに対し8月,ソ連側は樺太(真岡,本斗,豊原)への墓参を認めること及びそれ以外の諸地点への墓参については同意できない旨回答してきた。政府は北方4島及びソ連本土への墓参について,人道的見地からこれが実現されるようソ連側の再考を求めたが,ソ連側は上記の回答を最終回答であるとした。以上の結果,80年においては10月2日から9日に樺太墓参のみが実施された。
(ヘ) 未帰還邦人
政府は,日本への帰国を希望する在ソ連未帰還邦人に対し帰国指導を行うとともに,機会あるごとにソ連側がこれら未帰還邦人に対し遅滞なく日本への帰国を許可するよう要請してきた。
80年においては1名が一時帰国した。
(2) 東欧諸国
(イ) ポーランド情勢に対するわが国の立場
80年8月以降のポーランドを巡る情勢は,その進展いかんによっては,ヨーロッパのみならず全世界の平和と安定に深刻な影響を及ぼす可能性があるものと危惧された。このような認識に基づいて,80年12月6日,政府は,ポーランドの問題は外部からのいかなる干渉にもよることなく,ポーランド国民自身によって解決されるべきである旨の伊東外務大臣談話を発表した。わが国のポーランド情勢に対する強い関心の表明は,第94回国会における伊東外務大臣の外交演説を含め,他の機会にも行われた。
ポーランド情勢の原因の一つに同国の経済困難があるところがら,同国において速やかに政治的安定及び一致して経済困難に取り組む態勢が確立されることが望まれる。これと同時に,各国がポーランドに何らかの形の経済的支援を行うことが必要であるとの観点から,わが国は欧米諸国との協調も考慮しつつ,ポーランドに対する協力について検討を行った。
(ロ) チトー=ユーゴースラヴィア大統領国葬へのわが国総理大臣の参列80年5月8日執り行われたチトー大統領国葬に,わが国からは大平総理大臣が参列した(同国葬にはサッチャー英首相,シュミット西独首相など主要国首脳を含む121カ国の代表が参列した)。
ユーゴースラヴィア側はこれを多とし,故大平総理大臣の葬儀(7月)にはスタヴレフ副首相(欧州からの参列者中最高位)を参列せしめてこれにこたえた。
(ハ) アルバニアとの外交関係設定
政府は,アルバニア人民社会主義共和国政府との間で外交関係設定についての交渉を行ってきたところ,交渉の妥結を見たので,81年3月10日ベオグラードにおいて,わが方中江在ユーゴースラヴィア大使と先方プラカ在ユーゴースラヴィア大使との間で,外交関係設定のための書簡の交換が行われ,同日付をもって両国間に外交関係が設定された。
(ニ) その他
80年2月,ハンガリーのプヤ外相がわが国を公式訪問し,両国の友好関係の増進に努力した。
条約関係では,80年にはハンガリーとの間に租税条約の署名,批准書交換,ポーランドとの間で同じく租税条約の署名と通商航海条約の批准書交換が行われた。
わが国の80年の対東欧8カ国貿易は,総額12億3,000万ドル弱で,対前年比微減となった。なお,政府レベルの経済混合委員会が,チェッコスロヴァキアなど6カ国との間で,それぞれ開催された。
(あ) <要人往来>
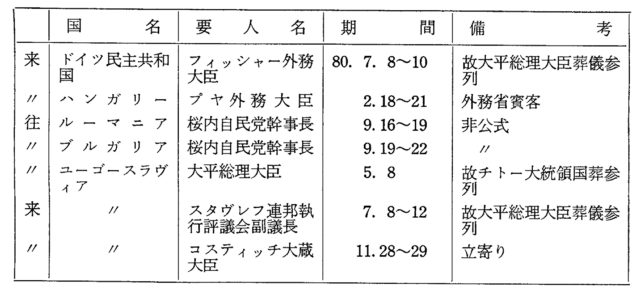
(い) <貿易関係>
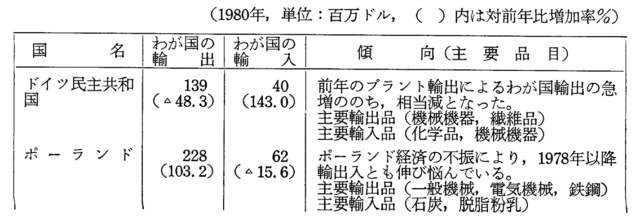
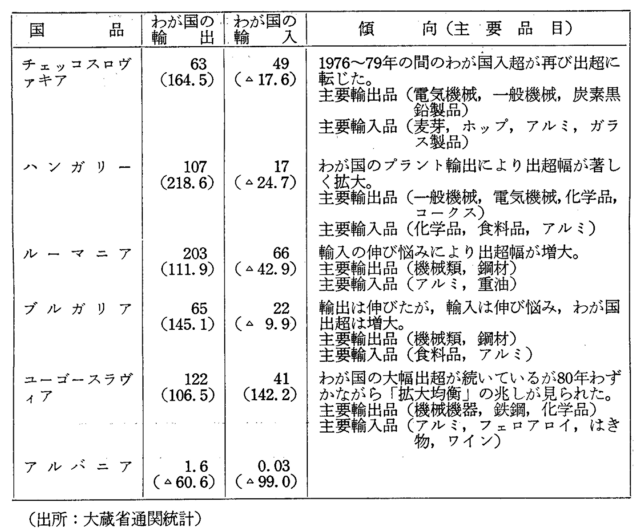
(う) <民間投資>
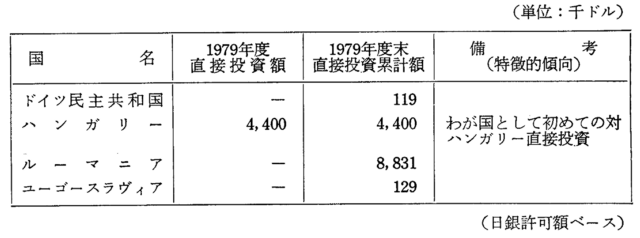
(え) <経済協力(政府開発援助)>