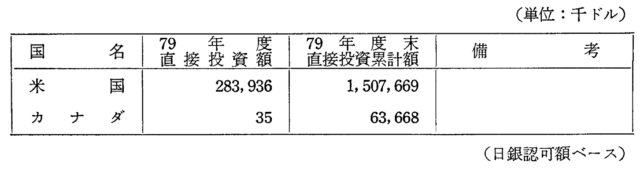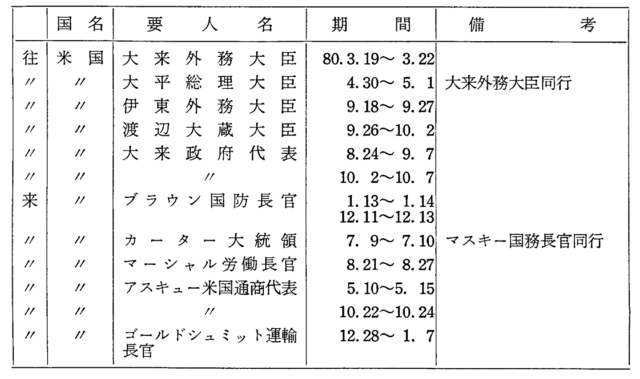
2. わが国と北米諸国との関係
(1) 米国
(イ) 日米経済関係
(a) 日米経済関係は,79年5月の日米首脳会談,同年6月の牛場・ストラウス会談によって比較的平穏に推移したが,80年初頭においても電電公社問題を始め,従来からの懸案はいまだ決着に至らず,また自動車,過剰米問題など新たな個別問題も顕在化してきた。
(b) 80年3月には大来外務大臣が訪米したが,米側閣僚との会談を通じて,日米経済関係は良好な基調にあるとの認識では一致したが,自動車問題に関する米政府の立場は,保護主義を回避するためにも,わが国自動車産業の対米投資とわが国市場の一層の開放を要望するというものであった。これに対して,大来大臣からは,問題の根本原因は需要の変化に対する米自動車産業の対応の遅れにあること,及び投資は企業の判断の問題であることなどを指摘し,この問題が深刻化して日米経済関係全般に悪影響を及ぼすことがないよう対処する必要のあることを強調した。
(c) 過剰米輸出問題については,4月の日米協議によって,80年から83年までのインドネシア,韓国,バングラデシュ,アフリカ諸国などへの輸出目標数量などにつきわが国の考え方を説明し,米側の理解を得たほか今後の協議メカニズムについて合意された。
(d) 5月には大平総理大臣が訪米し,カーター大統領との間で,日米両国が自由貿易を堅持することの重要性を再確認し,更に自動車,政府調達問題については,日米関係当局の間で問題の所在に対する理解とその対応に関する話合いが進んでおり,早期解決を図るべきことで意見の一致を見た。
(e) かかる一連の話合いを踏まえ,5月中旬アスキュー通商代表が訪日し,安川政府代表らと会談した。その結果,政府調達問題については引続き協議を継続することになったが,自動車問題については,アスキュー代表との意見交換をも踏まえ,日本政府はその自主的な措置として,(i)経済的に採算のとれる対米投資の勧奨,(ii)56年度からの自動車部品関税の原則撤廃,輸入車検査手続の追加的改善,自動車部品官民合同ミッションの米国への派遣(55年9月)などのわが国市場アクセスの改善を内容とするいわゆる「パッケージ」を発表した。このパッケージは米政府の評価するところとなった。
(f) 以上のような幾つかの進展を背景とし,9月初めに,米下院歳入委の貿易小委日米経済関係タスクフォースは,報告書(いわゆる第2次ジョーンズ・レポート)を発表したが,同報告書は日本側の市場開放努力を冷静に紹介し,日本の特有の貿易構造(エネルギー資源,食糧などの輸入のためには,輸出が不可欠)にも理解を示しつつ,長期的には,日米貿易問題解決のためには競争力,品質など米側の構造的問題の解決が一層重要になってきているとの認識を示した。
(g) 9月下旬には,伊東外務大臣が訪米し,自動車問題について日本政府は5月の「パッケージ」の履行に努めていること,わが国各企業の乗用車輸出に慎重な配慮を要請しており,55年第4四半期の対米乗用車輸出は前年同期実績を下回るとの見通しを得ていること,などを伝えた。また,伊東外務大臣から政府調達,たばこ問題については早期解決を期待するとの言及を行った。
(h) 11月末には,78年以来懸案であったたばこ問題が決着を見た。その結果,わが国としては関税率を引き下げ,また外国製たばこの販売,広告,流通の面においても大幅な改善がなされることとなった。
(i) また政府調達問題については,9月以降,12月までの間に5回にわたる大来政府代表とアスキュー通商代表との会談によって,日本側の主張した3段階方式を基礎として話がまとまり,12月19日に日米間で書簡を発出し,本件日米交渉は最終決着を見た。
(j) 12月には日米林産物委員会及び日米農産物会合が開催され,両国間の需給動向などについて意見交換が行われた。
(j) 日米間の貿易不均衡は,80年央ごろより再び拡大する傾向が現れ,米国議会など米側の一部にはこれを懸念する声が出てきた。結局80年の日本の対米黒字は,78年の101億ドル(米側統計116億ドル)には達しないまでも,79年の60億ドル(米側統計87億ドル)の水準を超え70億ドル(米側統計99億ドル)となった。日本側の対米黒字幅は81年に入ってからも拡大の傾向にあるやに見られる。
(k) 80年末から81年にかけて日米経済関係上,最も注目されたのが自動車問題であった。80年11月には,UAWなどの提訴に基づく調査の結果,ITC(国際通商委員会)は3対2の票決で輸入車は米国自動車産業の重大な被害の主要な原因ではないとの判断を示した。ITCのかかる判断にもかかわらず,米国自動車産業,議会には保護主義的な動きが高まった。これに対して,日本側からは,80年第4四半期,81年第1四半期の対米輸出見通しを発表し,各々見通しどおり前年同期比で若干の減少を示した。
(l) レーガン新政権に対しては,1月の天谷通産審議官訪米,2月の大来政府代表訪米を踏まえ,3月には伊東外務大臣が訪米し,レーガン大統領,ヘイグ国務長官らと会談した。この結果,日米間で自由貿易の原則の維持を主要な目的として,自動車問題について了解に達することを目指して話合いを続けることにつき意見の一致を見た。これに引続き,米国自動車産業再建のための国内施策などにつき説明のため,米政府ブリーフィング・チームが来日した。4月末にはブロック通商代表が訪日し,5月1日に日本側から3年間を限度とする対米措置(第1年度(81年4月~82年3月)の対米乗用車輸出を168万台に自主的に抑制することなどを内容とする)を発表し,これは米政府の歓迎するところとなった。
(ロ) 日米漁業関係
(a) 78年~79年においては,日米漁業関係は比較的平穏に推移したが,80年には,ブロー法案を始めとして,スタッズ法案,水産物貿易などが日米間で問題となり,これらの問題を巡り,政府レベル,あるいは民間レベルでの話合いが日米間で活発に行われた。
(b) 5月には,スタッズ法案(マグロを米国200海里法の対象に含めることが主たる内容)の審議との関連で,メキシコ湾におけるわが国クロマグロ漁船の漁獲活動が問題となったが,わが国関係業界が自主規制措置の強化(年間7,000尾,出漁隻数24隻)を打ち出したことにより,事態は鎮静化し,同法案の審議は中止された。
(c) また,同月には,外国漁業の米国200海里水域からの段階的締出し,入漁料の大幅引上げなど,外国漁業に極めて大きな打撃を与える内容を含んだ「米国漁業振興法案」(いわゆるブロー法案)の公聴会が開催され,同法案の審議が開始された。同法案は,結局11月に至り成立したが,成立した法の内容は,その間においてわが方官民より強力な対米働きかけが行われたこともあり,当初の内容に比べ相当緩和されたものとなった。今後は同法案の運用ぶりにつき注視する必要がある。
(d) 7月には,ワシントンにおいて日米水産物貿易協議が開催されたが,この協議において,わが方が輸入制限枠の運用の改正などを行うことを表明したことにより,2年越しの懸案であった本件問題が決着した。
(e) 80年末には,81年度の対日割当についての日米協議が行われたが,その過程で,ズワイガニを81年から禁漁にするとの動きが明らかとなり,日米間で大きな問題となった(81年4月現在未解決)。
(ハ) 日米安全保障条約
(a) 緊密な協議・協力
日米安保条約は,わが国のみならず,極東の平和と安全の維持に大きく寄与してきている。80年においても,日米安保条約の円滑かつ効果的な運用を図るため,日米間において引続き緊密な協議及び協力が行われた。
80年3月には大来外務大臣が訪米し,安全保障問題についてヴァンス国務長官,ブラウン国防長官などと幅広く意見交換を行:い,次いで,5月初めには大平総理大臣が訪米し,カーター大統領と会談した。同会談においては,イラン,アフガニスタン問題を始め国際情勢などについて幅広く意見交換が行われたが,同会談に際し,カーター大統領から,日本が防衛力の面で努力していることを多としており,今後の一層の努力が有益であるとの見解の表明があった。これに対し,大平総理大臣は,防衛力については今後とも自主的に一層の努力を続ける決意であり,わが国としても何を行っていくべきかについては真剣に検討していきたい旨述べた。
9月には伊東外務大臣が訪米し,マスキー国務長官,ブラウン国防長官などと国際情勢,安全保障問題などについて幅広い意見交換を行った。
12月にはブラウン国防長官が来日し,鈴木総理大臣及び大村防衛庁長官と会談し,国際軍事情勢などについて意見交換を行い,その際わが方からは,わが国が行っている防衛努力についての説明を行った。
更に,81年3月には,レーガン米新政権成立後の初のわが国の閣僚として伊東外務大臣が訪米し,レーガン大統領,へーグ国務長官,ワインバーガー国防長官などと現下の国際情勢及び二国間情勢につき幅広く意見交換を行った。その際,米側から一般的な形でわが国の自衛力強化についての期待が表明され,これに対してわが方からは,わが国としては憲法上その他の制約の範囲内で防衛力の整備に尽くしていきたい旨述べた。
(b) 日米安保体制の円滑な運用
政府は,日米安保条約・地位協定の目的達成と施設・区域周辺地域の経済的・社会的発展との調和を図るため,在日米軍施設・区域の整理統合を推進してきたが,80年においても施設・区域の全面返還,一部返還が相当数実現した。
また,81年度の在日米軍関連予算は,在日米軍のより円滑な駐留に資するよう前年度に引き続き増額された。
(ニ) 日米原子力問題
78年3月に発効した米国の新核拡散防止法は,米国産核物質などの受領国と米国との間の原子力協定について米国の規制権を強化する方向で改正することを求めている。日米原子力協定の改正に関する非公式協議は79年2月に行われたが,80年には目立った動きは見られなかった。
77年9月の日米交渉で合意を見た東海再処理施設の運転期間は81年6月1日まで延長され,再処理量も当初の99トンの枠に50トンが追加され更に,81年6月1日の口上書交換により,同施設の運転期間は81年10月31日まで延長された。
そのほか80年中,日米間で原子力平和利用と核不拡散に関する種々の協議が行われ,この分野における日米間の協力関係はますます緊密化した。
(ホ) 日米医学協力委員会など
日米医学協力委員会は,1966年に設置されて以来順次協力分野を広げ,現在,結核,肝炎など8専門部会において,日米共同で基礎的医学研究を実施してきている。10月16,17日の両日,東京において第16回合同委員会を開催し,第3次5カ年報告書を採択した。また同会合に先立ち免疫シンポジウムを開催した。
日米科学協力委員会は10月6,7日の両日東京において共同議長会議を開催し,前年度の活動報告を行うとともに,過去20年間の協力活動を総括する20年報の作成などにつき討議した。
<要人往来>
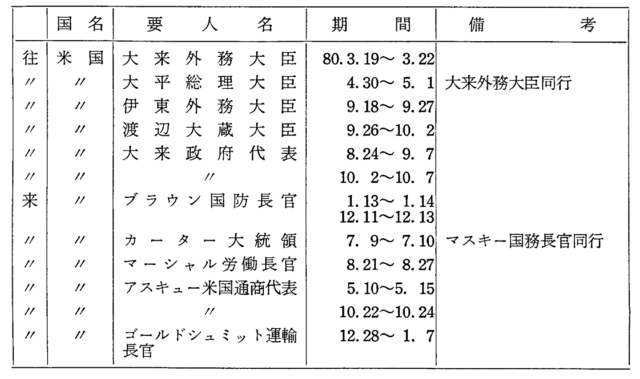
(2) カナダ
(イ) 日加関係全般
80年5月の大平総理大臣訪加は,従来の貿易経済分野中心の日加関係が政治分野での連帯を強め,更に文化,科学技術などの分野でも多様かつ立体的な発展を遂げていくための重要な契機となるものであった。
総じて,日加友好協力関係は従前にも増して盛り上がりを見せ,諸種の分野における両国官民レベルでの交流は極めて活発に進められた。
(ロ) 日加経済関係
(a) 80年5月の大平総理大臣の訪加,9月にアルバータ州バンフにおいて開催された第3回日加経済協力合同委員会での意見交換を踏まえ,種々の分野で両国間の経済協力関係に進展が見られた。
両国間の貿易動向は,引続きわが国の工業製品の輸出,カナダの一次産品輸出という形で相互補完関係にあり,往復貿易額は過去10年間で約3.8倍の71億6,000万ドルに達した。なお,二国間貿易収支は一貫して日本側の入超(80年は22億9,000万ドル)で推移している。
エネルギー分野では,わが国はアルバータ州のオイル・サンド開発のため加側企業などとの共同事業として二つの実験操業に参画し,その成果を収めつつある。石炭貿易に関しては,日加間で安定的な貿易関係が図られてきているが,80年5月の総理訪加に際してカナダ側から言及のあったBC州北東炭(原料炭)の対日輸出問題については,81年2月に至り,日加業界間の長期契約が締結されるに至った。また,一般炭の対日輸出問題についても,80年中には日本側関係者の訪加などを通じ意見交換が行われつつある。更に,石油に関しては,81年2月,日加業界間でボーフォート海石油開発に関する契約が締結された。
農林産業分野においては,わが国は菜種,小麦,大麦,製材などを安定的にカナダから輸入しており,特に対加依存度が高い菜種(100%)については,7月には日加菜種会議がカナダにおいて開催され,有益な意見交換を行った。
漁業分野では,78年4月の日加漁業協定に基づき3月に対日割当及び資源保存や技術協力に関する政府間協議が行われ,また,9月にも水産物貿易に関する協議が行われた。
(b) 民間レベルにおいても,80年5月京都において第3同日加経済人会議が開催されるなど活発な交流が行われた。
(c) 80年中においては,カナダ自動車産業の不振を背景にカナダに対する日本車輸出増の問題がカナダ国内において次第に注目を集めるに至った。カナダ側は,81年5月のわが国の対米乗用車輸出自主規制などにより日本車のカナダヘの輸出転換のおそれを強く懸念するに至り,日本側に対米措置と同様の措置を要請した。これに対し,日本側は81年4月~82年3月の対加乗用車輸出は,80年暦年実績(158,000台)の10%増を上回らない見通しであることなどをカナダ側に伝え,カナダ側もこれを評価した。
(ハ) 日加原子力問題
78年8月に署名された日加原子力協定改正議定書は80年5月国会の承認を得,9月2日発効した。改正後の協定に基づき日加間で各種の意見交換が行われた。
<要人往来>
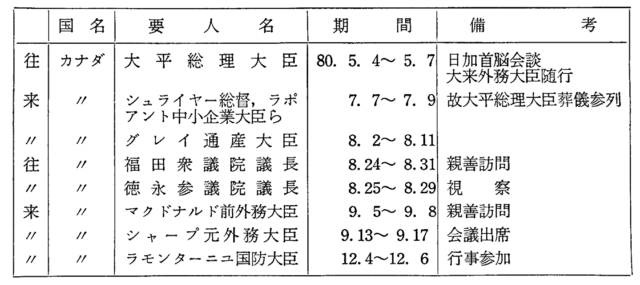
<貿易関係>
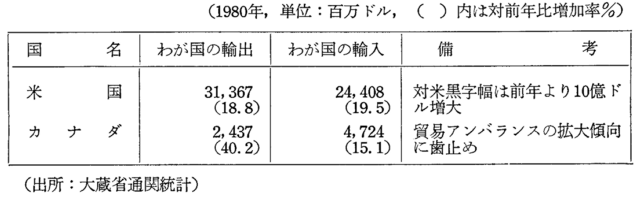
<民間投資>
(あ)わが国の対北米直接投資

(い)北米のわが国に対する直接投資