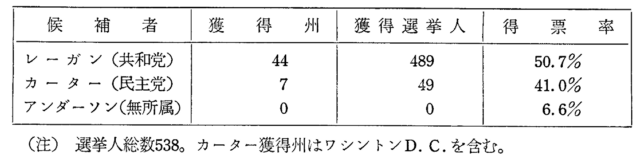
第3節 北米地域
1. 北米地域の内外情勢
(1) 米国
(イ) 内政
(a) 1980年大統領選挙で再選を目指したカーター大統領は,在イラン米国大使館人質事件と,ソ連のアフガニスタン軍事介入事件の発生を契機とした世論の結束を背景に,選挙の序盤戦で優位に立った。しかし,イラン及びアフガニスタン問題の解決が長引くにつれて国民の結束は弱まり,逆に焦燥感がつのるとともに,インフレを始めとする経済情勢の悪化に対する不満が増大し,カーター大統領の指導力が問われた。民主党全国大会(8月)はカーター大統領を党候補に指名したものの,大統領の人気低迷(6月以降世論支持率30%前後)を背景に,ケネディ上院議員が最後まで挑戦をあきらめないなど党内不一致が目立った。
共和党側では多くの候補が出馬したが,知名度,選挙組織の点で群を抜くレーガン前カリフォルニア州知事が早くから独走態勢を確立し,共和党全国大会(7月)は,政権奪還の希望に燃える熱狂的雰囲気の中で,満場一致でレーガン候補を指名した。
両党全国大会以後の本格的選挙戦については,政策論争,有権者の関心とも低調で,選挙結果の予測が困難な選挙と言われた。カーター大統領の人気が低い一方,レーガン候補についても超保守的政治家との印象から不安感が根強く,多くの有権者がいずれを支持するか決めかねていたのが特徴であった。選挙後の調査によれば,投票率は52.3%で,この30年間で最も低く,また投票した者の35%は最後の1週間に態度を決めたと言われる。
(b) 11月4日投票の結果は表1のとおりであり,レーガン候補の地滑り的勝利であった。同候補はその地盤である西部はもとより,ニューヨークを始め東部,中西部の主要州をすべて制し,更にカーター大統領の地盤である南部でも圧勝した。
レーガン候補当選の原動力は反カーター票であり,国民はカーター大統領の人柄と思想傾向に好感を抱きつつも,結局大統領は米国の現状を変革する有効な処方筆も強力な指導力も欠いているとして,政権交代を求めたと言える。各種世論調査によれば,レーガン候補に投票した者のうち,カーター大統領に対する失望・不満から政権交代を望んだ者が40%以上に上り,レーガン候補に対する積極的支持は30%に過ぎなかった。カーター,レーガン両候補の得票率と76年選挙と比較してのカーター得票率の変動ぶりは,表2のとおりである。黒人を中心とする非白人を除き,民主党支持層の大幅なカーター離反が見られた。
レーガン候補の勝利を助けた要因として,ここ数年顕著となってき
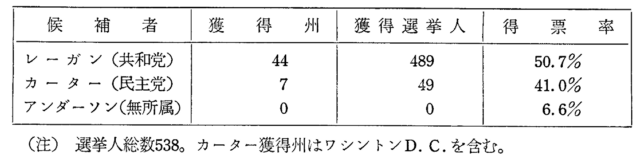
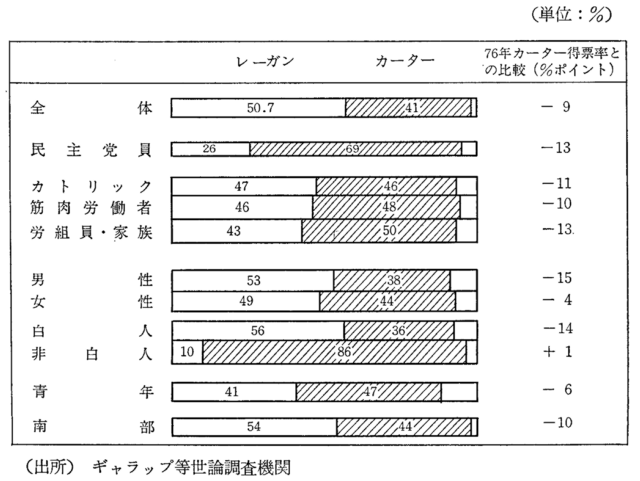
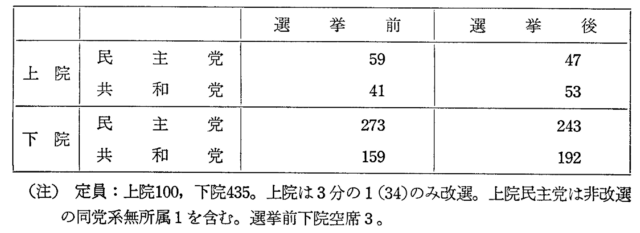
た国民の保守化の傾向を見落とせない。政府の役割の増大を通じて経済社会問題の解決を図ろうとする伝統的リベラリズムに対して,国民は懐疑的となりつつあり,国民生活に対する政府の関与の縮小を標榜するレーガン候補の保守的立場が受け入れられやすい状況になっていると言える。レーガン候補のソ連と共産主義に対する強硬姿勢,力による平和維持の主張も,国際社会における米国の威信回復を待望する国民の気持に訴える力があったと言えよう。
保守化の傾向とリベラリズムの退潮は,大統領選挙と同時に行われた議会選挙にも反映された。共和党は,表3のとおり,上院で一気に過半数を超え,下院でも大幅に勢力を伸ばした。多くの有力な民主党リベラル派議員に代わって保守的な共和党の新議員が当選した。共和党が上院で多数党となるのは54年以来のことである。レーガン大統領の当選と共和党の躍進について,米国のジャーナリズムは,「右への大旋回」,「米国政治の転換点」と報じ,一部には,リベラリズムの上に広範な国民の支持を維持してきた民主党にとって,党理念,党支持基盤の再構築が必要であるとの見方が生じている。
(c) レーガン新政権の滑り出しは1頂調である。レーガン大統領の「強力な米国」を回復しようとの呼びかけ,米国の伝統的な「自由」の理念にのっとった経済の再建,軍備増強と力による平和維持といった基本政策,更には実務型の政権人事と「チーム・ワーク」による政権運営,施政に当たり議会を始め広範な国民の合意を求めようとする積極的姿勢などは好感をもって迎えられている。しかしながら,新政権が80年選挙で国民から託された「現状変革」の使命を果たせるかどうかは,国民の最大関心事であるインフレを始め具体的問題について,今後いかに有効な政策を実施できるかにかかっていることはもちろんである。
(ロ) 外交
(a) カーター大統領は,1979年末の在イラン米国大使館占拠人質事件とソ連のアフガニスタン軍事介入事件以来高揚した米国内の危機意識を背景に,80年1月の年頭教書で,いわゆるカーター・ドクトリンと呼ばれる強硬な外交姿勢を表明し,国の内外において力を強め危機に対処していく決意を表明した。同時に,80年は大統領選挙の年であったため,これらイラン,アフガニスタン事件などの重要国際問題への対応は,極めて内政的な意味合いを有することとなり,米国の力と指導性の回復を唱えるレーガン共和党候補と,このように力のみを重視するレーガンの姿勢は米国を戦争に巻き込みかねないとするカーター大統領の間の「戦争と平和」の問題が国内経済問題と並んで選挙の争点となった。
こうした中で,国内経済の悪化と対外的な米国の威信低下に対する国民の焦燥感を背景に圧勝したレーガン新大統領は,ソ連の軍事力増強と第三世界への進出に強い懸念を表明し,同盟・友好国との協議・協調を重視しながら,「強い米国」を実現し,「力による平和」を確立して,これに対処していく決意を表明している。
(b) 80年の米国外交の中で注目すべきものは,米ソ関係,イラン問題対同盟国関係,対中東政策,米中関係などである。
(c) ソ連によるアフガニスタンヘの軍事介入で大幅に後退した米ソ関係は,マスキー国務長官とグロムイコ外相との2度の会談(5月ウィーン,9月ニューヨーク)は行われたものの関係修復には至らず,SALTII条約も議会での審議が中断されたまま,承認には至らなかった。更にレーガン政権発足後は,同大統領が強い対ソ姿勢を表明し,SALTを始めとする軍備管理交渉をその他の分野におけるソ連の行動と関連付けていく「リンケージ」政策を標榜していることや,エルサルヴァドル問題などでソ連が国際テロリズムを支援していると批判していることなどから,両国の関係修復にはなお時間がかかると見られている。また当面の米ソ関係を左右する要因としてポーランド情勢の帰趨が注目されている。
(d) 79年11月に発生した在イラン米大使館人質事件は,80年末以降のアルジェリアを仲介とする交渉の結果,81年1月19日,米,イラン間に合意が成立し,同月21日,52名の人質は444日ぶりに解放された。その間米国は,イランとの外交関係断絶や対イラン制裁の実施,実力による人質救出行動などを通じて本件の早期解決を達成せんとしたが,人質救出行動の失敗は,本件を巡ってカーター大統領と見解を異にしたヴァンス国務長官の辞任を招き,国民の挫折感を深めた。また,そうした中で,人質事件発生を契機に上昇していたカーター大統領に対する支持率も,解決が長引くにつれて下降し,大統領選挙でレーガン候補に勝利をもたらした一因になったとも言われる。
(e) 対同盟国関係では,80年においても,主要国首脳会議やNATOの場を通じて協調関係強化の努力がなされた。しかし,一方ではイラン,アフガニスタン問題との関連で対イラン制裁や対ソ措置が西側の同盟関係に新たな試練を提起し,ペルシャ湾地域の安全保障などで米国が多大の負担を負う決意を固めるにつれて,NATO諸国や日本に一層の防衛責任分担を求める声が強まった。
(f) 対中東政策では,カーター大統領は,ペルシャ湾地域を支配しようとする外部勢力のいかなる試みも米国の死活的利益に対する攻撃と見なす(カーター・ドクトリン)との認識の下に,緊急展開部隊の創設,ケニア,ソマリア,オマーンとの施設利用取極締結など,同地域の安全確保に努めた。
中東和平については,80年1月にエジプト,イスラエル間の国交正常化は実現したものの,パレスチナ自治問題についての合意成立には至らなかった。なお,米国政府は,レーガン政権下においても,キャンプ・デーヴィッド合意に基づいて本件解決を図っていく旨を明らかにしている。
(g) 対アジア政策では,カーター大統領による故大平総理大臣葬儀への参列,中国との関係拡大,マスキー国務長官による米ASEAN外相協議への参加,インド,パキスタンとの関係改善努力などアジア諸国との緊密な関係の維持に努めた。特に米中関係では,故大平総理大臣の葬儀に参列したカーター大統領と華国鋒総理との間で首脳会談が実現したほか,ブラウン国防長官の訪中(80年1月)や耿ヒョウ副総理の訪米(5月),米中貿易協定の発効(2月)など軍事,経済面の交流拡大が見られた。
(h) 以上のほか,モンデール副大統領のアフリカ歴訪(80年7月ナイジェリアほか)やマスキー国務長官の訪墨(11月)などを通じて中南米,アフリカ諸国との関係強化にも努めた。
(ハ) 経済情勢
(a) 80年全般の経済情勢
80年の米国経済は,前年に続く個人消費支出の牽引によって第1四半期3.1%のプラス成長(前期比年率)を記録した後,第2四半期には一挙にマイナス9.9%と戦後最大の落込みとなった。
しかし,第3四半期には弱含みながらもプラス2.4%の成長に回復した後,第4四半期もプラス4.0%の成長を記録し,第2四半期の急速だが短期間の景気後退から徐々に回復基調をたどることとなった。
今回の景気後退は,ピーク1月,底は8~9月で戦後6回の景気後退の中でも短期間に終わったが,全体の落込み幅は3~3.4%程度で中程度の景気後退であった。
景気後退の主な原因は,需要の3分の2を占める個人消費支出が実質可処分所得の急減,インフレの一層の悪化,金利の高騰と消費者金融規制の導入などにより急速に減少したからであるが,特に80年3月の通貨当局による消費者金融規制を含む金融引締めが既に下降に転じていた景気の後退に拍車をかけたと言われている。
他方景気回復の主たる原因は消費者金融規制の撤廃(7月)と金利の低下により個人消費支出がいち早く回復に向かったことにあるが,これに加え前回の不況時のような過剰在庫がなかったため,需要の回復に伴い生産の回復が速やかに行われた面もあると見られている。
また,インフレについては,石油市場の需給緩和などによって高水準ではあるが徐々に改善基調をたどった。しかし,消費者物価上昇率で見ると80年通年では前年の11.3%を超える13.5%(いずれも年平均伸び率)を記録した。
(b) 81年初頭の動向及び81年の見通し回復基調にあった米国経済は,再度の金利上昇(プライム・レートのピーク21%)などにより若干停滞に転じている。一方,インフレは国内石油価格の統制撤廃によるエネルギー価格の上昇もあって引続き高水準を維持している。
81年の米国経済の見通しについては,政府,民間とも年平均で1.1%程度の実質成長を予想している。他方インフレの見通しについて,レーガン政権は11.1%(消費者物価上昇率)と80年に比べ若干鈍化するとしているが,82年以降,経済再建計画の影響が現れ急速にインフレが鈍化する結果,83年には6.2%(同)まで低下すると予想している。
(c) 政府の経済政策の動向
カーター民主党政権に代わって登場したレーガン共和党政権は,経済における政府関与の縮小と民間活力の増大及び一貫性ある経済政策の運営を通じた国民の経済政策に関する信頼感の回復を基本方針として,2月18日に経済再建計画を発表した。
同計画は(i)財政支出の伸びの削減(82年度については486億ドル削減),(ii)減税(個人所得税の3年間にわたる毎年10%減税及び減価償却期間の短縮),(iii)政府規制の緩和,(iv)安定的な金融政策,の四つの骨子から成っている。
財政支出削減と減税の同時実施は従来にない新しい経済政策の組合せであり大きな注目を集めているが,これらは議会審議を経なければならないので,今後の動向が注目されるところである。
(2) カナダ
(イ) 内政
80年2月,政変により実施された総選挙の結果,自由党は進歩保守党から政権を奪還し,トルドー自由党党首は,79年6月の首相退陣後,わずか9ヵ月で首相に返り咲いた。
しかし,同総選挙では,自由党は単独で過半数の議席を制したものの,伝統的に支持基盤の極めて弱い西部諸州における念願の勢力伸長を果たし得ず,同党支持と進歩保守党支持が従来から東部と西部にそれぞれ偏るという地域的政治分極化の状態は解消されなかった。
ケベック州分離独立問題については,同州政権の主権連合構想(ケベックは,政治的にはカナダから独立し,経済的にはカナダと連合することなどを提唱)は80年5月の州民投票で否決され,一応決着を見たが,同年10月,トルドー政権が連邦議会に上程した憲法改正案の賛否を巡り,国民世論は分裂を深めた。
(ロ) 外交
80年3月3日,クラーク首相より政権を引き継いだトルドー首相は,対米協調を柱とする従来のカナダ外交を踏襲する一方,米国と他の西側諸国及び第三世界諸国との間の有効な橋渡し役になりたいとして,外交の多角化を積極的に推進した。
同年,トルドー首相は6月と11月の2回外遊し,西欧及び中東9カ国を歴訪,また,81年1月,アフリカ及び中南米4カ国を歴訪し,わずか10ヵ月程度の間に首相自ら3回にもわたる首脳訪問外交を意欲的に展開したことは注目される。
アジアとの関係では,カナダは,従来,太平洋国家としての自国の位置や役割について認識を深めつつあるが,トルドー首相は,80年5月の大平総理大臣訪加の際,わが国の環太平洋連帯構想に前向きの関心を示すとともに,クラーク前政権と同様,対日重視の姿勢を強めている。
(ハ) 経済情勢
米国経済と密接に結び付いているカナダ経済は,米国と同様,80年に入り景気後退に見舞われ,この結果80年通年の実質経済成長率はわずか0.1%となった。
一方,消費者物価で見たインフレは徐々に上昇傾向にあったが,80年に入り前年同月比は2ケタに達し,80年の消費者物価上昇率も10.1%を記録した。
国際収支について見ると,貿易収支が国内需要の停滞による輸出の伸びによって約80億ドルと前年の2倍以上の黒字を達成した結果,経常収支の赤字幅も74年以来最低の15億ドルに改善した。
かかるインフレと景気停滞の同時進行に対し,通貨当局は通貨供給量の伸びの抑制を目標に政策運営を行ったが,これにより公定歩合・市中短期金利が高騰したため,国内には景気に対する悪影響への懸念も生じた。
また,クラーク進歩保守党政権に代わって登場したトルドー自由党政権は,インフレ抑制のため財政支出の抑制を目標とするとともに,80年10月には,輸入石油への依存軽減などを目標とする「国家エネルギー計画」を発表し,連邦政府主導型のエネルギー政策を行う旨明らかにしたが,石油産出州は州の資源所有権を侵害するものとしてこれを批判しているほか,エネルギー産業のカナダ化を進めるとの方針に米国のメジャーも強く反発しており,同計画についての議会審議は難航している。