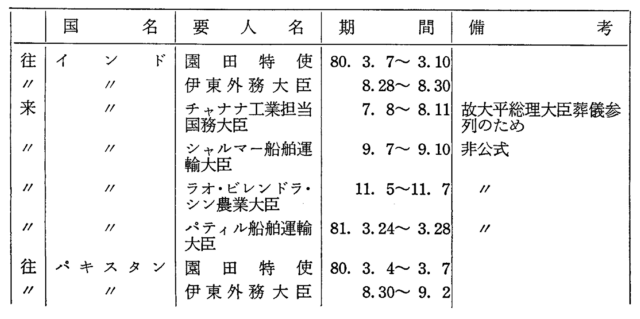
7. 南西アジア地域
(1) 南西アジア諸国の内外情勢
(イ) 概要
80年を通じ南西アジア地域においては政権交代はなく,各国政情は,種々不安定要因を抱えながらも基本的には平静に推移した。
域内各国の経済は,おおむね農業生産の好調に支えられ,比較的順調な伸びを示したが,各国ともに原油価格の高騰により外貨収入の大半を原油購入代金に充てざるを得ず,各国の貿易収支は,深刻な赤字基調となった。
域内各国はまた,アフガニスタン問題,イラン・イラク紛争などにより混迷の度を深める国際情勢に対処するため活発な外交活動を展開した。パキスタンは,1月及び5月イスラム諸国外相会議を主催し,インドは,81年2月,非同盟外相会議を主催した。更に,パキスタン及びバングラデシュの両国首脳は,イラン・イラク紛争のイスラム親善使節団に参加,インドの外相は,同様な非同盟のミッションに参加するなど,紛争解決のため尽力している。
80年5月,バングラデシュのラーマン大統領は,域内各国(インド,パキスタン,スリ・ランカ,ネパール,モルディヴ,ブータン)首脳に親書を発出し,域内全般にかかわる諸問題につき自由な意見交換を行うため首脳会議の開催を呼びかけた。右首脳会議の準備会議として,81年4月,域内の外務次官がコロンボにおいて会議を行うこととなった。
(ロ) インド
(a) 内政
1月の下院総選挙に大勝して政権に返り咲いたコングレス(1)党のガンジー政権は,5月に野党の支配する主要9州の州議会選挙を断行して,うち8州を掌中に収め地方の地盤をも固めるとともに,上院においても過半数を得て政権基盤を更に強固にした。
しかしながら,ガンジー首相の後継者と目され,党務をとりしきってきた次男サンジャイ氏の事故死(6月)は,ガンジー首相にとって痛打となりサンジャイ氏の下で進められていた諸政策は中断を余儀なくされた。
(b) 外交
ガンジー新政権は,非同盟,善隣友好外交を踏襲することを明らかにしたが,アフガニスタン問題においてはソ連を直接非難せず,また7月にはカンボディアのヘン・サムリン政権を承認するなどソ連寄りとの批判も受けたが,12月のブレジネフ議長訪印の際はソ連の主張に必ずしも同調しない姿勢をとり非同盟国としての威信の回復に努めた。印米間では米国の濃縮ウラン供給が部分的ながら再開された。印中間では,予定されていた黄華外相訪印が,インドによるヘン・サムリン政権承認問題もあり延期されている。
インド外交の基本たる非同盟運動に関し,インドは81年2月非同盟外相会議を主催し,従来から分裂の危機にあるとも言われた非同盟運動の取りまとめに重要な役割を果たした。
(c) 経済
農業においては順調なモンスーンに恵まれ,穀物生産は史上最高に近い豊作と予想されているが,インフラストラクチャーの不備による工業生産の伸悩み,依然継続するインフレ傾向により,全体的にインドの経済情勢は大きな改善を示さなかった。特に需要の6割以上を輸入に頼る原油の価格高騰,イラン・イラク紛争によるインド人出稼ぎ労働者の本国送金の減少は,インドの外貨事情に深刻な影響を与えるものと見られる。
(ハ) パキスタン
(a) 内政
79年末のソ連のアフガニスタン軍事介入に伴い,国民の対外的危機感が高まった結果,80年の国内政情は比較的安定的に推移した。
ハック大統領は,税制改革,無利子金融制の一部導入など真のイスラム国家建設を目指す措置を次々に発表した。また,81年3月には,当分の間現行憲法に代わるものとして暫定憲法命令を公布・施行した。
(b) 外交
80年を通じパキスタン外交は,ソ連のアフガニスタン軍事介入に対する自国の安全保障確保を主目的として展開された。特に,イスラム諸国との連帯を通じ相互支援体制を確立すべく,1月及び5月にイスラム外相会議を主催し,対ソ非難決議を成立させた。また,国連,非同盟会議などの国際場裏においてもアフガニスタン問題に対し世界の関心を集中させることに努力した。
(c) 経済
79年度においてはGDP実質成長率6.2%を記録し,77年度以来の回復傾向が維持された。農業部門は好天候と積極的農業振興策に支えられ,小麦,米,綿花などの生産が好調だった。工業部門は依然民間投資が停滞しているが徐々に生産は回復しつつある。依然問題は国際収支の窮状であり,貿易収支赤字は史上最大の23億5,000万ドルに上った。このような状況を背景にしてパキスタン政府の要請により,わが国を始めとする主要国による債務救済が行われることとなった。
(ニ) バングラデシュ
(a) 内政
80年は顕著な不安定要因は見られず,議会も順調に開催され,ラーマン大統領が本格的に社会・経済開発に取り組んだ年であった。大統領は国内開発への国民一般の参加を得るため,バングラデシュ・ナショナリズムの高揚に努めるとともに奉任活動による灌漑用運河掘削,文盲撲滅運動などを進めた。7月から第2次5カ年計画が着手されている。
(b) 外交
ラーマン大統領は善隣友好・全方位外交を推進するとともに,中国のほか,英国,日本,米国,フランスを訪問し西側諸国との関係強化に努めた。更にバングラデシュは,アフガニスタン問題イラン・イラク紛争解決のため活発な活動ぶりを見せた。またラーマン大統領は,イスラム諸国会議のイェルサレム委員会及びイラン・イラク紛争のイスラム親善使節団のメンバーに選ばれた。
(c) 経済
79年度のバングラデシュ経済は農業部門が前年度からの卓越の影響を受けたため,GDP及び一人当たりGNPの成長率は各々4.3%及び1.9%にとどまった。輸出は17%増加したものの輸入増(51%)がこれを大きく上回ったため外貨事情は悪化した。
(ホ) スリ・ランカ
(a) 内政
7月賃金引上げを要求する公務員のゼネストが発生したが,政府は非常事態宣言の発令などによりこれを無事収拾した。10月のバンダラナイケ元首相の公民権剥奪を巡る野党の反対運動も拡大することなく終息し,80年を通じインフレ高騰に対する国民の不満が見られたものの,基本的には内政は安定的に推移した。
(b) 外交
非同盟路線を堅持しつつ,すべての国との友好関係増進に努めた。特に中東産油国との関係強化に腐心し,サウディ・アラビア,クウェイト,リビア,アラブ首長国連邦,オマーンに大使館を設置した。
(c) 経済
天候不順による農業部門不振の影響を受けて,80年の実質成長率は5.6%にとどまる見込みである(79年は6.2%)。
引続き開発重視の方針を踏襲しているが,インフレの高騰(23%)の開発計画に与える影響が懸念される。
(ヘ) ネパール
(a) 内政
80年5月,ネパール国政史上初めて,その独特の政治制度である「政党なきパンチャーヤット制度」を一部改正の上維持するか,多数政党制を復活するかの国民投票が行われ,その結果パンチャーヤット支持派が55%の多数を占め勝利を収めた。しかし,反対票も予想外に多かったため,ビレンドラ国王は12月,国会議員の直接選挙制など民主化推進のための憲法改正を発表した。
(b) 外交
国王は2月から3月にかけ約2週間スリ・ランカ,シンガポール,ビルマ,バングラデシュ,インド,また11月には英国,パキスタン,ベルギー,サイプラス,ユーゴースラヴィアを訪問し,ネパール外交の機軸である非同盟政策の延長とも言うべき「平和地帯宣言」に対する支持の確認,ないしは新たな支持獲得に努めた。同平和地帯宣言に対してはわが国も12月原則的支持を与えた。
(c) 経済
80年の農業生産は順調な天候に恵まれ,前年比3.7%の増加が見込まれており,輸出もかなりの伸びを記録したものと見られている。
(ト) モルディヴ
ガユーム政権は,引続き前政権時代の独裁的色彩を払拭し,回教を基盤とする民主主義の復活に努めるとともに,教育・医療・運輸を中心とする地域開発「地方アトル(環礁)開発」を推進した。
2月ナーシル前大統領が首謀とされるガユーム大統領暗殺計画の事前発覚に伴い,反ガユーム派は一掃された。
(チ) ブータン
国内政情はワンチュク国王の親政体制の下で一応安定的に推移しており,ブータン国籍の取得を拒否するチベット人難民の退去問題についても,インドが約1,500人を受け入れることに合意し,解決に向かいつつある。
(リ) アフガン難民問題
78年4月のアフガニスタン革命に端を発するアフガン難民のパキスタンヘの流入は,79年末のソ連の軍事介入後急速に増加した。その結果,79年末には約40万人であった難民数は,81年3月現在約170万人に達し,パキスタンに対する大きな負担になるとともに,南西アジア地域における不安定要因となっている。
かかる事態に直面し,パキスタン政府の要請を受けたUNHCRは,80年中2回にわたり約1億ドルの拠出を求めるアピールを発出し,積極的にアフガニスタン難民の救済に当たっている。
(2) わが国と南西アジア諸国との関係
(イ) 各国との関係
80年には,わが国から園田特使に続き伊東外務大臣がインド,パキスタン両国,また,愛知外務政務次官がバングラデシュ,ネパール,スリ・ランカ及びモルディヴを各々公式訪問した。81年1月には,衆議院議員団(塩谷夫議員団長)がバングラデシュを公式訪問した。
81年2月には,皇太子同妃両殿下がスリ・ランカを公式訪問された。80年10月には,モルディヴのジャミール外相がわが国を公式訪問した。81年3月には,バングラデシュのハフィズ国会議長行がわが国を公式訪問した。
80年7月に行われた故大平総理大臣の葬儀に際しては,域内各国は,いずれも閣僚級の特使を派遣したが,特にバングラデシュからは,ラーマン大統領自身が参列した。
(ロ) アフガン難民問題
わが国はアフガン難民問題を人道及び南西アジア地域の平和と安定に係る問題として重視しており,80年3月園田特使をパキスタンに派遣したほか,同8月には伊東外務大臣がパキスタン訪問の際難民キャンプを視察した。救済援助については,80年初頭79年度予算の中からUNHCRに対し10億円を拠出したほか,同年3月パキスタン政府に対し3億8,000万円の援助を実施した。また,80年度予算においては世界食糧計画(WFP)に対する2億9,000万円の拠出(80年9月)及びパキスタン政府に対し3億円の援助(81年1月)を実施した。
<要人往来>
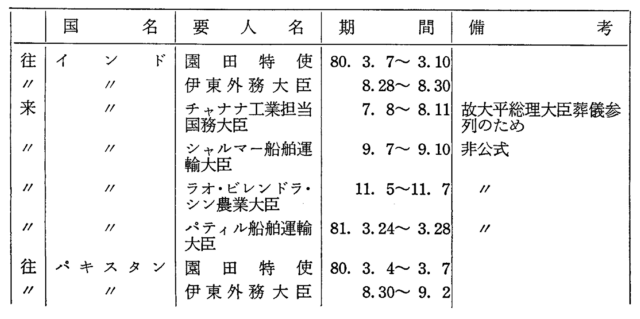
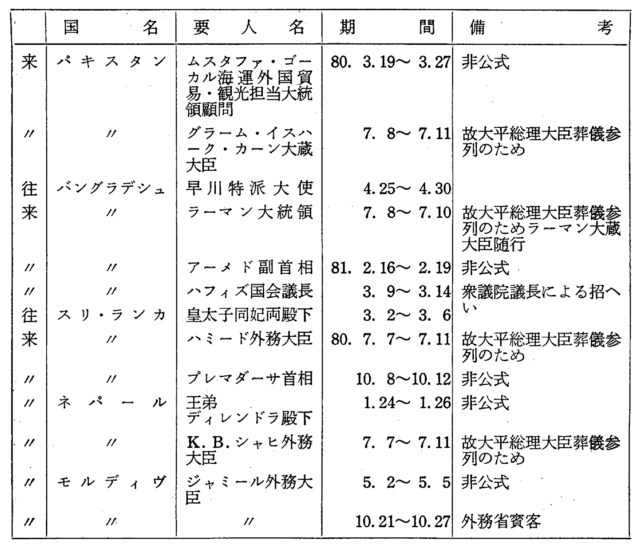
<貿易関係>
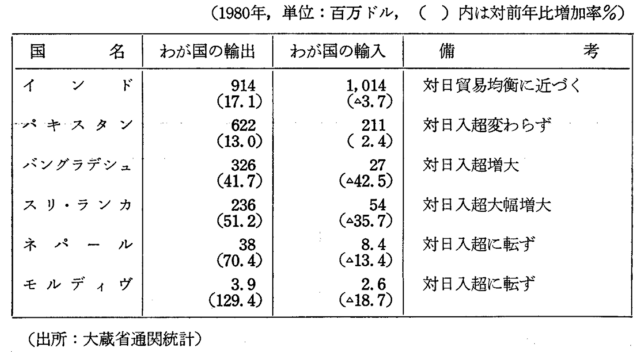
<民間投資>
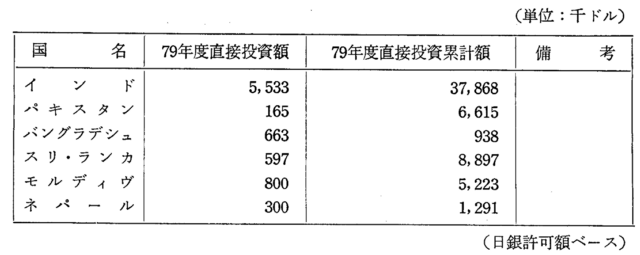
<経済協力(政府開発援助)>
