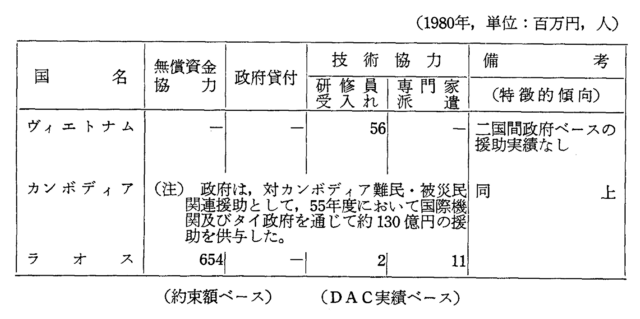5. インドシナ地域
(1) インドシナ諸国の内外情勢
(イ) ヴィエトナム
(a) 内政
80年のヴィエトナムの国内情勢は,79年以来のカンボディアヘの武力介入及び中国との緊張関係の継続により《平和でもなく,戦争でもない》不安定な状況に終始した。
79年からの経済社会情勢の悪化の中で,経済の立直し及び国内体制の引締めのため80年初頭より経済管理組織の強化,党組織の浄化と強化などが実施に移された。
すなわち,2月,内閣の大幅改造に引続き81年1月及び2月にも鉱山・石炭,食糧など経済関係の閣僚が更迭された結果,ほとんどの経済関係閣僚は新しい顔ぶれとなった。一方,従来から懸案であった党組織の浄化・強化及び党員の質の向上のため2月以降,党史上初めて党員証が交付され,交付の過程において党員の資格審査が行われた。その結果,80年1年間で54万余人に党員証が交付されたと伝えられる。
12月には国会(第6期第7回会合)が開催され,同国会において新憲法が採択され,81年4月には国会代表選出のための総選挙が実施された。
新憲法は,79年8月に発表されていた草案と基本的に同じものであり,統一後の「全国的規模で社会主義化に進む,過渡期の憲法」と規定されているほか,共産党が唯一の指導勢力として初めて明文化され,対外的にはソ連,ラオス,カンボディアなどとの戦闘的団結,あらゆる面における協力がうたわれている。また機構面では,従来の国会常任委員会と大統領の権限を併せ持つ国家評議会が創設されている。
なお,第9回共産党中央委員会総会(12月)において,81年末に第5回党大会を開催するとの決議が採択された。
(b) 外交
中国との関係は国境地帯における小競り合いがしばしば発生した旨伝えられているものの,軍事面での大きな衝突はなかった。
第2次中国・ヴィエトナム次官級会談は3月6日中国側が打切りを通告し,第3次会談を80年下半期にハノイで開催することをヴィエトナム側に提案した。
その後ヴィエトナム側が数次にわたり同会談開催を中国側に提案したが,中国側は「ヴィエトナムが中国敵視政策を進め,カンボディアの軍事占拠を継続している状況下では会談を開催する意義がない」などとしてこれを拒否し,80年中には再開されなかった。
ソ連との関係は,2月,レ・ズアン書記長が党創立50周年記念演説において「ソ連及びその他の社会主義国と全面的に団結・協力し,ソ連及びコメコンを主とする対外経済関係の拡大に努力する」ことが基本的政策であると述べ,また新憲法第14条においても同様の趣旨が規定されており,貿易,経済協力など多くの分野での関係が強化されている。
7月にはレ・ズアン党書記長,ファム・ヴァン・ドン首相が訪ソし,ソ連・ヴィエトナム首脳会談が開催された。その際ヴィエトナム南部大陸棚における地質調査及び石油・ガス採掘の協力に関する協定が調印された。
他方,ASEAN諸国とは,カンボディア問題を巡って対立し,関係が停滞している。
米国との関係改善については,79年に引続き何ら進展が見られなかった。
(c) 経済情勢
80年12月,グエン・ラム副首相兼国家計画委員会委員長は国会報告で,第2次5カ年計画(76年~80年)を総括し,75年との比較で農業生産及び工業生産(金額ベース)は,それぞれ18.7%,17.3%増加したなど過去5年間の成果を挙げた。しかし第9回中央委員会総会決議で明らかにされたとおり,同5カ年計画の主要目標の多くは達成されなかった。
また,80年度国家計画の目標の多くも低い達成率に終わったが,これは長期にわたる戦争,自然災害や投資計画,経済管理面での欠陥などのためと指摘されている。
農業面において,80年の食糧生産は目標の1,500万トンを100万トン下回り,特に都市住民に対する食糧供給に多くの困難をもたらしたと言われ,また鉱工業面において80年は電力,石炭,鉄鋼などの生産増加がなくエネルギー,原材料不足のため多くの工業生産が対前年比約5割に落ちたとされている。
かかる経済的困難を打開するため,81年1月新経済政策が打ち出された。すなわち,国営各企業において「出来高払制度」農業部門において「生産請負制度」を導入し,労働意欲を高め,労働生産性及び品質の向上,資材資源の節約とともに農工業生産増に取り組んでいる。第3次5カ年計画(81年~85年)については,81年単年の経済計画として一部主要部門の目標が設定されたものの,全体の目標及び位置付けは明らかにされず,81年の実績を踏まえて81年末に開催される第5回党大会で計画の方針,基本的課題,主要目標などに関する討議,決定が行われることになった。
(ロ) カンボディア
(a) 内政
民主カンボディア政府が79年12月に国家機構を改めキュー・サンパン首相が首相兼民族大連合愛国民主戦線臨時議長に就任して以来,シハヌーク殿下及びソンサン=カンボディア人民民族解放戦線(解放クメール)議長などのいわゆる第三勢力に対して幅広い反ヴィエトナム統一戦線の結成を呼びかけてきたが,シハヌーク殿下は政治の舞台から引退を声明し,ソンサン議長も民主カンボディアとの協力を拒否するなど統一戦線造りは一向に進展しなかった。
しかしながら,81年2月になり,ソンサン議長とキュー・サンパン首相との間で統一戦線結成について具体的な話合いが行われていたことが明らかにされる一方,シハヌーク殿下も,条件付きで民主カンボディアとの統一戦線結成を提案し,3月10~11日平壌においてキュー・サンパン首相と会談したが完全な合意には至らなかったとされている。
なお,カンボディア国内では西部タイとの国境山岳地帯及び東北部の山岳地帯を中心にヴィエトナム・ヘン・サムリン軍に対する抵抗戦が続いているが,軍事的には双方ともに相手に決定的打撃を与えることなく総じて大きな動きはなかった。
他方,いわゆる「カンボディア人民共和国」政権は同政権下の経済・社会復興に腐心しているが,事実上,軍事,行政,経済などほとんどすべての分野にわたってヴィエトナムに依存している。同政権は,このような状況下において,「総選挙」の準備を進めるとともに(81年5月1日実施),81年3月11日新憲法草案を発表した。
(b) 外交
民主カンボディア政府は,国際場裏における支持の確保に努力を傾注し,80年10月の国連総会では,わが国やASEAN諸国などの働きかけもあり引続き議席を確保した。しかし,79年12月の英国による同政権の承認撤回に続き,81年2月豪州も承認撤回を行った。
10月の国連総会において,ASEAN及びわが国を含む諸国は国際会議開催の指針などを含む共同決議案を提出し,これは,79年の決議と同様圧倒的多数(97-23-22)で採択された。
なお,81年2月ニューデリーで開催された非同盟外相会議では,カンボディアからはいずれの政権も出席しなかった。
他方,「カンボディア人民共和国」政権については,インドが7月に承認したが,同政権を承認する国の数は30カ国(同政権側の発表による)にとどまっている。同政権及びヴィエトナムは,カンボディア情勢は不可逆であるとの基本的立場を堅持するとともに,上述の国連決議を拒否する旨明らかにしており,80年1月(プノンペン)に続き7月(ヴィエンチャン)にインドシナ外相会議を開催し(タイ・カンボディア国境地帯に非武装地帯の設置,タイ・カンボディア両国間の交渉など4項目を提案),更に,81年1月のホーチミン市での第3回外相会議では,(i)沖国からの脅威がなくなれば越軍の撤退を検討(ii)タイのポル・ポット支援がなくなれば直ちに部分撤兵(司国連決議は内政干渉であり断固拒否(iv)中国との平和共存条約締結用意(v)ASEAN・インドシナ間の地域会議を開催し,両集団間で平和安定条約締結後,その承認保証のため広範な国際会議を開催するなどの提案を行った。しかし,国連決議に基づく解決を求めるASEAN諸国はこの提案を拒否した。
(c) 経済情勢
ユニセフなど国際機関は西側各国の拠出により,79年10月~80年12月の期間にタイ・カンボディア国境地帯のカンボディア難民及びカンボディア国内の被災民に対して総額約5億ドルの緊急人道援助を行ってきた。
ソ連,ヴィエトナムなどの社会主義国からは「カンボディア人民共和国」政権に対して直接援助が行われた。こうした国際援助の成果及び80年/81年の米の生産量が前年に比しかなり改善されたこともあり,食糧事情に改善が見られ,タイ国境地帯への住民の集結は次第に減少した。
他方,カンボディア国内では貨幣経済が復活され,その結果,市場が再開され,工場も一部が稼動しているが,全体としてはインフラストラクチャーが未整備であり,自立できていない。なお,ごく一部の国との間を除き,正常な貿易は行われるに至っていない。
(ハ) ラオス
(a) 内政
80年のラオスは人民民主共和国成立5周年を迎え,81年1月カイソーン党書記長兼首相は,過去5カ年の回顧と81年の方針に関する報告書において,これまでの国防,治安の確保,生産増大などの革命の成果をたたえ,81年からの5カ年計画に対する決意を表明した。同首相は同時に78年からの3カ年計画が成功裏に終わり,特に80年の米の収穫は過去最高の100万トンを超えた旨強調した。
しかし,一方では,現体制になじめない者などのラオス脱出が継続しており,また国内外における反政府グループの動きも伝えられている。
カイソーン政権の国内政策の中心は今後とも社会主義建設のための国防,治安の確保,国内生産の増大,党・政府・軍・人民間の連帯,人民の生活条件の改善にあると見られ,このため差し当たっては第1次5カ年計画の実施が大きな課題になるものと見られている。
(b) 外交
80年のラオス外交の基本はソ連を始めとする社会主義諸国との連帯強化にあり,特にヴィエトナムとの「特別な関係」が強調されるとともに,カンボディア(ヘン・サムリン政権)との関係の緊密化が図られた。
ソ連との関係は党,政府の戦略的指針であり,8月にはカイソーン首相が訪ソし,12月にはカッチェフ副首相がラオスを訪問するなど両国の友好関係は各分野,各レベルにおいて促進された。同様な関係強化が他の東欧諸国とも図られ,殊にチェッコスロヴァキアとは2月に友好協力条約が締結された。
他方,ASEAN,特にタイとはメコン河での発砲事件が再発した結果,6月及び81年2月の2度にわたり両国国境が閉鎖されるに至り両国関係は緊張した。
また,中国との関係も中越関係の悪化とともに冷却化し,中国に対し「帝国主義と結託する北京反動主義」との非難姿勢をとり続けている。
(c) 経済情勢
カイソーン政権の基本的経済政策は社会主義経済の建設にあるが,79年末に打ち出された通貨改革を含む新経済政策は,資本主義的経済原理が活用され,80年当初は経済活動が活発化したものの,その後は経済全体としてはラオス・タイ国境閉鎖などの外的要因も加わり,依然としてインフレーション,外貨不足,物資不足,恒常的財政赤字に直面している。党,政府は81年から実施中の5カ年計画に全力を挙げている。
(2) わが国とインドシナ諸国との関係
最近のインドシナの情勢を反映してわが国とインドシナ諸国との人的交流は不活発であった。
カンボディアについては,わが国は民主カンボディアとの外交関係を維持しており,7月7日~10日故大平総理大臣葬儀の際にイエン・サリ外務担当副首相が参列し,大来外務大臣と会談を行った。
<貿易関係>

<経済協力(政府開発援助)>