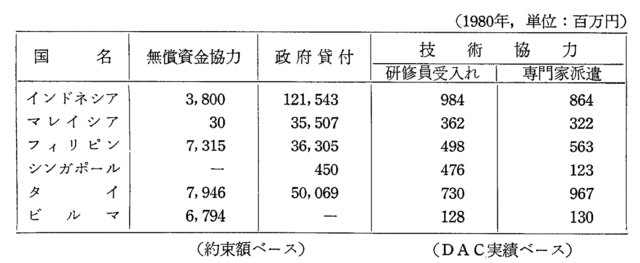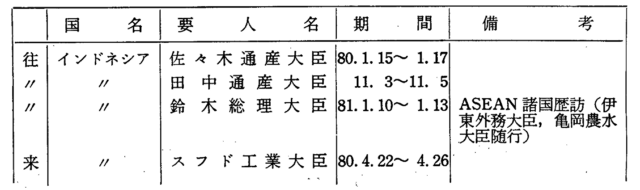
3. ASEAN5カ国及びビルマ
(1) ASEAN5カ国及びビルマの内外情勢
(イ) インドネシア
(a) 内政
1982年の総選挙及び83年の大統領選挙を控え,80年インドネシアは早くもいわゆる「政治の季節」に入った。
5月には現体制に不満を抱く退役将軍を中心とする約50人が連名で声明を発出し,政府を批判した。また,ほぼ時期を同じくして学生組織も学園内で集会を開き政府批判を行ったが,これらの動きに政府は厳しい姿勢で臨み,治安の維持に努めた。
他方,4月,ウジュンパンダンにおいて,また11月中部ジャワにおいて反華僑暴動が発生したが,比較的短期間に事態は平静に復した。
(b) 外交
80年のインドネシア外交については,カンボディア問題に関連して一貫してASEANの政治的結束を図ったこと,中国との国交正常化には依然として慎重な態度を維持したこと,ECと経済分野を中心に関係の強化を図り,対外関係の多角化が促進されたことなどが特筆されよう。3月末クァンタンにおいて,スハルト大統領はフセイン・オン首相と会談し,マスコミを中心としてインドネシアとマレイシアはヴィエトナムに対して妥協的な姿勢をとる旨合意したのではないかとの観測もなされたが,4月タイのプレム首相を迎えたスハルト大統領は,カンボディア問題に関するタイとの共通の立場を再確認した。また,6月には,グエン・コータック=ヴィエトナム外相がインドネシアを訪問したが,インドネシアはASEANの団結を明確にし,その一体性を強調した。更に,6月,ヴィエトナム軍のタイ領侵攻に伴い,クアラ・ルンプールにおいて開催されたASEAN外相会議では,関係諸国とともに対越強硬姿勢を打ち出し,第35回国連総会においても,カンボディア問題についてASEANの結束に努めた。
中国との関係については,80年1月には,スハルト大統領が,非インドネシア籍華僑に対する国籍付与及び国籍の明確化に関する大統領令,2月には国籍取得に関する大統領決定を発出するなど,中国との国交正常化の準備に着手したやに見受けられたが,その後華僑の国籍問題の解決は進まず,また,前述の反華僑暴動もあり,実現を見るに至らなかった。
また,アフガニスタン問題については,インドネシアは回教国,アラブ諸国との連帯の立場から対ソ批判の立場を明確にしている。
EC諸国との関係については精油所などの大プロジェクトを欧米企業が受注する事例が目立ち,また特に要人往来が頻繁になった。
(c) 経済情勢
(i) 80年のインドネシア経済は,石油及びLNG輸出の好調もあり,外貨準備の蓄積が顕著であり(80年末約80億ドル),懸念された物価上昇も一応小康状態に抑えられた。
(ii) 輸出は,石油の高値に支えられて好調であり,80年度は約224億ドル(そのうち原油・LNG約167億ドル),輸入は約156億ドルの見込みであり,80年度の国際収支は約27億ドルの黒字と予測されている。
(iii) 5月に石油製品50%の値上げを始め,電力,電話,電信,バス,鉄道などの公共料金が軒並み値上げされ,更に,対前年度比52%増の大型予算の物価に及ぼす影響も懸念されたが,財政・金融上とられた引締政策などにより,80年の物価上昇は15.9%と前年の22%を下回ったとされている。
(iv) 80年の石油生産は日産158万バーレルで,79年の日産159万バーレルを下回った。石油生産の停滞と国内需要の急速な伸びは輸出余力を減少させており,新規油田の開発及び代替エネルギーの開発に努めている。
(v) 農業面では,80年の米生産は未曽有の約2,000万トンの大豊作が見込まれている(対前年比約10%増)。(80年度の米輸入は,前年度の約半分に当たる128万トンに落ち着く見込み。)
(vi) 外国援助については,80年5月の対インドネシア政府間協議グループ(Inter Govemmental Groupon Indonesia;IGGI)会議において,インドネシア政府は80年度分の外貨所要総額を約21億ドルとし,うちIGGI・二国間援助として10億ドルを受け入れる希望を表明した。わが国は右要請に対し580億円の資金協力の意図表明を行った。
(vii) 対インドネシア民間投資は,80年には合計69件,9億9,300万ドルであり,その結果67~80年7月の累計では,795件,86億600万ドルとなっている(そのうち,わが国は206件,32億3,900万ドルで第1位である)。
(ロ) マレイシア
(a) 内政
フセイン首相は,78年の総選挙において連立与党国民戦線が圧倒的勝利を収めたことにより,その基盤を堅固なものとしたが,80年においても好調な国内経済発展を背景として,引続き安定した政権を維持した。同年9月には,78年総選挙以来初の実質的な内閣改造が行われ,初代首相アブドル・ラーマン時代の閣僚が完全に姿を消し,閣僚の若返りが図られた。また,同内閣改造は81年に開始される予定の第4次マレイシア計画(81年~85年)の実施に向け実行力ある内閣を造る目的もあったと思われる。
しかしながら,マレイシア政治の最も深刻な問題と言える人種間の軋轢は依然存在しており,貧困の撲滅とマレイ人の地位向上を目的とした新経済政策(71年~90年)の今後の取進め方を巡り,この問題がいかなる展開を示すかが注目される。更に中国系住民には,新経済政策の進行により,その経済的優位を失うばかりではなく,マレイシアの経済発展から取り残されていくのではないかとの危惧も存在していると見られる。また,ここ数年来社会的風潮として回教復古の現象が見られ,更にアロースター米騒動及びジョホール州警察署襲撃事件など,一部の回教過激派の動きも顕在化した。
また,フセイン首相は,81年に入り心臓病手術を受けており,同人の健康状態が注目される。
(b) 外交
マレイシア外交は,ASEAN諸国間協力の強化,イスラム諸国との協力,非同盟中立,米・中・ソ3大国との等距離外交,日,ECなど自由主義諸国との協力推進をその主要な柱としている。
この基本方針を背景として80年のマレイシア外交は,前年に引続き活発に展開された。
ASEAN諸国との協力については,6月のASEAN外相会議などに積極的な役割を果たしたほか,スハルト=インドネシア大統領(3月),プレム=タイ首相(4月)のマレイシア訪問,5月のフセイン首相のシンガポール訪問に見られるとおり,活発な首脳外交を展開した。
また,イスラム諸国会議のメンバー国として,リタウディン外相が1月のイスラム臨時外相会議に出席,5月の同外相会議にはモフタル外務副大臣が出席した。更に9月にはクウェイト国王がマレイシアを来訪した。
対ソ関係については,アフガニスタン問題につきマレイシアが非難の立場を明確にした(9月)ことが注目された。対中関係については80年3月には黄華外相,81年の1月には高揚農相のマレイシア訪問があった。両国間関係は実務的に進展しているが,マラヤ共産党に対する中国の支援問題が両国関係の障害となっていると見られる。米,EC,豪などの自由主義諸国との関係については,貿易,投資,技術移転,経済技術援助などの経済面で,政府・民間レベルの双方において着実に増進されている。
(c) 経済情勢
79年好調に推移したマレイシアの輸出は,80年に入り,先進工業国の景気後退による一次産品需要落込みの影響を受け増勢が鈍化した(対前年比13.4%増)。しかしながら,前年大幅な増加を見た輸出所得によりもたらされた旺盛な民間消費(対前年比実質12.5%増)及び民間設備投資の拡大(対前年比実質18.1%増)に加え,第3次マレイシア計画(76年~80年)の最終年度に当たり,実質17.2%増加を見た公共部門支出が景気上昇に弾みをつけた。この結果,80年の実質経済成長率は8.0%と見込まれ,第3次マレイシア計画期間中の実質経済成長率も目標を上回る8.5%となったと見込まれている。なお,マレイシアの物価上昇率は,過去5年間年率5%以下の低水準にとどまっていたが,80年は石油価格上昇に伴う諸物価の高騰により7.1%となった。
(ハ) フィリピン
(a) 内政
72年9月に布告された戒厳令の下で治安回復,経済開発,汚職追放などの施策を強化してきたマルコス大統領は,78年4月の暫定立法議会議員(地域代表)選挙,同年6月の暫定立法議会召集,80年1月の地方選挙実施と,近年「正常状態復帰政策」を着実に進めてきており,81年1月には,8年4ヵ月ぶりに戒厳令全面解除を宣言した。
マルコス大統領は,戒厳令解除後,与党KBL(与党連合)内に憲法改正起草委員会を発足せしめ,同委員会は政治制度をフランス型の強大な大統領制へ改組する憲法改正草案を作成した。同草案は3月6日,国会にて可決された。この憲法改正草案は,4月7日の国民投票において承認され,その後改正憲法に基づく大統領選挙(国民による直接選挙)が6月に行われた結果,マルコス大統領が80%以上の票を得て3選を果たした。
なお大統領選挙において野党連合はボイコット戦術をとったが,投票率は88%に達し,結局右戦術は初期の成果を上げ得ずに終わった。しかしながらマルコス大統領の最大の政敵で,現在米国ハーバード大学に留学中のアキノ元上院議員など野党有力指導者の動向は,今後とも引続き注目される。
(b) 外交
フィリピンは,75年春のインドシナ情勢の急変後は伝統的な対米特殊関係を再調整する一方,(イ)対日関係の強化,(ロ)対ヨーロッパ先進国との貿易関係強化,(ハ)対共産圏関係の緊密化,(ニ)ASEAN諸国との関係強化,(ホ)第三世界との連帯強化など多角的な外交を展開している。80年においては,対外関係は,全体として特に大きな動きはなかったが,伝統的な米国との関係の改善及びASEAN諸国との関係強化が目立った。
対米関係は,79年1月の軍事基地協定の改定以後,著しい改善を示したが,その後80年に入っても良好に推移した。4月のマルコス大統領の訪米(ホノルルでの全米新聞発行者協会総会に主賓として出席し,米国との連帯を強調)は,こうした対米関係の好転を示す一つの好例である。
一方対ASEAN関係については,フィリピンが国連安保理事国となったこと,及び80年7月からはASEAN常任委員会の議長国となったこともあって,インドシナ問題などを中心に活発にASEAN各国間の意見調整に努め,リー=シンガポール首相の訪比(80年2月),プレム=タイ首相の訪比(同年5月)といった首脳訪問を通じASEAN関係諸国との連帯強化に努めた。
(c) 経済情勢
80年のフィリピン経済は厳しい国際経済環境を反映して,経済成長率は,経済開発5カ年計画の目標(年率7.5%)を大幅に下回った。また輸出は砂糖,銅鉱石などの伸長に支えられ対前年比23%増を示した反面,輸入も原油その他の石油製品の輸入増により対前年比15%増となったため,全体として貿易収支が17億4,900万ドルの赤字を記録し,経常収支は14億7,300万ドルの赤字となったが,資本の大幅な流入が見られたため,結局総合収支は3億8,000万ドルの黒字(対前年比5億7,000万ドル黒字)となった。一方消費者物価は,年平均で17.6%と前年の16.5%を上回ったが,年央以降落着きを見せている。
なお,近年増加傾向にある対外債務残高は80年12月末現在で122億7,000万ドルに達した。
(ニ) シンガポール
(a) 内政
シンガポールにおいては,80年12月,独立後4回目の総選挙(国会は一院制,選挙は小選挙区制,議席数75)が行われたが,与党人民行動党候補が全選挙区で当選し,人民行動党による議会全議席の独占が更に続くこととなった。この総選挙に際し憲法が改正され,議席数がこれまでの69から75に増加された。今次総選挙を機に人民行動党においては,老齢,健康上などの理由により11名の現役議員が引退,このため空席分(1名)及び議席増分(6名)を合わせ18名の新人候補を立てたが,いずれも当選を果たした。
選挙後,81年1月5日に内閣の一部が改造された。リー首相,ゴー・ケン・スイ第一副首相,ラジャラトナム第二副首相など主要閣僚のポストに変更はなかったが,ゴー・チョク・トン,ダナバラン,オン・テン・チョンらの若手閣僚がそれぞれ2省の兼任大臣となっているのが目立った。
80年のシンガポール内政においては,他に特に目立った動静はなく,政情は極めて安定的に推移した。
なお,北京官話でも授業を行っていたことで特異な存在であった南洋大学がシンガポール大学に吸収合併され,80年7月に国立シンガポール大学として新しく発足することになった。
(b) 外交
シンガポールは,ASEAN諸国との協調を機軸に,国連や英連邦諸国会議などの国際的な会議の場をも十分に利用し,かつ最近は西アジア諸国との関係強化,更には日本及び他の西側先進国との関係の緊密化を図っており極めて現実的な外交政策を推進している。
シンガポール外交は首脳外交を積極的に展開しているところにも特色があり,リー首相は,80年には,西独(1月),フィリピン(2月),タイ(1月及び8月),インドネシア(7月),オーストリア(8月),インド(9月),ブルネイ(10月),中国(11月)を訪問,各訪問先で各国首脳と会談した。他方,外国からは,クライスキー=オーストリア首相(1月),ビレンドラ=ネパール国王(2月),プレム=タイ首相,サリム国連総会議長,ユンベ=タンザニア副大統領(いずれも4月),フセイン=マレイシア首相(5月)らがシンガポールを訪問した。
(c) 経済情勢
80年のシンガポール経済は,原油価格の相次ぐ上昇,2年目に入った大幅賃上げ(平均19%)などの悪条件にもかかわらず順調に推移し,実質で10.2%の成長率を達成した。実質成長率が2ケタとなったのは73年の石油危機以降初めてである。産業別では,金融・サービス部門,電子機器・造船を中心とする製造部門及び観光部門などが好調であり,これが高い成長率を達成する主要因となった。また,産業構造高度化政策推進の一環でもある大幅な賃上げと,原油を中心とする海外原材料価格の上昇に起因する卸売物価の上昇などにより,消費者物価は8.5%と大幅な上昇を示した(79年は対前年比4%増)。
対外貿易は,輸出(対前年比34.0%増),輸入(同33.9%増)とも大幅な伸び率を示したが,貿易収支は92億5,200万シンガポール・ドル(約43億2,000万米ドル)の大幅な赤字となった。しかしながら,貿易外収支は依然好調で,総合収支は,14億3,600万シンガポール・ドル(約6億7,000万米ドル)の黒字であり,外貨準備高も12月末で137億6,000万シンガポール・ドル(約64億3,000万米ドル)に達した。
また,アジア・ダラー・マーケットも順調に発展しており,80年末現在の総資産は540億米ドルに達している。
なお,労働市場はほぼ完全雇用の状態で,80年末の失業率は3.0%である。
(ホ) タイ
(a) 内政
クリアンサック内閣が,当面する石油不足,物価高騰などの経済問題に有効な解決策を見出し得ないことに対し,議会における野党の批判攻勢が強まった。クリアンサック首相はかかる批判に対処するため80年2月,内閣改造を実施したが,改造前に行った石油価格引上げを巡って国民一般に政府批判が高まり,軍部のクリアンサック政権に対する支持も動揺するに至ったため,同首相は2月末臨時国会を召集して自ら退陣を表明した。この後を受けて3月プレム国防相兼陸軍司令官が国内各派の支持を得て首相に就任し,主要政党連立による新内閣を成立せしめた。プレム政権は,ブンチュー副首相以下社会行動党系のテクノクラートを中心とした経済閣僚による経済問題取組みに期待をかけたが,その成果が表れないうちに,やがて閣内の政党間で確執,対立を生じ,81年2月には,サミット石油会社の石油買付権限問題を契機として閣内対立は一挙に表面化した。その結果81年3月プレム首相は下院第1党の社会行動党を除外した形で大幅な内閣改造を行った。
その直後,4月1日には,サン陸軍副司令官のほか一部若手将校によるクーデター事件が発生したが,国王,軍幹部の多数の支持を得たプレム首相はクーデター鎮圧に成功した。
(b) 外交
カンボディア問題について,タイは,カンボディアに直接隣り合ういわゆる「前線国家」としてASEAN諸国とともにすべての外国軍隊のカンボディアからの即時撤退及びカンボディアの民族自決を求めた79年の国連総会決議の実施を一貫して主張してきている。プレム首相は首相就任直後の80年4~5月にASEAN諸国訪問を行ってかかるタイの立場を改めて示し,これに対し他のASEAN諸国は,タイの立場を尊重し支持する旨再確認した。その際インドネシア,マレイシアは,石油の対タイ輸出量増加を約束した。
80年6月カンボディア駐留のヴィエトナム軍は,タイ・カンボディア国境を越えてタイ領を攻撃したが,これによりタイ・ヴィエトナム間の緊張は高まつ々10月にはニュー・ヨークにおいて両国外相会談が開かれたが,両者の立場の相違は克服されなかった。10月,タイは他のASEAN諸国とともに,国連総会で,79年の国連決議の再確認とカンボディア問題についての国際会議開催を求める決議を提案し採択に成功し,その後は同国際会議の開催実現に向けて努力している。
西側諸国との関係については,日本との関係発展が著しかったほか,米国は,6月のヴィエトナム軍のタイ領越境攻撃に際して武器の緊急空輸を行うなど,タイ支持の姿勢を見せた。
対ラオス関係は,79年のクリアンサック首相のラオス訪問及びラオスのカイソン首相の訪タイにより正常化の方向に向かったが,80年6月メコン河のタイ哨戒艇がラオス側に銃撃される事件が発生し,また81年1月には,ラオスの輸送船が銃撃される事件が発生し,タイ・ラオス関係は停滞した。
対中国関係では,80年10月のプレム首相訪中,81年1~2月の趙首相の訪タイを始め要人の交流により両国関係は緊密化が進んだ。
対ソ関係については80年11月アルン外務副大臣の訪ソ,81年1月ソ連のイマシエフ最高幹部会副議長の訪タイなどがあり,タイは,ソ連に対してカンボディア問題についてのタイの立場説明を行っている。
(c) 経済情勢
80年の経済情勢は国内総生産が6.3%の成長を見たものの物価高騰,金融逼迫,貿易収支悪化などの諸問題は解決されず,国内政局にも少なからず影響を与えている。
農業生産は,対前年比3.5%の伸びとなった。鉱業は8%の伸びを見せたが,製造業は,繊維品の輸出の伸び悩みにより前年が10.1%の伸びであったのに対し80年は6.1%の成長にとどまった。
物価は,依然高騰を続け,80年は消費者物価19.9%,卸売物価20.1%の上昇を見た。
対外貿易は,輸出は一次産品の価格上昇に支えられ総じて好調であったが,輸入が石油値上りなどのため著しく増大し,80年の貿易収支は約29億ドルの史上最高の赤字となった。
(ヘ) ビルマ
(a) 内政
80年のビルマにおける主な動きとしては,内政は安定の度合いを深めたと言えるが,(i)長年にわたり懸案となっていた政府指導下の仏教僧団統一化が実現したこと,(ii)この統一化を機として,恩赦が実施され,ウ・ヌ元首相を含む反乱軍約2,000名が帰順したこと,(iii)反体制派旧政治家に国家功労章が授与されたことにより,現政府とこれら旧政治家の関係も好転したこと,などが挙げられる。
中国,ラオス,タイとの国境方面においては,ビルマ共産党,少数民族諸派の各反乱軍が依然として活動を続け,国内の団結及び経済開発に対する一つの阻害要因となっている。この中で,ビルマ共産党反乱軍の活動状況は,近年鎮静化している。
(b) 外交
80年のビルマの首脳外交は,前年同様活発であった。すなわち,ネ・ウィン大統領は,中国(10月),インド及びバングラデシュ(11月)を訪問して,善隣友好関係の促進に努力した。
中国との交流については,上記ネ・ウィン大統領の訪中に続き,81年1月には,趙紫陽中国首相が,就任後最初の外遊においてビルマを訪問した。一方ASEAN諸国との交流も,プレム=タイ首相(80年7月),及びラジャラトナム=シンガポール第二副首相(80年8月)のビルマ訪問,レー・マウン=ビルマ外相のタイ訪問(80年9月及び81年1月)などがあり,活発化している。
(c) 経済情勢
ビルマ経済は,引続き拡大傾向にあり,79年度のGDPは,対前年度比5.4%という伸びを示した。その要因として,良好な天候と高収量品種のモミの普及によって米作を中心とする農業生産が順調であったこと,及び経済改革と外国援助導入の増加により国営企業の生産性が向上したことなどが指摘されている。80年度のモミの生産は,史上最高の1,306万トン(前年度1,049万トン)に達すると見られている。
(2) わが国とASEAN5力国及びビルマとの関係
(イ) インドネシア
(a) 80年における日本・インドネシア関係は前年に引続き順調に推移した。
7月には,「日本・インドネシア合同経済委員会」第2回会議が,また,10月には,両国間の官民各層の対話の場である日本・インドネシア・コロキアムがそれぞれ日本において開催された。その間9月には,81年7月まで各地巡回を予定されるボロブドール展が京都において開催された。
80年中も両国要人の往来が頻繁に行われたが,訪日要人の層も広がり,10月にはダルヤトモ国会議長,11月にはハビビ研究・技術担当国務相が来日した。
またインドネシアは,7月の故大平総理大臣の葬儀に副首相格のスロノ調整相をスハルト大統領名代として出席せしめた。
(b) 81年1月,鈴木総理大臣はASEAN諸国歴訪の一環としてインドネシアを公式訪問し,スハルト大統領と国際情勢,ASEAN地域協力及び二国間問題について話合いを行い,両国首脳の間に個人的な信頼関係が確立された。
また,今次総理インドネシア訪問の機会に,両国間の懸案であったエネルギー合同委員会の開催が具体化することとなり,また伊東外務大臣とモフタル外相との間で,「科学技術協力に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定」が署名された。
(ロ) マレイシア
日本・マレイシア関係は,引続き極めて良好に推移してきており,80年においても両国要人の相互訪問,経済,経済・技術協力,文化などの分野での協力を通じて一層緊密の度合いが深められた。
要人交流については,5月にはマレイシアからラザレー蔵相,ポール・レオン第一次産業相が相次いで訪日,また7月にはリタウディン外相が故大平総理大臣葬儀出席のため訪日した。日本からは,9月に田中通産大臣がマレイシアを訪問した。
また,81年に入り,1月鈴木総理大臣がASEAN諸国訪問の一環としてマレイシアを訪れ,首脳会談などを通じフセイン首相との間に個人的信頼関係が確立されるとともに,今後の両国関係の一層の緊密化,多角化の基礎が築かれたことは極めて有意義であったと言えよう。
両国の貿易関係については,80年においてもわが国は引続きマレイシアにとって最大の貿易相手国であったと見込まれ,貿易収支はわが国の14億1,000万ドルの入超となっている。
(ハ) フィリピン
80年においては,2月にヴィラタ蔵相,7月にイメルダ大統領夫人が訪日し,また,わが国よりは4月に竹下大蔵大臣,7月に田中通産大臣が訪比するなど,要人の交流により両国関係の一層の緊密化が図られた。
また,従来,日比間に存在していた貿易不均衡問題については,80年に入り大幅な改善が見られた。すなわち日比間の貿易は,76年以降わが国の一方的出超が続いてきたが,79年に至りその出超額が大きく減少し(3,900万ドルの黒字),更に80年に入ってからはわが国の入超(2億6,800万ドルの赤字)に転じた。
(ニ) シンガポール
シンガポールとわが国の関係は,近年,緊密化の一途をたどっており,特に80年に入ってからは,リー首相の主唱により「日本の経験に学ぼう」という大キャンペーンが行われるなど両国間の関係は緊密化の度合いを高めた。
現在,わが国はシンガポールに対し訓練センター及びソフト・ウエアー技術訓練センターなどの設立,シンガポール大学工学部拡充,同大学日本研究講座設立,教育制度拡充,生産性向上のための技術水準の向上などについて協力を進めている。
両国間の貿易は,引続きわが国の大幅輸出超過(約27億2,000万ドル)となっている。なおわが国は,シンガポールにとって最大の貿易相手国である。
(ホ) タイ
日・タイ関係は,80年7月の故大平総理大臣葬儀への出席のためのプレム首相の来日,8月の伊東外務大臣の訪タイ,81年1月の鈴木総理大臣の訪タイ,3月のシリキット王妃の訪日を始めとする要人の往来が従来より一段と活発化し,また,わが国のタイ重視政策とも相まって経済協力を始めとする各般の協力が一層強化された。
また,両国間の懸案である貿易不均衡は79年には改善されつつあったが,80年にはタイの対日輸出入額の比率は1:1.7(前年は1:1.5)と若干悪化傾向を示した。
(ヘ) ビルマ
80年においては,伊東外務大臣,田中通産大臣がビルマを訪問し,他方ビルマからは,イエ・ガウン農相,レー・マウン外相が訪日するなど,日本・ビルマ関係は引続き着実に進展した。経済協力の分野においては,有償資金協力として石油開発,セメント工場拡張などのための円借款315億円を供与する公文が交換されたほか,無償援助として橋梁建設,食糧増産などのため75億円の供与が決定された。
<要人往来>
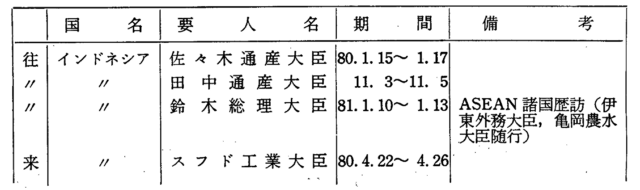
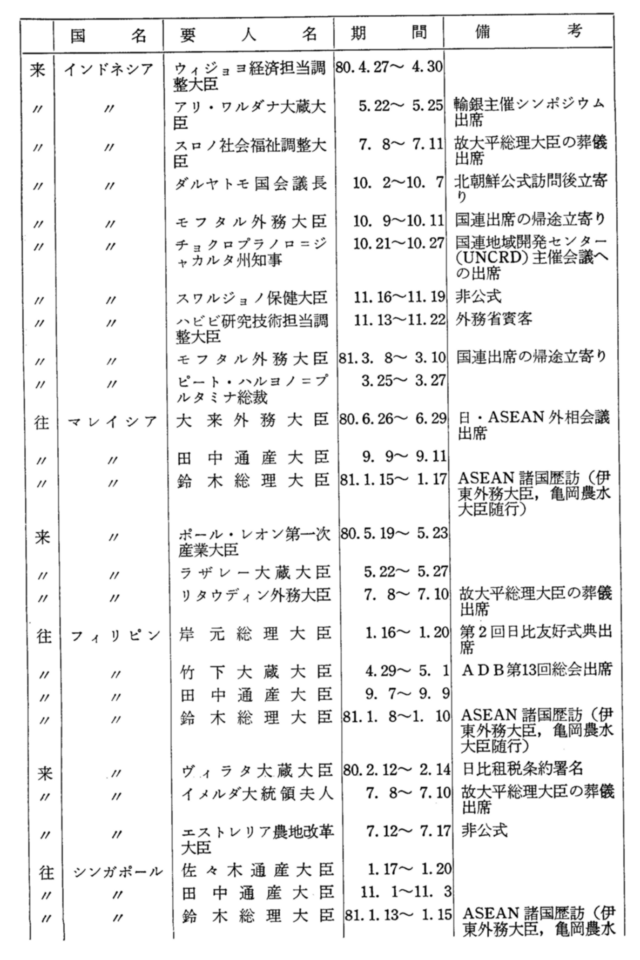
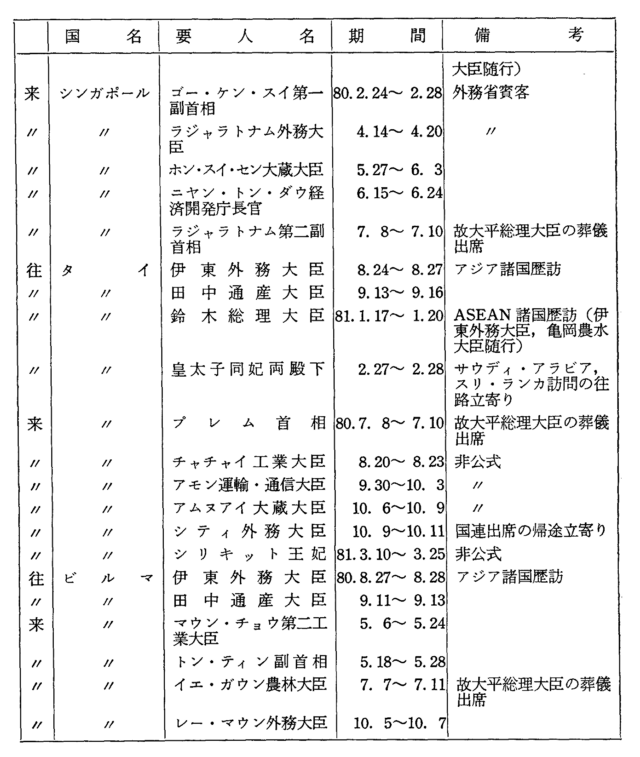
<貿易関係>
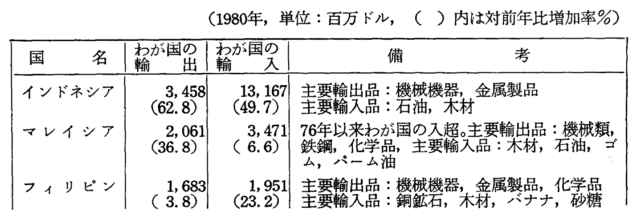
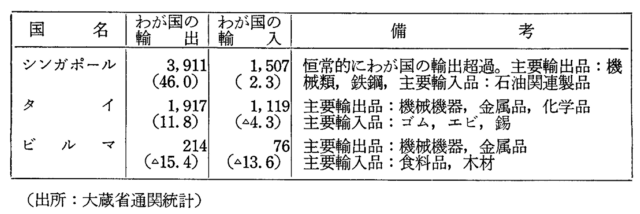
<民間投資>
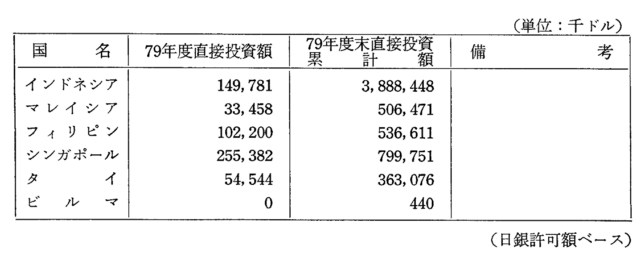
<経済協力(政府開発援助)>