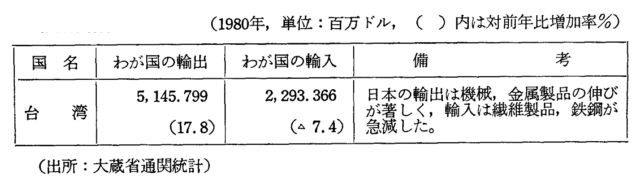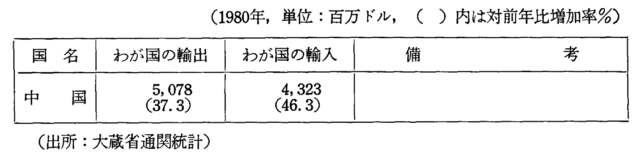
2. 中国
(1) 中国の内外情勢
(イ) 内政
(a) 79年6月の第5期全人代第2回会議以降,三中全会(78年12月)のラインに沿い刑法など各種法律の制定が進められ,経済政策も調整を機軸とする方策に切り替えられた。また階級闘争は主要矛盾でなくなったとして脱文革,脱イデオロギー傾向が打ち出され,更に,文革など57年以来の政治運動において党中央に誤りがあったことが明らかにされた。
(b) 党第11期中央委第5回全体会議(五中全会)の開催
80年2月の五中全会では文革が全面的に否定されるとともに,78年12月の三中全会における彭徳懐(元政治局員,国防部長,58年失脚)の名誉回復を皮切りに進められてきた過去の政治運動における失脚者の名誉回復の総仕上げとして,劉少奇元国家主席(69年死亡)の名誉回復が行われた。
また,同会議では「4人組」と近い存在とされていた注東興,紀登奎,呉徳,陳錫聯の4名の解任,党中央政治局常務委員の2名補選(胡ヨウ邦,趙紫陽)及び日常党務を行う党中央書記処の再設が決定された。
(c) 第5期全人代第3回会議
80年8月開催の第5期全人代第3回会議においては,80年初頭以来進められてきた幹部の終身制廃止,党務・行政職の兼職回避などによる集団指導体制の確立を目指すキャンペーンにも沿うものとして華国鋒主席がそれまで兼職していた総理を辞任し,代わって趙紫陽副総理が総理に昇格し,また,トウ小平,陳雲,李先念ら5名の長老が副総理より引退した。
また,華国鋒は同会議での演説の中で,華国鋒体制発足以来打ち出してきた計画・政策が「盲目的に高い目標を追求しバランスを欠いた」との反省の上に立ち左傾思想の一掃を呼びかけた。
同会議によって,トウ小平,陳雲らの実力者を後見人として,日常党務は胡ヨウ邦党中央総書記を中心とする党中央書記局,行政は趙紫陽新内閣によって運営されるという新たな指導体制がスタートするとともに,経済調整の強化を基調とした政策が推し進められることとなった。
なお,同会議では壁新聞の自由などを含むいわゆる「四大自由」を規定した憲法第45条を削除し,78年11月以降の民主化,人権を求める動きに歯止めがかけられたほか,婚姻法,国籍法などの4法案が可決成立された。
(d)「林彪・江青反革命集団」(4人組)裁判
「文化大革命」の総括,法制の確立などの目的をもって,11月20日よりいわゆる4人組裁判(林彪は71年死亡)が行われ,江青,張春橋は2年間の執行延期付き死刑判決,王洪文は無期懲役,林彪グループに属する陳伯達ら6名にはそれぞれ16年~20年の懲役刑の判決が申し渡された。
(e) 台湾に対する呼びかけ
中国は,米中正常化以後,台湾当局との話合い,郵便などの通信関係,航空・運輸関係などの実現を呼びかけたのを始め,統一問題についても現在の台湾の経済・社会体制を認める等の立場を表明しており,全体として柔軟な対台湾政策を打ち出している。
(ロ) 外交
(a) 全般
華国鋒総理は,79年6月の第5期全人代第2回会議における「政府活動報告」において,「覇権主義」と並んで「世界平和の維持」を対外活動の主要目標として初めて前面に掲げ,中国の対外路線としてソ連に対する対決姿勢と同時に,近代化達成のため日米欧との関係を重視していくことを公に明らかにした。
(b) 対米関係
米国との間では米中共同コミュニケ(72年2月)を基礎に,79年1月1日をもって外交関係を樹立した。
外交関係樹立以後,米中間には,経済,技術,文化を始め各分野における交流が急速に発展してきている。
(c) 対欧関係
中国は,EC,NATOの強化を評価するとともに英,仏,西独を始めとする西欧各国との関係及びEC委員会との関係強化を図っている。既に中国は,西欧の多くの国と科学技術協力協定,文化協定などを締結しており,79年にはポルトガル,アイルランドと国交を樹立した。また,79年10~11月には華国鋒総理が,仏,独,英,伊4カ国を訪問し,西欧諸国との友好関係の強化が図られた。現在,西欧で承認あるいは国交関係のないのはヴァチカン,モナコ,リヒテンシュタインだけである。
東欧との関係では,ルーマニア,ユーゴースラヴィアとの間の友好関係の強化が引続き進められた。
(d) 対ソ関係
国際政治の面において,中国は引続きソ連の覇権主義を激しく非難してきている。ソ連軍のアフガニスタン侵攻については,ソ連の覇権主義の露骨な現れであり,世界平和に対する重大な脅威であるとして,これに対し実質的な抑止措置をとるよう世界に呼びかけている。
しかし,他方二国間関係の面では,中国はソ連との国家関係を改善したいとの方針を明らかにしており,4月に「中ソ友好同盟相互援助条約」が終了し,中ソは無条約状態に入ったが,国境河川合同委員会会議,貿易会議は継続されており,また新しい駐ソ大使を派遣するなど,中国としてはソ連との国家関係は,従来以上に関係が悪化することを避けるとの姿勢を維持していることが看取された。
(e) 対アジア関係
(i) カンボディア問題について,中国は外国軍隊がカンボディア領土から全面的に撤退することが,問題解決のカギであるとしており,かかる形での解決が図られるよう民主カンボディアを始めとする抗越勢力を支持していくとの方針をとっている。
(ii) 中国はASEANを積極的に支持し,特に,その中立化構想を評価している。現在外交関係がないインドネシア,シンガポールともそれぞれ関係の回復・樹立の実現を期待している。
(iii) 北朝鮮との関係では,78年の華国鋒主席の訪朝以来,引続き関係の緊密化が図られている。中国は,「朝鮮人民の祖国自主統一を目指す闘争を支持する」との態度を堅持している。
(f) 対中近東・アフリカ関係
中近東との関係ではイラン,アフガニスタンにおける政変に関し,ソ連の進出に警戒心を高めるべきであるとの態度を強く打ち出している。アフリカに対しては,陳慕華副総理(3月),黄華外交部長(4月),姫鵬飛副総理(8~9月)がアフリカ諸国を訪問,これに対して,ザイール,ギニア,ケニアの各大統領が訪中し,招待,訪問外交を積極的に行ってきている。
(ハ) 経済情勢
(a) 79年から進められてきた経済調整政策は,80年に入り更に強力に推進されることとなった。調整の重点は財政収支の均衡,銀行の預金・貸付バランス,通貨発行抑制による物価安定などに置かれている。
このために基本建設投資の削減(81年度予算は当初計画の550億元から300億元に縮小),各種財政支出の減少を始め,銀行貸付の中央による統一管理強化など各種の緊縮措置が打ち出されている。
(b) 80年の国民所得は3,630億元で1970年不変価格で対前年比6.9%伸びたとされている。
(c) 80年の農業生産は計画では総額で対前年比3.8%増を予定していたが,実際は2.7%増にとどまった。これは農業生産の約半分を占める食糧生産が3億1,822万トン(対前年比4.2%減)にとどまったためである。
(d) 工業生産は,80年には,総額で対前年比8.7%増と計画(同6%増)を大幅に上回った。とりわけ軽工業の伸長は著しく(同18.4%増),これまでの重工業偏重政策によるアンバランスが相当程度改善されたと言われる。
産業別生産状況について見ると,原油1億595万トン(対前年比0.2%減),石炭6億2,000万トン(同2.4%減),電力3,006億KWH(同6.6%増),粗鋼3,712万トン(同7.7%増),化学肥料1,232万トン(同15.7%増)などとなっており,エネルギー生産は全体として低調であった(同1.3%減)のに対し,鉄鋼,化学肥料などは比較的順調であった。
(e) 大衆の生活水準向上に注意が払われ,賃上げなどにより国営企業の労働者の一人当たり年間平均賃金は,80年に98元増加し803元となった。また農産物買上価格の引上げにより農民の収入も増加した。これに伴い社会全体としての購買力も300億元増加した。
(f) 対外貿易は79年に続き大きな伸長を示した。80年の貿易総額は563億元(対前年比23.6%増),うち輸出は272億元(同28.7%増),輸入291億元(同19.2%増)と発表されている。輸出の伸びは主として重工業品(同39%増)及び機械,電気設備(同37.1%増)の伸長によるものである。貿易収支は19億元の赤字となったが,貿易外収入のうち観光収入は対前年比32%増の9億2,000万元となった旨報じられている。
(2) わが国と中国との関係
(イ) 華国鋒総理の来日
79年12月の大平総理大臣の訪中に続き,80年5月には華国鋒総理が来日し,大平総理大臣との間で2度にわたり首脳会談を行った。両首脳は国際情勢に関し意見を交換するとともに,日中二国間関係では貿易,経済協力,文化交流などの問題を話合ったほか,新たに閣僚会議を設置することに合意を見た。
(ロ) 伊東外務大臣の訪中
伊東外務大臣は,80年9月アジア諸国歴訪の帰途中国を訪問し,華国鋒総理,トウ小平副総理ら中国首脳と会談し,カンボディア問題を含む国際情勢及び日中閣僚会議の開催など二国間問題につき意見交換を行った。
(ハ) 第1回日中閣僚会議の開催
80年12月3日から5日にかけ北京にて第1回日中閣僚会議が開催され,日本側からは伊東外務大臣を始め6閣僚が,中国側からは8名の副総理(又は部長)が出席した。席上,国際情勢なかんずくカンボディア問題などアジア地域の情勢につき意見交換が行われるとともに,経済調整政策につき中国側より説明が行われたほか,日中二国間事項についても率直な討議が行われた。
(ニ) 日中経済貿易関係
(a) 80年の日中貿易は往復94億171万ドル(対前年比41.3%増)であり,全般的に大幅な伸長を見せた。
(b) 日中長期貿易取決めに基づく対中プラント輸出に関連し,80年末ころから中国側は一部既契約プラントの建設中止を決定したが,その後中国側はプラント機器の引取りを表明し,関連プロジェクト建設費用につきわが国政府に借款の供与を要請してきた。
(c) 政府ベースの円借款については,80年12月の日中閣僚会議において,80年度分限度額560億円の交換公文が取り交わされた。また,81年1月には,無償資金協力による北京市近代病院建設計画のための交換公文が取り交わされた。
(d)輸銀の石油・石炭開発金融(4,200億円)について,80年5月及び9月に石油1,石炭7の各プロジェクトに対し,合計1,438億5,000万円の借款契約が調印された。
(e) 資源開発協力としては,石油,石炭,電力,非鉄金属など多方面で行われている。このうち石油については,渤海南西部において,80年7月から物理探査が行われ,12月より試掘が始まっている。その他の分野においても調査団の相互派遣など,活発な交流が行われている。
(f) 政府ベースの技術協力は,79年から始められた鉄道を始め,経営管理,保健医療など各種の分野で幅広く進められている。
<貿易関係>
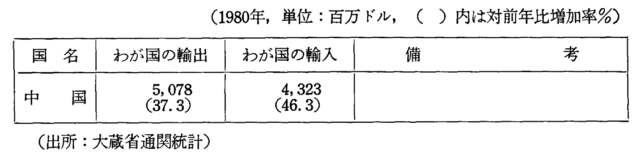
(ホ) 人的交流と文化交流
<要人往来>
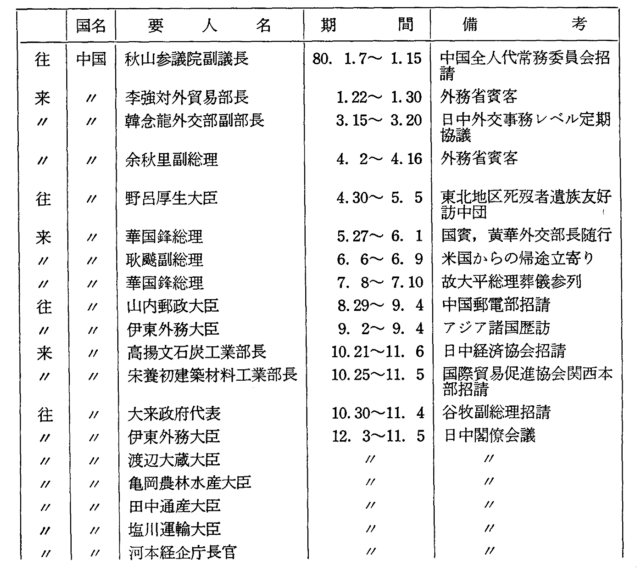
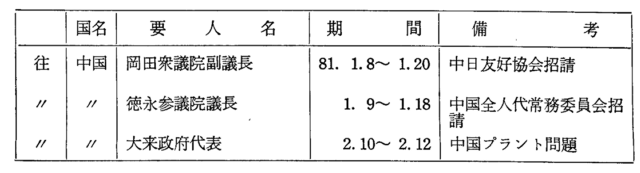
文化交流についても順調な進展が見られている。79年12月に署名された日中文化交流協定に基づいて80年9月,文化交流に関する両国政府当局者間の第1回協議が開催され文化交流に関する具体的計画などが話し合われた。
また大平総理大臣訪中の際提唱された対中国日本語教育特別計画に基づく中国人日本語教師に対する第1年度目の研修事業が,80年8月北京語言学院で開始され,その受講生ら130名が81年3月,1ヵ月にわたり訪日,日本における研修会に参加した。
なお,中国政府派遣留学生(訪問学者を含む)は,80年末で約530名に達した。
(3) 台湾
(イ) 内政
台湾の国民党政権は選挙法の制定など選挙制度の改革を進めた上で80年12月,5年ぶりに中央民意代表(国民大会代表,立法委員,監察委員)の増員選挙を実施した。
本選挙において,当選者の約8割を国民党系立候補者が占めたことは予想どおりの結果であったが,選挙が混乱もなく終了したことは,米中国交正常化後,一時動揺した台湾の政情が一応安定を取り戻した現れと見られる。
(ロ) 外交
台湾は80年も引続き外交関係を有する諸国(22カ国)に対し活発な訪問外交を行い,経済,技術などの分野での関係を強化するとともに,外交関係を有しない国に対しては,貿易・文化事務所の相互設置などにより,実務関係の拡大に努めている。
なお,中国政府による統一及び交流の呼びかけに対し,台湾はこれに応じない旨繰り返し述べている。
(ハ) 経済
80年の台湾経済は,輸出の伸び悩み,内需の低迷などにより国民総生産6.7%増と,台湾としてはここ数年来最低の伸びとなった。一方,消費者物価は対前年比19%増と大幅に上昇し,台湾製品の輸出競争力の低下が懸念されており,台湾当局にとり,輸出市場の多角化とともに産業構造の高度化が重要な課題となっている。
(ニ) わが国との関係
日台間の民間レベルの交流は,80年も引続いて大きな伸びを示し,80年の来日台湾人は通年約24万名に達した。また,日台貿易における台湾側の入超は前年を大幅に上回る28億5,000万ドルとなり,台湾側は日本側に対しその是正を求めている。日台間のチャネルとしては,日本側の交流協会及び台湾側の亜東関係協会がある。
<貿易関係>