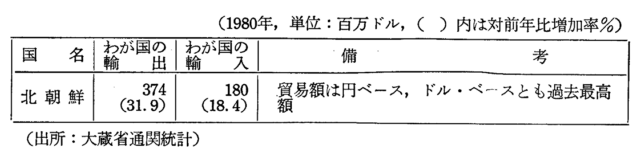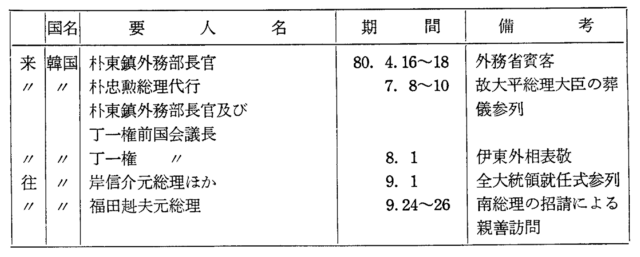
第2部
各説
第1章 各国の情勢及びわが国と
これら諸国との関係
第1節 アジア地域
1. 朝鮮半島
(1)朝鮮半島の情勢
(イ)韓国の政情
(a) 内政
80年及び81年初期は,韓国にとって朴大統領死亡後の一連の政治改革を推進し第5共和国を発足させた重要な時期であった。80年及び81年3月までの主要な韓国内政動向は次のとおりである。
(i) 光州事件と全斗煥大統領の就任
朴正熙大統領の死亡をうけて大統領に就任した崔圭夏氏は朴体制後の政治改革に着手したが,早急な改革を主張する野党や反体制側との間に意見の対立が見られ,労働争議や学生デモが各地で頻発した。5月14,15日には学生デモは全国的な広がりを見せ,非常戒厳令(朴大統領死亡後済州道を除き布かれていたもの)の解除及び全斗煥国軍保安司令官らの退陣などを要求する大規模集会等がソウルなどで行われた。政府はこれに対して,5月17日に,翌日から非常戒厳令を全土に拡大し,すべての政治活動を禁止する旨発表するとともに,金鍾泌氏・金大中氏らの政治家を連行した。
他方,非常戒厳令が全国に拡大された5月18日,全羅南道の光州市で学生及び一部市民が暴動を起こし,いわゆる光州事件が27日まで続いた。申鉉ファク内閣は,その責任をとって20日総辞職し,朴忠勲内閣が発足した。5月31日には主要閣僚と軍幹部28名から成る国家保衛非常対策委員会(委員長崔大統領)が設置され,この常任委員長に全斗煥国軍保安司令官が任命された。全斗煥氏は,更に8月16日崔大統領が辞任したのをうけて,制服を脱いだあとで第11代大統領に選出され(8月27日),国政全般の責任を担うこととなった。
(ii) 憲法改正
憲法改正は朴大統領死亡後の大きな政治課題であった。憲法改正案は10月22日国民投票にかけられ,投票率95.5%,うち賛成91.6%の多数で承認された。新憲法は全文131条と付則10条から成り,(イ)大統領の任期を7年として再選を禁止していること,(ロ)大統領による推薦議員制を廃止していること,(ハ)大統領選挙人団を5,000名以上とし選挙人の政党加入を認めていること,(ニ)大統領の緊急措置権の行使を交戦状態やそれに準ずる非常事態の発生時に限定していることなどの点で旧憲法と異なっている。新憲法は,また前文において第5共和国を発足させるものであるとうたつている。
新憲法の公布に伴い政党や国会は解散したが,11月22日,戒厳布告令により政治活動の一部緩和措置がとられ,新憲法下での大統領選挙,国会議員選挙に向けての政党結成活動が展開された。
政府は,他方「政治風土刷新のための特別措置法」を公布し(11月5日),大規模な旧政治家の追放を断行した。このため旧与野党の政治家を始め主要閣僚経験者など567名が88年6月末まで政治活動が禁止されることになった。このほか公務員5,600余名,公社職員3,000余名が解職された。
(iii) 金大中氏裁判
5月17日逮捕された金大中氏は,7月31日国家保安法違反内乱予備陰謀などの容疑で起訴され,第1審と第2審で死刑の判決を受けた。81年1月23日大法院においても死刑の判決が言い渡されたが,同日大統領特赦により無期懲役に減刑された。
(iv) 大統領選挙と国会議員選挙
新憲法に基づき81年2月11日大統領を選ぶための選挙人(5,278名)の選挙が行われた。引続き2月25日選挙人による大統領選挙が行われ現職の全斗煥民主正義党総裁が90.2%の多数を獲得し,柳致松民主韓国党総裁,金鍾哲韓国国民党総裁,金義澤民権党総裁を抑えて第12代大統領に当選し,大統領の就任式が3月3日行われた。次いで,3月25日,国会議員選挙が実施された。与党の民主正義党は276議席のうち地方区(92地方区から成り各地方区で2名選出)90名,全国区(92議席を地方区の獲得議席に応じて配分)61名の合せて151名を獲得し,単独多数議席を占めた。このほかの政党別議席数は,民主韓国党81名,韓国国民党25名,無所属11名,その他政党8名であった。
(b) 外交
(i) 基本方針
韓国の外交政策に関する基本方針は,全大統領が81年1月12日行った国政演説において次のとおり明らかにされている。
(あ)自主外交の推進
(い)成熟し密度あるパートナーシップとしての米韓関係の発展
(う)相互尊重と相互理解に立脚した日韓関係の強化
(え)欧州諸国及び中東諸国などとの協力強化による対外関係の多元化
(お)理念と体制を異にする諸国との相互関係の改善
(か)南北朝鮮最高責任者による相互訪問の実現
(ii) 対米関係
米国と韓国との間には相互防衛条約が結ばれており,米国との関係は韓国にとってとりわけ重要である。米国の対韓軍事コミットメントは,5月の光州事件の際にも改めて明らかにされたとおり80年を通じて堅持されたが,他方米国は韓国の政治発展が順調に遂げられることに対して大きな関心を繰り返し示したほか,金大中氏裁判の成り行きに関連しても種々憂慮の念を示した。
ところが,米国にレーガン政権が誕生し全斗煥大統領のワシントン公式訪問(81年2月1~3日)が実現したこと及び金大中氏に対する減刑措置がとられたことを契機に,米韓関係における一種のもやもやした雰囲気は一掃される形となった。特に米韓共同声明で明らかにされたとおり,米国が在韓米軍を撤退しないことを確約したことは,この問題がカーター政権下での争点であっただけに韓国を大きく満足させることとなった。
(iii) 非同盟諸国などとの関係
韓国外交は80年を通じて積極的に展開された。特に近年韓国の対非同盟諸国外交は積極化しているが,80年も11月から12月にかけて5人の閣僚クラスを各地に派遣し(盧外務部長官はアフリカ諸国を訪問),81年2月ニューデリーで開催された非同盟諸国外相会議に対する支持工作を活発化した。
韓国はまた,資源確保の観点から80年も前年に引続き対産油国外交を展開したが,特に注目されたのは5月の崔圭夏大統領のサウディ・アラビア及びクウェイト訪問であった。
なお,韓国は80年を通じてナイジェリア,キリバス,アラブ首長国連邦,バヌアツ,リビア,更に81年2月にレバノンと新たに外交関係を設定した結果,81年4月現在で韓国と外交関係を有する国は116カ国である。(なお80年にセイシェルが韓国と断交した。)
(c) 経済
韓国経済は60年代から輸出主導型の工業発展を遂げ,年平均実質成長率10%台の高度成長を持続してきたが,79年には7.1%の成長にとどまり,80年にはマイナス5.7%の成長を記録するに至った。この成長落込みの原因としては,80年5月の光州事件に象徴される社会・政治不安により国内投資などが低迷したこと,原油の相次く価格上昇などによりインフレが悪化したこと,異常冷害により主要穀物の米が凶作であったことなどが挙げられる。
80年における韓国経済は高インフレ(80年12月の卸売物価は対前年同月比で44.2%増),高失業(同5.2%増)及び経常収支の悪化(同マイナス55億3,000万ドル)という三重苦に直面したと言えよう。景気の後退に伴い,韓国政府は79年にとられた経済安定化政策を,80年初めから次第に景気浮揚策に転換しており,その効果は81年に次第に現れてくるものと予想されている。
80年1月,韓国政府は貿易収支の改善を主たる目的として,ウォンを切り下げ(IMF方式で16.6%),2月には従来のドル・ペッグ制を変更し,通貨バスケット方式に加えて他の要素を考慮に入れるという弾力的な為替レート設定方式を導入し,この方式の下で2月~12月の間にウォンを実質15.7%切り下げた。このウォン・レートの推移は,賃金上昇傾向の鈍化とともに韓国の輸出競争力の回復に相当寄与し,輸出は172億4,000万ドル(輸入は219億ドル)に達した。
(ロ) 北朝鮮の情勢
(a) 内政
北朝鮮においては,金日成主席を中心とする指導体制が堅持されている。80年は主体思想を基本指針とし,社会主義制度の強化を図る三大革命(思想,技術,文化)路線を推進する動きが従来に引続き展開された。
10月,朝鮮労働党第6回大会が10年ぶりに平壌で開催された。今回の大会には中国(首席代表李先念副主席),ソ連(首席代表グリンシン政治局員)を含む118カ国,177の各国代表団が招待された。
同大会では,政策面について金日成主席は,三大革命路線の継続推進による先進工業国家の建設,「高麗民主連邦共和国」への移行による南北統一の実現,非同盟・中立路線の強化による国際的地位の向上などの方針を打ち出した。党主要人事面では,金日成主席の子息金正日氏が初めて公の場に登場するなど党中央指導者層の陣容改編が行われた。また,経済専門家として李鐘玉(総理),桂応泰(副総理),姜成山(副総理)などが党中央機関に登用されたことが注目されている。
(b) 外交
(i) 北朝鮮の外交の基調としては,北朝鮮を友好的に遇するすべての国々と完全な平等と自主性,相互尊重と内政不干渉,互恵の原則に基づいて国家的,政治的,経済的及び文化的関係を結ぶとの方針が打ち出されている。
(ii) 北朝鮮は77年に入り非同盟諸国との間の要人の往来に積極的に取り組んできた。80年中には,金日成主席,朴成哲副主席,李鐘玉総理,許ダム副総理兼外交部長などを団長とする政府代表団が欧州,アフリカ,アジア諸国を往訪したほか,アフリカなどからの要人が北朝鮮を訪問した。
(iii) 80年を通じ,ジンバブエ,モーリタニア,レソト,バヌアツ,メキシコ,更に81年初めにレバノン,セントビンセントと外交関係を新たに樹立した。(なお,イラクは80年に北朝鮮と断交した。)この結果81年4月現在で外交関係を有する国は103カ国で,このうち韓国とも外交関係を有しているのは66カ国である。
(iv) 中国及びソ連との関係においては,北朝鮮はバランスの保持に留意する態度を維持している。中国との間では81年1月に李鐘玉総理が中国を訪問した。
他方,ソ連との関係においても同年2月,李鐘玉総理を団長とする朝鮮労働党代表団がソ連共産党第26回大会に出席のため訪ソした。
(c) 経済情勢
(i) 金日成主席は,81年1月の「新年の辞」において,80年の工業総生産高は前年に比し17%伸びた(79年は15%)と述べた。しかし,今回の新年の辞では例年と異なり,基幹産業部門における具体的な伸び率は全く明らかにされておらず,農業部門でも冷害の事実が明らかにされたことが注目を引いた。
今後の計画については,80年10月の朝鮮労働党第6回大会で金日成主席は,第2次経済7カ年計画の繰上げ達成を指示し,80年代に到達すべき経済建設10大展望目標(穀物生産1,500万トン,セメント生産2,000万トン,鋼鉄生産1,500万トンなど)を明らかにした。
(ii) 北朝鮮は,80年末現在,西側諸国を含む諸外国に対し,推定約20~30億ドルに達する債務を抱えていると伝えられる。北朝鮮は79年から80年にかけて西側各国業界との間で幾度か支払繰延べ合意を締結したが,支払いは滞りがちと言われる。
(ハ) 南北朝鮮関係
(a) 南北対話の現況
北朝鮮が80年1月李鐘玉総理及び金一副主席の書簡を韓国要人12名に送り,統一のための直接対話を呼びかけたのを契機として,南北総理会談のための準備会談が2月6日から8月20日まで10回にわたって板門店で行われた。会談では総理会談の開催場所,参加人員などに関して歩み寄りが見られたが,議題の問題で双方の主張は平行線をたどり,結局会談は中断された。
その後北朝鮮側は80年10月の第6回党大会において,金日成主席が「高麗民主連邦共和国」創設案を提唱したが,韓国側は,同提唱が北朝鮮側の従来の主張の範囲を出るものではないとの態度を表明した。
一方,韓国側は81年1月12日,全斗煥大統領が国政演説の中で「南北双方の最高責任者の相互訪問」を提案したが,北朝鮮側は,これに応ずる姿勢を見せていない。
(b) 軍事情勢
80年においても,朝鮮半島の軍事情勢は依然として厳しい緊張状態のまま推移した。すなわち,3月から12月にかけて8件の北朝鮮武装スパイ事件が発生し(78年,79年はいずれも4件),また北朝鮮の継続的な軍事力増強にほぼ並行して,韓国は戦力増強計画(76年~80年)を1年延長するとともに第2次戦力増強計画(82年~86年)を立案,更に国防費の対GNP比率を6%(79年:5.4%)に増大させた。
また3月の「チーム・スピリット80」を始め各種の米韓合同軍事演習が実施された。
他方,81年2月,全斗煥大統領の訪米の際,米国は在韓米地上戦闘部隊の撤退は行わない旨明らかにするとともに,両国大統領は北東アジアにおける侵略を抑止するための米韓協力の強化を誓約した。
(2) わが国と韓国との関係
(イ) 概観
65年の日韓国交正常化以来日韓関係は着実な発展を見てきており,80年から81年初期にかけても両国関係の円滑な進展を図るための努力が双方において払われた。
韓国国内政局との関連において,80年後半から金大中氏裁判が行われた。わが国としては,右裁判は韓国の国内問題であるとの基本的認識に立ちつつも,過去の経緯にかんがみ金大中氏の身柄についての関心を表明するとともに,隣国である韓国との関係を重視する観点から金大中氏の問題がわが国において持つ重要な意味合いにつき韓国側の理解を得るよう努力した。結局81年1月,大法院の死刑判決に対し韓国政府当局の減刑措置が講じられ,わが国は,これが日韓友好協力関係の維持増進に資するものとして評価する態度を明らかにした。
また,81年3月行われた全大統領の大統領就任式には,わが国政府を代表して伊東外務大臣が出席した。
その他の主な動きは次のとおりであった。
(ロ) 日韓大陸棚共同開発
大陸棚の共同開発事業は80年5月から本格的な試掘段階に入り,5月上旬及び7月中旬に第5小区域及び第7小区域において試掘が行われた。しかし,いずれも微量の油・ガス徴はあったものの,商業化可能量の炭化水素の発見には至らなかった。12月9日及び10日の両日,東京において日韓大陸棚共同委員会の第3回定例年次会議が開催され,共同開発の実施に関連する諸事項に関して協議が行われた。
(ハ) 通商関係
日韓両国間の貿易は依然として日本側の出超が続いている。80年においては,わが国の対韓輸出及び輸入は,それぞれ14.1%及び10.8%減少した。今後,貿易の拡大及び均衡を図ることが両国間の課題となっている。なお,80年7月には,127名から成る官民合同の輸入など促進ミッションを韓国に派遣し,大きな成果を上げた。
また日韓間の生糸及び絹製品貿易に関し,秩序ある貿易を確保するために80年6月,9月及び11月に専門家レベルの協議を行い81年1月に合意に達した。
(ニ) 漁業問題
北海道周辺水域における韓国オッター・トロール漁船の操業問題は,過去数年来重要な懸案であったが,両国政府間で鋭意話合いを重ねた結果,80年10月に話合いがまとまり,往復書簡が取り交わされた。この結果,11月から韓国側は北海道周辺水域におけるオッター・トロール漁業につき一定の自主規制を行い,また,わが方は韓国済州道周辺における底引網漁業につき一定の自主規制を行うこととなった。
竹島周辺水域の安全操業を確保する問題については,政府は引続き努力を払っている。
(ホ) 竹島問題
わが国は,韓国による竹島不法占拠に対し,従来から繰り返し抗議してきており,80年12月にも,同年9月に行われた海上保安庁巡視船の調査結果に基づき,竹島における韓国側各種建造物の設置及び官憲の滞在につき抗議し,これらの撤去を求める口上書を発出した。
<要人往来>
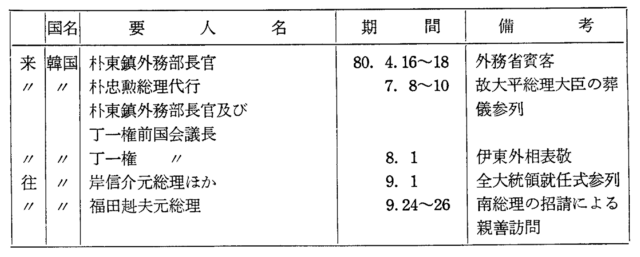
<貿易関係>
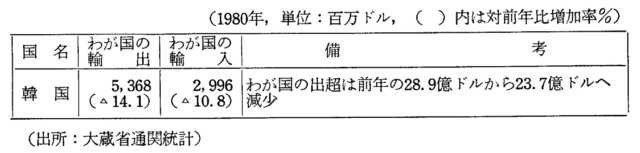
<民間投資>

<経済協力(政府開発援助)>
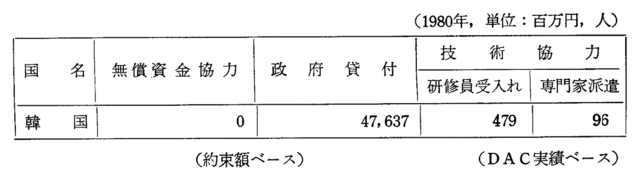
(3) わが国と北朝鮮との関係
わが国と北朝鮮との間には国交はないが,貿易,経済,文化などの分野で交流が行われている。80年における主な動きは次のとおりである。
(イ) 漁業関係
77年9月民間レベルで結ばれた日朝間の漁業に関する暫定合意書の有効期限が80年5月に延長され,82年6月末まで北朝鮮の実施している200海里経済水域内で,わが国の200トン以下の零細漁業者の漁業活動が認められることになった。
(ロ) 人的交流
(a) 80年中の邦人の北朝鮮への渡航は,年間旅券発給数(公用旅券を除く。)によれば,816名(79年は818名)であった。渡航目的の大半が商用となっている。
(b) 一方,同期間中の北朝鮮からの入国者数は261名で,79年の191名に比し27%増加した。
(c) 在日朝鮮人の再入国は,北朝鮮への里帰りを始め,スポーツ,学術,文化,商用,教育,祝典参加を目的とするものなどと見られている。
(ハ) 日朝貿易
80年の日朝貿易は,74年のピーク水準を超え過去最高の額となった。
対北朝鮮輸出は,機械類が中心であり,輸入は金属鉱などが中心である。
<貿易関係>