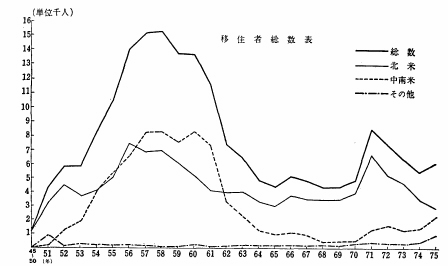
第5節 海外移住の動向
わが国の海外移住は,1960年代後半より質量両面で大きな変化をみせてきている。
まず移住者数についてみると,56年から60年までの間は年間1万3千名から1万5千名であつたが,60年代後半より4~5千名程度に減少し現在までこの状態が続いている。これは主として国民の生活水準の向上,労働需要の拡大という要因によるものと考えられる。最近はわが国経済の低成長に伴い労働需要の減少などの現象も見られ,送出者数増加の要因が生じているが,移住先国の受入基準の厳格化の傾向もあつて移住者数については基本的には現状のまま推移するものと考えられる。
移住形態についてみると,一般的に農業移住者の減少,技術移住者の増加という傾向にあり,また家族単位の移住が減少し単身青年の移住が増加している。
移住先国別にみると,まず米国については75年に約2,500名が移住しており,移住者の大半は日系米国市民や永住者による呼寄せ移住者で,一部は技術者やその家族である。
カナダへの移住者は,70年以降年平均750名前後であつたが,75年には約400名に減少した。これは,カナダの景気停滞とそれに伴う移住者選考の厳格化などの要因によるものと考えられる。また,カナダは75年2月政府が発表した移住青書を基礎にして議会などにおいて移住政策の再検討を行つている。
中南米地域には,農業及び技術移住者を中心として75年には約1,700名が移住した。主要移住先国はブラジルである。なお,わが国はブラジル,アルゼンティン,パラグァイ及びボリヴィアとの間に移住協定を締結している。
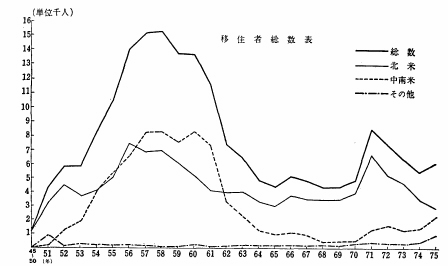
|
(注) |
1. |
本図の区分は暦年である。 |
|
|
2. |
本図は,外務省旅券課作成の旅券発給統計の移住関係旅券発給数に併記者推定数を加えたものである。ただし,1954年,1961年以降70年11月まで,および75年の数字は併記者を含む実績数である(15歳未満の者は親の旅券に併記し,独自の旅券は発給しないのが普通である)。 |
||
|
3. |
1970年12月以降は,新旅券法の施行により,永住のための再渡航者を含む。 |
(1) 国際協力事業団の業務
海外移住事業団の業務は74年8月に設立された国際協力事業団(移住部門)に引き継がれた。同事業団は,中南米地域などへの海外移住を円滑に実施するため,国内においては,海外移住に関する広報,相談,斡旋,移住希望者に対する訓練,講習など,また,海外においては,職業その他生活一般についての相談,指導及び医療,教育,移住地の道路整備等の援護,事業資金の融資,入植地の造成,分譲などを行つている。
これらの事業を行うため,75年度において政府は国際協力事業団(移住部門)に対し,約32億円の交付金及び4億5千万円の出資金を支出した。
このほか,中南米諸国への移住者のうち,渡航費負担能力の乏しい者に政府は渡航費を支給することにしており,75年度における支給者数は404名であつた。
事業団は,75年度においても移住者の定着安定のための現地援護に業務の重点をおいた。移住者の営農等生活基盤は安定に向いつつあるが,さらに一層の安定をはかるためにとつた業務内容の主たるものは次のとおりである。
(イ) 営農指導
移住者の営農上の技術向上をはかるため,前年に引続き巡回指導,農業講習会等に力をそそいだ。
また,雇用農移住者の独立援助のため,ブラジルのリオ・デ・ジャネイロ市近郊及びアルゼンティンのブエノス・アイレス市近郊に小移住地を購入し,独立希望移住者に分譲を開始した。
農業移住者のオリエンテーション,補完訓練及び雇用農移住者の独立前訓練講習を実施するため,ブラジルのジャカレイ移住地に農業移住センターを建設した。
移住者の農業技術指導のため,移住地に農業専門家を派遣しているが,75年度においては,新たにブラジルのトメアス移住地(アマゾン地域)及びアルゼンティンにそれぞれ病理及び花卉に関する専門家を派遣した。
移住者の営農指導等に寄与すべく農業試験場を設置運営しているが,これら試験場の機能強化,設備の充実に努めた。
各移住地の農家経営の改善と振興を図るため農業機械の貸与を行つているが,75年度には営農改善機械としてパラグァイのアマンバイ移住地,ボリヴィアのオキナワ移住地,ブラジルの第2トメアス移住地にトラクター,ブルドーザーなどを配置した。また,ドミニカのハラバコア移住地の共同乾燥場建設及びブラジルのイボチ移住地の井戸の掘削に対し,助成を行つた。
(ロ) 生活環境整備
事業団は,移住者の生活環境整備のため次のような援護を行つた。
(a) 医療衛生対策
前年度に引き続き移住地診療所の運営,医師の派遣,現地医療機関への謝金の供与,現地医療機関への巡回診療の委託,診療所設備の充実などを行つた。
(b) 道路対策
ボリヴィアのサンファン移住地幹線道路を5カ年計画で整備することとし,75年に同計画の実施に着手した。
(c) 生活改善対策
ブラジルのベラ・ビスタ移住地(アマゾン地域)における公民館新設のため助成を行つた。
(d) 電化対策
ブラジルのエフゼニオ・サーレス移住地(アマゾン地域)の電化のため助成を行つた。
(ハ) 融 資
国際協力事業団は,農業移住者及びその団体並びに独立して小工業を営もうとする技術移住者などを対象に,それぞれ農業融資及び工業融資を行つている。また,生活困窮のため自力で独立の生計を営むことの困難な移住者に対しては,速やかにその更生を図ることを目的として更生資金を融資している。
75年度には約11億5,000万円の新規貸付を行い,年度末の貸付残高は約30億3,000万円である。
(ニ) 教育対策
移住者の定着,安定は,移住者子弟の教育にまつところが大きいと考えられるので,現地における教育施策を補完して,現地学校への教具,教材の供与,教師に対する謝金の支出,寄宿舎の建設(新たにブラジルのべレーン市及びサルバドール市),奨学資金の交付,日本語指導教師の派遣(新たにアルゼンティンのブエノス・アイレス市),スクール・バスの配置(新たにブラジルのラーモス及びトレーゼ・デ・セテンブロ移住地),日本語教科書の配布などを行つた。また,移住地の青年の一般教養の向上を図るため,講習会などによる青年教育を実施した。
(2) 移住地現地調査
外務省は,75年度において次の調査を実施した。
(イ) 移住者子弟の日本語教育
移住者子弟の日本語教育援助の進め方を検討するため,現地日本語教育の実態,問題点について調査した。
(ロ) カナダ移住者等実態調査
カナダ移住者の実態調査を実施した。また,併せて農業派米研修生についても実態調査を行つた。
(ハ) 技術移住者実態調査
ブラジル向け技術移住者のオープン・プレイスメント方式による技術移住の実施に伴う諸問題を含め,技術移住者の実態調査を実施した。
(3) 都道府県の移住事業
全国都道府県は,それぞれ独自の立場で,在外県人に対する諸種の援護,海外知識の普及,移住者子弟留学生受入れなどの事業を行つている。
外務省は,都道府県の行う移住事業の健全な発展を図るため,一部の事業に対して補助金を交付している。75年度の補助金総額は約3,790万円であつた。
(4) 日本海外移住家族会連合会の事業
日本海外移住家族会連合会は,海外移住者の親族縁故者によつて結成された各県の家族会が62年に設けたものである。同連合会は海外日系人団体との連絡,移住者の消息調査,移住者の福祉増進,移住者子弟研修事業等を行つている。外務省は,このうち移住者子弟研修事業(研修期間2年,各年10名受入れ)に対して補助金を支給している。また同連合会は,在伯県人会と共同で67年よりブラジルから毎年20人前後の初期移住者の訪日団を受入れているが,外務省はこの事業に対して75年度は20人分につき往復旅費及び3日間の滞在費を支給した。
(5) 農業研修生派米事業
農業研修生派米協会は,66年より日米両国政府の後援を受けて毎年200人以内の農村青年を米国に派遣し,6カ月の学課研修及び1年半の農場実習を行つている。75年には97人が渡米した。なお米側ではビッグ・ベンド・コミュニティー・カレッジ財団が引受団体となつている。
第34回海外移住審議会総会(海外移住政策に関する内閣総理大臣又は関係大臣の諮問機関)は,75年1月16日開催された。本総会は,国際協力事業団の設立後(74年8月)初めて開催されたもので,同事業団の業務と関連して移住と国際協力のあり方,今後の移住施策の重点などを中心として種々討議がなされた。
また,76年1月22日には第35回総会が開催され,海外移住を巡る内外の環境の変化を背景として今後の移住行政のあり方について討議が行われた。特に注目されたのは人口問題,食糧問題などにも留意しつつ,海外移住を長期的観点からとらえていくべきであるとの意見が強調されたことであつた。