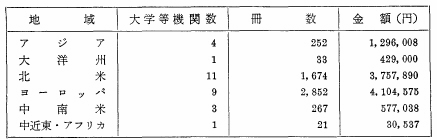
第1節 国際文化交流の現状
1. 文化的及び科学的分野の交流に関する諸取極の締結
(1) フランスとの科学技術協力協定の締結
74年7月2日,東京で大平外務大臣とド・ラブレー駐日大使との間で,日本国政府とフランス共和国政府との間の科学技術協力に関する協定が署名され,同日発効した。
この協定は,両国の政府機関及び特殊法人等の政府が監督する機関の間で行われる科学技術分野での協力を対象とし,人的交流,科学技術関係の会合の相互開催,共同研究の実施,情報の交換等を通じて協力を行うものとし,その効果的な実施のために混合委員会を設置し,更に,限られた特定分野の協力を進めるため必要に応じて専門部会を設置することを規定している。
両国間では,既に文化協定が締結されており,各種の文化交流が盛んに行われてきたが,本協定締結に伴い,今後は,同国との科学技術面の交流も一層組織的かつ活発に推進されていくことが期待される。
(2) ベルギーとの文化協定の批准
わが国とベルギーとの文化協定の批准書の交換が74年10月23日東京で,木村外務大臣とドールマン駐日大使との間で行われ,協定は同日発効した。
この協定は,73年5月4日ブラッセルで,大平外務大臣とヴァン・エルスランド外務大臣との間で署名されたもので,本文12条から成り,文化,科学,教育,スポーツの各分野における両国間の交流を奨励し,これを促進するため相互に便宜を供与することを規定している。
(3) オーストラリアとの文化協定の署名
74年11月1日,田中総理大臣の訪豪中に,キャンベラにおいて,吉田駐豪大使とウィットラム首相兼外務大臣臨時代理との間で,日本・オーストラリア文化協定が署名された。
この協定は,本文13条から成り,従来わが国が締結した他の文化協定とほぼ同様に,人物交流,各種機関間の交流,その他種々の手段を通じて,文化及び教育の各分野における両国間の交流を拡大,促進するため相互に協力することを規定している。本協定は,わが国においては国会の承認を得た上で,批准書の交換により効力を生ずることになつている。
オーストラリアとの間には従来より,各種公演及び展示の相手国における開催,学生,研究者等の人物の交流,姉妹都市の提携及びオーストラリアにおける日本研究促進事業等が行われているが,本協定締結により,従来より行われてきたかかる交流がより一層安定した基礎の上に促進されることが期待される。
2. 文化協定に基づく文化混合委員会(注)等の開催
(1) 第7回日仏文化混合委員会の開催
日仏文化協定(53年10月3日発効)に基づく,日仏混合委員会の第7回会合が74年5月28日,29日両日,東京で開催された。同委員会では,(イ)フランス語及び日本語の相互の国における教育に関する問題,(ロ)研究調査団の派遣,教育研修,語学研修,留学生の交換,学校機関間の提携,大学の学位及び資格証書の同等性等の教育分野における協力に関する問題,(ハ)討論会,研究会,及び国際会議の開催,双方の機関の間の直接取極,奨学金の供与等を通ずる文化・科学分野における協力の問題,(ニ)青少年交流,書籍等刊行物の交換,映画,テレビ,ラジオ等の視聴覚手段に関する協力,各種催し物の開催等の芸術交流及びフランスにおける日本研究促進基金に関する問題等が話し合われた。
(2) 第7回日米文化教育会議の開催
61年6月の池田・ケネディ共同宣言に基づく日米文化教育会議の第7回会議は,74年6月17日から20日まで,東京において開催された。
同会議では,前回会合以後の両国間の文化及び教育面の交流状況と,将来における相互理解の拡大強化の方策を検討し,国際理解教育,コミュニケーション・ギャップとマス・メディア,博物館交流,米国研究,日本研究の諸分野における諸問題につき討議が行われた。この結果20余項目の勧告を採択するとともに,既に存在する3つの小委員会に加えて,米国研究と日本研究に関する小委員会を設置すること等が合意された。
(3) 日仏科学技術協力混合委員会の開催
日仏科学技術協力協定(74年7月2日発効)に基づく,日仏科学技術協力混合委員会の第1回会合が,74年7月2日,3日の両日,東京で開催された。同委員会では,基礎科学,ライフ・サイエンスの研究等を含む生物医学,海洋開発,太陽エネルギー,海洋エネルギー等の新エネルギー開発等の各分野における協力及び,鉄道,電力,電気通信,建築等の技術分野における協力につき,その態様と将来の計画が話し合われた。
(4) 第8回日英文化混合委員会の開催
日英文化協定(61年7月8日発効)に基づく,混合委員会の第8回会合が,74年10月25日ロンドンで開催された。同委員会では英国における日本研究促進基金に関する問題,英国の大学における日本研究に対する国際交流基金からの援助に関する問題,日本研究,日欧文化交流の促進のための英国の諸団体に関する問題,両国間の学者,研修教員,留学生等の人物交流,奨学金の供与,美術展示会の開催等につき話し合われた。
(5) 第1回日白文化混合委員会の開催
日白文化協定(74年10月23日発効)に基づく,わが国とベルギーとの間の混合委員会の第1回会合が,75年2月27日,28日両日,東京で開催された。同委員会では,留学生,学者,研究者等の人物交流,共同研究協力,図書,刊行物の交換,各種展示会の開催等の芸術交流等両国間の各種文化交流につき,それらの実績及び将来の計画を中心に意見の交換を行うとともに,双方の奨学金制度の問題及び大学の学位,資格証書の同等性の問題について話し合われた。
(1) アジア太平洋地域文化社会センター
68年10月ソウルに設置されたアジア太平洋地域文化社会センターは,第7事業年度を迎えた。74年4月から75年3月までの間に,センターは,大学出版と国際協力に関する会議,社会開発セミナー,国際映画祭等の開催,ヴィエトナムの文化財修復調査を行つたほか,域内の学者,ジャーナリスト,教育者,芸術家等の域内研究旅行に対するフェロ-シップの支給,青少年の親善体験旅行に対するフェロ-シップの供与などの事業を行つた。
(2) 東南アジア文相機構(SEAMEO)への協力
58年教育,科学,文化の分野における東南アジア諸国間の協力を推進することを目的として発足した本機構は,現在,理数教育センター(RECSAM,在マレイシア),英語教育センター(RELC,在シンガポール),熱帯生物学センター(BIOTROP,在インドネシア),農業研究センター(SEARCA,在フィリピン),教育革新センター (INNOTECH,在ヴィエトナム)の各センターと,熱帯医学計画(TROPMED,本部はタイ,各国にそれぞれ特定研究テーマを分担するナショナル・センターがある)の6プロジェクトが実施されており,さらに,73年にはプノンペンに考古学・美術応用研究センターを設置することが決定され,現在準備のための事務所が開設されている。
これらプロジェクトは,各分野での教育者,研究者等の養成訓練,調査,情報交換等を主な事業内容としており,加盟国以外の諸国とも密接な協力を行つている。同機構事業の所要経費の半分は設立当初の経緯から米国政府の援助によつているが,米国以外の諸国も資金援助や人員,機材の提供等を行つている。わが国はSEARCAの機材の購入のために1万ドルの拠出を行つたほか,SEARCAの研究指導のための専門家の長期派遣,短期派遣,BIOTROP,RELC,TROPMED等のセミナー参加のための専門家派遣を行つた。
(3) ボロブドール遺跡復興協力
政府は,ユネスコの呼びかけに応じて,インドネシアが誇る世界的文化遺産であるボロブドール仏跡(8~9世紀頃建造されたヒンズー・ジャワ文化に属する石造仏教建築物)の復興用資金推定必要額775万ドルの一部として,年間10万ドル,6年間に計60万ドルの拠出金を計画し,74年度までに30万ドルを拠出した。
(1) 在外公館主催の文化事業
各在外公館はそれぞれ所在地域の特殊事情等を勘案して,講演会,音楽会,生花教室及び生花展,日本文化紹介展等の各種催し物を企画及び実施し,又は,現地諸団体のイニシアティヴに基づく文化的諸行事に参加するなど,日本文化紹介及び相互理解の増進に努力して来ている。74年度には,各地域を通じて生花(生花教室,講習会及び展示会)81回,講演会17回,音楽会14回,日本文化紹介展9回,浮世絵版画展9回,日本文化祭6回,現代版画展6回,その他各種の文化行事を行うとともに,現地各種文化団体等主催の催しに参加した。
(2) 日本紹介のための公演
わが国伝統文化及び現代芸能の海外への紹介は,わが国についての理解増進を計るための重要な事業の1つとして,国際交流基金が活発に行つている。
これらの事業は,多額の経費と長期の事業計画が必要であり,民間機関のみでは実施しにくい事情があるので,今後とも国際交流基金はその自主的事業として,これらの活動を行うとともに,民間団体の事業を一部援助していく形で積極的に推進していく必要がある。
74年に世界各地域で国際交流基金により実施されたこの種の事業は,次の通りである。
(3) 日本紹介のための展覧会
国際交流基金は,わが国の美術,工芸,現代版画,写真等を通じ,日本文化を海外に紹介しており,74年に行われた事業は,次の通りとなつている。
(4) 図書出版物による日本紹介
(イ) 国際交流基金は,海外における日本研究機関をもつ大学,研究機関,図書館等を中心に図書寄贈を行つているが,同基金が今年度中に行つた地域別図書寄贈の実績は次の表の通りである。
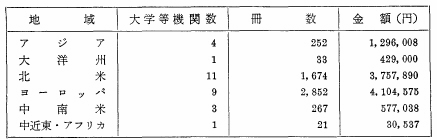
このほかに同基金はメキシコ及びサンパウロで開催された国際図書展に日本関係図書を出品した。
(ロ) 上記の図書寄贈のほか,同基金は現在海外の日本研究機関等に対する配布用として英語及び仏語によるわが国文学,学術,美術書等の翻訳・出版を行つているが74年度では7種の翻訳出版を行つた。
また,これらに加えて15種の日本紹介出版物を買い上げ配布している。
(5) 映画及びテレビによる日本紹介
映画及びテレビ・フイルムの活用は,日本人の思想,文化及び生活様式等を他国民に知らしめる上に非常に有効な手段であり,外務省及び国際交流基金は在外公館主催の映画会の開催,外国における民間映画関係団体の映画祭への参加,フイルムの貸出し等を行つているが,74年度中各在外公館は以下の通り映画会開催とフイルム貸出し,国際映画祭への参加等を行つた。
(イ) 在外公館主催映画会
74年には103回の在外公館主催劇・文化映画会を開催した。74年度に上映したフイルムのうち劇映画では「真剣勝負」,「大地の冬の仲間たち」,「旅の重さ」,文化映画では「JAPAN」,「京都御所」,「桂離宮」,児童映画では「わん白王子の大蛇退治」等が好評を博した。
なお,これら映画フイルムの購入は,国際交流基金が行つており,74年度中には劇映画(16ミリ)15本,児童映画(16ミリ)1本,文化映画(16ミリ)30本を購入した。
(ロ) 日ソ映画祭
60年6月,日ソ両国政府の合意に基づき相互に映画祭が毎年1回開催されることになつたが,この企画により映画芸術を通じて日ソ両国の友好親善と相互理解を深めるとともにわが国の国情,文化を紹介する上に非常な効果をあげている。
74年度はモスクワ,キシニヨフ,レニングラード及びナホトカの4都市で劇・文化映画の上映が行われ,またこれと対応して11月に東京,仙台,神戸の3都市でソ連映画祭が開催された。
日本側の出品作品は「神田川」(松竹作品),「ともだち」(日活作品),「むつごろう結婚記」(東宝作品)の3本の劇映画と文化映画「輪島塗」(桜映画社作品)の4本であつた。
なお,日本側より「ともだち」の監督沢田幸弘及び「むつごろう結婚記」の出演女優夏純子を国際交流基金が派遣した。
(ハ) 国際映画祭
42の各種国際映画祭より各在外公館及び在本邦関係外国公館を通じ,劇映画あるいは文化映画作品の出品参加の招へいを受け,このうち大半の国際映画祭に積極的に参加した。
特に第17回ゴールデン・マーキュリー国際映画祭(6月,ヴェニス)では文化映画「鍋島焼」(桜映画社)が金賞を,第6回国際科学映画祭(7月,リオ・デ・ジャネイロ)では「腸内菌叢と宿主」(シネ・サイエンス社)が最優秀賞を,また第11回イラン教育省主催国際教育映画祭(9月,テヘラン)では「鶴の来る駅」(NHK)が地理部門において銀賞をそれぞれ受賞した。
(ニ) テレビ番組放映「姫路城」,「港長崎の少年たち」,「装身具」,「柔道」(借用フイルム)等を各在外公館で放映した。
(ホ) 日米放送番組交流
国際交流基金ではテレビ番組を通じて,日米間の相互理解と親善を深めることを目的として,日本民族芸能に関するテレビ番組26本を購入,英語版を作成し,74年7月より米国公共テレビ局(P.B.S.)を通じて,米国全土に放映されている。
また,74年11月米国放送界訪日団を迎え,日米放送界合同会議が開催され,日米の放送番組の交流について審議され,また,年間4本のテレビ用マガジン番組(ニュース解説を内容とする)を製作し,相互交換を行うことを決定した。次いで,第2回日米テレビ番組フェスティヴァルが開催された。フェスティヴァルでは,米国作品の放送番組40本(1698分),日本出品30本(1108分)が3日間にわたつてそれぞれ試写された。
(6) 東南アジア「日本週間」
国際交流基金は,74年11月21日から75年1月31日までの間に,インドネシア,南ヴィエトナム,フィリピンの東南アジア3国で日本週間を開催し,日本音楽集団の伝統音楽の公演及び映画会の開催を行つた。
(1) 文化人の海外派遣
国際交流基金は,わが国の芸術,学術,思想,スポーツ等を紹介し,国際親善を促進するため,前年に引続いて文化人,学者,音楽家,茶道・生花及び柔道の師範等合計88名を派遣した。
(2) 文化人等招へい事業
国際交流基金は,次の招へい事業を行つた。
(イ) 文化人等短期招へい事業
外国の文化人,学者等をわが国に招き,わが国の事情を認識させ,わが国関係者と意見交換の機会を与えることを目的とし,74年度は76名を招へいした。
(ロ) 日本関係研究者長期招へい事業
諸外国から日本関係研究者を本邦に招き,研究者のわが国での実地研究に役立たせるため,74年度は69名を招へいした。
(3) 第3回アジア中学高校教員招へい事業
アジア諸国の中学・高校教員に対し,教育を中心としたわが国の実情を視察する機会を与えることにより,対日理解の促進と相互理解の増進を図ることを目的として,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,ビルマ,フィリピン,マレイシア及びヴィエトナムの8カ国より計130名を招待した。
(4) 日本語普及促進事業
国際交流基金は,従来,日本語普及事業をすすめてきた地域を対象に,日本語学習と日本研究の奨励,対日理解の促進を図るため,「海外日本語教師の招へい」及び「日本語講座成績優秀者の招へい」事業を実施してきた。
74年,日本語教師を1月16日から3月15日の間,アジア,太洋州及び中近東各地域から14名,日本語成績優秀者を3月13日から26日の間,アジア,中近東,太洋州,北米,中南米,欧州各地域から50名を日本に招いた。
(5) 学術調査隊,スポーツ団体及び登山隊に対する便宜供与
外務省は,74年度もわが国から派遣される学術調査隊(アジア,大平洋,中近東,アフリカ,欧州,北米,中南米向け33隊),スポーツ団体(アジア,大平洋,アフリカ,欧州,北米,中南米向け30団体)及び登山隊(アジア向け19隊)に対する便宜供与を行つた。
(1) 国際学友会による事業
財団法人国際学友会は,昭和10年創立され,外国人留学生のための日本語学校を運営,宿舎事業を行なうとともに,留学希望者に対する大学進学の斡旋等の事業を行つている。
日本語学校は,東京本部及び関西国際学友会で運営されており,学生定員は前者200名,後者180名であるが,74年度は,これらの日本語学校で371名の留学生に対し,日本語をはじめ,数学,理科,社会などの基礎学科を教授し,これら課程の修了者に対し進学を斡旋した。
(2) パリ大学都市日本館
パリ大学都市日本館は,パリ大学で学ぶ日本人留学生,外国人留学生及びフランス人学生のための学寮であり,館長は,日本館に居住する学生及び大学都市内の各館に居住する日本人留学生の補導にあたつている。
また,日本館内には,日本関係の図書を収集して日本研究に便宜を与えている。
外務省は,館長を推せんし,派遣しているほか,同館建物の内部修理及び若干の備品などに対し,援助を行つている。
(3) 外国人留学生の来日
わが国に留学を希望する外国人は,著しく増加しており,74年11月現在で約5,500人の留学生が日本の大学で学んでいるが,うち国費留学生は,1,014名,74年度新規採用の外国人留学生は406名である。
(4) 東南アジア日本留学者の集い
第1回「東南アジア日本留学者の集い」は74年11月26,27日の両日,外務省国際会議場において開催された。参加者は,留学生問題について意見交換を行い,その後関係施設見学,留学生問題関係者と,懇談を行つた。
この「集い」は,外務省の招待により,インドネシア,カンボディア,シンガポール,タイ,フィリピン及びマレイシア,南ヴィエトナム及びラオスの8カ国から,元日本留学者49名(及び同伴夫人34名)が参加して行われた。
(5) 日米教育交換計画(フルブライト計画)
74年度の本計画に基づく両国間学生,教授,研究員の交換実績は,来日米国人31名(客員講師13名,研究員9名,教員7名,大学院学生2名)及び渡米日本人35名(講師及び研究員18名,大学院学生17名)である。
(6) 日本研究事業
海外の大学の日本研究講座及び大学,学術研究所の日本研究を助成するため,国際交流基金は74年中に次のとおり日本人学者,研究者又は専門家を派遣した。
(イ) アジア地域における寄贈日本研究講座への援助
わが国は,アジア諸国で,日本研究について関心の高い主要大学に日本研究講座を寄贈開設することとし,65年度に,タイのタマサート大学(のちにチュラロンコン大学を含める),66年度に,フィリピンのアテネオ大学,香港の中文大学(のちに香港大学も含める),マレイシアのマラヤ大学及びインドネシアのインドネシア大学,更に68年度に,インドのデリー大学に,それぞれ日本研究講座を開設した。講座の開設に当つて,日本側と相手側との間に取交された文書により講座の目的及び運営(図書,教材の寄贈を含む),派遣教授陣の構成,地位,待遇等について合意された。74年における上記各関係大学への派遣教授陣の現状は教授7名,講師12名,計19名である。
(ロ) 欧州,大洋州,北米,中南米における日本研究への援助
国際交流基金は74年度に欧州においてはイギリスのオックスフォード大学,フランスのパリ第7大学,パリ第3大学,イタリアのボッコー二大学,大洋州のニューサウスウエルズ大学,西オーストラリア大学,北米においてはアメリカのハワイ大学,ハーバード大学等7大学,カナダのマッギール大学,中南米においてはメキシコのエル・コレジオ・デ・メヒコ,ブラジルのサンパウロ大学に計15名(うち教授14名,講師1名)を派遣する等9,200万円あまりの助成を行ない,それぞれの大学における日本研究の発展促進に協力した。
(7) 日本語普及事業
国際交流基金は,日本語普及のため,74年中に下記事業を実施した。
(イ) 日本語講師の派遣
(ロ) 海外日本語教師の謝金援助
(ハ) 海外日本語教師及び日本語講座成績優秀者の本邦招へい
(ニ) 日本語教材の寄贈
(ホ) 海外日本語講座主催弁論大会の援助
(8) 日ソ学者・研究員の交流
65年以降,わが国はソ連との間に,政府間取極により,相互主義に基づく学者・研究員の交流を行つているが,74年度には,日本側から長期2名,短期5名,ソ連側から長期2名,短期1名の学者・研究員の交換を行つた。
また,73年10月10日モスクワで「日本政府の関係研究機関とソ連科学アカデミーの研究機関との間の学者及び研究者の交換に関する交換公文」が交換され,日本側各省庁所管の研究機関及び大学とソ連側ソ連邦科学アカデミー及び連邦構成共和国科学アカデミーの研究機関との間で毎年長期10名(10カ月を越えない),短期10名(2カ月を越えない)の範囲で学者・研究者の交換を行うこととなり,74年度には,日本側から長期10名,短期9名,ソ連側から長期10名,短期9名の学者・研究者の交換を行つた。
(注) 文化協定は,締結国政府が両国間に行われる各種文化交流事業の促進をはかり,これを奨励することを主な内容とする協定であり,わが国は現在,14か国と文化協定を締結している。
混合委員会は,文化協定の適用を確保し,また,協定の実施条件を具体化すること等を主要な任務として,同協定により設置される両国の協議機関である。これまで開かれた委員会では一般に両国間の文化交流の実績を検討し,更に,今後の文化交流計画に関し協議が行われている。各委員会の日本側委員として,外務省代表のほか文部省等関係省庁の代表者や民間有識者が任命されている。