―中南米地域―
第4節 中南米地域
1. 概 観
前掲,中南米の情勢の項に述べた中南米の流動的な情況にもかかわらず過去1カ年,わが国との関係は従来の友好関係がさらに一段と増進されたということができよう.特に指摘すべき点は次の通りである。
第一に万博開催を機会とする各国政府,民間要人の来日により,わが国関係者との人的コンタクトが深まり,各国要人の対日認識が深まったこと。
第二に,わが国からも愛知外相のアルゼンティン,ブラジル訪問があり,更にアンデス地域諸国に対するわが国の協力の可能性を検討する経済使節団を派遣したこと。
第三に,わが国が75年までにGNP1%の対発展途上国援助方針を打出したことにより,アジア中心の経済協力を中南米,中近東,アフリカヘも積極的に行なう姿勢を示したが,これにともない中南米の鉱物資源に対する重要性の再認識と相まつて,今後の経済面での関係緊密化が予想されることである。
今後,わが国としては,中南米における新情勢を適確に把握し,協力関係をより深いものとする必要があろう。
愛知外相はアルゼンティン,ブラジル両国外相訪日の答礼として,両国政府の招待により1970年9月20日から22日までアルゼンティンを,また,同22日から26日までブラジルをそれぞれ公式訪問した。アルゼンチンではレヴィングストン大統領,デ・パブロ・パルド外相らと会談し,国連活動の強化の必要性,軍縮の達成等について意見の一致をみたほか,両国間の貿易促進,経済協力および科学技術協力など両国間の懸案について意見の交換を行なつた。
他方ブラジルにおいてはメジシ大統領,ギブソン外相,ディアスレィテ鉱山動力相等政府要人と経済技術協力問題をはじめとし,日伯間に存する諸問題ならびに今後の両国間の親善関係の緊密化につき意見の交換を行なつたほか,両国外相間でわが国としてはじめての技術協力基本協定が署名された。
(1) 対中南米貿易とその問題点
チリ,ペルーからの鉄,銅,などの鉱石,ブラジルの鉄鉱石,メキシコの綿花等が中南米からの主たる輸入資源であるがこれらは原材料としてわが国の経済発展に不可欠な資源であり,資源確保の意味からも中南米の輸入市場としての重要性は特筆すべきものがある。
ちなみに中南米からの輸入額が,わが国の総輸入額に占める割合は,鉄鉱石約25%,銅約11%,綿花約52%である。またアンデス地域には,石炭及び低硫黄度の石油が多量に埋蔵されていることが近年明らかになつたことから,今後わが国としても大いに開発協力をすすめて行くべきものと考えられる。
1970年(1~12月)のわが国の対中南米貿易は下記の表のとおりであるが,本年度も前年に引き続きわが国の入超に終つた。
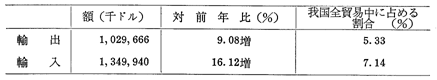
輸出についてはここ2,3年順調な伸びがみられるが,中南米諸国においては,次のごとき問題点が存する。すなわち
(あ) 国産化に伴う外国品輸入制限
(い) 自国産品を買つてくれる国から輸入する方針
(う) 片貿易国への輸入制限
(え) 欧米諸国産品との伝統的結びつき。
従来これらは,わが国にとつて大きな障害となつてきたが,官民の努力によつて近年徐々に改善されてきており,わが国の資本財,中南米の一次産品といつた形での補完関係での交易は今後ますます密接化するものと考えられる。
(2) 対中南米経済技術協力とその問題点
わが国は中南米諸国に対し日本輸出入銀行の資金利用による延払輸出を中心とし,輸出信用枠(クレジット・ライン)の供与,国際機関との協調融資,全米開発銀行及び中米経済統合銀行への融資,民間投資を通ずる経済協力,また専門家の派遣,研修員の受入れ,訓練センターの設置等による技術協力を行なつているが,次のような種々の問題が生じてきている。
(イ) 延払輸出の際の条件については米国,欧州の先進諸国が期間,金利の面でますます緩かなものを与えており,わが国も競争上,より緩和された条件のものを与える必要に迫られていること。
(ロ) 延払以外の協力については最近中南米の多くの国で,入札の条件として延払い(サプライヤーズ・クレジット方式)でなくバイヤーズ・クレジット方式さらにパンク・ローン方式を要求する例が多くなつていること。
(ハ) 輸出信用枠の供与については,アルゼンティン(500万ドル),チリ(800万ドル)の前例(いづれも70年末より2カ年単純延長した)があるが消費額が不十分であり条件等の改善を先方より要求されていること。
わが方としては以上の諸点を解決すべく,目下鋭意検討中である。
なお,技術協力に関しては,70年度中南米に派遣した専門家27名,受け入れた研修員215名,調査団派遣2件であつたが,いづれも好評を博している。
(3) 南米経済使節団の派遣
土光東芝社長ほか22名からなる政府派遣南米経済使節団は,10月3日から20日までの18日間コロンビア,ヴェネズエラ,エクアドル,ペルーの4カ国を訪問した。
これらはいづれもわが国の必要とする銅,鉄,石油,石炭等の地下資源に恵まれた国々である。またヴェネズエラを除く3カ国はチリ,ボリヴィアとともにいわゆるアンデス共同市場を構成する国々であり,ヴェネズエラも遠からず右市場に加入の気運にあり,これら諸国の動きが注目されている一方,右諸国の側では,わが国との協力を強く要望していることが今次使節団派遣の背景であつた。
上記経済使節団は現地事情を視察し,経済の動向を把握するとともに訪問先において,大統領をはじめ経済関係閣僚,商工会議所,工業連盟等政財界の有力者と会談し,わが国とこれら諸国との経済協力の方途について検討した。
(4) 日伯技術協力基本協定の署名
1970年9月22日ブラジリアにおいて日伯技術協力基本協定がブラジルを公式訪問中の愛知外相と伯国ギブソン外相との間で署名された。
本協定は技術協力を通じ日伯両国間の伝統的友好関係をいつそう強化し,かつ両国の経済社会的進歩を促進させることを考慮してわが国がブラジルに対し研修生の受け入れ,専門家,調査団の派遣,機材の供与等の形によつて各種の技術協力を行なう場合にブラジル側が右協力を実効あらしめるための国内的諸措置をとることを内容としている。本協定の発効にはブラジル側の国会の承認を必要とするが発効後は本協定により両国間の技術協力がいつそう円滑かつ効率的に遂行されることが期待される。
なお本協定はわが国が外国と絡んだ最初の技術協力協定である。
(5) 日量研修生学生等交流計画
1970年12月に就任したメキシコのエチェベリーア大統領は,同大統領自身の構想として,日墨間に研修生及び学生等を交流せしめる計画をわが国に提案越した。この計画はかねて民間ベースの日墨経済協議会の会議においても墨側から申し入れが行なわれていたものであるが今後の両国関係の緊密化に大きく貢献するであろうと考えられるので,わが方も上記提案を原則的に受諾することとし,1970年3月3日,ラバサ・メキシコ外相と在墨加藤大使との間で,本件計画に関する書簡をとりかわした。
その結果,1971年度中にメキシコ政府推薦のメキシコ人研修生100名以内がわが国の海外技術協力事業団及び海外技術者研修協会によつて受け入れられ,原則として10カ月間技術実習を主体とした研修を行ない,他方わが国からは経済団体連合会を通じて推薦された企業関係研修生及び大学等を通じて推薦された学生等計100名以内がメキシコの国家科学技術審議会によつて受け入れられ,10カ月間主として同国各地の大学において,スペイン語その他の科目を研修することとなる見込みである。
(6) 対ペルー債権繰延ベ
ペルー政府は1969年8月同国の外貨危機打開のため債務救済を目的とする国際会議開催を,わが国を含む主要債権国に要請した。同年11月ブラッセルで会議が開催された結果,1970年及び同71年に弁済期限の到来するペルー政府及び公的機関の延払債務であつて,かつ債権国の権限ある機関により保証されているものにつき1972年から76年の5年間に分割払いを行なうことを骨子とする計画の大綱が作成された。わが国は右大綱に基づきペルー政府との間に約877万米ドル(元本総額の75%)につき取決作成について交渉を行ない,合意に至つたので70年12月22日東京で繰延べに関する書簡の交換を行なつた。
(7) ペルー震災に対するわが国の援助
70年5月31日発生したペルー大地震の被害は死者5万,罹災者80万を数え,このため各国は,現金,物資,役務等の救援を行なつた。わが国政府も救恤金としてまず外務省予算より現金2万ドルを拠出したが,その後現地からの報告により災害の甚大さが判明したので,人道的見地及び両国の友好関係にかんがみ,罹災者に対する緊急援助として日本米玄米3,300トン(約58万ドル相当)がペルー日赤を通じて同国政府へ引渡された。また民間募金によりペルーに送付された額は20万ドルを超えた。
他方復興計画を助ける意味で,北部の工業都市チンボテと首府のリマを結ぶ送電線建設にわが国から1700万ドルに相当する円借款を供与することを検討している。これが実現すれば,中南米に対する円借款の供与は1959年の対パラグアイ船舶借款に次いで2度目である。
(1) 日墨経済合同委員会第3回会議
日墨経済合同委員会第3回会議は,1970年9月1,2の両日東京において開催された。外務省人見中南米審議官を団長とするわが国代表団と,ロドリゲス・アダメ駐日大使を団長とするメキシコ側代表団との間で,相互に自国の経済情勢を説明し,両国間の貿易,経済技術協力関係などの問題につき意見を交換し要望を行なつた後,共同新聞発表を行なつた。
(2) 日亜経済合同委員会第4回会議
日亜経済合同委員会第4回会議(毎年1回開催される民間ベースのもの)が70年9月7日から9日まで東京において開催された。アルゼンティン代表団はエクトル・スカルペニーニ団長のほか各業界の代表36名により構成され,永野団長(日本商工会議所会頭)ほか42名からなる日本代表団との間で,わが国の対亜輸出および経済協力問題,アルゼンティンの食肉,酪農産品,穀物,羊毛,皮革および鉱産物等の輸入問題ならびに両国間の海運問題につき意見の交換を行なつた。
(なお,日墨両国の民間の経済協議機関である日墨経済協議会の第4回会議は70年9月9,10の両日,日本側代表団長土光敏夫東芝社長を議長として東京で開催された。)
わが国とホンデュラスは1958年10月に国交を回復し,ホンデュラスは1964年7月以降外交使節(1967年7月までは公使,それ以後は大使)をわが国に派遣しているが,わが国は最近まで在メキシコ大使に在ホンデュラス大使を兼任させてきた。しかし両国間の関係のいつそうの緊密化をはかるため,わが国はホンデュラスに大使館実館を設置することを決め,1971年2月はじめ初代本任大使を同国へ派遣した。