 と相まって旅券発給の迅速化を図る。
と相まって旅券発給の迅速化を図る。-邦人の海外渡航-
第5章 邦人の海外渡航,移住の現状と在外邦人の保護
第1節 邦人の海外渡航
1969年(昭和44年)1月~12月の旅券発行数は483,447冊と対前年比152,230冊,46%増とかつてない大幅増加を示した。これは基本的には渡航の自由化,日本経済の高度成長に基づく国民所得の増加に起因しているのはもち論であるが,その他航空機の大型化,団体旅行の発達,青年学生層の海外旅行の普及等の特殊事情も働いたことによるものと思われる。
1952年以降の旅券発行数の推移はA表のとおりである。(以下に示す統計表はすべて旅券発行件数に基づくもので実際の渡航者数と一致するものではない。)
(1) 一般旅券の発給件数を渡航目的別によって分類するとB表のとおりであり,観光渡航が最多数を占め経済活動(業務,役務,赴任)がこれについでいる。
(2) 渡航先を地域別にみればC表のとおりであって欧州地域への渡航者が首位となっているが,これは旅券に記載された渡航先国の延数(1人の渡航者が例えば,ドイツ,フランスに渡航する場合は計2件と算定する方式をとっており,経由地も含まれる場合があるためで,主目的地別に渡航者実数をみれば,アジア地域が約5割で首位を占め,次いで北米地域,欧州地域の順である。
(3) 渡航者の大部分は渡航期間が3月以内の短期渡航者であり,移住,商社の支店勤務,長期業務,留学,学術研究等の長期渡航者は全体の7~10%で地域別内訳はD表のとおりである。
アジア地域での長期渡航者が渡航者数に比し少ないのは,留学,学術研究目的が比較的少ないこと,また一部の域内諸国においては長期入国査証取得の困難性等の事情によるものと考えられる。
最近における渡航自由化と人的な国際交流の拡大,多様化のすう勢に伴い旅券発行数も激増しておりわが国の旅券行政は一つの転換期に直面している。
この客観的情勢に対応すべく外務省においては旅券行政につき各種の改善を逐次行っているがその主なるものは旅券法の改正と旅券関係事務の機械化である。
(1) 旅券法改正の要点
昭和45年の第63特別国会に提出されている「旅券法の一部を改正する法律案」の要点は次のとおりである。
(あ) 5年数次往復用旅券の制度を大幅に採用し,渡航先もできるだけ包括的に記載できるようにすること。
(い) 都道府県知事に対する旅券事務委任を拡大し事務の地方分散と迅速化を図ること。
(う) 申請人の出頭義務の緩和,旅券の合冊,査証員の増補制度の採用,発給制限理由の改訂,在留届の制度化等事務の合理化と適正化を図ること。
(え) 手数料を改訂すること。
(2) 旅券事務の機械化
旅券事務処理にコンピューターの導入をする等機械化の推進は,外務省の重要施策の1として昭和40年以降努力してきているが,1969年度に実施または実施準備中の主なもの次のとおりである。
(あ) 外務省と神奈川,愛知,大阪,兵庫,福岡および北海道の各道府県をテレタイプで結び旅券申請および審査に関する情報のデータ伝送を行ない,外務省におけるコンピューター処理の能率化を図る。
(い) これらの各道府県におては,さらに旅券用の電動印字機を設置し,旅券の作成作業の一部を実施し と相まって旅券発給の迅速化を図る。
と相まって旅券発給の迅速化を図る。
(う) 外務省と取扱件数の最も高い東京都庁との間にITV(業務用テレビ)を設置し,照合連絡事務の迅速化と合理化を図る。
(え) 旅券用電動印字機は新型機種に切り替え印字能力を倍増する。
(付表,1969年の一般旅券の目的別渡航先別統計表参照)
わが国は,別項のとおり27ヵ国との間に査証相互免除取決めを結び,3ヵ月ないし6ヵ月の短期間の観光,商談等で,生業職業につくことなく,わが国に入国しようとする外国人に対しては,査証を免除することとしているが,これらの査証免除取決めの対象となる者,ならびに法務大臣から再入国許可を得て再入国しようとする者のほかは,外国人はすべて原則として外国にある日本の大(公)使館,総領事館あるいは領事館において,有効な旅券にわが国に入国するための査証を受けていなければ,わが国に入国することはできないこととなっている。
1969年中(1~12月)に,わが在外公館において発給した査証の種類別件数および比率は,次のとおりである。
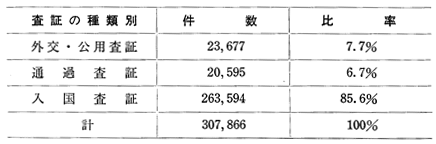 |
また,過去5年の地域別統計は別表のとおりであるが,その合計に明らかなように査証の発給件数は年をおって増加している。これはわが国と諸外国との友好,通商経済関係が緊密化するにしたがって,人的交流がますます盛んになりつつあることを如実に示すものといえよう。さらに,1969年中の査 証件数を地域別にみると,北米地域が最も多く,全体の半ば以上の52%にあたる159,932件となっており,次いでアジア地域が33.4%を占め102,917件であり,これら両地域の合計は,全体の85.4%を占めている。
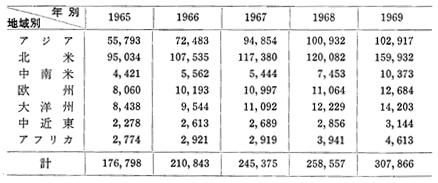 |
1.に述べたように外国人が観光,視察,商談など短期間わが国に滞在しようとする場合に査証を必要としないことを相互に約した国の数は,1969年11月にチリを加え,合計27ヵ国となった。これらの国を取決め締結の順に示すと次のとおりである。 ドイツ,フランス,テュニジア,イタリア,オランダ,ギリシャ,ベルギー,デンマーク,スウェーデン,ノールウェイ,ルクセンブルグ,スイス,ドミニカ,トルコ,オーストリア,フィンランド,パキスタン,アルゼンティン,コロンビア,連合王国,カナダ,スペイン,アイルランド,アイスランド,ユーゴスラヴィア,サンマリノ,チリ。
右のほか,わが国はインド,フィリピン,ソ連,米国,およびオーストラリアとの間に査証料の相互免除あるいは減額についての取決めを締結しており,中でも,米国およびオーストラリアとの間には相互に4年間の有効の数次入国査証を発給することを約している。従って査証に関する取決めの締結を行っている国は32ヵ国に上っている。
戦後におけるわが国の本格的な海外移住は1952年に始まり,移住者数は1955年から1961年の間には年間1万数千名に及んだが,その後は漸減してきた。1968年および1969年にはそれぞれ4,397名,4,390名となり横ばいの傾向を見せている。1969年における北米への移住者と中南米への移住者との比率は1968年とほぼ同様の6対1である。このうち半数は国際結婚による米国への移住者で,他の半数は北米,中南米に新たな職場を求めて移住した人々である。後者の構成についてみると農業移住者は減少し,技術技能移住者の割合が増加している。また,家族移住者が減少し,単身青年移住者の割合が増加している。
このように,最近における海外移住の傾向は,量的にも質的にも変化がみられる。これは,わが国の海外移住をとりまく内外情勢の変動が,わが国民の海外移住に大きな影響を与えていることによるものであるといえる。
すなわち国内にあっては,世界に類をみない経済の高度成長によって,国民の所得および生活水準が急速に向上し,また若年層労働力不足の問題が深刻化しているが,その反面マス・メディアの発達等により国民の海外への関心と知識はいっそう深まり,海外発展の意欲を強めている。
国外にあっては,中南米諸国の多くが自国の産業発展に貢献するような移住者を優先的に受入れるという方針を強めていることが注目され,他方,カナダ,アメリカのような生活程度の高い国がわが国に対しても門戸を広げるに至っている。以上のような内外の情勢の変化に伴い,わが国の海外移住は転換期を迎えており,今後の海外移住のあり方についても再検討を必要とする次第である。
海外移住は,個人が正しい情勢判断の下にあくまでも自己の発意で,確固とした信念と責任をもって海外に新しい可能性を求めて雄飛するものであり,この意味において海外移住は第一義的には個人の幸福追求のためのものであるといえるが,他面移住したわが国民が,わが国の経済,社会,科学,文化等の発達を背景として,優秀な技術,経営能力等を生かし,移住先国の発展に寄与することは,国際協力の一環として重要であり,また国際社会におけるわが国の声価の向上に資するものである。
従って,理想的な海外移住というものは,移住者自身にとって満足のいくものであり,また移住者受入国にとっても歓迎されるものでなければならず,しかも行政的観点に立った場合,それがわが国の国益に資することが必要とされる。要するに,理想的な海外移住とは,移住者,移住者受入国およびわが国の三者の利益という三位一体の上に築かれるべきものである。
このような観点から,今後の海外移住行政は,単に海外に職を探せばこと足れりというような消極的なものではなく,日本国内においてはその才能を十分に伸ばしていない有為の人材に対してそのエネルギーのはけ口を海外において見出さしめ,移住先国の発展に寄与せしめるという積極的なものでなければならない。
現在国内における若年労働力不足との関係で海外移住に消極的な意見もみられるが,わが国民の労働力の配置は国の内外を通じ,世界のどの地点においてわが国民の才能が最大限に発揮できるかという観点からとらえるべきである。
以上のような考え方の下に今後の海外移住は,ある期間海外に生活の本拠を置く一般在留邦人ないしは技術協力に伴う人的協力等諸分野との相互関係をよくふまえ,広くわが国民の国際的発展を助長する観点から,これを把握することが適切である。
(1) 新規移住者の概要
1969年度において渡航費の支給をうけて中南米へ渡航した移住者は598名であって,前年度の623名を下まわるに至った。1967年以降中南米への移住者の減少は,農業移住者と技術移住者の双方にあらわれているが,そのなかでも自営開拓農業を行なう移住者の減少はことに著しく,1969年度にはわずか数家族が移住したにとどまった。
(2) 既移住者援護のための受入国との交渉
(イ) 移住者の地租免除について
1969年わが国は,アルトパラナ移住地の入植者のためにパラグアイ政府と地租免除に関する交渉を行ない,土地取得後5年間免税措置が適用されることになった。
(ロ) 移住者の地権取得について
1960年,61年にブラジルのマラニオン州有植民地に入植した日本人移住者に対する地権交付については,わが方としては在ベレーン日本総領事館とマラニオン州当局との間に行なわれた移住者入植条件に関する交渉において,入植後3年を経過した移住者に無償交付する旨の了解が成立したものと判断していたところ,マラニオン州当局は上記了解は単なる意見の交換にすぎず,正式な取決めと認めることは出来ないとして,再三にわたる日本側の無償地権交付方申し入れにもかかわらず,これを拒否してきた。わが方は,1969年になって,上記了解については一応たな上げし,移住者のマラニオン州農業振興に貢献した点にも考慮し,移住者の地権取得の希望を容れるよう申し入れて積極的に折衝した結果,州側は1969年12月1日本件関係州有地の処分につき州法を公布した。これにより無償地権付与方申請を提出していた14名の邦人のうち,とりあえず11名の邦人移住者に対し近く地権の無償付与が行なわれることになった。
(3) 既移住者への援護施策の強化
第二次大戦後中南米諸国への移住者は約6万名にのぼるが,このうちいまだ定着・安定の域に達していない人々も少なくない。このような人々を積極的に援護するという方針のもとに,外務省および海外移住事業団は,1969年においても,次のとおり従来からの事業を拡充した。
(イ) 融資援護体制の強化
移住者の定着・安定促進のため,海外移住事業団が中南米の邦人移住者に対して行なっている融資事業の拡充をはかった結果,1969年度の貸付実績は565百万円に達し,1968年度を53百万円上回った。1969年度の融資対象はすべて農業関係であり,企業移住および技術移住者の独立のために1966年9月に設けられた小工業融資貸付けの実績は,1969年度において皆無であった。中南米へは毎年百数十人の技術移住者が移住し,1969年現在約1,500名の技術移住者(家族を含む)がいるが,そのうちには独立した事業経営を行なうことを欲するものもいると思われることにかんがみ,小工業融資の活用を積極的に図って行くことを検討している。
(ロ) 営農機械化
南米の邦人移住地の多くは奥地の森林地帯に位置しているため,農地の開墾および農耕作業には一般にはかなり苛酷な労働が要求される。このため,営農の機械化を進めることが必要であるので,海外移住事業団が現地農協にブルドーザー等,農業用大型機械を交付し,移住者がこれを適宜利用できるよう便宜をはかってきた。1969年度には,南部パラグアイ(アルトパラナ,フラム,チヤベスの3移住地)における営農機械化をはかるため,大型トラクター2台を事業団エンカルナシオン支所を通じ現地邦人農協に交付した。
(ハ) 移住地の電化
海外移住事業団は,現地電力会社と協力し,1967年度にはアルゼンティンのアンデス移住地において,また,1968年度にはブラジルのフンシヤール移住地において電化工事を実施し,いずれもすでに完成をみているが,さらに1969年度においては,ブラジルのグアタパラ移住地の電化工事(移住地域内配電工事14.5kmの総工事費の1/2づつを海外移住事業団と受益入植者が負担する。)を実施した。
(ニ) 沖繩移住地総合対策の推進
1967年ボリヴィアにある沖繩移住地の管理を琉球海外移住公社および沖繩海外協会より海外移住事業団に移して以来,現地調査に基づきたてられた沖繩移住地総合対策の年次計画に基づいて,主に道路の大改修と飲料水対策としての深井戸堀りを補助することになった。1969年度には,道路補修のための車輛(7台),機械(ブルドーザー1,グレーダー1,その他)の購入および深井戸堀り工事(54基)を実施した。
(ホ) 民間資本の移住施策への導入
(i) 海外移住事業団は,パラグアイ当局の産業振興政策にのっとり,日本商社の共同出資による現地会社パラグアイ絹糸株式会社(ISEPSA)とタイアップして,南部パラグアイ邦人移住地での養蚕を振興するため,1969年において60戸の邦人養蚕農家に対して桑植付融資(6,OOO万円)を行なった。
(ii) 南部パラグアイの邦人移住者の生産する油料作物の販路を開拓することによりこれら移住者の援護を行なうことを目ざして,海外移住事業団,経済協力基金および日本の4商社の共同出資を受け,1967年に発足した日本イタプア製油投資株式会社は,1968年12月エンカルナシオン市にイタプア製油商工株式会杜を設立し,製油工場を建設中である。操業は1970年中に開始される見込みである。
(iii) 南米開発投資株式会杜の牧畜事業計画は,世界における肉牛の需要の将来性に着目し,ブラジルおよびパラグアイにおいて現地法人を設立して大規模な畜産事業の経営を行なうものである。パラグアイにおける本計画は,パラグアイの邦人移住者の定着・安定にも資することにかんがみ,海外移住事業団直営のイグアス入植地の一部を牧場用地として同株式会社に有償で提供することによって,同計画に積極的に協力することとしている。
(4) 移住地現地調査
1969年度には,外務省は各省の協力を得て4調査団を中南米に派遣し,それぞれ次の事項につき調査を行なった。
(イ) 中小企業移住調査
南米諸国に対するわが国中小企業の資本,機械設備,労働力ぐるみの移動(いわゆる企業移住)の可能性を探るため,ブラジル,アルゼンティンの両国に調査団を派遣し調査した結果,企業移住の諸環境はかなりきびしく(例えば現地の金融は,金利が高く,また長期金融がないこと,労働事情についても技術を有する労働者を集めるのが困難であること等。),企業移住を行なうに先立って周到な現地調査と,現地日系コロニア企業または進出企業との密接な提携の必要性が指摘された。
(ロ) 移住地自治会調査
邦人集団移住地における自治会育成の方策をたてることを目的として自治会の実情につき調査を実施した。
(ハ) 移住地生活改善調査
移住地における生活方式の合理化と近代化のための対策をたてることを目的として移住者の生活環境の実態調査を行なった。
(ニ) 移住地保健衛生調査
1962年より引き続き実施されてきた邦人移住者の保健衛生調査の第7回目として,今回は皮膚科および泌尿器科を中心として行なった。
(1) 新規移住者の概要
1960年代においてカナダ・アメリカ両国は,相次いでアジアからの移住者受入れについて門戸を広く開くようになり,1960年代末にいたり,この新しい受入制度に基づく移住は,一応軌道に乗ったものと思われる。1969年に日本からカナダとアメリカに移住したものは,旅券発給統計によればそれぞれ578名(1968年より21名減),3,005名(1968年より41名増)である。最近の米国移住に関し注目すべき点は,米国移住者全体のなかで高級技術者,企業上級職員(家族を含まない数)の占める割合が,徐々に増加していることである。日本から米国へ移住した者のうち,高級技術者,企業上級職員の占める割合は,1966年,1967年,1968年の各米国会計年度にそれぞれ10%,15%,14%である。
(2) カナダヘの移住者に対する渡航前講習の充実
力ナダヘの移住者は,中南米への移住者にくらべ,邦人の間に混って生活することが少なく,直接現地人の社会に入ることが多いので,語学力が移住の成功に影響するところが極めて大きい。このため1967年以降,カナダヘの移住者に対する語学力補完を中心とする期間1ヵ月の渡航前講習が事業団の手で行なわれてきたが,1969年においては,受講者は84名であった。また,この他に農業関係のカナダ移住者に対して特別の農業実習を行ない,1969年においては40名が受講した。
(3) カナダヘの移住者の定着安定状況
1968年に行なった実態調査の結果によると,1966年の調査と比較して,月収が300カナダドル以上500カナダドル未満のものが約50%を占めたことには変化がないが,300カナダドル未満の月収の者が減少し,800カナダドル以上の月収のものが増加しているところからみて,カナダ移住者の経済的水準の向上がうかがえる。
(1) 移住者の渡航費貸付金に係る債務の一括免除
第二次大戦後1966年3月31日までに中南米諸国に移住した者および米国難民救済法の適用をうけて米国へ移住した者に対して貸付けられた渡航費に係る海外移住事業団の移住者に対する債権は,1969年5月現在約60億円に上っていたが,移住者,特に中南米移住者の生活水準等の実態にかんがみ,これら債権の免除を行なう必要があるという見地から1969年5月27日海外移住事業団法が改正され,移住者の渡航費関係債務が一括免除された。
なお,海外移住事業団が移住者から返済を受け,保管している渡航費回収金は,移住者全体の利益になるよう現地に還元贈与されることになった。
(2) ブラジルにおける海外移住事業団直営移住地のブラジル通貨建分譲
従来海外移住事業団はブラジルにある直営移住地の新規移住者に対する分譲に係る代金割賦払については邦貨建で行なうこととしていたが,1969年3月のブラジルの法律改正にしたがって,今後行なう分譲契約については,ブラジル通貨建で行なうこととした。なお利率は12%,支払期限は4年据置5年賦払とすることになった。これにより邦貨建支払により移住者が被る為替差損は解消することになり,永年の懸案が解決を見た。
なお,この新制度の恩典はすでに邦貨建で入植地の分譲をうけた移住者も新規入植者と平等に受けることができることとなっている。
(3) 海外移住に関する記念行事
(イ) 日本人の米大陸移住100周年記念式典
1969年は,約40名の日本人移住団が1869年に米国カリフォルニア州に移住してから丁度100年に当る。これを記念し1969年9月12日サン・フランシスコのゴールデン・ゲイト公園において日米官民合同の記念式典が盛大に行なわれた。
(ロ) 日本人のアマゾン移住40周年記念行事
1929年よりブラジルのアマゾンに入植した邦人は胡淑栽培をはじめとして,アマゾン地域の経済発展に大きな貢献をしてきたが,1969年11月14日ベレーン市において,また,同年12月7日にはマナオス市において,それぞれ日本人のアマゾン移住40周年記念祭が盛大に行なわれた。
邦人の海外渡航者の数は年々急増しており,海外における邦人の各種分野における活躍はめざましく,国際社会における地位も非常に高くなっている。
外務省が在外公館を通じて1969年10月1日現在で調査した結果によると,在外邦人数は,商社員,留学生などの長期滞在者が約7万人,永住者(日本国籍をもつもの)は約27万3,000人,日系人(外国に帰化した移住者その他,およびいわゆる二,三世)は約106万3,000人となっている(国別統計は付表参照)。これらのうち長期滞在者の地域別,職業別内訳は次表のとおりである。
長期滞在者を国別にみると米国が圧倒的に多く,約25,000人,次いでドイツ約4,300人,タイ約3,900人,フランス約3,400人,英国約3200人,中国約2,000人,香港約1,900人,オーストラリア約1,900人となっている。
また都市別にみると長期滞在者が1,000人以上の都市は次のとおりである。ニュー・ヨーク8,900,バンコック3,800,ロス・アンジェルス3,300,パリ3,100,ロンドン2,700,シカゴ1,900,香港1,900,デュッセルドルフ1,300,台北1,200,マニラ1,000
次に,移住者の多い国を順にあげると次のとおりである。(この数には,日本国籍をもつ永住者のほか,日本国籍をもたない二世,三世などいわゆる日系人も含まれている。)
ブラジル66万2,000,米国52万2,000,ペルー5万6,000,カナダ3万3,000, アルゼンティン2万3,000,ボリヴィア1万2,000,パラグァイ7,000(以上の数字はいずれも概数)
(1) 生活困窮者
中南米移住者のなかには,働き手である家長の死亡,あるいは病気のため家族が生活に困窮するケースが多い。これら生活困窮者に対し政府は生活費や医療費を交付し援助の手をさしのべている。また困窮状態から回復の見込みなく多額の帰国費用を負担することが難かしい場合は政府は旅費を貸付けて帰国を援助している。また,韓国には韓国人と結婚した日本婦人のうち極度に生活が困窮しているもの,あるいは帰国を希望しているものも少なくない。これらの人々に対しては現地における生活,医療などの援助および帰国希望者に対する帰国援護を推進しており,昭和44年度内には子供を含め,約180人が帰国した。
(2) 精神異常者
外国旅行中または滞在中,精神障害をきたす者もふえているが,その多くは環境が原因なので,早く帰国させる必要が生じ,同伴者の必要や旅費の調達の問題もからみ解決に手数を要することが多い。
(3) 無銭旅行者
渡航の自由化にともない,青年男女の渡航者が増加し,そのなかには無銭旅行者,帰国旅費を準備せずに出かけるもの,またはこれに近いものがめだって多くなっている。この現象は各国共通であり,ヒッチハイクで旅行してまわり,各地でアルバイトをしながら生活費や旅費をかせいで歩いている。これらの青年達も多くの場合は真面目に貧乏旅行を楽しんでいるが,なかには麻薬の吸飲とか密輸のかどで外国官憲に捕まったりあるいは乞食同然の身なりをし,周囲のひんしゅくをかったり,放浪の末旅費を使いはたして在外公館に泣きついたり,ホテル代未払いのまま立ち去りホテル側から在外公館に支払いを督促してほしいと依頼してくるケースなどもふえている。
(4) 国外犯罪者
1969年1年間で邦人の国外犯罪は約30件発生している。これらの中には次のような事件がある。
(あ) 麻 薬 犯 罪
青年旅行者のなかには麻薬の吸飲や密輸のかどで外国警察に逮捕されるケースが多い。これらは中近東で麻薬を求め,西欧まで運搬したり,ヒッピー族に加わって麻薬を吸飲して逮捕されるものである。1969年のケースではイスタンブールで麻薬を密買,吸飲し,8年4ヵ月の実刑を課せられたものもある。
(い) 公海上日本船舶内の殺傷事件
出漁中の本邦漁船員による殺傷事件はあとをたたない。1969年1年間で公海上でこの種の事件をおこした者の捜査取調べのため,海上保安庁より外務省へ援助を依頼してきた殺傷事件にはケニア,フィリピン,インドネシア,パナマ,米国,豪州,ナイジェリア,スペイン(ラス・パルマス)の沖などで発生したものがある。これらのうち,3件については海上保安官が直接犯人の身柄を引き取りに現地に赴いた。
(う) 逃 亡 犯 罪 者
そのほか,わが国で罪を犯し,その罪を逃れるため,外国へ逃亡するケースもある。
前述の長期滞在邦人約7万名のうち小学校,中学校の義務教育期に相当する子弟の数は7,OOO名に近いものと推定される。
これら在外子弟に対し日本国民としての教育の機会を与え,在外邦人が後顧の憂いなくそれぞれの任地における諸活動に専念できるよう,また,在外子弟が数ヵ年の外国在留後,再びわが国の学校に円滑に編入学できるようにするために,アジア,中近東,アフリカ,南米等の地域では,日本国内に準ずる教育を施す日本人学校を開設し,また先進地域にあっては国語,社会,算数等の補習授業校が設けられている。これら各学校に対しては外務省予算を中心にして教師の派遣,教科書,教材の配布,施設設備の充実整備などを援助している。
(1) 日 本 人 学 校
1969年度においてはジャカルタ,リマおよびシドニーの3地域に日本人学校が新設されたが,シドニーについては大洋州における初めての日本人学校として注目される。これにより日本人学校は既設校を含め21校となった。
その所在地,児童生徒数,教師数は次表「日本人学校一覧」のとおりである。日本人学校は小学校を中心とし,地域によって中学部を併設し,それぞれ国内の小学校,中学校の教育課程とほぼ同様の教育課程を編成し実施している。
日本人学校の教師は,文部教官(国立大学付属学校教諭),派遣講師(公立学校教諭および大学新卒者)ならびに現地採用講師(現地在留邦人より採用)からなっているが,1969年度予算では,文部教官については3 名の増員を図り16名,派遣講師については15名の増員を図り67名となった。同時に教師の待遇の改善を図ることとし,派遣講師の滞在費の単価を増額するとともに文部教官については配偶者手当を計上した。
(2) 補 習 学 校
北米,欧州地域等の先進諸国においては,在留国の学校に就学するかたわら,週数時間国語,社会,算数等の補習学校が開設されている。1969年度における補習学校の所在地,児童生徒数,教師数等は,次のとおりである。
補習学校の教師は現地在留邦人の中から,教諭免許状を有する人が委嘱されており,外務省はその謝金の一部を補助している。