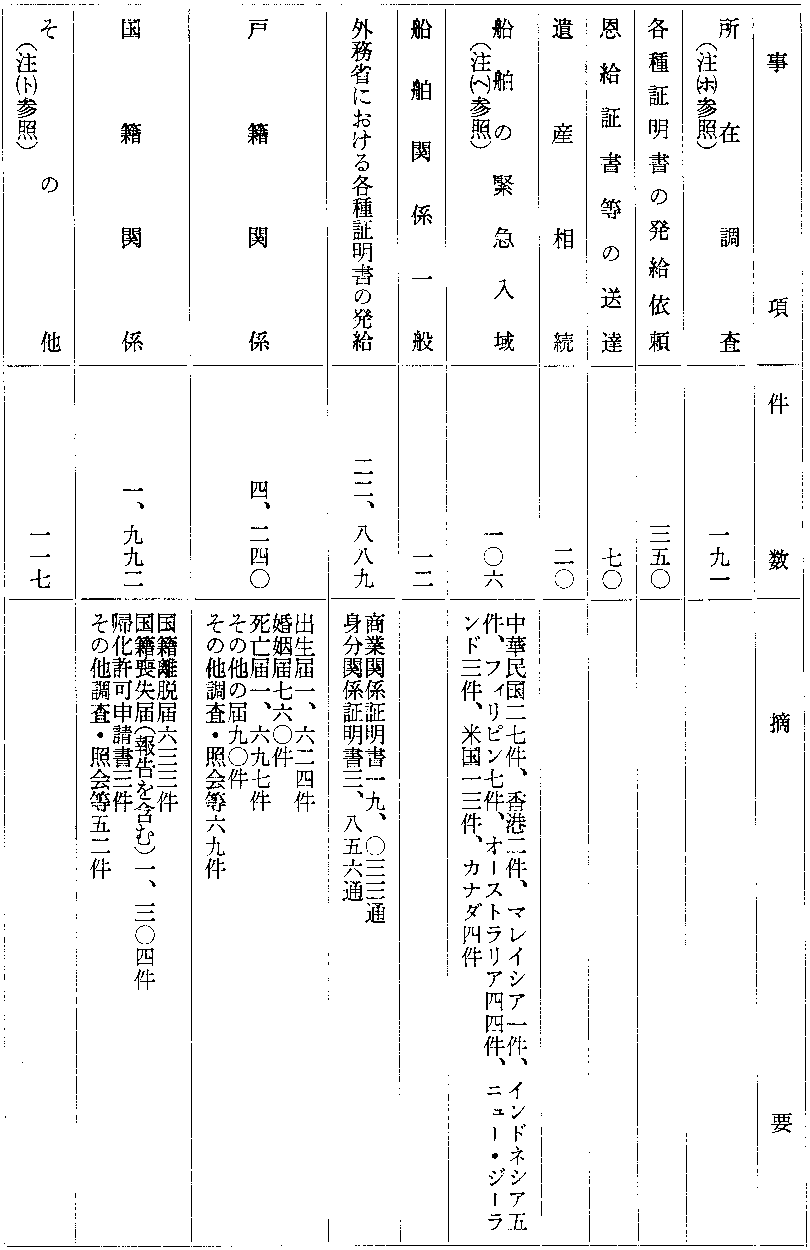
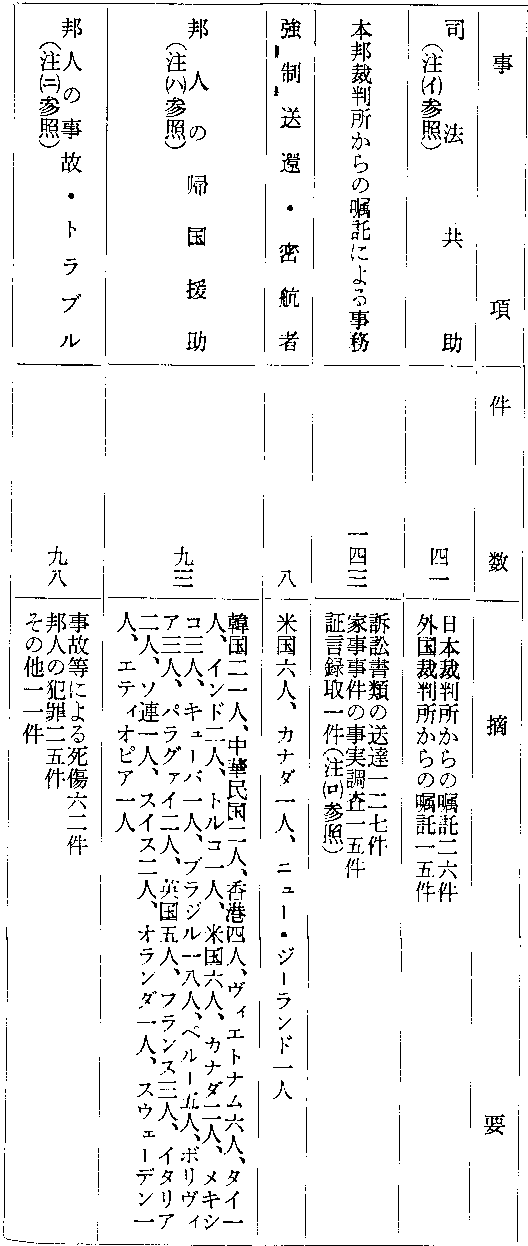
在外邦人の保護・援助
外務省および在外公館の行なう業務には、海外における邦人の保護・援助、身分関係事項に関する届出の受理などいわゆる領事事務および在外邦人の子女に対する教育に関する事務がある。外務本省においては、これらの事務は、一部を除いて、従来各地域担当局で分掌してきたが、最近の海外渡航邦人の増加に伴い、この業務が質的にも量的にも増大化するとともに、複雑化する傾向になったので、これを一カ所で統括し、その基本方針に関する企画・立案・実施に当たらせるとともに、迅速かつ効率的に処置する必要が痛感されてきた。よって、一九六七年六月一日外務大臣官房に領事課を新設し、前記事務の大部分を専任させることとなった。
領事事務の内容は、(3)の事項別件数の表に見られるように、種々雑多である。業務の性質上、詳細な説明は省略するが、一九六七年六月一日から一九六八年三月三日までの間に取り扱った領事事務のなかから、数例を参考までに次に掲げる。
(イ) 日本人と偽って本邦へ密入国を企図した外国人
一九六七年四月在釜山総領事は、日本から韓国に密入国した日本人が韓国官憲により身柄を拘束されており、韓国では、わが方が同人の身柄を引き受けるなら、密入国の動機において情状酌量の余地があり、起訴猶予とする旨述べているとして、早急に身柄引受けについて検討してほしいと要請してきた。
当初、本邦の関係機関を通じ、同人の身元を調査したが、本籍はもちろんその他なんらの手がかりもつかめなかった。その後、指紋で身元が割れ、同人は正式手続を経て出国した外国人であることが判明した。
よって、本件は、外国人が本邦へ密入国せんとして打った芝居であり、同人の身柄を引き受けるわけにはいかない旨を先方に通報した。
(ロ) 元船員の密航
熊本県出身の元船員は、一九六七年五月二六日横浜出港の米国向けフランス汽船船内に潜伏乗船し、不法出国したが、六月二二日同船が米国東海岸を航行中発見された。
同人の本邦送還にあたり身元確認の要があるため、警察庁ならびに海上保安庁に依頼して得た同人の認定事項を、同船の寄港地を管轄する在ニュー・ヨーク、シカゴ、モントリオール、トロント各総領事館に通報した。その後、同船がモントリオールに入港したので、在モントリオール総領事館員が同人を尋問し、ほぼ確認し得たが、念のため、尋問のさい撮影した写真および採取した指紋を海上保安庁に送付し、同庁において最終的に身元が確認された。
同人は、九月四日同船で大阪港に送還され、直ちに大阪海上保安監部において出入国管理令違反容疑で逮捕された。
取調べの結果、密航の目的は、アメリカを見物したいという単純なものであり、過去二回にわたり、不法出国を企てた前歴を有する密航常習者であることが判明した。
(ハ) 山岳隊員の遭難
一九六七年六月日本人二名がマッターホルン登はん中に遭難し、一名は死亡、他は重傷を負った。在ジュネーヴ総領事館において遺体処理、重傷者の入院、帰国につきあっせんした。
右とほぼ同時期ころ、アラスカにおいても登山隊の遭難事故が二件発生した。
(ニ) ポーランドにおける邦人の自動車事故死
一九六七年六月二九日本邦商社ベルリン駐在員は、ワルシャワ付近で自動車を運転中、英国人のスピード違反、前方不注意による追越し運転などの違反行為により、両車が正面衝突し、同駐在員は死亡した。
外務省は、在ポーランド大使館からの報告にもとづき、調査資料をそろえて、遺族に通知した。その後、遺族から外務省に加害者に対する刑事裁判事件の進捗状況、ポーランドにおける損害賠償手続などにつき調査を依頼越したりで、同大使館に訓令し、その調査結果を遺族に通知した。
なお、最近邦人の海外における自動車事故による死傷事件が多く報告されている。
(ホ) 日本漁船員の殺人事件
一九六七年六月九日南太平洋フィジー島附近の公海上を航行中の日本漁船船内で、一船員が他の船員により殺害された事件が発生し、同船は、同島スヴァに入港したが、事件を隠して死体を火葬にふそうとしたため、疑問をいだいた同島警察署は事件を調査、遺体を解剖に付するとともに、容疑者船員を抑留した。
外務省は、海上保安庁からの要請にもとづき、容疑者の身柄引渡しおよびその方法などにつき、在ロンドン総領事館に訓令し、英側当局の意向を打診の結果、英側は、同事件が公海上で発生した点を認めており、容疑者の日本側官憲による早期引取りを希望していることが明らかとなった。そこで海上保安庁は、七月二四日海上保安官二名をフィジー島へ派遣し、同島警察署から容疑者の引渡しを受けた。
(ヘ) テト攻撃のさいにおけるヴィエトナム在留邦人の保護
一九六八年一月三日早朝開始されたヴィエトコンによる対ヴィエトナム一斉攻撃により、ヴィエトナム在留邦人の安否が懸念され、在ヴィエトナム大使館では、現地日本人会とも緊密に連絡をとりつつ、全力を挙げて邦人の安否確認にあたった。
当初は、通信手段の途絶等もあり、安否確認は困難をきわめたが、ヴィエトナム国警および米国の協力をもえて、調査した結果、商社員等の三家屋が焼失したほかは、すべて無事であることが確認された(三月五日に至り、UPI通信邦人カメラマン一名が取材中、地雷に触れて死亡した事件があった)。
大使館では、邦人の無事を確認次第外務本省に打電し、本省では、電話、電報等により本邦商社等関係方面や留守宅に連絡した。
一方、今次事変勃発に伴い、現地においては、諸物資の入手が困難な状態にあったので、政府は、緊急用物資として、米、味噌、しょう油、インスタントラーメン、粉ミルク等の食料品、コレラ・ペスト・ワクチン等の医療品等を大使館あて送付し、これら物資の一部は、日本人会を通じて、邦人に渡された。
また、現地青木大使は、事態は流動的であり、復旧までになお時日を要すると考えられ、かつ、保健衛生上の問題をも考慮して、幼児を伴う婦女子については、一時帰国するか、あるいは、近隣国に避難することが望ましいとの趣旨を日本人会に伝えた。
その後、民間航空再開により各人の判断にもとづき、一部日本人は随時帰国した。
3 事項別件数(一九六七年六月一日から一九六八年三月三一日まで)
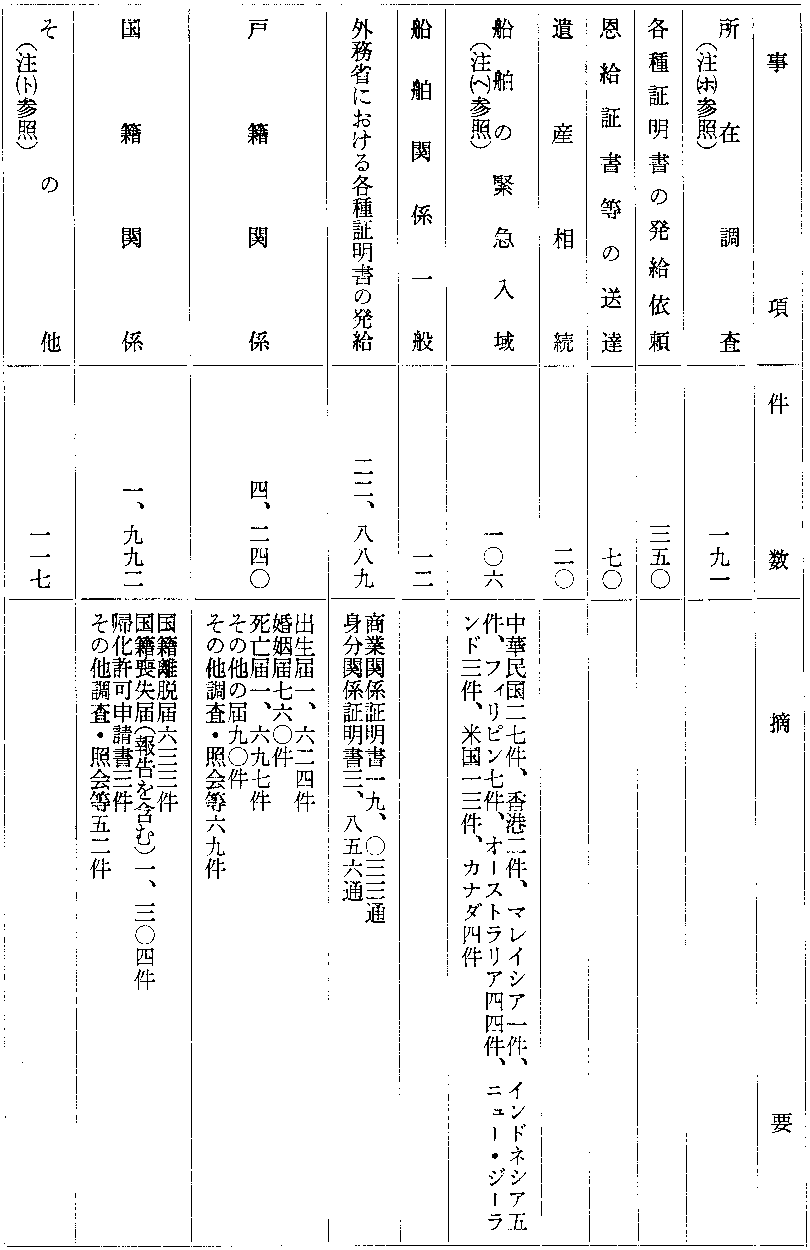 |
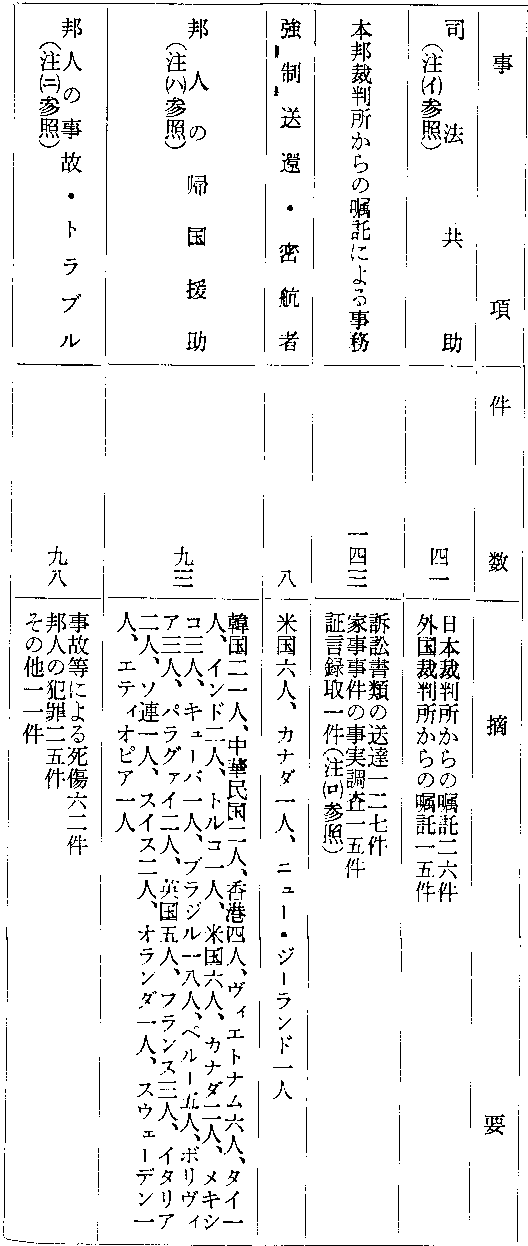 |
注(イ) 司法共助
わが国には「外国裁判所ノ嘱託二因ル共助法」があり、外国から証拠調べまたは書類送達につき、嘱託があれば、この共助法に照らして、相互主義にもとづき、これに応じることができることになっている。わが国からも外国裁判所に嘱託することがある。なお、わが国はスイス等多数の国と司法事務共助を取り決めている。
(ロ) 証言録取
日米領事条約、日英領事条約では、お互いに相手国領事官による証言録取を行なうことを認めている。
(ハ) 邦人帰国援助
海外にある邦人で帰国につき援助を求めてくるものは、大体次のように分類できる。
(i) 病気(特に精神病)、負傷のため、あるいは本人の怠惰によって外国で生活困難におちいった者
(ii) 十分な費用を準備していないため、または無計画に行動したため、所持金・帰国旅費に困っている者
(iii) 盗難、紛失等により帰国旅費を失った者
これら帰国希望者に対する帰国援助に当たっては、外務省は、その者の在本邦留守宅などに本人の困窮現状を知らせるとともに、帰国費送金の説得、送金方法の説明を行ない、帰国者が病気で単独帰国困難な場合などには、肉身者等の渡航を求め、あるいは、同行してくれる者を現地で探すなどしている。
(ニ) 邦人の海外における犯罪
日本人漁船員の殺傷事件、詐欺事件、銀行強盗・窃盗・万引き事件、麻薬所持、古美術品の不法持出し事件等があげられる(そのほか、事件にまでは至らないが、ホテル代や入院治療費などの不払い、不渡り小切手発行も見られる)。
(ホ) 所在調査
所在(消息)調査には、海外にある邦人または日系人の調査と、海外にある者からの本邦在住者の調査とがあり、前者の依頼は、はなはだ多い。最近は、公用地買収手続上必要ということで、これら用地の外国にいる名義人の所在調査依頼も相当数見られる。なん十年も消息を絶っている者や、現地日本人社会と絶縁状態にある者については、特に調査が困難である。
(ヘ) 船舶(特に漁船)および漁船員
海外にある本邦船舶およびその乗組員にかかわる業務の領事事務全般に対する比重はかなり大きい。この業務には、例えば、漁船員の傷病、死亡、暴動により、または台風避難のための外国港湾への緊急入港・避泊につき許可取付け、緊急入域に伴う費用の支払い、補給入港のさいの世話、殺傷事件、衝突事故などの調査がある。
(ト) そ の 他
たとえば、航空機事故、元日本兵所持品の返還申し出、離婚に伴う子供の引取りについての照会、事故死亡者にかかわる補償金問題、引揚者特別交付金や旧勲章年金の受給手続など多岐にわたっている。
わが国の経済発展に伴い、海外に進出する邦人は逐年増加しており、その子女数も一九六七年度には約五、○○○名にのぼっている。
これらの子女の教育は、東南アジア地域の多くでは、日本人学校が設立され、国内に準じた教育が行なわれており、北米、中南米、欧州地域では、現地の学校に就学しながら、さらに国語、算数等を中心とした補習教育が行なわれている。
一九六七年度における日本人学校の所在地、児童生徒数および教師数は第一表のとおりであり、これらの日本人学校に対しては、文部省の協力をえて、文部教官、講師の派遣、校舎借料の負担、教師用参考図書の送付等を行ない、児童生徒に対しては、教科書の配布を行なっている。
また、補習授業校の所在地、児童生徒数および教師数は、第二表のとおりであり、教師に対する謝金の補助を行なうとともに、児童生徒に対する教科書の配布を行なっている。