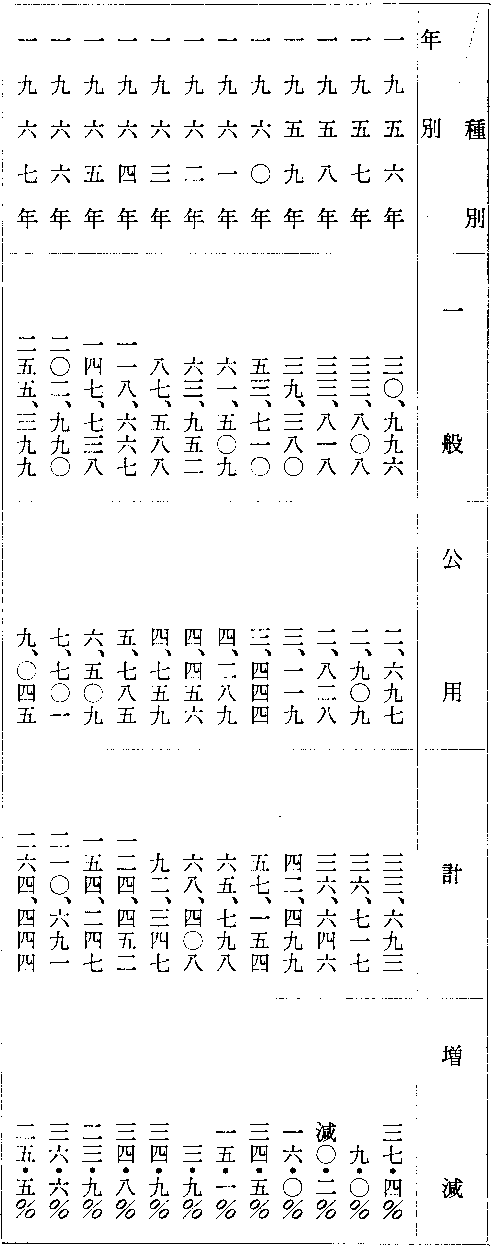
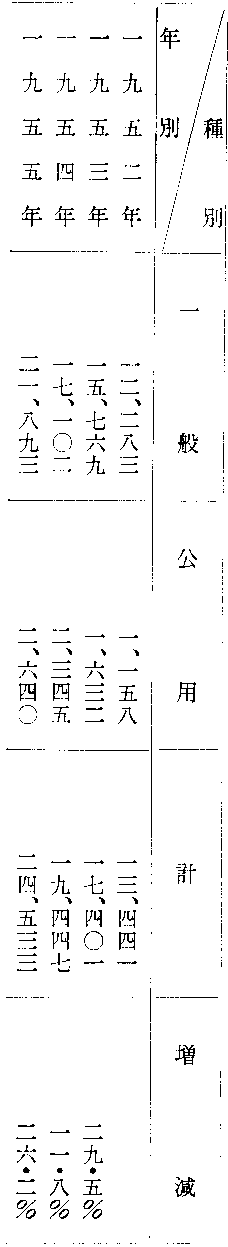
邦人の海外渡航と外国人の入国査証
(イ) 邦人の海外渡航は逐年増加の途をたどり、一九六七年において日本国民の海外渡航に対し外務省の発行した一般、公用旅券の数は二六四、四四四冊に及び、一九六六年の発行数二一〇、六九一冊に比し、約二五%、五三、七五三冊の増加となっている。
(ロ) 旅券の発行数は、一九五一年一二月旅券法が施行せられて以来、一九五八年の発行数〇・二%の減少を除き、各年とも増加しており、殊に一九六三年、翌六四年の業務、観光各渡航の制限緩和措置、一九六六年以降の渡航回数制限撤廃、すなわち業務、観光渡航のいかんを問わず、所要滞在費一回五〇〇米ドル以内で何回でも渡航可能となった頃より著しく増加し、一九六三年以降の旅券発行数は、僅か四カ年で八四六、一八一冊に達し、旅券法施行以来一六年間の総発行冊数一、二六二、九一八冊の六七%を占めるに至っている。一九五二年以降一九六七年まで一六年間の旅券発行状況及増加率は次表の通りである。
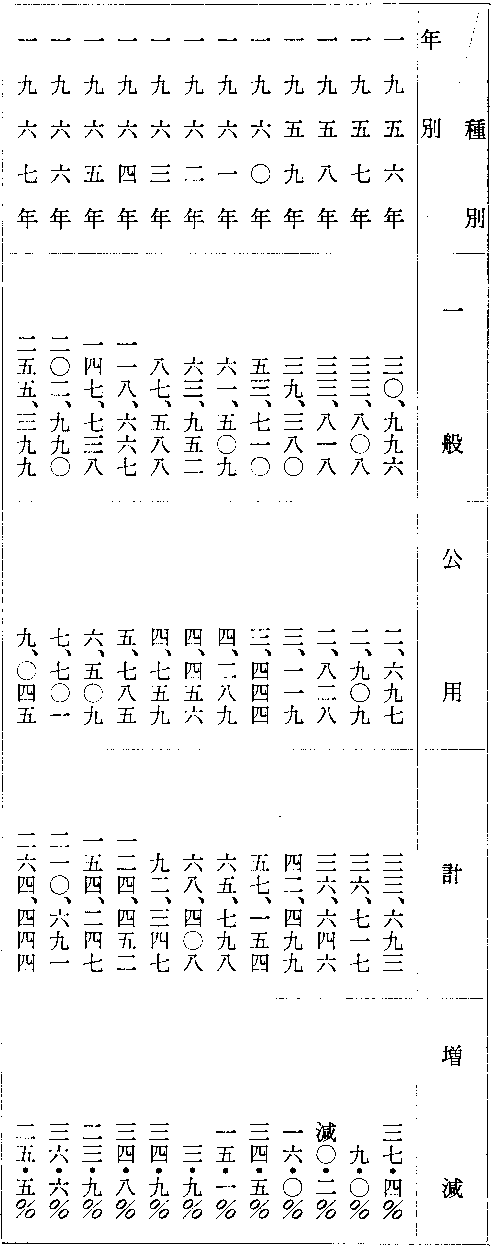 |
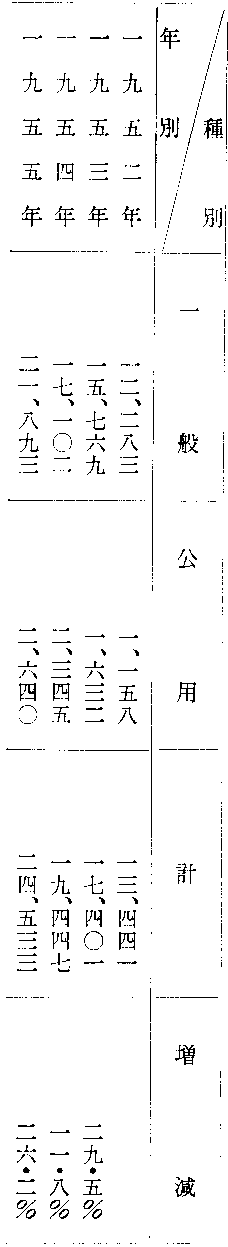 |
注一 本表は外務本省で発行した旅券冊数であって、在外公館で発行した分は含まれていない。
注二 旅券の名儀人は旅券の発行の日より六カ月以内に出国すればよいこととなっているので、旅券発行の年と渡航者の本邦出国の年とは必ずしも一致しない。本表は旅券発行の年を基準として作成した。
(ハ) 旅券発行の時期的傾向をみると、一九六六年も前年と同じく五、六月頃より発行数が上昇し、一〇月が例年になく多く、更に一二月に至り二六、五九三冊と最高の数字を示した。旅券申請が五、六月又は一二月が多いのは、夏期又は冬期休暇を利用する渡航者が多いためとみられる。
(イ) 一九六七年の一般旅券発行状況を渡航目的別に大別すれば、次の通りである。
渡 航 目 的 発 行 百 分 率
経 済 活 動 一〇四、二二五 四〇・八一
文 化 活 動 六、二八四 二・四六
移 (永) 住 七、一〇六 二・七八
観 光 一一七、五〇六 四六・〇二
そ の 他 二〇、二七八 七・九三
計 二五五、三九九
注 その他には興行、家族同伴、呼寄、知人近親訪問、休養、米軍用務、墓参等が含まれる。
(ロ) 観光を目的とする旅券
観光を目的とする旅券の発行数は一九六六年は一般旅券発行数の四四%を占め、経済活動を目的とする旅券発行数を凌駕したが、一九六七年もまた総発行数の四六%を占め、昨年に比し二八、四八四冊増加して、経済活動のための旅券発行数を再度上廻った。この伸長数を年をおってみると、観光渡航の制限が緩和された一九六四年四月以降
一九六四年 二三、〇二六
一九六五年 五四、一一〇
一九六六年 八九、〇二二
一九六七年 一一七、五〇六
と逐年激増しており、一九六七年は大体日本国民一千人のうち一人が国外観光旅行をしたこととなっている。
このような増加は、国民一般の生活に余裕ができた結果、国民の海外渡航への関心がさらに高められたもと思われる。
観光を渡航先地域別にみると、アジア地域一〇六、四七九、北米地域二二、五六六、中南米地城二、四三一、欧州地域一五、四一〇、中近東アフリカ地域五、二五九となっている。又職業別にみると、会社員五九、二六七、商工農業従事者五、七五六、学生一〇、四七八、無職二〇、一〇一、となって他の職業より断然多い。
年令別では若い者が断然多く、二〇代二八、九六二、三〇代、二八、六三〇、四〇代二二、八四七と年代が高くなるほど減少している。女性の渡航者も増加しているが、男性の四分の一程度である。
(ハ) 長期渡航を目的とする旅券
農業、技術移住者、商社等の勤務者、留学生、永住者等一カ国に六カ月以上滞在する渡航者に対する旅券の発給は、一九六七年は二八、七八四冊に及び、一般旅券発行数の約一二%を占めており、これを渡航先別に見ると次の通りである。
北 米 一二、五三〇
欧 州 五、〇四一
ア ジ ア 四、六九一
南 米 三、三四六
中近東・アフリカ 二、四三五
大 洋 州 七四一
右のうち主な渡航先国をあげれば次の通りである
米 国 一一、一一六
ブ ラ ジ ル 一、八七〇
ス ペ イ ン 一、八三五(注)
カ ナ ダ 一、四一四
その他南ア、ドイツ、英、ヴィエトナム、香港、タイの順となっている。
これ等長期渡航者を目的別にみると次の通りである。
勤 務 六、二八一
商 社 用 務 三、九〇二
同 居 六、九〇○
移 (永) 住 四、八五八
再 永 住 二、二四八
留 学 二、四二六
学 術 研 究 一、〇四六
注一 勤務とは支店駐在員事務所等への赴任者をいう。
注二 同居とは家族と同行又は呼寄により渡航する場合をいう。
注三 移住とは政府の計画、呼寄による移住、外国人と結婚しその外国人の国へ移住するため等の渡航をいう。
注四 再永住とはすでに外国に永住権を有するものが再びその国へ渡航する場合をいう。
(附記) 旅券法の特例に関する法律の施行
沖繩に本籍を有し現に沖繩に居住する日本国民が沖繩域外に渡航する場合は、従来琉球列島米民政府から「身分証明書」の発給を受けなければならず、これらの者が日本旅券を取得するためには、いったん本邦又は外国に渡航し外務本省又は在外公館において旅券の発給申請をする必要があった。この点を是正し沖繩住民が沖繩出発時から日本旅券の発給を受けられるようかねてから米国政府と交渉中のところ、一九六六年五月九日東京で開催された第九回日米協議委員会において合意をみ、右沖繩本籍者及び沖繩本籍者以外の日本国民に対し在沖繩の日本政府南方連絡事務所(現日本政府沖繩事務所)において日本旅券を発給することとなった。
これらの事務を実施するため、旅券法の特例に関する法律(昭和四十二年法律第百二十七号)及び関係政令、省令等が制定され一九六七年九月一五日より施行されるに至った。
ちなみに同法施行以来の一九六七年中におげる日本政府南方連絡事務所で発給された旅券発行数は七七〇冊である。
わが国は、後述のとおり二五カ国と査証の相互免除の取決めを結んでおり、これらの国民が、わが国に入国しようとする者、およびすでにわが国に在留していた外国人が法務省から再入国の許可を得ていて一時的に出国した者のほかは、原則として、わが国の出先在外公館から、有効な旅行文書に査証を受けたものでなければ、わが国に入国することはできない。
一九六七年中に、わが国の出先公館において発給した査証の種類別による、件数、および比率は、次のとおりとなっている。
査証の種類別 件 数 比 率
外交、公用査証 二三、六三三 一〇・〇%
通過査証 二〇、二一三 八・五%
入国査証 一九四、〇三九 八一・五%
合 計 二三七、八八五 一〇〇・〇%
さらに、この査証発給数を、発給地域別にみると、アメリカ地域が最も多く、全体の半分に近い四八・三%で、一一五、九二八件であり、次いで、アジア地域が、三六・九%の八七、三六四件であって、これら地域から、来日する外国人の多いことを示している。
また、過去一〇年間の統計は、別表のとおりで、わが国と諸外国との友好関係が緊密化するに従って、人的交流が盛んになりつつあることを示すように、外国人の入国者数は、年をおって、増加してきている。
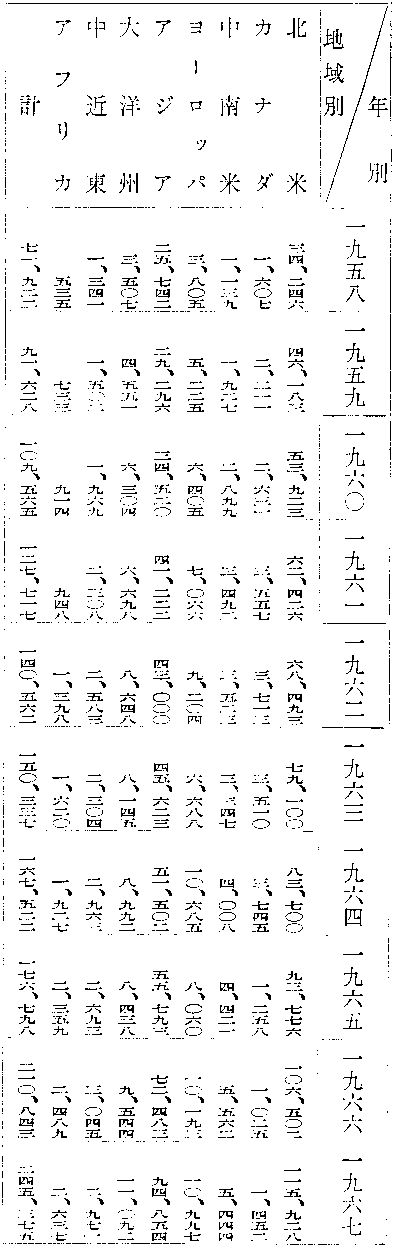
外国人が、観光、視察、その他の目的のため、短期間わが国に滞在しようとするときは、とくに査証を必要としないこととし、相手国政府と相互に免除することを約している国の数は二五カ国となっている。
一九六七年中に、わが国が、相手国と相互に、旅行手続の簡易化を促進するため、一部査証および査証料の相互免除を結んだ国は、ユーゴースラヴィアの一カ国である。
注、査証相互免除取決め国
ドイツ、フランス、テュニジア、イタリア、オランダ、ギリシャ、ベルギー、デンマーク、スウェーデン、ノールウェー、ルクセンブルグ、スイス、ドミニカ、トルコ、オーストラリア、フィンランド、パキスタン、アルゼンティン、コロンビア、連合王国、カナダ、スペイン、アイルランド、アイスランド、ユーゴースラヴィア。
(注) スペインはカナリア群島を基地とする漁業従事者を主とする。