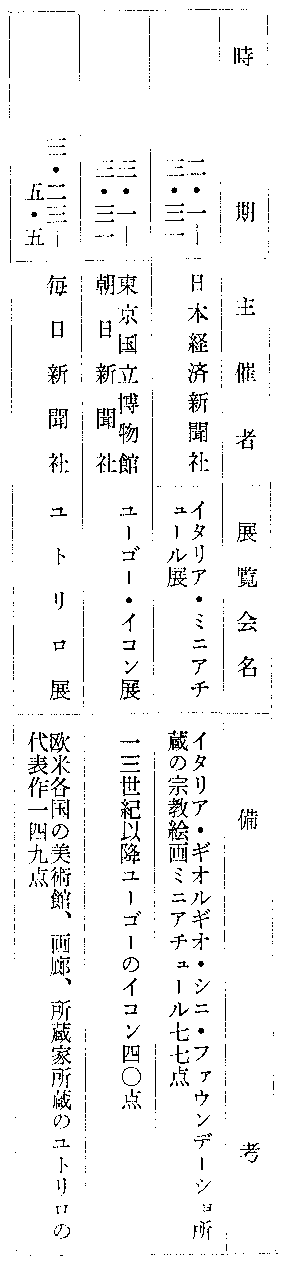
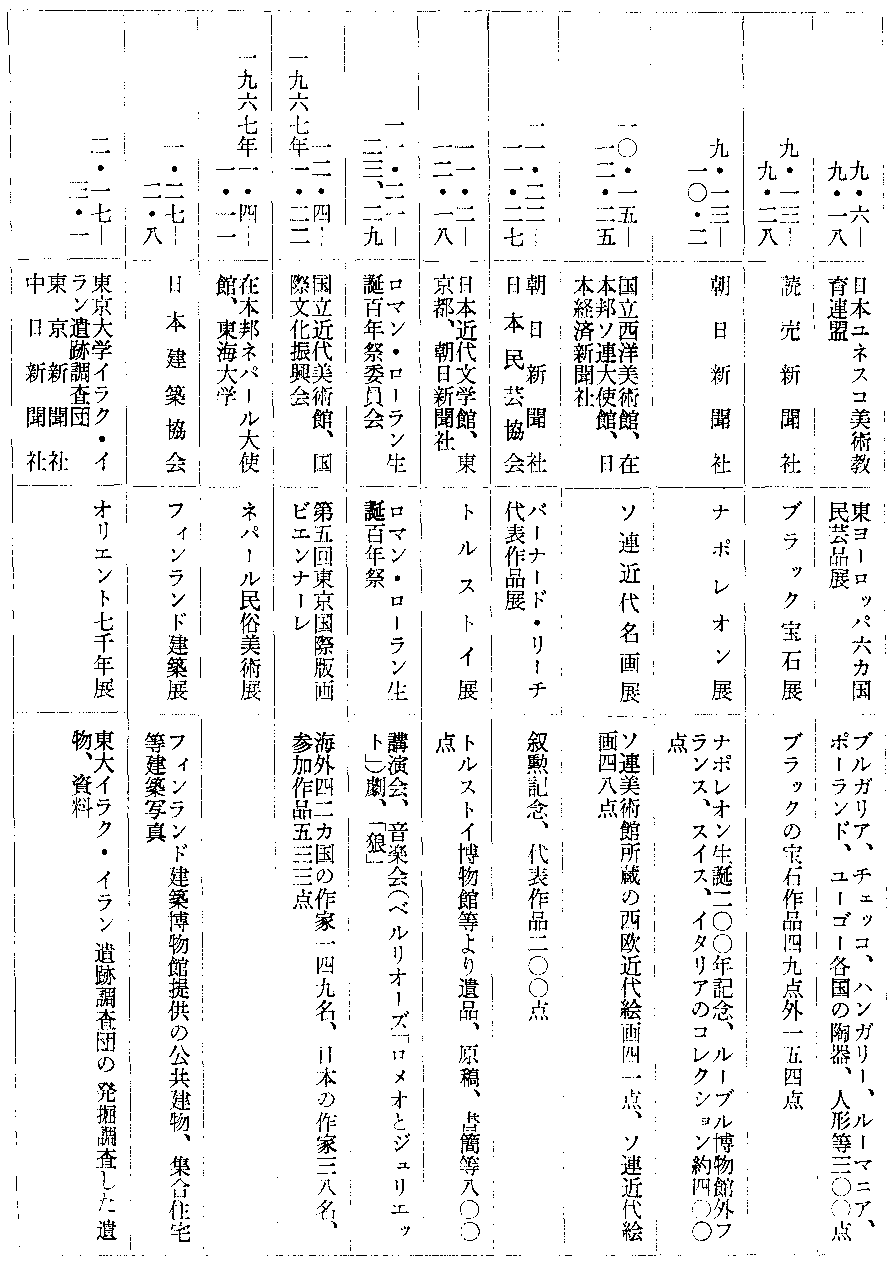
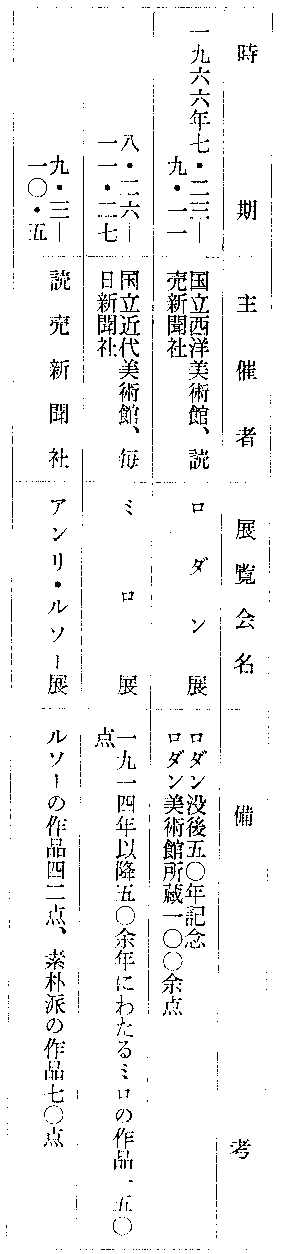
国際文化交流の現状
国際文化交流の目的は、文化を通じ各国民相互の理解と親善を深め、もって世界の平和と文化の向上に貢献することにある。第二次大戦後、各国政府は文化外交を重視し、強力な機構、スタッフと尨大な予算をもって、文化交流事業を活発に展開しているが、これは世界諸国民が戦争の惨禍を再びくりかえさないためには、諸国民間の相互理解がいかに重要であるかを痛感したためであろう。
わが国と各国との文化交流も経済的発展による国力の充実、国際的地位の向上に伴ない益々活発となってきている。
かような文化交流事業には、政府によるものと、民間によるものとがあるが、元来、文化交流はその性質上、まず、広く民間の自主と創意とによって行なわれるべきものであり、したがって政府としては、まず第一に民間の創意によるこれら事業を奨励し、できるかぎりこれに便宜を与えてその拡大をはかることを方針としている。
他方、日本文化の紹介には、極めて有意義であっても民間の事業としては実施困難な事業もあり、これについては、あるいは政府の事業として、あるいは関係補助団体の事業として実施することとしている。
戦前、日本はハンガリー、ドイツ、イタリア、ブラジル、タイ、ブルガリアとの間に文化協定を結んでいたが、これらの協定はいずれも第二次大戦の勃発によってその効力を失ったか、または効力が停止された。
戦後、日本は次の一一カ国と文化協定を締結した。
(1) フ ラ ン ス (一九五三年一〇月三日発効)
(2) イ タ リ ア (一九五四年一一月二二日発効)
(3) タ イ (一九五五年九月六日発効)
(4) メ キ シ コ (一九五五年一〇月五日発効)
(5) イ ン ド (一九五七年五月二四日発効)
(6) エ ジ プ ト (一九五七年七月一五日発効)
(7) ド イ ツ (一九五七年一〇月一〇日発効)
(8) パ キ ス タ ン (一九五八年一〇月二一日発効)
(9) イ ラ ン (一九五八年二月二〇日発効)
(10) 英 国 (一九六一年七月八日発効)
(11) ブ ラ ジ ル (一九六四年一一月一七日発効)
これらの文化協定は、締結国政府が両国間に行なわれる各種文化交流事業に対して便宜を与え、また、これを奨励することを規定したもので、協定により多少相違はあるが、その概要はつぎのとおりである。
(1) 書籍、講演、演劇、展覧会、映画、ラジオなどによる文化の相互理解の増進に対し、便宜を与える。
(2) 学者、学生、その他文化活動に従事する者の交換を奨励する。
(3) 相手国国民の修学・研究・技術修得に対し、奨学金その他の便宜を与える方法を研究する。
(4) 大学などで、相手国の文化に関する講義の拡充および創設を奨励する。
(5) 相手国の学位および資格をたがいに認めるように、その方法および条件を研究する。
(6) 相手国の文化機関の設立および運営に便宜を与える。
(7) 相手国国民の博物館、図書館の施設の利用に対して便宜を与える。
(8) その他、協定によっては、文学および美術の著作物の翻訳または複製の奨励、文化団体の間の協力の奨励、国際的運動競技の奨励などを規定したものもある。
(イ) 国際文化振興会(略称KBS)
国際文化振興会は、国際間の文化交流、特に日本文化の海外紹介をはかり、諸国民との相互理解を助け国際親善をたかめることを目的として、一九三四年(昭和九年)四月創立された団体であるが、近年欧米をはじめとし世界各国の文化活動が極めて盛んとなり、わが国としても、国際文化交流事業を強化拡充する必要が痛感されてきたので、外務省は、これに対処するため、関係省と協力して、同会に対する政府補助金の増大、民間からの積極的協力の確保およびこれに伴なう機構の整備と事業内容の拡充に努力し年々その実を挙げつつある。
一九六六年度に、国際文化振興会が行なった事業は、美術、芸能および国情紹介等の多岐にわたり、(イ)欧州においては、「富岡鉄斉展」、「第三三回ヴェニス・ビエンナーレ展」、(ロ)中近東においては、「日本学童生活紹介写真展」、(ハ)アフリカにおいては、「日本国情紹介写真展」、(ニ)アジアにおいては「日本舞踊団の公演」、(ホ)豪州、ニュー・ジーランドにおいては、「仙崖展」、(ヘ)中南米においては、「日本建築写真展」、(ト)北米においては、「日本古典音楽紹介展」等の開催または参加を行ない、一方、国内では、「第五回東京国際版画ビエンナーレ展」、「第五回国際アマチュア小型映画コンクール」を主催したほか、随時、在京外交団および在留外国人に対し、「能、狂言」、「古典演劇」の紹介、文化講演会の開催等極めて多彩な活動を行なった。
また、同会が出版した文化資料としては、「日本研究基本書目解題(英文)」シリーズとして、「文学篇」を、「日本文化叢書(英文)」の「日本経済入門」篇と「日本の思想」編を、さらに、「日本美術の伝統(英文)」と、「日本文化の手引(伊文)」を出版したほか、定期刊行物として月刊「国際文化(邦文)」、隔月刊「KBSブレティン(英文)」等を発刊して日本文化の紹介に努めている。
なお、国際文化振興会は、海外との接触が拡大し、わが国の実情を正確かつ直接紹介する必要性がたかまりつつあるのと、同会としても現地の文化事情を把握することが事業計画立案上必要であるので、一九六一年九月以来ニュー・ヨークに、また、一九六六年一月にはロンドンに、一九六七年一月にはブエノス・アイレスに、それぞれ駐在員各一名を派遣常駐させ、現地関係方面との緊密な接触を保ちながら啓発、調査等の活動を行なっており、後述の在ローマ日本文化会館の運営とともに、海外における文化交流活動を積極化せしめている。
(ロ) 国際学友会
日本に来る外国人留学生は日本語を解さず、また、日本人と風俗習慣、宗教、食生活などをいちじるしく異にしていることから、学業、生活などの点で、とくに来日当初は困難を感ずる者が多い。国際学友会は、これら留学生に宿舎と大学進学前の準備教育を与えることを目的として、一九三五年一二月、財団法人として創立されたものである。戦後、同会は、国費留学生(日本政府が招致し、奨学金を給与しているもの)、私費留学生を問わずすべての留学生を前述の宿舎に受入れて世話をしてきた。しかし、一九五七年、文部省の外郭団体として日本国際教育協会が発足し、国費留学生の受入団体となったので、学友会本部の国費留学生は同協会の宿舎に転宿し、現在、学友会本部は専ら私費留学生を収容している。
宿舎は、現在、東京本部だけで収容能力一六五名に達しているが、一九五六年には収容能力六〇名の関西支部が大阪市北区に、さらに六五年四月から京都に収容能力約五〇名の京都支部が開設された。
国際学友会東京本部は、宿舎、食堂を設けているほか、日本語学校も運営している。日本語学校は、日本で高等教育または技術研修を受けようとする外国人留学生(学友会在泊者には限らない)に対し、一年乃至一年六カ月を期間として日本語を教授し、併せて基礎的な日本事情を知らせることを目標としており、毎年四月、一〇月の二回新規学生を受入れている。そのほか、大学進学希望者に対しては、数学、理科、社会などの基礎学科も教授しており、これら課程の修了者には進学を斡旋している。同校の学生定員は二九五名である。
(ハ) 出版文化国際交流会
日本と外国との相互理解、友好関係の増進に寄与する出版物の交流を計る目的で昭和二七年に設立され、活発な活動を続けている。
一九六六年度において国内では、優秀な日本文化紹介図書に対して外務大臣賞その他の国際出版文化賞を創設し第一回表彰式を行なったほか、各地で世界児童図書展等を開催した。海外では、フランクフルト国際図書展、香港およびシンガポールにおける日本図書展、東アフリカ図書展に図書を出品する等の活動を行なった。
(イ) 在ローマ日本文化会館
在ローマ日本文化会館は、日伊文化交流のため日本文化の紹介を行ない、かつ、イタリアの学術文化の研究に資することを目的として、外務省が一九五九年から約三年の歳月を費やして建設したもので、一九六二年一二月開館した。会館は平安朝様式の建築で日本庭園が隣接して造られており、その醸成する日本的雰囲気はローマ市民の関心を集めている。同会館が一九六六年度に行なった主な事業は次のとおりである。
(i) 展 覧 会
町春草書道展
富岡鉄斉展
日本現代工芸展
(ii) 講 演 会
日本文化の一面 (大阪工大教授森暢)
日本工業の一面 (東工大名誉教授植村琢)
千利休とその思想 (建築家ギー・ドクールネール)
尾形光琳 (東京国立博物館千沢槇治)
日本と日本における科学研究 (ローマ大学教授キウルコ)
富岡鉄斉について (ローマ大学数授ジュリオ・アルガン)
(iii) 座 談 会
日伊両国の現代美術の傾向について (美術批評家中原佑介ほか六名)
なお、前記催物のほか、日本語講習会、日本映画祭、在欧邦人音楽家演奏会、点茶、生花の実演等多彩な事業を行なった。
(ロ) パリの大学都市日本館
パリ大学都市日本館は、通称薩摩会館ともいわれ、一九二七年薩摩治郎八氏によってパリ大学に寄贈されたものであるが、フランス留学中の日本人学生に対する宿舎の提供を主たる任務とし、また、構内に日本関係の図書を蒐集して日本研究に便宜を与えている。外務省は、従来から民間有識者の中から館長を推せんして派遣しており、また同館建物の内部修理費などに対し、援助を行なっている。
国際文化交流事業のうち、美術工芸関係の展覧会は、もっとも頻繁に行なわれており、美術工芸を通じての国際間の理解と親善の増進に貢献している。
(イ) 日本で開催された外国美術展等
日本で開催される外国美術展は、新聞社、美術館の主催するものが多いが、外務省も、その開催について側面より協力している。
一九六六年度において開催された外国美術展は次のとおりであるが、特に「ソ連国立美術館近代名画展」が開催されたことは注目に値する。
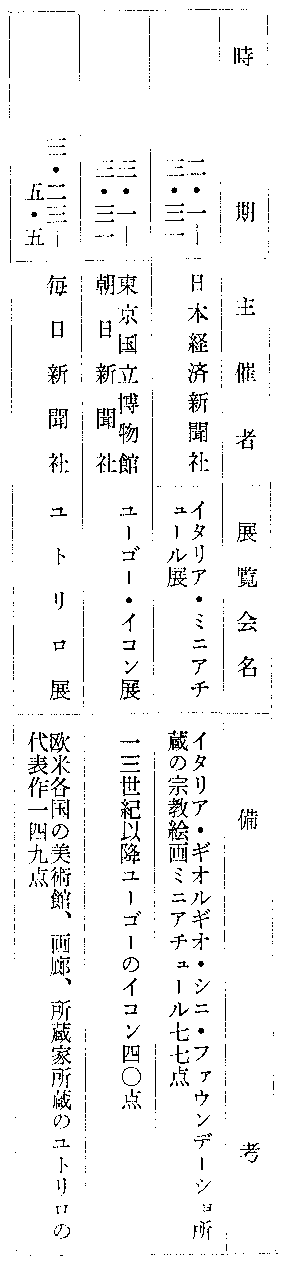 |
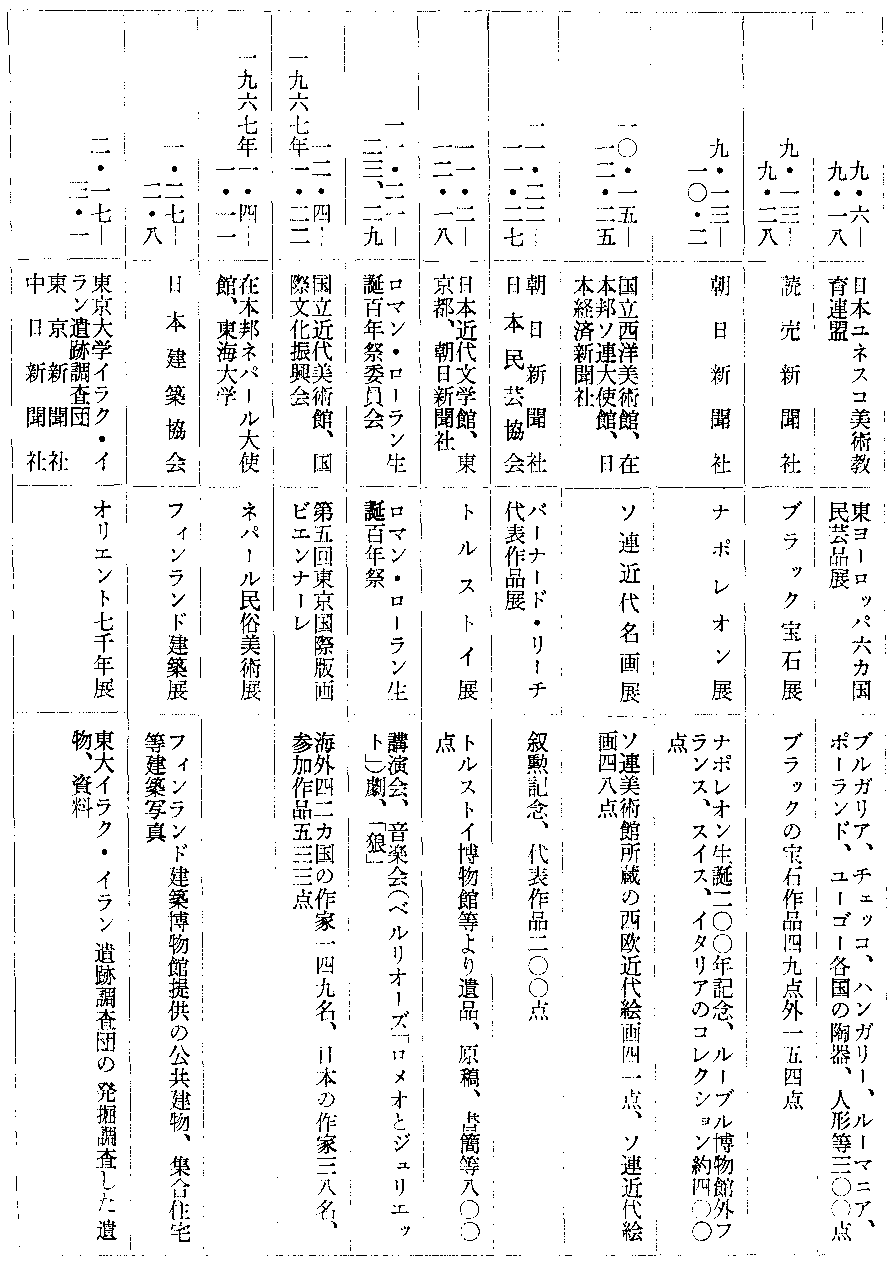 |
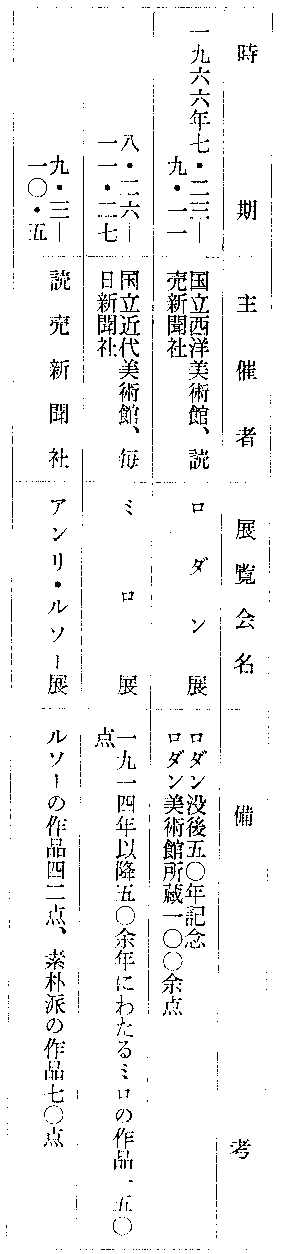 |
(ロ) 海外における日本美術工芸展
諸外国における日本の美術工芸その他の展覧会は、各国において多大の反響をよんでおり、日本文化の紹介に貢献している。
一九六六年度に開催された日本関係の展覧会は次のとおりである。
(i) 美術展関係
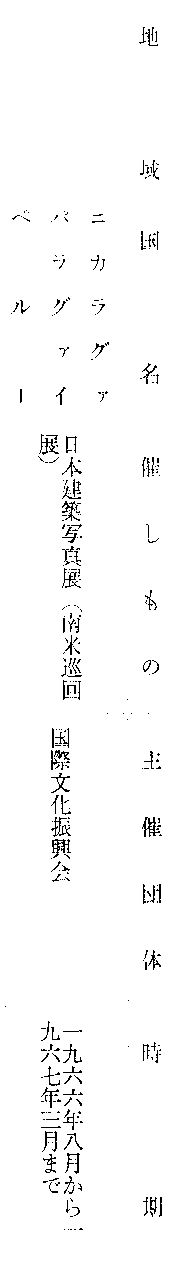 |
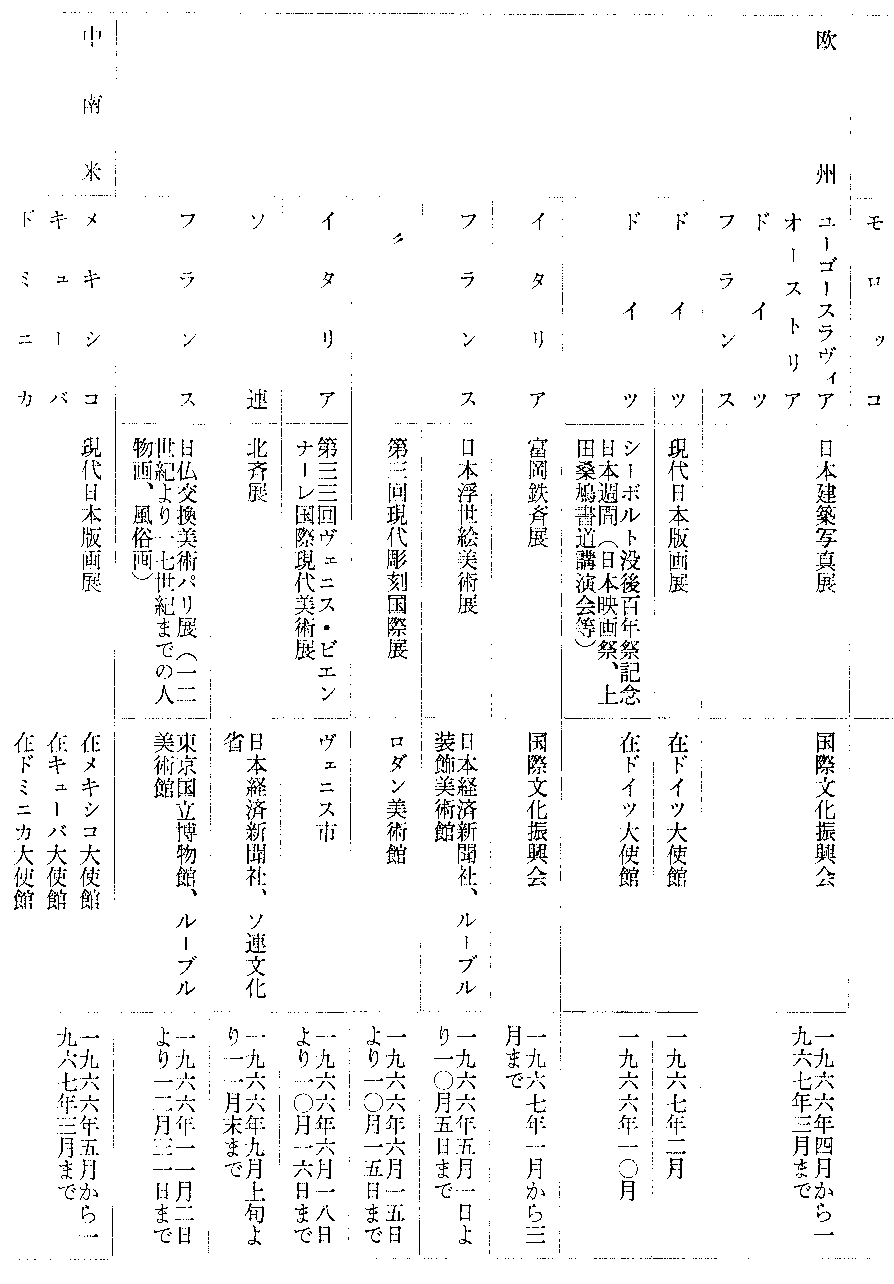 |
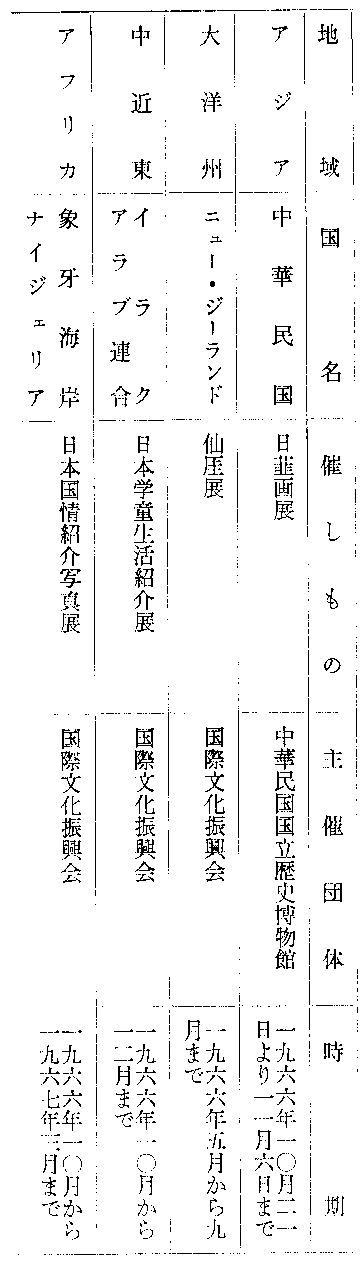 |
(ii) 工芸展関係
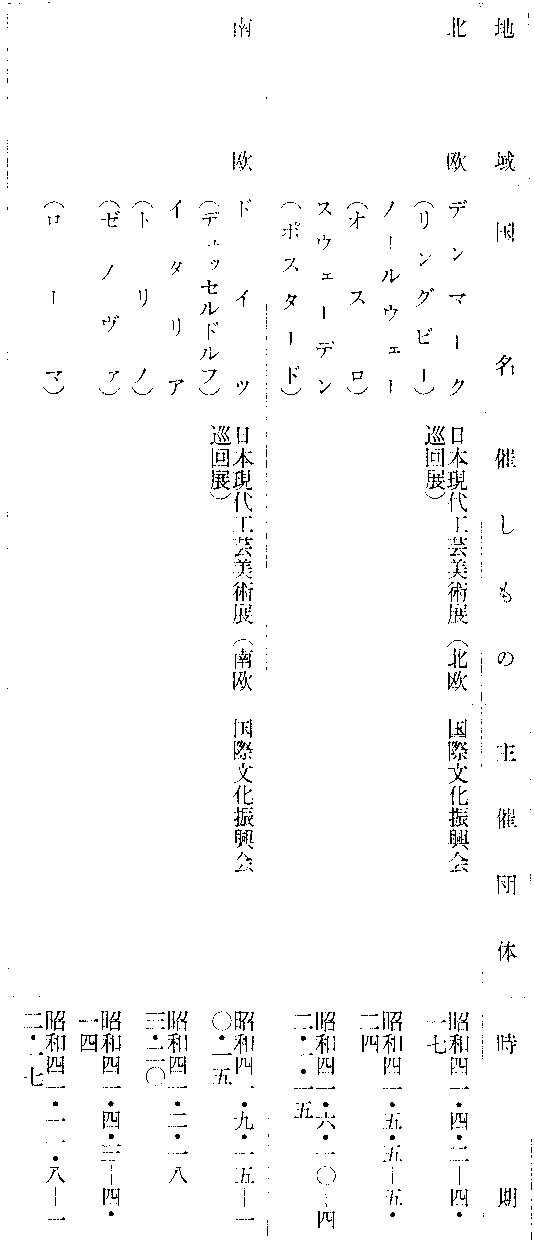
優秀な日本映画の海外における上映が、日本の文化・国情等に対する諸国民の正しい理解と認識に役立つことはいうまでもない。かような観点から、外務省では、日本文化紹介に適当と認められる映画を、地域による特殊性を考慮しつつ、諸外国にまわして在外公館主催で映画会を開催している。
また、権威ある国際映画祭に対する日本映画の参加、日本における外国映画祭の開催などに対しても種々の支援をしている。
一九六六年度における在外公館主催による日本映画会、海外の映画祭に対する日本映画の参加および、日本における外国映画祭の開催状況は次のとおりである。
(イ) 在外公館主催による海外での日本映画会(一九六六年四月から一九六七年三月まで)
(i) 劇 映 画
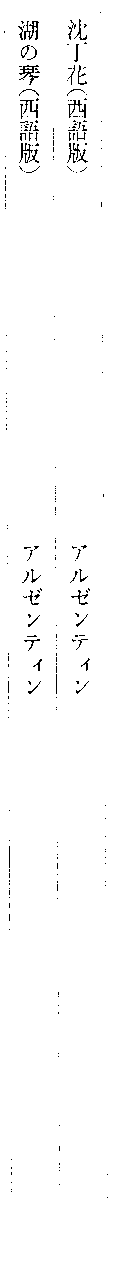 |
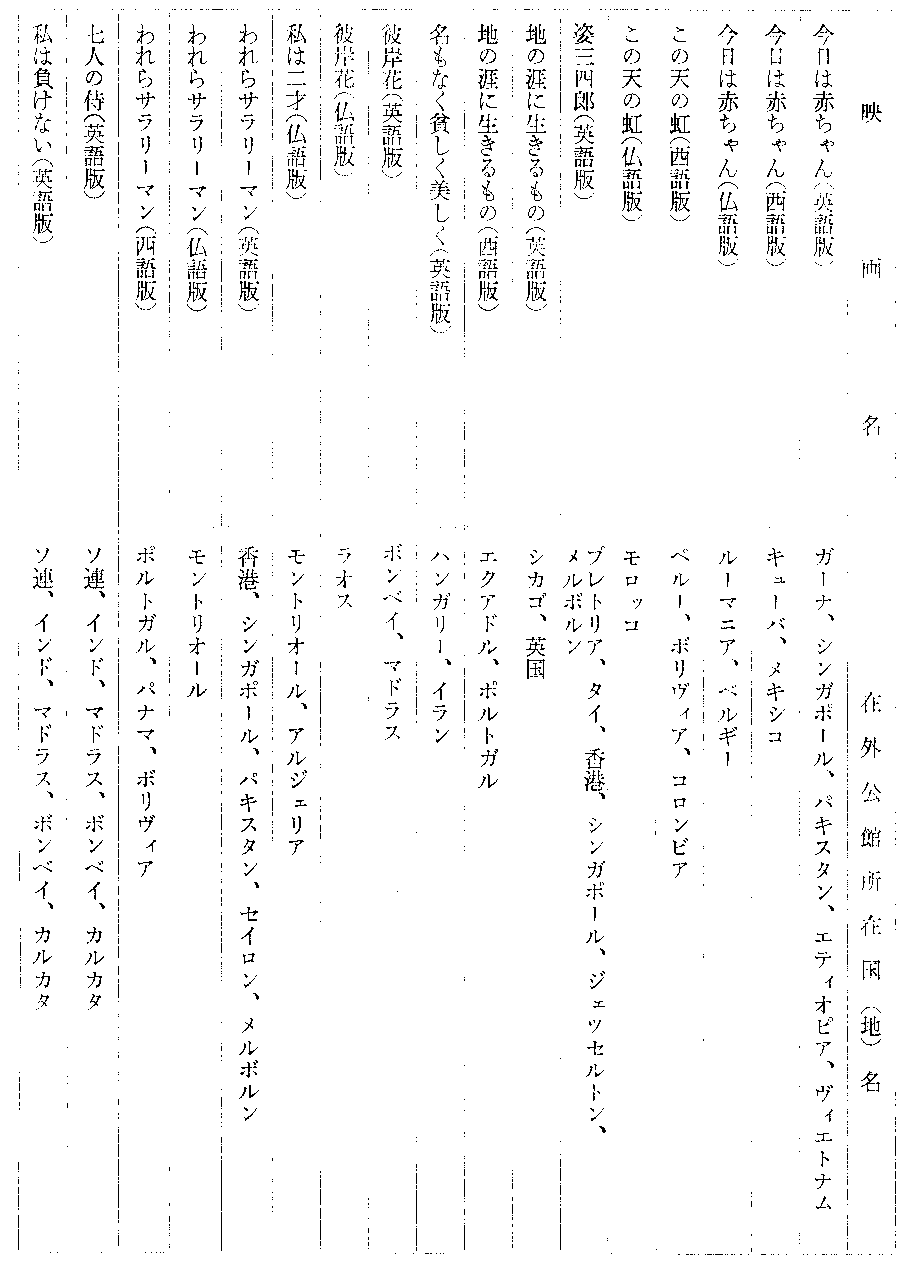 |
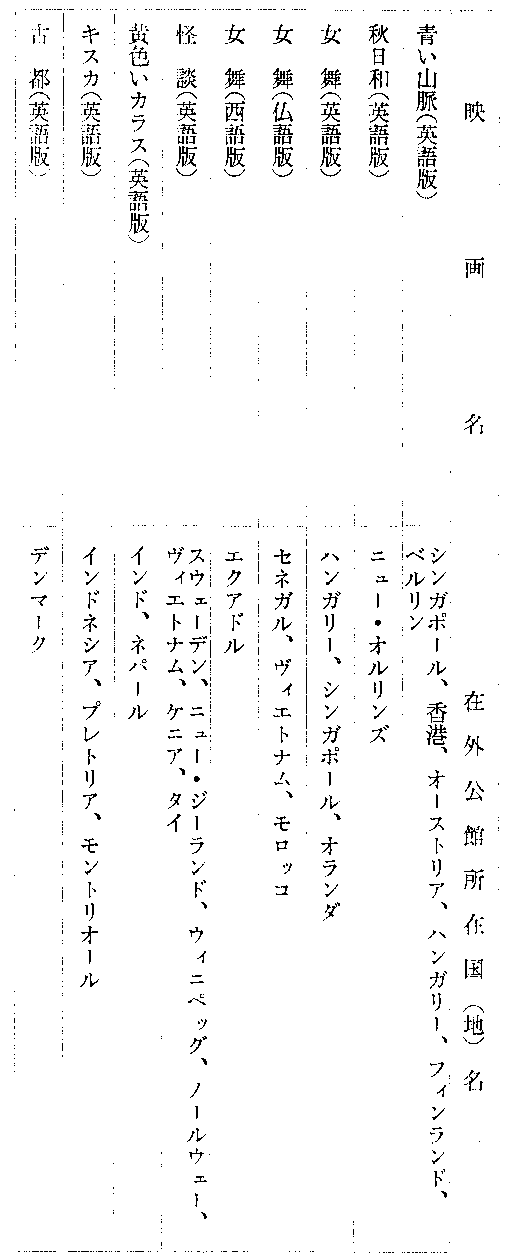 |
(ii) 文 化 映 画
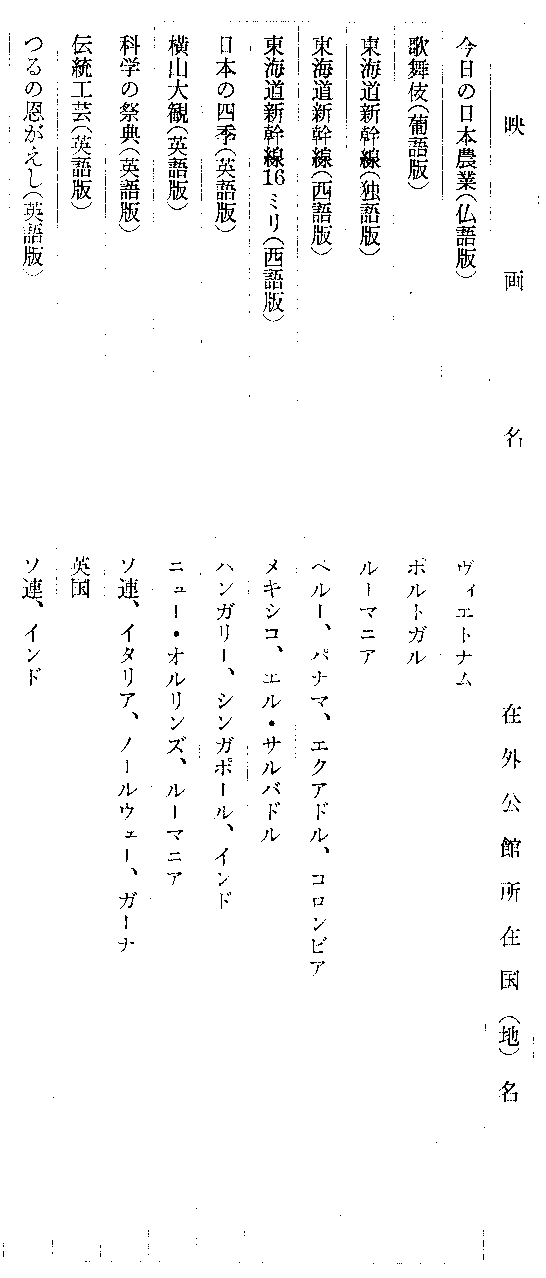 |
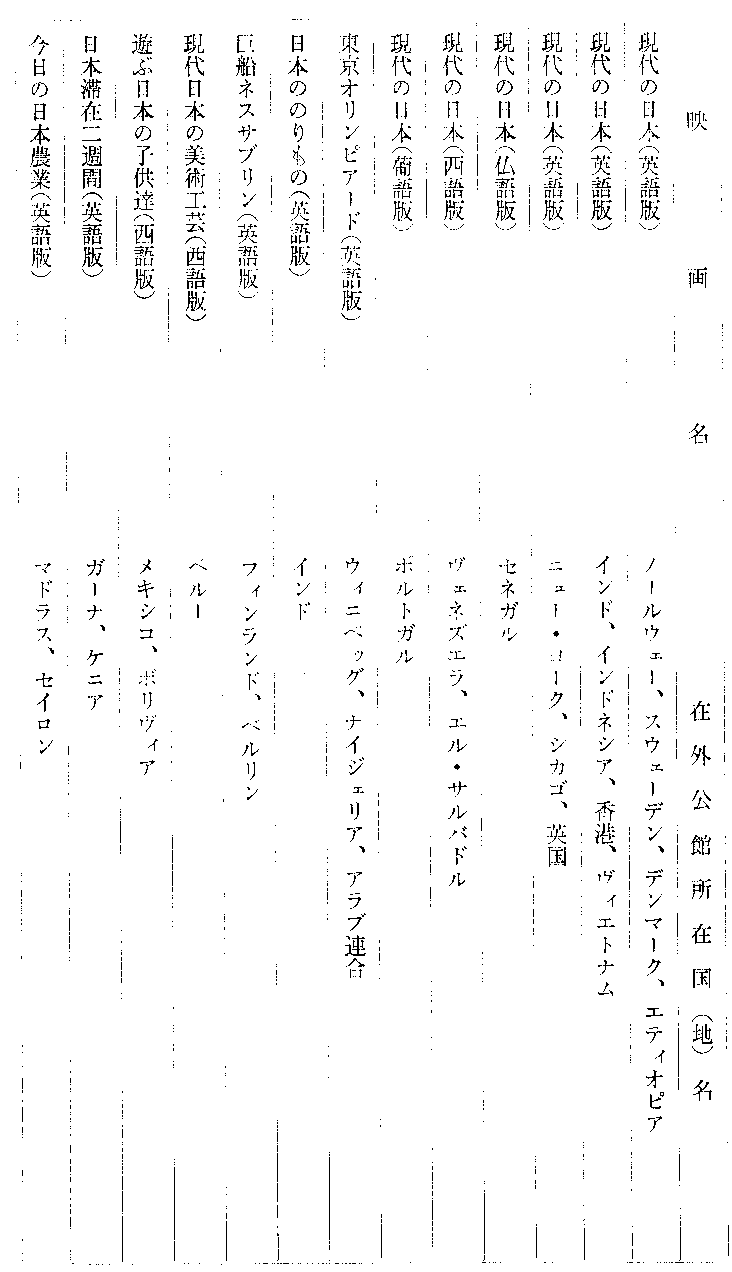 |
(ロ) 海外における映画祭に対する参加
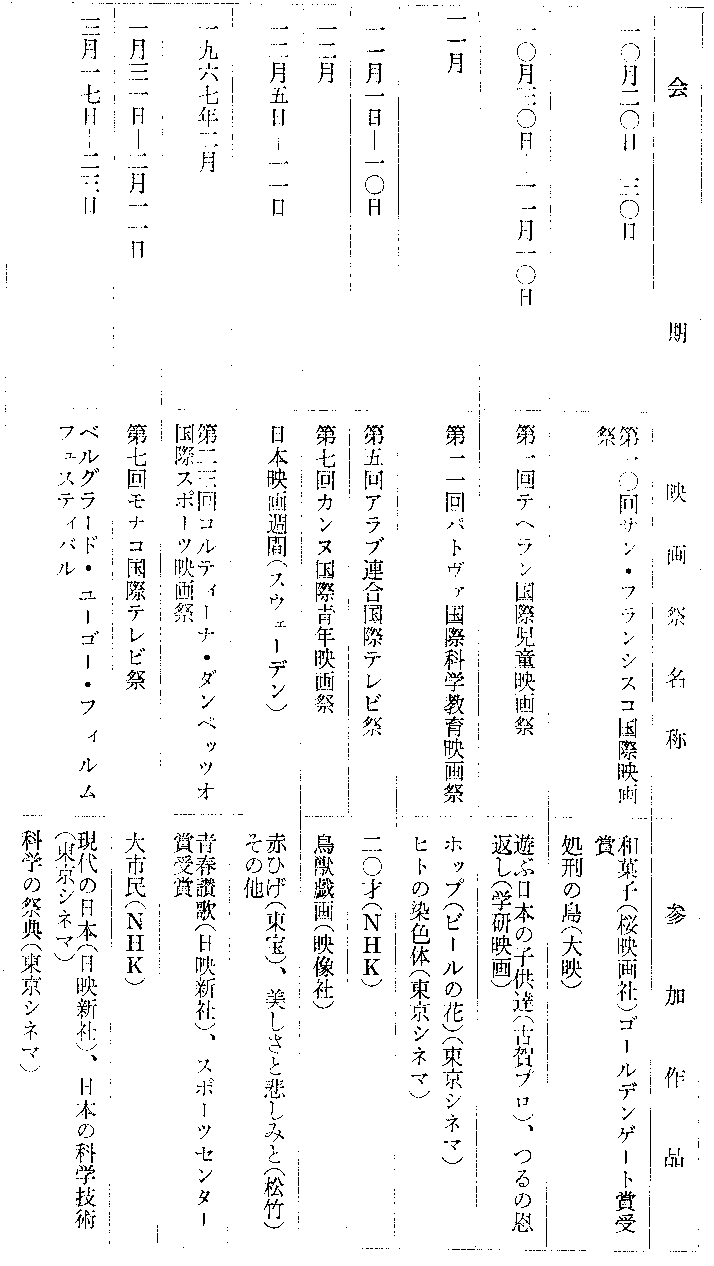 |
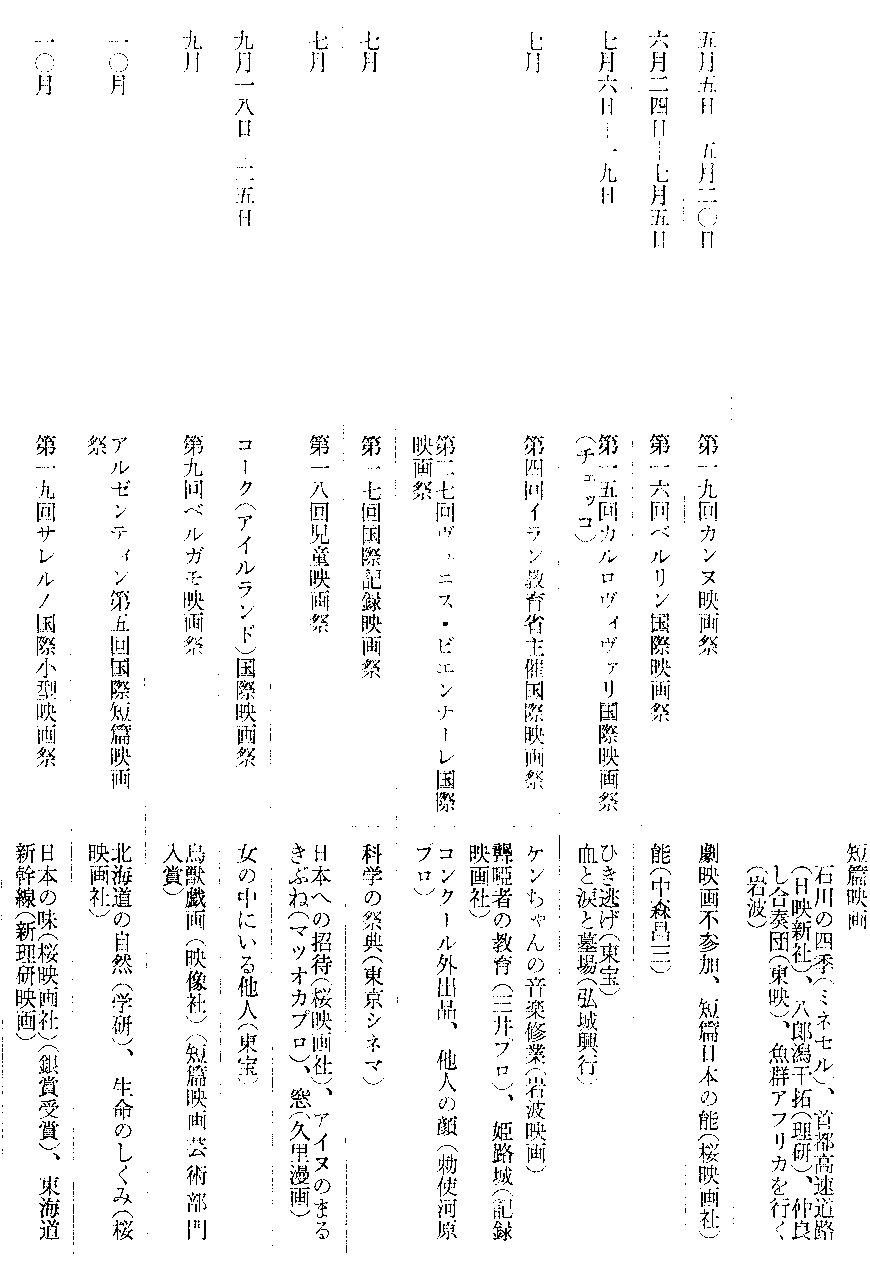 |
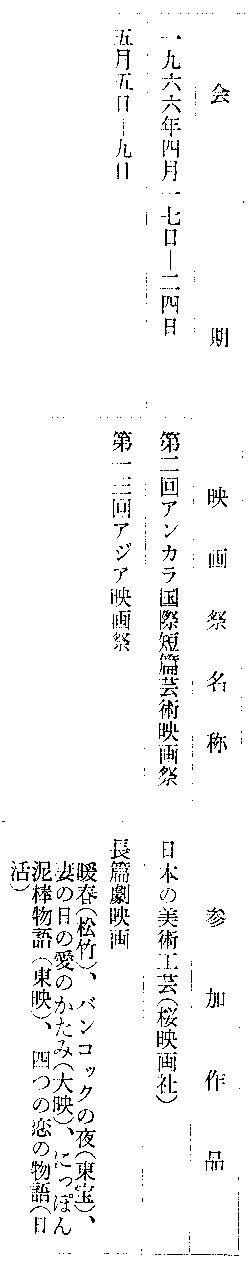 |
(ハ) 国内で開催された外国(国際)映画祭
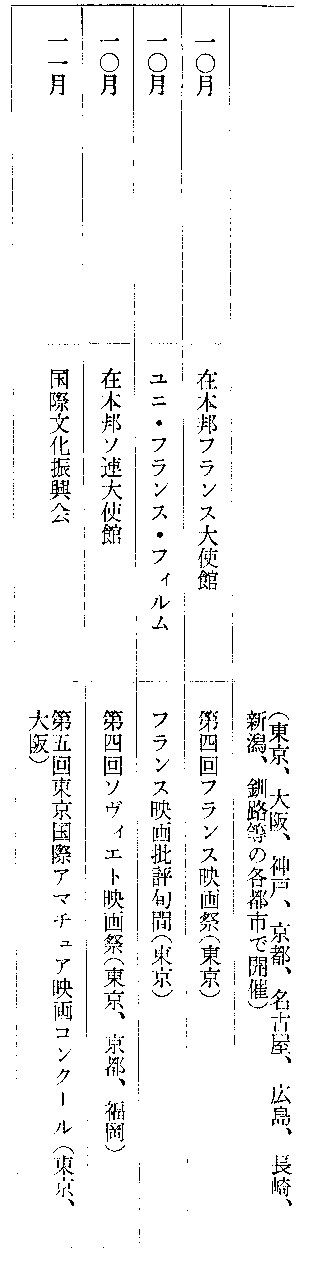 |
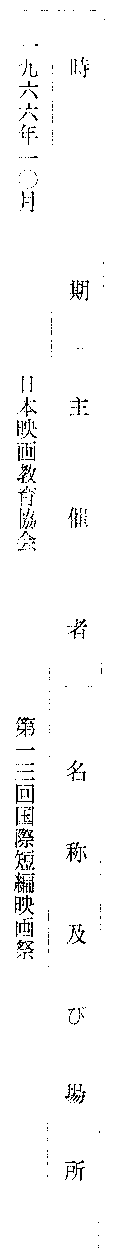 |
図書も文化交流の重要なメディアであるが、外務省では、(イ)在外公館に図書を備えつけ一般の利用に供する、(ロ)外国の大学、図書館等へ日本の図書を寄贈する、(ハ)日本図書展の開催、国際図書展への参加に協力するなどの方法によって、図書を通じての日本文化の紹介に努力している。
一九六六年度における図書寄贈および図書展への参加状況は次のとおりである。
わが国の文化人を諸外国に派遣してわが国文化に関する講演および実技指導を行なわせしめること、および諸外国の文化人を日本に招へいして、わが国の文化に直接ふれさせる機会を与えることは、わが国の文化を広く海外に紹介する上において極めて有効適切な方法であることは明らかなことであり、外務省は従来からこの趣旨にそって、文化人の派遣、招へいを実施して各国との文化交流および親善関係の促進に尽力してきた。
一九六六年度の実績はつぎのとおりであるが、外務省ではこれ以外に外国政府、学校、学術・民間団体などが実施する交流事業または日本文化の海外普及事業に対してもできる限りの便宜を図っている。
(イ) 文化人派遣
一九六六年度に実施した文化人派遣の内訳は、生花六件一二名、柔道五件一〇名、書道一件一名、体操一件二名、音楽(箏曲)一件三名、茶道一件二名、庭球一件二名および学術講演(主として日本の庭園および美術に関するもの)六件七名であって、合計三九名の文化人が東南アジア、欧州、アフリカ、中南米、米国、カナダ、中近東、大洋州の各地域の八一カ国へ派遣された。
(ロ) 文化人招へい
一九六六年度においては、フランス、オーストリア、メキシコ、アイルランド、フィリピン、香港、マレイシア、タイ、ニュー・ジーランド、インドネシア、オランダの諸国から合計一一名の文化人を招へいし、主として東京はじめ京都、奈良等の各地において日本文化の研究のほか、学者関係文化人と交歓せしめた。
一九六六年度の招へい実績はつぎのとおりである。
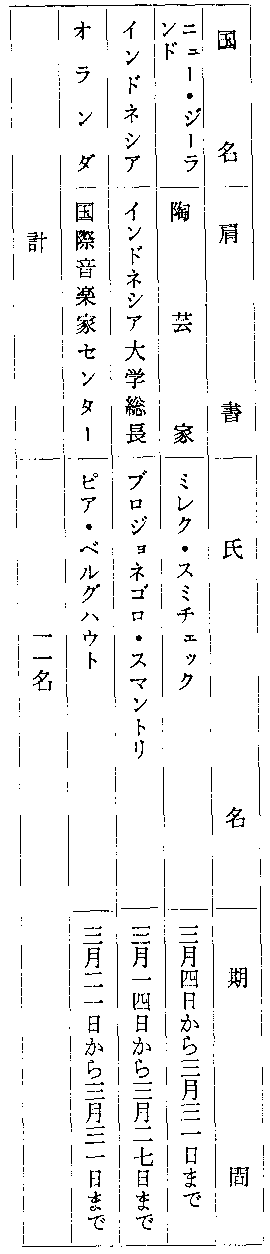 |
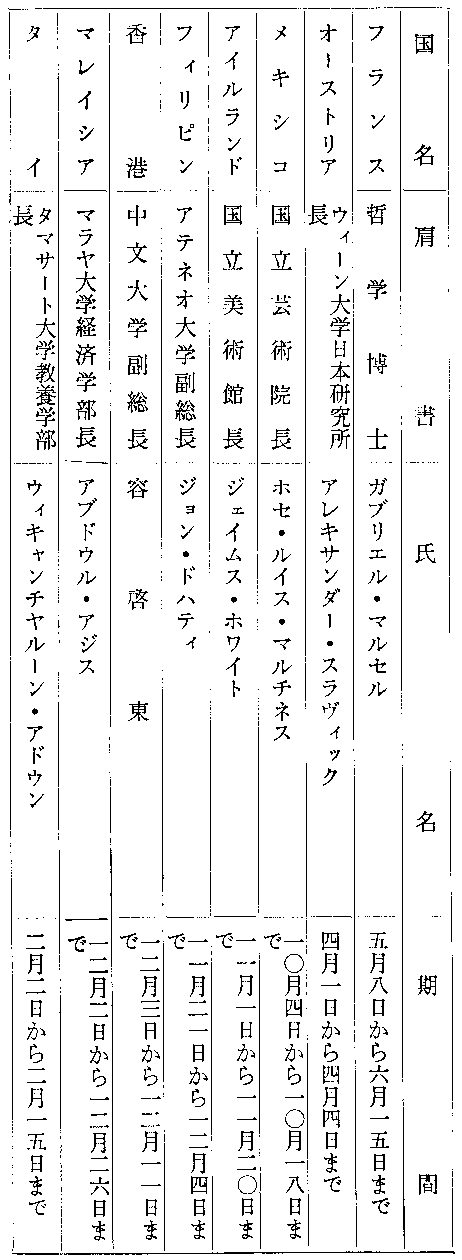 |
(ハ) 日ソ間の学者・研究員の交流
在ソ連邦日本国大使館と、ソ連邦対外文化連絡国家委員会との合意に基づき、一九六六年度においては、長期(一〇カ月)の学者交換と短期(二カ月)の研究員の交換が次のとおり実現した。
(i) ソ連側派遣研究員及び日本における受入先
ドルジーニン・ゲナディ・ヴェミーリヴイッチ(モスクワ大学法学部研究員)東京大学法学部
ヴィノグラードフ・ヴァレンタイン・ヴァミーリヴイッチ(モスクワ大学法学部研究員)東京大学法学部
クモフ・ニコライ・ヴェラミーリヴイッチ(アジア諸民族研究所研究員)東京大学文学部
ネフェドフ・ボリス・コンスタンティノヴィッチ(ゼリンスシー有機化学研究所研究員)東京工業大学工学部
バラーノフ・ゲナディ・ドミトリヴィッチ(モスクワ電子工学機械研究所研究員)東京工業大学工学部
パミンツェフ・イゴール・イヴァノヴィッチ(モスクワ力学工学研究所研究員)京都大学工学部
(ii) ソ連側派遣学者及び日本における受入先
アントロポフ・レフ・イヴァノヴィッチ(キエフ工科大学工学教授)北海道大学腐蝕研究所
ミハイロフ・イゴリン・ジョルジェヴィッチ(レニングラード大学物理学教授)東京大学理学部
ドラジレフ・ミカイル・サムイロヴィッチ(モスクワ大学経済学部教授)東京大学経済学部
(iii) 日本側派遣研究員及びソ連における受入先
原田竹治(農林省農業技術研究所研究員)モスクワ農業科学アカデミー
細川厳(科学技術庁航空宇宙研究所研究員)モスクワ大学理学部
橋本宏(在ソ連邦日本国大使館外交官補)モスクワ大学経済学部
三橋秀方(在ソ連邦日本国大使館外交官補)モスクワ大学歴史学部
松尾新一郎(京都大学工学部教授)モスクワ大学地質学部
山下香男里(北海道大学文学部講師)モスクワ大学言語学部
(iv) 日本側派遣学者及びソ連における受入先
水上茂樹(東京大学医学部助教授)ソ連科学アカデミー研究所
金沢武(東京大学工学部教授)モスクワ機械研究所
慶井富長(東京工業大学理工学部教授)モスクワ大学化学部
酒井寛一(国立遺伝学研究所応用遺伝部長)モスクワ大学農学部
近来青少年・学生団体等の国際的交流が増加しつつあり、外務省では、これらの団体に対し必要な助言と指導を与えてきているが、特に総理府が実施している日本青年海外派遣団に対しては、関係在外公館を通じて日程作成等につき協力している。
(イ) 青少年、学生団体の海外訪問
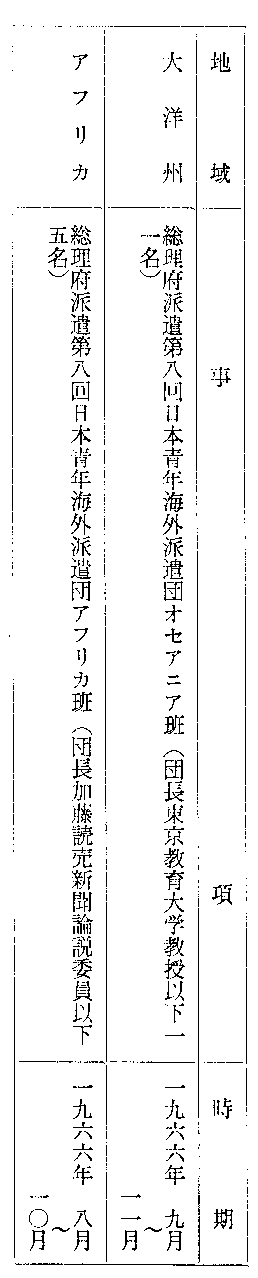 |
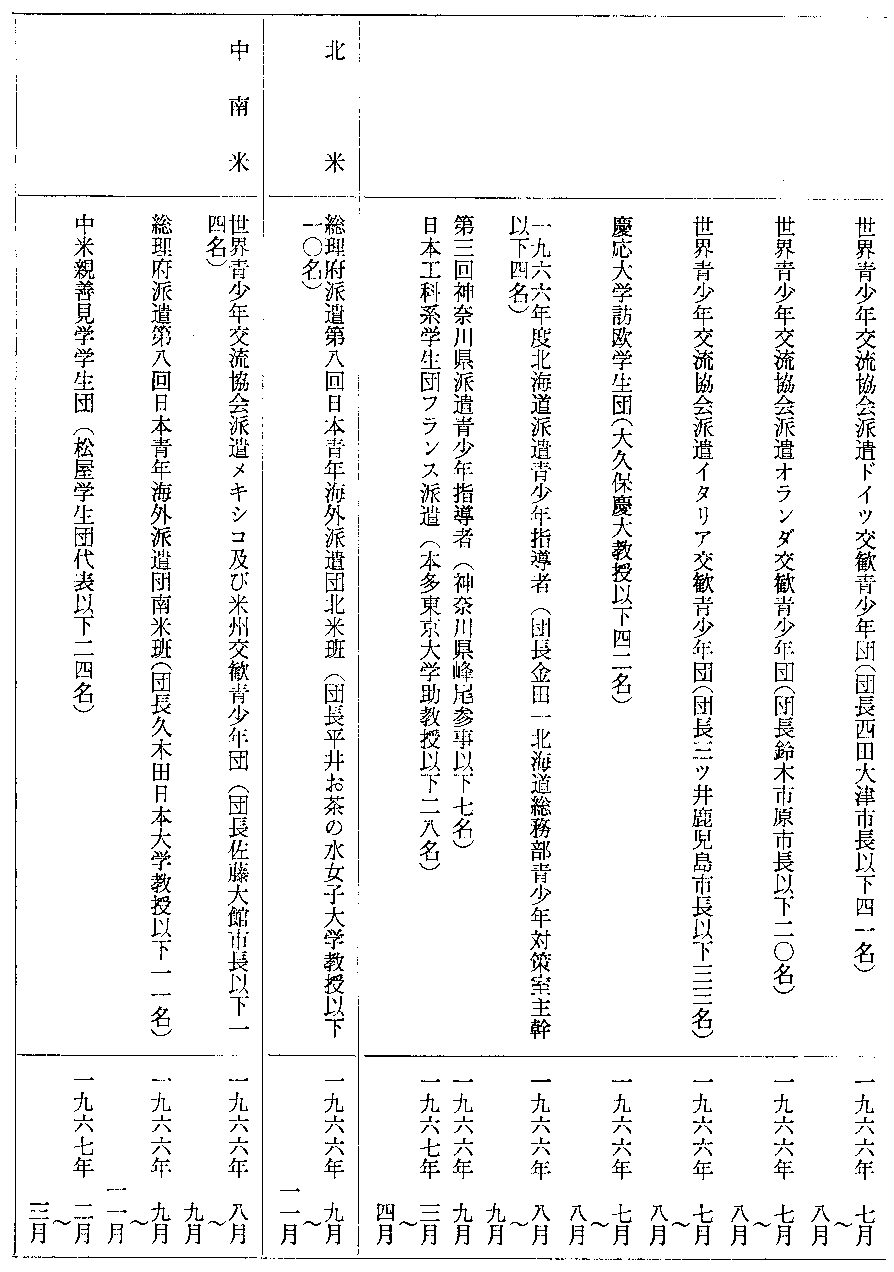 |
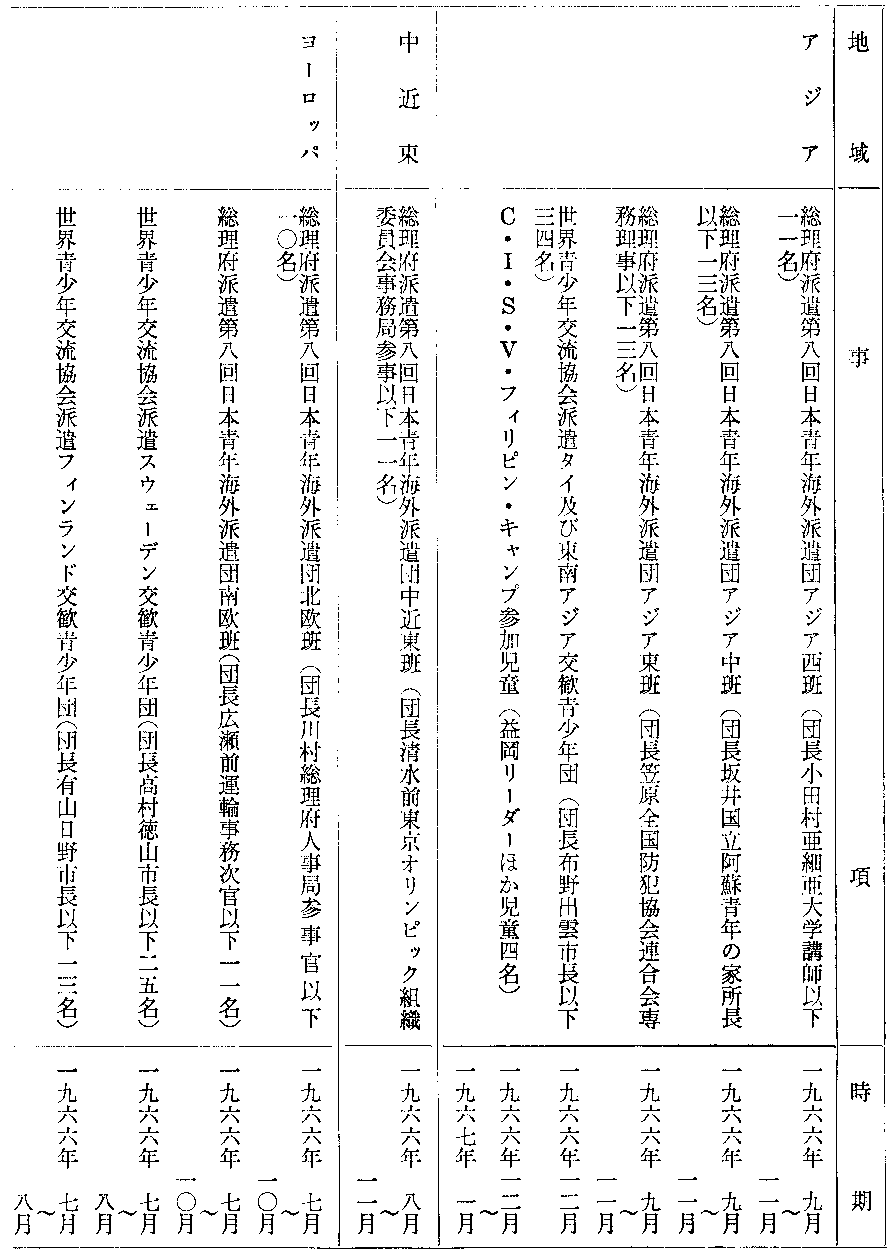 |
(ロ) 日本訪問

アジア、中近東、アフリカ、中南米諸地域への学術調査隊の派遣に対しても便宜供与を計った。
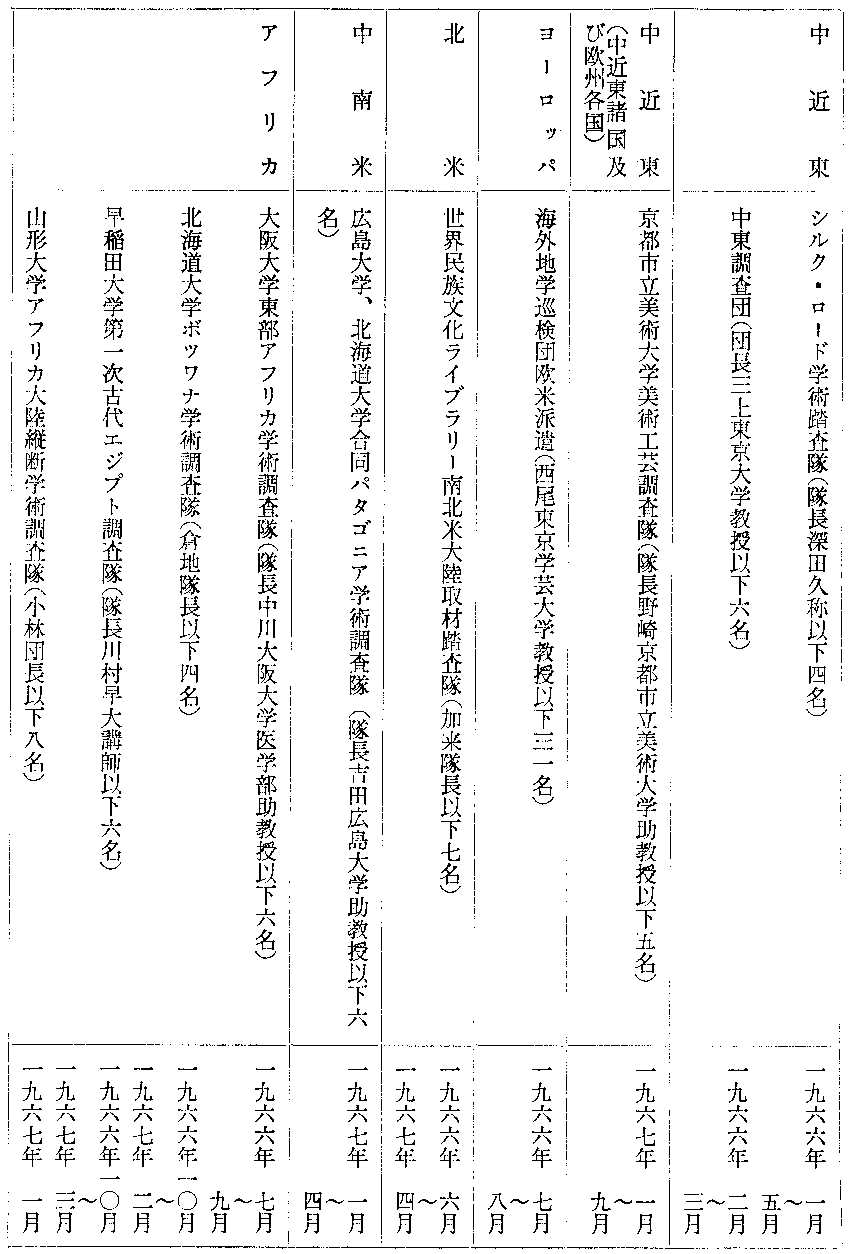 |
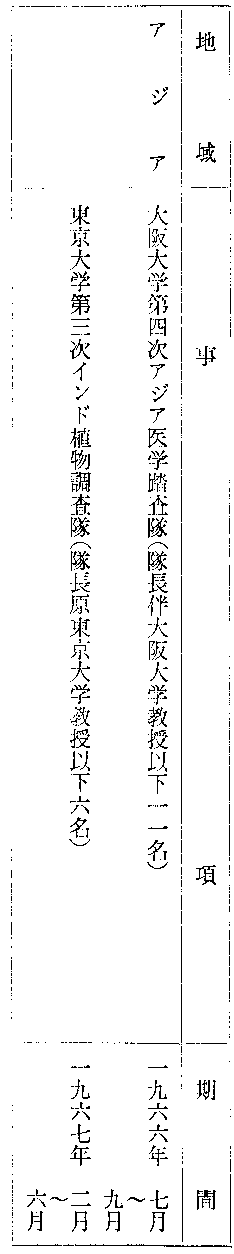 |
スポーツを通しての国際親善を図るため、民間スポーツの交流に協力するとともに登山隊の派遣に対しても便宜供与を行なった。
(イ) 登山隊派遣
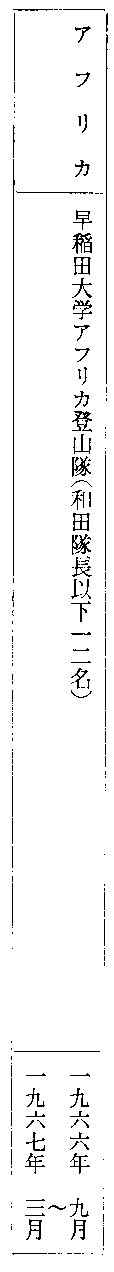 |
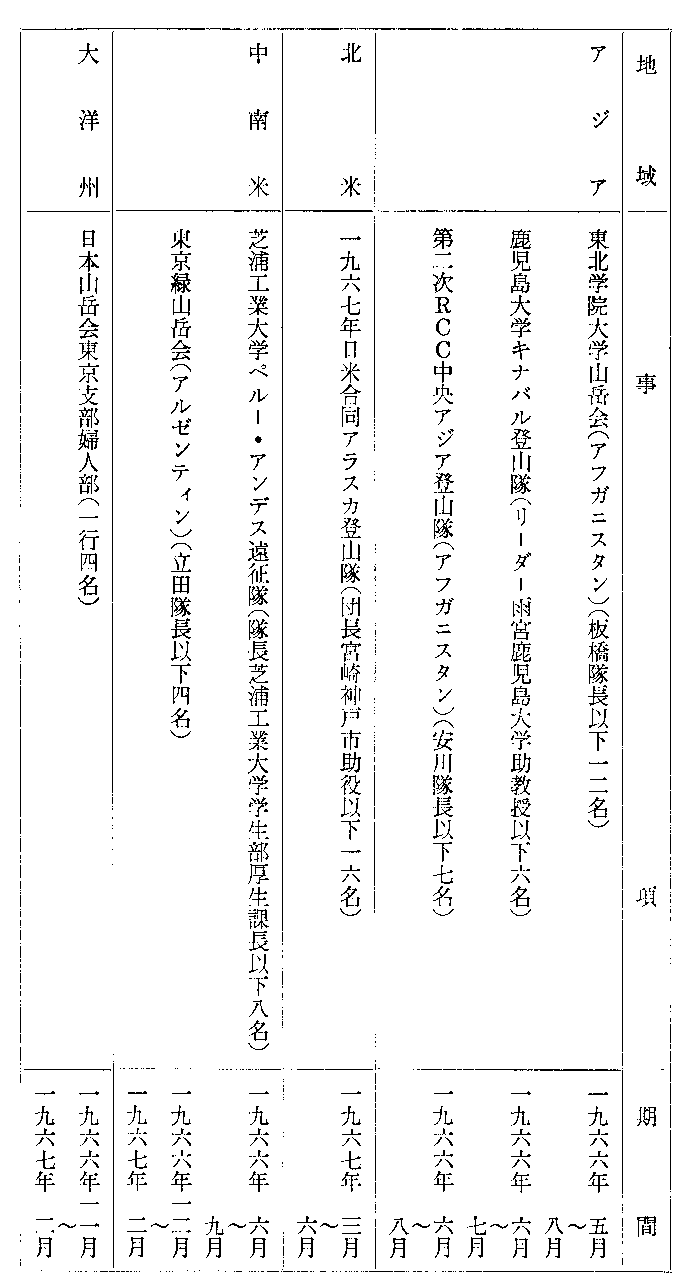 |
(ロ) スポーツの国内開催
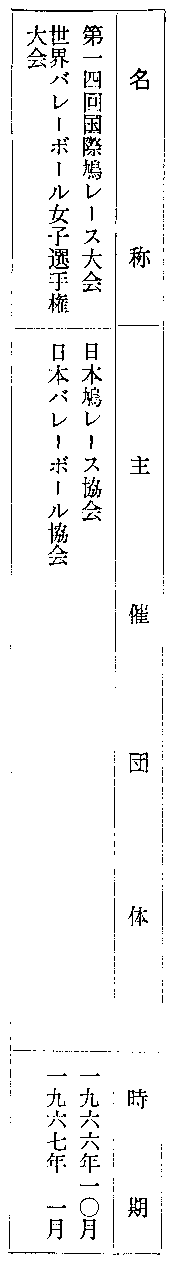
(ハ) 海外への日本選手派遣
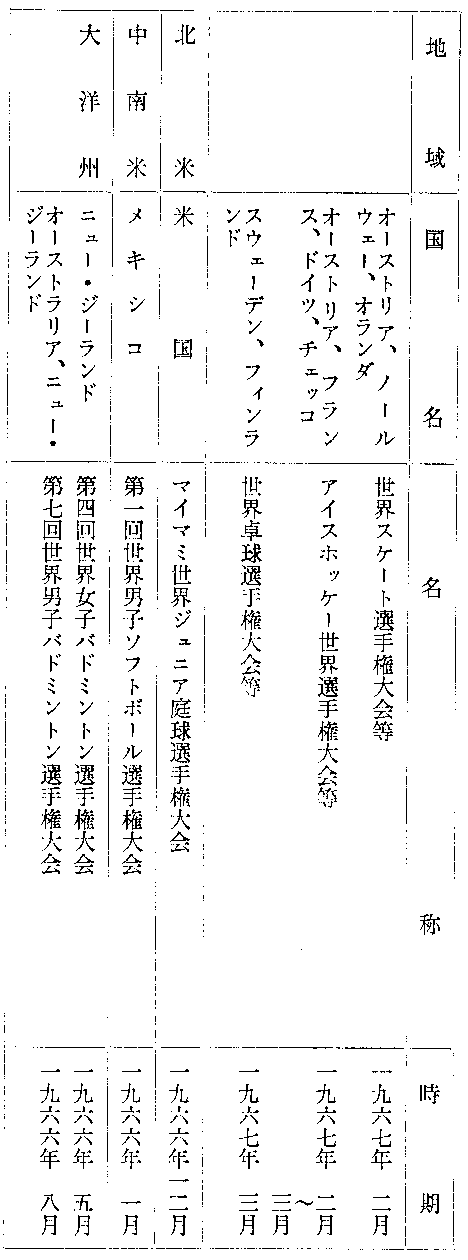 |
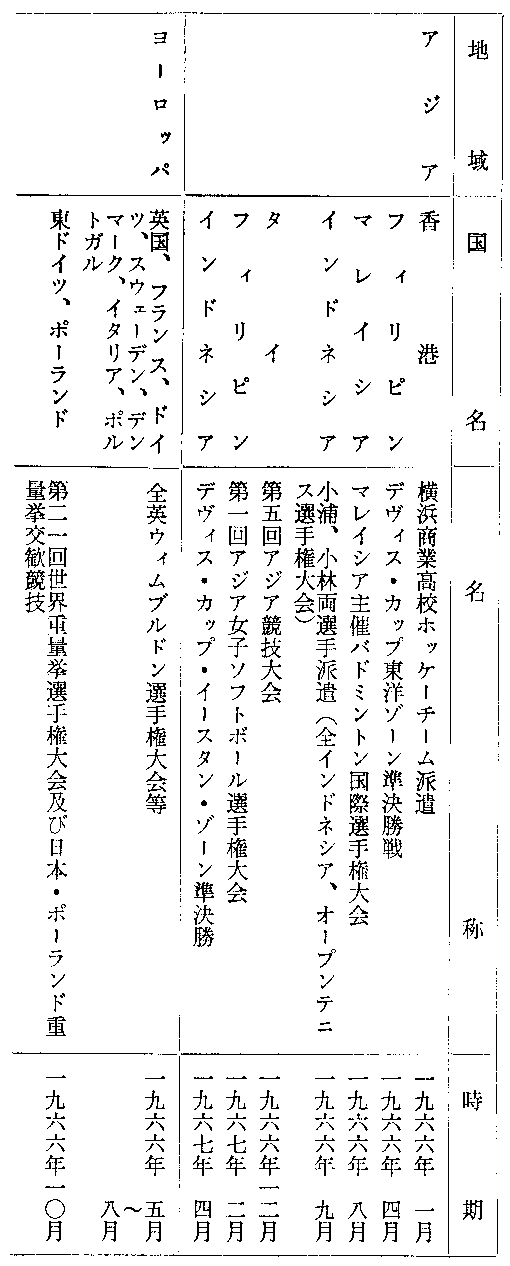 |
(イ) 海外訪問
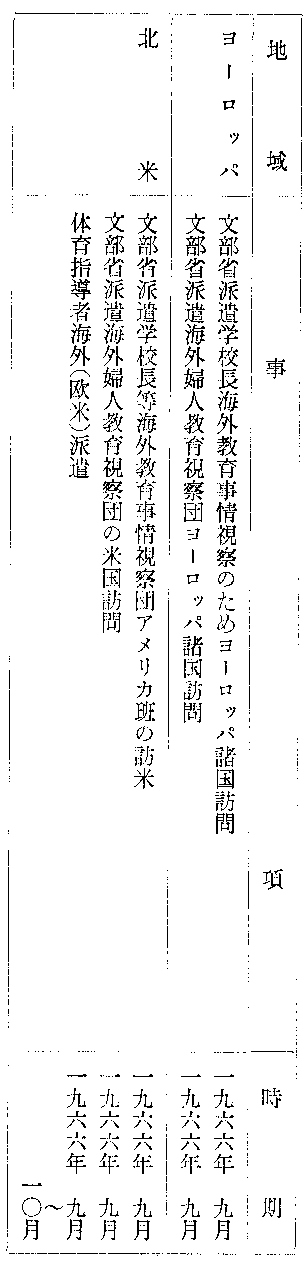
(ロ) 日本訪問
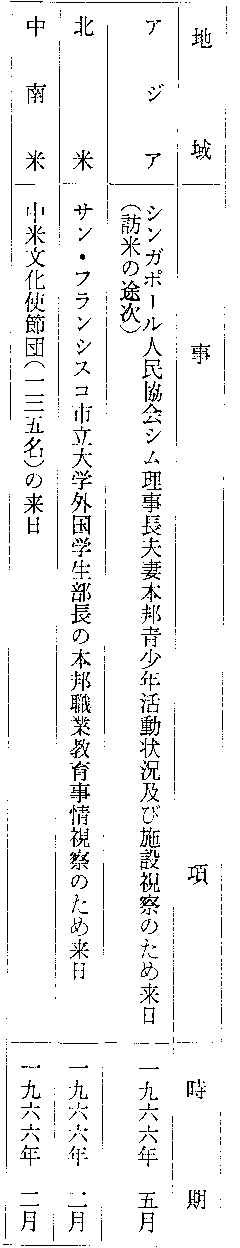
若い外国人留学生を国費をもってわが国の大学に留学せしめることは、わが国の学術水準のみならず、わが国の文化と生活を身をもって体験せしめ、わが国に対する理解と認識を深める上で多大の効果を収めうるものである。外務省は、この観点にたち、政府予算による外国人留学生招致に対しては全面的に協力している。
(イ) 文部省予算による文部省奨学金留学生招致制度
この制度により、一九六五年度一九四名、一九六六年度一九八名の外国人留学生が招かれた。一九六七年度には一八六名の留学生が招かれる予定である。この制度による留学生は、学部留学生(アジア・中近東諸国からの留学生のみを対象とし、期間五カ年、ただし、医科および歯科は七カ年)と研究留学生(全地域、期間二年)の二種類がある。奨学生に対しては、往復旅費(ツーリストクラス)、奨学金月額三○、○○○円、国内研究旅費(研究留学生および最終学年の学部留学生に対して)年額二五、○○○円および渡日当初の経費として一時金一〇、○○○円等が支給される。招致留学生の国別内訳はつぎのとおりである。
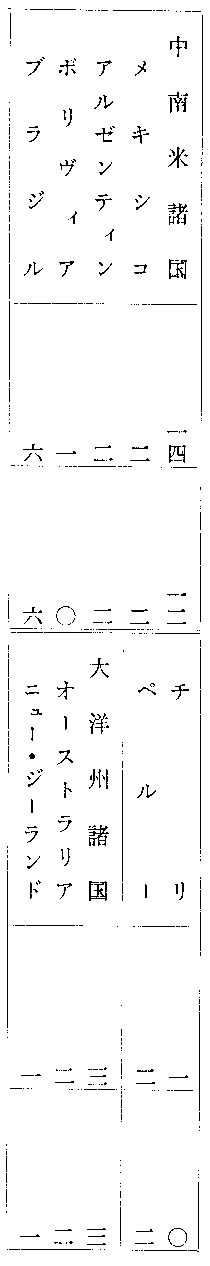 |
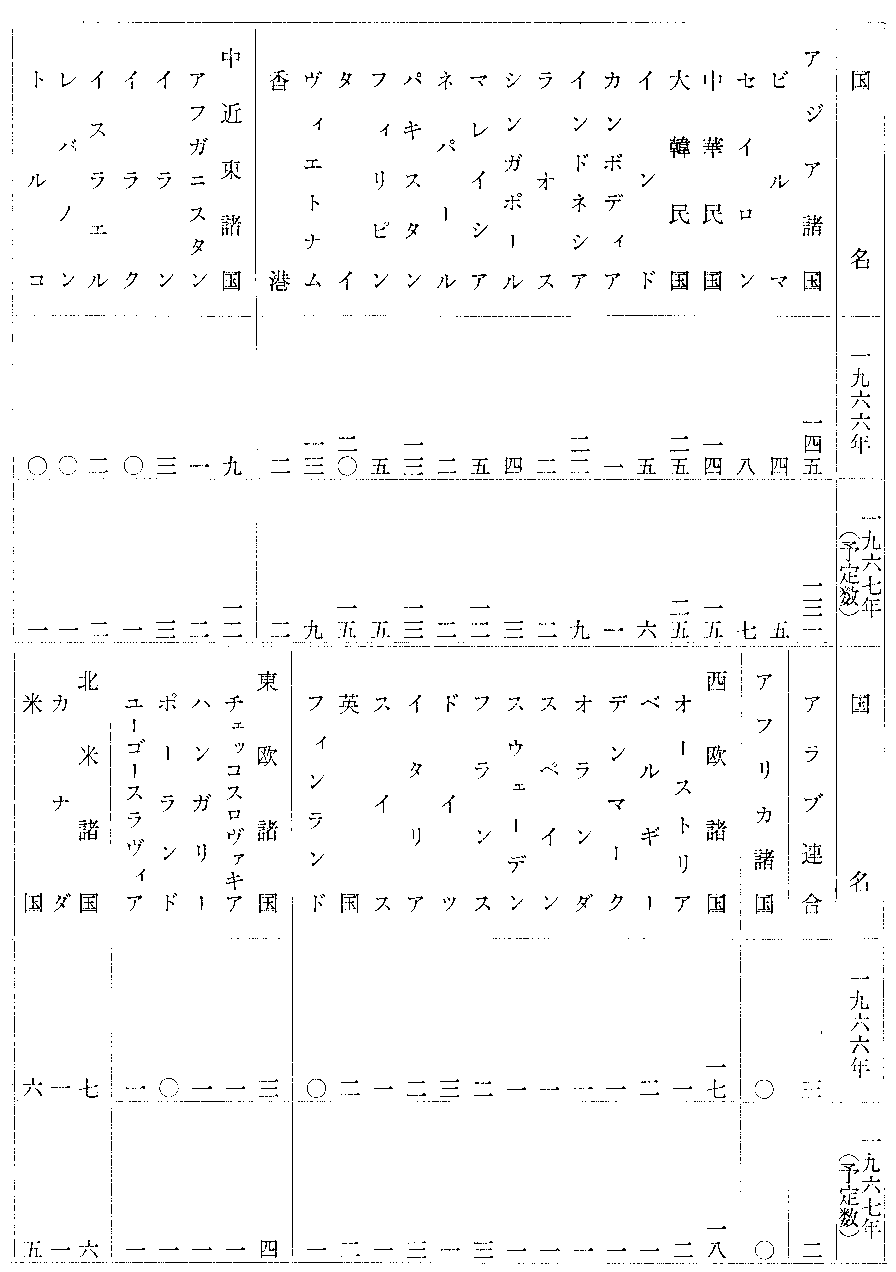 |
(ロ) 科学技術庁予算による外国人研究者招致制度
この制度は一九六二年度より始められ、奨学金支給額は往復旅費のほか、月額六万円ないし七万円である。招致実績は次のとおりであるが、外務省は本件招へいにつき在外公館を通じ協力を行なった。
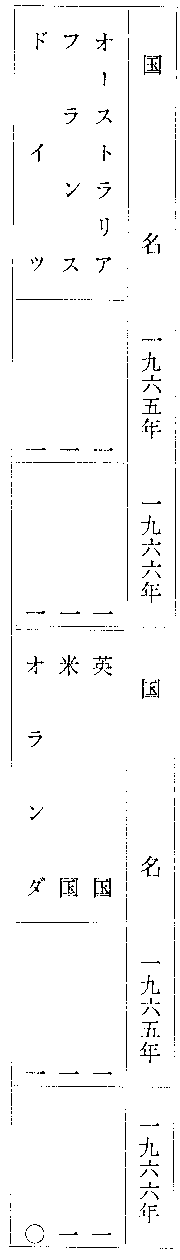
この計画により一九六五年度および一九六六年度にはつぎのとおり米国人学者および学生などが招かれた。
一九六五年
訪問教授 一六 研究学者 一〇 英語教師 六 大学院学生 一二
合 計 四四
一九六六年
訪問教授 二一 研究学者 一二 英語教師 五 大学院学生 一〇
合 計 四八
一九六六年度に外国政府または準政府機関の給費生として海外に留学したわが国の学者・学生はつぎのとおりである。
(イ) アジア地域
インド 一 タ イ 一 パキスタン 一
(ロ) 中近東地域
トルコ 三
(ハ) 欧州地域
オーストリア 四 ベルギー 七 デンマーク 一 フランス 八四
イタリア 二 オランダ 五 スペイン 一三 スウェーデン 一
スイス 三 イギリス 一三 チェッコスロヴァキア 一
(ニ) 米州地域
米 国 二七六 カナダ 一五
(ホ) 大洋州地域
オーストラリア 二
世界の主要先進国は文化交流事業の重要施策の一環として自国語の海外普及に強力な活動を展開している。
現在海外に外国人を対象とした日本語教育施設は、総計三三カ国四七一カ所が存在している。その内訳は左記の通りである。
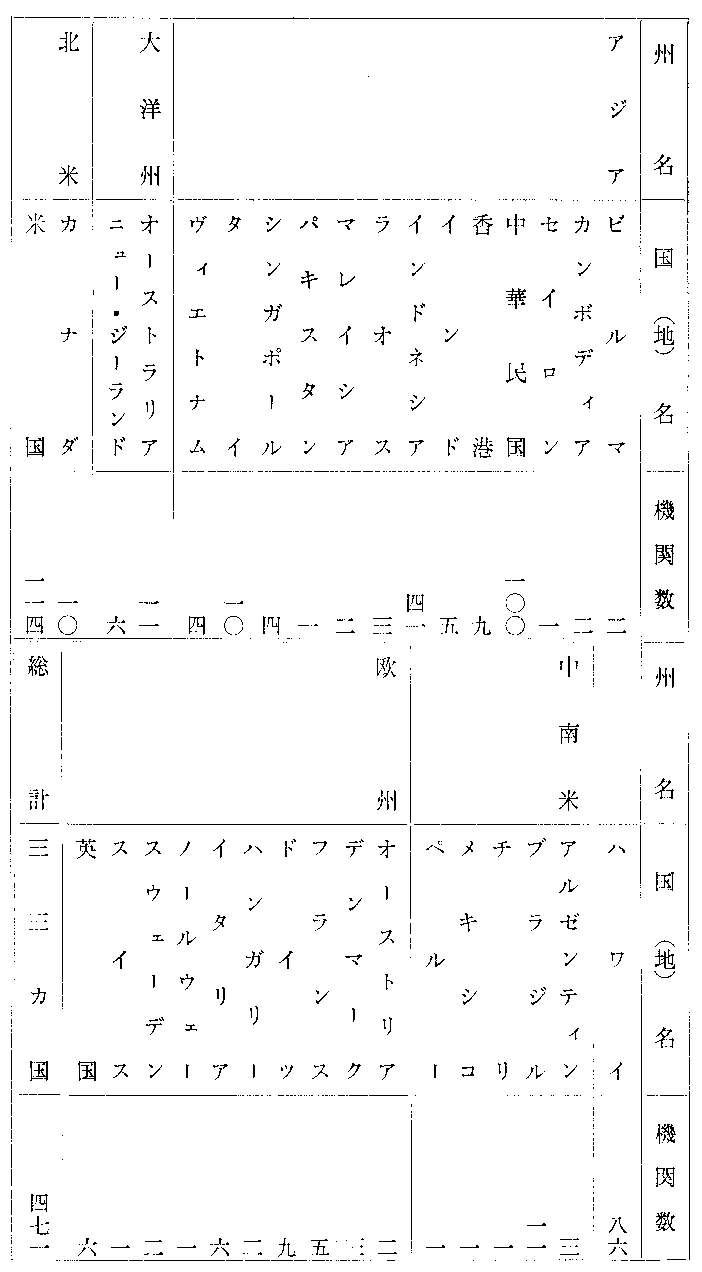
外務省として現段階においては、これら施設の中、在外公館がなんらかの形において、関係しているものについては一部講師謝金、会場借上費を支出しているものもあるが、教科書類については、予算の許す範囲内において在外公館よりの要望に応じ無償にて配布を行なっている。一九六六年度においては三四カ国に対し、一七、九九八冊を配布した。その内訳は次のとおりである。
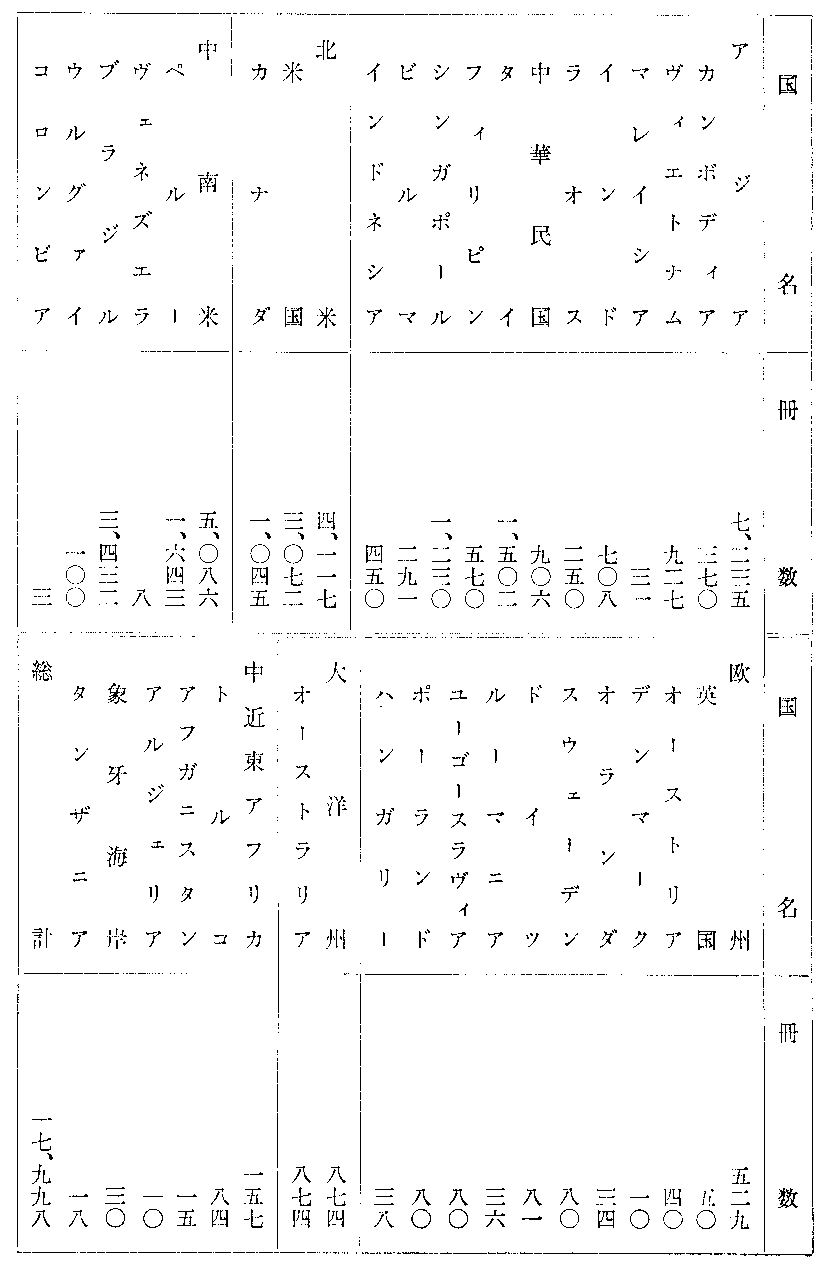
東南アジア諸国のわが国に対する関心が高まってきており、わが国の人文、科学及び社会科学の各分野についての高度の学問的探求の強い要望に応え、わが国はこれらの国の諸大学に、教授一名、助手二名を派遣、講座に必要な図書及び器材も提供し、日本研究講座の講義を寄贈することとし、一九六五年一一月にタイ国タマサート大学に、アジアアフリカ言語研究所河部利夫教授を派遣(同教授は一九六六年六月に赴任した後任の大阪外国語大学富田竹二郎教授と交替)、同大学に日本研究講座を開設したのを皮切りに、一九六六年末から六七年始めにかけて、次の諸大学に日本研究講座を開設した。
一九六七年四月現在の寄贈先大学及び、派遣教授助手講義題目等、次の通りである。
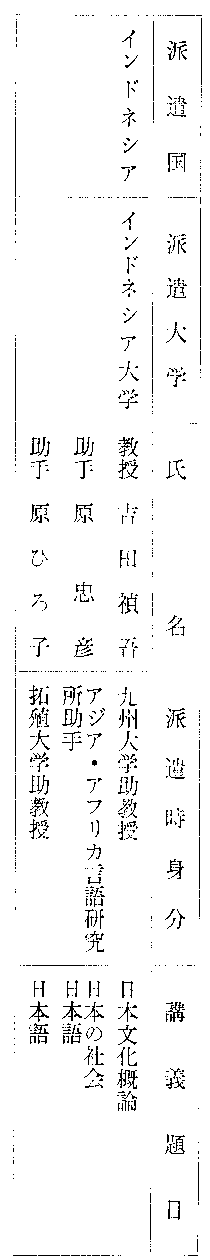 |
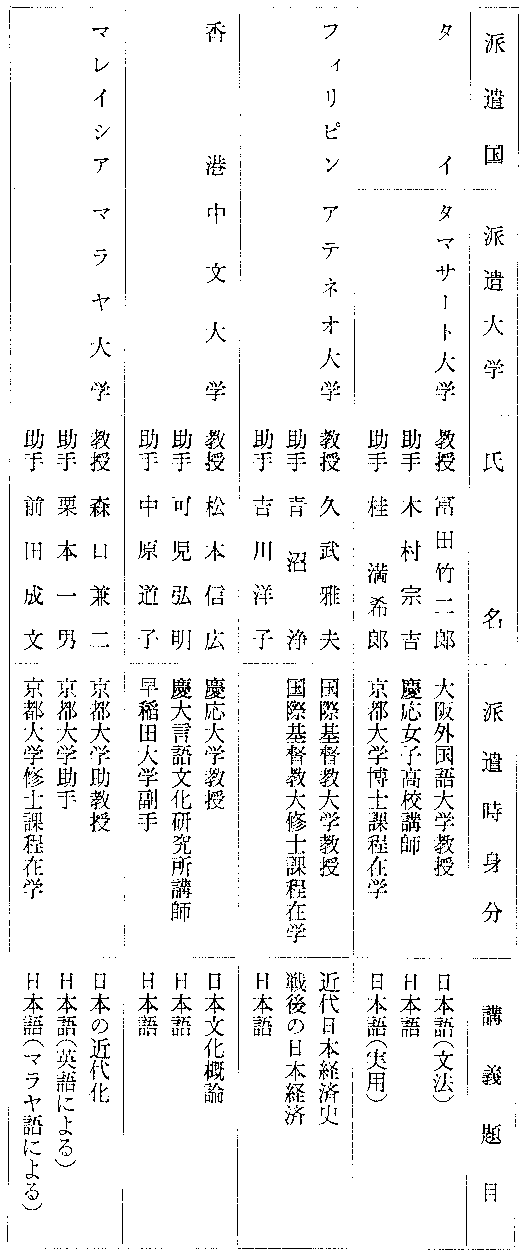 |