
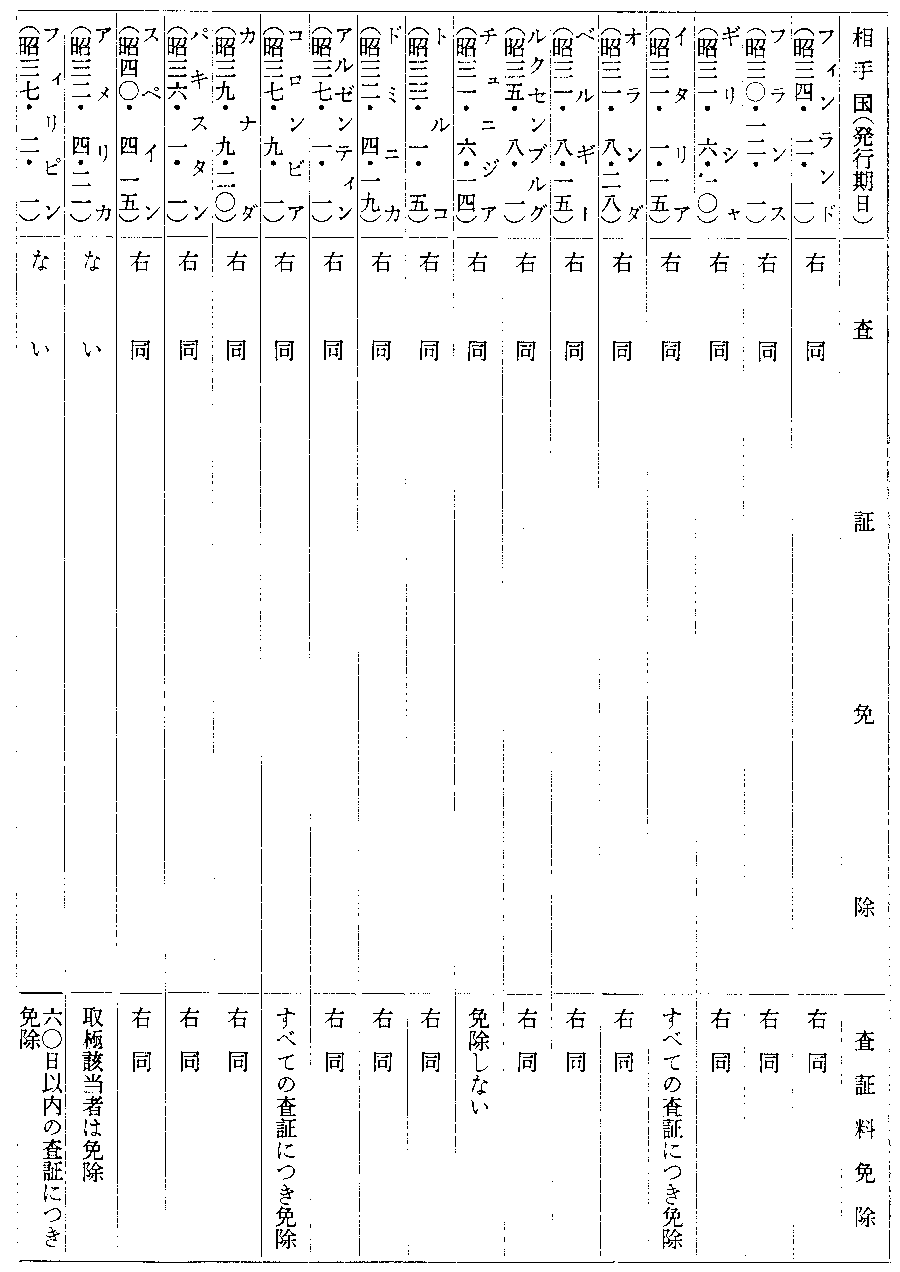
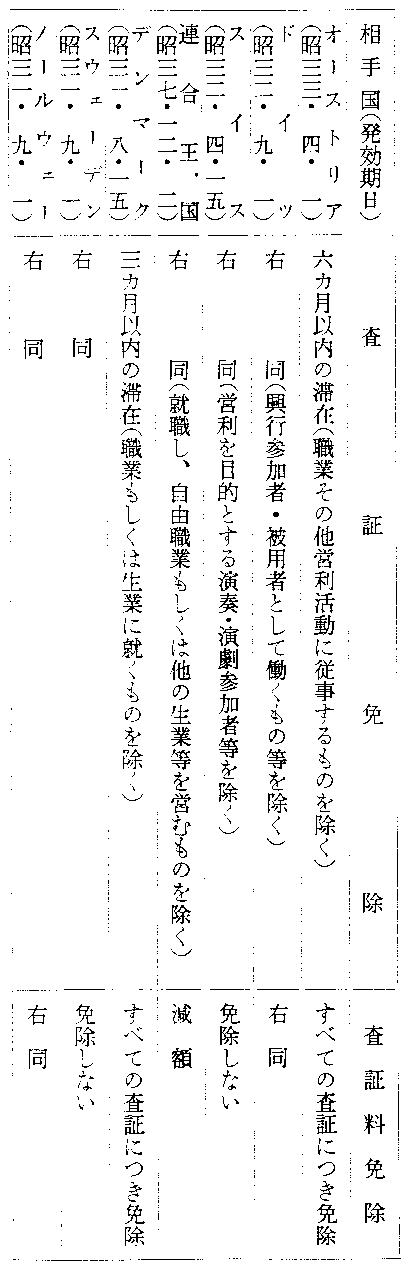
邦人の海外渡航と外国人の入国査証
1 邦人の海外渡航
(1) 概 況
(イ) 一九六四年(一月-十二月、以下同じ。)中、邦人の海外渡航に対し、外務省が発行した一般、公用両旅券の発行総数は、一二万四、四五二件(旅券の発行件数は、実際に渡航した人数とは一致しない。一五歳未満の子供を両親が同伴する場合は、両親のいずれかの旅券に各々三人まで併記できるし、また、旅券が発給されても、何らかの理由で渡航を取止めるものもあるからである。)にのぼり、対日平和条約が発効した一九五二年の発行数一万三、四四一件の約九倍に当る。
これを前年の一九六三年における総数九万二、三四七件に比較すれば、三万二、一〇五件、即ち約三五%の増加である。
旅券発行数の過去一〇年間における実績を見るに、一九五八年を除いてはいずれの年においても、発行数はその前年より増加しており、平均年間増加率は約二一%であるが、一九六四年が前述のように飛躍的な伸びを見せ、一九六三年と同率の高度な伸張を示した理由は、一九六三年中にとられた、業務渡航に対する規制の大幅な緩和に引き続き、一九六四年四月、観光渡航の自由化が実現し、これに拍車を加えたためである。
なお、一九五二年から一九六四年に至る一三年間の旅券発行総数は、累計六三万二、五三六件(次表参照)に達した。
(ロ) 旅券発行高について年間の趨勢を眺めると、例年、夏期に向って上昇線を描き、大体八月を頂点として再び下降する傾きがある。一九六四年は、この例を破り、九月が最高となり、月間発行高としては一万二、三九七件という新記録を樹立したが、特に、本年において挙げ得る特徴は、前記のように一九六三年に引続いて、発行高が激増したことと、二月以来、各月とも発行高に大きな開きがなくなり、平均化の傾向を見せたことである。
2月間発行高が最低となるのは、通常一月であるが、一九六四年もこの例に洩れず、同月が最低で、七、七六七件となっている。
(ハ) その他、一九六四年において注目に値いする現象は、一九六三年と同じく共産圏特に中共への渡航者が漸増しつつあること、並びに移永住関係が依然として低調であったことである。
(2) 目的別渡航状況
一九六四年の発行旅券を渡航目的により大別すれば、次のとおりである。
(イ) 一般旅券
渡航目的 発行件数 百分率
経済活動 六九、〇三五 五八%
文化活動 一二、七〇三 一一%
移永住 六、二七五 五%
観 光 二三、〇二六 二〇%
その他 七、六二八 六%
計 一一八、六六七 一〇〇%
注、「その他」とは、興行、家族および同伴者、知人近親者訪問、病気治療および見舞、休養、米軍用務、墓参等である。
(ロ) 公用旅券
渡航目的 発行件数 百分率
外 交 一、四二四 二五%
公 用 四、三六一 七五%
計 五、七八五 一〇〇%
(ハ) 観光を目的とする旅券
観光渡航の自由化は、前記のとおり、一九六四年四月から実施され、其後、多少の高低を辿って逐増しつつあるが、同年の最高記録は、十二月の三、三六九件で、これをその前月に比べると実に約三八%の増加率である。月間記録としての次位は、九月の三、〇四五件、前月比増加率約三一%であるが、四月から十二月まで九カ月間の平均増加率が約九%という意外に低い結果を招いた理由は、七月、十月および十一月の三カ月の発行高がいずれもその前月より低落したことに起因する。
最低は、四月の一、九三六件であって結局九か月間を通じての累計は、前項、(2)の(イ)に掲げたとおり、二万三、〇二六件に終り、当初予期された程のブームは現出しなかった。
観光旅行を渡航先地域別に見ると、アジア約四四%、北米約二八%を占め、欧州は、第三位の約二一%となっており、最下位は、大洋州、太平洋諸島(ハワイを除く。)である。
次に、職業別に見れば、会社員が最も多く全体の約三四%、次は無職の約二八%、ついで商工農業従事者の約一三%という順位で、最下位は、公務員の一%弱であるが、六月および七月において約二四%前後を占めていた学生は、休暇明けの九月以降、急激に減少した結果、第四位の約一一%に止まった。
年令階層は、二〇代約二八%、三〇代約二一%で、両者を合すれば、全体の約半数に達するが、性別としては、男性が優勢で約六二%にのぼっている。
(ニ) 長期渡航を目的とする旅券
一九六四年一月から一般旅券による長期渡航者実数(ここにいら「長期渡航」とは、主として一国に六カ月以上滞在する渡航を指し、「実数」の中には、一五歳以下の子供で両親のいずれかの旅券に併記されたものも含む。)に関する統計の作成を新たに開始した。
一九六四年の長期渡航者総数は、二万二、八八六名に達するが、これを国別に見れば、次のとおり、米国が圧倒的に多い。
順 位 国 名 人 数
1 米 国 一〇、四九三
2 ブラジル 一、八〇九
3 香 港 九七四
4 西ドイツ 八六二
5 英 国 五九〇
また、これを渡航目的別に区分すると、勤務が最も多く、以下次の順序である。
順 位 渡航目的 人 数
1 勤 務 六、六四五
2 同 居 五、八四六
3 国際結婚(主として米国) 二、七五四
4 留 学(主として米国) 一、九〇九
5 再永住(主として米国、ブラジル) 一、七七〇
注、再永住とは、外国に永住権をもっている者がその国へ再渡航する場合をいう。
2 外国人の入国査証と査証相互免除
(1) 入国査証
外国人は、原則として、わが国の在外公館で領事官から査証を受けた有効な旅券を所持しなければ、わが国へ入国することができない。一九六四年中にわが国の在外公館において発給した入国査証は、
外交、公用査証 一七、七六四件
通 過 査 証 九、八九〇件
入 国 査 証 一三九、八五八件
計 一六七、五一二件
となっており、最近十年間の査証発給状況を地域別および年度別にみると次表の通りである。
右表において、次に述べる査証免除取極の相手国が逐次増えているにもかかわらず、査証発給件数が減少することなく、逆に逐年増加しつづけていることは、査証免除取極のない国からの来訪者を始めとし、全般的にわが国へ来訪する外国人の数が増えつつあることを示すものである。
(2) 査証相互免除取極
わが国との間に査証相互免除取極を結んでいる国の旅券所持者が、観光、視察その他の目的により、わが国に短期間滞在しようとするときは、入国査証を必要としないこととなっている。現在わが国は、次表の通り二七カ国との間に、査証および査証料の相互免除に関する取極を結んでいるが、これらの取極には、おおよそ次のような内容が含まれている。
(イ) 短期査証の相互免除
相手国国民が、観光、訪問、会議出席等の場合のように、生業職業または報酬をうけるその他の活動に従事することなく、取極に規定した期間(三カ月または六カ月)内だけ入国滞在しようとするときは、相互に査証を相手国国民に対し免除するもので、我国は現在二二カ国と取極を結んでいる。
(ロ) 査証料免除または減額
短期査証の相互免除に加えて、査証を要する場合の査証料を免除する取極を結んでいる場合と、単に査証料のみの相互免除取極を結んでいる場合との二種類があり、また査証料についても、
○すべての査証につき査証料を免除しているもの 一二カ国
○減額その他条件つき免除をしているもの 五カ国
となっている。
(ハ) 査証の有効期間と有効回数
査証の有効期間は、わが国では通常六カ月間一回限り有効となっており、特に必要と認められるときは数次有効の査証を発給することとなっているが、アメリカ、カナダ等との間では査証を相互に一定期間数次有効としている。たとえば、アメリカからの観光客は四八カ月数次有効の観光査証を無料で発給される。
 |
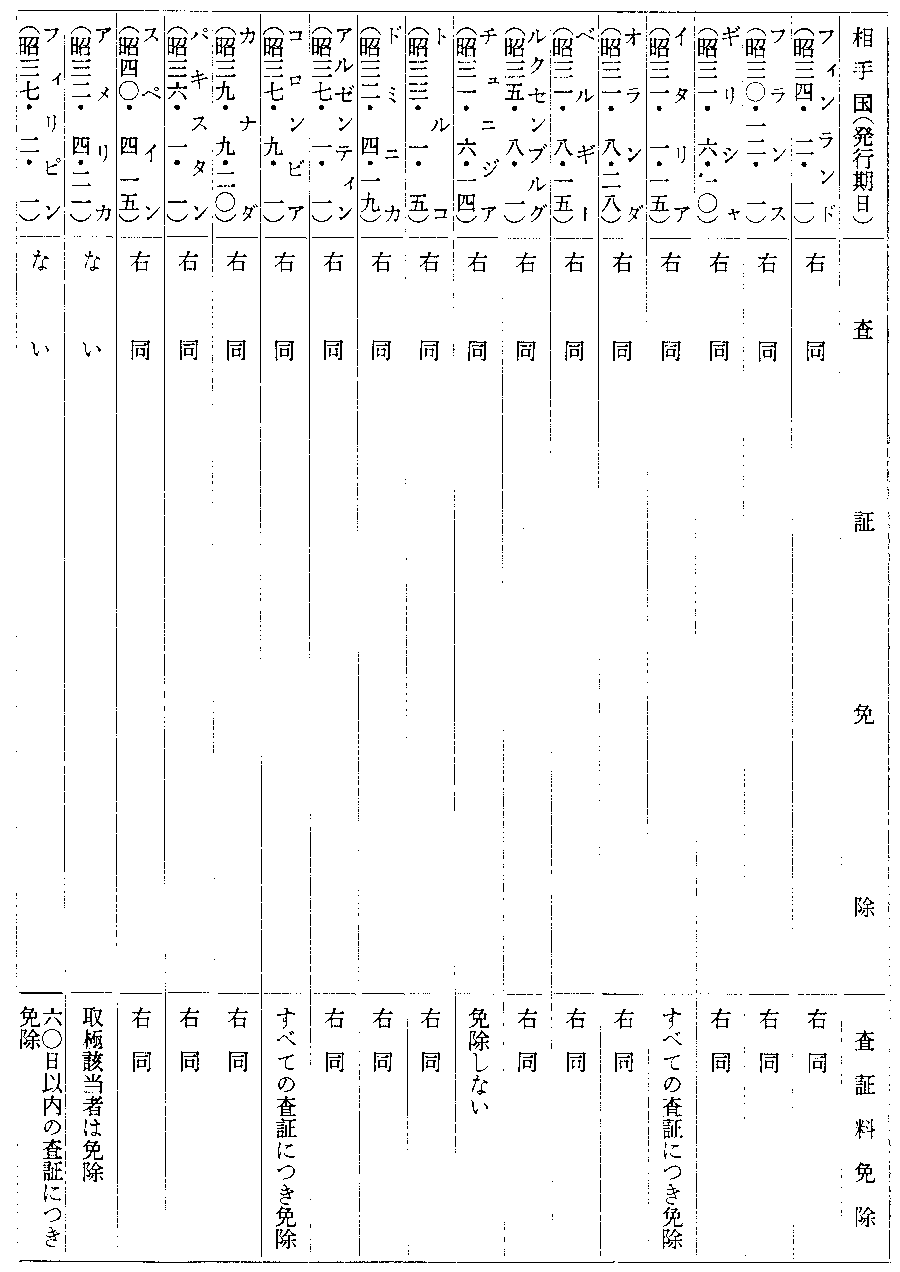 |
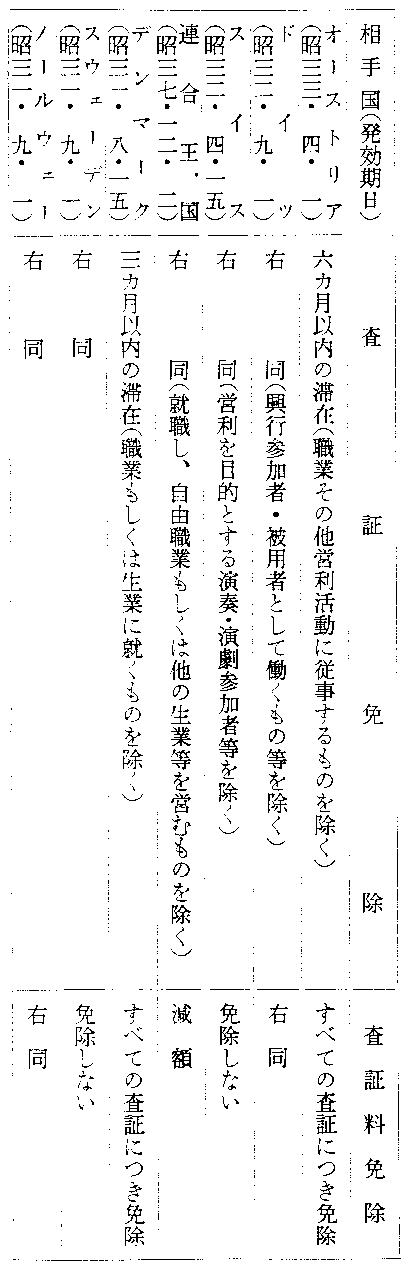 |
3 旅券事務の合理化
近年、旅券の発行数は増加の一途をたどりつつあることは前述の通りである。
これに対処するため一九六五年一月二十六日以降は、既設の電子計算機ならびに新規に導入したキーパンチ機およびフレクソライター(自動印字機)を併用し旅券事務を処理している。
この結果、
(イ) 従来、作業の大部分を手作業によっていた旅券の作成、帳簿の記入、統計等の事務が機械により処理されることになり、
(ロ) 旅券発給申請書の項目がコード化されたことにより、渡航者は記入の手間がはぶけ、外務省及び各都道府県は旅券事務を円滑かつ能率的に処理することが可能となった。
機械化の内容は次のとおりである。
(1) 旅券冊子様式の改正
フレクソライター(自動印字機)を使用し、旅券面に自動的に印字できるよう一般、外交および公用旅券の様式を改正した。主な改正点は、旅券の記載欄をよこ型(米国方式)にし機械に適合せしめたことのほか、記載事項の和英対比、外務大臣名の省略、国籍欄および本人記入欄の新設等である。
(2) 一般旅券発給申請書および公用旅券発給請求書様式の改正
電子計算機にインプットし得るよう様式を全面的に改正した。主な改正点は、必要項目のコード化、経由国欄の廃止、記載事項欄の整備、記入方法の簡略化等である。
(3) マイクロ・システムの採用
一般旅券発給申請書および公用旅券発給請求書等の書類の分類および保管を簡易、能率化するためマイクロ・システム(マイクロ・フィルム撮影による処理)を採用したことである。
(4) チェック・パーソン・システムの採用
要注意人物(旅券法第十三条第一項該当者等)の海外渡航を事前に抑制するため電子計算機によりチェックする方法を採用した。
4 旅券法改正作業
現行旅券法(昭和二十六年法律第二六七号)は占領末期に制定されたものであり、戦前の旅券制度をそのまま承継した部分が多く、船舶による海外渡航時代の旅券制度の名残りをとどめ、旅券の効力を原則として一回かぎりの渡航だけで失わしめ、かつ、旅券面に各渡航先を列記する建前をとっている。このため、渡航者に対し、渡航ごとに新規に旅券の申請をなさしめ、また渡航先追加申請等の煩さな諸手続きを課すこととなり、今日の渡航の実態にはなはだしくそぐわないものとなっているので、これら諸手続きの改善が強く要望されている。他方諸外国においては、一般に旅券に相当長期の有効期間(もっとも多くの国が五年)を付し、有効地域については、渡航先列記の建前をとらず、原則としてすべての国に有効とすることが通例となっている。また、一九六三年八月ローマで開催された国連主催の国際旅行及び観光会議更にOECD等の国際機関においても、国際交流促進の見地から、旅券に五年の有効期間を付し、原則としてすべての国に有効とする方式を採用するよう、加盟国に対し勧告している。
このような内外の趨勢にかんがみ、早急に現行旅券法を改正し、わが国旅券制度の近代化を図る必要があったので、一九六四年度初めより、本格的に旅券法改正作業に着手、同年九月以降、改正草案に基づき関係各省庁と意見の調整を行い、一九六五年二月下旬、各条項につき法制局審議も終り、旅券法の一部を改正する当省案がまとまった。
改正案においては、
(1) 旅券に五年の有効期間を付し、原則としてすべての国に有効とする、
(2) 旅券面への渡航先列記制度を廃止する、
(3) 旅券の申請及び交付の際の本人出頭主義を緩和する、
(4) 旅券の記載事項の訂正に関する事務を都道府県知事に委任する、
等、国民の海外渡航手続きの自由化と簡素化を図る一方、公共の福祉の立場から、好ましからざる渡航を抑制するため、
(5) 旅券の発給等の制限事由、
(6) 旅券の失効措置、
(7) 罰則等を整備することとし、
また、
(8) 渡航者の在留届、
(9) 緊急帰国証明書、
(10) 外国人渡航証明書等の新たな制度を設けたほか、
都道府県における族券事務を円滑ならしめるため、
(11) 族券手数料(三、〇〇〇円を予定した。)の半額を都道府県の収入とし、都道府県に対する財政的な裏付けを与えることとした。
その後、同改正案の罰則の一部に関し関係省と更に意見を調整する必要が生じたので、同改正案の第四八回通常国会提出は一時見送ることとなった。
しかしながら最近の海外渡航の自由化にともなう渡航者の激増に対処し、かつ貿易、文化交流等の業務渡航者の利便を図るには、わが国の族券制度を近代化し、族券事務全般の合理化を図る以外に方法がないので、今後益々旅券法改正の必要性は切実なものとなってくるものと思われる。