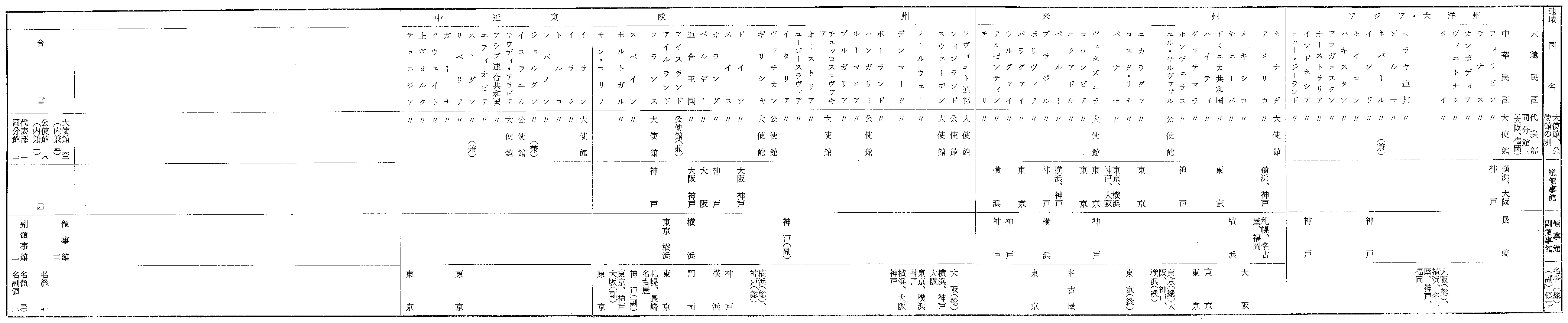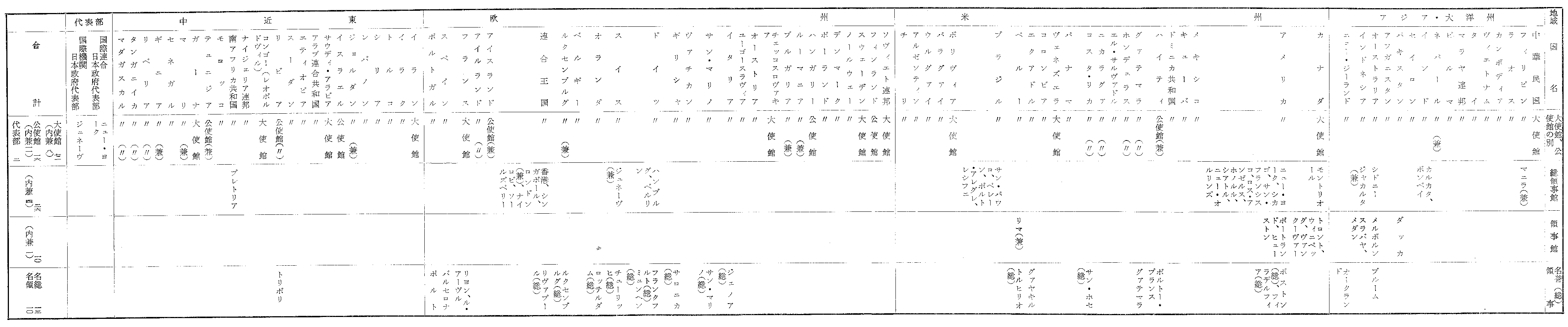
○文 化 関 係
文化および教育の交流に関する日米合同会議の最終コミュニケ
昭和三十七年一月三十一日
一 会議の目的
昭和三十六年六月、ケネディ大統領と池田総理大臣が行なった決定に従って、現在の交流活動を有効に推進し、強化する方途を探究する目的をもって、文化および教育の交流に関する第一回日米合同会議が昭和三十七年一月二十五日から三十一日まで外務省において開催された。本会議は友好的雰囲気の裡に行なわれ、両国代表は、人物交流、図書および資料の交換、芸術の交流、日本および米国の地域研究およひ語学教育、さらにこれらの活動を促進するための公私団体の問題について率直な討議を行ない、成果をあげた。
両国代表団は、相手国の知的成果と芸術的業績をさらに深く理解することは両国にとって有益であり、また双方の文化の独自性を認めその保存に努めることは相互理解を深めるものであり、さらに両国にとり共通の関心ある諸問題について共同して研究にあたることは、相互に利益のある結果をもたらすものであるということを認めた。本会議は日米両国間の過去十年間にわたる交流の実質的な成果を評価したばかりでなく、将来かかる交流をさらに改善するための多くの方策があることを確認した。両国政府がこれらの活動の多くに対して指導と支持を与えることは必要であるが、政府本来の役割は、これらの活動を統制することではなく、促進せしめることにあり、これらの活動は個人あるいは民間団体の最大限の創意と自治とに委ねるべきものであることに合意した。
二 次期会議
本会議は、文化および教育の交流について将来引続いて協議されることが両国にとり大きな価値をもつものであることに合意し、交流の進捗状況を検討し、新しい問題を探究し、将来の必要と機会を評価するため、昭和三十八年にアメリカ合衆国において第二回会議を開催することを勧告した。この間、両国政府に対し、必要な場合には、特定問題はこれに即した研究方法を発展せしめる臨時委員会の設置を含め、第一回会議の勧告を実現しうる範囲内であらゆる措置をとるよう希望された。
本会議の両議長、森戸辰男学長およびH・ボートン学長と他の民間代表は、これらの機関との連絡をとり、各自の専門分野において助言を与える等、でき得る限りの援助を行なうものとする。
人物の交流および外国語教育の改善等に関し、本会議と昭和三十六年十二月に開催された科学協力に関する日米委員会との間に共通の関心が存することに留意すべきである。
三 優先的に措置を要する勧告
本会議は、その行なうすべての勧告が政府および民間の機関によって検討されることを希望するとともに、なるべく早い機会において実際的措置をとるため両国政府は下記の事項にまず考慮を払うことを強く要請する。またあらゆる分野における交流に関しては、量の増加より質の改善に特別の注意を払うとともに、卓越した能力を持ち、将来相当期間にわたり活躍が期待される青壮年に対して、今後は一層の重点をおくべきことが要請される。
勧告第一
文化および教育の交流をはばむ最も大きな障害は言語の障壁であることを認識して、本会議は両国政府が関係団体と専門家の協力を得て極めて重要なこの言語教育の問題解決に集中的努力を注ぐことを要請する。解決の方法としては次の二方法があげられる。
(イ) 米国人に対する日本語教育と日本人に対する英語教育の改善のために共同して行なわれる主要な試みについて勧告を与える日米委員会を組織すること。
(ロ) 日本語および英語の教授と学習を能率的、効果的に行なうために、科学、技術の近代的学術研究成果を最大限に応用する方法を検討する主要研究計画を開始すること。
勧告第二
両国にとり共通な関心の存する学術的および非学術的問題、例えば日本研究、アメリカ研究、アジア研究等における特殊部面、大学における一般教育課程の問題、両国文化におよぼすマス・メディアの影響、現代ジャーナリズムの問題と技術等に関する共同研究の努力と二国間または多数国間におけるセミナーを一層奨励すべきである。
勧告第三
公的団体と私的団体の間には活動領域の分担が明瞭にされるべきである。また国際間の文化および教育の交流を促進するためには現存する組織の能力が強化され、充分に活用されなければならない。日米両国においてその計画を援助するための民間資金の獲得に役立つような機会がさらに醸成され、そのための助成策が強化されなければならない。教育および文化の交流を援助強化するため、新らしい型の二国間の機関を創設する必要を考慮すべきである。この機構については政府の援助が効果的に与えられることが望ましいが、その活動については自由で自主的なことを建前とする。
勧告第四
芸術の交流においては質の高い教育・文化テレビ番組、両国の大学間における才能ある若い舞台芸術家グループ、小都市における小規模で高級な展覧会開催と舞台芸術家グループ、長期間にわたって相手国で活動できる創造的才能をもつ完成した芸術家および将来性ある若い芸術家、ならびに初等および中等教育の芸術担当専門家の交流がさらに強調されるべきである。
勧告第五
両国において交換される学生の受入国における研修期間が、学術上および人間形成上極めて豊かな経験となるように、これらの学生に対するカウンセリング、オリエンテーション、語学研修およびその他重要な事業が適切に改善されるべきである。
勧告第六
翻訳、文献の要約および二国間共同作業ならびに出版を増加して、日本人の思想および学術研究成果を一層効果的にアメリカ合衆国に紹介しうるよう改善すべきである。
四 一般勧告
1 人物交流
すべて文化の発展は創造力に富む個人によるところが大きく、個人の経験があって、はじめて国際間の文化交流が豊かな国民生活を産み出すのである。従って、人物交流は本会議が検討したすべての議題にとって非常に重要である。
人物交流はそれ自体が目的ではないことが強調されるべきである。各々の人物交流の目的が明瞭でなければならない。広くいって人物交流には、(1)日米両国間の理解の橋を拡げること、(2)建築、絵画、その他の芸術の分野において日本からの影響によって米国文化が豊かになったように、各々の文化をさらに豊かにし、かつ、強化すること、(3)一国の学者をして他国の独自の文化に触れさせることにより、聰明かつ有能な人間を育て上げること、(4)両国から才能ある人物を集め、その協力により共通の基本的問題の解決にあたること、の四つの大きな目的がある。
本会議は、人物交流に携わるすべての機関が今後質の向上にとくに重点をおくべきことに合意した。この目的を達成する一つの方法としては奨学金の対象となる人々の選考にあたって、優れた潜在能力と若さの点をさらに重視すべきことがあげられる。創造力ある芸術家、日本の私立大学の教授、一般教育担当教授、新聞の編集責任者、さらに婦人、青年、および労働団体の指導者のような人々、ならびに、従来比較的軽視されてきた社会科学と人文科学の分野の問題に対してはより多くの注意が向けられなければならない。留学生その他の人々の受入れ国における経験を効果あらしめるためには語学の理解力、カウンセリング、計画の作成等の問題に、より以上の注意を向ける必要がある。さらに、例えば、真に両国相互間に関心のある分野における共同研究の如きもの、すなわち、日本研究、米国研究またはアジア研究の特殊部門、大学における一般教育課程の問題、国民文化におよぼすマス・メディアの影響、または国民文化に関する問題と技術等についての共同研究の如き比較的新しい型の交流が拡大されるべきであろう。
2 図書・資料の交換
印刷された言葉は、意思の疎通を持続するための基礎的手段である。それは映画、ラジオおよびテレビジョンの如き新しい手段によって相当に補足されてはいるが、決して代替されるものではない。交換される資料の質および量の両面において改善をはかること、また、英訳の日本の出版物ははなはだ少ないので、均衡をとるよう努めることが重要である。現存する機関または新しく設置される機関のいずれかにより次の三つの事項について充分検討がなされ、適切な措置がとられることが望ましい。第一は販売または寄贈によって交流する印刷物を質量ともに増加することである。日米両国の大学出版部間の協力が奨励さるべきであり、また、相手国の読者のため、図書の出版とその効果的な普及に関する特別な問題につき考慮を払うべきである。第二は相手国の言葉で要約または翻訳された広範囲にわたる重要資料を入手しうるようにすることである。出版物を翻訳ないし要訳するためのみならず、最高レベルの文化的所産および最高レベルの学術的著述を現わす映画、スライド、テープ、マイクロフィルムおよびその他の資料を最大限に流通させるための新しい機構を設置することが望ましい。第三は、図書目録を一層完備し、図書館相互の交換を行ない。かつ、その他の図書館事業を改善して図書および資料の利用を更に容易にすることである。
3 芸術の交流
芸術は、人間体験の源泉に触れる。この領域において、日米両国は、異る文化遺産を有するが故に、伝統的、現代的、古典的および通俗的芸術のあらゆる面において相互に寄与するところ大である。通常の商業的販路による芸術の交流は一流の代表的なものでなく、あるいは誤解を招く傾向さえあるから最良のものを確保し、各分野の文化的生活を網羅するためには、両国政府のみならず、民間団体の継続的な発意と財政的援助が必要である。
最高レベルの職業演芸家や学生レベルの芸術交流は尨大な経費を要するが、極めて価値がある。能、文楽、伝統的日本民族舞踊ならびにアメリカの演劇および民族音楽の如き従来あまり紹介されていない分野に注意を払うべきである。
現代および歴史的作品を含む総合的な美術展覧会を定期的に交流すべきである。できるだけ多くの人々に見せるため、このような展示は小都市にも巡回させるべきである。芸術的および教育的価値の高い映画が劇場およびテレビ網を通じて容易に上映されるよう措置をとるべきである。芸術の分野における学者の交流および初等、中等学校の美術教師の交流に加え、創造力に富む人々が、留学する場合には相手国の芸術家および学生と接触しやすいような状態に置くべきである。伝統的、現代的な芸術、工芸およびスポーツの専門的指導者の交流にも考慮が払われなければならない。
4 地域研究
米国における日本研究および日本におけるアメリカ研究は、各種専門分野がそれぞれ結びつけられているので、学術的レベルにおいて両国文明および両国文化の底に流れる精神を相互に理解する近路である。
本会議は、かかる研究を一層促進するため、慎重な選考を経て選ばれた専門家で、自分の専門分野で十分の訓練を受けたばかりでなく、語学能力を身につけ、自分の研究に国の特性をもたせるものを交換するように奨励する必要があることに合意した。このような専門家がセミナーや共同研究計画に参加するよう奨励されれば、有意義な貢献をなすことができるであろう。アメリカ研究および日本研究の発展を阻害している柔軟性を欠いた大学制度は改められるべきである。経済学とか哲学とかいった伝統的学科の専門家が同時に地域研究者として二重の役割りを演ずることができるということが自覚されれば、少しでも前進したこととなる。交換は、大学院学生の研修ばかりでなく、アンダー・グラジュエイトおよび一般教育課程において講座拡充をはからんとするすぐれた専門家の訓練と研究のためにもなされねばならない。日本研究およびアメリカ研究がさらに発展をとげるためには、公私のいずれからも一層の資金援助を得ることが極めて必要である。
5 語学教育
本会議は、文化を知る鍵として、また各種の交流にとって欠くべからざる手段として、言語のもつ基本的重要性を強調した。言語上の障壁は、文化・教育の円滑な交流にとって最も大きな障害となっている。アメリカ人に対する日本語教育ならびに日本人に対する英語教育の改善のために従来払われてきた相当の努力を一層強化するためには共同計画が必要である。日本語の近代的教育法を習得した日本人また、英語の近代的教授法を習得したアメリカ人を一層活用するとともに、近代的研究、科学ならびに技術を新しい資料や技術的工夫ならびに教員の現職教育に最大限に応用するため主要な調査を行ない、かつ、効果的な努力を払うべきである。
語学教育の問題は重大にして複雑であり、かつ、国際協力を必要とするので、実際的な方策について助言を与える専門家からなる合同委員会の設置を急務としている。
6 団体間の関係
本会議の勧告を実施することは、政府、学会ならびに各種の民間団体の課題であり、そのためにはそれぞれの団体は自ら最も適すると考える仕事をすることである。
日米間の交流の改善を促進するために、この種の公私団体の資力を強化し、有効に活用すべきであり、両国の新しい協力関係を樹立すべきである。交流の分野で、奨励すべき効果的な団体間の協力には、大学、学会、姉妹都市、教員養成大学、文化団体および労働団体ならびに青少年グループ間の連繋がある。
文化および教育の交流には、官民両側からさらに多くの資金を必要とするものであるから、両国政府は、民間団体に対し、文化および教育の交流計画に対する財政的援助を拡大するように充分な指導と刺戟を与えることが必要である。さらに、文化および教育の交流活動に関してこまかい点にまで政府の統制には服さないが、政府の援助を有効に使う道を開くような新しい形の団体の創設を考慮することが望ましい。
◎わが国の在外公館一覧表
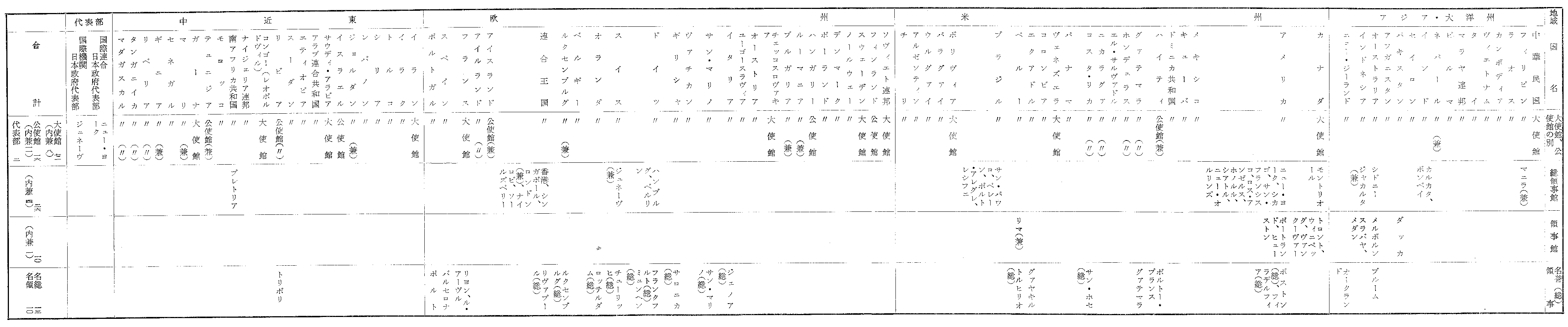
◎わが国に置かれている外国の在外公館一覧