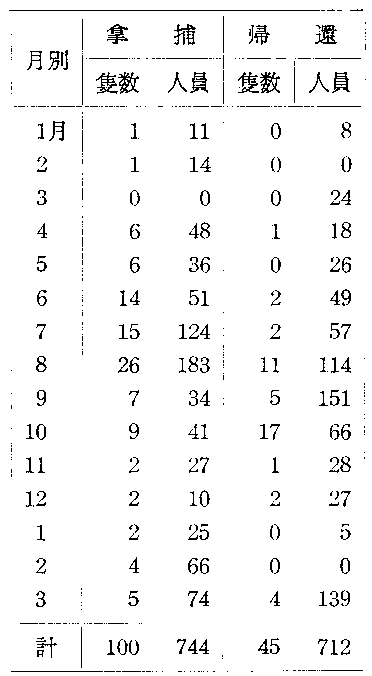
| 東欧関係 |
わが国は現在東欧地域においては、ソ連、ポーランド、チェッコスロヴァキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアおよびユーゴースラヴィアの諸国と外交関係を結んでいる。これらの諸国は相互にその歴史や国情は異なっても、いずれも現在共産主義の実現を目途としている点では共通であって、自由民主主義を基本信条とするわが国とは全く趣を異にする国々である。しかしながらわが国としては世界の平和を確保し、人類の繁栄をもたらすためには異った政治体制を有する国家との間にも、主権の尊重と内政不干渉という国際社会の基本原則を相互に守り合って平和的な交際を行なってゆくことが必要であると信じるので、このような方針にしたがってこれら諸国との外交関係をすすめて行くことに努めている。
これらの諸国の中、わが国と歴史的にも地理的にも最も多くの関係を有するのは、いうまでもなくソ連である。戦後日ソの共同宣言によって国交が回復されてから今日までにすでに五年余りを経過したが、なお両国の間には平和条約が結ばれるに至っていない。これは、わが国の固有の領土である北方の諸島をソ連が占領し、わが国への返還を拒んでいることによるのであるが、このような不自然な事態に直接、間接災されて、両国間貿易の著しい増大や文化面での交流にもかかわらず、日ソ間の関係は全体としてなお円滑を欠いていることを認めざるを得ない。
一九六一年は日ソ間にはとくに多くの出来事があった。百余日にわたる日ソ漁業交渉は例年のこととして、東京で開催されたソ連商工業見本市の開会式にはミコヤン副首相が来訪してわが国各方面の人々と接触した。右とほぼ時を同じくしてシベリヤの日本人墓地訪問のため遺族代表三十名が初めてわが国の航空機で訪ソした。ミコヤン副首相が池田総理大臣にもたらしたフルシチョフ首相の書翰は、その後両国首相の間に何回かにわたる卒直な書翰の往復を行なわしめることとなった。またソ連政府が突然核兵器実験の再開を決定し、しかも超大型爆弾の実験を行なったという報道は、わが国民の全部に深刻な衝撃を与え、わが国は史上唯一の原爆被災国として直ちにソ連政府に対して厳重な抗議を行なった。而してこのような多事の一ケ年を通じて、わが国が固有の領土として返還を求め続けている北辺の諸島の水域では、不法漁撈という理由でソ連側に拿捕抑留されるわが国の漁民が依然としてあとを絶たぬ状態であった。
わが国としてはソ連との間に今なお平和条約が締結されていないことを甚だ遺憾かつ、不自然なことに思っている。同時にまたわが国民は、ソ連政府こそわが国固有の領土を返還することによって日ソ平和条約への路をひらき得る立場にあると考えているのであって、ソ連政府が進んでこのような歩みよりを示すならば日ソ間の関係は現在よりもはるかに明るいものとなることは疑を入れないであろう。
なおその他の東欧諸国は、わが国との地理的な距りにも原因して、わが国との日常の接触面も全体としてなお極めて限られたものにとどまっているが、一九六一年わが国にルーマニア公使館実館が開設されたこと、わが国会の招待によりチェッコスロヴァキアの議員団が来訪したこと等のほか、わが国とこれら諸国との貿易面、文化面等の交流も次第に深められている。
一九六一年を通じ、池田総理は、フルシチョフ首相との間に、数次にわたり書簡の交換を行なった。これら書簡の内容は、コンゴー問題、ミコヤン副首相の訪日に関連する諸問題、領土問題および核実験に関するもの等多岐にわたっているが、これを問題別に列記すると次のとおりである。(核実験に関しては、別項「ソ連の核実験に関する日・ソ間応酬」参照)
二月二十五日、在京フェドレンコ大使は、小坂外務大臣を訪問し、コンゴー問題に関するフルシチョフ首相の池田総理あて二月二十二日付書簡を手交した。その要旨は次のとおりである。
私は、閣下に対しこの書簡をもって、アフリカの卓越した民族解放運動家、コンゴー共和国政府首班パトリス・ルムンバおよびその戦友達-上院議長ジョセフ・オキトおよび国防大臣モリス・ムポロ-の虐殺に関連して、ソ連政府の見解を申し述べる。ソ連邦においては、世界の他の多くの国におけると同様に、植民地主義者およびその手先達のこの罪悪に対する自然発生的な憤激の波が巻きおこった。この憤激の波は、コンゴーにおける植民地主義者達の暴虐を終わらせ、かつぺ・ルムンバおよびその戦友達を殺害した罪人共を厳罰せよとの要求と抗議の示威運動の形となってあらわれた。私がこの文章を書いているときでも、パトリス・ルムンバ殺害の報道が呼びおこした怒りとその死刑執行人達に対する嫌悪の感情をおさえるには大きな努力がいることをかくせない。あらゆる誠実な人の良心をかくも痛く傷つけた悪行に直面して感情を抑制することがいかに困難であろうとも、為政者の義務は、何よりも理性に立つ論拠と自国民の利益および平和の確保とを指針とすることである。時は、悲哀のもたらした傷痕を消しさるが、政治的問題は残るもので、これを解決しなければならない。
現在、われわれには、いかにしてコンゴーの友人達がコンゴー人民の正当な独立闘争を助けることができるかを新たに考えるばかりでなく、国連全体およびその将来にもふれる、より広範な問題についても考える必要が生じているように思われる。
すなわち、コンゴーにおける事件およびとくにルムンバ首相の殺害こそは、これらの事件においてハマーショルド事務総長がいかなる役割を演じたか、またハマーショルドの活動が平和の保持と諸国民の権利擁護とを使命とする国際機関としての国連の性格に一体いかなる陰影を投じているかの問題を真剣に検討せしめずにはおかない。
コンゴーで、何がおきたのか。今や、これは誰にも秘密でない。ルムンバおよびその友人達-コンゴーの強靱で忠実な愛国者達-は植民地主義的帝国主義列強の陰謀の犠牲となった。陰謀の源は植民地主義者の侵略から自国の独立を擁護するために、国連の支援に依拠しようとしたコンゴー政府の要請に対する回答として、ハマーショルドに隷属する外国軍隊がコンゴー領土に進駐してきたときにさかのぼる。西欧側の新聞は、植民地主義者達の新らしい塊儡たるイレオをめぐる好策を含めて、この悪行の準備に関する報道を文字どおり多彩に伝えている。
パトリス・ルムンバの肉体的抹殺は、植民地主義者達が、ルムンバは彼らの計画の実現途上に立ちふさがり、またコンゴー政府の首班は自国の完全独立とベルギー植民地主義者達からの解放をはからんとしていると確信するにいたったとき、実質上すでに予定されていたのである。
ハマーショルドに隷属する軍隊がコンゴーに到着するや否や、この軍隊はルムンバおよび彼を首班とする政府に対して使用された。飛行場は封鎖され、ラジオ局への通路は閉鎖され、正統政府の国内諸地方との連絡は断たれた。事態は、コンゴーの首相が援助を求めて派兵を要請した相手の機関たる国際連合に到着するために飛行機を受ける可能性さえも奪われるというところまで発展した。
国の分割が始まった。最も富裕な州カタンガは、コンゴーから事実上分離された。カタンガ州の首長には、ベルギー人の行政官に代わって、地方の住民から選ばれた替玉の傀儡チョンベが擁立された。彼は、植民地主義者達に身を売り、コンゴー領土のこの部分に対する彼らの支配の復活を陰蔽する衝立とならなければならなかった。
これらは、すべて何を意味するのだろうか。それは、国連の名において軍隊がコンゴーに送られたとき、ハマーショルドはすでに、なんのためにその軍隊が使用されるかを知っていたことを意味する。問題は、もちろんハマーショルド個人にあるのではなく、彼をしてその意志を執行させるものにあり、問題は、独立をかちえたかつての植民地諸国の国民を以前のように抑圧し、さく取しようとする独占資本家たる植民地主義者達の政策にあるのである。あたかも致命傷を受けた猛獣が自己の獲物を放さずに、まだ力のあるうちにこれを引き裂いてしまうように、ベルギー植民地主義者達とNATOの共謀者達は、かれらのかつての獲物であるコンゴーが独立の生活に目覚めて、自立しようとするのを到底容認することができないのである。
植民地主義者達のこの陰謀は、それ以前にもよく判かっていたといわなければならない。それ故、ソ連政府は第十五回総会において国連機関、主としてハマーショルドの行動と国連の現在の一方的な機構について批判を行なった。植民地主義者と平和の敵達が国連の前に横たわる国際的諸問題の解決を妨害しようと国連を利用して、いかなる戦術をとるであろうかは、当時すでに明らかであった われわれは、植民地主義的帝国主義列強が国連をいかに自己の利益のために利用しているかの明白な諸事例をみた。そして、もし社会主義諸国と中立政策を維持する諸国がこれを容認して沈黙したとするならば、これら諸国の指導者達は、現実的に事態を評価し、そこから必要な結論を引き出しえない単なる無能力者ということになるであろう。
植民地主義者達は現在、かれらによって搾取されている諸国民に対する往年の最も乱暴な支配形態を、より陰蔽、洗練された方式によって取替えようとしている。かれらは仮面をかぶり、替玉の人間を介して活動している。チョンベ、モブツ、カサブブのような小輩の叛逆者、裏切者で、自国民に奉仕せずに、最も多く代金を支払う者には誰にでも奉仕する人物はいつでもいるものである。
これらコンゴー人民の裏切者達は、いかなる資金によって生きているのであろうか。モブツとチョンベは、誰の財布から自己の匪賊達に代金を支払っているのだろうか。ベルギー植民地主義者達がかれらに代金を支払っていることは、誰にでも知られている。しかし、かれらばかりではない。われわれは、他の人達を名指さないが、閣下自身は、その源泉が相当広汎なものであることを知っておられるであろう。ベルギー政府の行動が、その軍事ブロックや植民地主義者ブロックの同盟国の支持なしには考えられないということは、明らかである。ベルギーは、コンゴーでは単に自己の政策を遂行しているばかりでなく、これは、NATO、CENTOおよびSEATOというようなブロック加盟国の政策でもある。それ故にこそ、ベルギー政府は己れが処罰されることのないという確信を抱いているのである。
歴史の進行を止め、植民地主義的圧制からの諸国民の解放を妨害せんとする者は、今日、相互保証によって連合し、全世界の自由愛好諸勢力に対して一致して対抗している。このことは、国連総会が今次の総会において植民地の諸国および諸国民に対する独立付与の宣言を採択したときに、明らかとなった。誰が被抑圧諸民族の解放に賛成し、誰がこれに反対しているかの明確な分水嶺が、そこに形成された。しかし、この場合にも植民地主義者達は、隠す所なく意見を述べようとせず、票決の際は棄権を選び、これによって彼らが総会の決定に賛成ではなく、その実施に抵抗するであろうということを示した。
結果は、長く待つまでもなくすぐ現われた。植民地主義者達は、独立のために闘争するコンゴー人民に対して積極的な攻勢を展開した。ルムンバおよびその戦友達の殺害は、植民地諸国民の解放に反対する者達が公然と不遜なテロ行為に訴えるにいたったことを物語っている。ルムンバおよびその戦友達の虐殺は、全世界に対してハマーショルド国連事務総長がコンゴー事件で果した嫌むべき役割を暴露した。コンゴー共和国の卓越した諸指導者の残忍な殺害は、国連執行機関の長に帝国主義者および植民地主義者達の傀儡がいるときこのような事態のいかに許し難いものであるかを悲劇的に示したものである。
ベルギーおよびその他の植民地諸国をして盗賊どもに武器を与えしめて盗賊どもによるルムンバ首相の奪取を助けた者は、ハマーショルドにほかならない。ハマーショルドは、植民地主義者達と陰謀をめぐらし、コンゴーの正統政府および議会を擁護すべき措置をとることを極力引き延すために、自己の総長の地位を利用した。ハマーショルドは、コンゴーへ赴いたときに相手かまわず誰とでも交渉を行ない、植民地主義者の傀儡たるカサブブ、チョンべその他の前に膝を屈したが、しかしルムンバの要請に基づいて若干の国連加盟国の軍隊がコンゴーに派遣されたにもかかわらず、ハマーショルドが国の正統な総理たるパトリス・ルムンバに会おうとしなかった事実は、意味深長ではないだろうか。パトリス・ルムンバおよびその他の為政者達が、雇われた死刑執行人どもの拷問を受け、そして卑劣な殺人準備の行なわれていることが全世界に明らかであったとき、国連事務総長は、手を洗って「不干渉」という偽善的な態度をとった。ルムンバの「逃亡」という乱暴な演出は、コンゴー独立共和国とその指導者達に対するハマーショルドの背信行為と直接につながるものである。腹蔵なくいうならば、実質的にはハマーショルドがルムンバを殺害したのである。殺害者は、刀やピストルをもっていたものだけではなく、主たる殺害者は、殺害者に武器を与えた者ではないだろうか。
以上が悲しむべき、憤激に値する事実なのである。そして、この事実は、ソ連政府をして、コンゴーにおけるハマーショルドの全方針が徹頭徹尾コンゴー人民の利益を卑劣にも裏切り、かつ、国連の諸原則と節度および名誉の初歩的な規範とを侮辱する方針であったという結論を下さしめずにおかなかった。このような者は、国連の指導的ポストにあるべきでない。われわれは、国連の黙認の下で行なわれた悪行を容認することはできない。われわれは、忌むべき殺人で自己の名をけがした者が国連事務総長であることを容認することができない。
「冷戦」がさらに一段と尖鋭化しないようにするため、また「熱い」戦争を防止するためには、国連の機構を当然改組しなければならない。ハマーショルドあるいは他の何人にせよ、とにかく現在の事態の下においては、植民地主義的帝国主義国列強の利益を擁護するその傀儡が、国連機関の長となるであろう。国連は、このような濫用が全廃される場合においてのみ、真の国際機関となりうるのである。
この問題についてのわれわれの立場は、昨年九月第十五回国連総会においてソ連代表が明白に述べたとおりであって、同総会においてわれわれは、植民地主義的帝国主義列強の利益を現在反映している事務総長の単独権力をなくするようにするために、国連機構の改組を提案した。当時われわれは、国連には事務総長は一人でなく、三人いて、その各々が世界に現存する主要な三つの国家グループ、すなわち西欧諸国の軍事ブロック加盟国、社会主義諸国および中立諸国の一つを代表するようにすることを提案した。
このような機構の下においては、各国家グループは国連において採択される諸決議の性格に影響をおよぼす平等な可能性をもつであろうし、そしてこれらの決議は、国連に加盟するこれら三つの国家グループに属するいずれの国の利益に反しても向けられないであろう。その時こそ、いずれの国家グループの狭い利益ではなく、社会および政治体制の如何にかかわらず、国連のすべての加盟国の共通の利益と、すべての国の平和と協力の利益とが、国連の活動を定めることになるであろう。これこそ、真の国際連合のあるべき姿であるが、世界の現実の状態に副わない現在の機構の下においては、そのような機関になっていない。
われわれは、国連において社会主義諸国が他の諸国家グループに対して、なんらかの特別の優位を獲得するようにしようとしているのでは決してない。国連におけるいずれかの国家グループの相対的な影響は不変のものではなく、時の経過とともに変化するものであることを念頭におく必要がある。もし現在の機構を維持し、帝国主義的植民地主義列強が自己に柔順なハマーショルドを通じて自己の政策を行ない、国連を支配するとしても、事務総長に対する影響をも含めた決定的な影響が他の国家グループ、たとえば社会主義諸国に移る時機が到来しうるのではないだろうか。しかし、われわれは、このことをも欲しているのではない。われわれが達成せんとするものはすべて、全国家グループが国連において真に同等な機会をもって自己の意志を他国に押しつけず、平和強化のために、平等の基礎において協力するようにすることである。しかしながら、現在の状態は、国連においてはその現在の機構の故に、数的にも人口的にも最も少い一つの国家グループが支配し、そしてこのグループが国連の執行機関を通じて、自己の侵略的植民地主義政策を行なっている。簡単にいえば、現在帝国主義列強は、社会主義諸国に対して、また植民地的従属から解放されて中立政策実施の途に立上った諸国に対して、国連を利用しようとしている。もちろん、このような方針は失敗に帰するであろう。もし何人かが国連において如上のような精神でいずれかの決議の採択に成功したとしても、このような決議はなんらの力をもたず、またもちろん、国連創設当時の任務、すなわち国際緊張緩和と軍事紛争の防止という任務に副うものではない。それのみか、自己の意志を他国に押しつけようとする帝国主義列強の試みは、情勢の一層の激化をもたらすのみである。
このような政策は、平和の事業に寄与せず、苦難を激発するものであって、危険な結果をはらむものである。コンゴーの事例で、このことはとくに明白に示されている。もしこの方針が継続されるならば、極度の尖鋭化を招来し、世界を第三次世界大戦の危険に立たせる慣れがある。
このような見通しを容認してよいであろうか。われわれは、決してこれを容認してはならず、またこの方向に向って事態の発展する可能性を排除しなければならないと考える。それ故にこそ、ソ連政府は、真に国連を強化し、これを生存力のあるものたらしめたいとする者、また国際情勢の緩和と平和の強化に賛成する者はすべて、正しい基礎に立つ国連改組の提案を支持せざるをえないと確信する。
首相閣下、私は、われわれの見解を隔意なく述べているのである。なぜならば、私は、ソ連政府がしっかりとこの立場に立っていることを閣下に知って欲しいからである。国連がすべての国の利益を平等に考慮する国際機関であることは外見だけで、実際には、国連の上級な公的地位にある傀儡達を通ずることなどによって、狭い国家グループの利益に奉仕していることを容認することはできない。このような状態は、諸国民の独立と自由を圧殺する政策をとっている植民地主義的帝国主義列強を益するだけである。
現在、植民地主義者の連合は、コンゴーにおいて自己の力を試している。かれらは、カサブブ、モブツ、チョンベ、イレオその他のようなコンゴー人中の傀儡の援助をえて、旧植民地を再びベルギーの権力下に引き戻そうとしている。もし植民地主義者達がこれに成功するならば、コンゴーにおける成功は、かれらを勇気づけ、自己の独立のために闘争しているアフリカおよびアジアのすべての国民の民族解放運動に対する不遜な攻勢政策を全戦線にわたってとらしめるようになるであろう。これを許さないようにする唯一つの手段は、植民地主義者達が狡猾に企らんだ陰謀を解明し、かつかれらの行動に、諸国民の自由および独立の真の友の団結と、コンゴーその他のアフリカ、アジアの新興諸国を新たに奴隷化せんとする計画粉砕の決意とを対抗させる能力を発揮することである。
コンゴーにおける諸事件の与える悲しむべき教訓は、植民地主義者達の受ける抵抗と反撃が弱まると、その行動がますます不遜になり、またコンゴーに対する侵略に直面して消極的であることは植民地主義者達を益するのみであるということである。
首相閣下は、ソ連政府がパトリス・ルムンバとその戦友達の非道な殺害に関連して、国連安全保障理事会でいかなる措置をとったかを御承知のはずである。コンゴーにおいては失われた一刻一刻が、コンゴー人民の独立の事業にとって宿命的なものとなりうるという情勢が醸し出された。現在ほど、躊躇、優柔不断および中途半端な措置が正当化されないときはないであろう。
安全保障理事会は、三回にわたりベルギーに対してその軍隊をコンゴーから撤退するよう呼びかける決議を採択した。しかしながら、侵略者達は事案上これらの決議を無視し、その軍隊のコンゴー撤退の外見のみを装った。コンゴーは再びベルギーの軍人と準軍人の充満するところとなり、かれらはコンゴー人民の愛国的勢力に対する懲罰を指導している。ベルギー側による国連決議のサボタージュに終止符を打つべきである。国連は、コンゴーにおけるベルギーの行動を断乎非難し、ベルギーに対しては、侵略者として国連憲章の定むる制裁を加えるべきである。
しかしながら、今やベルギーに対する処置のみでは不十分である。ベルギー人らは、その傀儡たるチョンベおよびモブツのために、ベルギーその他の諸国の将校によって指揮される相当大きな武装力をすでに形成し、新たな犯罪に備えてかれらを訓練している。
ルムンバの殺害は、すべてのことから判断して、チョンベおよびモブツ一味がコンゴーの全愛国勢力に対してなす軍事的進撃開始の合図であった。この関連において、コンゴー人民を新たな悪業から保護しうべき措置をとる必要が生じている。徹底的な手段は、一つあるのみである。すなわち、チョンベおよびモブツを即時逮捕して裁判にかけ、また彼らの一味を武装解除し、さらに侵略者をコンゴーから退去させることである。
国際的犯罪-コンゴー共和国の首相と上院議長および国防大臣の殺害-に責任がある殺人者を裁判に付し、厳罰に処さなければならない。この犯罪に対して誰に責任があるかは、全世界周知のとおりである。このような事態の下で、何んらかの調査委員会あるいは追審委員会を任命することが、なんの役に立ちうるだろうか。これは、長期にわたる「調査」の助けをかりて、すべての国の国民が要求するルムンバ殺害者の処罰を回避して問題を長引かせ、かつこの殺人が惹起した憤激と悲哀の烈情を時が払拭してくれるのを待とうとする植民地主義者達の策謀にすぎないということが明らかである。そして後日にいたって、きまって大尉程度の小輩が見つかるか、あるいはまずこういうであろう。すなわち、殺害者を探し出すことができなかったと。そしてまた、死刑執行人チョンベの不細工な作り事を繰返して、これは、カタンかその他のいずれかの村落の住民の自然発生的な憤激の結果発生したものだと。
われわれは、コンゴー人民の民族的英雄抹殺の組織者達が、植民地戦争において公然と人民の血を流し、かつかれらにとって役に立たない者や抵抗する者の死を用意しつつ、自己の雇人を通じて隠密の奸計をめぐらしている徒輩中の老練の殺人者であることを知っている。彼らの手段は、すでに何十年、何百年もにわたって知られており、そしてこれについては文献中にも十分に納得のゆくように記述されている。
もし現実的なものの見方をするならば、昨年の夏安保理事会の周知の決議の後にハマーショルドの指導の下で実施されたいわゆる「国連のコンゴー工作」は、安保理事会が考えていた目的を達成しなかったばかりでなく、全く正反対の結果を招いた。国連の委任をうけた軍隊がコンゴーに到着したとき、コンゴーには住民の圧倒的多数の支持の上に立つ、正当に選挙された国会と政府が活動しており、また国内には民主的自由が存在し、人民は国民経済の建設と取組んでいた。しかし、半年有余の歳月が流れると、どうなったろうか。これらはすべて破壊され、国会は追払われ、民族的巨頭達は殺害され、コンゴーの領土は分割され、そしてその領土の相当な区域では再び外国の植民地主義者がわがもの顔にふるまい、かつかれらの雇われ死刑執行人どもが暴虐にふるまっている。コンゴーの愛国君達の血は流され、また、外国干渉者どもの飛行機からの爆弾で発火した火事場の煙を、風が吹き散らしている。そして、これらすべての上に、国連の青い旗が飜えり、これらのすべてをハマーショルド氏に隷属するコンゴー領最大の武装力が冷やかに眺めている。これが、コンゴーーにおける「国連の行動」のみじめな成果なのである。
すべてこれらは、国連に対する諸国民の信頼を破壊するものである。今や情勢はますます複雑化しつつある。一部の国々の軍隊の撤退後、コンゴーの国土に国連旗の下で残っているのは、主として植民地主義列強の連合と直接または間接に結びつき、そしてコンゴー共和国に対して非友好的な諸勢力である。
もし事態を成行きのままに放置するならば、帝国主義的干渉者達の軍隊は、ベルギーの植民地主義者達とともに「国連軍」の外見の下で、コンゴー人民とその正統な政府に対して行動するであろう。ハマーショルドの政治的性格を知っていて、誰が、西方諸国軍事ブロックの軍隊をコンゴーの国土に呼び入れるような直接の挑発をかれはなすものでないと考えることができようか。今なお国連軍中に自国の部隊を保持している中立諸国については、これら諸国がコンゴーに派遣したその軍隊の使用目的につき影響力をもつ可能性の従来より一層少なくなるべきことはもちろんである。
ソ連政府は、これらのすべての事態を考量して、コンゴーの独立のため、また国連の威信のために、いわゆる「コンゴーにおける行動」をすみやかに停止し、そこからすべての外国軍隊を撤収し、もってコンゴー人民に対して、その国内問題を自ら決定する機会を与えるべきであるとの結論に到達した。
もちろん、この要求に対して、植民地主義者とそのあらゆる種類の追随者達は動揺し、そして外国軍隊の撤退はコンゴーにおける内乱の危険を誘発するとか、コンゴー人を外国の後見なしに放置してはならないとか、またコンゴー人は自分で事態を処理することができないなどと叫ぶであろう。われわれは、これらの「論拠」を見えすいた偽りと考えるものであって、これらの論拠は、植民地主義者達がコンゴーから引揚げて、コンゴー人民を自国の主人たらしめることを欲しないことから生じたものである。それ故にこそ、かれらは、コンゴーの地に戦争をもたらしたものは外国の干渉者たる植民地主義者達であることが周知のとおりであるにもかかわらず、コンゴー人民を誹謗しているのである。
コンゴーに平和、秩序および静謐が支配的となるためには、何よりもまずこの国の人民をあらゆる形の外国干渉から解放し、パトリス・ルムンバの後継者アントゥアン・ギゼンガを首班とするこの国の正統政府に対して援助と支援を与えることが必要である。周知のように、この政府は、「コンゴー共和国の平和、秩序、統一、合法性および保全を回復するため」の援助を求めてすべての国に呼びかけた。ソ連政府としては、コンゴー共和国に対して友好的な他の諸国とともに、このような援助をコンゴー人民とその正統政府に対して与える用意がある。
コンゴー国民の愛国的勢力とその正統政府に対して決定的な援助を与えることは、コンゴーを相互に競争する国家群間の「冷戦」の舞台と化すであろうというものが往々いる。私の見解によれば、このような問題の建て方は、根本的に正しくない。そして私は、このような考え方は、植民地主義者達がコンゴー国民に実効ある援助を与えようとする諸国家を分裂させるために、とくに流布しているものと信ずる。コンゴー人民は、自己の完全解放と独立のために闘争しているのであるが、この場合、一方の諸国家は植民地主義者達を支援してコンゴーの内政に干渉し、他方の諸国家は侵略と外国のコンゴーに対する内政干渉に反対している。ここに、コンゴー問題における諸勢力の分界線が現実に存しているのである。ルムンバとその戦友達の虐殺は、この不動の事実を新しい力で表面化したにすぎない。
コンゴーを植民地主義者達の侵略から解放し、国の独立を回復することを目指す措置の実施は、われわれの見解によれば、安全保障理事会の決議にしたがって軍隊をコンゴーに派遣したアフリカ諸国の代表者から成る委員会を創設することによっても、これを促進しうるであろう。この委員会の任務は、パトリス・ルムンバの代理で現在コンゴー共和国首相の職務を執行しているアントゥアン・ギゼンガを首班とする同国の正統政府と完全な接触を保って行なう侵略者の撤退、およびすべての形の外国干渉終止の措置と、コンゴーの政府および議会の正常な活動のための条件設定とに対する監視を含むべきであろう。
西欧のどこかでは、ルムンバの生存中にかれを苦しめ、ひそかにベルギーの植民地主義者とその雇人達にコンゴーの国民的英雄の肉体的抹殺をけしかけた者どもの声が、衷心よりの弔意の表明と混淆している。このような偽りの弔意の表明にどんな価値があるかは、次の事案が示している。先般安保理事会においてコンゴー民族解放運動の領袖達の虐殺を非難する内容の決議案が上程されたとき、殺人事件について涙を流す恰好をした人々は、この決議に賛成の手を挙げなかった。決議中には、殺人犯の姓名さえも挙げるではなく、ただ殺人自体が非難されているだけにすぎなかったのである。現在、平和愛好の美辞、"冷戦"激化に反対する麗句あるいは軍事紛争に対する偽善的警告をもって偽装しようとする人がいる。このような言明の目的は明白であって、それは、諸国民をしてルムンバの抹殺を容認させ、また植民地主義者達の替玉たる傀儡どもがコンゴーの愛国主義的勢力に対して優位を占めるような条件を設定しようとするものである。しかし、われわれには、善行の一致しない人々の説得と偽りの論拠に属することは、先見の明のない政策以上のものであるように思われる。
われわれは、ここでは実質上、二十世紀の初頭に米国大統領テオドル・ルーズヴェルトの提唱した「手中に大きな棍棒をもちながら、柔かな口調で話す」という有名な帝国主義的政策の原則を現在適用しようとする試図を相手としているのである。西欧のある為政者達が、今日でもその演説中において「大きな棍棒」の命題を発展させていることは偶然でない。
棍棒は左して恐ろしいものではないと、いいえよう。もちろん棍棒にはいろいろある。たとえば、ロシアには昔から、「小さな棍棒」を勤労の具として謳った歌もある。しかし、テオドル・ルーズヴェルトが讃美し、現在そのある後継者達が振り廻している「大きな棍棒」は、全く別のものである。これは、諸国民に対する暴力であり、弱小国を武力によって隷属させようとするものである。
いずれかの小国に対して侵略政策をとっても、たとえば、キューバやパナマの如きをその犠牲とした侵略者達は、当時の条件の下においては罰されずにすんだが、われらの世紀の黎明期においても、それはもちろん罪悪な侵略的政策であった。しかし、今や時代は変った。今やこのような政策は、成功すべきなんらの機会をももたないのみか、この政策を実施しようとする人々にとっては、死活上の危険をはらむのである。今や他の諸国家も、西欧のある政治家達が「大きな棍棒」とよんでいるものをもっており、そしてこのようなものによる威嚇の支持者達は、その望みを托しているものよりも、はるかに大きな打撃を与えうる「棍棒」のあることを究局において知らないもののようである。かれらは、このような政策がこれを用いる人々の全く予期しないような結果をもたらすことを知らないもののようである。このような政策上の方途は、行き詰るか、あるいはさらに悪く、破局をもたらすだけであるということは明らかでないだろうか。
ダレスとアイゼンハワーは、周知のように、その外交政策を「力の立場」と「大きな棍棒」の原則の上に打ち立てようと試みた。しかし、何人も、この政策が彼らの国に栄冠をもたらしたとあえて断ずることはないであろう。逆に、現実的に思考するアメリカの為政者達は、これが、アメリカとその国際的威信に高価な代償を要した全面的失敗の政策であったことを正しく指摘している。
このような政策は、すでに過ぎ去った時代の産物である。現在は「棍棒」に頼らず、理性の上に立たなければならない。ソ連邦もまた、「大きな棍棒」をもつにいたったことを誰でも知っている。しかし、ソ連邦は威嚇や「棍棒」を振り回す政策に断乎として反対し、その政策においては、すなわち理性の上に立ち、戦争の脅威を除去し、平和を強化するために、国家間の合意達成に努めている。もし経験が、とくに近年の経験が何物かを教えるとすれば、それは、何よりもまず列強は他国の問題に対する干渉と他国の自由の扼殺者たる役割を演ずる試みとを断念し、国際緊張の緩和達成と重要な国際的諸問題、なかんずく軍縮問題の一致をみた解決とにその努力を集中しなければならないということである。
恐喝と威嚇ではなく、各国の主権を厳に尊重し、かつ相互の利益に現実的な考慮を払うこと、これが、ソ連政府の主張しているものである。
首相閣下、平和を強化し、かつ各国民の安全を確保するためには、現代の重要な国際的諸問題について、各国間に共通の言葉を見出すようにすることが要請される。私は、貴我両国政府がコンゴー共和国の自由と独立を擁護する事業について、共に努力するものであることを期待したい。
これに対し、池田総理は、三月八日、フルシチョフ首相あて大要次の如き書簡をもって日本政府の見解を明らかにした。
私は、コンゴー問題に関するソ連政府の見解を述べた一九六一年二月二十二日付貴書簡に関連し、日本政府の考え方を申し述べたい。
まず最初にわが国は独立達成を目指す植民地諸民族の熱望には万腔の同情を寄せるものであり、その独立と国民の幸福なる生活の建設には同情と協力をもって臨むものであることを明らかにしたい。さらにわが国はせっかく独立を獲得しながら不幸な事態の下に不安な生活を送っているコンゴー国民に深い同情をもつと同時に、コンゴー共和国に法と秩序が速やかに回復し、コンゴー国民が一日も早く外部からの干渉なしに国民自らの手で自らの欲する国内体制を築き、平和と安定の中で統一と独立を確保できる日がくることを切望するものである。従ってわが国は、コンゴー共和国内に東西の冷戦と植民地主義を持ち込まず、法と秩序の回復と和解に基づく国内の統一の早急な実現のため、世界の各国が協力して同国を援助することが必要であると考える。このような援助のための最も有効な手段を提供するものは国際連合であり、コンゴー問題の解決に当っては、国際連合を除いて他に適切な援助の方法はない。
ソ連政府は、コンゴーにおける従来の国際連合の活動を一方的に植民地主義の手先と断定しているが、日本政府は、このような一方的断定に同調しえない。国際連合は、コンゴーに対する外部からの干渉を排除し、かつ、コンゴー国内に冷戦をもち込まないようにするためにこそ、コンゴー問題に介入しているのであり、国際連合のほとんどすべての加盟国が国際連合のこの任務を支持している。国際連合がコンゴーにおける植民地主義の手先となったことはなく安全保障理事会および第四回緊急特別総会の諸決議の規定の範囲内で治安の維持のため最善をつくしてきたことは、事実に徴しても明らかである。日本政府は、二月二十一日安全保障理事会が採択した決議が有効に実施されるようすべての加盟国がその実施に協力すべきものであり、また同決議の規定に違反する国際連合を通じない一方的行動は、厳重に禁止されるべきであると信ずる。コンゴーにおける従来の国際連合の活動に将来さらに改善の余地ありとすれば、このような改善は、全加盟国の全面的協力によってのみ達成されるものであることを全加盟国は銘記すべきである。
ソ連政府は、コンゴー問題を契機として国際連合事務局を改組して三グループを代表する者で構成するよう要求しているが、日本政府はこの主張に同調しえない。事務総長は、国際連合に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位をもち、いかなる国、いかなるグループの利益の代弁者であってもならない。それにもかかわらず、事務総長がグループの利益を代表すべきことを前提とし、この前提の上に事務局を改組すべしとの主張は、事務局をそれぞれのグループの政策の手段とするものであり、ひいては国際連合の機能を完全に麻痺させ、その瓦解を招くものといわざるをえない。
以上申しのべたとおり、日本政府は、コンゴー問題に介入している国際連合の目的にかんがみ、すべての加盟国がコンゴー問題解決に当っての国際連合の努力に最大限の支持と協力を与うべきであると考える。
東京におけるソ連見本市に出席のため訪日したミコヤン第一副首相は、(別項ミコヤン第一副首相の来日」参照)池田総理との会見に際し、要旨左記のとおりのフルシチョフ首相より池田総理あて八月十二日付書簡を伝達した。
私は、ソ連大臣会議第一議長代理ア・イ・ミコヤンの訪日の好機を利用し、貴下に私の挨拶とともに、日本国民への平和、幸福および繁栄の希望を伝えたいと思う。
われわれは、ア・イ・ミコヤンがその開場のために日本へ派遣される東京のソ連見本市が、互恵の通商・経済交流の一層の発展を助長するとともに、ソ連邦と日本国との間の善隣関係および相互理解をはかる途上における重要な道標の一つになることを期待する。
ソ連政府は、東方におけるわれわれの隣邦たる日本国と、平等、独立および主権の相互尊重、相互の内政不干渉に基づいて、平和、友好および協力の関係を樹立することを誠実に希求している。ソ連邦は、話し合いによってすべての未決定の問題を日本国と調整し、貴我両国の関係を完全に正常化したく思っている。われわれは、政治・通商・経済、科学および文化の各分野で互恵の交流および協力を発展させるためのすべての可能性があると確信している。このような協力は、日本国およびソ連邦の両国民の切実な利益に答え、両国民にもっぱら福利をもたらし、かつ貴我両国の安全と極東の平和とを強化するであろう。
しかしながら、ソ連邦と日本国との協力を発展させるための可能性は、遺憾ながら十分に活用されていない。貴総理、私がこの関連において、日本国がアメリカ合衆国と軍事同盟を締結しており、そして日本国領域内に外国軍事基地の維持されていることは、貴我両国間の信頼の増進と関係の完全正常化とを助長しえなかったことを指摘しないならば、私は誠意を欠くことになるであろう。しかし、私は、日本国の国土から外国の軍隊および軍事基地が一掃されて、ソ連邦と日本国との間の善隣関係を一層増進するための途を開く時が到来するものと信ずる。
私は、この書簡においてこの問題のすべての面に触れようとは思わないが、ただ貴総理にここで強調しておきたいことは、ソ連邦が軍事ブロックと他国領域にある軍事基地との完全解消ならびにすべての国家間の友好および協力の発展をこれまでも常に断乎主張してきたが、今後も不屈に主張するであろうということである。ソ連政府は、破壊手段生産の分野における競争に代わって、物質的福祉と精神的財産とをつくる分野における競争に入るように絶えず呼びかけている。
われわれは、平和の維持と国際の安全とをよりよく保障するものは、軍事ブロックや軍事同盟ではなくて相互理解の実現と友好的協力であると深く信じている。ソ連邦と日本国との政治および社会体制が異なっていることは、日本国およびソ連邦の両国民の実り多い協力を妨げるものであってはならない。
貴我両国間の関係には、暗い面の外に、明るい肯定的な面もあることを満足をもって指摘したいと思う。私は、この肯定的な面としては、貿易、文化および科学の交流を発展させる上に一定の進展がみられたことをあげたい。貿易取極が調印されて、これに基づいて貿易が拡大し、一連の長期貿易契約が締結され、また科学および文化の分野における交流も行なわれている。
われわれは、貿易関係の拡大をとくに重要視しているが、これは、互恵平等の貿易が、国と国の関係をより緊密かつ友好的にし、また社会・経済体制の異なる各国を平和共存および協力へ導く頼もしい橋であるからである。貴総理も御承知のように、ソ連邦は、世界の多くの国と広汎な貿易を行なっている。われわれは、日本国とも貿易を発展させたく、この発展には、ソ連邦のみならず日本国も関心を寄せているように、私には思われる。貴総理が、一再ならず声明されたように、日本国は、その商品を販売し、かつ必要な原料を入手するために、安定した外国市場をとくに必要としている。貴我両国が地理的に近接していることと、各自の必要とする商品をお互いにもっていることは、ソ連邦と日本国との貿易を成功裡に発展させるための良好な条件をつくっている。両国の政府および関係会社、貿易団体の努力によって、この貿易をより強固な長期的な基礎の上におくことが課題となっているのではないかと思われる。私は、双方がこれに向ってまい進するならば、近い諸年の間にソ連邦と日本国の貿易額を三~四倍、あるいはそれ以上に拡大できるであろうと信ずる。
現在、ソ連邦と日本国との間においては文化交流の問題に関する協定の締結交渉が行なわれている。ソ連政府の見解によれば、これは、極めて重要かつ必要なことである。実践の示すところによれば、貴我双方は文化の分野において互いに見せ合い、互いに学び合うべきものをもっている。日本国国民は、ソヴィエト芸術の多くの代表的なものをすでに観賞し、かつわが国の芸術家を友情をこめて暖く迎えた。ソ連邦においても日本芸術の代表者は暖く迎えられている。極く最近わが国においては日本の古典劇歌舞伎の公演が大成功をおさめた。科学および技術の分野における交流は、調整されつつある。この分野における日本の諸成果は、わが国においてよく知られている。他方、日本の科学者は、世界に当然のことながら認められ、かつとくに人間による宇宙征服の大成功への道を開いたソヴィエトの先進科学および技術の諸成果を興味深く研究している。
貴我両国が適当な協定、例えば日本国がイギリス、フランスその他の諸国と締結しているような型の協定を締結するならば、それは、ソ連邦と日本国との間の科学・文化の交流と協力とを両国民の利益となるように一層発展させるべく助長するであろうということにつき、貴総理は、私に賛同されるものと期待する。
ソ連政府が、日本国とソ連邦との間の関係に関する限り、日本国政府の提起することがあるべき共通の利害関係を有するいかなる問題をも検討する用意があることは、いうまでもない。
最後に、私は、貴総理とア・イ・ミコヤンとの間に可能となった今次の意見交換が、ソ日関係を改善する目的のために利用されるよう期待するものである。
以上にみられるとおり、右書簡は、日ソ両国の関係全般にわたって、ソ連政府の所信を述べているので、在ソ山田大使は、グロムイコ・ソ連外相に対し、池田総理よりフルシチョフ首相にあてた八月二十六日付書簡を手交した。右は、日ソの関係を中心として、わが国の外交の基本理念を明らかにしたものである。その要旨は次のとおり。
私はミコヤン・ソ連第一副首相の訪日に際して伝達された閣下の御挨拶に謝意を表明するとともに、ソ連国民の平和、幸福および繁栄をお祈りいたします。私もまた閣下と同様に、東京で開催されているソ連商工業見本市が客年貴地において開催された日本見本市と同様多大の成功をおさめ、日・ソ両国間の通商経済交流の今後の増進、発展に寄与するであろうことを期待しております。
閣下は、ミコヤン第一副首相に托された書簡の中で、日ソ両国の関係全般に関する閣下およびソ連政府の所信を述べられました。よって私もまたこの機会にとくにわが国と貴国との関係を中心として、わが国の外交の基本理念を明らかにしておきたいと考えます。
閣下は、ソ連政府が平等、独立、主権の相互尊重および相互内政不干渉の諸原則に基づいてわが国と平和、友好および協力の関係を樹立することを心から希望していること、および、対日懸案のすべてを話し合いによって解決し、両国間の関係を完全に正常化したいと考えている旨を述べられました。閣下は、また、日ソ両国民がかくの如くして生活の各分野で、双方の利益になるような交流と協力を発展させるための諸々の可能性があるとの見解を表明されました。これらの点については、私も閣下と見解を一にするものでありますが、私は、かような可能性は日ソ両国が相互の立場を認め合い、その基礎の上に立って日ソ両国がおごそかに宣言した国際約束たる日ソ共同宣言に忠実である場合にのみ発見できると信ずるものであります。
閣下は日ソ間の国交の完全な正常化に書及されましたが、それには両国間の平和条約を締結することが必要であります。日本国民は、ソ連政府こそ日本国固有の領土を返還することによって、平和条約への路を拓き得る立場にあると考えております。しかるに閣下は、わが国が米国との間に安全保障条約を結び、わが国の領土内に外国の軍事基地が維持されていることをとりあげ、あたかもそれが日ソ両国間の関係の正常化を妨げているかのように主張されるのであります。しかしながら、日ソ両国が両国間の関係を正常化する意図をもって共同宣言に署名した当時、すでに日米間の安全保障条約が存在していた事実は閣下も御承知のとおりであり、日ソ共同宣言は、国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的または集団的自衛の権利を確認しているのであります。しかのみならずこの日米安全保障条約は、その後わが国民の意志に基づいてさらに合理的に改定され、国連憲章に基礎を置く防衛的性格を有するものであることが一段と明らかにされております。したがってソ連政府が、安保条約は、ソ連その他の平和愛好国を脅威するものであるからかかる条約の存在に無関心たりえないと主張し、この条約の解消を主張することは、日本国民の全く理解しえぬところでありまして、およそ他国の安全を脅かす意図を有しないものにとっては、この条約の脅威を云々する理由は存在しないはずであります。他国の外交・防衛政策について一方的、主観的な解釈を加えてこれを論難しその政策の改変を呼掛けるごときは、閣下がソ連政府の方針として述べられている内政不干渉の原則と相容れないものであると申さねばなりません。
ソ連政府が軍事ブロックの完全な解消を主張しながら、旧安保条約の締結以前すでに中共との間にわが国を対象とした同盟条約を締結していること、および、ごく最近北朝鮮との間にいわゆる相互援助条約を締結したことは、この貴国政府の主張と全く矛盾するものでありまして、このことはソ連が東欧諸国に軍事基地を保有していることとともに日本国民の納得し難いところであります。今日米国の軍事基地がわが国のみならず英国等多くの国にも存在する事実は、閣下のつとに御承知のところであります。
わが国は、自由民主主義を最高の政治理念として追求するものでありまして、この方針は、今後とも不動のものであります。しかしながらたとえわが国と政治理念を異にする国家であっても、紛争はつねに平和的に解決し、武力による威嚇を慎み、他国の内政には絶対に干渉しないという原則を厳守するものである限り、わが国はこれと善隣友好の関係を樹立するに吝では無いのでありまして、前述した日ソ共同宣言もわが政府としてはこのような精神に基づいて署名したのであります。しかしてわが国は、今後ともつねにこのような精神に基づき、相互理解と友好的協力を通じて世界の平和に寄与するよう努力するものであることをこの際重ねて強調しておきたいのであります。
最近数年間における日ソ間の貿易伸張の実績は満足すべきものであり、私は、今後ともその拡大に努力したいと考えます。その際両国間の貿易を、国民の消費生活向上のために必要とする物資の面で拡大するならば、日ソ貿易の規模はさらに著しく増大すべきことは明らかであります。日ソ文化の交流は、近年次第に活発となっておりますが、日本政府としても近く適当と認める形式の文化取極案を貴国政府に提示する用意をしております。
ミコヤン第一副首相は、今回の日本滞在中、日本の国民大衆の物質的福利と精神的財産の状況を親しく御覧になりました。日本政府の所得倍増計画は、日本の国民生活を今後ともより豊富なものといたすでありましよう。なおまた私は、ミコヤン第一副首相が今回の訪日において、片寄った政治的主張をもった一部の人々に限らず、ひろくあらゆる階層の人々に接してわが国の真の姿を知られたことは、今後の日ソ関係の改善に貢献するところが多いと信じるのであります。
私は、閣下が破壊手段の生産の競争に代って、物質的福利と精神的財産をつくる競争に入るよう呼びかけられたことに賛意を表するものであります。私は、ソ連政府が困難な条件を付して原水爆実験停止の協定の成立を不可能ならしめざるよう切望するものであります。原水爆戦争は、交戦国はもとより全人類の破滅を意味することに想いをいたし、ソ連政府が恐るべき原水爆兵器の製造を中止し、またその貯蔵をも廃棄することによって世界平和の確立に寄与することを衷心より望むものであります。
今日平和こそ世界人類の共通の願いであり、繁栄こそすべての国民の望みであると考えます。この立場に立って両国が虚心坦懐に話し合って、今後懸案を解決することを希望するものであります。
これに対して、九月二十九日、在京スズダレフ臨時代理大使は、武内次官を訪れ、再び要旨下記のとおりのフルシチョフ首相より池田総理あて九月二十五日付書簡を手交した。
東京におけるソ連商工見本市の首尾よき開催についての協力とソ連大臣会議第一議長代理ア・イ・ミコヤンに対して貴国において示された厚遇とに対して、閣下御自身および日本政府に謝意を表明したいと思います。われわれの見解によれば、ア・イ・ミコヤンの日本訪問は、貴我両国間の実務的な善隣関係を増進するために非常に有益でありました。この訪問の当時に、ソ・日両国民は善隣国民にふさわしく平和かつ友好裡に生活すべき自分達の意思を確認しました。
貴簡中には幾多の重要な問題が触れてあるので、これらについて自分の所信を表明したいと思います。
貴下は、ソ連政府が日本との一切の懸案問題を話し合いによって解決し、両国間の関係を完全に正常化したいとの念願に原則的に賛同するものである旨を述べておられます。
ソ連政府は、以前からこの方向に向かって積極的に行動する用意があります。われわれは、両国関係が故鳩山総理のもとで醸成され始めたように発展するよう心から希求するものであります。
問題は、今やソ・日関係の完全な正常化のためおよび貴我両国間に双方に有利な、多面的関係を増進させるために具体的手段をとるということにあります。
貴総理は、ソ・日関係の完全な正常化のためには平和条約の締結を必要とすることに同意する旨を書いておられます。しかし、貴下のこの問題の取扱方は、遺憾ながらこの重要な問題を行詰りから打開しようとする熱意を決して証明するものではありません。そればかりでなく、日本国政府が今後もこの途上に人為的障壁を作り出そうとしているという印象が与えられるのであります。領土問題は、一連の国際協定によって久しき以前に解決済みであるにかかわらず、貴下がこの問題を新たに持ち出されたことを、われわれは、以上のように評価せざるをえないのであります。
日本国の領土でない領土の日本への返還問題をどうして提起できるのでしょうか。日本国自身がよく知られている領土に対するすべての権利、権原および請求権を放棄していないのでしようか。「固有の領土」についての問題を自ら提起することによって、昼下は、一歩後退し、サン・フランシスコ条約の当該諸規定の承認を避けようとされるのでしょうか。直言しますが、このような態度は、両国民がもちろん関心をもっていないソ・日関係の激化をもたらすだけであります。
貴下は、ソ連邦と日本国が相互により良く理解することの重要性を正しく強調しながら、同時に日ソ関係に関連する幾多の問題についてのソ連邦の立場を理解する希望を表明しておられません。このことは、外国軍事基地ならびに新日米条約締結の国際的結果に関してのわれわれの立場を、貴下は何故か貴国の内政に対する干渉と解釈しておられる一事によっても立証されます。われわれがわが国に隣接する国の領土をわれわれと他の平和愛好国民に向けられた軍事前哨基地と化すことを非難したソ連政府の発言を、どうして内政干渉ということができるでしようか。沖縄島を含む日本国の領土に、ソ連邦、中華人民共和国、朝鮮人民民主共和国に対して直接に向けられた一連の外国軍事基地が設けられ、外国のロケット装置およびその他の最新の軍事技術の手段が設置されていることをどうして傍観することができるでしょうか。
ソ連政府は、周知の幾多の文書において日米条約の真の本質をあますところなく暴露しており、日本国政府は、この条約によれば、新しい諸条件のもとで自発的に自国の領土を外国の軍事基地として提供したのであります。これらの文書において、あたかも新軍事条約が防衛的性格をもち、かつ国連憲章の規定と両立するものであるという日本国政府の口実の根拠なきことが示されています。われわれは、新軍事条約の締結が日本の国土に軍国主義と侵略の種子の成長を助長し、何よりもまず極東の平和の事業にとって危険な結果をはらんでいるものであることを一度ならず貴下に率直かつ公然と申し上げました。
ソ連政府は、わが国の安全上の利益に直接に触れる行為に対して警告の声を高めざるをえません。これは、アメリカ合衆国およびその同盟諸国が対独平和条約締結に関するわれわれの提案に関連して、欧州において軍事紛争を引きおこすという露骨な脅迫に訴えている現在、特別の意義をもっています。
これらの諸条件のもとにおいては、日本国における米国の基地がソ連邦およびその他の平和愛好諸国に対して利用されないであろうという効果的な保証を、誰が与えうるかという問題が当然起ってきます。
しかし、私は、基地問題に関する今一つの考えを強調したいのであります。それは、すなわち次のことであります。
日本国における外国の軍事基地は、隣接諸国家にとってのみならず、日本国民自身にとっても脅威となっています。真摯な考え方をする人々は、軍事紛争の場合に外国軍事基地の主人公たちが日本国民の意見および民族的利益を考慮するであろうと信じうるでしようか。
だが、このことは、日本国民にも数えきれない災厄を約束しています。貴下は最近ソ連新聞に公表されたCENTO軍事同盟の秘密書類を知悉されているものと、私は思います。この書類が証拠立てているように、この「防衛」ブロックの指導者たちは、ブロックを通じた自分たちの仲間の領土をも含めた、尨大な領土を、かれらの-繰り返えして申しますが、かれらの-裁量で、死の地帯に変えようとしています。このことを決定するのは、NATO、SEATO、CENTOの諸軍事ブロックを主導している国々の代表者を首班とする参謀部でありましよう。
ソ連邦はあらゆる軍事ブロックの創設と他国領土上に軍事基地をつくることに一貫して反対しています。私どもは已むを得ない対抗措置としてのみ、一連の相互援助条約の締結を行ないました。このことが必要となったのは、西側列強が、軍事基地とブロックの廃止、集団安全保障体制の創設を目指すわが方の一切の提案を拒否したからであります。これらの国は、例えば、ヨーロッぱにおける二国家群-NATOとワルシャワ条約-間の不侵略条約を締結することさえ望まなかったのであります。ソ連邦と中華人民共和国は、ソ連邦、中国、日本、米国その他の太平洋沿岸諸国との間の平和および友好条約の締結ならびに太平洋全域を非原子地帯と化する提案を一再ならず提起してきました。しかしながら、これらの提案もまた日本国政府およびその他若干の諸国の政府の側の当然の注意は受けませんでした。
ソ連邦は、他国領土内にあるその軍事基地をすべて清算しました。貴下も良く御承知の如く、とくに、日本の近辺にあるソ連の海軍基地も清算されました。米国およびその軍事ブロック上、協定上の仲間は、われわれの例に従いませんでした。それどころではなく、彼らはソ連政府の平和的提案を拒否し、ソ連邦およびその友好諸国周辺の軍事基地をますます拡大し、犯罪的冒険実現のために侵略勢力によっていつでも利用されうるロケット核兵器をこれらの基地にますます多く蓄積しつつあります。
貴総理は、その書簡の中で、破壊手段生産の分野における競争の代りに、物質的福祉と精神的価値の創造の分野での競争に移ろうというわれわれの呼び掛けに同意しておられます。まさにその通りで、われわれは、この目的に向って絶えず、かつ熱心に努力し、その実現のためにはいかなる努力も惜むものではありません。もしも米国および他の西側諸国の側からの執拗な抵抗がないならば、人類は今直ぐにでも、全面完全軍縮に関するわれわれの提案の具体化をみることができるでありましよう。
遺憾ながら、国際連合における討議においても、またその他の場合においても、世界は今までのところ全面完全軍縮、核兵器の禁止およびそのストックの廃棄に関する提案を支持する日本国政府の確固たる不撓の声を耳にすることがなかったのであります。これらの極めて重要な問題が解決され、人類が永遠に、確固たる平和を見出だすためには、善意の願望のみに止まっていてはならないのであります。もしも日本国政府がこの方向において行動することを望まれるならば、日本国政府は疑いもなく、全面平和の強化の事業に協力する用意についての貴下の言葉を具体的行動によって裏付けるために必要な方法と手段を見出だすでありましよう。われわれとしてはこれを歓迎するのみであり、またそれのみかこれを支持するでありましよう。
私は、結論として、われわれの見解では、相異なる国々の指導者の間の直接の接触と率直な意見交換、とくに隣接国間の接触は、よりよき相互理解の達成のために常に重要な意義を有するものであることを指摘したいと思います。一連の問題に関する意見の不一致にもかかわらず、われわれは、われわれ両国間に真の友好善隣関係が確立されうること、また確立されなければならないことを確信するものであります。しかしながら、このためには双方の努力が必要であります。
それでは全世界の平和のために、われわれ隣国間の関係を平和と友好の精神をもって打樹て、両国国民の福祉のために互恵の交流および実務的協力を一層発展させるよう努力しようではありませんか。
前述の九月二十五日付フルシチョフ首相書簡は、軍事基地の問題、日米安保条約の問題、軍縮問題等幾多の重要な問題に触れたほか、懸案の北方領土問題に関しても、ソ側の一方的な主張を述べたものであるので、池田総理は、十一月十五日、領土問題に関する日本政府の見解を明らかにする大要左記のとおりの書簡を、フルシチョフ首相に送付した。
私は、さきに閣下にお送りした本年八月二十六日付私の書簡に対する返簡として閣下が送付越された本年九月二十五日付の書簡を注意深く拝見しました。
貴簡の中には軍事基地の問題、日米安全保障条約の問題、軍縮問題等いくつかの重要な問題が触れられてありますが、これら諸問題に対する日本政府の見解は、閣下ならびにソ連政府にあてたこれまでの私の書簡ならびに日本政府の文書においてすでにたびたび述べたところで明らかなとおりでありますので、ここに再び繰り返す必要はないと思います。しかしながら領土問題については、これが極めて重要な問題であると考えますので、閣下の述べられているところで遺憾ながら事実に反する点を是正する意味で、私の所信を表明したいと思います。
閣下は、日・ソ間の領土問題についてこれが一連の国際諸協定によってすでに解決済みであると述べておられますが、元来戦争の結果としての領土の帰属変更が平和条約により初めて確定されるものであることは、閣下も十分に御承知のところであります。
しかして日・ソ両国政府は、歯舞、色丹を除いては領土問題について合意に到達できなかったので、戦争状態を終結する形式として平和条約によらず共同宣言によることとし、もって国交を回復することとなったのでありまして、こうした経緯に徴しましても、未だ平和条約の締結されていない現在、領土問題が日ソ間において解決済みでないことは余りにも明瞭であります。
閣下が日・ソ間の領土問題は解決済みであると主張する根拠とされている「一連の国際協定」なるものが、具体的にはどのような協定を指しているか明らかではありませんが、おそらくヤルタ協定、サン・フランシスコ平和条約等を指しておられるのではないかと推察されます。
しかしながらヤルタ協定は、ソ連に対し南樺太を返還し、千島列島を引渡すべき旨述べてはいますが、しかし同協定については、米国は「単にその当事国の当時の首脳者が共通の目標を陳述した文書にすぎず、その当事国による何らの最終的決定をなすものでなく、また領土移転のいかなる法律的効果をもつものでもない」と、明言しているのであります。
しかのみならず、わが国はそもそも本協定の当事国でもなく、またわが国が受諾したポツダム宣言も、ヤルタ協定にはなんら触れておらず、しかも本協定は、当時全く秘密とされていたのであります。したがってわが国としては、法律的にも政治的にも何ら同協定に拘束されるものでなく、貴国政府は、わが国との関係において本協定を援用することはできないものであります。
また閣下がおそらくその主張を根拠づけるため援用しておられると思われるサン・フランシスコ平和条約についても、日本が同条約により「南樺太及び千島列島に対する一切の権利、権原及び請求権を放棄した」ことは事実でありますが、同条約には、日本が何国のためにこれ等地域に対する権利を放棄するかは規定されておりません。サン・フランシスコ平和会議のソ連首席代表であったグロムイコ現外相は、同会議の席上行なった演説の中で、「日本がこれ等領土に対するソ連邦の主権を認めるべき日本の明白な義務については何も述べられていない」と述べて、同条約がソ連政府の主張する権利を否定するものとして非難した経緯があり、しかもこのような点をも理由としてソ連政府が同条約に署名を拒否していることからみても、ソ連は、サン・フランシスコ条約によって日本が放棄した領土に対し、何らの権利をも主張できる立場にないのであります。
こうした事情を考慮すれぱ、「領土問題はすでに解決済みである」という閣下の主張が根拠を欠くことはきわめて明瞭であります。
日本政府が受諾したポツダム宣言にはソ連政府も参加しておりますが、同宣言にはカイロ宣言の条項が履行されるべき旨明記されております。しかして、このカイロ宣言には、日本は、日本が「暴力及び貧欲により略取」した地域から駆逐されると述べられている外、連合国自身については、「自国のために何等の利得をも欲求するものでなく、また、領土拡張の意思も全く有しない」旨がはっきりと宣言されております。しかるにソ連政府が、日本が決して「暴力及び貧欲により略取」した領土でない千島列島のみならず、古来日本人のみが居住し、しかもかつて他国に領有されたことのないクナシリ、エトロフ両島にまで、その領有権を主張していることは、このカイロ宣言の条項とも全く矛盾するものと申さざるを得ません。
閣下はまた、日本政府は「日本の領土でない領土の日本への返還問題を提起し、『固有の領土』についての問題を自ら提起することによって、サン・フランシスコ条約の当該規定の承認を避けようとしている」と述べておられますが、「『固有の領土』についての問題」とはおそらく、クナシリ、エトロフ両島を指すものと考えられます。しかしながら、これ等諸島は幕府時代の十九世紀中頃よりすでに日本固有の領土として国際的にも認められていたものでありまして、帝政ロシア政府も一八五五年の日露通好条約によってこれ等諸島が日本の領土であることを承認しているのであります。しかして日本政府とロシア政府との間に結ばれた一八七五年の千島・樺太交換条約は、「千島列島」としてウルップ以北の十八島をあげ、その千島列島は南樺太と交換の上で日本領土とさるべきことを定めたものであります。従って日本政府がサン・フランシスコ条約によってその権利を放棄した「千島列島」は、この歴史的にも明らかな概念であるウルップ以北の十八島を指すものであって、元来「千島列島」に含まれぬ固有の日本領土であるクナシリ、ニトロフ両島については、日本政府は何等の権利をも放棄したものではないのであります。
しかもこれ等両島には戦争終結に至るまで日本人のみが居住していたのでありますが、今やこれ等の日本人は、すべて放逐され、父祖代々の墳墓に参拝することすら許されない状態にあるのであります。しかして終戦と同時にこれ等の島を占領したソ連政府がその国民を続々と本国よりこれ等の島へ移住せしめている事実に、日本政府は無関心たり得ないのであります。
固有の領土に対する民族の愛着は、他国の固有の領土を占領した上これを合法化ぜんとするこのような試みによっても決して消え去るものではありません。私は閣下が、日本民族固有の領土を速やかに返還されることによって、日・ソ両国民が良き隣人として共存し得る基盤を作り上げるよう尽力されることを切望し止まないのであります。
私は何人にもまして、日・ソ間に領土問題が解決し、速やかに平和条約が締結されることを望むものでありますが、遺憾ながらいまだその実現をみるに至っていない現在においては、両国は、もっぱら日・ソ共同宣言を指針として相互の関係を律して行くべきものと考えます。すなわち、それは一般的原則として、国際紛争の平和的解決、武力による威嚇または武力の行使を慎むこと、国連憲章第五十一条の個別的、集団的自衛の固有の権利の確認、相互に国内事項に干渉しないことの四点を含むものであります。
私は両国政府によってすでに確認せられたこの基礎の上に立って、日・ソ両国の善隣関係増進のため、ひいては全世界の平和のために、あらゆる努力を惜しむものではないことを本書簡を結ぶに当ってとくに申し添えるものであります。
これに対し、十二月十二日、在京フェドレンコ・ソ連大使は、池田総理を訪れ、要旨次のとおりの十二月八日付フルシチョフ首相の書簡を手交した。
本年十一月十五日付の貴簡を受領しましたので、若干の見解を申し述べたいと思います。
貴下が一九五六年十月十九日付の宣言の諸原則にしたがい、日本とソ連邦との間の善隣関係を増進させるために努力を惜しむものでないと述べられたことを拝聴して欣快に存じます。ソ連政府は、ソ・日関係を完全に正常化し、かつ両国国民の死活的利益に副う善隣的協力を調整することを絶えず希望するものでありますので、このような御意見には全く同感であります。
他方、直言すれば、両国関係の今後の発展に関する実際的な諸問題につき意見を実務的に交換する代わりに、われわれの書簡交換を究極においていわゆる領土問題に関する無益な論議に帰着せしめようとする意図が表明されていることを私は悲しむものであります。この論議は、平和条約の締結を阻止し、かつソ連邦と日本との間の関係の安全正常化を妨げる目的をもって人為的に、故意に煽られているのであります。とくに、軍事同盟によって米国と結ばれている日本が、ソ連邦を目標とする外国軍事基地としてその領土を自発的に提供している現在の諸条件のもとでは、この論議が他の結果をもたらすものでないことは、貴下自身も御了解のことと思います。
貴簡中に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお未解決のままであり、またこの問題についてソ連邦から態度の変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取付けるなんらかの根拠があるかのように見せかけようとする試みが新たに行なわれております。貴総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するにすぎないものであることを、私は、極めて率直にかつ断乎として閣下に述べなければなりません。実質的には報復的であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
私の見解では、日本政府の領土要求を根拠づけるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および文書を改めて現在取り上げる必要はありません。しかし、私はこれらの事実および文書の若干について想起せしめたいと思います。
日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州および四国の諸島ならびに若干の小島に局限しています。
日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するであろうという誓約をしました。千島諸島が日本の主権の下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側からの千島諸島に対する現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
日本政府が、貴下もその書簡で確認されているように、千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求をあえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。貴総理、どこに論理があるのでしようか。
貴簡中に、千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約にはこの諸島がいかなる国に帰属すべきかが記載されていないので、問題は未解決であるかのように主張されています。日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものでないことが周知のとおりであるのに、日本政府はこのような問題を提起することにより、一体何を求めようとしておられるのかをお伺いしたいものです。日本政府は、誰の利益について配慮されているのでしょうか。日本政府はソ連邦の極東沿岸への道を遮えぎる千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいられるのでしようか。それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらしているソ連邦を目標とした軍事基地に加えて、千島をも新たな軍事基地とすることに反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしようか。
しかし、貴総理、ソ連邦は自分の権利を譲渡するわけには行きません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連邦に引渡されたのであります。
貴下は千島諸島のソ連邦帰属に疑問をさしはさもうとして、日本政府がヤルタ協定の加盟国でないこと、したがって同協定が日本に関係がないかのようなことを引き合いにだされています。ヤルタ協定は日本と戦った諸国家間に締結されたものである以上、日本が同協定に加盟せず、また加盟することのできなかったことは、もちろん当然であります。しかし、日本は降伏して、連合国の決定した条件を受諾しました。そして連合国は、この点については既存の連合国間の諸協定を出発点となしているのであり、その中にはあらゆる国際協定と同じく、拘束力を有するヤルタで署名された協定も含まれているのであります。
米国政府の若干の声明を引用することによって日本側の主張を裏付けようとする貴簡中の試みは、全く成り立ちません。米国政府もかつてヤルタ協定は自国を拘束するものと無条件で認め、この協定にしたがって行動してきたことを指摘しなければなりません。このことを確証する幾多の文書があります。例えば、この関連において、一九五一年三月二十九日付のおよび五月十九日付のソ連政府あて米国政府の覚書に注意を向けることができますが、これらの覚書から明らかなことは、南樺太および全千島諸島のソ連邦帰属問題については米国とソ連邦との間には何んらの不一致もなかったことであります。
周知のごとく、ヤルタ協定中にも、一般命令第一号中にも、サン・フランシスコ条約中にも千島列島の区分はなんらなされておりませんし、全体としての千島諸島が問題となっていたのであります。このことは、とくにソ連邦と米国との政府首脳間にとり交わされた往復書簡によっても確認されています。したがって、当該国際諸協定があたかもソ連邦に全千島諸島ではなく、単にその若干の島のみを譲渡するものとしているかのように主張する日本側の試みは、全く根拠のないものであります。
クナシリ島およびエトロフ島が千島諸島中に含まれていないという主張は、これまた成り立ちません。このような遁辞を弄して、日本の歴史的および地理的文献が戦前に逆のことを主張していたことを忘れているようにみえます。例えば、一九三七年に日本海軍省水路局が出版した水路誌や観光局が一九四一年に出版した公的な日本旅行案内書あるいはその他の多くの日本出版物を御覧になれば、貴下は、看板を塗り替えて地理に適合しないようにしようとする者がいかに自分を滑稽な立場に陥れるかを確信されるでありましよう。また、クナシリ島およびエトロフ島が千島列島に帰属していることは、戦後においても日本政府によって一再ならず認められていることも周知のとおりであります。
貴下はその書簡で、一八五五年および一八七五年の日露条約を引用されていますが、これらの条約が本件となんらの関係もないことは明らかであります。もし貴下の例にしたがって歴史を反転させるならば、一九〇四年に日本がロシアを背信的に攻撃し、戦争を誘発し、ロシア国民に多大の悲しみを与え、ロシアから樺太の半分を奪取し、かつロシアにポーツマス平和条約の苛酷な掠奪的条件を押付けたことを想起させる必要がありましよう。これらの行動によって、日本は一八五五年および一八七五年にロシアとの間に締結した諸条約を破り、これによりこれらの条約を引き合いに出す権利を自ら失ったのであります。また二十年代の初めにおけるもっと新しい例をも挙げることもできます。すなわち、当時日本は一九〇五年の条約を破り、再びロシアへ侵入し、北樺太およびソヴィエト領極東を占領し、これらを掠奪しました。このほかにも周知のこの種の歴史的諸事実があります。
私は、日本の現政府を非難するためにこれらのことについて申し上げているのではありません。しかし、貴簡は、貴下の挙げられた諸事実が日本の有利になることを物語るものでないことを示すために、私をしてこのような歴史的回顧をなさしめずにはおきませんでした。そして論議を続けるための基礎を遠い過去に求めずに、日本に一定の義務を課している国際語協定を厳守することが必要であるようにみえます。
日本側によるソ連との平和条約締結の引延しは、当然日本政府の企図についてソヴィエト人に警戒的な気持を起させないわけに行きません。なぜ日本は平和条約の調印を欲しないのだろうか。また、日本はソ連と平和裡に生きることを欲しないのではないだろうか、という当然の質問をソヴィエト人は発しています。これは、あるいは一部の人々が平和条約の火除を日本における軍国主義的、報復主義的気運を復興させるために利用しようと考えていることによって説明されるのでありましようか。もし国家が、国家間の平和と友好を希求するならば、平和条約を調印しない理由はありえないのであります。
平和条約の欠除は、貴我両国間の協力の発展を困難ならしめているのであります。日本政府はこのことを考慮しないばかりか、最近には貴我両国間の関係を完全に正常化する途上において善隣関係を発展させるための条件をつくることに対しても新たな障害を設ける措置をとったのであります。ソヴィエト人は、日本が特定層の努力によって、その鉾先がソ連邦およびその他の平和愛好諸国に向けられている米国の結集する侵略的軍事同盟およびブロックに引き入れられているという悲しむべき情勢に注意を向けざるをえないのであります。日本は戦争準備を鋭意行なっている人々と積極的に協力し、かれらに対し、日本の諸隣国の安全を脅威する目的で自国の領土を利用させているのであります。
このような情勢のもとにおいて、貴国の公的な代表者たちが平和愛好とソ連邦に対する友好的感情を確約するとしても、果してかれらが、日本領土に配置されている米軍基地と米ロケット・核兵器の援助のもとで、ソ連邦およびその他の諸国との友好および相互理解を強化しようと考えているのかという問題が生ずるのも已むをえないのであります。これらの基地と兵器とは、他の目的をもっているようにみえます。
ソ連政府は、一連の周知の文書において、余すところなく日米軍事条約に関する自国の立場を表明しました。したがって、私はここで再びこの問題のあらゆる面に触れるつもりはありません。
現在われわれの共通の課題は、現存する困難と障害とを克服し、ソ連邦と日本との間に真に良好な善隣関係を設定すべき道を求めることにあると思います。この関連において、ソ連邦と日本との間の貿易、経済、文化およびその他の関係を一層拡大するために、また全面完全軍縮、核兵器の禁止、核兵器貯蔵の破壊、植民地主義の一掃をはじめとする最も重要な国際問題を調整する闘争上の協力をはかるために相互に努力することが、現在第一義的な意義をもつであろうことを、私は再び強調したいと思います。これが、私の信ずるところによれば、貴我両国国民の利害が完全に一致する分野であり、相互の協力がとくに実を結びうる分野であります。
疑いもなく、現代の最も重要な問題は、全面完全軍縮の問題であります。この問題の進展は、すべての国の共同の努力によってのみ可能であり、各国の義務は、人類の運命に大きな意義をもつこの崇高な事業に貢献することであります。国際関係において重要な地位を占める日本も、軍縮に関する最終的協定の達成を容易ならしめるために多くのことをなしうることは疑いありません。しかしながら、これまで日本の公的な代表者たちは、この問題において米国の蔭に隠れており、もし行動するとしても、それは原則として、西欧列強とともに軍縮問題の解決に向けられていない提案を支持するためであります。
ソ連政府は、先般核および熱核兵器の実験禁止に関する具体的協定案を提出しました。貴下は、この新提案の内容を知る機会をすでにおもちになったことと思います。同協定は、疑いもなく、日本を含むすべての国民を不安ならしめている問題に関して早急に合意をとげるための現実的な可能性を開くものであります。広島および長崎の悲劇を体験した日本国民のこの問題に対する態度は、われわれには全く理解できます。日本政府は、核兵器の実験継続に対して否定的態度を表明した一連の声明を行ないました。日本政府は、とくに、アフリカにおけるフランスの実験実施を非難するものであることを当時確認していたのであります。事実、多くの人々は、日本が最近これらの声明に反して、アフリカにおける核兵器の実験および配置を禁止する決議の支持を国連で放棄するにいたったことに驚きました。だが、米国が設置した侵略的軍事ブロックの加盟国である。パキスタン、イラン、タイ、フィリピン、ノールウェー、デンマーク、アイスランドは、この決議に賛成投票をしたではないでしようか。
日本政府が、軍拡競争と戦争の脅威から人類を解放し、全国民の平和愛好的希望に応えるような提案を支持するために、大きな一貫性を表明し、その声を高めるよう期待したいものであります。
最後に、現在意見の不一致があるにもかかわらず、良識が勝ちを占め、ソ連邦と日本との間の関係が相互の利益になるよう真に善隣の関係となるだろうとの確信を表明したいと思います。私どもは、日本政府がソ・日関係を完全に正常化する事業に必要な意義を付し、この途上に横たわる障害を排除する手段をとるよう期待するものであります。
私は、貴総理に対し、ソ連政府としては、貴我両国民のために、世界平和の強化のために、ソ連邦と日本との間の関係を改善すべく、今後ともあらゆる努力を傾けるべきことを確言できます。
一九六一年八月三十日ソ連政府が核爆発実験の再開を声明するに至ったので、九月二日日本政府の訓令に基づき、在ソ連山田大使は、クズネツォフ外務第一次官を往訪して、次のような口上書による申入れを行なった。
日本国政府は、ソヴィエト連邦政府が八月三十日核爆発実験の再開を決定したことに対して、深甚な遺憾の意を表明せざるを得ない。
わが国は、不幸にして核爆発の恐るべき惨禍を身をもって体験した最初にして唯一の国として、つとに、人類が再びこのような不幸を繰返すことのないよう希望してきた。このような立場からわが国は、従来およそ核実験を行なうものに対しては、強く抗議してその中止を求めてきた。しかしてまたわが国は、国連加盟以来今日まで毎年総会において核実験の停止を目標とする努力を続けてきたのであるが、とくに第十五回国連総会においてわが国が、多数の国家とともに、核実験停止および核兵器拡散防止に関する決議の成立に努力したことは周知の事案である。
わが国は、このような努力を通じて、核爆発物を保有する関係諸大国がすべてまずその実験を停止するとともに、右に関する有効な合意が一刻も速かに成立することを期待し、とくにジュネーヴにおいてかかる目的のために行なわれている関係諸国間の交渉に絶大な望みをかけてきた。池田総理大臣が、フルシチョフ首相に対する親書において核実験停止協定を不可能ならしめざるよう要請したのも、上記のような日本国民の真しなる熱望に促されたからにほかならない。しかるに、ソヴィエト連邦政府が現在交渉の成立のため努力が続けられているにかかわらず、突如一方的に実験再開を声明したことは、日本国民挙っての悲願を踏みにじるのみならず、戦争をおそれ平和を愛好するすべての国民の平和への期待と祈りとを無残に破壊するものである。日本国政府は、ソヴィエト連邦政府の今次決定がソヴィエト連邦政府がこの決定を正当化するためいかに説明しようともそのつねづね唱えている「平和共存」、「世界平和達成の念願」と矛盾し、人類に恐怖を与えることによって政治目的を達成せんとするものと認めざるを得ない。ソヴィエト連邦政府のかかる決定は、他国を実験再開へ強制する結果となり、ひいては全人類を破滅の道へ陥し入れるであろう。日本国政府と全国民は、ソヴィエト連邦政府のかかる決定に対してここに厳重抗議するものである。
日本国政府は、ソヴィエト連邦政府が今次核実験の再開が全人類の運命に及ぼすべき重大な結果を真剣に考慮し、今回の決定を撤回し、実験を実施せざるよう強く要請するとともに、ソヴィエト連邦政府が進んで関係諸大国と協力して速かに真に有効な実験停止協定の締結に努力することを期待する。
しかしながら、ソ連政府はこうした日本政府の申入れを全く無視して、一連の核実験を始めたことが確認されたので、九月二十日法眼欧亜局長は在京スズダレフ臨時代理大使を招致し、口上書をもって次のとおり重ねて申入れた。
日本国政府は、ソヴィエト連邦政府が本年八月三十日核爆発の実験再開を決定したことに対して、九月二日在ソ日本国大使を通じてソヴィエト連邦政府に対し書面をもって深甚な遺憾の意を表明し、同政府が前記決定を速かに撤回するように申入れた。この申入れを行なうに際して在ソ日本国大使は、ソヴィエト連邦政府がすでにその時までに実際に核実験を開始したか否かの点を質問し、この質問は、さらにその後も再三モスクワおよび東京においてソヴィエト連邦政府に対して繰り返えされた。しかるにソヴィエト連邦政府の当局者は、この問合せに対して今日まで何らの回答をも行なっていない。
しかしながら日本国政府の気象関係機関は、ソヴィエト連邦政府によって核実験がしばしば行なわれた事実を科学的に観測した。
日本国政府は、日本国政府が行なった厳重な抗議に対してソヴィエト連邦政府が全く何らの回答をも行なわず、次々と実験を強行していることに対し、ここに強くソヴィエト連邦政府の反省を促すものである。
核実験問題に関する日本国政府の立場は、すでに同政府がソヴィエト連邦政府に送った書面の中に明らかである。すなわち、日本国は、核爆発の怖るべき惨禍をみずから体験した国として、およそ核の開発が人類を破滅に導くような軍事的目的のために用いられることを絶対に認めることができないのであって、このような基本的立場は、核実験が行なわれることの結果蒙ることあるべき放射能の影響の有無によって左右されるものではない。
しかしながら日本国は、その地理的位置からもソヴィエト連邦内で行なわれる核実験の影響を直接に受ける可能性が極めて大
であり、すでにその最初の危険な徴候があらわれている。したがって日本国政府はソヴィエト連邦政府が強行している無暴な実験の結果、日本国政府および国民が蒙ることあるべき一切の損害に関し、ソヴィエト連邦政府に対して賠償を請求する権利を留保するものである。しかして、日本国政府は、何よりもまず、ソヴィエト連邦政府がさきに日本国政府の行なった申し入れに対し何らかの誠意ある意思表示を速かに行なうことをここに要求するものである。
これに対し、ソ連政府は、九月二十八日、ツガリノフ極東部長より在ソ連重光臨時代理大使に対し、九月二十七日付口上書をもって、九月二日のわが方の申入れに次のとおり回答してきた。
ソ連政府は、ソ連が自国の安全の強化のための措置をとったことにたいする日本政府の抗議を拒否する。日本政府は、その覚え書から明白なように、ソ連による核実験再開問題を、ソ連政府をしてこのような決定の採択を余儀なくさせた今日の国際情勢からまったく切りはなして、また軍備全廃問題との関連なしに、考察している。
しかし、実験には、最近数カ月間、アメリカ合衆国とそのNATO(北大西洋条約機構)同盟国が国際情勢を激化させる露骨な方針をとり、平和愛好諸国にたいする威嚇を強化したことを認めないわけにはいかない。かれらは、ソ連政府による対独平和条約締結の提案にこたえて、とめどもない戦争ヒステリーをあおり立て、ソ連その他の社会主義諸国を公然と戦争でおどしている。これらすべては、ソ連政府をして、自国の防衛能力を強化し、侵略者が新しい戦争をおこすのを阻止するために、必要な措置をとることを余儀なくさせたのである。
核兵器の禁止とそりストックの廃棄が実現されていない諸条件のもとで、もし侵略者によって戦争がひきおこされたならば、その戦争は不可避的に全滅的なロケット・核戦争になるだろうということを考慮にいれないことは、ゆるしがたい無思慮であり、犯罪であるだろう。ソ連閣僚会議議長エヌ・エス・フルシチョフの声明に言われているとおり、ソ連政府は、「いまきびしい必要に直面して、核兵器の爆発実験を再開しなければならない立場におかれているが、それはただ、ソ連国民と全人類が、日本の都市-広島と長崎でおきたような核兵器の爆発を自分の上に経験しないようにするために、ほかならないのである」。
多年の間ソ連は、もちろん核兵器部門における完全な軍備撤廃をも含む、全面的な軍備撤廃の実現のために、終始一貫して、ねばり強く努力している。ソ連政府は自己の平和愛好的な提案を具体的な実践的な行為によって裏づけた。ソ連政府は、一方的に核実験を停止し、兵力の著しい削減を行ない、外国領土における軍事基地を撤廃した。西側諸大国は、これにたいして、核兵器その他の近代兵器の熱病的な集積と、あらゆる戦争準備の強行、社会主義諸国をとりまく多くの軍事基地におけるロケット・核兵器の強力な集中をもって応えた。それと同時に、西側諸大国は、あらゆる種類のでたらめな口実をもうけて軍縮交渉をひきのばし、そしてそれを完全な失敗に終らせようとした。かれらは、建設的なソ連の提案をうけいれることを系統的に回避し、そしてソ連がかれらの提案をうけいれるや、自分自身の提案をさえ、一度ならず拒否した。
ソ連は、ジュネーヴ交渉で、あらゆる核実験が無条件に、全面的に、かつ永久に禁止されるようにするために努力した。しかしながら、米国および英国は、協定が結ばれた場合にも、この致命的な兵器を発展させるための活動の継続を可能にするような一定の種類の核実験を合法化しようと、あらゆる手段をつくして努力している。両国の同盟国フランスは、原子爆弾を改良する仕事を強力におしすすめている。フランスは、周知のとおり、どのような条件のもとでも、核実験を停止することに同意せず、NATOの同盟諸国のために核実験を案施しつづけた。西側の諸大国は、核実験禁止問題におけるこのような二面政策によって、ソ連にたいする軍事的優位性を確保しようと試みたのである。したがって、軍縮問題全般、および核実験停止の問題についての協定がこんにちまで結ばれなかったことにたいする全責任は、まさに西側諸大国が負うべきである。
ソヴィエト国家の外交政策の根底には、つねに平和共存の原則があったし、これからもかわることなくこの原則が根底におかれるだろう。ソ連は、米国および同盟諸国の平和をおびやかす行動に直面して、安全を確保するためのやむをえない措置をとるにあたり、世界のすべての国の国民、政府にたいし、世界が戦争にむかって滑りおちるのを防ぐために力を合わせるよう、呼びかけるものである。
ソヴィエト政府は、あらゆるさしせまった国際問題を話合いによる平和的な手段で解決するよう、西側大国にねばり強く提案している。ソヴィエト政府は、熱核兵器の実験にたいしても永久に終止符を打つことを可能にする効果的な国際管理のもとでの軍備全廃についての協定を、いつでも結ぶ用意があることを厳粛に宣言した。
軍備全廃のためのソ連の断固たるたたかいは、平和を愛するすべての国民の熱望に応えるものである。ソヴィエト国民は、米国によるこの致命的な原子爆弾の野ばんな使用の最初の犠牲になった日本国民が、このたたかいに示している積極的な支持を、高く評価している。
しかしながら、現代の最もさしせまった問題を解決する上で、ソ連が日本政府から何の支持もうけなかった事実は、指摘せざるをえない。軍縮と核実験に関する問題の国連での討議の過程で、日本政府は、事実上つねに、軍縮に関する建設的な提案の採択に反対する勢力と手を結んできた。日本が核実験の停止に形式的には賛成投票した場合にも、日本は、実際には、核兵器実験を全面的、かつ永久にやめてしまおうとするソ連その他平和愛好諸国の努力を支持するどのような措置をもとらなかった。
日本政府が、軍縮に反対して実際にロケット・核戦争の準備をすすめているものたちを、その政治的および実際的行動で事実上支持しているという事情を見すごすことはできない。同盟国アメリカにおもねって、日本政府は、太平洋地域を核武装禁止地帯にするというソ連の平和的提案に否定的態度をとった。しかし、このような提案の採択が、だれよりもまず日本国民の切実な利益にかなうことは証明するまでもない。日本政府は、別の道をえらんだ。同政府は、日本領土、とくに沖縄で、米国のロケット基地、原子兵器貯蔵所の建設が、さかんに、ますます大規模にすすめられ、日本に隣接する平和愛好諸国家に対するロケット・核戦争の準備のためにいっさいのことが行なわれるのを許した。一〇カ所以上の日本の大空軍基地が、日本政府の同意のもとに、米国空軍によって、核および熱核兵器運搬用の超遠距離爆撃機の根拠地に利用されている。
平和の事業にとって危険なこの方針をとることによって、日本政府は、今日の緊張した国際情勢-このためにソ連は自国の安全を保障する措置の一つとして核実験を再開することを余儀なくされたのだが-の発生にたいする責任のすくなからぬ部分を、みずから引受けたのである。
以上述べたことに照してみて、日本側は、世論を惑わし、国際情勢の緊迫化に対する真の責任者から注意をそらそうと試みている、と認めないわけにいかない。
もし日本政府が、人類がロケット・核戦争の恐怖から救われることを本当に望んでいるとすれば、日本政府は、侵略勢力の画策に積極的に抵抗するための大きな可能性をもっている。この可能性は、日本の為政者が、平和をおびやかしている危険を冷静に評価し、口先でなく行動の上で焦眉の国際問題の平和的解決をうながすために自分の影響力を利用するとき、はじめて現実化されるだろう。ソ連政府の見解では、効果的な国際管理のもとでの世界の軍備全廃に関するソ連の提案を日本が支持すれば、これは平和の強化の事業に対する重要な貢献になるであろう。この課題が案現すれば、いっさいの核兵器実験の停止問題も自動的に解決されるであろう。
その後フルシチョフ・ソ連首相は、十月十七日の演説で、一連の核爆発実験の最後に、五〇メガトン水素爆弾の実験を行なわんとしていることを明らかにしたので十月二十日在ソ連山田大使は、政府の訓令に基づきクズネツォフ外務第一次官と会見し、次のような口上書を手交した。
フルシチョフ・ソヴィエト連邦閣僚会議議長は、本年十月十七日第二十二回ソヴィエト連邦共産党大会の席上行なった演説の中でソヴィエト連邦政府は、現在実施している一連の核実験の最後に、五〇メガトンの水素爆弾の実験を行なう予定である旨を述べた。原爆の惨禍を身をもって体験した日本国民は、かかる恐るべき兵器の実験が行なわれんとしていることにつき、極度の不満と不安の念を禁じ得ない。ソヴィエト連邦政府が現在かかる実験を行なう目的につきいかなる説明方法を用いようとも、平和を愛好する諸国民を納得せしめることは不可能であろう。
加うるに、このような恐るべき破壊力を有する爆発の実験により製造せられるべき兵器は、攻撃的性格を有することは疑いを容れないところであって、ソ連政府の日頃唱道する平和主義そのものに反するものであるのみならず、国際緊張のより一層の激化をもたらすことは明らかである。
この無謀な実験の結果として多量の放射能降下物が再びわが国全土を襲うべきことについては、今さら多言することを要しない。九月二日付口上書をもって日本国政府がソヴィエト連邦政府の核実験の再開に関し抗議を行なったのに対する同月二十八日の回答の際、ソ連邦外務省係官がソヴィエト連邦政府の今回の実験においては実害が発生しない旨言明したにもかかわらず、すでに日本各地においては雨水の放射能が増大し、最近において三八、〇〇〇カウントを越える放射能を検出した地域さえある事実にソヴィエト連邦政府の注意を喚起せねばならない。
日本国政府は、かかる無謀な実験を企てようとするソヴィエト連邦政府に対し、ここに深い反省を求めるとともに、本件計画を直ちに撤回することはもとより、すべての平和愛好国民の希望にしたがい、核実験をすべて停止するよう重ねて強く要請するものである。
十月二十三日ついにソ連政府は大型核爆発の実験を行なったので、小坂外務大臣は、十月二十五日在京スズタレフ臨時代理大使を招致し、これに対し口上書をもって次のような抗議を行なった。
さきに十月十七日フルシチョフ・ソヴィエト連邦閣僚会議々長がソヴィエト連邦政府は五〇メガトンの大型水素爆弾実験を計画している旨言明したことに対し日本国政府は、右実験が全人類の運命に及ぼすべき重大な結果を真剣に憂慮し、十月二十日在ソヴィエト連邦日本国大使を通じ、右に対するソヴィエト連邦政府の深い反省を求め右計画を直ちに撤回するよう強く申し入れた。それにもかかわらず今回ソヴィエト連邦政府がかかる無謀な実験を強行したことは、日本国民の要望を無惨にも踏みにじる行為であり、日本国民はこれに対し深い失望と憤懣の念を禁じ得ない。
ソヴィエト連邦政府によって大型核爆発の予告がなされて以来、全世界の平和愛好諸国民が限りなき不安と脅威にさらされ、その実施を思い止まるよう要望してきたことはソヴィエト連邦政府の十分承知するところである。しかるに、ソヴィエト連邦政府が、右実験を敢えて強行したことは平和を希求する世界の世論に挑戦するものであり、最早やこれを正当化するいかなる弁明の余地もあり得えない。
右大型核爆発は、世界の平和に対し、極めて有害である。またその結果放出される放射能は、全世界の罪なき諸国民ならびにその子々孫々に対し計り知れぬ不幸をもたらす危険がある。ソヴィエト連邦政府が、それによって直接間接の被害を蒙る幾億の平和な諸国民に対して負うべき責任は正に重大であると言わざるを得ない。
日本国政府は、ソヴィエト連邦政府が強行した無謀な核案験の結果、日本国民が蒙るべき一切の損害に対し、ソヴィエト連邦政府に対し賠償を請求する権利を有することを表明するとともに、ここにソヴィエト連邦政府に対し、最も厳重なる抗議を行なうものである。
また右会談に際し、スズダレフ臨時代理大使は、持参せる次のような十月二十四日付池田総理大臣宛フルシチョフ首相書簡を小坂外務大臣に手交した。同書簡は、核実験を行なうことについてのソ連政府の立場を説明したもので、同文書簡がヌクルマ・ガーナ大統領等へも送られている。
私は、ソ連邦が原水爆兵器の爆発実験を行なうことを余儀なくされているということについて、不安の念を表明された貴下のノートを受領いたしました。
われわれは、かかる決定をわれわれに取らせた理由をすでに陳述いたしました。私はただもう一度、われわれがこの処置をとったのは長い間の熟慮の後であり、諸国民間の平和の確保という理想を重んじる者には誰にもかかる心の痛み、悲痛の感なしにはとれなかったということを強調したいと思います。われわれの国が、万人の目前で行なわれているNATO諸国による戦争準備の激しい努力の面前に立たされている情況を想定して貰いたいと思います。そうすればおそらくソ連政府には他の選択の余地はなかったということを貴下が理解される助けになることでしょう。
一世代の生涯の間にドイツ軍国主義者の大軍の略奪的攻撃を二度蒙ったソヴィエト人達は戦争のことを耳で聞いて知っているのではなく、自分の家で目のあたりに見たのであります。公平にいって、いかなる他の国民も、いかなる他の国も、第二次世界大戦においてわが国民、わが国ほどの大きな犠牲を払い、広範な荒廃にさらされはしませんでした。そしてまた、肉親および身近な人々の犠牲と喪失は補ない得ないものであり、しかもほとんどすべてのソ連の家庭はそうした喪失を受けたということを説明する必要がありましょうか。
戦争とはいかなるものであるか、とくにロケット・核兵器を使用する現代の戦争がいかなるものであるかを他の多くの者よりよく理解し、われわれは、人類社会の生活から戦争を排除し、全面完全軍縮を達成するためすべての努力を傾けてきたし、また
傾けているのであります。このためには、われわれによって少なからざる努力が費されました。しかし遺憾ながらこのわれわれの努力は、目下のところでは成功を収めておりません。
われわれは、単に醸成された現状況で第二次世界大戦の残滓を一掃し、ドイツ平和条約を締結することができるという最も平和的なことを提案しました。一体われわれは、西欧列強より回答として何を受けとったでしょうか。一体彼等は、ドイツ平和条約の共同作成のため円卓会議を開くというわれわれの提案を受け入れたでしょうか。列強間のあつれきを生ぜしめる主要な原因の排除、武力衝突の防止、第三次世界大戦の阻止に貢献するような基礎のもとで平和条約を作成するとのわれわれの希望に彼等も賛同していると声明したでしょうか。そうでありまぜん。貴下の御存知のとおりわれわれの提案は西側諸国により受諾されなかったのであります。
戦後十六年を経過し、漸く、現に存在する二つのドイツと対独平和条約を締結しようとする提案に対する答として、われわれは、アメリカ合衆国、フランス、英国、西独および侵略的軍事ブロックに属する他の同盟国のいずれの為政者が、もしドイツ平和条約が締結され、その基礎の上に非軍事化自由都市の地位を得る西ベルリンの状態が正常化されるなら、NATO列強は、これに対して力をもって答えるであろうとわれわれに想起せしめていることをほとんど毎日耳にしております。そして、かれらは、単に、戦争をもって威嚇しているだけでなく、それは熱核戦争になるだろうと公言しているのであります。
ドイツとの平和条約締結に関するソ連邦政府の提案に対し、NATO列強が威嚇をもって答えているにもかかわらず、ソ連邦がいかなる場合にも核兵器の完成化を含む自国の防衛力強化に関する追加的措置をこの上差し控えるとしたなら、ソ連邦はどうなることでしょうか、池田総理閣下の御理解を得たいと思います。もし、われわれがかかる措置を執らないとしたら、歴史によっても、いわんやわが国民およびヒットラー軍隊の侵略を蒙った諸国民によっても到底是認されることのない行動をとったことになるでしょう。もし、われわれが他の行動に出たとしたなら、われわれは、平和のために闘い、平和の確保を欲しているいかなる国民からも、決して是認を受けることはできないでしょう。
われわれは、わが国が、アメリカの軍事基地によって包囲され、また、これらの軍事基地が現在、強化されている事実を考慮しないわけにはいきません。アメリカ合衆国は、ヨーロッパに対し、自国の軍隊および軍事技術を投じております。本年初頭より、アメリカ合衆国の軍事予算は、六〇億ドル以上増加されました。核装備軍である戦略軍隊の増強は、加速度的に進められております。"ポラリス"ロケットで装備された潜水艦の数は急速に増加しております。滑走路にあるべき戦略爆撃隊の数は、五〇%増加されました。遠距離航空機の数は増加されました。予備役の補充部隊は召集され、そして、陸海軍部隊および海兵部隊を兵員および装備の定数にまで増強するための諸手段が執られているのであります。国家が通常かかる手段を執るのは、事態が戦争に至る時においてのみであることは今さら申すまでもありません。西独の報復主義者たちは-ところでアデナウアー宰相およびシュトラウス国防大臣は、かれらの合唱を指揮しているのでありますが-いよいよ執拗に、また、声を高くして、すでに現在西欧諸国において最大の軍隊になっている西独軍隊のため核兵器を要求しております。そして、それにもかかわらずNATO列強は、われわれが自国の軍事力強化および完成を放棄することを欲しているのであります。もし、われわれが、かくの如く行動したとするなら、それは実際に平和を欲し、戦争を呪っているすべての誠実な人々に背を向けることになるでしょう。また、それは、われわれ自身に対してのみならず、平和強化の事業において努力を弱めることのないようソ連邦に呼びかけている人々に対しても背を向けることになるでしょう。
貴下は本当にそうであろうかと疑われるかもしれません。しかし御一考願いたいと思います。すなわち、もしNATO列強が自国の軍事力の増強を継続するのに、ソ連および社会主義諸国が何もなさずに自国の安全確保について配慮しなかったとしたならば、これはNATO諸国の武器による威嚇政策によって醸成された諸条件下においては、もちろん平和の強化をもたらすものではなく、逆に侵略者を冒険に、重大な結果を伴う戦争の誘発に招くこととなるでありましょう。
たとえば、アメリカ上院議員マーガレット・スミスが行なったような声明に無関心でありうるでしょうか。スミスは、対独平和条約締結に対する回答として、ソ連に対して核兵器の使用を実質上要求しているのであります。貴下は、この関連においてアメリカ大統領の実弟である検事総長ロバート・ケネディと米国国務長官マクナマラがどのような威嚇の挙にいでたかを、お読みになっているでしょう。両氏はケネディ政府の核兵器を使用する計画について声明しています。また、最近英国外相ヒューム卿と外務政務次官たる国璽尚書がどのような声明をなしたかを御覧願いたいと思います。彼らの全部はソ連およびその他の諸国が対独平和条約に調印するならば、NATO列強はこれに対して熱核戦争を誘発するであろうという一事を吹き込もうとしています。
われわれは、西欧列強とともに交渉のためにテーブルを囲んで第二次世界戦争の結末をつける問題の平和的処理をできるだけ速かに計りたいと思う旨を一度ならず声明してきました。しかし、西欧列強がこれを欲しないとしても、われわれは、ヨーロッパにおける平和強化上の利益が要求するところの平和条約の調印を余儀なくされ、これを調印するでありましょう。
われわれが、NATO列強による脅喝の試みを無視することができないのはもちろんでありますが、しかしこのような試みは目標をはずれて向けられているといわなければなりません。もし平和条約締結の反対者が、戦争の手段をもって平和条約反対のために戦おうとするならば、われわれは戦争を誘発するいかなる試みをも阻止するために、威力の劣らない諸手段を持たなければならないのであります。
ロケット・核戦争の焔を発火しようとする威嚇が、米国またはソ連にとってよりも何倍もの危険な戦争の結果をうけるであろうものの口から放たれているとき、とくに疑惑を感ずるのであります。英国国璽尚書は、われわれを戦争で威嚇しております。
しかし、英国璽尚書は英国が大きくない島であって、そこにはポラリス・ロケットを有する米国潜水艦基地があり、かつ核兵器で装備される米国爆撃機が配置されておることと、軍事行動誘発の場合に、同島が核攻撃の破壊力を最初に経験するものの中に入ることを忘れているように思います。
NATO列強の今日の政策は、もはや放射能の降下物ではなく、核兵器自体の殺人的な破壊力を危惧せざるをえないように立ち至らしめております。これが今日人類が選択すべく直面させられていることであります。われわれは人類が決して核戦争の惨禍を経験しないために、実験的爆発を行ない、かつ武器を完成しているのであります。ソ連の手中に核兵器が存在することは、対独平和条約締結問題に関連して威嚇を行なっているすべてのものに対する威嚇的警告となっているのであります。
平和的、創造的労働に従事しているソ連国民およびその他社会主義諸国民にとって戦争は不用であります。われわれは全世界に向かってこのことを、わが国における共産主義建設の偉大な綱領を確認する第二十二回党大会の壇上から宣言しました。この綱領を実験するためには、われわれに平和が必要であります。われわれは喜んで完成された威嚇的武器を大洋に投下するでありましょう。しかし、わが交渉の相手方が共に兵器を投下せしめるため話合いをつけることを欲しないとすれば、その時には当然われわれにもそれが必要であります。われわれは、諸国民の平和と平安は侵略者に対し愛や忍耐の言葉で哀願してこれがえられるものでないことを知っています。軍事的威嚇に対し、われわれはわが国の軍事力の強化をもって答えることを余儀なくされており、他に途はないのであります。
すべてこれらのことからして、西欧諸国-NATO加盟諸国の政策が国際緊張および軍拡競争の源であることが明らかであります。もし平和の利益と核戦争の防止について配慮するとすれば、全平和愛好諸国政府の努力、諸国民の努力は西欧列強をして武器をガチャつかせることを止めしめ、第二次世界戦争の残滓に結末をつけるため話合いを付けしめることに向けられなければなりません。これが平和と安全とに導く唯一の賢明な途であります。ソ連側からは従来どおり、この崇高な目的を達成するため、あらゆる努力が払われるでありましょう。
ソ連政府がすでに説明してきましたように、核実験停止に関する問題の解決への途は、全面的完全軍縮問題を解決することであります。そうした場合、核兵器の実験の停止および同兵器の不使用の問題も完全かつ最終的に解決されるでありましょう。核兵器の実験や軍拡競争を終結するためには、全面的完全軍縮問題の遅滞ない解決を達成することが必要であります。
ソ連政府は、極めて厳重な国際管理下における全面的完全軍縮条約を調印する用意があることをすでに一度ならず声明してきました。われわれは今日でもそうする用意があります。
私は、貴我両国民が全面的完全軍縮問題の速かな解決、核兵器の完全かつ無条件禁止、新世界戦争の脅威からの人類の解放のための闘争においてその努力を共にするよう期待したいと思います。
右書簡に対し、池田総理大臣は、十月二十八日次のような返書をフルシチョフ首相に送り、同書簡は法眼欧亜局長より在京ソ連大使館のマミン参事官に手交された。
私は、閣下の本年十月二十四日付書簡を注意深く拝見しました。
その書簡において閣下が述べておられる核実験の問題は極めて重要かつ緊急な問題と考えますので、私は、ここに閣下に対し、折返し書簡を呈する次第であります。
日本国政府の核実験問題についての立場は、本年八月三十日のソ連邦政府による核実験再開声明以来、四回にわたってソ連邦政府に提示された日本側口上書によってもすでに明らかなところでありますが、私は、貴簡を閲読した所感として、次の諸点をとくに申し述べたいと思います。
閣下は、第二次大戦中とくにソ連邦国民が戦争の悲劇を身をもって体験したものであることを強調しておられますが、戦争がいかに悲惨なものであるかを体得したものは、ひとりソ連国民に限らないのであります。不幸にして核爆発の恐るべき惨禍を自ら体験した最初にして唯一の民族たる日本国民は、戦争を嫌悪し世界の平和を希求することにおいてソ連国民に優るとも劣らないものであることを、まずここに強調したいと思います。
ところで閣下の申される平和は、世界各国民の希求する真の平和とはその内容が異るものであるように思われてならないのであります。閣下は、対独平和条約の締結に関するソ連邦の提案を最も「平和的なもの」と呼び、この問題についてソ連邦が採ってきた措置はことごとく平和的意図に出ずるものであると言明しておられます。しかし、例えば、長年静ひつを保ってきたベルリンをめぐっての現下の緊張状態がそもそも何によって齎らされたかについて虚心たんかいに考えてみる必要があると思います。それが、明らかにベルリンの現状をすべて一方的に自己に有利に解決しようとするソ連邦政府の政策に端を発していることは真に世界の平和を欲するすべての人々の知悉しているところであります。私は、ドイツ民族の統一を達成し、もってヨーロッパにおける平和を保つ最善の途は、ドイツ民族の自由に表明された意思、すなわち「民族自決主義」に基づくものでなければならないと信ずるものでありますが、ソ連邦政府の政策は、この原則と相反するドイツの分割を追求しているものとみなさざるを得ないのであります。
ドイツ問題をめぐる国際情勢の緊迫に関連し、閣下は、西欧諸国が最近採った軍事的諸措置を列挙して、ソ連邦の核爆発の実験はこれにより強いられたものであると述べられていますが、西欧諸国によって採られた措置は、ソ連邦政府のとった一方的措置によって余儀なくされたものであり、その結果双方が互いに対抗措置をとることによって緊張が加速度的に増大しているというのが現実の事態なのであります。閣下はソ連邦政府が行なう軍事的措置はすべてやむを得ない防衛措置であって、西欧諸国が行なう軍事的措置はことごとく侵略的目的を有するものであるかのごとく主張しておられます。しかしながら、自国の行なう軍事的措置はすべてやむを得ない防衛措置であると他国に対して主張しながら他方において、他国の行なう防衛措置は一切防衛措置とは認めないという態度は到底常識ある人々を納得せしめるものではありません。ソ連邦政府による核実験の再開は、西側による同様の決定を誘発しましたが、私は、閣下が客年初頭の演説で「核実験を先に始める国は、諸国民に対して重大な責任を負う」旨言明されたことをここに想起するのであります。
閣下は、核実験の停止を求めた日本国政府の要請に対し、日本国民を納得せしめるような何らの処置も採ることなく、ただ核実験再開の責任を他に転嫁しようとしておられます。しかしながら、このような試みは、前述したソ連邦政府のいわゆる「已むを得ない防衛措置」と同じく、日本国民に対しては何らの説得力をも有しないのであります。けだし日本国政府は、かつて日本が受けた恐るべき不幸を二度と人類が繰返さぬよう心から願うが故にこそ、たとえ何人によるとまたいかなる理由によるとを問わず、およそ軍事目的のために行なわれる核実験はすべてこれを停止するよう要請しているのでありまして、核保有国たるソ連邦政府から実験再開の理由づけを求めているのではないのであります。
もとより日本国民は、いわゆる全面軍縮の実現を望ましいものと考えるのでありますが、現実の問題として全面軍縮が一朝一夕には案現し得ない現状においては、核実験停止問題を全面完全軍縮に結びつけることは、核実験の停止を遅らせることにほかならず、こうした「すべてか、無か」というソ連邦の態度は納得できないのであります。日本国政府としては現情勢下においては、実行可能なる措置、とくに最も危険な核爆発の実現を停止することからはじめるべきものと考え、国際連合においてもこのような立場から本問題に関する重要な幾つかの決議案を成立せしめるため、極めて積極的な努力を払ってきました。こうした努力の一つの結果として五〇メガトン核実験停止をソ連邦政府に要請する決議案が国際連合総会政治委員会において圧倒的多数で可決されたことは、閣下も十分御承知のことと思います。
五〇メガトンという巨大な爆弾から放出される放射能が、罪なき世界諸国民ならびにその子々孫々に対し計り知れぬ不幸を齎らす危険があることは、いくら強調しても強調しすぎることはないと思うのであります。
さらにソ連邦政府は、現在次々と実験している恐るべき核爆弾をかねて貴国が誇示する強大なロケットによって地上のいかなる地点にも正確に投射することができると声明しております。閣下はまた貴簡の中で、英国は大きくない島であって核戦争の際には米ソの何倍もの危険にさらされるというようなことにとくに触れられております。こうした書辞は力の政策に基づく威嚇としか解し得ないのでありまして、人類を破滅に陥れかねないこの恐るべき武器を威嚇の自的に用いられていることはとくに私の甚だ遺憾とする所であります。
私は、閣下がかかる威嚇の意図を含む核実験の再開につきその責任を他に転嫁する如き試みはとり止め、現在行なわれている実験の結果生ずる放射性降下物の齎らす恐るべき結果に思いをいたし、一刻も早く実験を停止するとともに真の世界の平和招来のため、まず厳正な国際管理を伴う核実験禁止協定の成立に誠実な努力を傾けられることを日本国民の名において要請するものであります。
十月三十日ソ連政府がさらに超大型核爆発実験を強行したことが明らかとなったので、池田総理大臣は十月三十一日次のような電報を直接フルシチョフ首相に宛てて打った。
ソ連邦政府が十月三十日超大型爆弾の実験をついに強行したとの報道により、私は、これまでにない大きな衝撃を受けました。
日本政府は、核実験に対し繰返し抗議し、ソ連邦政府の反省を強く求め、また国連も決議を行なって実験の中止を要請してきましたが、閣下がこれらの抗議や実験中止の要請に何らの考慮を払うことなく、今回空前の核爆発実験を敢て行なったことを衷心より遺憾とするものであります。日本国民の憤激は名状すべからざるものがあります。
閣下はつねづね平和共存の政策を唱えておりますが、今回の暴挙は世界人類の平和の希望を踏みにじる力の外交を赤裸々に示すものと云わざるを得ないのであります。
私は、ソ連政府による一連の強力な核実験が世界の平和と人類の安全を脅威するものとしてその重大なる責任をここに改めて指摘し抗議するものであります。
これら一連のわが方抗議に対しては、十一月十一日在京ソ連大使館マミン参事官が法眼欧亜局長を来訪して、次のような十一月九日付池田総理大臣宛フルシチョフ首相の書簡を手交した。
本年十月二十八日および三十一日付の貴簡を受領しましたので、貴下に回答を寄せたいと思います。
貴下が、全人類のために平和を堅持し、擁護することを唯一つの目的とするソ連邦政府の措置を評価するに当って客観的な態度をとる希望を示されなかったことを遺憾に思います。このことに、米国およびその同盟諸国の軍事・政治体制に対する日本政府の愛着のほどが表明されているようにみえます。
貴下は重ねて、ソ連邦の立場につき根拠のない断定を下して、われわれが自国の防衛力強化のために余儀なくとった諸措置が「力の外交を暴露する」ものであるかのように述べてさえおられます。
これが正しくないことは、もちろんであります。われわれは、長い熟慮の後にしぶしぶ核実験再開の挙にいでたのであります。われわれをしてこの挙に出づるのを余儀なくしたものは、力の政策を実際にとっているNATO加盟諸国がつくり上げた情勢であります。われわれが他の行動に出づることのできなかったことを、貴下自身においてもお考えの上、御理解をえたいものであります。
現在における枢要な問題は、全面完全軍縮であります。この問題に関する合意を達成することは、核実験、核兵器一般に関する問題をもことごとく解決するでありましょう。
ソ連邦政府の代表たちは、国連における代表をも含めて、もし他の列強が全面完全軍縮に進むならば、単にあらゆる形態の核実験が停止されるばかりでなく、われわれは、その保有する核兵器の一切の貯蔵を喜んで海中に投ずるであろうと一度ならず言明してきました。
ソ連邦政府は、短期間に全面完全軍縮を実現すべき具体案を国連に提出しました。しかしながら、西欧列強の立場によって、今日までこのような重大問題についてなんら実際的結果が達成されるにいたっていないのであります。
この関連において、日本政府がわれわれの計画を支持されず、軍縮に関する具体的方策の作成につき熱意を示されなかったことを指摘せざるをえないのであります。日本の国連代表は、言葉の上では軍縮の重要性を認めてきましたが、実質的には、今日の諸条件の下では軍縮が不可能があることを立証するためにその努力を傾けてきたのであります。本年十月二十八日付の貴簡によって判断すれば、日本政府は今もって全面完全軍縮を遅滞なく実現する必要があることを考慮しようとしていないのであります。
日本政府は、米国と新たな軍事条約を締結して、意識的に極東情勢を複雑化する挙に出でました。この条約は、米軍による日本占領を維持することを米国に許しました。日本の領土は目の細かい米国軍事基地網で蔽われました。米国軍部は、南朝鮮にも根をおろし、中国の島である台湾を保持し続けています。核・ロケットを含む近代兵器の予備が強度に蓄積されています。米軍が東方からソ連邦とその友邦および同盟国たる中華人民共和国および朝鮮人民民主共和国とを脅威するために、これらの地域に駐留していることは誰にも明らかでないでしょうか。
ソ連邦政府は、米・日軍事同盟の締結が日本を危険な道に押し進めるものであることに対し、一再ならず日本政府の注意を喚起してきました。しかしながら、日本政府はこれを考慮しないで、西欧列強、とくに米国によって実施されている戦争準備のますます積極的な参加者となりつつあります。
われわれが一再ならず、極東および全太平洋地域における非原子地帯の創設に関する提案を行なったことを想起せしめることも時宜に適することであります。米国による原爆の惨禍を経験した日本は、このような地帯の創設に他国に劣らない関心を寄せるべきであるように思われます。しかし、日本政府は、このわれわれの提案を拒否しました。今や、極東は、平和地帯に代わって、日本の直接参加の下で、戦争の危険な火元の一つになりつつあります。
また、十月二十八日付の貴簡でなされたドイツ問題に関するソ連邦政府の立場を歪曲した姿で示そうとする試みも黙過することができません。われわれは、対独平和条約の締結およびこれを基礎とする西ベルリンにおける状態の正常化に関するわれわれの見解をすでに一再ならず申し述べてきました。ソ連政府がドイツの軍国主義および報復主義に対する確実な障壁をつくるために、欧州の中心部における戦争の脅威の危険な火元をなくすために、ドイツ問題の調整に努めていることは周知のとおりであります。
しかるに、西ドイツの軍国主義および報復主義の抑圧を目的とするソ連のこれらの措置に対して、西欧列強は何をもって答えたでしょうか? われわれが対独平和条約を締結した場合にはNATO列強は実力を行使するであろうとの威嚇が、すでにここ数カ月間も全世界に聞え渡っております。この列強によって展開された戦争準備は、これを考慮に入れなくてもよいというような単なる口先だけの威嚇でないことを物語っています。米国官辺筋の人々は、米国が核兵器をも使用しうる旨を直言しています。西欧列強のこのような行動が国際情勢を極度に灼熱化したことは、もちろんであります。われわれは、それでもなお寛容を示し、ソ連邦の安全を十分に確保するために必要な措置をとらないことができましょうか? いや、できません。
ボンの報復主義者および庇護者たちと連携する者は、平和の事業に対してよくない奉仕をなしています。
われわれは、米国およびその同盟諸国が軍事侵略諸ブロックを組織し、われわれを軍事基地で包囲し、社会主義諸国および他の平和愛好諸国家に対する挑発を行なってきたとき、日本政府が抗議したということを耳にしたことがありません。
われわれは、米国および英国が太平洋に在る日本の島々の直接近辺で、核爆発を実施してきたとき、日本政府の声を実質上、耳にしなかったのであります。日本政府がその西欧友邦に送るわざとらしい形式的な書簡を真面目に受取ることはできないのであります。仏国がサハラで原子兵器の実験を行なったときでも、日本政府の声はほとんど聞かれなかったのであります。しかして、われわれが、われわれに対する露骨な威嚇に直面して、ソ連邦の安全を強化する措置をとっているとき、日本政府はソ連邦に対して敵意ある運動を煽るのに努めております。
総理閣下、私は貴簡についても、ソ連邦政府に圧力をかけ、われわれの防衛力強化を放棄することを強いようとする試みであるとのほかには、これを評価することが因難であります。もちろん、もしソ連邦が自己の合法的利益を守り、また、もし必要ならば、われわれまたは、われわれの友邦に対する攻撃がある場合には、侵略者に対して殲滅的打撃をえるために不用意であったとしたら、誰かにとって非常に好都合でありましょう。
もし貴総理が国際の平和を確保するために有益な諸措置をとることを真に欲しておられるならば、なぜ貴下は米国、英国、仏国、西独および他の西欧友邦に対して、ソ連邦に対する威嚇と戦争準備を止め、直ちに全面完全軍縮に進み、もってあらゆる核実験を停止するように呼びかけられないのでしょうか。
ソ連邦についていえば、われわれは有効な国際管理を伴う全面完全軍縮の早急実現を強くかつ断乎として支持するものであることを貴下に確言することができます。われわれは、いかなる時でも、いかなる瞬間でも、たとえ今日にでも、当該国際条約に調印する用意があります。
最後に、私は日本政府が言葉の上でなく、事実において国際緊張の源泉を除去することを助長し、また日本が全面完全軍縮に関する国際的合意の早急な達成を目ざすソ連邦の努力に同調するよう期待したいと思います。
ソ連は、一九六一年九月十日、タス声明をもって、ソ連政府が、中部太平洋の一部水域において九月十三日より十月十五日までロケット発射実験を行なう旨発表したので、九月十二日、新関欧亜局長代理は、在京ソ連大使館スズダレフ公使を招致し、口上書をもって左記の趣旨の申入れを行なった。
ソヴィエト連邦政府は中部太平洋の一部水域において九月十三日より十月十三日までロケットの発射実験を行なう由であるが、日本国政府は、ソヴィエト連邦政府がこの種の実験を行なうことに対し、遺憾の意を表明せざるを得ない。
ソヴィエト連邦政府は、今次実験のため長期間にわたり太平洋の指定海域に他国の船舶および航空機が立入らないよう関係各国政府に対し指令を出すことを要請しているが、日本国政府としては、この種区域の設定を行なう場合は、他国による海洋の使用の権利を不当に害することのないよう、できうる限り狭い区域とできうる限り短い区間に限ってこれを行なうべきものであると考える。
日本国政府として、日本国および日本国民が当該区域に対し漁業上その他深い利害関係を有するので、ソヴィエト連邦政府の措置または行動によって日本国および日本国民が蒙ることあるべき一切の損害または損失につき国際法上要求しうべき補償要求の権利を留保するものである。
これに対し、スズダレフ代理大使は、九月十八日、法眼欧亜局長を訪れ、本国政府の訓令に基づくとして、要旨次のとおりの口上書を伝達した。
ソ連大使館は日本国外務省に敬意を表するとともに、同外務省の本年九月十二日付口上書に関連し、ソ連政府が来るべき実験に関して日本国政府を含む世界各国の政府に適時に広く通知し、かつそれら諸国の船舶および航空機が実験の短期間中太平洋の極めて限られた水域および空域に立ち寄ることのないよう自国当該機関に指令発出方要請したことについてその注意を喚起する光栄を有する。
以上にかんがみ、日本国民およびその財産に対するこれら実験の何らかの好ましくない結果を予防することは、日本国民に対して適当に通知するために、日本国政府の講ずる措置にかかっている。
さらに、ソ連政府は、十月十三日に至って、タス通信を通じ、さきに中部太平洋におけるロケット発射実験のため設定した一部海域閉鎖期間を、十月三十日まで延期することを公表したので、十月二十日、法眼局長は、スズダレフ代理大使を招致し、十月二十日付口上書をもって、次のとおり重ねて対ソ抗議を行なった。
ソヴィエト連邦政府は、中部太平洋の一部水域におけるロケットの発射実験を十月三十日まで継続する由であるが、日本国政府は、ソヴィエト連邦政府のかかる決定に対し遺憾の意を表明せざるを得ない。
日本国政府は、さきに昭和三十六年九月十二日付口上書をもって、ソヴィエト連邦政府が今次実験のため長期間にわたり他国の船舶および航空機の立ち入りを禁止する閉鎖海域を太平洋の一部に設定したことに対し、これが他国による海洋使用の権利を不当に害することのないよう、できうる限り狭い区域とできうる限り短かい期間に限るよう申し入れた。しかるにソヴィエト連邦政府が日本国政府のこの申し入れに対しなんらの考慮を払うことなく、かえってその期間を十五日間も延長することに決定したことは、他国の有する海洋使用の権利に対する一層の制約を意味するものであることにつき、日本国政府はここに再びソヴィエト連邦政府の注意を喚起するものである。
日本国政府としては、前記口上書でも述べたとおり、日本国および日本国民が当該区域に対し漁業上その他深い利害関係を有するので、ソヴィエト連邦政府の措置または行動によって日本国および日本国民が蒙ることあるべき一切の損害または損失につき国際法上要求しうべき補償請求の権利を留保するものである。
一九六一年八月十五日より東京で開かれたソ連産業見本市の開会式に参列するためミコヤン第一副首相が来日するという報道は、同年三月初め頃からあった。これに対して大平官房長官は、三月二日の記者会見で、ミコヤン来日については未だ正式の申出ではないが、一九六〇年夏モスクワで開催された日本産業見本市にわが方から石井通産大臣が日本政府代表として出席した経緯もあり、ミコヤン第一副首相が来日するならば、日本政府はこれを歓迎するであろうと述べた。その後わが方は、在ソ門脇大使を通じて、この報道の確認を求めていたが、ソ側は、七月二十二日に至り、在京ソ連大使館を通じてミコヤン第一副首相の来日が決定したことを通報してきた。
よって、政府は、ミコヤン第一副首相がソ連政府およびソ連共産党内の最高幹部の一人であること、および石井通産大臣訪ソの際のソ側の待遇振りなどを考慮し、ミコヤン第一副首相を日本政府の賓客に準ずる待遇をもって迎えることに決定した。
かくてミコヤン第一副首相は、ミコヤン子息夫妻のほか、クジンソ外国貿易省次官、ネステロフ連邦商業会議所会
頭、ツガリノフ外務省極東部長等随員二九名を従え、八月十四日ソ連政府特別機で羽田着、翌十五日のソ連見本市開場式に臨んだ後、八月二十二日まで滞日した。この間、池田総理、小坂外務大臣、佐藤通産大臣、河野農林大臣と会談したほか、日本の政界、財界等の要人との会談、関西旅行、石井光次郎氏とのテレビ対談、工場見学等を行なった。
滞日中のミコヤン第一副首相の言動および訪日の際携行してきたフルシチョフ首相の池田総理あて親書(別項「池田総理とフルシチョフ首相の書簡交換」参照)は政治的色彩を帯びたものであったので、一般にわが国内においては、これらは、わが国の内政に干渉するものであるとの非難を呼んだ。すなわちミコヤン第一副首相は見本市の開会という純粋に経済的、通商的な任務の遂行を建前として訪日したのであったが、その際、日米安全保障条約や在日米軍基地の問題等にまで言及したことは、かねてソ連政府が唱導する内政不干渉の原則と相容れないものであったので、わが国内にかような反響を呼起す結果となったのである。
他方、ミコヤン第一副首相の滞日中、その身辺護衛のため非常に多数の警官が動員されたことについて、これが同第一副首相の自由な行動を束繋したという批判も一部にはあったが、これは、日ソ間に領土問題、近海漁業問題等未解決の問題が残っている現在、ミコヤン第一副首相を迎えるわが国内の民心の動向もさまざまであるので、政府としては何らか不測の事態の発生をも慮りこの要人の訪日を支障なく終了せしめて、両国関係の好転に資せしめようと望んだためにほかならず、結局、憂慮された反ソ的動きも街頭における反ソ宣伝ビラの貼布、見本市会場の飾り旗をちぎる等のいやがらせ程度で終ったことのかげには、治安当局の万全の警備が与って力あったものと思われる。
(イ) 概 説
北西太平洋日・ソ漁業委員会第五回会議は、一九六一年一月二十三日から東京において開催されることに前回の会議で決定されていたが、ソ側委員が病気のため開会が遅れ、二月二十日より本会議が開催された。なお、これに先立ち、日・ソ双方の話合いにより、委員会の運営改善と会期の短縮をはかるため、二月六日から、科学技術小委員会が開催された。会期は、百余日を要した後、五月二十一日、日・ソ双方は、合意議事録に調印、会議を終了した。この間、開かれた会議は、科学技術小委員会の会議十三回、本会議二十九回、両国委員の非公式会談五十回に達した。これは、会議の難航を示すものであった。
日本側からは、藤田巖(大日本水産会副会長)、新関欽哉(外務省参事官)、武田誠三(水産庁生産部長)の三委員、ソ側からは、モイセーエフ・ペ・ア(全連邦海洋漁業海洋学研究所長代理)、パーニン・カ・イ(太平洋海洋漁業海洋学研究所長)、スズダレフ・エス・ペ(在日ソ連大使館参事官・公使)の三委員ならびに双方の専門家が参加したほか、本年は、日・ソ双方が米国の希望に応じて、米国政府オブザーヴァーを科学技術小委員会の会議に出席せしめた。
(ロ) 主要問題の審議経過
二月二十三日の本会議において、議事日程が採択され、藤田議長(毎年日ソ交替で選出)の下で議事が進められたが、主要問題とその審議経過は、次のとおりである。
(a) さけ・ます年間総獲量
規制区域内のさけ・ます年間総漁獲量その他諸規制の決定の基礎となるべき条約区域におけるさけ・ます資源状態の問題については、科学技術小委員会における審議の結果、日・ソ双方とも、本年は一応豊漁年にあたることを認め、その水準が豊漁年たる一九五九年の水準に比し低い水準であろうということに合意した。しかし、ソ側は、日本の沖取りとくに規制区域外の南方水域における北海道根拠の漁業が強度なため、さけ・ます資源とくにます資源が急激な減少傾向にあると主張し、まず、現在大体北緯四五度以北となっているさけ・ます漁業に関する規制区域を拡大してさけ・ます全生息区域を規制区域として条約に基づく共同の規制措置をとることとするよう強い態度で提案し、南方水域の問題が解決しないうちは、規制区域内年間総漁獲量、禁止区域その他の諸規制措置の審議決定は不可能との態度をとるとともに、禁止区域その他の諸規制の強化を日本側に押しつけるための道具に規制区域内年間総漁獲量の問題を利用する態度をとったので、本年も、年間総漁獲量の決定は、結局会議終了直前まで持ち越された。
日本側としては、(一)本年の規制区域内年間総漁獲量は、一九六〇年決定の六七、五〇〇トンとその前年に決定された八五、〇〇〇トンとの間で決定されることが科学技術小委員会の結論からしても適当であり、(二)規制区域外南方水域の漁獲については、一九五九年の同水域の漁獲量(約九万トン)よりも二万トン程度減少せしめることを目途とした一連の自主的規制措置をとるという日本側の一方的声明を行なうことで規制区域の拡大を防止する策に出たが、ソ側は、前述の規制区域拡大を固執して譲らなかった。
漸く四月二十日にいたって、ソ側は、年間総漁獲量、禁止区域および漁期に関する声明を行ない、一九六一年における規制区域内年間総漁獲量を五万トン(二千五百万尾)以下とするとの数字を提示し、同時に、漁船数の制限を提案してきた。これに対し、日本側は、八万トンの数字を主張し、爾後双方の対立は、度重なる委員非公式会談によっても容易に解けなかった。
結局、双方の歩み寄りにより、五月十九日非公式会談において、六万五千トンとすることに妥結し、同月二十日の本会議で正式にこれを採択した。
(b) 規制区域の境界
前述のとおり、ソ側は、規制区域の南方への拡大を強く主張し、四月十二日の本会議において、一九六一年以降四五度以南のさけ・ます全生息区域および全操業区域を規制区域に入れ、現行規制区域内での措置に相応ずる措置をこれら全区域にも実施しようという提案を行なった。
これに対し、日本側は、規制区域の拡大は漁業条約の基本に触れる問題で軽々に取扱うべきでないこと、規制区域外の漁獲については、自主的に必要な措置をとれば十分であるとの見解を表明するとともに、日本側のとるべき規制措置を詳細に通報した。
その後もソ側の強硬な態度のため、双方の対立が打開できないままに南方水域の漁期が到来したため、四月二十日の本会議において、日本側はソ側に対し、従来よりもさらに強化した自主的規制の下に、規制区域外への出漁を許可せざるを得ない事態に立ち至った旨を正式に通告し、南方水域への一方的出漁を断行した。
ソ側は、かかる日本側の一方的行為が漁業条約の目的と委員会の任務を無視するものであると非難し、この問題はなお未解決であり、委員会が今後決定を採択すべきであるという趣旨の声明を行なった。これに対し、日本側は、規制区域外への出漁は条約上自由であり、今回の出漁は万止むを得ずしてとられたものであることを強調した。
その後、この問題は、討議に持ち出されず、規制区域の変更は事実上行なわれなかったが、ソ側は、その後の年間総漁獲量、禁止区域の審議に当りつねにこの日本側の「一方的行為」に対する報復的態度を示し、交渉の難航を招来したことはいうまでもない。
(c) さけ・ます漁業禁止区域および漁期問題
禁止区域および終漁期の問題は、過去の例にならい一つの議題に含めて審議されることとなったが、ソ側は、従来と同様、資源の減少、ソ側沿岸漁獲量の減少を理由として、禁止区域の拡大および漁期の短縮を要求してきた。
四月二十日の本会議においてソ側の提案したところは、(一)オリュートル岬南東二十海里の点、北緯五三度五〇分東経一七〇度の点、北緯五三度五〇分東経一六二度の点、北緯四五度東経一六二度の点を結ぶ線以西の全区域を含む水域を禁止区域とする、(二)沖取漁業の終漁期を七月二十五日とするというものであった。
日本側は、(一)総漁獲量の制限がある以上、禁止区域の設定は二重の規制であり、(二)日本側としては、一九六〇年分禁止区域をそのまま継続することが最大限の譲歩で、昨年限り設けられた規制区域南部の二つの漁獲停止区域は撤廃すべきであり、(三)終漁期は、八月十日が認めうる最大限で、短縮の必要なしという趣旨の声明をもってソ側提案に答えた。
ソ側としては、規制区域外への日本側の出漁断行に対する報復の意図もあったため、本問題に関しては極めて強硬な態度をとり、その後、日本側の努力により、五月六日、ソ側は、(一)漁期に関する提案の撤回、(二)禁止区域に関しては、(イ)コマンドルスキー群島以北の新禁止区域の撤回、ただし、そこで操業する日本側母船数の隻数の半減を要求する、(ロ)東経一六〇度以東北緯四九度以南の新禁止区域の撤回等の譲歩を示した。しかし、四八度以南の規制区域南部における禁止区域については、いぜんとして譲らなかった。
その後累次の会談で、結局、本年の禁止区域としては、昨年の禁止区域にさらに前年限りということで設けられた二つの漁獲停止区域を禁止区域として追加した上に、さらに、北緯四五度五一分東経一五五度の点、北緯四五度五一分東経一五一度三〇分の点を結ぶ直線以北の水域を加えることで合意が成立した。
なお、ソ側が新たに本年設定しようとした前述のコマンドルスキー群島北方の禁止区域は撤回せしめたが、日本側は、この区域で同時に操業する船団を二船団に制限することを声明した。
(b) べにざけ漁獲規制
べにざけ資源の保護問題は、第一回会議以来ソ側が提起してきたものであるが、本年、ソ側は、非公式会談において、一九六一年における規制区域内のべにざけ漁獲量を七百万尾とし、そのうち二百万尾までは東経一六五度以西の区域で漁獲することができる旨の提案を行なった。
日本側は、べにざけの漁獲制限は、従来の経験に徴し非現実的であること、および本年合意された資源状態からしても、ソ側の提案は根拠がないと主張した。
結局、昨年どおり、日本側がその声明で、母船式漁業につき試験的に実施するものとして、(一)べにざけ漁獲限度を七百七十五万尾以内とし、(二)そのうち二百五十万尾を東経一六五度以西の漁獲量とすることで解決した。
(e) 未成熟魚の混獲および網目の大きさの問題
さけ・ます資源の保護、とくにべにざけ未成熟魚漁獲防止のために流網の網目を大きくする問題は、従来の会議でも討議されてきたが、本年ソ側は、(一)規制区域全体にわたり、流網の配列の長さの半分は六〇・五ミリメートル、残り半分は六五ミリメートルの網目のものを使用すること、(二)さけ・ますの全生息区域にわたり、五五ミリメートル以下の網目の網の使用を禁止することを提案した。
しかし、本問題は、双方ともなお研究を要する点が多いことを認め、ソ側も歩み寄りを示したため、(一)両国は、一九六一年において網目を大きくする問題およびより大きな網目の網を使用する区域の境界問題について引続き調査研究を行ない、この調査研究には、日ソ互いに若干名の専門家を他方の科学調査船に乗船せしめることとする、(二)一九六一年および一九六二年においては、母船操業区域で使用する流網の総数のうち、五〇%を下らない部分は六五ミリメートルを下らない網目の網とすること、(三)未成熟魚の混獲許容限度の決定に関する問題については、一九六一年において調査研究を行なうということで解決した。
(f) 流網の網糸の太さの問題
さけ・ますの損傷を少なくするため、網糸の太さを太くする問題については、今回の会議においては、ソ側より、日本側が細い糸の網を使用しているため損傷魚がいぜんとして多いと主張し、糸の太さを太くする必要を認める旨の提案があったが、日本側は、その調査研究結果に基づいてこれを反駁し、かつ、本問題は、さらに引続き調査研究することとし、結局、本年も、糸の太さを太くする可能性を研究するため調査研究を継続するということで落着した。
なお、損傷の種類、部位、状態その他の判定のため合意された従来の基準が今回の会議で若干修正された。
(g) つり漁具の問題
今回の会議においても、ソ側は、つり漁具による漁業は魚体を損傷する不合理なものであるとの立場を固執し、日本側の調査研究の結果を不十分とし、日本側のつり漁具による漁体の損傷率の高いことを主張した。
三月七日の本会議において、日・ソ双方は、一九六一年において、つり漁具による損傷の程度を少なくする可能性を究明するため、調査研究を行なうという趣旨の決定を採択した。
(h) 害魚等のさけ・ますに及ぼす影響の問題
本問題は、第三回会議以来日本側の提起した問題であるが、今回の会議においても審議の結果、昨年どおり、調査研究を継続し、かつ、拡充し、その結果を次回の会議で審議する旨の決定を採択して審議を了した。
(i) にしんに対する規制措置
三月十三日の本会議において、ソ側は、樺太・北海道にしんの資源が減少したことに関連し、一九六一年以降五カ年にわたる禁漁実施と、生物学的調査の継続を主張し、日本側は、樺太・北海道沿岸海域が近年にしんにとって好適な自然的条件でなくなっていると認められるので、これが好転しない限り、漁業規制を行なっても、この資源状態が過去の高い水準にまで回復することは期待できない旨を声明した。
ソ側も、樺太・北海道にしんに対して自然条件が影響していることは認めたものの、なお漁獲制限等の人為的措置の必要を強調した後、三月十六日にいたり、日・ソ双方、樺太・北海道にしんの資源状態の悪化にかんがみ、一九六一年において、資源状態の特徴づけおよび回復に関する科学的調査研究を強化、継続することを勧告する旨の決定を採択した。
(j) かに漁業に対する規制措置
四月四日の本会議において、ソ側は、かに漁業禁止区域はじめ、かに網の沈設規則、めすがに・子がにの混獲許容限度、缶詰製造函数その他の提案を行ない、四月八日には双方の間に非公式合意が成立し、決定案の公式採択の運びに漕ぎつけられたが、同日、ソ側は、前述第二項の南方規制区域拡大問題にからませ、かゆ問題の正式決定を遷延する態度をとった。このため、かに問題と南方規制区域問題が並行して審議されることとなった。
双方論議を尽した上、四月二十二日の本会議において、カムチャツカ西海岸に近接する北緯五六度二〇分以北・北緯五六度五五分以南の区域および北緯五一度以北・北緯五三度以南の区域を禁止区域とするとの委員会決定を採択し、(イ)日本側は、一九六一年における西カムチャツカ水域の母船数は四隻を超えず、缶詰製造函数は二十六万函(半ポンド缶四十八個)、ソ側の母船数は六隻をこえず、函数は三十九万函(日本と同じ計算にして)を超えないものとする、(ロ)五月二十五日以前および八月十日以後の期間、日・ソ双方の専用漁区を設定(漁区設定の順序は昨年の逆)とする、(ハ)網の沈設期間は、四月中大昼夜、五月中八昼夜(日本側)、(ニ)沈設反数は、各母船につき、四月中一万五千反、五月中二万反(日本側)とするとの趣旨の声明をそれぞれ行ない、また、めすがに・子がにの混獲許容限度については調査研究を行なうことに決定された。
北西太平洋日・ソ漁業委員会第六回会議は前回の会議の決定どおり一九六二年二月二十六日からモスクワにおいて開催された。
日本側からは藤田巖(大日本水産会副会長)、重光晶(在ソ連邦日本国大使館公使)、および大口駿一(水産庁生産部長)の三委員、ソ側からはモイセーエフ・ぺ・ア(全連邦海洋漁業海洋学研究所長代理)、ミロノフ・ニム・エヌ(ロシア共和国大臣会議附属魚類資源保護漁業規則国家監督総局長)およびチェルノフ・イ・エフ(ソ連外務省一等書記官)の三委員ならびに双方の専門家が参加したほか、日ソ双方の合意に基づき米国政府のオブザーバーが科学技術小委員会に出席することが認められた。
同会議は二月二十八日の第二回本会議において二〇項目にわたる議事日程を採択し、爾来三月末までに本会議一四回、科学技術小委員会会議一〇回のほか随時非公式会談を開いて、条約の規定および委員会決定の前年度における双方の通報および規制区域における漁業の管理手続ならびに条約区域におけるさけ・ますの資源状態等の問題を審議したが、なお漁業の規制措置および規制区域における年間漁獲量の決定など重要な問題の審議が残っており、これが解決を促進するため政府代表として高碕達之助氏が三月二十八日東京発空路モスクワに赴いた。
日ソ漁業委員会第五回会議の決定に基づき、本年六~七月、日ソ間の学識経験者の交換が実施された。
すなわち日本側学識経験者の調査団は、陸上関係および海上関係の二班にわかれ、前者は樺太、オホーツク、西カムチャツカ地方を視察し、また後者はソ連側調査船に乗込んで共同調査を行なった一方、ソ連側調査団も陸上班は北海道および関西地方を視察し、海上班は日本側母船および調査船にそれぞれ分乗して調査を行なった。
一九六一年八月二十一日河野農林大臣と当時来朝中のミコヤン・ソ連副首相との会談の際、一九六二年の日・ソ漁業委員会第六回会議の早期妥結をはかるため日・ソ漁業条約の対象である資源および技術の問題についての双方の専門家による討議を本年秋に行なうことに意見の一致をみた。
右に基づき日・ソ間で協議の結果、十一月二十七日より一カ月間の予定をもってモスクワにおいて日・ソ漁業専門学者会議を開催することとなり、日本側よりは大口水産庁生産部長以下の専門家、学者が、またソ連側よりはセムコ太平洋漁業海洋学研究所カムチャツカ支所長以下の専門家、学者参加の下に予定どおり会議が開かれた。
同会議は北西太平洋さけ・ますの資源状態の評価を主として、その他技術的問題をも審議したのち、十二月二十七日合意文書の署名をもってその幕を閉じた。
日・ソ間の領土、領海等の問題が未解決である結果として、一九六一年以降もわが国の北方海域出漁々船とその乗員が引続きソ連側に拿捕抑留されており、一九六二年三月三十一日現在で、終戦以来のソ側による拿捕漁船および乗員の総数は九八七隻、八四二三名に上り、そのうち六八七隻、八三三九名および遺骨一名が帰還し、二八四隻、七一名がソ連側に抑留されたままと推定される。このほか一六隻が撃沈または船体放棄され、一三名が抑留中死亡している。
一九六一年一月から一九六二年三月三十一日までの漁船および乗員の拿捕、帰還の月別統計は次のとおりである。
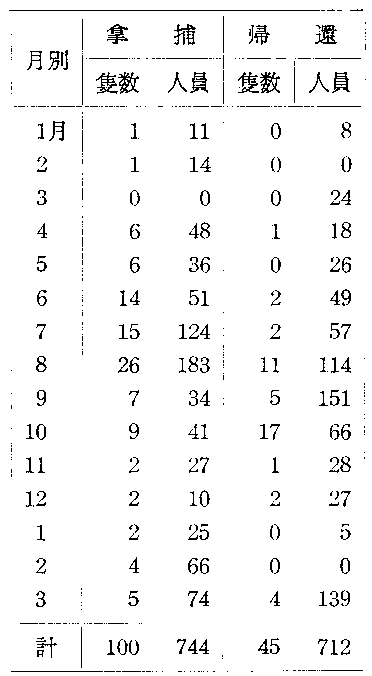
前記の期間に、外務省は、ソ連外務省より在ソ大使館を通じ口上書をもって一一回にわたり拿捕の事実について、六回にわたり拿捕漁船乗員の裁判の結果について、また二七回にわたり釈放された乗員および船体の引渡しについて、通告をうけた。乗員および船体の引取りについては、その都度外務省から海上保安庁へ連絡し、同庁の巡視船を使用して行なっている。
ソ側の通告によれば、裁判の結果有罪の判決をうけた乗員の罪は、「ソ連邦の領海内で不法漁携を行なった」ことにあり、乗員の責任者である船長、船主あるいは漁撈長は禁錮一年ないし四年(執行猶予の場合もある)、船体、漁具、漁獲物没収の判決をうけている。ただし、これらの者のほとんど全員は、これまで刑期満了前に釈放され、帰還している。裁判をうけないで釈放される漁船とその乗員は、通常約二カ月間抑留されたのち、船体とともに帰還せしめられている。このほか、海上においてソ連国境警備艇の臨検をうけ、現場においてそのまま釈放された漁船も多数に上っている。
外務省は、一九六〇年四月および一九六一年十月在ソ大使館を通じソ連側に抑留されている漁船の返還を申入れたが、これに対しソ連外務省は一九六二年一月、日本側から返還を要求された船舶は、「ソヴィエト司法機関の決定により没収された」ものである旨を回答し、日本側の返還要求を拒否している。
引揚問題に関し、政府は、本問題の完全解決を計るために、現在ソ連に残留しているもので帰国を希望しているものに対する援助、消息不明者の調査、死亡者に関する資料提供ならびにソ連に所在する日本人墓地の参詣等について申入れておいたところ、一九六一年四月ソ連側はハバロフスクおよびチタに在る日本人墓地の参詣を許可してきた。よって遺族代表者三十名のほか政府係官、報道関係者等四十四名が八月十五日全日空機で羽田を立ち、ハバロフスク、チタ両墓地を巡歴して同二十八日に日航機で帰国した。
その後右両墓地以外の墓地の参詣に関しても申入れ中のところ、一九六二年一月三十一日、ソ連側は、ナホトカ、ハバロフスク、チタ、イルクーツク、タシケントならびにモスクワ郊外のクラスノゴルスクおよびリュブリノの七カ所に在る墓地への参詣を許可してきたので、目下実施計画につき検討中である。
一九六一年五月十八日在京フェドレンコ大使は、小坂外務大臣を来訪し、日・ソ文化交流問題に関する同年一月二十一日付の日本政府提案に対する回答を手交した。同回答は、政府刊行物の交換、科学者等の交流、映写会の相互開催について取極を結ぶというわが方の提案に原則的に同意してきたものであるが、双方の案にはなお細部において若干の差異があったので、九月二十五日法眼外務省欧亜局長は、在京スズダレフ臨時代理大使を招致し、あらためてわが方対案を手交した。
その後、一九六二年三月二十日、フェドレンコ大使の賓客として訪日したソ連邦閣僚会議対外文化連絡委員会ジューコフ議長(閣僚)は、小坂外務大臣を訪問し、この機会に、日本との間にかねて懸案となっている文化取極を締結したいとの希望を表明したので、法眼欧亜局長と、右文化連絡委員会コヴアレンコ部長との間に具体的交渉が進められた。右会談に際しソ連側は、再び、一九五八年に日本政府に提案した文化協定案を再検討するように要請し、もし日本政府として同案が受け入れられない場合には、ソ連が米国、イタリア等との間にとりきめている文化交流方式にならうべきことを提案した。これらは、いずれも、締約国相互間における広範囲な文化交流を定めたものであるが、日本政府としては、予算上の制約もあってこのような提案を受諾できないことは、過去においてもしばしばソ連政府に説明したことであり、しかもソ連側もすでに原則的に了解していたことであった。結局、ソ連側も、取極の内容を日本案どおり、政府刊行物の交換、科学者等の交流、映写会の相互開催の三点の事項に限定することに再び同意したが、かし、その際、右取極の外に、日・ソ間に共同コミュニケを発表し、両国政府が民間文化交流を奨励する旨の文言をし入れるように提案した。日本政府としても、コミュニケを発表することには異議はなかったが、ソ連案のような一種の「精神視定」を含めることは、元来政府間の「実施取極」を行なうという日本政府の意図に副わぬことでもあり、ひいては、実施を約する三項目のほかにさらに広汎な義務を負うことともなるので、同意しがたいという立場を一貫した。かくてソ連側も、一たんは、コミュニケの表現に関する日本側の主張に同意したが、最終段階に至って、再びその前の案に立戻るに至ったので、交渉は止むなく中断し、ジューコフ議長は、四月八日、コヴァレンコ部長を帯同して帰国した。なお、文化交流取極交渉は、今後東京およびモスクワにおいて通常の外交経路を通じて継続されることとなった。
一九六一年八月東京で開催されたソ連商工業見本市開会式に出席のため来日したミコヤン・ソ連第一副首相は、河野農林大臣との会談の際、河野農林大臣が提案した日・ソ両国間の農業技術交流に賛意を表明し、直ちにこれを実行に移すことが約束された。農林省はこれに基づき、外務省にたいし、本件の具体的実施についてソ連政府の了解を取付けるよう依頼してきた。
農林省の交流計画は、両国間で相互に研究者、技術者および農民より成る視察団を派遣交換し、彼我の農業に関する研究、技術について理解を増進するとともに、相互に進歩した研究成果、農業技術を吸収し合い、農業生産力の向上に資することを目的とし、相互に視察団を派遣しようとするものであるが、外務省は、同年十月在京ソ連大使館を通じ、右日本側提案をソ連側に伝達した。
これにたいし在京フェドレンコ・ソ連大使は、一九六二年二月十五日武内外務次官を来訪し、ソ連側は日本との間に相互主義に基づき、農業代表団を交換することに同意し、かつ、代表団交換の諸問題(期間、構成、目的、受入条件等)については日・ソの関係当局の間で、その都度合意する方法によりたい旨文書により回答した。
よって、外務省は三月二十日、日本政府が一九六二年六~七月に若千名よりなる作物育種班をまずソ連に派遣したい旨をソ側へ申入れた。
(1) 議定書の調印
日・ソ国交回復以来両国間貿易は着実に発展し、一九五七年十二月六日には「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の通商に関する条約」が調印されたが、その際両国政府代表間に交換された「日ソ諸港間の定期航路開設に関する書簡」に基づいて、一九五八年六月三日、飯野海運、川崎汽船、山下汽船の三者により共同運営されるジャパン・ナホトカ・ライン(通称JNL)とソ連極東国営船舶公社「モルフロート」との間に「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦とり諸港間(横浜/ナホトカ)の定期航路開設に関する協定」が締結された。
この協定に基づいて日本/ナホトカ/日本間に定期貨物船航路が開設されたが、その後の事態に即応して、一九六一年七月十二日モスクワにおいてJNLとモルフロートの代表者間に前記協定を充実させるための「議定書」が調印された。
(2) 調印に至る経緯
(一) 原協定の主要取極め事項
(イ) 双方は、神戸、大阪、広畑、門司、八幡、舞鶴、敦賀、富山伏木、新潟、函館および小樽を寄港地とする横浜/ナホトカ間の定期貨物船航路を開設する。
(ロ) 双方は、本航路の就航船舶として積載力の等しい三、五〇〇~四、○○○トンの船舶を配船する。
(ハ) 双方の船舶は、それぞれ月に一回、年間十二航海を行なう。
(ニ) 双方は、両者の船舶が貨物を公正かつ均等に積取り得るよう努力する。
(二) 協定改定交渉の経緯
(イ) 爾来日本側は前記三社が山下、川崎、飯野の順序で、またソ連側は「モルフロート」が単独で、双方それぞれ協定の枠内で配船し、協定は比較的円滑に運営されてきた。しかし一九六〇年以降、ソ連側は、次第に右協定内容を超えて運航を行なうようになってきた。例えば同年ソ連側は、二十七航海を実施し、就航船舶に五、○○○トン以上の、時には八、○○○トン級のものを使用し、積載貨物の積取りも必ずしも当初の合意どおりには行なわれなくなってきた。
(ロ) このような事態に対し、協定の日本側当事者であるJNLはソ側当事者たる「モルフロート」、および「ソフフラフト」(全連邦国営傭船公社)に対し一九六一年一月十三日付書面をもって、日本/ナホトカ航路の現状にかんがみ、また日ソ貿易今後の発展も考慮し、この際双方により現行協定を再検討の上適当な改正を加えることを適当と考える旨、ならびに右に関するソ側見解を承知したい旨申入れた。
(ハ) 次いで二月二十六日夜の日本向けモスクワ放送は、ソ連イントゥーリスト・シズメンコ東方課長談として、『ナホトカ/東京間「旅客船」の定期航路は一九六二年五月二十六日に開かれ、これにはソ連ディーゼル船スモールヌイ号が就航する。同船は客席約二〇〇で月二回定期的に日本へ航海する云々』の発表を行なった(その後、就航船はモジャイスキー号に訂正された)。
(ニ) 日本政府は、かねてJNLを通じ、ナホトカ航路の現状に注目していたが、客船就航に関する前記シズメンコ談にはとくに大きな関心を有したので、取敢えず二月二十八日JNLをしてソ連側の意図および計画の詳細を照会せしめるとともに、在ソ大使館を通じソ側計画の詳細、その法的根拠等を確かめることとした。
(ホ) その間三月中旬には「モルフロート」よりJNLに対し、モスクワにて改定交渉を行なうことに同意する旨回答越し、その後の折衝により交渉期日は六月下旬と予定された。また「モ」号の就航についても四月下旬ソ連政府より日本政府に対して正式通告があったが、その際ソ連側は「モ」号は貨物輸送をも行なうべき旨を明かにした。
(ヘ) わが方としては、「モ」号が旅客運送のほか貨物輸送をも行なうのであれば、当然現行協定で規整さるべき性質のものと考えた。また本件協定の改定交渉は大部分純粋に商業的性質のものであるとしても、現行協定の交渉に際しては、日ソ双方の政府代表が政府間協議事項検討のために参加した経緯ならびに現行協定の基礎となった前述第一項の「日ソ諸港間の定期航路開設に関する書簡」中の了解事項にかんがみても、改定交渉に政府関係官が列席することは当然であり、またこの際目・ソ間の旅客輸送に関しても所要のとりきめを行なうこととなれば、この点からも政府代表が参加することが適当であると考えたので、この旨をソ連政府に申入れた。その後両国政府間に折衝が行なわれた結果、わが方は、協定改定交渉以前に「モ」号が臨時に就航することを認め、ソ側は、六月開催予定の交渉に同意した。わが方は、六月二十七日政府関係官二名を含む代表団七名のリストをソ側に提示し、七月三日より交渉開始の希望を申入れた。ソ側もこれに応じ、交渉は、七月三日開始され、前述のとおり同月十二日妥結し、議定書が調印された。
(3) 議定書の主要取極め事項
(イ) 双方は、本航路運営のため原則として積載力六、○○○トンを超えない船舶を使用し、それぞれ原則として年間十八ないし二十航海を行なう。各船のスケジュールは各四半期に作成する。
(ロ) 双方は、それぞれ積載力六、○○○トンの船舶の代りに総積載力六、○○○トンを超えない限り二隻以上の船舶を配船することができる。従って、この場合総航海数および各月の発航数は増加する。
(ハ) 双方は、旅客輸送のため、ナホトカおよび日本諸港間に客船または貨客船を配船しうることに合意する。そのスケジュールおよび寄港地はJNLと「モルフロート」間において直接協議決定する。
(ニ) 客船または貨客船の航海数は前記(イ)の貨物船の航海数に含まれない。ただし、客船または貨客船に貨物を積む場合、その積高は、双方それぞれの貨物の割当量に含まれるものとする。
チェッコスロヴァキア社会主義共和国国民議会副議長ワツラフ・シコダ博士は、同国民議会議員八名および随員二名を帯同し、一九六一年五月一日来日し、同月十一日まで滞在した。
この間、議員団一行は天皇陛下に拝謁を賜り、衆・参両議院議長、池田総理大臣、小坂外務大臣およびその他と会談したほか、関西、広島、北九州および北海道の各地方の視察旅行を行なった。
なお、わが国会議員団はさきに、チェッコ国民議会の招待により一九五九年夏、同国を訪問したが、今回のチェッコ議員団の来日は、わが国会の招待によるものである。