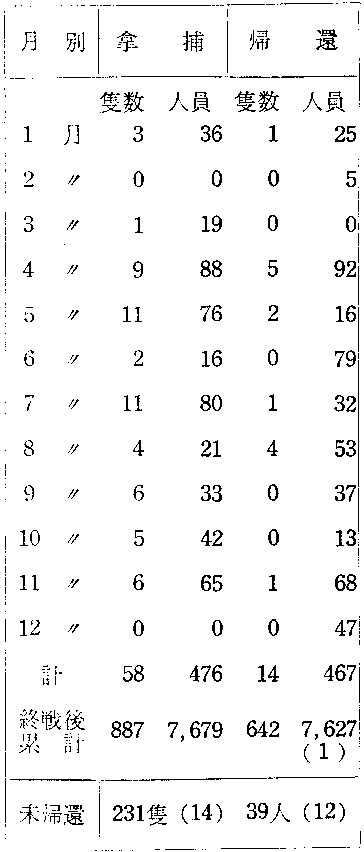
| 東欧関係 |
戦後、北海道・樺太・千島の近海において、領土、領海等の問題が未解決の結果として、わが国の出漁漁船ならびに船員が、多数ソ連側にだ捕抑留され、わが政府も種々これが対策を講じていることについては本書第一号より第四号までの各号に詳述したところである。ソ連側によるだ捕は本年に入っても引続き行なわれているが、昨年末現在、終戦いらいのだ捕漁船および船員の総数は、八八七隻、七、六七九名に上り、そのうち、六四二隻、七、六二七名および遣骨一名が帰還し、二三一隻、三九名がソ連側に抑留されたままとなっている。この他一四隻が撃沈または船体放棄され、一二名が抑留中死亡している。
昨年度における漁船および船員のだ捕、抑留、帰還の月別統計は次の通りである。
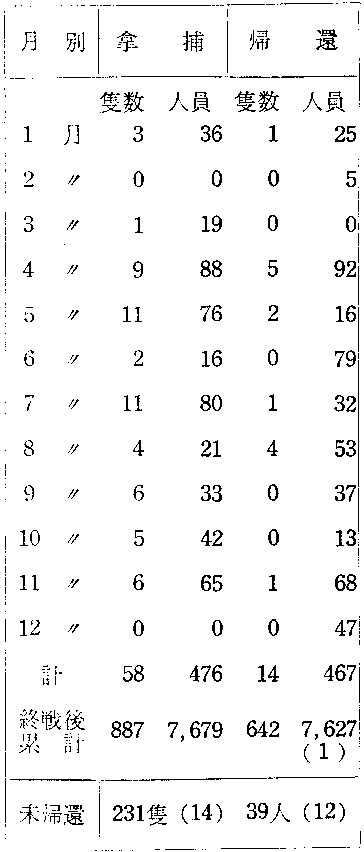
領海三海里説をとっているわが政府としては、未解決の領土問題をも含め、ソ連政府のこのような措置を容認し得ないので、一九五六年七月、当時の在京ソ連漁業代表部時代より十回にわたりソ連政府の措置に抗議するとともに漁船、漁具の返還等を要求した、さらに、一九五九年三月には本問題を国際司法裁判所へ付託する意志があることを表明したが、ソ連政府はこれに応ぜず、かえってこれら漁撈はわが国の漁業家による計画的組織的なソ連領侵犯であり、わが政府の責任であると非難して今日に至っている(本書第四号参照)状態であり、昨年度には本問題は何ら解決の徴を見せなかった。
わが国の北方海域における漁船および漁夫のだ捕問題は、領土、領海等の問題が最終的に解決しないかぎり解決の見込みがないので、わが政府はだ捕問題とは別個に一九五七年六月、在ソ門脇大使を通じ、わが国の小漁船が歯舞、色丹、国後、択捉およびその他の千島諸島の周辺海域でこんぶ、かに、ほたて貝等の採取をみとめられるようソ連政府と交渉せしめた。これに対しソ連政府は同年八月、わが政府が申し入れた「若干の海域のソ連領域における漁獲および海産物採取問題について日本側と交渉に入る用意がある」旨を回答してきたので、わが政府は具体的な協定案を示してソ連側の回答を求めた。
しかるに一九五八年二月ソ連政府はこの問題を平和条約とからませ「日本政府が今なお平和条約を締結する用意を表明しないことにかんがみ、本件漁業問題を審議する条件が未だ熟していない」と回答してきたので、この問題は頓座するに至った。その後ともわが政府は機会をとらえてソ連政府と折衝し、その再考を求めた経緯は本書第二-三号に詳述したとおりであるが、さらに本年一月北太平洋おっとせい委員会第四年次会合に出席のため来日したソ連政府イシコフ漁業部長が、一月二十三日小坂外務大臣と会談した際、同外務大臣よりこの問題にふれ、「日本政府日ソ双方が平和条約未締結の責任を論難し合うのみではなんら問題の解決にはならず、両国が善隣友好の精神から、本問題を人道的見地に立って現実的に解決することが望ましいと考えているので、ソ連政府が本問題を平和条約と関連せしめることなく、さきに日本側が提示した日本政府の暫定協定案を検討され、すみやかに日本政府と交渉に入り、日ソ両国関係改善に一歩前進されるよう希望する」と述べた。これに対し、イシコフ漁業部長は、「ソ連の態度は、一九五八年となんら変りない」との趣旨を述べた。
同日の午後イシコフ漁業部長は池田総理大臣とも会見し、その際同総理大臣から、わが国の零細漁民に対する人道的見地からソ連側から本件について寛大な気持ちで対処して欲しい旨重ねて要望したが、その後とも本件は何らの進展をも示していない。
(1) 北西太平洋日ソ漁業委員会第四回会議
北西太平洋の公海における漁業に関する日ソ間条約に基づき、一九五七年以来毎年東京かモスクワかで開催されてきた日ソ漁業交渉、すなわち北西太平洋日ソ漁業委員会の年次会議は、昨年もまた二月二日より五月十八日まで、モスクワで開催された。
この会議には、日本側から藤田、法眼、武田の三委員のほか、顧問および随員二十一名が、ソ連側からはモイセーエフ、パーニン、フレストフの三委員のほか、二十名の随員が参加し、本会議三十回、科学技術小委員会会議二十六回、両国委員間非公式会談四十回に及ぶ審議を重ねた。なお四月中旬以降は漁業交渉代表としてわが国より到着した福田農林大臣と高碕大日本水産会長とが、ソ連国家計画委員会漁業部長イシコフ大臣との間に、さけ・ます年間総漁獲量などの重要問題について交渉を行なった。
右会議で審議決定された最も重要な問題はさけ・ます年間総漁獲量であって、合計六万七千五百トンと決定された。この他にも各種の問題が審議されたが、これらのうちでとくに重要な問題の審議の模様およびその結果は概要次のとおりである。
(イ) さけ・ますの年間総漁獲量の決定
日本側は従来とも、さけ・ますの総漁獲量問題は、その資源状態の審議に引き続いて審議決定すべきであるとし、今回もこれを主張したが、ソ連側は漁業禁止区域をはじめ、漁業規制措置に関する諸問題の解決の後にこれを決定すべきであると主張した。このため、本問題の審議と決定とは結局会議の後半に持ち越される結果となり、しかも後述するような他の諸問題の審議の結果と関連して解決せざるを得なかった。
本問題の審議にあたり日本側は、さけ・ますの資源状態は過去において日ソ双方が行なってきた程度の漁獲を持続し得る状態にあること、一九六〇年の資源全体としての豊度も、不漁年であった一九五四年、一九五八年を上廻り、ほぼ一九五六年のそれに匹敵すると考えられること、などに基づき、条約上の規制区域での年間総漁獲量を八万五千トンとすべきことを主張した。しかしソ連側はこれに反対し、科学技術小委員会が一九六〇年を不漁年と認めているとなし、各魚種の資源は近年における極めて強度の漁獲の結果著しく減少しており、ことにますの減少が極端である旨を主張した。またその結果として、一九六〇年にはますの全面禁漁を行なうべきであるが、それが実行不可能であるとすれば、委員会はさけ・ますの産卵場への通過のため、最良の条件を保障できるような一連の規制措置を採択すべきであり、そのような措置は規制区域の内外での沖取の漁獲量を本質的に削減することを併せて行なわなければ効果がないとし、一九六〇年における現行規制区域内での漁獲量は五万トンを超えてはならないという声明を行なった。
このような双方の意見の対立の下に、福田・イシコフ会談、高碕・イシコフ会談が始められた。日本側は総漁獲量につきソ連側の再考を求めるとともに、規制区域内外、ことに北緯四十五度以南においては自主的に規制措置を講ずるものであることを説明して鋭意折衝につとめた。
その結果ソ連側も、もし日本側でその提案の漁獲量を削減するならば、ソ連側提案の禁止区域について若干譲歩する用意のあることを暗示し、交渉は漸く妥結の方向を示すにいたった。結局において、禁止区域については後述のような合意が成立するとともに、総漁獲量についても互いに歩み寄り、五月十七日にいたり総漁獲量を六万七千五百トンとすることに妥結した。かくして翌十八日の本会議でこれを採択し、同時に第四回会議の議事録も調印された。
(ロ) 規制区域外の漁業規制問題
さけ・ますは漁業条約上の規制区域外、すなわち北緯四十五度以南においても、日本漁船によって漁獲されているが、漁獲されるさけ・、ますは規制区域の内外において同一系統のものであるため、ソ連側は第四回会議では後述する規制区域内の禁漁区域問題およびその他の問題とともに、規制区域外における禁漁区域の設定の問題を提示してきた。その区域は北緯四五度東経一五五度、北緯四〇度東経一五五度、北緯四〇度東経一六〇度、北緯四五度東経一六〇度の四点を直線で結ぶものであった。
これに対し日本側は、規制は最も必要と考えられる公海についてこれを行ない、その他の区域については国内的に必要な措置をとれば足るべきことなどを主張し、日本側のとるべき自主的規制措置として、漁獲物陸揚地の限定、延縄漁業の規制、操業許可の場合の漁獲割当量の明確化、監視船の増加、漁船の大型化不許可などを披露した。しかしソ連側はなおその規制措置の内容について満足するにいたらず、問題が解決しないままに福田・イシコフ会談が開始されることになった。そこで福田農林大臣からも、日本側はその自主的規制によって二~三万トンの漁獲減となるべきことを説明し、その他の問題とともにこの問題をも解決すべきことを申しれた。イシコフ大臣は日本側の自主的規制措置とはげん条維持に過ぎないと反駁していたが、さけ・ますの年間総漁獲量について双方の歩み寄りがみられるに及び、規制区域外における日本側の自主的措置に関しわが政府の誠意を信じようとの態度をとるにいたった。
(ハ) さけ・ますの禁漁区域設定問題
ソ連側は第四回会談において、前年設定せられた漁業禁止区域をさらに拡大した広い禁止区域を、規制区域内に設定すべきことを提案した。これは前述のとおり、規制区域外の漁業規制その他に関する提案とともに提示されたものであるが、その範囲はカムチャツカ半島および千島列島から東方に向かって凹凸状に張り出し、二カ所の凸部はべーリング海の半ば(東経一七五度)に及ぶものであった。その上ソ連側は漁期を七月十五日に制限すべきことをも提案した。
日本側としては全面的にこれに反対したが、さけ・ますの総漁獲量につき審議が開始されるに及んで、日本側としても大体前年に設定された禁止区域を一九六〇年においても認めるという案を示した。ソ連側もまた譲歩案を示してはきたが、前年度の禁止区域のほかに、なお千島東方において北緯四五度と四八度、東経一五五度と一六〇度によって囲まれる四角形(前年の禁止区域につづく)および北緯四五度東経一五二度により南と東から囲まれる三角形(同じく前年の禁止区域につづく)をも禁止区域とすることを固執して譲らなかった。その結果日本側も交渉の最後の段階において右三角形を認めるとともに、同区域と同一の面積を、前記四角形の南部から削除することとした上でこれを認めた。従って一九六〇年の禁止区域は、オホーツク海のほかに、コマンドルスキー群島の周辺、東千島の東方および南千島の東南方において、ことに広大な範囲におよぶ結果となった。
なお漁期の制限については、ソ連側もその提案を撤回するにいたったので、従来どおり八月十日となった。
(ニ) べにざけ漁獲規制問題
ソ連側はひとりべにざけのみでなく、さけ・ますの各魚種につきその資源状態を検討し、それぞれに対して措置をとることを必要とするとの見解を述べたが、べにざけについてはとくに一九六〇年の漁獲許容量を八千トン以内に制限すべきことを主張した。日本側はこれに反対し、べにざけを多く漁獲する母船式漁業につき、前年同様の方式でその漁獲目標を二万二千トン(大体千百万尾)とすることを主張したため、問題は容易に解決しなかった。しかし結局福田・イシコフ会談において、べにざけの漁獲量を一万五千五百トン(大体七百七十五万尾)と定めて妥結した。
(ホ) 未成熟若年魚の漁獲規制、網目制限問題
ソ連側はしろざけおよびべにざけの未成熟魚の混獲許容限度を一〇%とすること、しろざけ、べにざけの優勢な沖合区域での流網の網目を六八-七〇ミリ・メートルまで大きくすることなどを提案した。これに対し日本側は、一九六〇年から四年以内に母船式独航船の網を毎年二五%ずつ六五ミリ・メートルのものに取替えることなど従来の決定に基づき、これを実施する場合の規定などを説明して折衝した。結局未成熟魚の混獲許容限度の問題は、来年の委員会に持ち越すことに双方合意し、網目については大体前記六五ミリ・メートルの網目を使用する場合の詳細規定をつくることなどによって解決した。
(ヘ) 網糸の太さ、釣漁具問題
ソ連側は今回もまたさけ・ますの損傷を少なくするため、流網の糸の太さを現在よりもさらに太くすることが望ましいとし、その可能性について専門的調査研究を継続する案を提示したが、この点については日本側も異論なく、その趣旨の決定を互いに採択した。
釣漁具による損傷を少なくすることその他についても、種々論議の後、結局前年のとおり調査研究を続行するという決定を採択することとして解決した。
(ト) かに漁業規正問題
日ソ双方からかに資源の評価につき意見の開陳があった後、かに漁業の禁止区域、漁業終期、網の標札および設置日ソ操業区域の調整、めすがに、子がにの混獲、製造函数、カムチャツカ西海岸以外の方面のかに漁業規制などにつき、ソ連側から提案があったが、日本側から対案を示して折衝した結果、カムチャツカ西海岸について大体前年の条件に近い決定を採択した。もっとも網の長さ、間隔、標札などについては新しい規定を採用し、また製造高については前年よりやや少なく、日本側は二六万函、ソ連側は三九万函(日本式計算方法により換算)とすることを決定した。
(チ) にしん漁業規制問題
ソ連側から北海道、樺太南部、国後島沿岸における樺太・北海道にしんの禁漁を提案してきたが、日本側からこれに反対した結果、前年と同様、北海道沿岸のにしんの主要産卵場における調査を行なうこと、樺太西岸に産卵にしんの禁漁区を設けることなどを決定した。
(2) 日ソ漁業関係学識経験者の交換
第四回会議では前年と同様、漁業に関する学識経験者の交換について勧告を行なったが、なお、前記(ホ)の網目の問題に関連して、科学調査船にそれぞれ相手方の専門家を乗船させて調査させることを新たに決定した。
右に基づき両国政府間で、具体的な計画の実施方法について打ち合せた結果、双方それぞれ次のような視察と調査を行なった。
日本側は荒井北海道さけ・ます孵化場長ほか外務省員一名、水産庁員その他五名、計七名から成る視察団をして、昨年七月二十五日稚内発、樺太本斗、オホーツク、イーチャ、キクチク、ウスチ・ボリシェレツク、オゼルナヤ、クリールスコエ湖などを視察せしめ、さらに八月二十日以降、右七名のうち三名を九月十五日までクリールスコエ湖に滞留視察せしめた。
また右一行とともに、水産研究所員二名、外務省員一名を本斗に派遣し、同地よりソ連調査船ゼムチューグ号に乗り組ましめて、八月二十五日までソ連側の海上調査を視察せしめた。
またソ連側からは、ア・シドロフスキー・アムール国立養魚局長を団長とする八名の視察団が、九月六日来日した。一行は月余にわたり北海道、東北地方の漁場施設、孵化場、水産研究所などを視察したが、東京では水産庁当局とも漁業取締問題などにつき意見を交換した後、一行中三名は十月十九日、他の五名は同月二十五日帰国の途についた。なお日本側船舶にソ連側専門家が乗船して視察することは、今回は結局実施を見るにいたらなかった。
(3) 北西太平洋日ソ漁業委員会第五回会議
日ソ漁業委員会第五回会議は本年一月二十三日から東京で開催されることに前回の会議で決定をみていたが、ソ連側モイセーエフ首席委員が病気のため右期日の開会は不可能となった。そこで同委員を除いて東京に先行してきたソ連側代表団を迎え、予定よりも遅れて二月六日から外務省で開催された。
このような事情もあり本年の会議では、例年と異なり本会議に先立って、まず科学技術小委員会が開催されたが、同小委員会は二月二十二日第十三回目の会議を開いて委員会に対する報告書を採決し、事実上その議事審議を終了した。
なお同小委員会には日ソ双方の合意に基づき、今回はじめて米国政府のオブザーヴァーの出席を認めることとし、このため仮議事手続に所要の改正を行なった。
一方委員会本会議は二月二十日より開始され、三月末までに二十二回にわたる会議を重ねる一方、この間しばしば非公式会談を行なってきたが、本稿執筆の現在会議は続行中であり、その終了までには、なおかなりの時日を要するので、第五回会議の詳細な経過はこれを次号に譲ることとする。
(1) 樺太よりの引揚げ
日ソ国交回復後再開された樺太よりの邦人引揚げは、一九五七年より一九五九年までの間に、第十二次より第十八次まで七回の配船が行なわれ、計二、三〇〇余名(家族たる朝鮮人を含む)が帰国した。しかしながら現在もなお同地に居住している邦人から帰国希望の嘆願書が在ソ日本大使館へ寄せられているので、わが政府は機会あるごとにソ連側にこれら帰国希望者に対する援助方につき申入れを行なっている。
(2) 消息不明者調査問題
わが政府は、日ソ共同宣言第五項に基づいて、消息不明邦人の現況に関しソ連政府へ調査方を依頼しているが、これにたいしてソ連赤十字社より、一九五九年十一月二日に六〇二名、同年十二月三十日に一、二八〇名の死亡邦人名簿を提供してきた。その後さらに昨年四月二十日に至って、一、四四六名の名簿を送付越した。
(3) 引揚げ問題促進に関する申入れ
本年一月二十七日在ソ門脇大使はソ連外務省に対し、(イ)帰国を希望する邦人の帰還促進、(ロ)帰国を希望しない残留邦人の名簿の通報、(ハ)消息不明者の調査促進、(ニ)日本人墓地参詣のための代表者派遣の許可等につき、その促進方を要望する旨の申入れを行なった。
日ソ間定期航空連絡問題に関しては、従来航空路を東京-モスクワ間としようとするわが国の主張と、これをわが国の一地点と、ハバロフスク間としようとするソ連側の主張とが対立し、現在まだ解決されていない(詳細は本書第四号一三〇-一三一頁参照)。
ソ連機の本邦不定期乗入れについては、わが国は従来相互主義を条件として三件六回これを許可してきた経緯があるが(詳細は本書第四号一三一頁参照)、昨年においては、本邦で公演のレニングラード劇場団員九〇名の往復輸送のためソ連機が五月三十日と七月十六日の両日それぞれ一時わが国に乗入れることを許可した。
さらに東京で開催された第四十九回列国議会同盟会議に出席するソ連最高会議代表団の往復輸送のためソ連機が九月二十六日および十月十日の両日それぞれ一時わが国に乗入れることを許可した。
一九五八年六月十一日ザブローヂン在京ソ連臨時代理大使は山田外務次官を来訪し、「日ソ文化交流に関する条約案」を手交するとともに、同条約の締結交渉を東京において開始するよう提案した。
その後、昨年十二月十二日に至り、再びモスクワにおいてジューコフ・ソ連対外文化連絡国家委員会議長は、在ソ門脇大使に対し一般文化協定とは別に、米ソ間の方式に則った広汎な一九六一年および一九六二年度の文化および学術協力プログラムを手交して、わが政府による検討方を要請した。
右二回に亘るソ連政府の申入れに対し、わが政府は、各般の要素を慎重に検討した結果対案を得、本年一月二十一日武内外務次官は、フェドレンコ在京ソ連大使を招致して同案を提示し、ソ連政府の検討を求めた。
昨年一月十九日改定日米安全保障条約が両国政府間で調印されたが、翌二十日プラウダ紙にソ連極東軍管区司令官ワレンチン・ペニコフスキーの「日本はどこへ行く」と題する論文が掲載された。この論文は、改定安保条約の調印を強く非難し、このような新情勢の下では歯舞群島や色丹島の引渡しは困難であるという旨を述べた点で注目された。
その後一月二十七日に至り、グロムイコ・ソ連外相から在ソ門脇大使に対し右論文と同趣旨の次のような覚書が手交された。
(1) 新条約は、極東太平洋の多数の国、就中ソ連・中国のごとき直接の隣国の利害に重大な影響を及ぼす。
(2) これによって、日本は、自発的に外国軍の駐留、外国軍事基地の設置に同意し、自国の主権を危うくし、国家的独立を失った。
(3) 同様に、日本は、ロケット・核兵器による装備を含む軍事的潜在力を増大すべき義務を負い、自国憲法に違反して再軍国化の道に入った。
(4) これは、日本を新戦争に引入れる危険をもたらす。もし戦争が起れば、日本全土は、最初の瞬間に広島、長崎の悲劇的運命に陥る恐れがある。
(5) 日本は、軍縮目的と全く相反する目的を追及する新軍事条約を締結した。
(6) ソ連は、日本の平和的独立を目的として他の諸国とともに日本の中立を保障する用意がある。
(7) 歯舞群島、色丹島を日本に引き渡すというソ連政府の約束の実現を今や不可能ならしめる新しい事態が作り出された。したがって日本領土からの全外国軍の撤退と日ソ平和条約の締結を条件としてのみ、これら諸島を引渡す。
このソ連覚書に対し、わが政府は、とりあえず一月二十八日外務省情報文化局長談を発表して、反駁を行なった。
同年二月五日、山田外務次官は、フェドレンコ在京ソ連大使を招致し、一月二十七日付の前記ソ連政府覚書に対するわが政府の回答として要旨、次のような覚書を手交した。
(1) 新安保条約は、国連憲章の目的と原則にしたがった純粋に防衛的な性格のものであり、ソ連の主張は、全く根拠のない独断である。
(2) わが国が軍縮について真摯な熱意を有することは周知の事実である。
(3) 日本は、独自の立場から自ら核武装せず、また核兵器の国内持込みも認めない。
(4) ソ連政府の説く中立の諸方策は、日本の安全保障の立場に反するから受入れることはできない。
(5) 日本は、現下の国際情勢下において米軍の駐留を必要と考える。
(6) 日ソ共同宣言によれば、歯舞群島および色丹島は日ソ平和条約締結後、日本に引渡されることになっており、しかもこの宣言調印当時すでに外国軍隊が駐留していたのであるから、ソ連の主張は一方的に国際約束を変更するものであり、承認しえない。わが政府としてはその他の固有の領土の返還もあくまで主張する。
(7) ソ連政府は、核兵器の威力を誇示して、一国の外交政策の変更を迫っているが、これは不当な干渉である。
(8) ソ連政府が日本憲法の解釈問題を云々することは甚だしい内政干渉であり、相互に遵守すべき日ソ共同宣言の規定に反する。
同年二月二十四日、プーシキン・ソ連外務次官は在ソ門脇大使に対し、二月五日付のわが政府の覚書に対するソ連政府の回答として要旨次のような覚書を手交した。
(1) 新条約は、アジア、極東地域の平和に新たな障害を作り出し、外国軍事基地の温存を確保するためのもので、決して防衛的ではない。
(2) 日本の指導者は、この条約の適用範囲は中国、沿岸州、千島列島に及ぶこと、日本軍がロケット核兵器を使用する可能性があること、また、日本側は在日外国軍隊が核兵器を所有しているか否かを調べる権利のないことを明らかにした。従って、ソ連政府は、日本政府の軍縮に関する「真摯な熱意」を信じえない。
(3) ソ連は、日ソ共同宣言を忠実に履行して、日本の国連加入支持、戦犯送還等に努力してきたが、日本は、同宣言の履行を回避し、善隣友好関係を発展させるべき義務に違反し、解決済みの領土問題を持ち出して、平和条約の締結を故意に引き延している。
(4) 日本の領土要求は、復讐主義への危険な傾向の現われである。
(5) ソ連は、隣国の権利として日本の現在の方策のあやまりを指摘しているだけであって内政干渉ではない。
(6) ソ連は、一貫して核兵器の全面禁止ないし平和のため斗っている。
(7) 新条約締結の結果起るべき結果の全責任は日本政府にある。
右ソ連政府覚書に対し、わが政府は、とりあえず翌二月二十五日外務省情報文化局長談を発表して反駁を行なった。
同年三月一日、山田外務次官はフェドレンコ在京ソ連大使に対し二月二十四日付の前記ソ連覚書に対するわが政府の回答として、要旨次のような覚書を手交した。
(1) 二月二十四日付ソ連政府覚書は、歯舞群島・色丹島の引渡し条件に関するソ連政府の一方的な変更について説明していない。のみならず、日本が日ソ共同宣言に違反しているかの如く述べて、自己の約束履行の責任を回避しようとしている。
(2) 新条約は、日ソ共同宣言にも認められている国連憲章第五十一条の自衛権に基づく純粋に防衛的な条約である。
(3) 領土問題は未解決であり、日本国民は、固有の領土たる国後島、択捉島の引渡しを求めることは当然のことと考えている。この日本国民の心からの念願は、歴史上、国際条約上正当であり、これを復讐主義への現われと称するに至っては全く驚くほかはない。
(4) 日本は、日ソ共同宣言を遵守し、さらにこれを発展せしめることを願っている。ソ連は、善意をもって日本の立場を研究し、その態度を変更することを望む。
同年四月二十二日に至り、グロムイコ・ソ連外相は、在ソ門脇大使に対して要旨次の覚書を手交した。
(1) 日本は、新条約の防衛目的を繰り返しているが、誰に対して自からを防衛するのか不問に付している。ソ連は、日本の安全保障のための種々の建設的提案を行なったし、また、日本が軍事同盟不参加、外国軍事基地の解消を実行する場合には中ソ同盟条約の軍事条項を再検討しうることを声明してきた。
(2) 新条約は、在日外国軍の治外法権を固定化し、事実上日本を被占領国としている。同条約と同時に調印された日本国における米国軍隊の地位に関する協定は、以前の占領条件の存続のみならず、外国軍隊に対する「追加的施設および領域」の供与に及んでいる。また、この協定の付属議定書では、外国軍隊に対し、日本国領域へ「任意の種類の兵器」を持ち込み、使用する権利を興えている。しかも日本政府は、日本の領域からの外国軍隊の作戦行動の実施について事前に同意を表明している。のみならず、日本自身の軍事力を強化し、外国軍隊と協力して、かれらの在日基地を反撃から共同して防衛する義務を負っている。
(3) この条約の適用範囲は、ソ連中国を含む他国領域に及んでおり、明らかに侵略の目的をもっている。
(4) 日本は、極東における原子兵器非武装地帯を第一とするアジア・大平洋平和地帯の設置のごとき建設的提案の受諾を回避し、自らは何ら提議することなく、新条約締結によってアジア諸国を脅威している。
(5) 新条約の調印は、日ソ両国の関係改善と相互理解の発展をさまたげ、日ソ共同宣言の精神および明文に反するものである。
(6) 歯舞群島・色丹島の問題については、一月二十七日付覚書で述べたとおりである。日本の他の領土要求は根拠なく、すでに解決済みの問題である。
(7) ソ連は、新条約締結によって生ずる全責任は日本政府にあることを再び強調する。
これに対し、わが政府は、翌四月二十三日とりあえず外務省情報文化局長談を発表して、反駁を行なった。
同年五月一日米U-2機がソ連領空上で撃墜されるといういわゆる「U-2機事件」が発生して東西関係がにわかに緊張するに至ったが、五月二十日、クズネツォフ・ソ連外務次官は、在ソ門脇大使に対し要旨次のとおりの覚書を手交した。
(1) ソ連政府は、一貫して日本国民に対する平和・友好・尊敬の感情に基づき、日本に新条約のもたらす危険性について警告してきたが、日本政府は遺憾ながら必要な結論を下さなかった。
(2) しかるに五月一日のU-2機事件は、このようなソ連の警告が根拠のあるものであることを確認した。米国は、軍事条約に従って諸国の領土に基地を設け、これをソ連に対する挑発のために使用している。しかも米国は、諜報飛行のためこれらの基地を使用することは国策であると自認した。
(3) 在日米軍基地にもU-2機があることは周知のことであり、これらの米国機は、ソ連国境を侵犯して諜報活動を行なっている。岸首相は、これらの飛行機は「気象観測」に従事していると述べているが、一九五九年九月藤沢市に不時着した「黒いジェット機」事件も米国の諜報活動を裏づけている。
(4) 以上にかんがみ、ソ連政府は、新条約に基づいて日本の領域からソ連に対して行なわれる挑発のもたらす結果につき、その責任は不可避的に日本政府にあることにつき、日本政府の注意を喚起する。
さらに同年六月十五日グロムイコ・ソ連外相は、在ソ門脇大使に対し再び要旨次のようなソ連政府声明を手交した。
(1) 日本政府が五月二十日付のソ連政府覚書に対して回答を遷延させていることは、日本政府が自国を米空軍に利用させることの重大性と危険性を真剣に考えていない証拠である。
(2) しかも日本政府は、ソ連その他の隣接諸国に対する侵略のための軍事条約の批准に全努力を傾けている。
(3) 六月七日ハーター米国務長官は、条約の適用範囲がソ連、中国その他にも及ぶという破廉恥な声明を行なったが、これはこの条約の侵略性の新たなる裏づけである。しかしソ連は、侵略者の欲望を打ち砕くために十分な手段を持っている。
(4) 米国がU-2機の目的に関し、周知の虚偽の説明を取り消した後にも、日本の指導者達は、在日U-2機は気象観測用に使われていると主張し続けているのは驚くの外はない。
(5) 日本は、侵略者に追随して、侵略者の一種の防壁と化そうとしているが、このような防壁は、軍事紛争が勃発する場合、最初の反撃を受けよう。
新安保条約はその後同年六月十九日国会の承認を受け、六月二十三日、日・米両国政府間にその批准書が交換された。
右に関連して同年六月二十九日、ソ連政府は、さらに要旨次のような声明を発表した。
(1) 数日前日米間で日本国民の意志に反して、日米軍事条約批准の芝居が行なわれたが、これは、米国支配者の破産した「戦争瀬戸際政策」の醜悪な申し子である。
(2) 日本国民は、未曽有の反対運動を行なって、同条約文書を無効とした。同条約支持者からすらも、その合法性・有効性について疑義が表明されている。
(3) 日本は、条約によって自発的にあるいは不本意の中に米侵略政策の加担者と化さしめられるものである。
(4) 日本の当事者は、同条約の助けをかりて日本国民、アジア諸国の利益に反して軍国主義を復活させ、長年抱懐している拡張政策の実現を図っている。
(5) ソ連の一貫した平和政策は、故鳩山首相を含む愛国的な日本世論の広汎なグループの間でもよく理解されてきた。
(6) 米国との軍事条約の締結は、それを推進した岸首相にも、またそれを当てにした日本の層にもよい結果を生まなかった。平和愛好国の日本に対する信頼は薄らぎ、日本国内に深刻な政治的危機を招き、岸氏は日本国民に烙印を押されて不面目な辞職を余儀なくされた。
(7) 日ソ関係の発展への道を拓くためには、国民の意志に反した暗い運命をもつ日米軍事条約を放棄することが必要である。日本国民の米帝国主義に対する反抗の実現が早ければ早いほど、それだけ日本国民および極東の平和に役立つわけである。
同年七月一日、藤山外務大臣は、フェドレンコ在京ソ連大使を招致し、前記四月二十二日および五月二十日付ソ連覚書と六月十五日付ソ連政府声明に対する要旨次のような回答覚書を手交した。
(1) 日本政府の対外政策の基本は、平和主義の政策であり、国連憲章の目的を忠実に遵守し、すべての国との平和友好関係を維持発展し、あくまでも侵略に反対して世界平和の増進に寄与せんとするものである。今次の日米安全保障条約の改定もこのような目的に寄与せんとする基本的立場より行なわれたものであり、この点に関するソ連の主張は、全く根拠のない中傷である。
四月二十二日付ソ連覚書は、安保条約が侵略的であるとの理由として種々の点をあげているが、これらの理由が曲解にすぎないことは、次に述べるとおりである。
(イ) ソ連覚書は、安保条約と同時に調印された「施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(地位協定)に言及して、この協定によって、日本は従来のものに追加して新たなる施設及び区域を駐留米軍に提供することとしたとしている。
ソ連覚書にいう「追加的施設および区域」云々は地位協定第二条第二項をさすものと思われるが、本条項は一九五二年二月二十八日に調印せられた行政協定第二条第二項と同文であって、新たに設けられたものではない。また、ソ連覚書は、「追加」にのみ言及しているが、同項は「返還」についても規定しているのであって、要するに、同項は、合衆国軍隊の使用している施設及び区域の現状を再検討するための規定である。そして、この条項の適用によって、合衆国軍隊の施設、区域は、旧安保条約発効当時のそれと比べて、現在約四分の一に減少しているのである。この事実だけからしても、ソ連覚書の陳述が根拠のないものであることは明らかである。
(ロ) ソ連覚書は、あたかも日本国が米国軍隊に核兵器を日本国内へ持込む権利を与えているかのごとく断じている。
日本における米国軍隊の地位は、新安保条約第六条によって、前記地位協定および他の合意される取極によって規律されることとなっているが、これらの条約・協定調印に際して交換された条約第六条の実施に関する交換公文において、核兵器の日本国内への持込みのごとき合衆国軍隊の装備における重要な変更は、両国政府間の事前協議の対象とすることになった。
そして日本国政府が核兵器の持込みを許可しない方針をとっており、ソ連覚書の言うところは、改定の趣旨とは全く逆であり、ためにする一方的言いがかりと言うほかはない。
(ハ) ソ連覚書には、日本側は、軍事力を増強し、外国軍隊と協力して彼らの在日基地を反撃から共同して防衛する義務を負っているとある。
およそ独立国である以上、自国の防衛のため、必要な措置を講ずべきは当然のことである。新条約第三条は、武力攻撃に抵抗する能力を維持し発展させることを規定しているが、右は日本が自国の「憲法上の規定に従うことを条件として」すなわち自国の国土防衛のため、必要最少限度において自国の防衛力を維持し、発展せしめることを意味するのであって、このことについてソ連が異議をとなえる理由は存しない。
ソ連覚書は、また、日本が在日米軍基地を「反撃」から共同して防衛する義務を負っているとしている。
新条約第五条は、日本の施政の下にある領域において武力攻撃が発生した場合に、日米両国が共通の危険に対処するよう行動すべき旨を定めている。この場合に日本が武力攻撃を排除するため必要な行動をとる自衛権を有することは何人もこれを否定しないであろう。ソ連覚書のいう「反撃」が在日米軍がまず第三国に対して侵略行為を行なうことを前提としているものとすれば、このことこそ本件安保条約の基本的性格を故意に曲解し、かかる曲解を宣伝するための想定以外の何ものでもない。日米安保条約は、その第一条および第七条に明記してあるとおり、当事国の侵略行為をいかなる意味においても承認しまたは正当化するものではない。
(ニ) ソ連覚書はさらに「日本国政府は、日本国の防衛とは、何らの関係のない目的のために、日本国の領域からする外国軍隊の作戦行動の実施について事前に同意を表明している」と述べているが、これも、歪曲のはなはだしきものといわざるを得ない。
条約第六条の実施に関する前記交換公文は、米国が、日本自身に対する武力攻撃の場合以外に、その自衛権の行使として、あるいは国際連合の行動として、軍事行動を執るに当り、日本国内の施設及び区域を戦斗作戦行動の基地として使用しようとするときは、とくに日本政府と事前に協議すべきことを定めている。このような事前協議制度を設けたことは米側戦斗作戦行動が日本側の意向に反して行なわれないようにするためであり、この点は今回の条約改定における主要点の一つである。
日本政府としては、国連憲章に違反する侵略行為が起り、かつそれが日本の安全に緊密な関係のあるような場合のほかは、米国が日本から戦斗行動を執ることに同意しない方針である。
(ホ) ソ連覚書は、「条約の適用範囲は故意に日本国の諸島に局限されず、ソ連邦および中華人民共和国の領域を含む日本国領域のはるか彼方にある地域に及んでいる」としている。
新安保条約第五条は「日本国の施政のもとにある領域」に対する攻撃の場合に限られるのであり、したがって、いわゆる「条約区域」は現存するこの種条約のいずれよりもせまく定められている。
新条約は、「適用範囲」なるものを、どこにも定めていない。
この条約において「極東における国際の平和と安全」として日米両国の共通の関心が示されている区域は、旧安保条約にも謳われている観念である。この区域は、日本の領域以外の地域が武力攻撃によって侵略された場合実際問題として在日米軍が日本の施設及び区域を使用してその侵略を排除する防衛努力に寄与しうる区域を意味し、ソ連および中国大陸はこれに含まれていない。しかも、米国軍隊が日本の基地を使用して戦斗行動をとる場合には日本政府との事前協議が必要であり、日本政府としては日本自体の安全に緊密な関係のある場合にのみ同意を与える方針であることは前述のとおりである。
六月十五日付のソ連政府声明は、この問題について六月七日ハーター米国務長官がなした声明を引用しているが、日本政府および米国政府の見解はこの声明および翌六月八日付国務省声明で明らかなとおり全く一致している。
日本政府がソ連覚書が言及している日米安保条約の諸点に関し、以上のように詳細な説明をなす所以のものは、この条約に関し、ソ連政府の見解が誤解に基づくものならばこれを正し、誤解に基づいて平和増進に逆行するがごとき事態の生ずることなきを願うためである。また、右は、日本政府が、地球上のいずれの地域においても、平和と安全は、中傷や脅迫の政策によってではなく、関係諸国による相互理解のための誠意ある努力によってのみ保障されることを信ずるがためである。
(2) ソ連政府は、五月二十日付覚書および六月十五日付声明において五月一日に起ったソ連における米国飛行機の撃墜事件に関連して、「日米安保条約は正にこのような米国の不法な諜報活動を可能にする基礎を与えるものである」と言っているが、右は全く根拠のない独断である。
すべての国家が相互に主権と領土とを尊重し合うことは、およそ国際社会の基本原則であり、日米安保条約が、日本を第三国に対する不法な活動の基地にすることを認めているものでないことは言うまでもない。日本政府はいかなる国に対しても日本を第三国に対する不法な活動の基地に使用することは許すつもりはない。
(3) ソ連政府は、日本政府に対し、外国軍事基地を撤廃し、いわゆる中立政策をとることを繰返し勧奨しているが、ソ連が一方において、共産圏外の国に、中立政策を勧奨しながら、他方において自己陣営に属する国が独自の中立政策をとらんとした場合これを強く非難し、あるいは弾圧によってその企図を放棄せしめたことは吾人の記憶に新たなところである。
四月二十二日付ソ連覚書は、ソ・中・日・米等を当事国とする日本国の中立保障に関する条約の問題に言及しているが、ソ連のいうこの種中立保障条約は、その前提としてまず駐留米国軍隊が日本より撤退することを要求するものである。すなわち、その狙いとするところは日本国の現実の防衛力を中立化かつ無力化せんとするものである。しかしながら日本国政府は、第二次大戦終了後におこった冷厳なる極東の諸事態を考慮するとき自国の安全を確保するためには安保条約に基づく米軍の駐留を必要なりと考えている。
日本政府は、また、一九五六年十月十九日モスクワで日ソ共同宣言が調印された時、旧日米安保条約はすでに存在し、共同宣言はこの事実を前提として締結せられたことについてソ連政府の注意を喚起したい。
またソ連政府が言及している極東および全太平洋地域に非核武装地帯を設置する問題については、日本政府は、一九五九年五月十五日付日本側口上書に詳しくその見解を述べている。日本政府は、全世界的規模における核兵器全廃の実現を請い願うものであり、日本に関する限り、このような大量殺りく兵器を所有しないことはもちろんのこと、その国内持込みをも許さない方針であることを繰返し宣明している。日本政府は、また、核兵器全廃の問題に最大かつ直接の責任を有するのは、このような兵器を現に所有する国であることを指摘するものである。
(4) 日本政府は、曲解と偏見に基づく非難を繰返すことにより日米安保条約改定問題に関する日本の国論の動向に不当な影響を及ぼそうと試みているソ連政府の態度は、日本国の内政に対する不当の干渉というのほかなく日ソ共同宣言における国内事項不干渉の原則に違反することを重ねて指摘するとともに、ソ連政府のこのような態度を深く遺憾とするものである。
昨年一月十五日ソ連最高会議は、各国議会および政府にあてた軍縮に関するアピールを発表したが、同月十八日フェドレンコ在京ソ連大使は、山田外務次官を来訪して、右「アピール」(英文)を手交し、わが政府および国会に伝達方を要請した。右「アピール」の大要は次の通りである。
(1) ソ連は従来の自主的な兵力削減に加えて、一層の大削減を行なうことに決定した。すなわち兵力をさらに三分の一、百二十九万人削減するから、その後の兵力は二百四十二万三千人となる。
(2) 近代兵器は無限の行動範囲と破壊力を有するようになった。今や、実際的な軍縮を開始する時期である。軍縮は、諸国民の生活水準の向上に役立つものである。
(3) 諸国の議会および政府は、軍縮の実現のため、できる限りの努力をすべきである。ソ連最高会議は、ソ連の一方的新規兵力削減が、他国とくに最大の軍事力を有する諸国に対する手本となることを希望する。
また同年六月二日モスクワにおいて、トゥガリノフ・ソ連外務省極東部長は、在ソ門脇大使に対し、フルシチョフ首相より岸総理大臣にあてた軍縮問題に関する書簡およびこれに添えて「全面的完全軍縮条約の基本規定に関するソ連政府の提案」を手交し、これらを岸総理大臣に伝達するよう要請した。右書簡の要旨は、次のとおりである。
(1) ソ連は、今回その全面的完全軍縮計画の発展として、西側の考えも採用して諸提案を作成した。
(2) 本提案においては、第一段階ですでにすべての核兵器運搬手段の禁止および廃止が規定されている点を強調する。
(3) 本提案中には、軍縮諸処置の管理規定が詳細に記述されている。
(4) 西欧列強は、ソ連に深い疑惑をもっており、本質的には軍縮のない管理を提案している。
(5) ソ連の真の全面的完全軍縮提案について日本政府の理解と支持を得たい。
同年六月十五日、右フルシチョフ首相の書簡に対し、金山外務省欧亜局長は、在京スズダレフ・ソ連公使を通じ、次の内容のフルシチョフ首相宛岸総理大臣の返簡を手交した。
本年六月二日門脇在ソヴィエト連邦大使を通じ伝達された同日付の貴簡を多大の関心をもって閲読した。
第二次世界大戦後における戦争手段の飛躍的発展は、将来における戦争発生の場合人類の絶滅すらをも招来すべき危険な段階に達しており、わが政府は、人類を万一起りうべき破局から救うためには、有効な管理査察を伴なう全面的軍縮の措置が執られるべきであることを確信している。このような軍縮の実現のためには世界のすべての国がその責任を分かつべきであることも当然であり、従って、今回の貴提案にはわが政府としても深い関心を有する次第であり、慎重にこれを検討する所存である。
一方、効果的な軍縮措置を実現するためには強大な軍備を有する主要国間の話合いが成果をあげることを必要とする。その意味において、本大臣は、貴首相が現在ジュネーヴにおいて開催されている軍縮委員会における討議の実質的な進展のため、一段と努力されることを切に希望するものである。
さらに同年六月二十七日に至り、ソ連外務省は、在ソ日本大使館に対し、再び軍縮に関する大要次のような覚書を送付してきた。
(1) ソ連は、一方的に自国兵力の三分の一を削減している。またソ連は、軍縮に関する国連総会の決議の実施を促進し、重要な問題で西欧諸国の希望に譲歩し、十カ国委員会の順調な交渉のためにできるだけのことをした。しかし同委員会の交渉は、諸国民のかけた希望に沿わなかった。
(2) それは、米国とその同調国が話しをまとめる意志を示さず、かえって十カ国委員会を、スパイ行為を可能とする軍縮のない管理と査察に関する自己の提案の審議に引込んだからである。
(3) 現在、軍縮は絶対的に必要であるのみならず、しかるべき努力が傾注されるならば、完全に可能なのである。
ソ連政府は、日本政府が軍縮の偉大な人道的事業に全面的に協力することを希望する。
9、コンゴー問題に関するソ連政府の対日申入れとわが政府の回答
昨年十二月六日ソ連政府はコンゴー情勢に関してルムンバその他の即時釈放等を要求する権利を有するとの趣旨を明らかにしたが、同日ソ連外務省は、在ソ日本大使館あて口上書をもって同声明を送付し、わが政府に伝達方を依頼してきた。
本年に入り、コンゴー情勢はますます悪化し、二月十二日にはルムンバ首相が殺害されるに至ったが、二月二十二日、フェドレンコ在京ソ連大使は、小坂外務大臣に対し、フルシチョフ首相より池田総理大臣あての要旨次の書簡を手交し、これを同総理大臣に伝達するよう要望した。
(1) 殺されたルムンバ首相とその他のコンゴー指導者は、植民帝国主義諸大国とその意志の執行人であるハマーショルド国連事務総長の陰謀の犠牲となったものである。
(2) 現在、人口の最も少ない諸国のグループが国連を支配して、自己の植民地主義的政策を行なっている。われわれは国連が三つの主要な国家グループを代表するように、三名の事務長制を執ることを提案した。
また殺人を行なった人間を国連事務総長として認めることはできない。
(3) 現在のコンゴーの事態を収拾するには、ベルギーの塊儡チョンベとモブツを即時逮捕して裁判にかけ、かれらの徒党を武装解除し、侵略者をコンゴーから退去させることが必要である。
またルムンバ首相等の殺害という国際的犯罪の責任者を厳重に処罰すべきである。
(4) コンゴーの平和のために、外国の干渉を排除し、ルムンバの後継者のギゼンガを首班とする合法政府に援助と支持を与えるべきである。
(5) コンゴーの独立回復は、国連安全保障理事会の決定に基づいてコンゴーに派兵しているアフリカ諸国の代表の委員会を創設することにより促進される。
(6) 大国は、他国に対する干渉を止め、国際緊張の緩和、軍縮等の重要な国際問題の解決に努力すべきである。
(7) 平和を強化し、各国民の安全を確保するためには、重要な国際問題について各国間に共通の言葉が見出されることが必要である。
われわれ両国政府がコンゴー共和国の自由と独立を守る事業に対し、その努力を共にすることを期待したい。これに対しわが政府は同年三月八日池田総理大臣の次の書簡をもって回答した。
私は、コンゴー問題に関するソ連政府の見解を述べた一九六一年二月二十二日付貴書簡に関連し、日本政府の考え方を申し述べたい。
まず最初にわが国は、独立達成を目指す植民地諸民族の熱望には万腔の同情を寄せるものであり、その独立と国民の幸福なる生活の建設には同情と協力をもって臨むものであることを明らかにしたい。さらにわが国はせっかく独立を獲得しながら不幸な事態の下に不安な生活を送っているコンゴー国民に深い同情をもつと同時に、コンゴー共和国に法と秩序が速やかに回復し、コンゴー国民が一日も早く外部からの干渉なしに国民自らの手で自らの欲する国内体制を築き、平和と安定の中で統一と独立を確保できる日がくることを切望するものである。従ってわが国は、コンゴー共和国内に東西の冷戦と植民地主義を持ち込まず、法と秩序の回復と和解に基づく国内の統一の早急な実現のため、世界の各国が協力して同国を援助することが必要であると考える。このような援助のための最も有効な手段を提供するものは国際連合であり、コンゴー問題の解決に当っては、国際連合を除いて他に適切な援助の方法はない。
ソ連政府は、コンゴーにおける従来の国際連合の活動を一方的に植民地主義の手先と断定しているが、日本政府は、このような一方的断定に同調しえない。国際連合は、コンゴーに対する外部からの干渉を排除し、かつ、コンゴー国内に冷戦をもち込まないようにするためにこそ、コンゴー問題に介入しているのであり、国際連合のほとんどすべての加盟国が国際連合のこの任務を支持している。国際連合がコンゴーにおける植民地主義の手先となったことはなく安全保障理事会および第四回緊急特別総会の諸決議の規定の範囲内で治安の維持のため最善をつくしてきたことは、事実に徴しても明らかである。日本政府は、二月二十一日安全保障理事会が採択した決議が有効に実施されるようすべての加盟国がその実施に協力すべきものであり、また同決議の規定に違反する国際連合を通じない一方的行動は、厳重に禁止されるべきであると信ずる。コンゴーにおける従来の国際連合の活動に将来さらに改善の余地ありとすれば、このような改善は、全加盟国の全面的協力によってのみ達成されるものであることを全加盟国は銘記すべきである。
ソ連政府は、コンゴー問題を契機として国際連合事務局を改組して三グループを代表する者で構成するよう要求しているが、日本政府はこの主張に同調しえない。事務総長は、国際連合に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位をもち、いかなる国、いかなるグループの利益の代弁者であってもならない。それにもかかわらず、事務総長がグループの利益を代表すべきことを前提とし、この前提の上に事務局を改組すべしとの主張は、事務局をそれぞれのグループの政策の手段とするものであり、ひいては国際連合の機能を完全に麻痺させ、その瓦解を招くものと言わざるをえない。
以上申し述べたとおり、日本政府は、コンゴー問題に介入している国際連合の目的にかんがみ、すべての加盟国がコンゴー問題解決に当っての国際連合の努力に最大限の支持と協力を与うべきであると考える。